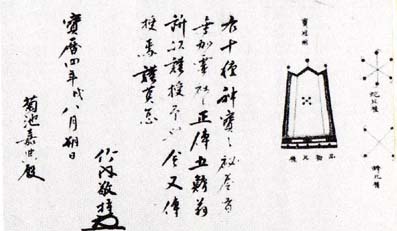|
��������������������������������������������������������������������������������
Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@�}���R�[�i�[
�܁@�����މ��v�Ƌg�@�̔Y��
�@�g�@�̓^�J��肪�D�����B
�@����͂����̗V�тł͂Ȃ��A���m�����ɕ��|�̗͂��������邽�߂��B
�@�w������ۂɖ��ɗ����̂�I�B
�@�������ĉ��v�͂���ɂ����߂���c�c�B
1 �鏫�R�g�@ top
�@�ꎵ��Z�N�i���ۏ\��N�j�O���A���{�̎���ł��鉺���������i�����˂灁���ˎs�j�́A��������ǂ�߂��ɂ܂�Ă����B
�@�n�ɂ܂����������m������������ŌQ����Ȃ��Ă��邩�Ƃ������A���������̖�����ނ�ɂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ����q�i����������Œ��₯���̂����肽�Ă�l�j�����}���܂��ĂЂ���ł���B
�@�����́A���R����g�@���������̕x�m�̊�����i�l�����牓���ɂ��čs�����j���܂˂čÂ����努���̓����������̂ł���B
�@���̓��A�g�@����o���𖽂���ꂽ�Ɛb�i�Ɨ��j�͓��A����ɐ��q�Ƃ��Ă��߂�ꂽ�_���́A�����i�ނ����j�A�헤�i�Ђ����j�A�����i���������j�A�㑍�i�������j�̎l�����ɂ܂�����A���̑����͈�Z�����Z�Z�Z�l���܂�ɂ̂ڂ����B
�@��p���܁Z�Z�Z���Ƃ������������������A�K�͂����݂�ƕx�m�̊������͂邩�ɏ�����̂Ƃ����Ă悢�B |

�������̎��̂悤���@�努���ŁA
�C�m�V�V��V�J���Ƃт����Ă���B��������}���ّ�
|
�@�g�@�́A������̏��R�̂����A�ƍN�ƂȂ��Ŏ�̍D���ȏ��R�ł������B
�@���̏������̊����������������݂̂̌��ꂾ���A�Ȃ��ł��g�@����Ԃ��̂̂́A�P�������^�J���Ƃ��Ċl�����Ƃ炦�������^�J���
* �ł���B
* �^�J����@���ł́A��l���Ɨ����S����ɂ��Ă����̂������̂ŁA��]�̐M������߂�̂ɖ��������B�܂��A�y�n�̂悤����A�_���̂��炵�Ԃ�����邱�Ƃ��ړI�������B
�@�^�͎��́A���y�E���R���ォ�炫�イ�ɐ���ɂȂ�A���m�̌��͎҂̗V�тƂ��č]�ˎ���ɂ͂����Ă��悭�s��ꂽ�B
�@�����A�ܑ㏫�R�j�g���u���ޗ��݂̗߁v�����z���ċ֎~�������߁A�������~���ꂽ�B
�@�Z��Ɛ�A����ƌp���A�^�J���̍Â��͂����Ȃ�Ȃ������B
�@����ɂ������A�g�@�͏��R�ɂȂ�Ƃ��������A�^�J���̕����𖽗߂��Ă��邩��A���̔M���̓x���������X�łȂ��������Ƃ��킩��B
�@���ہA�g�@�͊����Ƃ��������Ƃ����A�Ђ܂�����ƁA���̉H�D�ɖؖȂ̂����̂Ƃ����y���ŁA�����^�J���ɏo�������B
�@���R�̃^�J��肪���т����Ȃ�A���f����͓̂��̏Z���ł���A����i�^�J��������ꏊ�j���ӂ̔_���ł���B
�@���̂��тɁA���R�̈�s�ɋC�������A�_�앨���ӂ݂��炳��Ă��A���܂��Ă������̂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B
| �@���i���݁����R�j�̂��D���Ȃ��́@�@�����i�݂����́j�Ɖ��i�����j�̓�V�i�Ȃj |
| �@���R�̍D���Ȃ��̂́A�^�J���Ɖ��̎҂��ꂵ�߂邱�Ƃ��A�Ƃ����Ӗ��ł���B |
�@�ނ�͂��߂Ă̂��Ƃɂ�������� * �i�炭���ぁ�ᔻ�₩�炩���̈Ӗ������߂��́j������A�g�@�̃^�J���D�����������B
* �����@��ʂ̐l�X���A�����������Ď��̌��͎҂₻�̐�����ᔻ�����́B�l�ڂɂ��₷���悤�ɁA��╻�ɂ͂����蓹���ɗ������肵���B
�@�����A�g�@�͔ނ�̋������������A�����������^�J�������߂悤�Ƃ͂��Ȃ������B
�@�g�@�ɂ́A�g�@�Ȃ�̍l��������������ł���B
�@�u���������Ƃ����悤�ɁA���m�͊w��ƕ��|�̗����������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�Ƃ��낪���̍��́A�w��͂Ƃ������A���|�̂ق����������肨�낻���ɂ���A���m�炵���C�������Ƃ낦�����ł���B
�@���m�́A��ɏ����i���傤�ԁ������Ƃ��Ƃԁj�̐S�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���̏����̐S��{���ɂ́A���|�ɂ͂��ނ̂���Ԍ��ʂ̂��邱�Ƃł���A�^�J�������̖ړI�̂��߂ɍs���Ă���̂ł���v
�@���m�̗�����ŗD�悵���l�������ł͂��邪�A�m���ɐ킢�̂Ȃ��Ȃ��������A���m�́A���m�炵���S���Ȃ����Ă����B
�@���m������킵���Ȃ�A���{�̗͂����Ƃ낦�Ă���B
�@������g�@�́A�^�J�������������ł͂Ȃ��A
�n�p
* �E�C�p�i��C�������Z�p�j�E�|�p�i�|���˂�킴�j�E���j�E���n�i��n�Ő����킽��X�|�[�c�j�Ȃǂ̕��|�̕����ɂ������낪���A�����ɂ������ނ��Ƃ����サ���B |

�^�J����@�g�@�́A�^�J���ɂ����
���m�炵���C���������悤�Ƃ����B
|
* �n�p�@�g�@�́A�I�����_�l�P�C���Y����Ă����A�傫�ȃA���r�A�n���C�ɂ���A���������Ɨ��̍֓������ɂ߂����āA�I�����_���̔n�̈���������A�̂肩�����Ȃ�킹�Ă���B
�@�g�@���ǂ�قǕ��|�̏���ɗ͂�����Ă������́A���S�N�ԂƂ����Ă������L�n�i��Ԃ��߁������Ă���n�̏ォ�����˂Ă܂Ƃɂ��Ă镐�|�j�܂ōċ����Ă݂������ƂɁA�͂����茻��Ă���B
�@���̌��ʁA�ꎞ�I�ł͂��邪�A���m�̊Ԃɏ����i���傤�ԁj�̋C���������܂�A���|�ɂ����ꂽ�Q�l��������������Ђ炭�Ƃ��������i���݂���悤�ɂȂ����B
2 ���ۂɖ𗧂w����I top
�@�g�@�́A�݂��ڂ̔������A����ׂ̂���������A�ǂꂾ�����������邩�Ƃ������Ƃ̂ق����ɂ����B
�@���̐��_�͋��ۂ̉��v�Ɉ�т��ė���Ă���A�g�@�̊w�������ԓx�ɂ�����Ă���B
�@�g�@���ӂ����S���������A�M�S�Ɋw�̂́A�a�̂Ȃǂ̋M���I�ȋ��{�ł͂Ȃ��A���ۂɖ𗧂w��A�Ƃ�킯�������s���̂ɖ𗧂w��ł������B
�@���R�g�@�̊w��ɂ������邱�̑ԓx�A�܂���w���݂̂́A����܂ł̏��R�Ƃ���ׂ�ƁA�����Ԃ����B
�@�����Ă��̂悤�Ȏ��w���݂̂́A�g�@�̊S���A���[���b�p�̊w���i�m�w�Ƃ��Ă����j�ւƂނ��킹�邱�ƂɂȂ����B
�@�g�@�͂��т����I�����_���و� * �����ɗm�w�Ɋւ��鎿���������A�]�����A���v�Ȃǂ̗A���𖽂���������Ă���B
* �I�����_���و��@���{�͍���������Ƃ��Ă������A�I�����_�ƒ��������ɂ͖f�Ղ������A����̏o���ɃI�����_���ق��������B�I�����_�l�͂����ɏZ�݁A���{�Ƃ̖f�Ղ��Â����B
�@�ꎵ��Z�N�i���یܔN�j�A����̃I�����_�ʎ��i�ʖ�j���P�O�Y�炪�A
�@�u�m���̗A���������Ăق����v�@�Ɗ肢�o��ƁA�g�@�͂��̂��Ƃ��������ɔF�߂��B
�@���{�͈�Z�O�Z�N�i���i���N�j�ƈ�Z���ܔN�i�勝��N�j�̓�x�A�L���V�^���M�̐N�����ӂ����Ƃ������ڂŁA�m���̗A�����֎~�������A�m�w�̖��͂��������g�@�ɂ��Ă݂�A���̋֗߂����łɕs�K�v�������̂ł���B
�@���w�̂����A�g�@�����ɔM�������̂́A�V���w��C�ۊw�ł������B
�@�ꎵ���N�i���ێl�N�j�A�g�@�͒���̗L���ȓV���w�Ґ���@���i�ɂ����킶�傯��j���܂˂��ēV����p�ɔC�����A�܂��Z�c���v�Ԓ��i���c��j�ɓV�����ݒu���ēV�̂̊ϑ��ɂ����点���B
�@����ɋg�@�́A�]�ˏ�̒�ɂ����������A�����̉J�ʂ��͂����ē��L�ɂ������ނ��Ƃ��������Ȃ������B
�@�ꎵ�l��N�i���ۓ�N�j�̏��H�A�g�@�͉J���̂��܂肮�������݁A���L�̃y�[�W������Ȃ���A������Ɏ���Ђ˂��Ă����B���̂悤���ɋC�Â��������i�����傤�j���A
�@�u�ǂ����Ȃ��ꂽ�̂ł����v
�@�Ƃ����˂�ƁA�g�@�͂��炢������Ă��������B
�@�u�]�˂��͂��ߍⓌ�i�֓��j�Ƃ��̋ߕӂ́A��A�O���̂����ɑ�J�ɂ݂܂��A�e�n�ő傫�Ȕ�Q���o�邾�낤�B
�@�O�����ċ~�ς̑�����Ă�悤�A�������V���ȉ��ɐ\���`����v
�@�g�@�̂��̗\���̓s�^���Ƃ�����A���ꂩ��܂��Ȃ��ӂ�͂��߂��J�́A�֓��E�b�M�i�R�����E���쌧�j�n���̐�����ӂꂳ���A�]�ˎ���ő�Ƃ������^�����Ђ����������B
�@�͂��ߋ^�������������V������A���̎��Ԃ��܂̂�����ɂ��A�C�ۊw�ɂ�������g�@�̗����̂ӂ����ɂ��炽�߂Ă��ǂ낢�����A�܂��ɋg�@�̎��w�͐��ƂȂ݂̃��x���ɂ������Ă����킯�ł���B
�@�g�@�͂܂��A���낢��ȐV�����_�앨�͔̍|�����サ���B
�@���̒��ŁA���ɗL���Ȃ̂́A�Ï��i���偁�T�c�}�C���j�͔̍|�ł��낤�B
�@�T�c�}�C���́A���[���b�p���璆�����ւāA�\�����I�O��ɋ�B�ւ�����ꂽ�_�앨�ł���B
�@�V�����Ă����肵�����n��������̂ŁA�Ђ낭�͔|�����悤�ɂȂ��āA�Q�[�i������j�̂Ƃ��ȂǂɈЗ͂������B
�@���̂悤�ɁA�T�c�}�C���̂�����Ă���Ƃ�����g�@�ɋ������̂́A���w���i�I�����_�̊w�����������w�ҁj���؍��z
*�i����悤�j�ł���B���̂��Ƃ��獩�z�͐��Ԃ���u�Ï��搶�v�Ƃ���ꂽ�B
* �؍��z�@�]�˂̏��l�̎q�ŁA�͂��ߎ�w���܂ȂсA���{�̐}�����Ǘ����鏑�����̖��ɂ����B�̂��ɁA�I�����_����Ȃ炢�A���w�̂��炵�����g�@�ɋ������B |

�؍��z�i����������悤�j���@���w�Ґ؍��z�́A�Q�[�̂��Ȃ��Ƃ��āA�Ï�(�T�c�}�C��)�͔̍|�����シ��悤�A�g�@�ɐi�������B
|
3 ���Ώ��Ə��ΐ�{���� top
|

���Ώ��@��E�֍��F��B�����܂������Ώ��������A�Ύ���ւ������B
�u���Ώ���g�̐}�i�G�n�j�v���B���c�R����ّ�
|

���@�~�R������B�u������}�v���B�~���@��
|
�@�]�ˎ���ɂ͂悭�u�Ύ��ƌ��܂͍]�˂̉ԁv�Ƃ���ꂽ���A���̕����ɂ��������̓��₩�����������̂́A�����炸�ł߂��ۂ��А��̂悢���Ώ��������B
�@�W�����W�����Ɣ����i�͂傤�����`�̂���j���Ȃ�ƁA�Ȃɂ͂��Ă����Ă��Ύ���ɂ������A�ӂ肩����̕������̂Ƃ������E�������Ί���
* ������Ђ낰��\�\�ނ璬�Ώ��͂܂��ɍ]�˂��q�̂Ȃ��̍]�˂��q�������Ƃ����Ă悢�B
�@�������Ώ��̐��x���������̂��A��͂�g�@�ł���B
* ���Ί����@���̎���̏��Ηp��́A�������ɂ��������|���v���Z�b�g�������f�i��イ�ǁj���A�����A�̂��������Α��ɂ����邽�߂̑傫�Ȃ����킭�炢�ŁA�����������Ί����͂ł��Ȃ������B
�@���Ώ����o������ȑO�̍]�˂̏��́A��Ώ��Ƒ喼�Ώ����s���Ă����B
�@��Ώ��͊��{�̎w��������Α��ŁA��Z�ܔ��N�i�������N�j�ɂ��������A�牌�i������j�Ƃ���Ώ������i���イ�����m�̏��g���j�����ۂ̏��Ί����ɓ������B
�@�喼�Ώ����قړ������ɂ͂��܂�A�喼�����������̗͂ʼn��~����邽�߂ɑg�D�����̂����������A�����͖��{�̖��߂ɂ����̂ŁA���i���{������炤�����j�ɂ������ďo������l���������߂��Ă����B
�@�������A��Ώ��i���傤�Ђ����j�A�喼�Ώ��Ƃ��A���̂����Ȉ����͕��Ƃ��Z�ޒn�̏��ɂ����邱�Ƃł���A���̂��ߒ��l�̏Z�ޒ����̏��Α̐��͂Ƃ����蔖�ɂȂ肪���������B
�@�����ŁA�g�@�͈ꎵ�ꔪ�N�i���ێO�N�j�A���l�����ɋ��͂����邱�Ƃɂ��A���ňꎵ��Z�N�i���یܔN�j���Ώ��̐��x�������߂āA�s���̏��Α̐������������̂ł���B
�@���̐��x�ɂ���Ēa���������Ώ��́A����͎l�\���g�ɂ킩��A�e�g���Ƃɂ��̒n��̏����s�����ƂɂȂ��Ă����B
�@�����A�l�\���g�ł͂��܂�ɂ킯���������܂����A������ƉΎ����傫���Ȃ�ƁA��g�����ł͎肪�܂�肩�˂��肵���̂ŁA�ꎵ�O���N�i���ۏ\�ܔN�j�ɂ�����\�g�ɂ��肩���Ă���B |

�܂Ƃ��@�Ώ����̑g�̂��邵�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|
�@�e�g�ɂ͐��̉Ώ���������A�ނ�̂܂��Ȃ���p�̑啔���͂��ꂼ��̒������S�����B
�@�g�@�͂܂��A�h�Α̐�����߂邽�߂ɁA�ꎵ��O�N�i���۔��N�j�A�߂��߂��̒��ɉ̌��E������悤�ɖ��߂����B
�@�̌��E�͂��̑O���炠�������A�E�̂������Ƃ̉���������i���悻��E�����[�g���j���������āA�l���i���悻��w�N�^�[���j���݂킽����悤�ɂ������ƁA�̔ԓ��˂ɂ����ĊĎ����������ƂȂǂ��A�g�@�̖��߂̐V�����Ƃ���ł������B
�@�g�@�̖h�Α�Ƃ��ẮA���̂ق��s���ɋ�n�������Ėh�Βn�тƂ������Ƃ�A���Ԃ��A�y���Â���̌��������サ�����ƂȂǂ������邱�Ƃ��ł���B
�@���Ԃ��A�㑠�Â���̏���́A�̂��ɋ����I�Ȗ��߂ƂȂ�A�ᔽ�҂ɂ͔����Y�Ȃǂ��ۂ��ꂽ�B
�@���̂悤�Ȗh�E���Α� * �ƂȂ�сA�g�@�������Ȃ�����v�Ȗ����i�݂��j�Ƃ��Ă݂��Ƃ��Ȃ����̂ɁA���ΐ�{�����i����������悤���傤����j�����������Ƃ���������B
* ���Α��@���̂ق��ɂ��A�����ɂ̂ۂ��ĉ̕��������Ƃ߂邱�Ƃ��߂�������A�Ύ���̍��G�������邽�߂ɁA�ƍ�������Ԃɂ�Ŕ��邱�Ƃ��ւ����肵�Ă���B
�@�ꎵ���N�i���ۘZ�N�j�A�ݒu��������̖ڈ����i�������j�ɁA���̂悤�ȓ������������B
�@�u�]�ˎs���ɂ́A�a�C�̎��Â����������Ȃ��n�����l�X����������B
�@�ނ���~�ςł���͖̂��{�����Ȃ��̂�����A�ǂ��������̗×{����ݗ����Ăق����v
�@�����҂́A���ΐ�`�ʉ@�i������j�O�ɏZ�ޒ���ҏ���♑D�i���傤����j�ł������B
�@���̓������g�@���Ƃ肠���A���ꎵ���N�\�A���ΐ���i���{�̖͔|���j�̕Ћ��ɂ��点���̂����ΐ�{����
* �ł���B
* ���ΐ�{�����@�����s������ɂ��鏬�ΐ�A���������̐Ւn�B��ƎR�{���ܘY�̏����w�ԂЂ��f��杁x�́A���̗{�����̂��悤�������������̂ŁA����Ƃ��Ă����Ă���B
�@���m�������ɂ͂߂��炵�����̖�����Î{�݂ɂ́A���Ȃ���łȂ��A�O�Ȃ��Ȃ�������A�ʉ@���Â̂ق��A���@���҂����������B |

���{�̏��ΐ���ł������A�����c�鏬�ΐ�A�����B
���̈�p�ɏ��ΐ�×{�����������B
|
�@���@�̏����͂��т����������A����������@���������ƁA�ē~�̈ߗނ���Ȃǂ������Ŏx�����ꂽ����A�n�����a�l�ɂƂ��Ă͓V���̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@�J�݈Ȍ�A���̊Ǘ��^�c�ɓ������̂͒���s���ł���B
�@�����̗v�]�ɂ��������ď��ΐ�{�����͖����܂łÂ����B
4 ���v��ᔻ����� top
�@�g�@�̂����Ȃ������{�������v�́A��̂̂Ƃ��됬�������Ƃ����Ă悢�B
�@�g�@�����R�ƂȂ��������A���ɋꂵ���������{�̍������A���v�������ނɂ�Ă悭�Ȃ�A�啝�ȍ����ƂȂ����B
�@�������A���̉��v�ɂ������āA�ᔻ�҂���l�����Ȃ������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�@�ᔻ�҂͗L�͂ȑ喼�̂Ȃ��ɂ�����A���̋}��N�͌�O�ƕM���������ˎ哿��@�t�i�ނ˂͂�j�ł������B
�@�@�t�͂��ċg�@�Ə��R�̍��𑈂����g�ʂ̒�ł���B
�@�Ƃ����Ă��A�@�t�{�l�͕��j���i�Ȃ̂ԁj�̓�Z�Ԃ߂̎q������������A�O�r�ɂ��܂�]�݂͂Ȃ��������A�ꎵ���N�i���ۏ\�l�N�j�A���B������i��Ȃ���͂������ɒB�S�j�̏����`���i�悵�܂��j����p�̂Ȃ��܂ܖS���Ȃ������߁A�ނ������ĎO���̑喼�ƂȂ����B
�@����ɗ��N�A�g���i�悵�݂��j�̂��Ƃ������ꂿ�����̌Z�p�F�i���Ƃ��j���}���������Ƃɂ���āA�����������������˂̘Z��ˎ�̍��ɂ����Ƃ��ł����B
�@���̍K�^�Ԃ�͂ǂ����g�@�̏ꍇ�Ǝ�������Ă���B
�@�������A�����ɂ�������l�����́A�����ԋg�@�Ƃ������Ă����B |

�ɂ��키���É��̒��@�@�t�̐���ɂ���āA���É��鉺�͊��C�ɂ݂��Ă����B
�u�����G���v���B���É��鑠
|
�@�@�t�i�ނ˂͂�j�́A�����̐S�������邵���w���m���v�i�������悤�j�x�Ƃ����{���c���Ă��邪�A���̒��Ŏ��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���B
�@�u�l�ɂ͍D�݂Ƃ������̂�����B�����̍D�݂𑼐l�ɂ�������̂́A��ɂ��҂��������Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��v
�@�u��ɂ��҂͐��Ԃ̎�������邱�Ƃ�������A���Ƃ����ĕ����ɉʂł��킵���Ȃ��Ă��ꂱ�ꂳ��������ƁA�������Đl�X�ɋꂵ�݂��������邱�ƂɂȂ�v
�@�u���邱�Ƃ��苭������ƁA���߂̐S���������Ȃ�A���̂܂ɂ��l�X���ꂵ�߂鐭���ƂȂ肪�����v
�@�u���v���邱�Ƃ����̏ꍇ�ɂ��������Ƃ͂����炸�A���̂��Ƃ��킫�܂��Ă��Ȃ��ƁA���Ȃ炸�傫�ȊԈႢ���������v
�@�@�t�̂����̌��t�́A����������������i���傤�ԁj�̐S���ې��i�������j���A���v�ɂ����v�����������߂��g�@�̐����ɂ�������A�ɗ�Ȕ���Ɣᔻ�ɂȂ��Ă���B
�@�����ď@�t�͔����ˎ�̍��ɂ��ƁA���������w���m���v�x�̓��e�ǂ���̕��j���������Ĕ˓��͐������w�������B
�@�܂�A�g�@�̌����ɔ������Ђ邪�������̂��B
�@�ł́A�@�t�͋�̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ������̂��Ƃ����ƁA�����ł���B
�@�����˂ł́A�O�̔ˎ�̌p�F�̑�܂ŁA�g�@�̌���ɂ��������A�鉺�����É��Ŏŋ����s�����Ƃ�V���������邱�Ƃ��֎~���Ă����B
�@�@�t�́A�����̋֎~�����Ƃ��Ƃ��Ƃ�������łȂ��A���i�����ꂢ�j����i��肠���j�̐������̂����A�˓��̌��������������߂��̂ł���B
�@���̂��߁A���ۂ̉��v�ɂ���đS���̓s�s���̂������悤�ɂЂ����肵�Ă��������A���É����������������Ƃ��A���X�ɂ͗z�C�ɑO�ނ��ɐ������y���ސl�X�����ӂꂽ�B
�@����܂��c�ɂ������������É����A���Ɠs�s�Ƃ��ċ}�������A�O�s�i�]�ˁE���E���s�j�ɂ���s��ւƔ��W�����̂��A���̍��ł���B |

���Ղ��@�����L�d��B�剪�����́A�]�ˏ����̋C����
���U�����邽�߁A�čՂ�����サ���B���ꂪ�]�˂�
�O��čՂ�̂�����ł���B�u�]�˖����}�G����B
|
5 �@�t�̔s�k top
�@�@�t���g�@�Ɛ����̐�����Ƃ������ɂ́A�I�ɂ̋g�@�ɏ��R�E���Ƃ�ꂽ���Ƃւ̔�������Ƃ̍��݂��������Ƃ�����B
�@���R�ƂɌ�p�̂Ȃ��ꍇ�́A��O�ƕM���̔�������Ƃ��玟�̏��R���ނ�������̂����̂��Ƃ̏�������������A���̂悤�ȍ��݂̂��������@�t�ɂȂ������Ƃ͂�������Ȃ��B
�@����͂Ƃ������A�@�t�̊J���I�Ȑ����́A�̖��i�̒n�̐l�X�j�̑劽�}���������B
�@���̂���̂���L�^�́A�l�X���u���߉ނ��܂�����E�q�i���イ�����������j���������ꂽ�H���i�������j�̖��N�v�Ƃ��ď@�t���������A�����̂Ȃ݂��𗬂��������A�Əq�ׂĂ���B
�@������������̖��̕]�����悭�Ă��A���R�g�@����݂�A�@�t�̂�肩���͖��炩�Ɏ����ɂ������锽�R�ł���B
�@���R�Ƃ��āA�@�t�̂͂˂��������C���Ă������Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�����ŁA�g�@�͈ꎵ�O��N�i���ۏ\���N�j�܌��A���d���猳���ƐΉ͏���Y�������g�҂Ƃ��Ă�����A�@�t�������₢���������B |

���É����@����ł���������2�����E���ŏĎ����A���Č����ꂽ�B
|
�@���̎�|�́A�@�t�����{�̌���߂���炸�A�ؔ��i���сj�Ȑ������������Ă���Ƃ����_�ɂ������B
�@����ɂ������A�@�t�͓��X�Ǝ��̂悤�ɔ��_�����B
�@�u�g�@���͌���̈Ӗ����悭�킩���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@��̎҂�����Ƃ����ċ�������܂����Ȃ�A�Ƃ���ɍ���͉̂��X�̏����ł��낤�B
�@��̎҂������Q��邩�炱���A���ꂪ���X�ɗ���Ă����ď��������邨���̂ł���A���̂��Ƃ��܂��V���̔ɉh�ɂȂ���̂ł���v
�@�@�t�����̔��_ *
���m���Ɉ�̍l�����ł͂���B
* ���̔��_�@�@�t�̐S�ɂ́A���l�ɂ͖{���̂����Ƃ������͐\�������A�_���̔N�v�͂₷�����āA�݂�Ȃł��̐������̂������炻���ł͂Ȃ����A�Ƃ����l�����������B
�@�g�@�͂��̔��_�ɂ����A�ЂƂ܂��@�t�U���̂ق��������߂��B
�@�������A���̂����ɔ����˂̍������A�@�t�̔h��Ȑ���̂�����������A�ꂵ���Ȃ��Ă����B
�@�@�t�́A�g�@�ւ̔��_�̂Ȃ��ŁA�ؔ��Ȑ��������Ă��Ă��̖������ɂ��炽�ȕ��S�������Ă͂��Ȃ��Ƃ������Ă��邪�A�@�������܂��������̋ꂵ���̂��߁A�Ƃ��Ƃ��@�t�͂��̌��t���Ђ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B
�@�ꎵ�O���N�i�����O�N�j�A�@�t�͒��l�E�_���ɁA���킹�Čܖ����Ƃ����V�����ł������߂����邱�Ƃɂ����B
�@����ƁA����܂ŏ@�t�𖼌N�Ƃ������Ă����˓��̐l�X�̊ԂɁA�悤�₭�s���̐���������͂��߂��B
�@�����ւ����̂��A�g�@�ł���B
�@���N�ꌎ�A�g�@�͔����˂̉ƘV��������т����A
�@�u�g�̍s���������炸�A���ƂƂ̂킸�A�m�������i���݂イ�j�v�Ƃ������R�ŁA�@�t���B���ސT�i���傫��j�̏����Ƃ��邱�Ƃ𖽂����B
�@�@�t�͂��˂Ă��由�����邱�Ƃ��o�債�Ă����̂ŁA�ꌾ��������킸�A�g�@�̖���
* �ɂ����������B
�@�������A�g�@�͂�قǏ@�t�������Ă����悤�ŁA�@�t�̍߂͎��ʂ܂ŋ����ꂸ�A��������̕�ɋ��Ԃ����Ԃ�����Ƃ������肳�܂������B
* �g�@�̖����@�@�t���B���ސT�̐g�ƂȂ����̂ŁA�����ˎ�͔��Z�i���j���{�˂̏����`�~�i�悵���j�������B�@�t�͉B�����A25�N���1764�N��69�˂Ŏ��B
6 �������i���傤�ׂڂ��j�̉Əd
top
�@�g�@�́A����܂ł݂��悤�ɏ��R�Ƃ��Ă͐����������A�ƒ�I�Ɉ�̑傫�ȔY�݂��������Ă����B
�@���j�̉Əd�i���������j�̂��Ƃł���B
�@�u�Əd�ɂ����������̂��B�����������A�ǂ��ɂ��Ȃ�ʂ��̂��낤���v
�@���ɂ����Ă͂���Ȃ����̂́A�g�@�̋��̂����ɂ́A�������̎v����������ƂȂ��Ă킾���܂��Ă����B
�@������A�ނ�͂Ȃ��B
�@�Əd�͂��܂���a��ŁA���t���͂����肵��ׂ邱�Ƃ��ł����A�e�̋g�@����݂Ă��͂��䂢�قǏo���̈����q���������̂��B
�@���̂��߁A�g�@�̓^�J���ɂꂾ���ĕa��ȑ̎����������悤�Ƃ�����A���邢�͂܂�����ꗬ�̊w�Ҏ��ꑃ�i�ނ낫�イ�����j���ƒ닳�t�ɂ�Ƃ��āA���̏��R�ɂӂ��킵���w�⋳�{��g�ɂ������悤�Ƃ�����A�l�X�̐e�炵���z�����Əd�ɂ��킦���B
�@�����A�Əd�̓^�J���ɂ��w��ɂ����������ɋ��������߂����A�������Ă��ُ̈킳�͔N�ƂƂ��Ɉ������Ă������肾�����B
�@�V�т����̂݁A���ɂ��ڂ�Ė������������̂͂Ƃ������A��\�˂������Ă��Q���ւ����邱�Ƃ����т��т���A�u�������i���傤�ׂڂ��j�v�ƉA�����������ꂽ�肷�邠�肳�܂������B
�@�u����ƂāA���j�̉Əd�����������āA���O�j�ɏ��R�E���䂸�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����c�c�v
�@�g�@�̔Y�� * �́A�ӂ��܂����ł���B
* �g�@�̔Y���@�Əd�����O�j�̏@���̂ق���������Ă������A���Ƃ��͍˔\��w��̂���Ȃ��ł͂Ȃ��A�����܂ł��ƕ��₤�܂ꂽ���Ԃł��߂���̂���������A�g�@�͂Ȃ�B
�@�������ċg�@���Əd�̂䂭�������������Ȃ��ł��邤���ɁA�Əd�̔N��͎O�\�˂������A�g�@���g�������җ��i�������N�ŘZ�\��ˁj���ނ����Ă����B
�@�u�������B�����͎������C�Ȃ����ɉƏd�����R�E�ɂ��A���̌㌩�i��������j����������Ƃ����̂��A��Ԃ悢���@�ł͂���܂����v
�@�����l�������g�@�́A�ꎵ�l�ܔN�i������N�j�㌎�A�����������ĉƏd�ɏ��R�E���䂸�����B
�@�����ċg�@�͂��肼���A�Əd�̐��������肽�Ă����A���̂悤�ɐ��O�Ɉ��ނ������R�̂��Ƃ��䏊�i����������j�Ƃ����B
�@������̏��R�ł́A�ƍN�A�G���ɂ��A�g�@���O�l�߂̑�䏊�ł������B
�@�Ƃ��낪�A���\�Ƃ݂��Ă����Əd�́A���R�ƂȂ����Ƃ���A���ɂ��������������Ƃ𖽗߂��āA�l�X�����Ƃ납�����B�@�Ȃ�ƕ��g�@�Ɏd���đ����̌��т̂������V��������W�i�̂肳�Ɓj���A���߂����Ă��܂����̂ł���B
�@�����Ƃ��A���̏�W�̏����́A���낢��Ȏ�����l����ƁA���͋g�@�̔��Ă������炵���B
�@�܂�A�g�@�͐��O�ɏ��R�E����߂�����ǂ��A�ݐE�͎O�\�N�ɂ���сA���̊ԁA�O�ɏq�ׂ������̓���@�t�ɑ�\�����悤�Ȕᔻ�҂��������܂ꂽ�B |

����Əd�摜�@��㏫�R�����A
�a��ł����ꂽ�Ƃ��낪�Ȃ������̂ŁA
�����͕��̋g�@���Ƃ����B
|
�@���R�̑�ւ��ɂ������āA���̂悤�ɔᔻ����Ă���҂��A�Ђ��Â��������Ƃ�̂́A�����ɂ��s���������B
�@�����ŁA�V��������̐V������������ۂÂ��邽�߁A����]���Ƃ��ċg�@���I�̂��A��W�������Ƃ������Ƃ��B
�@�悤����ɋg�@�͐V���R�Əd�̖��ɂ���āA���т̂������Ɨ�����
*
���ƂŁA���{�ւ̕s�����͂炢���낤�Ƃ����킯�ł���B
* �Ɨ������@���܂܂ł���������͂������B���Ƃ��A�Ɛ邪�ӌR�ɂȂ����Ƃ��́A����g�ۂ��Ǖ�����A�g�@�����R�ɂȂ����Ƃ��́A�V�䔒�Ɗԕ��F�[���Ǖ�����Ă���B
7 ��O���i�����傤�j�̐ݒu
top
�@�g�@�ɂ́A�Əd�̂ق��ɎO�l�̒j�q�������B���̂����̎O�j�@���i�ނ˂����j�͉Əd�Ɛ����ɕ����i�Ԃ�ԁj�Ƃ������ꂽ�l���ł���A�l�j�@���i�ނ˂����j�����}�Ȑl���ł͂Ȃ������B
�@�u���j���Əd�łȂ��A�@�����@���ł����Ă��ꂽ�Ȃ�A���������ƈ��S�ł������̂��c�c�v
�@�g�@�́A�Ƃ��ǂ����������������Ƃ�����B�������A����͂����Ă݂Ă��������̂Ȃ����Ƃł���B
���ꂾ���ɋg�@�͏@���Ə@�������̔\�͂ɂӂ��킵���n�ʂɂ��Ă�肽���ƍl���Ă����B
�@�₪�āA�悢�l���������B
�@�u�_�N�ƍN���͏��R�ƂɌ�p�̂Ȃ��ꍇ�ɂ��Ȃ��āA��O���i���R�Ƃɂ������E�I�ɁE���˂̓���Ɓj��������ɂȂ����B
�@���̗�ɂȂ炢�A���̎q�������ɂ����ʂ̉Ɗi���������Ă�邱�Ƃɂ��悤�B
�@�Əd�͂��̂悤�ɕa��ł����ɂȂ�Ȃ����A�������̂��Ƃ��������Ƃ��A�����̉Ƃ����������A��p�����̉ƁX���炾���悤�ɂ���A��ΓƂ������̂���v
�@�������Ēa�������̂��A�c���i���₷�j�ƁA�ꋴ�i�ЂƂ��j�ƁA�����i���݂��j�Ƃł���A��O���i�����j�ɂ���������O�� * �i�����傤�j������B
* ��O���@��O�����珫�R�ɂȂ����̂́A�ꋴ�Ƃ̏o�g�ł���\��㏫�R�Ɛāi�����Ȃ�j�ƁA��O�Ƃ̐��ˉƂɂ��܂�A�̂��ꋴ�Ƃɗ{�q�ɂ͂����āA���R�Ƃ������\�ܑ㏫�R�c��i�悵�̂ԁj�̓�l�B
�@��O���͓����ɐݒu���ꂽ�̂ł͂Ȃ��A��ԍŏ��ɂ�������ꂽ�̂́A�O�j�@�������邶�Ƃ���c���Ƃł������B
�@���ꂪ�ꎵ�O��N�i���ۏ\�Z�N�j�̂��ƂŁA���Ɏl�j�@���i�ނ˂����j�����邶�Ƃ���ꋴ�Ƃ��ꎵ�l�Z�N�i�����ܔN�j�ɒa���B
�@������̐����Ƃ���������ꂽ�͈̂ꎵ�ܔ��N�i���N�j�Ƃ����Ԃ������A���邶�ɂ͉Əd�̎��j�܂�g�@�̑��ɂ�����d�D�i�����悵�j���ނ�����ꂽ�B�@��O���̘\���͈�Z���Ƃ���A��O�Ƃ�肽���ԂЂ����������A���ʂ͌�O�ƂƓ��i�̎O�ʌ����[���ł������B
�@��O���̉��~�͂��ׂč]�ˏ���ɂ����ď��R�Ƃ̉Ƒ��Ƃ��đҋ��������A���̂��Ə��R�Ɍ�p���Ȃ��ꍇ�́A��O�Ƃł͂Ȃ��A��O���̂Ȃ�����I���̂���ƂȂ����B
�@�Ȃ��A�g�@�͐����Ƃ�����������O�̈ꎵ�܈�N�i���N�j�Z�\���˂ł��̐������������A��O���̐ݒu�͋g�@�̐��O�Ɍ��肸�݂̂��Ƃł������B |

����g�@�̕�@���̊��i���ɂ���B
|
8 ��Â̑�Ꝅ top
�@�ꎵ�l��N�i������N�j�����A�P�H���i���Ɍ��j�̔˓��S����S���Ꝅ�i�_�����c�����Ďx�z�҂ɔ��R���邱�Ɓj���܂�������A�可���i���̑�\�ҁj�E���l�Ȃǂ̉Ƃ��\�Z�����������킳�ꂽ�B
�@���̑O�̔N���勥���i�Ă̑�s��j�������̂ɁA�˂����т����N�v���Ƃ肽�Ă��肵�����߂ł���B
�@�P�H�˂̑S�ˈꝄ�͂��悻����ɂ����߂�ꂽ���A���̔N�̕��ɂȂ�ƁA���x�͉�Ô��i�������j�ł���ȏ�ɋK�͂̑傫���S���Ꝅ�����������B
�@������ *
�P�H�˂̏ꍇ�Ɠ������삾���A�˂��v�H���i�Ԃ����܂����_���̐H���ƂȂ�āj�Ǝ�q���i���˂��݁j��ݕt��Ƃ��ɁA���N�ɕԂ����Ƃ������Ƃ������Ƃ��A�Ꝅ�̐����������肽�Ă��B
* �����́c�@���삪�Â��č��������邵���Ȃ������߁A�˂ł͔_���̔N�v�����������A���N�̏t�ɂ܂�����݂܂ł��Ƃ肠�����B���̂��߈ꗱ�̕Ă��Ȃ��_�Ƃ��������B |

�S���Ꝅ�����������@
���т����N�v�̂Ƃ肽�Ăɔ��R���āA�_�������͂���������B
|
�@�u�Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ȃ�A�������͏����邱�Ƃ��ł��Ă��A���N�͂��Ȃ炸�ꂵ�߂���B
�@�ǂ����݂����߂ɂȂ�Ȃ�A���N���߂ɂȂ��Ă��������Ƃł͂Ȃ����v
�@�Ꝅ���͌��X�ɂ����сA�͂��߉�Ô˂̎x��̒��c���ɂ����悹�����A�₪�ĕ����������A�{��̎ᏼ��ɂނ��čs�i���͂��߂��B
�@�����܁A�Z�S�l�������Ꝅ���́A���̊Ԃɂ݂�݂�ӂ��ꂠ����A�˂̑��y�i�����̕��m�j�S�C�g���o�����Čx������鉺�̖،ˌ��i�o�����j�ɂ�������ɂ́A�����l�̑�W�c�ɂȂ��Ă����B
�@����ɂ������A�˂ł́A�ƘV��S��s��h�����Đ������悤�Ƃ������A�Ꝅ���͔N�v�����Ȃǂ�v�����Ĉ�����Ђ����Ƃ͂��Ȃ��B
�@���̐����ɂ����ꂽ�˂��A�鉺�̒��l�ɖ����Ď���H�ו�����������ƁA�Ꝅ���͂�����������܂܂ɂ݂̂������A
�@�u���ւ��ǂ��Ă����͂Ȃ��A�������̂��ƁA�����ɂ����ċQ�����ɂ���̂��悢�ł͂Ȃ����v
�@�ƁA�܂��܂����킬���āA���܂ɂ��،ˌ����ӂݔj���ď鉺�ɗ������悤�Ƃ������������߂����B
�@���̊Ԃɂ��Ꝅ�̐l���͂ӂ��Â��A�ᏼ��͂₪�Ĕނ�̕�͂̂Ȃ��ɌǗ����Ă��܂��B
�@���܂����̂́A�˂��B
�@�����Ŕ˂ł́A�Ƃ��Ƃ��Ꝅ�̗v�� *
���̂ނ��Ƃɂ��A���̂��Ƃ��Ꝅ�ɓ`�������A�ނ�͂Ȃ����C�ł������B
* �Ꝅ�̗v���@�_���̔N�v�̂�肠�����Ђ������A�Ƃ��ɂ܂������_���̔N�v�͔����ɂւ炳�����B�܂��A�_���ɂ������Ă��т����ԓx���Ƃ�����l�́A���̐E����߂�����ꂽ�B
�@�u�ؕ�����������B����������Ȃ�������A���U�͂ł��܂���v
�@�拭�ɂ��������͂�A�Ă��ł��������ʂ��܂��ł���B
�@���ǁA���̂Ƃ����˂̂ق����䂸��A�Ꝅ���͏ؕ�������ƁA
�@�u�肢�̂��Ƃ͂��Ƃ��Ƃ����Ȃ������v
�@��낱�т̐��������Ȃ���A���ꂼ��̑��ɂЂ������Ă������B
�@�Ꝅ���̗v�����قƂ�ǔF�߂��A�ؕ��܂ŏ����Ƃ����̂́A�߂��炵����ł���B
�@�����A�˂�ɂ���͂ǂ̂��킬�����������̂�����A���̂��Ƃ������ł��ނ킯�͂Ȃ��B
�@�͂����āA��Ô˂͈Ꝅ�������S�ɉ��U�����̂����͂���ƁA����������d���i����ڂ�����j�̑ߕ߂ɂ̂肾���A�O�Z�Z�l�قǂ�S���ɂƂ����߂��B
�@���̒�����A���Y�i�͂���j�Ǝa��i������邱�Ɓj���킹�ď\��l�̋]���҂��o�Ă���B
�@���̗��N�̈ꎵ�܁Z�N�i�����O�N�j�A���{�͑S���ɂ��ӂ�������A�_���̋��i�i���傤���j�ⓦ�U�i�Ƃ�����j�����т����֎~�����B
�@�������A�_���̐����͂��̑O�ォ�狛���Ɉ������A���{���֎~���Ă���ɂ�������炸�A�e�n�łЂ�҂�ƈꝄ����������悤�ɂȂ����B
9 �����v�z�̂߂� top
�@�Əd����㏫�R�ɂȂ�������A���s�ł͉Əd�ƈ�˂������̊w�҂��A�Ⴂ���Ƃ����̊Ԃɑ�ςȐl�C���W�߂Ă����B
�@���O���|�������i�����ԁj�Ƃ������̊w�҂́A�z��̍��i�V�����j�̂��܂�ŁA�͂��߂͈�w�̕����������ŋ��s�ɏo�Ă����̂����A������w�A���w�A�_���̂ق��ɂӂ����肵�A�Ɠ��̎v�z
* ���ƂȂ���悤�ɂȂ����B
* �Ɠ��̎v�z�@�w�Î��L�x��w���{���I�x������{�̍��̂�������������A���{�͑�a���쎞�ォ��A�V�c���������Ƃ�V�c���S�̍��������Ƃ���l���B
�@���Ƃ��A����Ȃӂ��ł���B
�@�u�V�c�͂���̌N�i��N�j������A���ł���A�V�ł���A�n�ł�����B
�@������킪���̐l�X�▜���́A�݂ȓV�c���Ƃ��ƂсA��S�i���ނ����Ƃ���S�j�Ȃ�����ɂƂ߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v
�@���̂悤�ɓV�c������܂��l���������_�i�������j�ł���B |
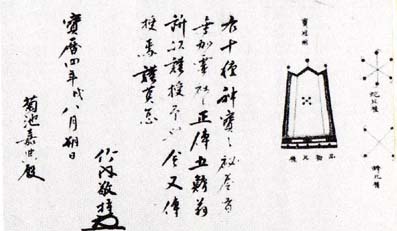
�|�������̎��M�̏��@�����͓V�c������܂��v�z������A
���{�Ƃ̊W���������݂�ێ�h�̌��ƂƑΗ������B
|
�@���쒆�S��`�Ƃ��������Ă��悭�A�|�������͓V�c����Ƃ������A�킪���̐����Ȏx�z�҂��Ǝ咣�����̂��B
�@�������|�������́A�����ς瑸���i����̂��j����������ŁA�����i�Ƃ����j�ɂ��Ă͈ꌾ���ӂ�Ă��Ȃ����A���̂悤�Ȏv�z�͖����ɐ���ɂȂ����������i�����Ƃ����j�̎v�z
* �̌��i�݂Ȃ��Ɓj�Ƃ����Ă��悢���̂������B
* ���������̎v�z�@���{���������Ƃ��Ă����̂ł́A�O���̂��������ɕ����Ă��܂��B���{���������āA�V�c�𒆐S�Ƃ��邠���炵����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���l���B
�@�܂��A�]�ˎ���̒���́A���{�ɂ���Đ���������S�ʓI�ɋ֎~�������A�������肩�����Ђ��߂Ă����̂ŁA�|�������̎咣�͓��R�A���쌠�Ђ̕������肤���Ƃ̊Ԃɂ����x���������邱�ƂɂȂ����B
�@�����̏m�ɂ́A�ނh���A�ނ̍u�`�������ɏW������Ƃ��������\�l�قǂ���A�ނ�͂₪�ĔM���̂��܂�A���������i�������́j�V�c�Ɏ����̊w�����u�`���͂��߂��B
�@�����A��������ɂׂ͂̈ӌ��̂����ʂ��������B
�@�֔��i�V�c���������ځj����i�݂����j��߉q���O�i���������j�����ێ�h
* �ł���B
* �ێ�h�@�V�c�̍s���⌠���́A1615�N�ɂł����u�֒����тɌ��Ə��@�x�v�ł��߂��Ă���̂ŁA�V�c�͂��������Ė������������ɂ��点�悢�A�Ƃ���l�����������Ă����B
�@�u�|�������̐��͊댯�v�z���B���{�Ƃ̊W�������������܂������Ă���̂ɁA�����炩�疋�{���h������悤�Ȃ��Ƃ͂����ׂ��ł͂Ȃ��v
�@�ނ�ێ�h�͂����咣���A�V�c�ւ̍u�`����߂����悤�Ƃ����B
�@�����A�V�c���g�����łɎ����̊w���ɂЂ������Ă���A�u�`���Ñ�����قǂɂȂ��Ă�������A�ێ�h�̔��Θ_�͂Ƃ���Ȃ������B
�@����ɂ���Ă���������@���������߂��ێ�h�́A�����Ŗ��{�Ƃ̘A�����ł��镐�Ɠ`�t�������j��������āA���s���i���i���債�������V�c����ƁA�����喼�Ȃǂ��Ď���������j�ɂ������o���B
�@�u�ߍ��A�|�������Ƃ����҂�������ɂ�������ʐ����ƂȂ��Ă���A���Ƃ̒��ɂ����̉e�����������Ƃ�������҂�����B
�@����āA���V�i�����������{�j�̎�Œ|�����������撲�肢�����v |

�����V�c���@������������1758�N�A
�����V�c��18�̐N�ŁA
�_���Ȃǂ̕��ɔM�S�������B�_���@��
|
�@�ꎵ�ܔ��N�i���N�j�Z���A���s���i��͂��̂������������āA�|��������s���ɂ�т������B
�@�����̎撲�ׂ́A���i�㏼���P���Ɠ�l�̒���s�̓��ȂŁA�����N�̔����ɂ͂��߂�ꂽ�B
�@������u����i�ق��ꂫ�j�����v�Ƃ��ł���B
�@�����A�����̎v�z���A���ꂩ����Z�Z�N��̑��������^���̌��_�ƂȂ�Ƃ͂����������Ȃ������ނ�́A�����̎v�z�̂ǂ����悭�Ȃ��̂��A�悭�킩��Ȃ������B
�@�������A���삩�琳���ɂ�����������������ɂ́A���߂Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B
�@���̌��ʁA�����ɂ������������͋��s�Ǖ��Ƃ��������������܂��Ȃ��̂ł���A������Ƃ̊Ԃɂ����Ђ낪���������v�z�́A�قƂ�ǖ����̂܂ܖ����Ɉ��p����邱�ƂɂȂ����B
top
��������������������������������������������������������������������������������
|