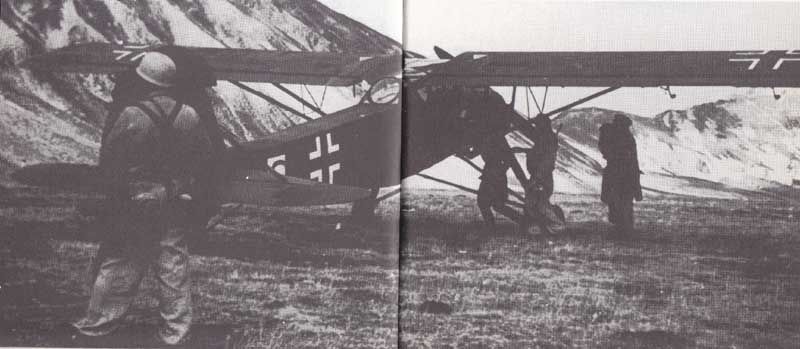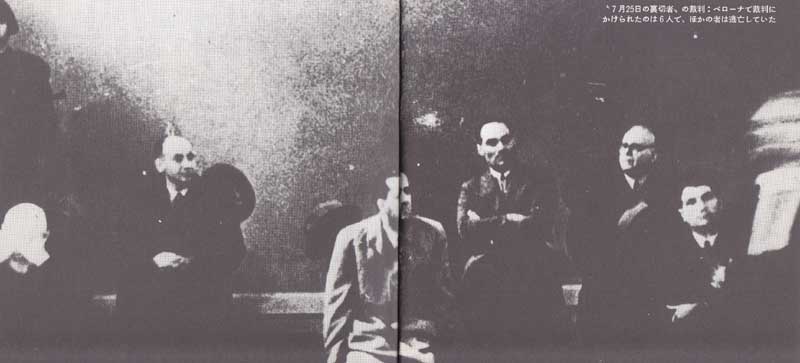|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
8 脱出、そして共和国樹立
ムソリーニを乗せた救急車は、全速力で、クインチノ・セラ通りにある警察隊の宿舎にむかった。
そのあいだ、彼は黙っていた。
しかし救急車がとまり、構内に降り立つと、彼はあたかも視察旅行であるかのように、顎を突き出してあたりを見まわした。
1 まだ悟らない事態の真相 top
自分が逮捕されたのだということは、まだ彼の頭にはうかばなかった。
のちに彼が告白しているように、彼はまだ「すべてこれは、国王がいわれたように、私の身をまもるためにとられた手段だ」と考えていたのである。
彼は将校食堂に連れて行かれ、約一時間ほど一人にされたあと、またべつの自動車で、レニャーノ通りの警察隊宿舎にはこばれた。
そこについたとき、ムソリーニはひどい病人のようにみえたので、警察隊長が医者をよんだ。
医者は、彼の脈拍が非常に遅く、顔色も真っ青で、まるで死人のようであったといった。
彼は食事をだされたが、それをことわり、ただ顔をそるために床屋をよんでほしいと頼んだ。
そして十一時にあかりを消して、寝ようとした。
二時間後に、ムソリーニにあてたバドリオ元帥のメッセージをたずさえて、陸軍の将官が到着した。
そのメッセージには、ムソリーニの抑留は、ただ彼の身の安全をはがるためであり、また各方面の信頼すべき情報によれば、彼の生命をねらう重大な計画があるためだ、と書かれていた。
さらに、もし彼が希望する土地があれば、あらゆる正当な考慮をはらって、その地につくまで安全に護衛するであろう、とのべられていた。
2 ポンツァ島に幽閉をきめる top
しばらくためらってから、ムソリーニは返書を口述した。それは従順で、卑屈といってもいいほどの手紙だが、彼はそのなかで、故郷の別荘、ロッカ・デル・カミナーテに行きたいとたのみ、さらにバドリオにたいして
「これまで一緒に仕事をやってきたことを想い出して、面倒なことは何も起さないし、あらゆる面で協力する」
と約束した。
そして手紙の最後を「バドリオ元帥が、国王陛下の名によって命令をうけた重大な任務が、成功の栄冠をもってかざられることこそ、私の熱烈な希望である。私は二一年のあいだ、国王の忠実なしもべであり、今後もそうであろう」とむすんだ。
だが、バドリオがこの返書をうけとったとき、すでに、ムソリーニをロマーニヤにかえさないほうが望ましい、という決定がくだされていた。
フォルリの当局者は、ムソリーニをどこかほかの場所へ連れて行くよう求めていた。というのは、いま彼にたいする反感が非常に強いので、彼がリンチをうけないとは保証できない、というのであった。
そこで、海軍諜報部長フランコ・マウゲリ提督に、ムソリーニをひそかに小さなポンツァ島〔注〕に連れて行くよう訓令がだされた。
〔注=ローマとナポリの中間にあるガエタ湾の島で、政治犯の流刑地であった〕
3 初めて知った“絶望の極” top
七月二十七日夕刻、ムソリーニは再び自勣車にのせられ、警察隊宿舎から連れ出された。
彼は計画の変更についてはなにも知らされておらず、フラミニア通りを通って北方に行くものと思っていた。
しかし自動車のブラインドの隙間から、彼はアッピア通りとアルバノ通りを通って南の方に向っているのに気がついて、「我々はどこに行くのだ?」とたずねた。
彼につきそっていた警察官は「南のほうです」と答えた。
「ロッカ・デル・カミナーテではないのか?」
「べつの命令がきました」
自動車がガエタにとまったとき、ムソリーニは、法王ピオ九世が一八四八年にここに避難し、また、イタリア統一の大英雄、マッツイーニが一八七〇年にここに抑留されたことを想い出して、憂鬱ではあったが、誇らしくも思った。
彼は、マッツイーニのいた同じ部屋にいれられるかもしれないとさえ、おもいをめぐらしはじめた。
しかしまもなく、その夢も消えた。
彼はポンツァ島に連れて行かれたが、そこには一九二五年に、彼の生命をねらったかどで逮捕された元社会党議員のチトー・ザンボーニや、かつてフォルリで、彼と一緒に投獄されたこともある、社会党のピエトロ・ネンニ〔注〕もながされてきていた。
〔注=戦後、社会党左派の幹部で副首相、外相などを歴任〕
彼のために用意された、ポツンと離れた灰色のくすんだ家は、かつてエチオピアの愛国者ラス・イメルの牢屋であった。
彼が案内された寝室はちょうどしっくいを塗ったばかりで、部屋のなかには、むきだしの鉄の寝台、酒屋からもってきたきたない木の机と、シートから中味のはみだした椅子以外は、なんの家具もなかった。
隅には安物の洗面器があった。
彼は絶望におちいった。
突然、彼はコブシをにぎりしめ、窓のほうに向って「もうこんなことはたくさんだ!」と怒鳴った。
そして両手で頭をかかえこみ、椅子に崩れ落ちた。
4 キリストに似ていると喜ぶ top
このような光景を、困惑しながら見まもっていたポンツァ警察隊の特務曹長は、部屋に入って、ファシストの敬礼をした。
彼は神経質そうに、そこにつっ立って何か言おうとしたが、言葉が咽喉につかえてしまった。
「閣下、我々はあなたが、ポンツァにこられるとは知りませんでした。
私は、ほんの三〇分まえに知らされたのです」
「心配するな。私はこれまで、時々君とあって話したいと思っていたが、もう今となっては遅過ぎた」
ムソリーニはこの島に一〇日間とどめられ、特務曹長や牧師、医者、そのほか訪問を許された人々と話しあい、自分のやったことを正当化し、彼を失脚させた“あわれむべき陰謀”を非難した。
また数時間も一人にされていたので、カルダッチの『オディ・バルバール』〔野蛮人〕をドイツ語に翻訳する仕事にうちこんだ。
またジュゼッペ・リッチオッティの『キリストの生涯』を読んで、キリストと自分の運命のあいだに、“驚くほど似たところがある”のを発見した。
七月二十九日の誕生日には、ゲーリンングからの手紙をうけとることを許された。
それは、彼との兄弟のような友情と、完全な団結を保証したものであった。
二日後、彼は妹につぎのような手紙を書いた。
「私は葬式――どんな形式の葬式であっても――を望まない。
もしわが故郷、ロマーニャの人々の怒りが静まったなら、私はぜひロッ力に行くことを許されて、そこで、なるべく早くきてほしいと思っている、私の生涯の終りを、静かに待ちたいものだ」 |
5 独の救出おそれ、また移す top
さてドイツ軍が、ムソリーニをポンツア島から救出しようとくわだてるおそれも考えられたので、バドリオ政府は八月六日、ムソリーニをもっと安全で、人里離れた、サルジュア島北方の海軍基地のあるラ・マッダレーナ島に移すよう、マウゲリ提督に指示した。
ここで、ムソリーニは、すっかり気おちしてしまった。
ラ・マッダレーナ島は大空襲のあと、ほとんどの島民が退去して、荒れ果てた寂しいところであった。
彼はまた、そこの雰囲気が“敵対的、かつ脅迫的”なことを知った。
とくにこの海軍基地の司令官は、攻撃してきた英駆逐艦に、なんの損害もあたえずに、味方の艦三隻を失ったかどで、彼が軍法会議にかけた男であった。
さらに困ったことに、この男はイギリス人の妻をもっていたのである。
ラ・マッダレーナ島ですごした三週間は、ポンツァ島ですごしたときよりも、もっとみじめであった。
そこはたえがたいほど暑く、風もなかった。
すべてのものが、太陽のもとで、クギづけにされているようにみえたほどだった。
彼はほとんどイギリス人がたてた別荘を離れず、そこで“哲学的、政治的、文学的”な文章で、日記をうずめたり、またこの誕生日に、ヒトラーから贈られた二四冊のニーチェ全集をよんで、ほとんどの時間をすごした。
このニーチェ全集には、ケッセルリンク空軍元帥からの、つぎのような添書きがついていた。
「もし、このドイツ文学の偉大な著作が、ドゥーチェ〔統領〕、あなたに少しでもたのしみをあたえるならば、またあなたがこれを、総統の親愛の情の表現であると考えられるならば、総統は幸せに思われるでしょう」 |

「一九二二年、ドゥーチェが王政を救った時、
国王は感謝された」:ムソリーニの失脚後、
イタリアの連合軍占領地域に投下されたドイツのビラ
|
6 グラン・サッソの山頂に! top
一方ヒトラーは、ムソリーニがどこにいるのか発見しようと努力していたが、まだわからずにいた。
ヒトラーはマッケンゼン大使に、国王に会見して、ムソリーニを訪問する許可を求めるよう訓令した。
しかしバドリオは、ムソリーニ閣下の個人的利益のために、遺憾ながらその訪問に同意することはできない、と答えた。
そして、ムソリーニが、ラ・マッダレーナで発見されるのではないかとおそれて、今度は本土のアペニン山脈の最高峰グラン・サッソにある、スキー客専用のホテルにうつした。
ここについたとき、ムソリーニは子供のように喜んで
「オー、世界中でもっとも高い牢獄よ!」と叫んだ。
彼は、祖国の運命よりも、自分自身の悲劇のほうに、はるかに関心があるかのようにみえた。
自分の運命を、ナポレオン、シーザー、キリストの運命と比較しながら、どうやら、彼にとっての最大の問題は 「いったい、歴史は自分にどのような審判を下すのだろうか?」にあるようだった。
ホテルの女主人は、つぎのようにのべた。 |

ムッソリーニが監禁されたグラン・サッソのホテル:
ここは世界でもっとも高い牢獄だった
|
「彼は悲しみも、屈辱感もみせなかった。
ただ自分が見つめられていると知ったときには、わざと考えぶかそうな表情をつくった。
彼は、読書や著述だけで時をすごしたわけではなかった……
時々窓ぎわに立って、雄大なグラン・サッソを双眼鏡で眺めたり、あるいは構内の低い壁に腰をおろして、有名な『セントヘレナ島のナポレオン』の油絵のように、遠くの方を、放心したようにみつめていた」 |
7 連合軍に引渡す放送に興奮 top
彼はラジオがながす戦争のニュースにも、特別な興味をみせなかった。
彼はニュースで、残酷な空襲や、多くの人命が犠牲にされたこと、連合軍のシチリア島占領、イタリアにドイツ軍が侵入したこと、降伏と休戦条約、さらに国王とバドリオ政府が、ローマからブリンディシに逃げだしたこと、などを知った。
しかし彼は、これらの事件を、自分が個人的に関係していないので、まるで他人ごとのように聞いていた。
だがついに彼は、休戦条約に「ムソリーニは連合国に引き渡される」という一項があることを正式に発表したアルジェ放送を伝える、ベルリン放送を聞いたのであった。
監視兵の一人の話によると、この放送を聞いた翌日の朝早く、ムソリーニは、自分はけっしてこのような屈辱をうける気はなく、自分の拳銃をわたしてほしい、ともとめたメッセージを彼に送った。
このメッセージをうけて、監視兵がムソリーニの部屋にかけこんでみると、彼は寝台のうえに座り、手首の血管を切ろうとしていたかのように、ジレットのカミソリの刃を、無器用にふりまわしていた。
監視兵は、ムソリーニの手からカミソリの刃をもぎとり、そして部屋中から自殺に使われそうなものを、一切取り去った。
それから彼がムソリーニに、自分はけっしてイタリア人を、イギリス人に渡すようなことはしないと約束すると、ムソリーニはワッと泣きだした。
しかし彼は、心のなかでもっと悪いことに思い悩んでいることを、ムソリーニには知らせなかった。
それは、彼が「ムソリーニを、生きたままドイツの手に渡してはならない」という重大な訓令を、うけていたことである。
|
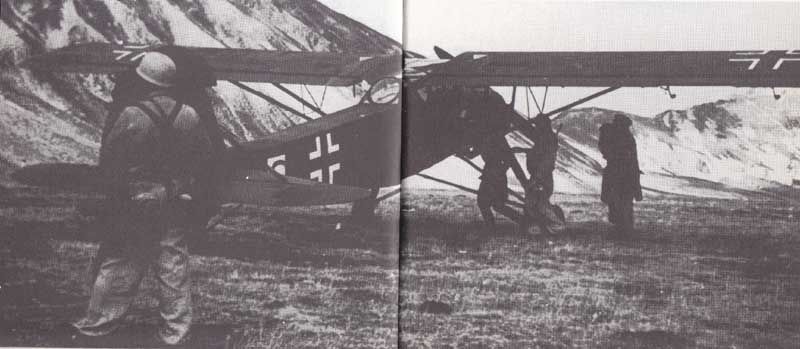
ムソリーニ救出のため出発準備をするフィーゼラー「シュトルヒ」機
|
8 独将校、空から救出を計画 top
ドイツが計画していたのは、まさにこのこと、ムソリーニを生きたまま救出することであった。
この不可能ともいえる任務は、武装親衛隊の特別部隊の若い大尉、オットー・スコルツェニーにあたえられた。
この命令をあたえられたとき、スコルツェニーは、ムソリーニがどこにいるのか全く知らなかったし、まして「自分の友人で、忠実な戦友を救出せよ」というヒトラー総統の命令を、どのようにして実行するか、おもいもうかばなかった。
まもなくスコルツェニーは、ムソリーニがポンツアにいることをつかんだが、“囚人”はラ・マッダレーナ島に移されてしまった。
そしてムソリーニを、そこから救出する作戦をねっているうちに、彼はまたグラン・サッソに移されたのだった。
ムソリーニをグラン・サッソから救出することは、島から連れ出すより、はるかに困難なことであった。
とくに高い山上にいる、ムソリーニのところへ行くただひとつの可能な方法は、ホテルのうしろの斜面に、訓練された要員で編成したグライダー部隊を、強行着陸させる以外にはないように思われた。
そしてうまくいけば、あらかじめパラシュート部隊で占領する予定の、アクイラ飛行場から、ハインケル機でムソリーニをドイツに運ぼうとする計画であった。
スコルツェニーは、九月十二日にこの危険な仕事を開始したが、成功の可能性は、全くすくなかった。
そして彼の部隊の通信兵が、ローマからハインケル機をよびよせるための空軍との連絡に失敗し、さらにかわりの、谷間に離着陸できる軽飛行機が、着陸のさい大破して使えなくなったとき、成功の可能性は増々すくなくなったように思われた。
こうなると、ほかのすべての方法が失敗したばあいに、最後に採用するようきめられていたフィーゼラー
「シュトルヒ」機〔注〕を山の頂上の台地に着陸させて、ムソリーニを運び出す方法をとるよりほかなかった。
〔注=コウノトリの意味。離着陸距離のきわめてみじかい軽飛行機で、偵察、連絡用に使われた〕
しかし、先決問題は、ムソリーニを、イタリア警察隊の、保護という名目の“監視”から無事に救いだすことができるかどうかであった。
このために、スコルツェニーは、イタリアの将軍、ソレティの援助をうけることにした。
9 強行着陸に成功、ついに救出 top |

オットー・スコルツェニーに救出されたムソリーニ

スコルツェニーと一緒のムソリーニ:
救出を喜んでいるよりも、むしろ心配している。
|
スコルツェニーの奇襲部隊が、グライダーで強行着陸すると、ソレティ将軍は「撃つな! 撃つな!」と叫びながら、驚いているイタリア警察隊のほうへ、空地〔あきち〕を横ぎって走っていった。
奇襲部隊は、短機関銃をかまえて、ホテルのほうにはしったが、イタリア人は発砲するなど思いもよらず、避難所に逃げこんだ。
おかげでスコルツェニーは、ホテルの一階にかけこんで、通信士の椅子を蹴飛ばして、設置してあった無電装置を破壊することができた。
彼はすぐムソリーニと対面し、きちんと“気をつけ”の姿勢をとって、劇的に
「ドウーチェ? 総統が私を派遣されました! あなたは自由です!」とのべた。
ムソリーニは腕をのばして、スコルツェニーを胸にだきしめ、劇的に
「わが友アドルフ・ヒトラーが、私を見捨てるはずはない」といった。
彼は階段をおりて、スコルツェニーとともに戸外に現れたが、顔色は青く、みすぼらしい服、黒いへりの広い帽子、それに大きすぎる冬の外套をきて、まるで年老いた病人のようだった。
パイロットがこまったことは、おもそうなスコルツェニーが、ムソリーニと一緒にフィーゼラー「シュトルヒ」機に乗って、プラクティカ・ディ・マーレ飛行場へ行く、といいだしたことである。
パイロットは、一人のお客を乗せてさえ、離陸できるかどうかを首をひねっていたのに、まして二人を乗せてとは……。
ムソリ−ニも同じように考えたが、それを口にだすには、誇りが許さなかった。
それに、ドイツ奇襲部隊の隊員が、イタリア警察隊の連中と一緒に、ホテルからの道にならび、ファシスト式やりかたで“ドゥーチェ!ドゥーチェ! ドゥーチェ!”と叫んで、ムソリーニに敬礼したのだ。
ムソリーニはもうあとにひけなかった。彼が飛行機にのるとき、ちょっとためらったことに、スコルツェニーは目ざとく気がついた。
しかしなにもいわなかった。
また飛行機が轟音をあげて、台地を滑走しても、車輪がまだ地面から離れていないのを感じながらも、ただ黙っていた。
飛行機は瞬間的に上昇したが、ちょっとおちて岩にあたり、それから台地の端をこえて谷に突っ込んでいった。
それはうすい空気のなかを、絶望的におちていった。
そして風がムソリーニニの耳もとでうなったとき、彼は“本当の恐怖の瞬間”を味わったと、のちにスイスの記者に告白した。
やっと飛行機は、地上数十メートルスレスレで機首をたてなおし、南方のアベツァーノの方に向った。
10 地におちたみじめな“巨星” top
プラクティカ・ディ・マーレ飛行場から、ムソリーニは、ハインケル機にのりかえて、ウィーンにおくられた。
そこにヒトラーが救出を祝う電話をかけてきたが、ムソリーニは
「私はつかれた。非常につかれた。休みたい」といって、電話に出ることを断った。
ゲッベルス宣伝相は、これでムソリーニが、まだ役にたつと考えた。
彼はヒトラーが、ファシズムの崩壊を“ナチズム崩壊の前奏曲”と受取られるのをおそれて、ムソリーニを再び権力の座につけようと、望んでいることを知っていた。
しかしゲッベルスは、それと違って、ムソリーニをぬきにしたイタリアの構想に賛成していた。
すなわちドイツ人が好きなようにできる、イタリアを望んでいたのだ。
そしてサポイ王朝〔注〕とは全く関係のない、新しいファシスト政権を北イタリアに樹立する、というヒトラーの提案にムソリーニが同意したのは、そうしなければイタリアがドイツに占領され、支配されることを知ったためであった。
〔注=イタリア国王〕
ムソリーニがドイツの計画をしぶしぶ受入れたこと、彼が明らかに私的な生活に戻りたいと望んでいること、裏切者たちを処罰せずに放置していること、これらはヒトラーとゲッベルスを、ともに幻滅させた。
ムソリーニは、イタリアの破局から、ヒトラーの期待したような結論を引きだそうとはしなかった。
ゲッペルスは日記に、つぎのように書いている。
「ムソリーニは当然のことだが、総統にあい、再び自由の身になったことに大喜びしていた。
しかし、総統がムソリーニに第一に期待したことは、裏切者に十分な復讐をくわえることであった。
しかしムソリーニはそんな気配をみせず、それが彼の本当の限界をしめしていた。
彼は総統やスターリンのような、革命家ではない。
彼はイタリア国民に、非常に密接にむすびついているので、世界的な革命家や、反乱煽動者としての、ひろい資質に欠けている……
結局彼は、イタリア人以外のなにものでもなく、彼はこの遺伝から脱することはできない。
年老いたヒンデンブルク〔注〕はかつて、ムソリーニといえども、イタリア人からイタリア人以外のものをつくりだすことはできないといったが、これは全く正しかった」 〔注=ヒトラーのまえのドイツ大統領〕 |
ゲッペルスは、自分がヒトラー総統とちがって、かつて一度もムソリーニを崇拝したことがなかったことをみずから祝って、椅子にもたれ、皮肉な調子で
「ドゥーチェ! ドゥーチェ! ドゥーチェ!……」
と、ファシストの口調を真似してみせた。
11 ヒトラーの傀儡〔かいらい〕政権ヘ
top
ムソリーニは、すでに自分は歴史的人物――過去の人――になってしまったと考えていたので、復活したファシスト党の指導権を、ほかの人物にゆずりたいとのぞんだ。
しかし彼以外のイタリア人は、だれもヒトラーの心にそわなかった。
たとえば、親ドイツ派のロベルト・ファリナッチ、反ユダヤ主義者ジョバンニ・プレツィオシ、政治的狂信主義者アレッサンドロ・ハポリーニなどの名があがったとき、ヒトラーは考えてみようともしなかった。
彼らはムソリーニの逮捕後、反革命を組織しようともせず、また国王に全軍の指揮権をドイツ軍に渡すよう強制するどころか、さっさとドイツヘ逃げこんできたのである。
「こんなイタ公たちと一緒に、なにができるか!」
ヒトラーはイライラしながらそう叫んで、彼らを無視した。
ムソリーニは肉体的、精神的にも弱くなっているにもかかわらず、ほかの人物に換えることができなかった。
新しいイタリア共和国を指導する人物は、ムソリーニでなければならず、またその本拠は、ローマ以外の地におかれることになった。
というのは、ローマは近く連合軍の手におちるものと予想されたので、新しい首都は、ローマから五〇〇キロも離れた、ガルダ湖畔のサロがえらばれた。
かくて、このイタリア社会主義共和国〔注〕は、一九四三年九月十七日、同日づけの六項目の命令によって樹立された。 〔注=通常、サロ共和国という〕
その第一項目は、イタリアにおけるファシズムの最高指導権を、ドゥーチェが再びにぎることを規定していた。
またほかの項目は、ファシスト党がファシスト共和党として復活したこと、ファシスト国民軍の再生、ドイツとの同盟の確認、七月二十五日事件の裏切者を処罰する党の決意、などを表明したものであった。 |

救出後、ヒトラーと自動車に同乗するムソリーニ

傀儡政府樹立:ヒトラーの要請で、しぶしぶ、
正式カムバックを表明するムソリーニ
|
12 裏切者の処刑をきめる top
新政権の閣僚には、ロベルトラァリナッチ、ジョバンニ・プレツィオシの二人の過激派は含まれていなかったが、いずれも裏切者たちを裁判にかけることを認めており、ムソリーニもこれについては、当然のこととして決意しているようにみえた。
裏切者たちの名前があげられると、彼の表情は固くなり、すでに心をきめているようにみえた。
しかし彼の秘書たちは、彼が心のなかで本当はどう思っているのか、見当がつかなかった。
ある者は、ムソリーニがその大理石のような表情のうらに、ドイツ側の要求のいいなりになっている屈辱を、隠そうと努力しているのだと信じた。
またある者は、彼が愛娘と孫にたいする憐れみの情を――というのは娘婿チアノ伯は、ほかの裏切者たちとともに、明らかに処罰されなくてはならなかったので――隠そうとしているのだと思った。
またべつの者は、彼が厳格な正義と公正さをしめし、往年の名声をとりもどそうと努力していると想像した。
外務次官セラフィーノ・マゾリーニ伯にたいして、ムソリーニは、裁判は国家の純粋理性のために必要であると語った。
またムソリーニは、ジャーナリストのイバノエ・フォッサーニに、もっとはっきりと「裁判はドイツとの信頼感を回復するために、必要である」と語った。
確かに彼は、裏切者たちをドイツ人の手から救おうとする、家族や友人からの訴えを固くこばんだ。
娘のエッグが駆け付けてきて、ほとんどヒステリー状態になったとき、ムソリーニは彼女に
「そんなに逆上するな」とつぎのようにさとした。
「ジッペントロップは、おまえの夫、チアノの裏切りについて、十分すぎる証拠をあたえてくれた。
とくにイギリスに関してだ。彼を釈放することなど、問題にならない」
またエッグが、彼女の父、子供たちの祖父としてのムソリーニに、熱情をこめて哀訴し、ワッと泣きくずれたとき、ムソリーニはつぎのようにさとした。
「古代ローマ人の父親は、息子たちを犠牲にすることをけっしてためらおうとはしなかった。
ここにいるのは、父親でも祖父でもない、ファシズムのドゥーチェなのだ」 |
|
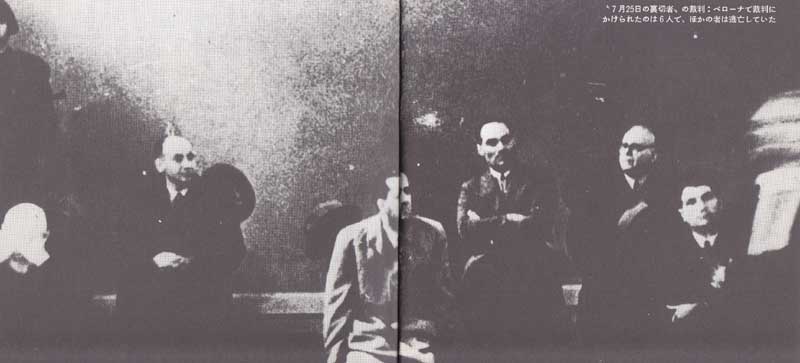
“7月25日の裏切者”の裁判:ベローナで裁判にかけられたのは6人で、ほかの者は逃亡した
|
13 椅子にしばりつけ五人銃殺 top
こうして裏切者の裁判は、一九四四年一月、ベローナではじまった。
ムソリーニは裁判長にたいし、“被告がだれであろうとも、考慮することなく”審理をすすめるように訓令し、裁判に干渉するようなことはいっさいしなかった。
裁判にかけられたのは、チアノ伯のほかにわずか五人――デ・ポーノ、チアネッティ、マリネリ、ゴッタルディ、パレスキ――であった。
ほかの一三人は、スペインヘ逃げた指導者のグランディのように、外国に逃れるか、イタリア国内に隠れていた。
これらの人々のうち、大評議会で反対投票したものの、苦悶の末、翌朝になってその投票を撤回したチアネッティをのぞき、すべて死刑を宣告された。 |

1944年1月、ベローナで5人の裏切者――ゴッタルディ、
マリネリ、パレスキ、チアノ、デ・ボーノの銃殺が執行された
|
そして処刑の日がきたとき、人々は、ローマ進軍の四天王の一人で、尊敬をうけていた軍の長老デ・ボーノ元帥は、すくなくとも死刑は免れるであろう、と思っていた。
しかしムソリーニからは、減刑について、なんの命令もこなかった。
こうして五人は、学校の椅子にしばりつけられたまま、一列に並べられて、うしろから射殺された。
ムソリーニは、処刑のニュースをじっと黙ったまま聞いていた。
あとになって彼は、彼らがりっぱなイタリア人、またファシストとして死んだことを喜ぶ、とのべただけであった。
しかし彼は、その朝執務室に行くまえに、全く朝食を口にせず、妻のラケーレは、彼が“絶望の涙を浮べていた”のに気づいた。
ムソリーニは、信頼する秘書ジョバンニ・ドルフィンに、つぎのようにうちあけた。
「我々は、イタリア国民の同情もうしなうだろう。彼らは私の苦しみを、けっして理解しないだろう」
14 元気になったり落胆したり top
しかし翌日になると、彼の気分はもう一度かわった。
彼は閣僚の一人に、きびしくこういった。
「こうして、首を切りおとしはじめた以上、我々はとことんまでやろう」
そして彼は警察長官に、信頼できないファシスト党員のリストをわたし、即刻逮捕するよう命じた。
しかしその命令をだすやいなや、また彼はそれを撤回した。彼はまた気がかわったのであった。
このような突然な心がわりは、当り前のことになっていたので、彼の側近は、あたえられた命令を実行するまえに、一、二日間は待つという習慣になっていた。
非常に興奮したあとには、かならず陰鬱〔いんうつ〕な落胆がやってきた。
情け容赦のない決意のあとには、不安と動揺が続いた。
突然激しい怒りが爆発すると、そのあと静かな悲しみと、すべてを許してしまう気持ちがやってきた。
ファリナッチはリッペントロップに、ムソリーニは“明らかに梅毒の第三期”にあると保証した。
しかしムソリーニがイタリアに帰るとき、ヒトラーが一緒に行くよう命じたドイツ人医師、ゲオルグ・ツァハリエ博士は、ムソリーニの血液を注意深く分析したが、性病にかかったきざしはみつからなかった、といっている。
しかし博士は、ムソリーニが健康どころではなく、神経衰弱、不眠、食欲不振に悩んでいるとのべ、ベルリンにつぎのように報告を送っている。
「ムソリーニは、ごくわずかしか食事をとらない。彼は胃の痛みで、睡眠不足になっている。
血圧はひくく、皮膚はかわき、腹部は非常にやせ、肝臓がはれている」 |
15 政治への意欲を失う top
ムソリーニは、サロ北方数キロのところにある、ガルニャーノの、フェルトリネリ荘の執務室で、長時間にわたって仕事をしていた。
しかし彼がそんなふうにしてすごした理由は、彼をイライラさせる嫁たちや、騒々しくあそびまわって、邪魔をする孫だちから逃げだすためであり、また近くのピットリアーレ荘の一室に囲っていたクラレッタ・ペタッチを妻がみつけたため、その妻とのいさかいを避けるのが目的と思われた。
確かに彼は、執務室では新聞を読み、切りぬきをとじこみ、注釈をくわえ、また論文を書いたり、閣僚や新聞記者などの訪問者だちと、とりとめのない話をして時をすごしたが、建設的な仕事はなにもしなかった。
そのうえ彼は、ほかの人々が全くつまらないと考えたもの、事実見当はずれの仕事にうちこんだりした。
たとえば、集団農場を導入する可能性とか、福祉国家の枠づくり、またファシズムに、彼が青年時代に失ってしまった社会主義的原則を取入れること、法王庁に新政権を承認してもらうこと、貧乏な結核患者のために病院を設立すること、などであった。
そして彼は、突然これらの考えに熱中したかと思うと、またすぐ情熱をなくしてしまい、すべてを断念して、また元のあきらめと、気おちした内省的な気分に戻るのであった。
当時サロにいた若いドイツ軍将校フュルスト・ウーラッハは、故郷への手紙で、つぎのように書いている。
「ムソリーニは、あらゆる政治的問題から手をひこうとしている。
もしあるドイツ軍の将官が、なにか要望するために彼のもとをたずねると、彼は“ああ、それなら、国防相のグラチアーニと話してください”という。
またもしレイエルスかだれか経済専門家がくると、彼は“では、経済相におあいになりませんか”という。
さらに、ほかの者よりずっと強硬な訪問者が、大統領ムソリーニ自身の決定が重要なのだと主張すると、彼は“もし決定が本当に重要であるならば、私がそれをすることはできない。
ドイツ人が決定を下すのであって、私はたんにガルニャーノの市長にすぎない”と答えた」 |
16 “牢番”ドイツにつよい反感 top
このような、ドイツ人にたいする反感の爆発は、普通のことになっていた。
彼は、窓の外を眺めても、いつもドイツのヘルメットが見えるだけだ、とこぼしていた。
イタリア駐屯親衛隊の司令官カルル・ウォルフ将軍と、親衛隊将校オイゲン・ドルマン大佐の二人が、ムソリーニのいわば“牢番”であった。
ムソリーニの不平は、かならずしも不当ではなかった。
ドイツ軍の警備兵が、いつも構内をパトロールしていたし、ドイツ大使のルドルフ・ラーンは、ウォルフやドルマンと同様、たえずムソリーニのもとを訪れていた。
フュルスト・ウラッハは、つぎのように語った。
「ムソリーニは、驚くほど厳重に警護されていた。
私は庭園を通り過ぎるとき、いつも歌をうたうか、口笛をふいた。
というのはすべての木の影に、拳銃をもった親衛隊員が隠れていたからである。そこには、何人かのイタリア人の黒シャツ隊員もいたが、それはただ体面をつくろうためだけであった」 |
このような環境のなかでも、ムソリーニは、実にいろいろなことをよくしやべった。
自分の過去の栄光と業績や、自分がイタリアのために行ったすべてのこと、同時代の人物などについて。
ルーズベルトについては、かつてないほど強く嫌うようになったが、チャーチルは、崇拝すべき“頑固な老人”と評し、スターリンの力をうらやみ、またフランス指導者たちの“生物学的な頽廃”について語った。
彼はさらに、フレデリック大王、ナポレオン、ガリバルリー、ビスマルク、ワシントン、マッツィーニなど過去の偉人たちをも話題にした。
とりわけ彼は、自分について語った。若くて熱心な人民文化相フェルナンド・メザソーマは、つぎのようにのべている。
「ムソリーニはただ、歴史と、そのなかで自分がどのようにみえるかだけを考えていた」 |

人民文化相フェルナンド・メザソーマ
|
17 突如、興奮して大いに自賛 top
あるとき、党本部での会議の席で、退屈した彼は、突然たちあがって部屋を歩きまわり、それから立ち止まって腕をくみ、夢中になってつぎのように自問自答した。
「ファシズムとはなにか? それは一言で答えることができる。ファシズムとはムソリーニ主義である。我々は自分をあざむいてはならない。
ファシズムは、主義としてはなにも新しいものをふくんではいない。それは近代的危機の産物である」 |
彼は、ファシズムを創り出したのではない。
彼はただ、イタリア人が生まれつきもっているファシズム的傾向を、利用したにすぎなかったのだ。
「もしそうでなかったとしたら、私は、二〇年ものあいだ、人々に慕われることもなかったであろう。
イタリア人は、もっとも移り気な民族である。
私が去ったとき、歴史家や心理学者は、どうして一人の男が、このような国民をこんなに長いあいだ指導する力をもつにいたったかを、かならず問題にするものと確信する。
たとえ私が、ほかになにもしなかったとしても、このひとつのことだけは、私を忘れさせることを不可能にするであろう。
ほかの人々は、銃剣をもって征服するであろうが、おそらく私がやったように、人々の同意をえてやったのではないことは確かだ。
人々が我々をさして、ブルジョア階級の自衛軍というならば、それは恥知らずの嘘つきだ。
私はだれよりも、労働者の進歩のためにつくした――私はくもりのない良心をもってそう言い切ることができる。
私はまた、独裁制を崇高なものにした。
実際に私は独裁者ではなかった。
なぜならば私の権力は、イタリア国民の意思にほかならなかったからである」 |
18 「私は狂気の詩人である」 top
しかしときとして彼は、歴史がこのように有利な判決を、自分に下すとは確信できないこともあった。
彼は、かつて一九〇二年、北イタリアのボー河畔にあるグァルティエリで一緒に教師としていたときからの友人で、元共産党員のニコフ・ボンバッチに、つぎのように語った。
「我々は完全に敗れた。あるとき、歴史は我々を審判し、なるほど多くのビルがたち、多くの橋が川にかけられたと評価するであろう。
しかし精神に関するかぎり、最近の人間の良心の危機にさいし、我々は共通して、時流の単なる手先であり、まだ最後まで手先だった、と結論されざるをえないだろう」
彼はべつの日に、つぎのようにのべた。
「ヒトラーと私は、狂人のように幻想にとりつかれた。我々には、ただひとつの希望が残されている。
それは神話を創ることだ」 |
ムソリーニは、いまやドイツとの同盟がそもそも、彼とイタリアにとっての災厄であったことをさとった。
彼はニコラ・ボンバッチに、つぎのように告白した。
「ヒトラー・ドイツは、ファシストであった。
大集会、目のくらむような行進、活力と、軍事的栄光の叙事詩的な雰囲気、これらはすべて、私を盲目にした。
私はそれを認めざるをえない。私はまた神秘的で、英雄的な生活や、征服、栄光を愛した。
私は、自分の未来が“独・伊枢軸”にかかっていると考えた。
私は芸術家の国民を、戦士の国民にかえようとした。
私は、政治家であることを忘れ、数百万人の運命を無視した」 |
しかし彼は、フランシスコ・コッポラにたいしては、自分はけっして政治家ではなく、むしろ変えようとこころみた国民と同じように芸術家であった、とつぎのようにのべている。
「私は政治家ではない。私はむしろ詩人、それも気の狂った詩人そっくりだ」
19 気まぐれな構想、また絶望 top
一九四四年六月に、ムソリーニを訪問したオットー・スコルツェニーは、つぎのように回想している。
|
「彼はもはや、閣僚たちを指揮する強力な首領ではなかった。私には、彼はむしろ哲学者のようであり、行動することを完全にやめてしまったようにみえた」 |
ムソリーニは、自分がしなければならない仕事が、まだひとつ残っていると感じていた。
それは和平を交渉することによって、イタリアを戦争から救いだすことであった。
戦線の後方でのイタリア人相互のあらそい、また内戦の様相をおびそうになってきたファシスト対反ファシストとの、ますます拡大する戦いに打ちひしがれて、ムソリーニは時々、ファシスト党をもっぱら軍事的な動員組織に改編しよう、と考えた。
すなわち、一九歳から六〇歳までの男子で、まだ共和国の軍隊に入っていない者をすべて動員し、人殺しや敵との通謀者にたいし、公共の秩序と市民の平和的生活をまもるための、武装した黒シャツ隊をつくりあげようというのである。
しかし彼は心のなかでは、このような措置をとるにはすでに手遅れで、和平を講ずるよりほかに、道のないことを知っていた。
一九四五年三月、ムソリーニは、きたるべき共産主義との戦いで、もう一度指導者になれるかもしれないという、見はてぬ夢を抱いて、ミラノ大司教シュステル枢機卿と交渉をはじめた。
しかし枢機卿は、バチカンから“連合国は無条件降伏を主張しており、和平交渉に入る積りはない”ことを知らされていた。
ムソリーニは、現実からますます逃避し、絶望的になって、ガルニャーノの夢の世界へと帰っていった。 |

ミラノ大司教のシュステル枢機卿
|
20 ひたすら夢の世界のなかで top
彼は、ドイツの新聞係事務官の妻に、つぎのように語った。
「私の星は地におちた。私の任務は終った。
私は働き、自分を励ましているが、それがすべて喜劇であることを知っている。
私は、嵐のなかの船の船長である。船は壊れ、私は荒れ狂う海のなかで、破片につかまって漂流している。
行動することも、事態を救うことも、もはや私には不可能である。
だれも私の声を聞かないし、私はいまや、沈黙のなかに身をひそめている……
死は友だちになり、もはや私を驚かさない。
死は、あまりにひどく苦しんだ者にとっては、神からの贈物である……
しかし、いつの日か、きっと世界はまた、私の声に耳を傾けるであろう」 |
メザソーマ人民文化相は、つぎのようにのべている。
「彼は夢によって、夢のなかで、夢を通して生きている。
彼は現実と少しも取り組もうとしない。
彼は自分でつくりあげた、完全に想像的な世界のなかで、生活し、働いている。
彼は現実の時の流れの外に生きており、彼の反応、情熱、失望は、生活とはなんの関係もない」 |
だが、フェルトリネリ荘での幻想の壁をこえた現実の世界では、イタリアでの戦いが、まさに最高潮に達しようとしていたのであった。
top
**************************************** |