|
****************************************
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9
正午二分前(関東大震災3)
もちろん、ある程度の不正確さは免れないが、かなり根拠のある見積りによると、関東大地震の震動――続いて起った大火災は別として――によって破壊された家屋は、東京市内の全家屋約五十万戸の一パーセントにしかすぎなかった。
しかし、東京は震央から南方に九十一キロ離れていたが、横浜は南二十七キロだったので、ずっと近く、従って被害の割合も違っていた。
横浜では、十万戸ほどの十二パーセントが、主震によって倒壊してしまった――従って、直接地震による死者も多く、かつ火事の起り方も早かった。
この横浜でさえも、最大の被災地ではなかった。
相模湾にのぞむ小さな町の方が、さらに被害が大きかったのであって、その町々は震央にもっと近かったばかりでなくて、東京湾沿岸の町々と違って、大小さまざまの津波に襲われたのであった。 |
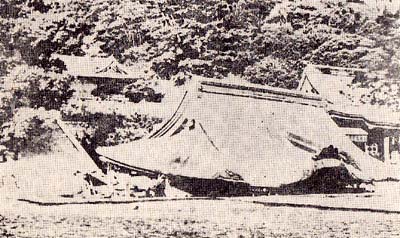
倒壊した鎌倉八幡宮舞殿
|
中でもとくにひどかったのは鎌倉で、ここでは地震はもちろんのこと、火災と津波とに見舞われたのである。
まず地震だけで、全部で約二千五百戸のうちの八十五パーセントが破壊された上に、その残りの半分が火災にやられてしまった。
倒壊家屋十軒に一人の割で、死者が出た。
さらに痛ましかったのは、出産を控えた十九歳の山階宮(やましなのみや)佐紀子妃殿下であった。
ちょうど侍医が診察中に地震がやってきて、妃殿下も侍医も押し潰されてしまったのである。
鎌倉在住の多くの著名人の一人に、八十八歳の高齢でかなり弱っていた松方正義公爵がいたが、彼は看護婦につきそわれて別荘に起居していた。
松方公爵は、日本近代史における二つの劇的な時代のかけ橋となった元勲の一人であった。
一八六八年の明治維新に当っては、徳川将軍家を倒して日本を近代世界の仲間入りをさせるために力をつくした、若き志士の一人であった。
明治天皇親政となってから位人臣を極めた公爵は、政府にはいっては急速に力をえて、大蔵大臣と総理大臣を何度かつとめた。
彼と同時代の人々のなかには、刺客に殺された者が何人かいたが、あくまで運の強かった彼は、何度かねらわれながらも、無事に難を免れたのであった。
九月一目の午前、老公爵は一階の一室の畳の上に横になっていたが、その真上の部屋では京都大学にいっていた二十三歳の令息三郎が、窓辺に坐って、ビクトル・ユーゴーの『レ・ミゼラブル』を読んでいた。
地震があったときには――震央は近かったために、事実上初期微動というものはなかった――震動が余りにも激しかったので、三郎は、当時よく相模湾沖で行なわれた海軍の実弾射撃のそれ弾丸が、自分の家に当ったのかと思ったほどであった。
彼が気がついたときには、家の屋根の上にいたが、その屋根はじかに地上にあるように見えた。
どうして自分がそんなところにいたのか、はっきりとは思い出せなかったが、家が潰れると同時に、意識を失ったまま屋根にあいた穴から屋根の上にほうり出されてしまい、その穴がまたふさがったのではないかと、彼は考えたのである。
右脚にかなりの傷を負ったにもかかわらず、彼は屋根の傾斜をはって地上におりだ。
三郎は、潰れた家の下から無傷ではい出て来た三人の召使いたちと力を合わせて、屋根の一端を持ち上げて、家の下敷になっている父の遺骸を探し出そうとした。
ところが驚いたことには、老公爵の運の強さはまだ続いていたのである。
彼は、看護婦ともども潰されずに、全く無傷であった。
い天井の梁に支えられた床の長方形の空間に、二人ともはまり込んでいたのだ。
その梁が、落下した二階を支えていたので、二人はわずか三十センチほどの高さの空間にいたのであった。
公爵は、静かにそこをはい出してきたが、間もなく関東地方一帯と同じように、断続する余震のために揺れている庭園で、昼食をとるほどの余裕が出てきた。
三郎の方は、そうはいかなかった――患者が多すぎて、くたくたに疲れた医師が駈けつけたときには、彼は出血多量のために重態に陥っていて、何度も注射をしたほどであった。
それから一年たって、父上が大往生をとげたときにも、彼はやっとのことで葬儀に参列できたのであった。
松方家の別荘は、相模湾のなかの鎌倉湾を見おろす小高い土地にあった。
その西方数百メートルの、もっと海岸に近いところに、これもかなり有名な退役外交官の陸奥(むつ)広吉伯爵が住んでいたが、そのイギリス人の夫人は、鎌倉の歴史などについてのエッセー集の筆者として知られていた。
伯爵の一人息子のイアンは、午後、鱸(すずき)釣りに出るための準備を、二階の自分の部屋でしていた。
釣りには、午後一時の満潮時がいちばんいいので、彼は正午少し過ぎに出かけるつもりでいた。
襲ってきた地震の衝撃で、陸奥の家は潰れてしまったが、しかしイアンはどうやら窓から木をつたわって逃げ出すことができた。
彼が地上におり立つと、彼の父は大丈夫でいたが、何人かの召使いのことを案じていた。
伯爵は彼に、おりから海水浴にいっていた母を見てくるようにいいつけ、伯爵自身は倒れた家のなかを調べるために、そこに止った。
イアンは、海岸に出かけたが、何歩もいかないうちに、湾の水面がいつもと異っているのに気がついた。
満潮時であったのに、海水はかつて見たことのない速さで退いていた。
そして数分後には、干潮時にも見られないほど遠くまで、退いていったのである。
いつもなら、殆んど水面下にある岩はもとより、かつて見たことのない岩まで、にょきにょきと出ていた。
イアンはふと、地震のあとにはよく津波がくるものだと聞かされたのを思い出した。
と同時に彼の目に、その小さな湾の入口いっぱいに、長くて平たい水の壁のようなものが、恐ろしいほどの速さで、彼の方に押し寄せてくるのが映ったのである。
イアンは逃げ出した―――はじめは、沿岸の斜面にそって水から逃げていたが、やがてもっと急な丘にそって、海岸より高いところへ。
道路を横切るときに、とまっている車を見たので、運転手に大声でいうと、運転手は道路の高い方にいこうとして、車をバックさせはじめた。
イアンは、道路の高い方へ、そして海岸線から離れた方へと、走っていった。
道路を四十五メートルほど走って、海岸より九メートルほど高いところにつくと、彼は立ち止って、うしろを振り返ってみた。
津波は、殆んど岸まで――四十五メートルほどのところまで――寄せていたが、最初見たときよりもかなり大きくなっていた。
近づいてきたのを見ると、それは五メートルほどの高さで、壁というよりもけわしい崖が湾の全面に押してくるような光景だったのである。
波は決してくだけることなく、巨大なうねりのままで岸におおいかぶさってきた。
海水が、ごぼごぼと音を立てながら、町の低いところにはいり込み、波が立っていた堤防にそって流れている滑川の河口に流れこんでいった。
波は十五分ほどそこにじっとして、津波が続いてやってくるのかどうかを見きわめようとしていた。
そして、もうやってこないとわかると、家に帰りはじめた。
途中、さっきの車が横倒しになっており、そのわきに運転手がどうしようもないというふうに立っているのを見かけた。
家に帰ってみると、やはり津波のこないうちにうまく高いところに逃げていた母が、無事に戻ってきていた。
津波は、家まではきておらず、家人にも――二百人ほどの町の人たちとは違って――大怪我をした者は、一人もいなかった。
イアン陸奥が鎌倉で見た津波は、こうした現象のなかでも、まことに典型的なものであった。
鎌倉の小湾は、馬蹄型をしている上に、その底がゆるやかな傾斜をしていたので、津波が陸地に寄せるに従って、その高さを増しながらひろがっていくには、もってこいの形だったのだ。
しかし、鎌倉の場合は、まだ震央から五十キロほど離れていたのであって、このこと自体は、津波の場合には、土地の動きの場合ほどには影響はしないものではあるが、それでもかなりの影響を及ぼすいくつかの要素の一つとはなりうる。
あとで測定されたところによると、鎌倉での高潮線は最高四・八メートルであった。
相模湾の別のところでは、それがもっと高くなったところがあったし、ところによっては、津波が相ついで二度も寄せてきた。
伊東では、百トン級の漁船が陸地に四百メートルも押し上げられたのであった。
津波自体よりも危険なのは、その引き波の方であって、三百戸ほどの人家が沖の方までもっていかれてしまった。
しかし一七〇三年にもっとずっと大きな津波を経験したことのある伊東では、町民たちは一人の死者もなしに避難した。
十六キロ北方の熱海では、津波の高さは十一メートルにも達し、百六十人が溺死したのであった。
熱海、伊東その他の地方の町々では、津波による被害が、それより数分前に地震で受けた損害や、地震に続いて起った火災によるものと同じ程度か、あるいはそれをしのいでいた。
たとえば熱海では、地震で倒壊した家屋と津波で流されてしまった家屋の双方とも百五十五戸で、それは同町の全戸数のほぼ四分の一に当っていた。
伊東では、地震で破壊された家屋は二百戸にすぎず、これは全体の十分の一にしか当らなかった。
しかしまた、熱海、伊東その他の小さな町村では、津波で火災を消されたおかけで、災害を免れたという家も多かった。
地震の激しさが最高に達し、それによる被害が余震によるものよりも遥かに大きくて、最も印象的だったのは、これらの町村ではなくて、もう少し西にいったところの、相模湾の海岸線の中央部に位置するあたりだったのである。
地震前に五千戸あった小田原町では、地震の翌日にはわずかに二百五十戸ほどしか残っていなかったが、その半数は地震によるものであった。
近くの曽我と下曽我の両村では、全民家のそれぞれ九十パーセントと九十七パーセントが、地震によって破壊されたが、破壊状況があまりにも徹底していたために、火災を起す材料もなくなってしまったほどであった。
最も徹底的にやられたのが、熱海の近くの根府川の河口を占める根府川村であった。
この小さな川の狭い崖になっているところに、上流の丘から地滑りでくずれてきた泥土が、幅百八十メートル、深さ十五メートルの“泥の氷河”となって、河口を埋めてしまった。
この地滑りで、約三百人の村民が死に、村の大部分が“泥の氷河”によって、湾に押し流され、あたりは全く手がつけられないほどに、泥にうずまってしまったのである。
根府川駅は、水面からそそりたった急な斜面に刻みつけられたような形でひっかかっていたが、これは地震だけによる最も激しい災害の見本みたいだった。
この根府川駅に停車していた列車―――熱海からくる上り列車を待っていた――――は、東京からの下り列車で、これには、伊東にいって大いに楽しもうという白石辰雄と八人の運転手仲間が乗っていた。
地震の最初のショックで、駅の上の丘が耳も聾せんばかりの大音響とともに地滑りを起して、列車も、駅も、そしてその乗客も、四十五メートル下の海中に払い落してしまったのであった。
白石は、そのときの数少い生存者の一人だった。どうしてやったのかは彼にも思い出せないが、とにかくどうにかして、やっと水面に浮き上った。
同じことをやった何人かの中では、記録によると彼だけが、生きて海岸までたどりついた唯一の者だったのである。
彼は夢中で岸に向いながらも――泳ぎというものは殆んど知らなかったので、いま少しで溺れるところだった――自分の身体の状態を眺めまわした。
頭を切ったのと、何ヵ所かのかなりの打撲傷は受けてはいたが、しかし何分か前に汽車のなかでうとうとしかけたころと、大した違いはなかった。
彼はそこで少し休んで、地滑りを逃れて海岸までやってきてぼんやりしていた少数の根府川の村民たちとしゃべっていた。
やがて、することといっては何もなかった彼は、急傾斜の上手をよじのぼって、鉄道線路の上に出ると、東京の方向にむかって歩きはじめた。
根府川駅で彼らの乗っていた汽車と交換する筈だった東京行の上り列車は、彼に追いつくようなことはなかった。
この列車は運よくも、トンネルの中で地滑りに会ったのであった――ただし、列車の前方のトンネルの口は、ふさがれてしまった。
機関車が障害物に突っ込んだはずみで、数人の乗客が負傷したが、それ以外の乗客は、トンネルのうしろの方の口から、脱出することができた。
白石辰雄が家にたどりつくまでには、三日もかかったのだが、その帰る道すがら目に映ったおかしな現象は、沿道のみかん畑にいた雀たちが、地上に釘づけになったように見えたことであった。
雀たちは、少しはとび上るのだが、もっと飛ぼうとしても、せいぜいみかんの木のいちばん下の枝くらいまでしかいけなかった。
数秒後にまた余震がくると、やっと枝にとまっていた彼らは落ちてしまって、いくら羽はたいても飛べなかったのである。
このほかにも、鳥や、獣類や、魚までが、ふだんは見られない状態に陥ったのを目撃したものはたくさんいた。
相模湾のトロール船の乗組員たちの話によると、何百尾というシゲ――大型の深海魚の一種――が地震のあった翌日、水面に浮いていたという。
彼らは、急速かつ極端な水圧の変化のために、ちょうど川にダイナマイトを投げ込むと、川魚が死んでしまうみたいに、死んでしまったものらしい。
地震の起る直前に、各地で雉(きじ)がさかんに鳴くのが聞こえたし、また横浜市にいた一目撃者の言明したところでは、野原につながれていた馬のいななきで、余震の強度を計ることができたという。
馬という動物は、恐らく、地震学的見地からは、二足動物に比べてはるかに精巧にできているので、人間の感覚よりも早く地震を感知したのであろう。
その馬のいななきが高いほど、続いて起った地震の強度も高かったということである。
九月一日に、横浜港の防波堤の内側に碇泊していた船のなかに、ブルー・ファンネル・ラインのフィロクテテス号があったが、この船の乗客の一人が地震が起ったときの情景を実に詳しく目撃した。
この人はのちに神戸クリニクル紙に無記名記事を寄せて、見事な筆致で、当時の模様を伝えているのである――
正午きっかりに、自分の船室で読書をしていた筆者は、全船の激しい震動でびっくりした。
それは、大洋航行船のスポーツ室によくおいてある”電気木馬”に乗ったときの震動によく似ていた。
独特の衝撃感が、あまりにも執ようかつ激しいものだったので、船の汽缶が爆発でもするのではないかと、思ったほどであった。
船に乗っていた人は、みんなびっくりした。誰かが――恐らくそれは、こんなことには経験の深い、日本人のウィンチマンだったと思う――地震らしいと言った。
まさにそれに違いなかった。
最初の震動は、丸一分間ほどだったと思うが、それは五分間にも感じられた。
船の各層の甲板が、あまりにももの凄く震えるので、これでは竜骨が砕けてしまうのではないか、とさえ思った。
これは、地震に際してはどこよりも安全だと考えられる船しかも一万四千トンの巨船の上でのことである――地上の状況については、筆者などよりは経験のある者の記述にまかせよう。
この長い衝撃があってから一分間ほどすると、黄色い雲――はじめは薄かったのが、見る見るうちに大きくなっていった―――が、陸地の家やドックなどのうしろから、そしてついにはかなたの丘のむこうからも立ちのぼった。
この雲は、長い帯になって湾の上におおいかぶさったかと思うと、ぐんぐんと大きさを増し、雲も濃くなっていって、北の方へ猛烈なスピードで動いていった。
それは疑いもなく、倒壊した建物から出たほこりによって形成されたものだが、間もなくあたり一帯をおおってしまったのである。
船の上の人々は、茫然として見守るばかりだったが、陸地の人たちの窮状は、それこそと思われたのである。
筆者のいた位置からも最初の震動直後に大損害が起ったことが、はっきりと認められた。
遠くから見ても、陸上の建物がかなり変形してしまったことが、ありありとわかった。
横浜港の東部境界線とたっていた二本の防波堤が、かなり様相を変えてしまった。
双方の防波堤の港の入口を形成していた部分が、完全に姿を消してしまった。
防波堤の北部にある検疫所に使われていた建物は、見る影もないほどにこわれてしまった…… |
フィロクテテス号上のこの鋭い観察の想像とは反対に、災害の程度は――その強さは別として――市内で見たところは、海上という有利な場所から見たほどにははっきりしていなかった。
船の手すりのところから、歩み板を上げるのを眺めていたエンプレス・オブ・オーストラリア号上の乗客たちは、税関の突堤が揺れ出すのを見たのだが、そのときは、これは船の方が動いているからだという錯覚におそわれたくらいだった。
しかし、この桟橋の動きは、決して錯覚によるものではなかった――桟橋の基礎杭がこわれていくに従って、その両端が水中に没してしまって、見送りの人たちは、離れ小島のようになったその中央の小さな部分に取り残されてしまったのである。
桟橋の上の群衆の中に、ロバート・ブルームという十一歳のアメリカの少年がいたが、彼は兄といっしょに、アメリカに帰国する山の手のセント・ジョセフ学校の級友を見送りに来ていたのであった。
大揺れがきた拍子に、彼は足場を失いかけたが、それを取り戻そうとして、こんどは麦わら帽を失いかけた。
当時流行の縁の堅いボート選手型の帽子だったので、桟橋にぶつかって、ころころと転がっていって、水に落ちそうになった。
一瞬、混乱のさ中――市街がこわれてしまいそうな、ごみやほこりと大騒音で一杯だった――ではあったが、ブルーム少年にとっては帽子を取り戻すことも、また重大なことだった。
彼が、あわてて走りよって、身をかがめて帽子をつかんだときに、近所にいた誰かがこう叫んだ。
「こんな地震がもう一つきたら、横浜はなくなってしまう!」
もう一つくる可能性はなかったのだが、桟橋上の人々には、まだそのことはよくわかっていなかった。
ブルームは、帽子を取り戻した。
縁のところが、少しひん曲ったが、彼はそのままかぶった。
そして数分後には、ほかの人々と一緒に、桟橋からはしけにのせられた。
ところが、誰かが津波がくるかも知れないというと、その言葉がたちまちのうちにひろがって、はしけに乗っては危いというふうに変ってしまった。
人々ははしけを出て、エンプレス・オブ・オーストラリア号と同じ桟橋の反対側に碇泊していたフランス客船、アンドレ・ルボン号に乗り込んでいった。
日本と往復するフランス船は、横浜港でエンジンの分解修理をすることになっていたので、このアンドレ・ルボン号も、そういうわけで航行不能であった。
その日の午後、同船は陸上の火災を避けるために、ボートをおろして船を港内ブイにつなぎ、ワイヤをまいて桟橋から離れたところに移っていった。
ブルームは、この船の上で夜を明かした。
その翌日、彼は兄と一緒にP・O・ラインのドンゴラ号に移されて、大勢の避難民と一緒に神戸に運ばれた。
ブルーム少年のセント・ジョセフ学校の学友のいま一人に、ダンテ・デンティチという、いかにも耳ざわりのいい名前の子がいた。
この子のその日の計画では、エンプレス・オブ・オーストラリア号の見送りではなくて、映画を見にいくつもりであった。
彼は家にいて、そのための金一円を父親にねだっていたが、そのときに地震がやってきた。
父親の方のデンティチは、四十年ほど前に日本にやってきて、横浜最初のヨーロッパ式パン屋をはじめたのだったが、地震と同時に、彼は床の上に投げ出され、天井が落ち、息子のダンテ・デンティチは下じきになって、口に怪我をしてしまった。
父親は息子を引っぱり出したが、一時間以上もかかった。
そのころにはもう、横浜市内には百ヵ所も火災が起っていて、デンティチ父子は他の何千という人々と一緒に、海岸の方へ逃げていった。
最初の揺れで潰れてしまった主だった建物のひとつに、徴兵ユナイテッド・クラブがあった。
いつもだと正午には大勢集ってくるのに、この日はエンプレス・オブ・オーストラリア号の見送りがあったために、とても閑散だったのだが、それでもクラブの中にいた六人は、全部死んでしまった。
その中には、クラブの図書館員として知られていたW・B・メイスンがいた。
この人はラフカディオ・ハーンの親友であったが、地震の起る寸前にベランダから図書室にはいっていったのだった。
ベランダで彼と話をしていた二人の男は助かった―― 一人は街にとびおりて助かり、いま一人は、クラブの入口ヘいったときに地震がきたが、その入口が落ちてくる石の支えとなったのであった。
横浜正金銀行ほか二、三の建物だけを例外として、横浜市の主だった建物は、一瞬にして瓦礫の山と化してしまった。
数少い例外中のひとつに、グランド・ホテルがあったが、これは木造建築だったために、二、三メートルヘだたった隣りの煉瓦と石造りのオリエンタル・ホテルなどとは違って、ゆっくりと潰れたのであった。
グランド・ホテルから逃げ出して助かった者はかなり大勢いたが、その中の一人のモリス・チチェスター・スミス夫人は、身の丈一・八メートルにも及ぶ堂々たる体躯の持ち主として知られていた。
地震がきたとき、彼女は二階の部屋で風呂にはいっていた。ホテルが潰れたときに彼女のいた揚所は、室内の配管のおかげでほかの部分よりもゆっくりと落ちていって、彼女が気がついたときには、風呂おけの水も殆んど元のままで、海岸通りの幅の広い通りのまん中に移動していた。
この派出な光景を目撃していた者に、いたって沈着な男がいて、ゆっくりと自分のシャツとズボン下を脱いでチチェスター・スミス夫人に渡したので、彼女はそれを身にまとって、海岸に向った。
暫くすると彼女は、いまにも全市を焼きつくしてしまいそうな熱気から逃れるために、またもや水浴びをしなければならなかったのであった。
このチチェスター・スミス夫人と対照的な経験をしたのは、ほかならぬ彼女の夫で、この大地震がきたときに全く気がつかなかったという、関東地方を通じて唯一の人物であった。
チチェスター・スミス少佐は、第一次大戦で勇名をはせたイギリス空軍のエースで、日本陸軍の飛行教官として滞在中であった。
食前に身を清めるという意味では、夫人と同じであったが、しかし彼の場合は、横浜と鎌倉のあいだを走っている列車の洗面所にいたのであった。
列車が絶えず動いている上に、きつくて廻らない蛇口に気を取られていた彼は、外界の異変にはまるで気がつかなかったのだ。
この地方を走っていた多くの列車と違って、彼の乗っていた列車は脱線はしなかったし、機関士が逸早く停車の処置をとったために、多少の衝撃はあったが、無事に止った。
そこで洗面所を出てきた少佐は、ほかの乗客たちに何ごとがあったのかと尋ねて、はじめて大地震のことを知らされたという次第であった。
三秒ほどおくれて東京に本震が起ったころには、横浜はすでに潰滅していた。
帝国ホテルでは、犬丸徹三支配人の部屋で幹部会が続行されていた。
その後どんなことになったかについては、犬丸氏がパンフレツトの形で公けにした当時の思い出のなかに、如実にえがかれている――
建物が揺れ出すと、私はすぐに「調理場は、どうなっているか?」と思った――そして、その方向に駈け出した。
途中で、来賓の方々が中庭にいるのを見かけた私は、そのままそこにいるようにいった――いちばん安全な場所だったのである。
調理場にきてみると、電気レンジが落ちて、みんな燃え上っているのが目にはいった。
料理用ストーブの上にあった油に火がついたのであった。
火の手は、いたるところから上っていた。
この調理場の火の手を見た私は、あたりを見まわした。
「誰か、火を消すのを手伝う者はいないか?」隅のテープルの下に、四人がうずくまっていた。
「火を消さんか?」と、私はいった。
電灯は、全部ついていた。
「これは、元のスイッチをとめなくては」と、私は思った。
そして、ボーイを発電室に走らせた。
とにかく、火は消しとめた。調理場の天井は高かったので、火が燃え移らなかったのである。
それから十分ほどたつと、レンジは全部駄目になってしまい、壁に火が移っていった…… |
犬丸徹三の調理場での逸早い行動は、帝国ホテルの火事を大事に至らせなかったことの一つの原因だった。
いま一人機転をえた行動をとった者がいたが、それは森田伝治という若い電気技師で、三年前に高等工業高校を卒業すると、すぐにホテルに就職したのであった。
犬丸が命じていかせたボーイが、果たして発電室にいきついたかどうかは、記録に明らかではないが、それはどうでもよいことであった。
というのは、そこにはすでに森田がいたからである。
地震が起ったときに、彼は電力調節室にいて、いつものように計器の点検をしていたのであった。
新らしいビルでは、往々にして漏電による事故が起るものである。
とくに、電気による調理や暖房がまだもの珍らしかった一九二三年当時には、この危険は大きかったのだ。
すでにこの帝国ホテルでも、前年の夏にショートによる火災が起っていて、木造の旧『別館』を焼失したばかりであった。
この激震で接続が全部いかれてしまったところへ、送電が続けられた場合にどんなことが起るか、ホテルのどの幹部よりも森田がいちばんよく知っていた。
場合が場合だったから、かりに森田がすぐさま地下の発電室を逃げ出したとしても、非難はできないところであろう。
しかし、彼は決然として揺れ動く床をよろめきながら五メートルほどいくと、元スイッチを切ってしまったので、このために、犬丸が中庭を歩いているころには、全館の電流は切られていたのである。
帝国ホテルは、東京の湿地帯である下町と、山の手の住宅街のあいだに引かれた線に近いところに建っていた。
市内の各地では、それぞれの地盤によって、地震による被害も大いに違っていた。
西の方の岩石の台地に住んでいた人たちは、その辺は揺れこそ激しいが、破壊の程度は一年前の地震くらいのもので、全部こわれてしまうようなことはないだろうと考えていた。
下町では、湿地帯に家がびっしりと建て込んでいたので、震動が伝わりやすく、従って被害も大きかった。
鎌倉や、それ以西の町村ほどひどくはなかったとしても、荒廃ぶりは大きく、なかでも激しかったのは東京のコニー・アイランド(ニューヨーク市ブルックリンにある歓楽街)ともいうべき浅草だったが、土曜日の午後のことなので、人々がいよいよ詰めかけてきていたこの浅草で、実に目立ったことが起ったのであった。
それは、当時の東京でいちばん高いので有名であり、お上りさんの注目の的となっていた『十二階』が、くずれたのだった。
この『十二階』には、もっと有名なイタリアの『ピサの斜塔』のように、塔自体が傾斜しているというおもむきなどはなかったが、しかしそれを補うだけの独特の魅力は備えていた。
その一つは、上のバルコニーから見おろす東京全市の眺めであったが、その上までいくには螺旋形の階段をあがっていくようになっており、ここを経営していた老夫婦が切符を売っていた。
もう一つは、この『十二階」の周辺にたむろしていた街娼たちが安い値段で供給してくれる“商品”で、それは八百メートルほど北にいったところの吉原で販売していたのと、同じ商品だったのである。
地震が起ると、『十二階』は前後に揺れ勁いていたが、その間の数秒間というものは『ピサの斜塔』そっくりに見えた。
やがて、一目撃者のいうところによると、「それは、ていねいにお辞儀をするような恰好になり」そして八階のところから、折れてしまった。
運よく、上部四階の破壊によるお辞朧なるものが、おりから群衆がむらがっていた三つの方向にではなくて、第四方向である近くの小さな池に向ってなされたので、外にいた者で、下敷になって死んだのはほんの数名ですんだのだが、経営者の老夫婦は、二十人ほどの見物人と一緒に、潰されてしまった。
付近の芝居小屋の裏方二人は、昼食をとるために上のバルコニーにあがっていたところ、地震と同時に池の中に投げ出されたが、不思議と怪我ひとつせずに済んだ。
青木満喜子が、大磯にいく仕度を整えていた高圧は、浅草からはそんなに遠くはなかったが、隅田川を隔てた反対側にあった。
その部屋は、家族の住む屋敷のなかの独立した離れ家の二階の一室であった―――父親の青木氏が、彼女とその妹が、騒ぎまわる下の小さな弟たちに邪魔されることなしに、家の仕事ができるように、二人めいめいにこうした別室を与えたのであった。
満喜子の部屋には、本物の西洋の家具である椅子と机が入れてあった。
満喜子にとって、この部屋と家具を与えられたということは、編み上げ靴と、最近になっていちいち親に物を買ってもらわずに、ちゃんときまった小遣いを与えられるようになったことと同様それだけ彼女が成長した証拠だったし、彼女はこうした待遇を、非常に喜んでいた。
最初の大揺れがきて、彼女の記憶しているこれまでのどんな地震よりも激しく壁をゆすぶり、家がゆれ動いても、彼女はどうすればいいかを、ちゃんと心得ていた。
彼女はまず地震のいちばん激しいときが過ぎるまで、ヨーロッパ製の机の下にもぐっていた――非常の場合には手ごろの場所だった。
次に起き上ると、ヨーロッパ製の椅子を頭の上にかざして――こうすることが地震のときに身を守る最善の方法であることは、誰もが知っていた――離れ家をとび出すと、屋敷を駈け抜けて、祖母がお経の仕度をしていた母屋に走っていった。
母屋にいってみると、そこにいたのは祖母だけではなくて、いつもより早目の昼食のために、祖父と、伯父と、弟も集っていた。
いちばん落ち着いていたのは祖母で、こんな地震くらいに負けてなるものか、という態度であった。
「さあ、みんな坐って、お昼をいただきましょう」と、老女はいった――そして、余震のために家が絶え間なく揺れているのに、一同は低い長方形のテーブルを囲んで、畳の上に坐ったのであった。
しかし問もなく、満喜子の伯父が、屋上の物干台に上っていって、近所の模様を見てくることになった。
戻ってきた伯父の話によると、南の方にいくつかの火災が起っているということであった。
そこで一同が、みんな上っていって見たのだが、伯父のいったことは本当だった。
六本ほどの煙が、真っすぐに空に上っているのが、よく見えたのである。
同じように人口の稠密な本所区の、そこから一キロほど離れたところでは、池口医師が――患者の足に丹念に包帯をまきつけ終って――診察室の隅にある手洗鉢で、手を洗っていたときに、地震が起った。
その主震は非常に激しくて、手洗鉢に両手でしっかりつかまっていなかったら、とても立ってぱいられなかった。
一揺れすむと、彼は居間にはいっていって――居間では、ガラス製の電灯のかさが天井から落ちて、砕けた以外には被害はなかった――家中の者の名を呼んだ。
家族構成は、妻と、九歳になる長女と、五歳と三歳の二人の息子と、それに四人の使用人であった。
四人の使用人は、看護婦と、女中と、書生と、人力車夫であった。
全員を呼び集めた医師は、地震があまりにも激しく、火災の恐れもあるので、全員がどこかへ避難した方がいいと思う、といった。
彼は、恐らくいま診たばかりの患者のことを思い出したのであろう、表の道路にはいろいろな危険な物が落ちているだろうから、みんなに足袋をはいていくように言い聞かせた。
そして妻に、あるだけの足袋をみんなに分けてやるように、子供たちには必ずはかせてやるように命じた。
彼はまた女中に、充分の米をたいて握り飯をこしらえ、それを昼食のかわりに食べさせるように、そして沢庵をたくさんつけておくように頼んだ。
そして、一同が彼にいわれたことをやるために散っていくと、彼は外の様子を見るために街に出ていった。
その通りの角にあったせんべい屋は、すでに火災を起していて、煙が静かな暑い空に真っすぐに立ち上っていた。
家人はとっくに逃げてしまって、火を消し止めようとする者は一人もいなかった。
top
**************************************** |