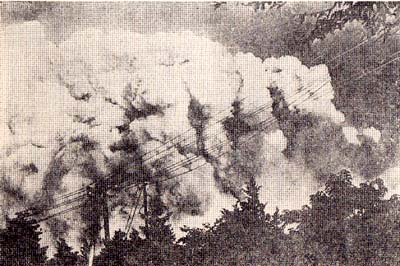|
****************************************
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9
竜巻(関東大震災5)
有名な今村明恒教授の研究によると、火災をともなわない、純粋な大地震による死者の数は、倒壊家屋十一戸当り一人ということになっている。
東京市の倒壊家屋は一万戸をこえてはいなかったから、この比率でいくと、死者の数は千人に及ばない程度である筈だった。この比率を、東京市以外の地域にも当てはめれば、大地震による全死者数は八干人から九干人のあいだであった筈だ。
ところが、実際には十四万人――行方不明も含めて――もあったということは、火災によるものはもちろんだが、とくに東京にはそのほかに独特の原因があったのである。
その一つは、隅田川とそれ以外の無数の運河にかかっていた橋であった。火災にあった地域の三百五十の橋のうち、二百五十が破壊されたが、そのうちの多くは、そこへ避難した人たちが、非常に燃えやすい家財を大量にもち込んだからであった。 |
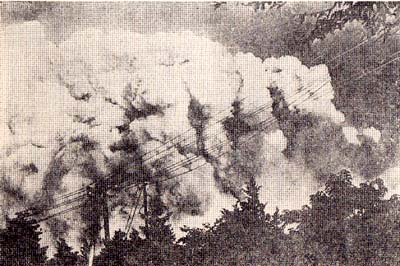
山の手方面から見た東京大火災の入道雲
|
しかし、死者が多かったことには、そのほかにもう一つ特別の原因があった。
それは、火災の最中に気象が変ったことであり、しかもそれは大体において火災のために変ったのであった。
東京西部の高台から眺めていた人たちが認めた、画のように美しい雲柱の原因となった上昇気流が、地上すれすれのところに部分的な真空をつくる原因ともなった。
東京では、そのために風が起ったが、横浜では強風となった。
フィロクテテス号上からの一目撃者は、その模様を、次のように生き生きと描写している――
陸上の火災は、南の強風にあおられて、ますます広がっていった。
海が荒れていたのと、乗員が陸上の火災の消火にいってしまったのとで、ほったらかしになったサンパンや大型はしけが火を発してもやいを離れ、風のまにまに港内を流されていった。
そして、これらの多くの流れる溶鉱炉が、猛烈に燃えながらえらいスピードで、まっしぐらに港内に碇泊している船舶の方に流れていった。
しかも、はしけには、たいがいアメリカやカナダの貨物船からおろしたばかりの木材や板材が積んであったので、いったん火がつくと、あの強風のなかでけしとめることは、まず不可能だった。
それが、外洋航路の船舶に向って、突っ込んでいったのである。 ` |
こうした燃えさかるサンパンやはしけに、強風と石油による陸上の火災とが加わって、事態をいよいよ悪化させた。
陸上の火災を避けるために、陸地近くの碇泊場所を離れつつあったロンドン丸は、風に流されてブルー・ファンネル汽船のライケオン号に突き当った。
そこを離れようとして、こんどはまずフィロクテテス号にぶつかり、そしてまたもやライケオン号にぶつかって、やっとのことでもう一隻の日本貨物船につないでもらった。
一方、フィロクテテス号の船長は、大戦中にドイツの潜水艦をかわしたので有名だったが、巧みに操舵しながら、壊れた防波堤のあいだを通って、外港に出た。
五時までには十二隻の大型船がフィロクテテス号に従って防波堤のそとに出たが、フィロクテテス号は五時十五分に錨をまいて、神戸に向った。
そして同船が三浦半島の沖合をすぎていくあいだに、乗客たちは、横須賀の石油タンクから二本の巨大な火柱が立ち上っているのと――この火事は、それから一ヵ月のあいだ燃え続けた――のちに暗くなってからは、相模湾沿岸の町や村がまっ赤になって燃えているのを望見したのであった。
海岸ぞいに南西の方向に航行していたフィロクテテス号は、陸地に向って航行する客船ウェスト・プロスペクト号とすれちがった。
この船は、アメリカから神戸を経由してマニラに向う途中で、飲料水が欠乏したので、それを積み込むために横浜に寄港するところだった。
この船がまず見たものは、横浜市の大火が夜空いっぱいに照りはえている姿であった。
その翌朝、ウェスト・プリスペクト号は、若干の食糧品と医療品とを陸上げして、十五人ほどの乗客を乗せて出航したが、これらの乗客たちは、旅路を神戸に避難した数百人の避難者のうち、九月三日に着いた最初のグループであった。
海岸地区では、すでに港内を大混乱に陥れていた。いよいよ強まってきた風が、さらに猛威をたくましくしていた。
そうした風は東京でも横浜でも、ちょうど炉のなかの火の熱が高まれば高まるほど、通風の勢いも強く効果的になっていくのと同じように、いよいよ火勢をあおり立てていった。
横浜では、火の手があまりにも速く広がったので、消防隊としても手のつけようがなかったが、東京では監視塔から見ていた消防部長が、配下の各消防署の自主的な判断で行動する以外に手はないと見て、新らしい計画を採用した。
それは、大きな火災を下町の繁華街に集中局限するということであった。
四時半に、使いの者によって召集された各消防署長、組長は、そうした目的にそって行動するように命令された。
大部分が組織的な破壊消防であって、陸軍工兵隊の援助があったのと、夕方になって風向きが南から西にまわり、さらに北に変ったことで、一応の成功を収めた。
このために二十人の消防士が犠牲となったが、しかし結局九月三日の早朝に至って、鎮火という第三段階に漕ぎつけることができた。
しかし、第二段階にあったころは、一万エーカーほどにも及んだ下町の大火災は、各所に気象学上の異変を起した。
地震が火事を引き起したように、こんどは大きくなった火災が、つむじ風や大旋風を発生させてしまった。
そして、とくにこの竜巻が、地震による火災に特別の性格を付与し、身の毛もよだつような惨事になったのである。
つむじ風と大旋風とは、技術的に区別しておく必要がある。
つむじ風は、よく街角などでごみなどを吸い上げているもので、比較的単純な現象だが、これは、風が街の一画によって分けられた結果できる二つの気流が、急に合流することによって発生する。
大きな火災になると、街が煙突の役割を果たして通風をよくするので、しばしばこのつむじ風が起るが、これにはいくつかの特徴がある。
その一つは、つむじ風は、火とまじって熱くなるので上にあがりやすく、そしてあがるときに火の子や燃えたままの物体をもっていくので、とび火をさせる場合が多いということである。
このような単純なつむじ風と、はっきり区別する必要のあるのが、大旋風(トルネード)である。
アメリカでは、『トウィスター』(疾風:しっぷう)というニックネームで呼ばれ、その他世界各地でいろいろな名で呼ばれているこの大旋風は、温帯性低気圧(サイクロン)、旋風性大暴風(ハリケーン)、台風(タイフーン)などと同じものである。
地表に近いところに起るつむじ風と違って、大旋風は高空の雲の中の大気の動乱(タービユレンス)によるもので、大気の動乱が下降するときの偏差によって発生する。
他の旋回する暴風と同様に、この大旋風(トルネード)は、北半球では左巻きに、南半球では右巻きに旋回するが、これは地球の自転によるものなのである。
大旋風(トルネード)は、旋回する大暴風のなかでは最も小さいものだが、しかしそれが発揮する猛威は、決して最も小さいものではない。
つむじ風よりは遥かに強力で、旋回速度はしばしば、時速百六十キロをこえることすらある。
東京の火災で発生した、ふんわりと厚い積雲性の雲――被服廠やそのほかの場所にいた人たちは、この雲が雷雨をもってくると誤解して、いまに雨が降って火事を消しとめてくれるだろうと考えていた――は、全然雨を含んではいなかった。
実は、強力な大気の動乱を含んでいたのであって、強烈な上昇通風に対する複雑な反応として、一つだけでなく、いくつもの大旋風を、下の大火災の地域に偏向させることになった。
雲から下に向って偏向されるというその特徴にもかかわらず、大旋風の回転には、上に向う煩向があって、それが非常に強い場合がある――アメリカの“トウィスター”はしばしば、車をひっくり返したり、屋根をめくったり、納屋や人家を破壊したりする。
二百十日の午後に東京と横浜に発生した大旋風は、アメリカの南西部に起った最も破壊的なのに較ベたら、とくに強力だったとはいえない。
にもかかわらず、それが遥かに多くの死者を出しだのは、火をともなっていたという、極めて簡単な理由によるのである。
東京の大火災の場合は、つむじ風も大旋風も完全に同じ様相――焔のすじのはいった、いかにも陰気なまっ黒な雲の柱――を呈していたのであって、当時の生存者でこの点を詳しくいえる者は数えるほどしかいないが、双方ともに同じような音響をともなっていたという。
その上、いま一つの共通した特徴があった。
どんな形でも、火というものは酸素を消費して、比較的少量でも吸った場合には死んでしまう一酸化炭素を残すものである。
酸素は、大火災の場合でもたくさんあるもので、火が燃え、人が生きているためには充分な筈なのだが、ただしこれは、火と人間とが別のところにいる場合のことで、これが一緒にいると人間の方が焼け死んでしまうのは、いうまでもない。
ところが、つむじ風や大旋風が火を含んでいる場合となると、話は別なのだ。
東京の大火災では、大型のつむじ風や大旋風が通過したあとには、かなりの量の一酸化炭素が残されたので、火では死ななかった人でも、その毒で数分間で死んでしまったのである。
東京の大震災の際は、つむじ風は、街の交差点のような、いろいろな方向から強い風が吹いてきてぶつかる場所でおこった。
本当の大旋風は、おもに、もっと広くて邪魔物のないところで起ったのだが、そういう場所だとまとまった火力が太い上昇気流をつくり出すからであろう。
このつむじ風と大旋風をちゃんと区別することのできた目撃者は、極めて少なかった――その上、日本語の『竜巻』という言葉は、概念がはっきりしておらず、つむじ風にも大旋風にも通じるので、かりに目撃者がいたとしても、はっきり区別していうのはむずかしいわけだ。
たとえば、公式発表によると、横浜では四時から八時までのあいだに三十のつむじ風が発生し、そのうちの十七は移動性で、その最大のものは二千二百メートルも移動したとある。
こうしたいかにも正確な数字は――大震災全般について発表されている多くの統計数字がそうであるように――若干の疑念を抱かせるが、要するに、そのつむじ風のうちのいくつかは、大旋風だったに違いないのだが、どれがそうだったかは全くわからないのである。
東京の場合、記録に残っている五十ほどの『竜巻』について、充分な説明をえることは極めて困難であるが、これには相当の理由がある。
まず、生存している当時の目撃者が非常に少いところに加えて、その目撃者が記憶を潤色(じゅんしょく=誇張)してしまうあまり、出てくる結論が間違ってしまうのだ。
この後者の面白い例として、浅草地区の一目撃者の大旋風の目撃談というのがある。
それによるとこの人は、一人の警官が大旋風のために、警察署の入口から吸い込まれて、二階の窓から吐き出されたのを見たのだという。
これは、かつて見たことのある手品かなにかがもとになっている幻想なのだろう。
警察側の記録をしらべたところによると、その事実は、二人の警官の関係したことであって、はじめに一人が署に駆けこみ、次にいま一人が火を逃れようとして、二階からとびおりたということだったらしいのである。
いまひとつの話は、ある男が竜巻に巻き上げられて、そのまま東京湾のまん中までもっていかれ、静かにおろされて、そこから岸まで泳いで戻ったというのである。
この男は、どうしても見つからなかった。
そのほかに、かなり信用できる話もあるが、その多くは、主に死体の状態という状況証拠から、死因が焼死よりも一酸化炭素による中毒死であったことによる。
一つの例証として、吉原の近くの一広場で起った悲劇がある。
地震の翌日、六百人ほどの人たちが、死体となって発見された。
多くは、火から逃れようとして故にとび込んで溺死するか、あるいは焼け死んだのであった。
ところが、死体をしらべると、焼けてもいないし、溺死でもないのがあった。
そしてそれは、その地区の上を大旋風が通過したことを示していたのである。
とくに状況証拠の多いのは、大震災プラス竜巻のなかで最も激しかった場合についてであって、これは単純な大旋風ではなくて、文句なしに、かつてなかったほどの破壊力を示したものであった。
そうした大旋風が、四時数分前ごろ隅田川の河口近くの上空に発生して、西方に方向を転じ、さらに十数分ほどしてから川を越して東に向った。
この大旋風の形態と、その動向については、これまた今村教授が日本の科学雑誌『科学知識』に寄稿した記事を引用することにしよう――
高さは百メートルないし二百メートルで、幅は国技館(現日本大学講堂)と同じくらいあった。
左巻きに旋回しながら、川の小さなはしけを水面から二、三メートルほど吹きとばした。
浅草側の高等工業の燃えている火が、その力を強めた。
それから川を越して被服廠の方に近づいていって、安田邸の中央上空を通過して、被服廠に到達した。
速度は、毎秒七十ないし八十メートルくらいだったと思われる。 |
今村教授の記事が正確なものであることはいうまでもないが、しかし科学的な記録の範囲を出てはいない。
旋風が、実際にはどんなふうに見えて、見たものはどう感じたか、というような細かいことについては、それを見た四万人の群衆の生き残りの何人かの人たちの記憶と、その威力についての状況証拠とに頼らなければならない。
状況証拠のなかには、木の枝にぶつかって巻きついてしまったトタン板や、同じく木の枝に装飾の花輪のようにへばりついてしまって、くしゃくしゃに潰れた自転車や、安田邸内の池の真ん中にはまりこんだ荷馬車などがある。
付近の警察署の警官だった人の目撃談を引用しよう――
滝のような音が聞こえてきた。安田邸の前の隅田川の水が、十五メートルほど吸い上げられた。
一隻のはしけが転覆した。
そしてその水柱は安田邸の方に向い、やがてまっ黒な柱と変っていった。
その柱は左巻きに旋回していたと、私は思った。 |
また、近くの別の警察署の一巡査部長も、これと同じような思い出を、こう述べている――
一軒の半ば完成しかけていた家が、吹きとばされてしまった。
空はまっ暗だった。
私は地べたに投げ出されてしまった。
そして、そのまま横たわっていた私の顔に、砂利がとんできた。
トタン板や足場材料がとんでいった。
一人の男が、とんできた丸太で脚を折られているのを見た。
十八歳の少女が、まるでボールのように転がってきた…… |
この巡査部長の回顧のなかの、トタン板と足場材料のところは、非常に重要なのである。
東京市は八月に被服廠あとの一画に、小学校一校と、いくつかの建物を建てる準備をしていたのであって、そのための材料、装備が大量に、そこに集積されていたのである。
この装備のなかには、多くの電話ボックスが含まれており、旋風の話のなかにこれが何度か出てくる。
被服廠の南側の群衆のなかにいたある公務員は、四時ごろの状況を、次のように思い出している――
隅田川の方から、耳もろうせんばかりの音をともなった、物凄い風が吹いてきた。
みんなが、口を大きく開けたまま、じっと立ってため息をついていた……
私は、荷車の下に顔をかくしていたのだが、それでも大きな木の枝で怪我をした。
私は、電話ボックスの屋根の部分を拾うと、それをかぶって、鼻と口にフランネルの切れっ端を当てがっていた。
風は、びゅうびゅうと音を立てていた…… |
いま一人の生残者は、同様の経験をこう述べている――
私は、雨戸と畳を借りに街に出ていった。
十人の私の家族は、荷車と雨戸の下にかくれていた……
物凄い突風が南西から起って、一瞬のうちに私たちの雨戸と畳をもっていってしまった……
私たちのわきにあった荷車は、空中高く舞い上ったと思うと、郵便局の屋根の上に落下した。
私が、びっくりして見ている間に、何百人もの人たちが空中にまき上げられて、豆つぶみたいに見えた。
最初の竜巻は、約二十分ほどのあいだ続いた。そして、竜巻が起ってから十分間ほどは、火の子が雨のように降り注いだ。 私たちの衣類などを積んだ荷車にも、火がついた。
私の近くに、水たまりがあったので、私はタオルをそれにつっこんでは身体を濡らして熱気を防いでいた。
竜巻は、まるで飛行機のエンジンのような音を立てていた。
人々は、被服廠の中央の方へと、ひしめいていった…… |
川向うの西側地区では、高等工業のグラウンドにある小屋に住み、地震と同時に川の堤防のところに安全な避難所を見つけた、高等工業の門衛だった人は、その日の午後を通じて見た竜巻は、十を下らなかったと語った。
そして、その竜巻の殆んどが、煙の柱の形をしていて、下の火の海の上を通りすぎると、火と煙の柱に変った。
その高さは、大体いちばん高い工場の煙突くらいだった。
そして、四時と五時のあいだに、被服廠の方角で、何とも形容のしようのないような音響を聞いたという。
いま一人の目撃者は、一本の高くて傾斜した火の柱が、川を渡って安田邸の方に向うのを見たと語っている。
この地区で起った事態を誰よりもよく記憶していたのは、池口医師であった。
池口医師が、幼い息子がびっくりしてまっ黒な空を見つめている表情に気がついてから間もなく、安田邸では状況が急変したのであった。
巨大な焔が、あたりの立木を激しく打ちのめした。
異様な咆えるような音が、耳もろうせんばかりだった。
口に言い表せないような、強烈な力と熱気のこもった風。
池口家の家財を積んであった荷車の上に坐っていた二人の警官が吹きとばされた―― 一人は邸の入口の方へ、そしていま一人は、空中に舞い上ったと思うと、それっきり見えなくなってしまった。
直径六十センチもあろうというパサニア(かしの一種)の木が、根こそぎ抜かれて北の方へもっていかれた。
ほかの立木も、引き抜かれるか、地べたに倒れてしまった。
すべてこうした出来ごとが、ほんの二、三秒のあいだに起ったのであった。
池口医師は、邸内にいたほかの人たちに、門の方へいくように叫ぼうとした。
しかし、ふりしぼった彼の声が、彼自身にも全然聞こえなかったのである。
このときまでに医師は、五歳になる男の子を背負い、娘を抱いていた。
下の男の子は母親の背に負われていた。
家族一同を川の中に入れようとした彼は、身振りで門の方へいくように夫人に示したが、しかし一歩も進めなかった。
こんどは夫人の方が手真似で、家のまわりをまわってみようというしぐさをした。
みんなでそれを試みると、どうやらうまくいって、暫らくのあいだは最悪の事態を避けていることができた。
しかし次の瞬間には、巨大なまっ赤な焔が川面を渡って、邸の方にやってくるのがみんなの目に映じた。
邸の正面入口の車回し(ドライブ・ウェー)は、古風な馬車出入口(ボルト・コシエール)をくぐるようになっていて、入口は川に面していた。
この馬車出入口がトンネルのように長かったので、医師は、この下にはいっていれば、少しは防げると思った。
自分たちの努力と、風の力に押されたのとで、医師の家族と召使いたちと、ほかの避難民の何人かが、われ先にとその中にはいっていった。
しかし、ここも何の役にも立たなかった。
焔が一方の口からはいって、いま一方の口に抜けていったのだ。
トンネルのような形をした馬車出入口は罠のようなものであった――出ようとしても、風のために出られず、おまけに一方の口は火のついている二台の車によってふさがれていた。
トンネルを吹き抜ける焔には川からもってきた煮えたぎるように熱い霧が含まれていた。
中にいる者は、祈ったり、叫んだり、悲鳴をあげたりしていた。
いまや池口医師も、もうこのままじっとして死を待つよりほかはないと観念をしたのである。
それから数分たつと、風は静まり、叫び声も悲鳴もやんだ。
そしてこんどは、全く静かになった。
あたりを見回した医師には、急にそうなったわけがわかった――みんな、死んでいたのだ。
池口医師は、三人の子供たちと夫人の死体を地上に並べた。
そのそばに横になった彼は、自分も死んでしまいたいと思った。
しかし、彼は考え直した。
そして、いま自分も死んでしまったら、この家族の死を葬ってやる者がいなくなる、と思った。
彼は、少くとも彼らの葬いをまかせることのできる人を見つけ出すまでは、死ねないと考えをきめた。
この考えが、彼の頭を占領した。
顔を地べたにつけていた方が、息がしやすいことを知った彼は、トンネルの中をはいながら、川に面した方の門に近づいていった。
ともすると風に押し戻されそうになったが、彼は正門近くのパサニアの木を目標にして、はっていった――そのパサニアの木も、根のところが抜けかかっていたのを、彼は覚えている。
ついに彼はパサニアの木まで到達し、息がしやすいように顔を土の柔かいところにつっこんでいた。
この間に、彼の両手の甲は骨まで焼けてしまった。
髪の毛と、頭の天辺の皮膚も、すっかり焼けた。
耳は、両方とも焼け落ちてしまった。
そのとき彼が着ていたアルパカ地の上着のおかけで、背中は焼けずにすんだが、不思議なことに、その上着も焼失はしなかった。
門のむこうには川があるのだから、どうしてもあの門までいかなくてはと決心していた彼は、こんどは塀を乗り越えれば、同じように川に出られると考えた。
そして、塀のところにたどりついて、よじのぼろうとしたが、風に吹きまくられて失敗した。
彼は、もう一度やってみた。
するとこんどは、力を入れたせいか、塀が火のために弱っていたせいか、塀がくずれてしまったので、彼はそこを抜けて出た。
そこは道路になっていて、そのむこうが川であった。
彼がとび込むと、聞いたことのある人の声がした――同じ町内の警官だった。
水につかると、火傷の痛みも薄らいだ――これなら死なないな、と彼は思った。
川を越して安田邸の庭園を横切って、池口医師の家族全員を殺した大旋風は、そこへ逃げてきていた人たちをも全部殺したが、その中には焼失した洋館に住んでいた人たちもはいっていた。
その洋館の持ち主だった安円善雄も、翌朝になって、池口医師が根元の掘り返された土のところで息をついていた。
あのパサニアの木の下のところで、多数の死体にまじって発見された――発見当時の彼は、まだ生きていたが、その日のうちに死んだ。
しかし、安田庭園に逃げ込んだ人たちは、安田家の人たちを含めても三百人をこえてはいなかった。
大旋風は、そこから避難民のひしめいている被服廠へと、移動していったのである。
のちに、同庭園に生き残っていた数本の木や、もろもろの物体が吹き上げられた高さや、トタン板の曲がった程度などを基礎として判断したところによると、旋風の回転速度は、今村博士がいっているように、毎秒七十メートル前後であった。
一方、その進行速度は毎秒十ないし十五メートルで、時速にして三十ないし五十キロにすぎなかった。
このようにゆっくりした速度で進んだ上に、今村教授の計算によると、柱の直径が、底部では三百メートルもあったというし、また遠回りをしながら進んでいったとも思われるので、大旋風は被服廠地区の中と上空には、数分間はとどまっていたものと見て差支えない。
いずれにせよ、その地区にあった引火性の物を全部燃してしまい、火焔が一酸化炭素、もしくはその双方の合わさったものによって、そこにいた者を全部殺してしまうのには充分な時間であったのだ。
大旋風が襲来してきたとき、被服廠には四万人が逃げ込んでいたが、助かっと者はわずかに数百名で、いずれも他の死体の下になっていたか、大旋風の及ばないところにいた人たちであった。
満喜子が、棒の先にビーチ・タオルをくくりつけた急造の旗を目印にして、三時間も前からじっと侍っていた場所は、被服廠の南口つまり隅田川下流の方の入口から、ほど遠からぬところであった。
彼女と一緒に来た四人の職工たちは、被服廠の中央部めがけてどんどんと押し寄せる群衆をやりすごしていたが、たちまちのうちに一杯になっていくのであった。
その中央部が、三方から火が押し寄せてきた場合に、いちばん安全な場所であることはわかっていたが、満喜子は、少くとも家族のほかの人たちがやってくるまでは、入口近くの現在地を離れまいと心にきめていた。
いずれにせよ、火事が大変なことになろうとは、全く考えなかったのである。
満喜子が彼服廠にきてから三十分して、これも四人の職工たちに伴われた弟と幼いいとこが姿を見せた。
彼らは、満喜子が予期していたとおり、彼女の急造の旗を見つけて、群衆を押し分けてやってきたのだった。
こうして一同は入口の近くに構えて、やがて彼らを探しにくるであろう青木氏を待っていた。
その間彼らは、引きも切らずにやってきては、自分たちと家財道具をおく場所を探している群衆を眺めていた。
その人たちは一人で来るものも、組になって来るものもいたが、多くのものは、寝具や、衣類や、鍋釜、瀬戸ものなど、こまごました家具を満載した荷車をひいており、なかには鳥かごをぶらさげているものもいた。
殆んどの婦人は、背中に子供をおぶっていたが、上の子たちが下の幼い子をおぶっているのもいた。
近くの病院の患者たちが、看護婦がつきそい、担架にのせられて運び出されてきたが、いかにも弱々しい、あっけにとられた顔をしている者ばかりだった。
家財道具を一杯に積んだ馬車をひいてやってきた男がいた。
満喜子がよく見ると、その男はかなりの老人で、顎には銀色のひげが生えていた。
二学期の始業式帰りの、制服の生徒たちも何人かいた。
辺り一帯には、恐慌状態を思わせるような気配はいささかもなかった。
それどころか、何世紀にもわたって『江戸の華』の経験を重ねてきた東京市民には、ことが起った場合の覚悟はちゃんとできているようにさえ見えたのであった。
恐らく家は焼けてしまうだろう、そうなったら少くとも一晩、場合によっては二晩か三晩は野宿をしなければならないものと覚悟した多くの人たちは、荷車や自転車や天びん棒などで、貴重品や家具類のほかに、食糧のはいった箱や、畳や、布団までもってきていた。
被服廠の、ここなら大丈夫という場所についた彼らは、めいめいの場所をできるだけ居心地よいようにした。
みんなが、なかなか行儀がよくて、争っていい場所を取ったりはしなかった。
その間に、地面は相変らず揺れ動いていたが、集った人たちはいずれも、それが余震であって、決して最初の地震のようなことはないとわかるほどに、地震については経験を積んでいた。
火事についても、おびえているような人はいなかった。
彼らの考えは、当局がちゃんと考えた上での指示に従ってきたのだから、いろいろと不便や困難はあるにしても、とにかく危険だけは避けられたのだ、ということであった。
いまのところは、遠くから火事を眺めているよりほかに仕方がないが、一日か二日経ったら、焼跡の家に帰り、再建をするのだというのが彼らの気持ちであった。
その間に、見ず知らずの人たちが旧知の間柄のようになって、お互いの数刻前の地震のときの話をし合っていた。
将棋盤をもってこなかったことを悔んでいる者もいた。
家を出るときすっかり興奮していた満喜子は、昼食をとることなどは全く忘れてしまった。
彼女は、まわりの人々が持参した包みをといて、握り飯や菓子を食べるのを――決して羨ましいとは思わなかった――眺めていた。
恐らく新聞社からきたと思われるカメラマンがやってきて、廠内の写真をとりはじめた。
まるで大規模な野営のような光栄で、非常に活気にみちており、人々の話し声、お互いに呼び合う声、子供たちの笑い声、お腹がすいたという泣き声、遊んでいる叫び声などが、あたりにひびいていた。
午後の時間がたっていくにつれて、気味の悪い煙がだんだんひろがってきて、空がいよいよ暗くなってきた。
巨大な雲があらわれた――煙っぽいかすみを通して見ると、雷雲のように見えたので、いまに雷雨がやってきて、火事を消してくれるだろうという人もいた。
満喜子はふと、これで彼女の家も、新築したばかりの彼女たちの離れも、みんな焼けてしまうのかと思うと、どうにもならないことだが、急に腹が立ってきた。
時折、遠くの方で爆発音がするのが聞こえてきた。
ある人が、あれは朝鮮人に違いない、朝鮮人がこの災害を利用して、騒ぎを起しているのだと言った。
それから数秒後に、全くの無警告で突如起った事態についての満喜子の思い出は、驚くほどに首尾一貫している――
突然、私は衝撃を感じた――被服廠全体が、ぐるぐる回っているみたいだった。
坐る場所もなかった。
人々は立ったまま、鰯(いわし)かなにかのように重なり合っていた。
どうしてそうなったのか、私には全くわからないのだが、人々が群をなして倒れはじめた。
まさに、地獄そのものだった。
恐らくは、火事が起ったためだったのかも知れない。
私は、弟といとこをつかまえて、みんなでしゃがんでいた。
あたりは暗くなった。人々が祈っているのが聞こえた。
私たちは、火の手の雨の中にいた。
私は死ぬんだな、と思った。
私たちが被服廠に着いたのはおそかったので、入口からそんなに離れてはいなかった。
折り重なっている死体の山のかげにかくれていた私は、突然一頭の馬が暴れ出しだのを見た。
それは、妖怪のように見えた。
すると突然、私の右わきで何かが燃え出した。
自分では気がつかなかったけれども、このとき私は火傷を負ったのだった。
「火事だ!」と、私は叫んで、弟といとこを人の山から引き離した。
次の瞬間には、二人とも見えなくなっていた。
物凄く強い風が吹き出していたから、彼らは吹きとばされてしまったに違いない。
私は、走らずにはいられなかった。
そして何かにぶつかって、気を失った。
やがてわれに返ると、私は死体の山の上に立っていた。
私は、またもや吹き倒された。
また駈けだしたが、突然何も見えなくなってしまった。
目がつぶれてしまったのだと思った。
そして、そのまま引き込まれるように倒れてしまった。
何もわからなくなった。
誰かが、倒れかかってきた。
こんな状態に三度ほどなったと思う。
こんどはもう起き上るまいと思った。
息がつまってきて、いつでも走っているような気がした。
やがて急に、生きたいと思った。
髪の毛を手でかぎ上げてみて、目が見えることがわかった。私は、川の方へ走っていった。
井戸が目にはいったが、身体だけが意志に反して走っていたので、それを通りすぎてしまった。
へたへたとくずれてしまうと眠くなったが、無理に目をさましていた。
火の子で火傷していた。
そして、――また走り出した。水たまりがあったので、泥水に顔を突っこんだ。
私は、池のそばにいたのだ――安田邸内の池の。
顔を上げてみると、風は吹き止んでいた。私は、われにかえった。靴が片一方なくなっていた。
残っていた片一方も、脱いで捨てた。
水の中にいた方が完全だったので、池にはいっていった。 |
top
**************************************** |