|
****************************************
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最悪の時(関東大震災4)
関東大地震が起った時間――正午に二分弱前――には、特別の意義があった。
それは、この地方一帯の何百万という台所で、一せいに食事の仕度のために火をたき始めた時間であり、それも決して帝国ホテルのような大ホテルの台所だけではなくて、何百軒というもっと小さなレストラン、何千軒という小食堂、さらに何十万軒という小さな木造家屋の台所でもそうだったのである。
こうした状況に、家屋の構造と都市地区独特の構成が加わって、どの都市でも地震が起れば大火災が発生するのは、必至と見られていた。
東京の火災は、当然、最大のものであった――池口医師と青木満喜子の見た煙の柱こそは、史上最大の火災の発生の必至なことを示すものだったのである。
しかし、東京の大火災には、燃えつくすための広大な地域と尨大な量の燃料があった。
従って、それが頂点に達するまでには、数時間を要したのである。
これに対して南西の小さな都市では、地震はもっと激烈で、火災も遥かに早く発生した。 |
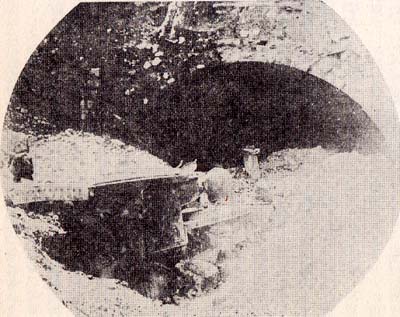
根府川付近のトンネル入口で土砂に埋役した機関車
|
そうした小さな都市では、火災は確かに早期に起ったが、それと同時に、たとえば伊東、熱海、鎌倉以外の小都市のように、津波がかえって火消しの役を果たした所もあった。
また、もっと小さい町では、住民の大部分が――倒壊家屋の下敷きになった者は別として――周辺の田舎に逃げることができた。
そして一時間で全町に火がまわり、その夜のうちに灰塵に帰してしまった小田原町でさえも、死者の人口比は、東京や横浜にくらべて、遥かに低かったのである。
大軍港都市の横須賀でも――人口は六万ほどだった――火災の大きさに比較して、死者の数は少なかった。
ここでは、地震が起ったとたんに、遠足で列車に乗っていた二百人の学童が、駅のわきの高い崖が崩れたために、列車ごと生き埋めになってしまったし、一方では全艦隊が二年間行動できるだけの重油の貯蔵タンクが倒れて火を発し、燃えたままの油が港に溢れ出て、まさに火の絨毯の様相を呈した。
それにもかかわらず、碇泊中の艦船や周辺の田舎が避難場所となり、町こそ灰塵に帰したけれども、死者の数は七百人余という、比較的少いものですんだのである。
横浜でも、横須賀と同様に、尨大な量の石油が貯蔵されていた――そして、ライジング・サンやスタンダードなどの石油会社では、駅に近い高台にタンクをもっていた。
これらのタンクが地震でこわれると、中の石油は排水用の掘割や大岡川を伝わって港に流れこみ、その途中で引火した。
そうした状況だったから、東京の火災がやっとはじまったころ、海岸に面していて南風をまともに受ける形となっている横浜では火災が頂点に達していたのは、異とするに足りないことだった。
全体のスケールとしては、東京のそれにはかなり劣ってはいたが、比較的にみると横浜の火災の方が破壊的であった――結局、東京の六十パーセントに対して、横浜では八十八パーセントが破壊された上に、死者行方不明の合計も、東京の十万七千人に対して、三万三千人に達したのである。
東京では、外人の住宅は西部高台にあって、ここは地震に対しても、火災に対しても比較的安全度が高かった――現在までに知られているところでは、西欧人は地震によっても、火事によっても、一人も死ななかったという。
これに反して横浜では、居留外国人の死者数は、日本人のそれを上回ることはなかったにしても、その割合からいって、大体同等であった。
外国人犠牲者――約二百五十人に上った――のなかで、最も悲惨だった者の一人に、若いアメリカ領事のマックス・デビッド・カージャソフがいたが、この人は両親がロシア人だったのをアメリカに帰化した人で、領事公邸の庭で妊娠していた夫人と下のお嬢さんと三人でまっ黒こげの姿で発見された。
地震が起ったときに公邸の方にいなかったカージャソフ氏は、急いで家族を救出するために帰っていったのだったが、三人とも火に囲まれてしまったのであった。
外国の都市で死亡したアメリカの市氏については、それぞれの土地のアメリカ領事館によって、公式の合同記録書に一人ずつ別のページに記載されることになっているのだが、横浜のアメリカ領事の合同記録書の場合は、彼の後任者が、他の地震の犠牲者たちについては三十八ページを費しているのに、カージャソフ氏については簡単に記している。
その他の犠牲者たちの一人に、フェリス女学校の校長ミス・ジェニー・カイバーがいたが、彼女は次の月曜日から始まる授業の準備をするために、地震の日の前夜軽井沢から戻ってきたのであった。
彼女は、焼けくずれた校舎の下敷きになってしまい、おりから近くにいた先生や生徒たちが彼女を救出しようとしたが、彼女はとても助からないことを知っていた。
そのときの先生や生徒たちの伝えたところによると、彼女のいまわのきわの言葉は、こうであった。
「私は父なる神に召されていくのです。みんな、あっちへいらっしゃい。火がすぐそこまで来ていますよ」
言われた人たちは、火が自分たちの服に移りそうになってきたので、やむなく彼女の命令通りにした。
そして、近くの庭まで逃げていった彼らの耳に「さようなら、皆さん」という言葉についで彼女の歌う讃美歌が聞こえてきたという。
横浜下町の繁華街では、地震で死ななかった人たちが、大体三通りの方法で焼けくずれる家から避難をした。
その中でいちばん多かったのが、海岸であった――海面には、油が燃え続けてはいたが、しかし、ここが結局いちばん安全であった。
ここまで逃げてきた人たちは、火事の方に背を向けて、腰くらいまで、場合によっては首まで水につかって、火炎を防いでいた。
こうして、何干という人たちが、夜になってから小さな舟がやってきて、港内に碇泊している大型船舶に収容されるまで、頑張っていたのである。
繁華街の別の地区で、火事で海岸の方へ逃げることもできない人たちは、掘割や川に逃げこんだ。
こうした掘割や川には、油が燃えていたり、火がついてもやい綱の切れたサンパン船が漂流していたりしていたが、しかし危険はそれだけにとどまらなかった。
横浜では――東京湾沿岸の他の都市もそうだったが――相模湾沿岸の町とちがって、津波は押し寄せてはこなかったが、その代りに地震がくると間もなく水がひいて、水位が六十センチから九十センチも下り、その状態が数時間も続いたのである。
湾の水位が下るにつれて、掘割の深さも通常の平均一・二メートルほどの半分ないしはそれ以下に下った。
その上に、両岸からは強烈な火勢がおそいかかってきたのでとても防ぎきれず、掘割に避難した人だちからは、何千人という焼死者を出した。
好運にも生き残った者の中に、若い商人の磯野ツネユキとその夫人がいた。
彼は夫人を連れて、石油タンクのあるところよりももっと川の上流の水の中に避難した。
そして火勢が衰えたころ、水の中からはい出し、橋の上に出てみると、不思議なことにその橋は一晩中なま温かった。
翌朝になって、堤防をはいおりだ磯野氏には、その不思議な現象がわかった。
橋の真下にあったはしけが燃えて、ストーブの役割をして橋を温めていたのであった。
下町の人たちが避難した三つ目の方法は、河岸から一・六キロほどはいったところの、二十エーカー(八万平方メートル余)ほどある横浜公園であった。
火の壁によって海岸への出口をふさがれた何千という群衆が、この公園に殺到した。
地震でこわれてしまったために消防隊には最初から使用不能だった給水本管が、実は大きな助けとなったのである。
こわれた本管から溢れ出た水が、公園を沼みたいにしてしまい、その湿気によって――周辺にいた何千という人たちは、焼け死んでしまったが――中央部にいた人たちは四方からおそってきた火熱に耐えることができたのであった。
横浜公園に避難して助かったなかに、若い経済記者ナミカタクニハルがいた。
地震がきたときに、生糸業者をまわって取材していた彼は、木造家屋に上から倒れかかられて、怪我こそしなかったが、重い梁のあいだにはさまれてしまった。
助けを求めた彼の耳に、一度は、いま助けてやるからしっかり待っていろ、という声が聞こえたのだが、急にそうした声もしなくなって、あたりは気味の悪いほど静かになってしまった。
さては、救助に来た人たちもみんな逃げてしまって、火が近くにまわって来たのだなと感じた彼は、超人的な努力をして、なんとかそこを抜け出し、ただもうもうと煙が立つばかりで人っ子一人いない街頭にとび出した。
街の角の方へ走っていって、そこを回ろうとした彼は、あやうく生糸取引所の理事長にぶつかりそうになったが、その理事長は、
「大災害の最中にもかかわらず、君のような、命がけで火災の取材をする記者がいるとは、君の社も鼻が高いな!」
といったので、彼は苦笑いをしたことだった。
二人は一緒に、猛火のだけり狂う街を公園に向った。
そして、頭から泥をかぶって熱気を防ぎながら、その夜をそこで明かしたのだった。
焔にさえぎられて海岸にも公園にも出られなかった多くの人たちにとって、いちばん安全な場所は横浜正金銀行のはずであった。
ここは耐火建築になっているといわれており、事実地震でも倒れなかった六軒ほどの建物の一つである。
正金の行員たちと、暫らくたって何百という外部の人たちが、地下の金庫室に逃げこんだ。
結局扉は閉めなければならなかったので、おくれてやってきた何百人は、はいれずにそのまま焼け死んでしまった。
しかし、あとから考えると、この人たちの方が幸せだったともいえる。
というのは、あとになって、火が地震でゆがんだ窓から侵入してきたために、地下室の何百人の方は、じわじわと蒸し焼きにされてしまったからである。
しかし、その夜、ダンテ・デンティチとその父親が目撃したものは、この横浜正金銀行の凄惨さを遥かに上廻るものであった。
海岸に出ようとして、火の壁にさえぎられた親子は、山の手(ブラフ)の端の崖下にある湿地に逃げこんだのだった。
その夜、何百人という山の手の住民は、この崖の端まで火に追いつめられてきていたが、ここでその人たちはそのまま焼け死ぬか、思い切って三十メートル下までとびおりるかの、どちらかを選はなければならない破目に陥っていた。
そして彼らがいよいよどうしてもとび降りなければならなくなってとびおりると、先にとび降りた者の上にあとからあとから重なってとび降りることになり、いずれも大怪我をしたので、動くこともできなかった。
ダンテ・デンティチは、その人たちが怪我をして苦しみ唸っている声や、死んでいくときのうめき声を、夜通し耳にしていた――夜があけて、明るくなってからわかったことだが、その崖にはぼんやりとながら道がついていて、それに気がついていたらかなり多くの人たちが混乱を起さずに降りられたかも知れなかったのであった。
一八六一年に、日本政府は海外に使節団を派遣したが、その目的は広く諸外国の生活様式を視察させ、報告書をつくらせることであった。
この使節団一行の記録は実に興味深いものがあるが、それを読んだヨーロッパの人たちの印象は、筆者たちが西欧諸国の防火施設について、不釣合なほどに多くのスペースをさいていることであった。
しかし、この記録を読ませる対象としての日本人にとっては、それは当然のことだったのである。
日本では、殆んどの大地震が、大火災の原因となっているといえるのだが、しかし、決して地震だけが原因なのではない。
それどころか、日本の都市、とくに大都市では、いろいろな原因から大火災が起る危険性がある。
徳川幕府二百五十年の治政を通じて――この間に江戸の人々は、百万から二百万のあいだを往復したが――五百件以上の大火災が記録されている。
そのなかの百件以上が、三千戸以上を焼失しており、同時代に西欧諸国に起った火災の最大のものに匹敵するという一六六六年の江戸大火を、焼失面積においても、死傷者においても遥かに上回る規模のものが、五十件をくだらないのである。
徳川時代の江戸には、水道がなかったばかりでなく、消火設備としては手桶と、破壊用具くらいしかなかった。
そういう状態では、火が出るとすぐ消し止める以外にはなかったのだ。
いったん一軒の家が燃え出すと、必ずほかの家に燃え移ってしまう――そういう場合によくとられた方法としては、風向きのまま火を家の建っていないところ、つまりその町の終るところまで進ませて消えさせるか、雨の降り出すのを侍つかということだったのである。
二万五千の犠牲者を出した一七七二年の大火のような、最大級の火災の殆んどの場合が、火が幅の狭い帯状をなして通り抜けている。
しかし、そうした火勢を局限するやり方でも、どうすることもできなかった大火もあった。
江戸の火事で最大のものは、一六五七年の大火事だったが、これはおりからの北西の強風にあおられて、繁華街の六千エーカーをなめつくし、海岸までいってやっと消えるまでに、十万人の死者を出したのである。
大火事というのは、江戸の日常生活にはつきものになっていた――三度大火事に出くわさなければ一人前じゃあない、といわれたくらいであった。
困難を堪え忍ぶということは、厳格で誇り高いサムライ精神のひとつの表れでもあり、それはスパルタ精神をはるかにしのぐものであった。
真の江戸っ子――江戸に少くとも三代は住んだもの――は、どんな不幸に見舞われても、鼻の先でせせら笑ったものであるが、同様に厳寒にも家の中を温めるようなことを軽蔑したのであり、その家が城になるとなおさらのことであった。
江戸のむかしから『七転び八起き』という禁欲主義的な諺(ことわざ)があるが、これこそは、そうした心意気を簡潔にあらわしている。
火事で丸焼けになり、無一文になってしまったものが、また身代をたて直してこそ、みんなから尊敬されたのである。
大火事を『江戸の華』と呼んだ粋な言葉こそは、決していやみでも自嘲でもなくて、苦い経験を重ねてきた結果から生れた、立派な自負心だった。
明治にはいってから、海外視察使節団の持ち帰った知識を取り入れた結果、東京はかなりその因習を訂正した。
首都として恥かしくないだけの消防組織もできて、九百人の消防士と千四百人の補助員とがら成る消防隊が、全市の要点三十ヵ所に配属された。
これらの献身的な消防士たちが『江戸の華』の精神を、効果的に実行したおかげで、明治維新後の六十年間を通じて、焼失家屋三千戸以上の大火は、わずかに十件にとどまったのであった。
関東大地震が起ったあとの東京では、他の都市同様、電話が完全に破壊されてしまったので、地震と同時もしくはそれ以後に各地で発生した火災の報道が、殆んど不可能になってしまった。
それにもかかわらず、最初の一時間に百三十六件の火事が消防隊によって発見され、そのうちの三十六件が実際に消しとめられている。
しかし、その日の正午ごろには殆んど気がつかなかったくらいのそよ風がだんだんと強まってきて、暑さのために明け放しになっていた窓などを通っていくうちに恰好の乾燥の役割を果たす結果となった。
そして、ひとつの火事の現場からの火の子が、そうした風にのって飛び、地震で瓦がとんでしまった屋根が、重大な意味をもつことになった。
瓦がとんで下地の木の部分に火が燃え移り、そんなことさえなければ耐火建築だった多くの建物をも焼いてしまった。
あれよあれよという間に、火は移っていって、別の火と合わさり、勢力が倍加されていったのである。
地震が起るとすぐに、東京市の消防部長(当時の東京市の消防組織は、警視庁の消防部が管掌していた)は、かつてない非常事態に当面したことを感じた。
中央の監視塔から見たところでは、市内各地から火を発していたのである。
それと同時に危険をはらんでいたのは、混乱した街の中を人々が――大部分の人は、荷車に家財道具を積んで、引いていた――火に包まれた迷路を安全な場所を求めて右往左往している状態であった。
警視庁消防部としては、各消防署との連絡には、歩いていく以外になかった。
そして、連絡員が派遣され、各消防署は各自の判断に従って処置をとるようにと伝えられたのである。
市の中心部――大学街の一部をも含む――は、こうして、消防署の善処によって救われたが、下町一帯の火勢はいよいよ猛烈になっていった。
隅田川の両岸には、いくつかの大火が発生した。
その一つは、川の右岸すなわち西側の地区である浅草公園に発生したが、ここには多くの小さな飲食店が密集していたので、火はたちまち燃えひろがり、しかも店の経営者たちは、もうとても消火は不可能とみると、逃げだしてしまったのである。
ここから数丁離れた吉原の一画でも、火が数ヵ所から出た。
隅田川の左岸地区すなわち本所方面では、火の出たのはおそかったが、燃えひろがった地域は浅草方面よりも広かった。
こうして、二つの地区で発生し、しかもいくつもの火事の合わさった火事の集団がまとまった形をなして一つの方向に進み出したころに、一つの興味ある動きが始まった。
隅田川の両岸地区の住民たちの双方が、じっとしていたら火にやられてしまうと考えた結果、川の反対側にいけば助かるだろうと、判断したのである。
こうして川の両岸近くには、すっかり恐慌状態に陥った群衆が――大部分は引火し易い家財を荷車に積んで引いていた――橋を目ざしてひしめいていたのだが、そのどちらの群衆もが、反対側もさかんに燃えているのに気がついていなかったのである。
隅田川の、泥深い東京湾に近い五キロのところには、一九二三年にも現在と同様に八百メートルほどの間隔をおいて五つの橋がかかっていた。
普通の状態だとこれらの橋は――一九二三年当時は全部木造であった――通行人を主体とした交通量には、充分に耐えるカをもっていた。
しかし、この九月一日の午後には、川の両側から押し寄せる群衆を維持できないことを、事実で示してしまったのである。
両側から追っていった避難民の先頭にいた人たちは、だんだんと橋に近づくに従って、橋を渡っても意味のないことを勘づいたが、しかしあとからあとから押されるので、いまさら引き返すことはとてもできなかった。
そして一部の人たちは、橋の上なら両岸の火事から遠のくことになるから、それだけ安全ではないかと瞬間的に判断したが、あとに続く人たちも同様に考えるようになったので、避難の群衆はいよいよ橋に向って殺到したのである。
火が川の両岸から橋に近づいてきて、さらに大勢の人たちが橋に殺到しはじめるにつれて、橋の中央部にいた人たちは川の中にとびおりるか、押されて落ちてしまった。
泳ぎの出来る人たちの方が、泳げない人たちよりも不運であった――――泳げない者は、すぐに溺死してしまったが、泳ける者のなかには、じわじわと焼け死んだ人が多かったからだ。
橋の上に残った人たちも、結局は同じ運命をたどった。
火の子が、遊難民のもってきた燃え易い荷物に降りそそいだ。
そして、まずその荷物が、そしてついには橋が燃え出した。
五つの橋のうち、翌日になって残っていたのは『新大橋』だけであった。
この『新大橋』が残ったのは、羽鳥原作という一巡査の勇気と良識によるところが大きかった。
火事の原因となるものが、避難民がもってきた布団や手回り品であると判断した彼は、部下たちに命じて、『新大橋』には一切それを持ち込むことを禁止させたのだ。
そのおかげで、この橋に避難した一万二千人の命は前かったのである。
橋に避難したケースだけが、震災下の東京における唯一の大量避難ではなかった。
事実は東京全市にわたって、あるいは少くとも下町では、全市民が同時にあらゆる方向に向って、動き出していたのである。
ある意味では、山火事に追われて山を逃げまわる動物たちにも似ていたが、しかしひとつだけはっきりした相違点があった。
山火事の場合は、火元は大体一つであり、火事は単一のものとしてひろがるので、方向もはっきりしている。
しかし、この震災の場合は、火元はたくさんあった上に、いろいろな方向にひろがっていった。
そして各方面からやってきた避難民の群衆が、お互いにぶつかり合って動きがとれなくなってしまった――立往生してしまったのは、決して橋の上だけではなかったのである。
東京の下町地区には、避難するには恰好な三ヵ所の広大な空地があったので、避難民の殆んどが、そこを目ざしていった。
ひとつは五平方キロの『宮城前広場』と呼ばれていた、いまの皇居前広場であった。
西方の住宅地の山の手と下町の境に当るこの場所では、よくパレードやデモ行進が行なわれ、また市民の休日の散歩場でもあったが、北方の神田、東の銀座からの大勢の避難民のうちで、運のいい人たちがここに到着した。
隅田川右岸の浅草区の住民たちにとっては、上野公園がいちばん避難場所として適当だった。
ここには動物園もあり、日本最大の美術館もあった。何万という避難民がここへ集ったが、いずれも無事だった。
動物園の動物たちも無事だった――浅草公園の見世物動物園の動物たちとは違って。
川の左岸に当る本所、深川地区の住民たちにとって絶好の避難場所は、建物が取り払われたのちでも住民たちが被服廠と呼んでいたところであった。
隣接している安田庭園を加えると――ただし、安田庭園は塀を囲らしており、一般市民ははいれなかった――二十五エーカーほどの広さになり、これに同庭園の面している隅田川の川幅を加えると、火のこない地域の広さは殆んどその二倍にもなった。
各消防署では、警視総監から委ねられていた権限によって、本所方面の市民は被服廠に避難するように指令を伝えた。
一時になると、その辺の空一帯に大い煙の柱が立ち上り、おびただしい数の避難民が、被服廠目かけて殺到しはじめたのであった。
それから四時間から五時間のあいだに、東京各地の火事がひとつにまとまってきて、結局地上かつてみたことのない大火災となってしまった。
この火災に比較できるものとしては、第二次大戦中の日本の火災がある――広島、長崎の原爆投下による火災と、一九四五年三月十日の東京、同五月二十九日の横浜の焼夷弾攻撃による火災である。
しかし、これらの火災も、その破壊効果においても、その地域においても、東京のこの大火災には及ばなかったのである。
しかし、東京全体が焼けてしまったのではない。
それどころか、ひとつには消防隊の活躍により、またひとつには気象学上の現象と都市計画のおかけで、高台の山の手一帯の大部分は、小さな火事がそこここに発生した以外には、無事だったのだ。
これらの高台の住民たちのなかには、大火災を見物していた者もいたのであって、その人たちの回顧談によると、恐ろしくはあったが、確かに美しい眺めだったという。
突如として地上から高熱であおられたために、東京の上空には巨大なえもいわれない素晴らしい、ふわっとした白い雲が出来上り、地上近くの真っ黒い煙と、形容できないほどの美しい対照をなした火焔は、まるで火の海のように、真っ赤な渦や波となって、地上数キロにわたって広がっていた。
さらに視野を広げて眺めると、それはまさに溶鉱炉の内部をのぞいているようであった。
あたりが暗くなってくるにつれて、火焔はさらに空中高く上っていった――どのくらいのところまでいったかは、見当がつかなかったが、夕方になって暗くなると、まるで東京の空全体が燃えているような景観であった。
気象学者たちがのちに推測したところによると、火焔そのものの高さは――雪に反映したものは別として――九十メートルをこえてはいなかったが、大小の火の子が下から吹き上げる風にのって、八キロは上っていただろうという。
その日の午後を通じて、高台から下を眺めていた人たちには、あの一面の火の海のなかで人間が動き回っているとは思えなかったという。
もちろん、現実には、何千何万の人々が動き回っていたのである――その人々の殆んどが、目前に危険が差し追っているとは知らないで。
その人々の中には、きちょうめんな池口医師と、よそ行きの服を着て、新らしい編み上げ靴をはいた青木満喜子がいたのである。
青木満喜子の場合は、どういうことになったかというと――彼女が父親と二十五人の職工といっしょになってから、その後の方途をきめるための会議が開かれた。
会議が開かれているあいだに、職工の一人が町に出ていって状況を見てきての話では、警察では被服廠に避難するようにすすめているかいう。
青木氏は、それはいい考えだと思い、家族も職工たちもそうするようにといった。
満喜子は、週末の大磯行きのための準備に、必要品はビーチ・タオルに包んであったので、すぐにでも出かけられた。
彼女はすぐに、四人の職工だちと一緒に出かけて、祖母と幼い弟はあとから、青木氏と残りの職工たちも、工場の方を片づけておいて、やはりあとからくることになった。
そして満喜子は、被服廠の入口のところで祖母だちと待ち合わせ、家族は一緒になる筈だった。
表通りに出ると、二、三台の路面電車がとまったままになっていたが、乗客はみんな降りてしまい、運転手と車掌たちが、そのそばに途方に暮れた面持ちで立っていた。
街は人でいっぱいだったが、その人たちの大部分が、警察がそういうのだから安全だろうと、被服廠へと向っていた。
いよいよ押し合いへし合いになって、進まなくなると、職工の一人が満喜子に、どこかの橋をわたって、上野公園にいったほうがいいではないだろうか、といった。
満喜子は、その提案も考えてはみたが、しかし断った――父は彼女に被服廠にいくようにいったのだし、それに、もしも彼女がほかのところにいってしまったら、祖母が彼女を探しまわるだろうし、心配や混乱が起ると考えたのだ。
普通なら歩いて十分くらいの被服廠まで、このときは一時間もかかった。
きてみて満喜子は、あまりにも多くの群衆なので、これでは祖母が自分を探すのは大変だろうと思った。
彼女の特っていたビーチ・タオルの模様はとても派手だったので、家族の人から見れば、すぐに彼女のものだと気がつく。
彼女は長い棒を見つけて、その先にタオルをしばりつけたのを高くかかげながら、廠の入口のところに立った。
池口医師の場合は、準備が整い次第家を引き払うというのが、最初の計画だった。
しかしこの計画は実行不可能になってしまった。というのは、地震で怪我をした人たちが続々と治療を受けにやってきたからである。
二時近くに、安田家からの使いの者が二人、荷車をもってやってきて、主人からの命令で火の手がまわる心配があるので先生のご家族を、荷物と一緒にお連れするようにという口上であった。
そして、池口医師が患者の手当てをしているあいだに、夫人と召使いたちで家財を荷車に積み込んだ。
準備が整うと彼は、自分はすみ次第あとからいくから、先にいっているようにと一同にいい渡した。
一同は、川にいちばん近い安田邸の入口のところの洋館のわきで、彼と落合うことになった。
良心的な医師である彼は、それから三時すぎまで患者の手当てをしていた。
もうそのころには、物の燃える音が彼のところまで聞こえてきて、強い南風が家に火を吹きつけていた。
ようやく出かけた彼は、芋を洗うようにひしめいている街の群衆をかきわけて進みながら、一方では火をよけていかなければならなかった。
しかし、安田邸についてみると、火はかなり遠くなり、すぐに家族や召使いたちと合流することができた。
安田邸の門の左側にあった洋館というのは、東京で最初に建てられた煉瓦造りの建物で、その辺の目印の一つとなっていた。
池口夫人以下の人たちは、彼にいわれた通りの場所に立っていた。
池口夫人は、煙が濃くなってだんだん近づいてくるのを見ながら、夫を案じていたのであったが、その夫がやっとついたので、子供たちと一緒に大いに喜んだ。
そうしているところへ、安田家の家令が出てきて、中にはいってお茶をあげるようにとすすめた。
医師は礼を述べてそれを断った。
家族といっしょに庭にいるつもりだったからである。
そうこうしているうちに、四時近くなった。
風がだんだんと強くなり、しかも、その方向が不安定であることに医師は気がついた――時おり対岸の火の子が風に送られてきたが、それがだんだんと増していった。
対岸の状況は、どうにも手のつけようがないらしく、次第に深刻さを増していった。
こちらは、すぐに危険がくるというほどでもなかった。
医師のかかえの車夫が、腹が減ったといったので、彼はみんながまだ昼食をすましていなかったのを思い出した。
女中と夫人が握り飯の包みを開いて、みんなで食べはしめた。子供たちは、大はしゃぎだった――彼らには、一家総出のピクニックみたいに思えたのである。
近くにいたよその子供たちが――もうそのころには、邸内には十二、三組の家族、五、六十人の人たちが避難してきていた――いかにも腹を減らしているように見えたので、池口家では彼らをよんで、待っていたものは全部あげてやった。
彼らが庭に坐って、間に合わせの昼食をとっていると、突然、まるで飛行機が低空飛行をするときのように、物凄い音が聞こえてきた――はじめは遠かったが、だんだん近くなり、ついにはすぐそばにやってきた。
それと同時に、空が急に暗くなってきて、殆んど真黒に見えた。二つ目のお握りを口に入れようとしていた五歳になる池口医師の息子が、急にその手を止めた。
そして、ぽかっと口を開けたまま、まるで夜のように真っ暗な空を見つめていた。
top
**************************************** |