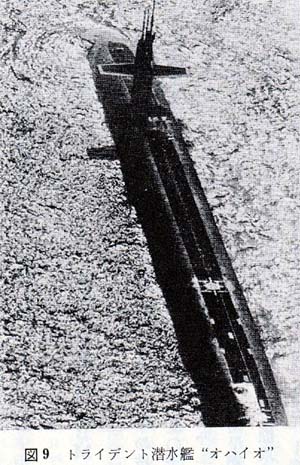|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章
第四章 空と海の戦略兵器――新型爆撃機とミサイル潜水艦――
軍事技術革新の波は、第一章でとりあげた弾道ミサイル迎撃絅(BMD)や第二章で述べた大陸間弾道ミサイル(ICBM)の分野だけでなく、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)や戦略爆撃機の分野にも押し寄せてきている。
新型のSLBMとしては長射程、高命中精度で、可変軌道弾頭(MaRV)も取付けられるトライデント・ミサイルがあり、爆撃機としてはマッハ最大二・二B1B爆撃機、それに高命中精度の巡航ミサイルがある。
中でも注目されるのは今後の核戦略において、ミサイル潜水艦の果たす役割が高まっていくと見られることであり、同時に、それを突き崩すような対潜水艦作戦(ASW)の発達である。
巡航ミサイルは、一九八四年頃からは日本を含む西太平洋にもやってくる。
1 「渚にて」――水爆による破滅への予感
top
戦略爆撃機や原子力潜水艦の恐るべき役割を教えた物語として、英国の作家ネビル・シュート・ノーウェイが一九五七年に発表した小説『渚にて』(邦訳・東京創元社、一九六五年)がある。
当時、米、英でベストsラーに数えられ、映画になって日本でも多くの観客を集めたもので、一九XX年××月×日に第三次大戦が勃発し、三十七日間で北半球が壊滅するだけでなく、その放射能雲のため、南半球の人々も死んでいくという筋書きである。
大戦はアルバニアに始まってたちまち中東に移り、時を移さず米ソの戦略空軍機が出動して、合わせて四千七百発の原水爆を投下する。
小説の主人公は孤独な米国の原子力潜水艦、スコーピオン号である。
濃い放射能の中で帰るべき港もなくなり、オーストラリアのメルボルンに着いてから、自沈する。
艦長の恋人もそれを見届けてから、やがて毒薬をあおって自殺をとげることになる。
ネビル・シュート・ノーウェイのこの小説は、映画の主題曲となったウォルチング・マチルダの調べとともに、水爆による破滅を予感した当時の人々の心に、深い感銘を与えた。
戦略爆撃機や原子力潜水艦が核戦略の中に占める役割は、大陸間弾道ミサイル(ICBM)が発達した今も、当時とそれほど変かっていないようにみえる。
だが詳しく調べると、この分野でも、危険な変化が起ころうとしていることが分かる。
広島、長崎に原爆を投下しだのに、現在では旧式のプロペラ機のB29爆撃機だったが、米ソではなお戦略爆撃機炉戦略兵力の重要な柱となっている。
爆撃機の特徴は、速度は遅しが柔軟性に富み、いったん発進したあとでも呼び戻すことができることにある。
一九五七年にICBMが登場した時、ソ連のフルシチョフ首相は、爆撃怖がやがて博物館入りするだろうと語った。
だが現実には米ソの爆撃機は、その後ますます高性能化の一途をたどっている。
米国の戦略爆撃機は八二年現在、By二百十六機からなり、戦略弾頭のほぼ四分の一を運搬できるものと考えられている。
核爆弾は一般に、ミサイルの弾頭よりは大型なので、運搬可能なメガトン数にすると、全戦略核兵器のそれの半分にもなる。
爆撃機は相手の防空網などのため、目標に接近できないような時には、そのはるかに手前から空中発射のミサイルや巡航ミサイルを発射することができる。
2 核爆弾の性能――超低空投下型へ
top
爆撃機用の核爆弾としては中型のB43や大型のB53(約九メガトン)、小型のB57(最大二十キロトン)、B61(百~五百キロトン)などがあることが知られている(Bは爆弾Bomb、または爆撃機Bomberの頭文字をとったもので、そのいずれを示すのにも使われる)。
これらについては米軍備管理軍縮局(ACDA)が毎年、議会に提出する軍備管理影響報告の中に、比較的詳細な説明がある。
たとえばACDAの八二会計年度報告は、現在開発中の新型B83爆弾について、おおよそ次のように述べている。
それによるとB83(爆発威力は可変)はB52戦略爆撃機や各種戦術空軍機用で、戦略爆撃の効果を高めるためのものとされる。
目的は、ソ連がICBMのサイロや発射台、指揮・管制・通信施設、核貯蔵庫を強化したのに対処することにある。
B83には最新のパラシュートが付いていて、高空あるいは四十五メートルという超低空のいずれからも投下できる。
B83爆弾には無許可の使用をなくすための許可作動リンク(PAL)が付いているだけでなく、安全性も高められている。
核物質を取巻く起爆用の通常火薬の一部が誤って爆発したような時、TNT火薬にして一・八キロを超える核爆発を起こす可能性も、百万分の一に抑えられている。
軍備管理軍縮局報告の一九七九会計年度版はB銘、B61、B77爆弾について述べている。
それによると爆弾は元々都市、産業目標や、中程度に強化された軍事目標の攻撃用につくられた。
だが六〇年代の初めごろからソ連のICBMのサイロや各種の軍事目標、指揮・管制・通信施設が相次いで強化された。
このため、これらの目標に対する従来の爆弾の効果が低下した。
一方ではソ連の防空網が強化された結果、米国の爆撃機戦略は超低空で目標上空に侵入し、爆撃する方法に切り換えられた。
B43やB77はいずれもそうした低空投下用である。
B61は重さ約三百二十五キロの軽量、多目的の水爆で戦略、戦術空軍機が、防空網の発達した地域で使うものとされている。
超音速で飛行中の航空機から投下でき、地表あるいは空中で爆発する。
小型のパラシュートを使って、巧みに目標に命中させる。
B83などと同様にPALが付いているが、B61のPALは鍵をあげる際に誤った符号を入れてしまうと、工場に送り返さないと開かないようになっている――。
以上が軍備管理軍縮局報告にみられる現在の米国の爆弾のあらましである。
ここで注目しなければならないのは、戦略爆撃用の爆弾が、ますます軍事目標攻撃用になっていることであり戦術用とともに超低空投下型になっていることである。
ソ連の戦略爆撃機(長距離空軍機)としては、Tu95“ベア”、MY4“パイソン”が有名で、合わせて百五十数機がある。
七〇年代の戦略兵器制限交渉(SALT)で、大きな話題になったものとしては、“バックファイア”爆撃機がある。
可変翼で最大マッハ約二・五の中型爆撃機で空中給油によって大陸間兵器になり得ることが問題化した。
バックファイア爆撃機は、極東地域にも配備されていることが明らかになっている。
戦略爆撃機のほかにも、米国は欧州に数百機の核装備可能の戦術空軍機を配備している。
ソ連のそれは約千機にのぼる。
NATOのF104やF4、ワルシャワ条約軍のSu7、Su20などがそれである。
そのほか米国には百ないし二百機の核装備可能の艦載機がある。
3 復活したB1爆撃機――三十二個の核爆弾を積んで
top
米戦略空軍では一九六二年にB52の生産が終わる前から、その後継機種の選定に着手していた。
まず白羽の矢が立ったのはノースアメリカン・エビエーショソ社のB70超音速爆撃機で、二機の原型鴒がつくられた。
だが六〇年五月に長距離偵察機のU2が撃墜されて、B70のような高空爆撃機がソ連領内に侵入できないことが分かった。
B70計画は結局中止になったが、その後も改良型有人戦略爆撃機(AMSA)の研究開発が続けられる。
B1という名称が初めて浮上したのは、レアード国防長官時代の一九六八年のことで、七〇年には主研究開発契約社として、ノースアメリカンの後身のロックウェル・インターナショナル社が選ばれている。
B1爆撃機の基本構想は一九七〇年に固まってから今日まで、基本的にはほとんど変化していない。
B52よりやや小型の可変翼の有人機で、最高速度はマッハ二・二、無給油で約一万キロを飛ぶことができる。
機内に二十四個、機外に八個の核爆弾を積んで、相手のレーダーをかわすため、高度三十ないし九十ノートルの超低空で目標上空に向けて侵入する。
MXミサイルの時代になお有人爆撃機が必要な理由としては、戦略態勢を柔軟化して何らかの危機の際に決意を表明するのに役立つことがあげられている。
有人爆撃機は、性質上は報復力とされる。
人間が乗っているので、ミサイルとは違って随時、必要な目標を選ぶことができる。 |
 |
だが防空網の発達した今では、爆撃機の使用は電話で用件を伝えたあとで電報を届けるようなものだ、という批判もある。
米国の機上警戒管制システム(AWACS)は、今では地表すれすれにやってくる航空機をも発見できる。
ソ連が同様な下方監視能力を高めていることも、明らかである。
B1のような有人爆撃機が役立つのは、ソ連が対応策を講ずるまでの数年間にすぎないという見方もある。
カーター前政権は一九七七年六月にB1を採用しないことを決め、代わって現在のB52爆撃機に、空中発射の巡航ミサイル(AICM)を搭載することに決めた。
だがこの方針もレーガン政府になって覆(くつが)えされた。
レーガン大統領は八三会計年度の予算教書で、B1改良型のB1B用に、四十八億ドルの予算を要請している。
八六年頃から実戦化して、最終的には百機を配備する計画といわれる。
B1B計画のもう一つの問題点は、一機当たり約四億ドル、必要な給油機まで含めると、百機で一千億ドルを越すとみられていることである。
ソ連にもあとを追わせて、ツ連経済を圧迫するのも狙いの一つというが、それは米国にとっても大きな負担となりそうである。
航空機技術の新しい流れとしては、超低空侵入と並んで、見えない飛行機の“ステルス”がある。
一九九〇年代に実用化することをめどに研究が進められているもので、機体の寸法や形声工夫し、表面にはレーダーの電波を吸収する材料を使って、相手のレーダーをくらます。
電波の吸収材としては、たとえばフェライトなどがある。
フェライトはこれまで優れた磁性材料として知られ、最近ではまた電子レンジからの電波洩れや、テレビの受信障害の防止に使われてきた。
日米軍事技術協力ともがらんで、八一年に米国から日本のメーカーに引合いがあったとも伝えられている。
ステルス技術についての研究の結果は有望で、最初は各種の小型無人機に使われる可能性があるといわれている。
だが軍事技術の常で、レーダーの側でもそれへの対応が始まっている。
電波の吸収が少ない波長の長い電波に切り換えたり、電波の発射と受信を別のところで行って、識別度を高めるなどの方法が、それである。
4 多発した重大事故――三十年間に三十二件も
top
有人爆撃機について是非触れておかねばならないのは、核事故である。
米国では一九五〇年代に大量報復戦略のもとでB47、B52など合わせて約二千百機のジエット戦略爆撃機がつくられた。
これら爆撃機の弱点は、ミサイルによる奇襲攻撃に弱いことである。
このため一九五七年にソ連がスプートニク一号を打上げたあと、米戦略空軍(SAC)では全世界に展開している戦略爆撃機を、緊急待機の態勢下に置いている。
五、六百機の戦略爆撃機が原水爆を積んで、滑走路上あるいは空中での待機に入ったのである。
原水爆パトロールは一九六八年までほぼ十年にわたって続けられたが、その結果、核兵器にからむ事故が多発した。
一九五八年三月には訓練中のB47がサウスカロライナ州フローレンス付近で、誤って原爆を投下し、核爆発はなかったものの、地上に直径二十五メートルの大穴をあけている。
一九六六年一月にはスペインのパロマレスで四個の水爆を積んだB52が、空中給油機のKC135と空中衝突し、二個の水爆の中の高性能火薬が爆発して、地上にプルトニュームをまき散らした。
その結果、汚染された表土約千四百トンが回収され、米本土に送られた。
原爆は特別の電気装置によって、ウランやプルトニュームを取巻く高性能火薬に同時に点火して、爆発するようになっている。
だからただ起爆用の火薬が爆発したというだけでは、核爆発は起こらない。
だがそうした安全装置も、常に一〇〇%確実に働くという保証はない。
一九六一年一月にノースカロライナ州ゴールズボロで起こったB52の事故では、誤って投下された二十四メガトン水爆の中の六つの安全装置のうち、五つまでが働いていなかったことが分かっている。
この事故では残るたった一つのスイッチが、広島型原爆の三千七百倍という大爆発の発生を防いだといわれている。
米国防総省とエネルギー省が一九八一年に発表した「一九五〇年から八〇年までの核兵器事故」についての報告によると、この間に三十二件の事故が起こっている。
国防総省では、これら核爆弾の本体にかかわる重大事故を“ブロークン・アロー(折れた矢)”と呼んでいるが、それには至らぬ“ペント・スピア(曲ったヤリ)”事故の数は、分かっているものだけでその数倍もある。
核爆撃輯がある限り、今後もこの種の事故はなくなることはないだろう。
5 巡航ミサイル――空前の命中精度もつ小型無人機
top
新型爆撃機と並ぶもう一つの新兵器に巡航ミサイルがある。
巡航ミサイルは超小型のジエット・エンジンの開発に、新型の電子誘導装置を組み合わせたもので、空中を亜音速で飛び、空前の命中精度をもつ。
レーガン大統領の八三会計年度の予算は、その配備促進のために九億ドルを要請している。
米国最初の大陸間ミサイルに、“スナーク”というのがある。
第二次大戦中のナチス・ドイツのV1号の流れを汲む無人機で、天測航法で星の光を頼りにマッハ約〇・九で、八千キロを飛ぶことができた。
長さ約二十一メートルの無人ジエット機と考えればよい。
だが速度の遅いスナークは、大陸間弾道ミサイル(ICBM)が現れて、たちまち忘れられてしまった。
歴史は繰返すというが、巡航ミサイルはその現代版である。
スナークよりもずっと小型で長さは六メートル程度だが、慣性誘導と“ターコム”(TERCOM)という特殊な誘導装置で、数百キロから数千キロを飛び、CEPは二十五ないし三十メートルともいう。
ターコムというのに地形等高線対照(ターレン・コムパリゾン)の略で、あらかじめ目標付近の地形をデジタル地図にして記憶し、それと実測値とを比較して目標のありかを確認する。
それに先立っては、迎撃を避けるために、地表すれすれをジグザグコースで飛行できる。
一度に多数発射すると、さらに迎撃が難しい。
巡航ミサイルには空中発射のもの〈AICM〉や地上発射のもの〈GICM〉、海中発射のもの〈SICM〉がある。 |
 |
空中発射のものはB52やB1B爆撃饋から発射して、相手の防空網を突破するのに使われる。
B52には、翼をたたんで二十数基(SALT1では二十八基に制限)が搭載される。
弾頭を核にすれば、ミサイル・サイロなど強化された目標を破壊することができる。
一九八〇年二月には、差し当たって二百二十五基つくることが決まり(八三会計年度予算では四百四十基)、八二年中には最初のものが実用化する。
最終的には八七会計年度までに、三千四百十八冓が生産される計画となっている。
地上発射の巡航ミサイル(GICM)は戦略兵器というよりは戦域兵器として、ソ連のSS20中距離弾道ミサイルに対抗して、一九八三年以降合計四百六十四基が、NATO(北大西洋条約機構)諸国に配備される。
のちに述べるように、一九七九年十二月のNATOのこの決定が、パーシング・ミサイルの配備とともに、一九八一年秋の反核運動の直接の引き金となる。
海中発射のもの(SICM)は“トマホーク”(北米原住民のマサカリ)の名で知られ、潜水艦の魚雷発射管などから発射される。
最初のものは一九八二年頃から、ロサンゼルス級の攻撃型原潜に、十二基ずつ搭載される。射程約二千四百キロで、核弾頭による対地、ならびに通常弾頭による対艦攻撃用である。
別に退役ポラリス原潜を改造して八十基以上をのせ、巡航ミサイル空母にすることも考えられている。
その候補としてジョージ・ワシントン号や、イーサン・アレン号の名もあがっており、これらがやがて西太平洋にやってくることは確実である。
巡航ミサイルは高度の電子頭脳をもつものの、基本的には小型無人機なので、生産コストがきわめて安いという特徴がある。
推力わずか六百キロというエンジンは、ベトナム戦争当時、海兵隊員が背中に背負ってジャングルを飛び越すために研究されたもので、新型の軽量の材料が使われている。
だが、この革命的な兵器に対しても、その性能についての疑問が出されている。
一九八〇年五月に米ワシントン州のセントヘレンズ火山が、十ないし五十メガトン相当の大爆発を起こした時、米軍の四発機のエンジンが噴煙を吸い込んで故障し、不時着している。
繊細な巡航ミサイルのエンジンが、核爆発の環境下で、うまく働くだろうか。
また目標付近に大雪が積ったらどうか。ターコム誘導装置は精巧になればなるほど、積雪などによる地形の変化に迷わされる。
目標を見失った巡航ミサイルが、雪の原野をあてどなくさまようことも考えられる。
6 トライデント・ミサイル――新型のSLBM
top
潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の分野での第一の技術革新は、新型のトライデント・ミサイルの登場である。
レーガン大統領は八三会計年度の予算教書で、トライデント原潜に三十七億ドル、同ミサイルに十億ドルの支出を要請したが、一九八九年に実戦化するトライデント・ミサイルは、一九八六年に完成予定のナブスター衛星網による世界的位置決定システム(GPS)と相まって、MXミサイル並みの精度と軍事目標攻撃能力をもつことになる。
トライデント・ミサイルには、Ⅰ型とⅡ型がある。
I型はマーク4弾頭(百キロトンのW76爆弾を内蔵)を八個もち、射程は従来のポラリス、ポセイドンより長く、七千四百キロに達する。
その結果、潜水艦は従来の十倍もの面積の海域で行動できる。
それだけ、対潜哨戒機などによって潜水艦を探し出し撃滅する“対潜水艦作戦”(ASW)が困難になる。
トライデントⅠ型は一九七九年頃から十二隻の“ラファイエッ卜”、“ベンジャミン・フランクリン”級のポセイドン潜水艦に積換中で、一九八二会計年度中に積換えが終わる。
トライデント・ミサイル専用の新型潜水艦の建造も始まっている。
米海軍では一九八七年までにまず九隻をつくる計画で、その第一号の“オハイオ”は一九八一年十一月十一日に就役した。
“オハイオ”は全長約百七十メートル、排水量はポセイドン潜水艦の十一倍以上の一万八千七百トンあり、ミサイル発射管の数も八本増えて二十四ある。 |
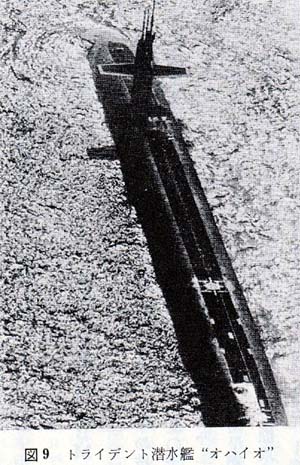
|
弾頭の総数は百九十二、総爆発威力に一隻で一九・二メガトンになる。
米国が第二次大戦中に欧州と日本に投下した爆弾の総量は約二メガトソだったから、一隻でその約十倍の破壊力をもつことになる。
この潜水艦一隻で、従来のポラリス潜水艦十隻分の目標を攻撃することができるといわれる。
第二号の“ミシガン”も八二年中に就役することになるが、これらトライデント潜水艦最初の九隻の基地は、ワシントン州のバンゴールに置かれる。
トライデント潜水艦の登場に伴って、二十年の耐用年数に近づしたポラリス潜水艦の一部は解体され、一部(八隻)は攻撃型潜水艦に改装されている。
トライデント・ミサイルの命中精度を示すCEPは、約五百メートルとされている。
従って、ミニットマンⅢのような、強化された軍事目標に対する攻撃能力はない。
だがレーガン大統領が開発促進を決めたトライデントⅡは、そうではない。
一九八九年に実戦化すれば、ミニットマンⅢと同じW78爆弾を搭載し、GPSによる命中精度の向上と相まって、MX並みの軍事目標攻撃能力をもつようになる。
トライデント・ミサイルにはまた、可変軌道弾道(MaRV)のマーク500を装備することも考えられている。
MaRVは大気間内に再突入したあと、小さなヒレで空気力学的に落下コースを修正するもので、それによって、弾立ミサイル迎撃網(BMD)による迎撃が行われても、それをかわすことができる。
7 “原潜の父”の警告――不安定化する核戦略
top
原子力潜水艦はポラリス(北極星)からポセイドン(ギリシヤ神話の海神)を経てトライデント(ポセイドンの持つ三叉のほこ)へと破壊力を増してきたが、早くからポラリス潜水艦などを育ててきたハイマン・ジコーバー提督は一九八二年一月、八十二歳で引退するに当たって議会で証言し、『世界の軍備競争は常軌を逸しており、人類は早晩、核戦争で滅亡するだろう』と警告した。
“原潜の父”といわれた提督の言葉だけに、その瞬間、両院経済合同委員会(ロイス委員長)室は、音もなく静まり返ったという。
ジコーバー提督はこのお別れの証言の中で、核装備で世界最強の海軍をつくり上げたことなど誇りには思っていないし、国際条約ができたらすべての原潜を破壊するだろうといった。
ここで注目したいのは、同提督が米海軍の百数十隻の原潜が、ソ連海軍のすべての艦船を沈める能力をもつとした点てある。
核戦略という点では、ミサイル潜水艦はこれまで、相手に探知されないという特徴を生かして、核報復力を温存するものと考えられてきた。
それによって核戦略が不安定化するのを避けるのだともされてきた。
だが一九八〇年代に入ったいま、トライデント・ミサイルがMX並みの軍事目標攻撃能力を手に入れようとし、一方ではジコーバー提督が示唆するように、米国の対潜水艦作戦(ASW)が非常な進展をみせている。
ASWではいうまでもなく、米側が圧倒的な優位にある。
とすれば、やがては米側が陸海空のすべての面で、ソ連に対して先制攻撃能力をもつようになることも考えられる。
実際にそうならなくてもソ連側が、そうなりつつあると考えたような場合、核戦略はきわめて不安定化する。
米ソ関係が緊張したりすると、ソ連はすぐに全ミサイルを発射の態勢に置くだろう。
ついでにいうと米国の戦略弾頭は、五〇%が潜水艦に搭載されている。
これに対してソ連の戦略弾頭は、多くがICBM用で、潜水艦と爆撃機の分は、わずか二五%程度であるに過ぎない。
ソ連の戦略ミサイル潜水艦は一般に稼働率が低く、常時約七分の一の十隻が任務についている程度という。
ミサイルとしては射程七千四百キロ、二百キロトン三弾頭のSS-N-18などが知られていたが、最近になって二十基の発射管をもつ史上最大のタイフーン級潜水艦が進水している。
これには八〇年代の半ば以降、新型のSS-NX-20ミサイルが搭載されるだろうという。
だがソ逓のSLBMの命中精度はかなり低くて、SS-N-18でCEPにして数千メートルという推定がある。
従って強化された軍事目標に対する攻撃能力をほとんどもたない。
ASWにも攻防の二つの側面がある。攻撃の面では目標を探知し、識別し、破壊する能力が拡大される。
防御面では、自分の側の潜水艦を発見されにくくして、その生存能力を高めようとする。
水中での探知は、すべて水中音響によって行われる。
そこでは各種のセンサーの能力の向上と、それらが捕えた膨大な情報の自動処理が、決め手となる。
米国のASW計画や、その研究開発については、国防報告や、軍備管理軍縮局(ACDA)の年報に多くの具体的な記述がある。
それには対潜監視システム、攻撃型原潜計画、海上哨戒機(P3)、水上艦戦術曳航式アレー・ソナー(TACTAS)、軽機上多目的システム(LAMPS)、それにマーク60キャプターなど種々の魚雷、爆雷がある。
だがここで引用しておきたいのは、ACDA年報一九七九会計年度版の中の次の一節である。
「高度の攻撃・生存能力をもつ米国の潜水艦隊は米海軍や、米国と海外同盟国との間のシーレーン(航路帯)に対する攻撃を、きわめて高価なものにする。
その意味で米国の潜水艦戦術戦システム(STWS)技術は、副次的損害を減らし、危機時の安定度を高める。……
だがSTWS計画の一部はソ連に対して、海の戦略報復能力に対する信頼を失わせる。
その結果、ソ連はSTWS計画を、戦略報復力に対する潜在的脅威とみなす可能性がある」 |
米国ではMXミサイル問題ともからんでしばしば、米国のミサイル潜水艦が、ソ連のASW能力の向上によって、一九九〇年代には脆弱化する、といった観測が流される。
だがソ連のASWは技術的に遅れているだけではなく、地理的にも不利な立場にある。
事実、米海軍では一九六〇年以来四十一隻のポラリス、ポセイドン潜水艦が延べ千五百回にわたって一回六十日のパトロールをしたが、一度も探知されたことはないといっている。
8 SOSUSと日本 対潜水艦作戦のなかで
top
米海軍のASW費は一九八〇会計年度だけでも七十億ドルに達し、海軍の全予算のざっと一六%にのぼっている。
その海中監視能力の中核となっているのが、音響監視システム(SOSUS)網である。
SOSUS網の設置は一九五四年に始められ、今では米大陸の西岸の大陸棚をはじめ、大西洋のアゾレス諸島、ハワイ付近、日本の北部や南部、アリューシャン冲、北大西洋のベア島とノルウェーの北部沿岸の間などの大陸棚上に、設置されている。
聴音器は油の詰まった金属製の円筒の中に浮かべられていて、捕えた音は符号化されてケーブルで陸上の基地へ送られ、コンピューターで分析して、通りがかった潜水艦の位置や速度、進行方向を計算する。
海中での音波の伝播はきわめて複雑なので、探知距離は状況に応じて、三十キロから九十キロと大きく変動する。
情報は次いで米本土や同盟国へも伝えられ、それぞれの探知システムによって、さらに精密な位置の決定や追跡が行われる。
だがSOSUSの欠点は、相手からの攻撃に対して脆弱なことにあるとされている。
対潜哨戒機としてはよく知られているように、P3C“オライオン”がある(Pは哨戒Patrolの頭文字。名称は星座名オリオンの英語読み)。
米国のこれら対潜哨戒機は、世界にひろがる基地網を利用することによって、ソ連のミサイル潜水艦の予想展開海域のすべて(約五千百五十万平方キロ)をカバーできるといわれている。
P3Cにはレーダー、電子監視装置、磁気・赤外線監視装置などがあり、随時ソノブイ(浮遊型の聴音機)を投下するほか、各種の対潜兵器も搭載できる。
それには、核爆雷やマーク46軽量魚雷、四十五ノット以上のスピードで目標を追う音響追尾兵器などがある。 |
 |
要するに米国のASWは現実に、ソ連のミサイル潜水艦のかなりの部分の生存性を脅しているといわれ、米国では、それによる核戦略の不安定化を防ぐために、ASW制限交渉の必要性や、少なくとも双方の潜水艦の聖域を設けることを提唱している人々がいる。
米ソともにICBMの命中精度の上昇によって、陸上基地のICBMが脆弱化すると、核戦略の安定を取戻すためには、戦略兵力の比重を大きく海に移さなければならなくなってくる。
にもかかわらず米国のASWの発達によって、ソ連にそれができないと、核戦略はますます不安定になっていくからである。
聖域の具体案としては、たとえば次のようなものがある。
米国はASW活動を大西洋や太平洋、あろいは、ノルウェー海に限り、ソ連のミサイル潜水艦にとって重要なバレンツ海や、オホーツク海での活動を差し控える。大西洋ではその活動をグリーンランド、アイスランドと英国とを結ぶ線の南の海域に制限する。
一方、ソ連は米海軍のミサイル潜水艦基地付近での活動を、差し控えることにする。
ミサイルの射程が長くなればそれも可能になるわけで、それによって相互に安心感が得られ、互いに軍備競争を抑制することができるようになるというわけである。
鈴木首相は一九八一年五月の訪米で、日本が南に延びるシーレーン千カイリの防衛に協力すると語った。
だがこのシーレーンは日本にとって重要な海上輸送路であるとともに、SOSUSのある水域にも当たる。
とすればシーレーンの防衛は単なる輸送路の防衛というだけでなく、米第七艦隊がインド洋、中東に向かったような場合、そのあとを埋めて、SOSUSを防衛することにもなる。
それを通じて米国の核戦略の中へさらに深く組みこまれることにもなりそうである。
top
****************************************
|