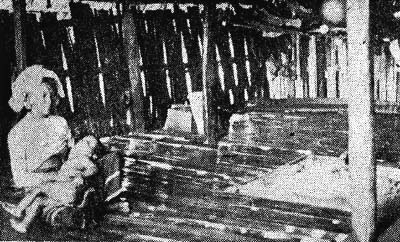|
****************************************
Home 概要 チベット潜行十年(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) カチン族の首かご(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ)
Ⅱ カチン族の独立
1 カチン少年挺身隊 top
次の日、朝飯を食べているとき、ザオパンがこんなことを言い出した。
「カチン族を指導したり、命令して仕事をさせたりするのに、私たち二人だけでは手がたりない。
そこで酋長や村長の息子たちの中から何人かをえらんで、私たちの手足になって働く少年挺身隊を、つくりましょう。」
「なるほど、うまい考えだ。」
私はすぐ窪田中尉にこの話をすると、隊長も賛成した。
ザオバンは、さっそく川岸で働いていた者を、近くの村へ伝令にだして、志願者をつのった。
すると昼すぎには、もうカチン・バッグに毛布をひっかけ、山刀を肩からつった六名の少年がやってきた。
カチン・バッグというのは、日用品をいれて肩からぶらさげている袋である。
少年たちは、みんな十五、六才で元気のいい顔をしていた。
ザオバンは、この六名の挺身隊の世話役に五十才くらいの男をえらんだ。 |

六名の少年挺身隊とその世話役のメイレイジュリョウ
|
この男は、とても名前が長くて、呼ぶのに不便だった。
それで私は「命令を受領する者」という意味で「メイレイジュリョー」(命令受領)と、よぶことにした。
「メイレイジュリョー。」と呼ぶと、彼は直立不動の姿勢で、
「オーツ、ドウァ。」と、答えた。
オーツ、ドウァとは、カチン語で
「はい、旦那さま」という意味だが、これでは私が、叱られているみたいに聞えるので、
「ハイ、ドウァ。」と、答えるように頼んだ。
これで「カチン少年挺身隊」はできあがったが、窪田中尉はやはり私に護衛をつけたほうがよかろうといって、先日、カチン部落へ一緒にいった二名の兵隊をつけてくれた。
私たちは次の渡河点スカ川へいき、また渡河準備をしなければならないめで、その日の午後、第一番の筏でチャンカをわたり、さきをいそいだ。
メイレイジュリョーは、愉快な男で、挺身隊が黙って歩いていると、
「モートカ、モートカ、ブツ、ブツ、プ、プ、プ、プー。」
と、あやしげな自作童謡「自動車」というのを、体に似合わない、かわいい声でうたい、みんなを笑わせた。
行軍の途中、ふいに十数人のカチン族が道にとびだしてきて、びっくりした。
話をきいたら、英印軍が捨てていったライフル銃と弾丸を、私たちに献上しにきたという。
おかけで少年挺身隊には、各人に一丁ずつの小銃が渡った。
生まれてはじめて、新式銃を手にした少年たちは、二人の日本兵から扱い方をおそわり、大喜びだった。
やがてスカ川の渡河点へ着いた。
そこには、もうザオバンの命令でつくりあげた筏(いかだ)が、密林の中にかくされてあった。
待っていたカチン族が私たちを、すぐむこう岸へ渡してくれた。
午後おそくなって、私たちの一行はテインパイのバンガローへ着いた。
ここにはだれもいなかったが、ようすを調べにでた三人の少年隊員が、一人のカチン人をつれてきた。
私たちは、このカチン人から重大な知らせをきいた。
ここから八キロさきには、この道筋で一番大きいカレンジャンという部落がある。
戸数は約百戸あり、村全体がクリスチャンで、英語を話すものが多い。
英印軍はその部落を逃げていくとき、日本軍の悪口を嘘をまじえて宣伝していったから、手向かいするかもしれないという、知らせである。
私は考えた。
「たとえ土民軍でも数百人が手向かってきたら、面倒なことになる。
でも英語がわかるなら、私が通訳なしでも話ができるわけだ。よし、何とか説きふせてやろう。」
私は、そう決心した。
少年隊は二人の日本兵に頼んでバンガローにとどめ、ザオバンだけをつれて、その村へでかけていった。
ナットの神を信じる蛮地の山の中に、クリスチャン村があるなんて、不思議でならなかったが、ザオバンが道々、この謎についてこう説明してくれた。
約三十年前に、信仰心のあつい三人のイギリスの尼さんが、死をおそれず危険もかえりみず、この蛮地に入ってきた。
三人はカレンジャンに教会をたて、熱心にキリスト教の教えを説いた。
精霊とまじない師、罰の恐ろしさだけしかしらなかったカチン族は、ほかに救いの神があると知らされて、すっかりおどろいてしまったらしい。
初めは、中々教会にちかづかなかったカチン族も、しまいには、我もわれもとキリスト教を信じ、村中全部がクリスチャンになった。
そして尼さんたちがいなくなったいまでも、キリストやマリアの像をおがみ、賛美歌をうたっているというのだった。
また読み書きを全くしらなかったカチン族に、文字を教えたのもこの三人の尼さんたちであり、彼らが現在使っているのは、英語のアルファベットで発音をつづったものだという。
これは、日本語をローマ字で書くのと同じやりかただった。
2 クリスチャン村 top
|

機(はた)を織るカチン族の少女
カレンジャンのクリスチャン村
|

子供の髪をゆうカチン族の母親
|
カレンジャンは、まるで人の死にたえた村のように、しずまりかえっていた。
何となく不安だったが、私は、わざと平気なようすをして、村へ入っていった。
村へ入る前に村人に誤解されないため、ピストルをはずしてザオバンに持たせた。
ザオパンは、はじめから銃は持っていない。
村の入口に小さな土橋があった。
そのそばの一軒の家から、五才くらいの男の子が顔をだしていた。
ザオバンが、カチン語で何か話しかけたら、ちょこちょことでてきた。
私とザオバンが、両方から手をひいて歩き出すと、子供は平気でついてきた。
私はためしに幼いころ、日曜学校でききおぼえた賛美歌を英語でうたった。
すると、どうだ。その子供が、それにあわせて歌い出したではないか。
これに力をえた私は、しっているかぎりの英語の賛美歌を、大声で歌いながら、村長の家へむかっていった。
初めは人のいない村のようだっだのに、いつのまにか三人、五人、十人と現れた村人が、私のうしろについてきた。
村長の家のまえにつくころには、五、六十人の合唱になっていた。
そこで村人らに話しかけた。
「明後日頃、日本軍の一隊が、ここを通過する。
目的は当地の地理や英印軍や重慶軍の動きを調べるだけで、あなたたちには何もしないから、安心するがよい。」
すると群集の中から、一人の男がすすみでて訊ねた。
「イングリイがとおったとき、彼らはこのようなことをいった。――
ジャパンがいまにくるぞ。命がおしければ、殺されるまえに戦え。
彼らは赤い顔と、耳までさけた口を持ち、女や子供を食う。ことにクリスチャンは一人のこらず殺す。――
これは本当のことか。」
イングリイとは、イギリス人のことである。
人食い人種から人食い人種かときかれて、私はめんくらった。そこで私は答えた。
「そのイングリイは嘘つきだ。日本人が人食い人種でないことは、ここにいるザオバンにただしてみるがいい。」
「あなたの顔は赤くないし、口も耳までさけていない。かわいらしい顔と口を持っている。
皮膚の色も目の色も、わしらと同じだ。日本人は変化の術を使うのか。」
これには、ますますあきれた。
「いや、これは本当の顔と口である。日本人は魔法をしらない。」と、脇からザオバンが話してくれた。
あとでわかったことだが、カチン族のまじない師の中には、魔法を使う者があるらしかった。
その男は、さらにたずねた。
「さっき、あなたの歌う賛美歌をきいたが、クリスチャンを殺すほどの者が、賛美歌を歌うはずがない。
これでイングリイが嘘を着いたことはわかった。あなたもクリスチャンであろう。」
「いや、自分はクリスチャンではないが、子供のころ、教会にいったことがある。
日本軍の中には、クリスチャンがたくさんいる。
ここへやってくる日本軍の隊長は、熱心なクリスチャンである。」
さっきから、じっと、聞き耳をたてていた人たちは、これをきいて、
「おーっ」と、どよめいた。
すると村長が歩みより、はっきりした正しい英語で話しかけた。
「実は私たちは、イギリス軍のライフル銃をすこし持っています。
これは英印軍が私らにくれたもので、ライフルをわたすとき、日本軍のことをこっそり調べている将校の一人が、私にこういいました。
『イギリス軍がさったあとに、日本軍がくるだろう。
私は日本を長いあいだ研究していて、日本人のことをよくしっている。彼らがくれば心配はない。
しかし、日本軍が来るまでにすこし間がある。
そのすきに、武器をもったビルマ人がおそってきて、村人に危害をくわえるかもしれない。
そのときこのライフル銃で、君ら自身を守るがよいだろう。』と。
だからこれらのライフル銃は、日本軍と戦うためでないことを誓います。持っていても、いいですか。」 |
これで私が村へ入ってきたときに、だれも手向かってこなかったわけがわかった。
カチンからライフル銃を取上げたところで、日本軍にはなんの役にもたたない。
それに、ライフル銃を取上げると、かえって彼らの反感を買うだろうと考えたから、
「日本軍に手むかいしないなら、ライフル銃は持つていてよろしい。」と、はっきり答えた。
これは、日本軍の隊長の決めることで、一等兵の私の決めることではなかったが、この場合しかたがなかった。
カレンジャンの部落民は大喜びで、つづいて、いくつかの歌を私のためにうたってきかせた。
私とザオバンは、日のおちた山道を帰ることにした。
途中は真っ暗闇だったが、部落民の三名がライフル銃をかついで、テインパイのバンガローまで送ってくれた。
3 サンプラバムヘ向って top
テインパイのバンガローでは、さらに八名の少年が挺身隊に志願した。
それに、メイレイジュリョーとあわせて、全部で十七名になった。
もう充分であるから、二人の日本の兵隊は必要がなくなった。
次の朝、私とザオバンは戦利品の馬をわけてもらい、部隊と別れて目的地のサンブラバムにむかって馬を進ませた。
お昼前にカレンジャン部落へ着いた大勢の男女が道ばたに集り、日本軍の歓迎準備で大さわぎをしていた。
清水のはいった素焼きの瓶(かめ)をならべ、テーブルの上にはバナナやパパイアが、山のようにもってある。
そしてみんなが、手に手に「日の丸」の旗をもっている。
日の丸がすごく大きいのやバカに小さいのや、いろいろだ。
それに絵の具がないのか、赤の色がいやに黄色っぽかった。
しかし、どんなにへんな日の丸の旗であろうと、日の丸の旗にはちがいない。
彼らの歓迎の気持ちには、いつわりがないのだ。
あとからくる兵隊は、さぞ大喜びするであろう。
そう思うと私はあまりのうれしさで、ひさしぶりに歌をうたった。
右手(めて)に血刀(ちがたな) 左手(ゆんで)に手(た)づな
馬上ゆたかな 美少年…… |
カレンジャンをすぎて、三キロほどいくと、思いがけない人が道ばたで、私をまっていた。
カチンの盛装をした少年の手をひいた、五十才くらいの太った女だった。
彼女は私を見るとかけよってきて、何事かをうったえた。
ザオバンの通訳で事情がわかった。
この少年は、このふきん一帯を支配する酋長の一人息子で、女はその乳母だという。
カチン族の掟(おきて)では、酋長や村長の役は代々の家の息子がつぎ、普通の人はその権力をもつことは許されない。
ところがこの領地に一人の片目の男がいて、この少年の父であった老酋長にとってかわろうと、日頃から機会をねらっていた。
英印軍が引揚げた後その片目の男はこの時とばかり、親族や金で集めた仲間とともにある晩、酋長の家をおそった。
そして家に火をつけ、老酋長をひきずりだして、猛獣や毒蛇のいるジャングルのなかへ、おいはらってしまった。 |

前の酋長の子供とその乳母――乳母は筆者に子供の世話を頼む。
|
いくら蛮族でも酋長を殺すのは大変な罪なので、自分では殺さず証拠を残さずこの世から消す方法をとったのだ。
ジャングルに追払われた酋長は、二度と再び、姿を現さなかった。
一方、少年は乳母にだかれて火のなかをくぐりぬけ、悪人どもの目を運よくのがれて、今日まで彼女がかくまっていた。
酋長がいなくなったのちも、一人息子が生きていると信じている領民たちは、片目の男が酋長になることを、承知しなかった。それでこの悪人は、やっきになって少年のゆくえをさがしまわっている。
「もうこれ以上、かくしとおせません。かわいいこの子が、殺されてしまいます。どうか、この子をつれていってください。できることなら、あなたの子にして、日本へつれていき、立派な男にしてください。」
と、乳母は泣きながらうったえた。
少年は九才だった。少年挺身隊には幼なすぎたが、捨てておけば殺されてしまう。
ザオバンも、
「少年はつれていきましょう。その片目の男はゆるせない。時間があれば私がやっつけてやるのですが、いまはそのひまがなくて残念です。」と、いった。
私は、この少年に、マイサン(私の息子という意味)という名をつけ、隊員にくわえた。
それとしって乳母は、地面にひざまずき、私とザオバンをおがんだ。
少年マイサンはその日から、私の軍隊用鞄を肩にかけ、片時も私のそばをはなれなくなった。
フーコン路とサンブラバム街道とが接するマイトンカの三叉路までくると、そこの谷間にたくさんのイギリス軍の自動車がつきおとされ、赤錆びているのが見られた。
乗用車・トラックージープ・装甲車・救急車と何十台あるやらわからない。
それよりもっと、私たちをおどろかしたのは、そこから、ずっとつづいている死体の列であった。
そのほとんどが中国兵の死体で、中にはカチン族らしいのが、中国兵と組みあったまま、白骨となっているのもあった。
中国兵の大部隊は、フーコン路をとおって、マイトレカにでて、そこからサンブラバム街道を北へむかっている。
道ばたには、石をつみかさねて二、三百人が炊事した跡がところどころにあり、行けども行けども死体の列はたえなかった。
中国軍の兵士らは食糧に困って、カチン族の食糧を奪いとろうとし、カチン族の反抗をうけて、逆にやられたものらしかった。
夕方、サンプラハムにつうじる最後の渡河点のシナンカに着いた。
今までの、どの渡河点も急流であったが、それらとはくらべものにならないほどの大変な急流であった。
私たち一行の力では、どうすることもできず、ただ、滝のような流れを見守っているばかりであった。
次の日、助けにやってきたカチン族の手をかりて、やっとの思いでシナンカの急流を渡った。
私たちはあとからくる本隊が、ぶじに渡河できるように手配してから、再び、前進を続けた。
4 緑の丘の町 top
次の日の夕方、私たちは、待ちのぞんだサンブラバムの見おろせる峰にでた。
ミッチーナを出発してから十数日の苦労をかさねたすえ、とうとうやってきたのだ。
「サンブラバムが見えたぞ。」
挺身隊員のさけぶ声に、私は急いでかけだした。
カチンの首都サンブラバムは、そこから六・四キロのところにながめられた。
「ああ、美しい。」私は思わず嘆声をあげた。
目の下の谷々をへだてて、緑の丘の斜面に真っ白な壁、真赤な屋根のバンガローの集団が、樹海にうかんだ蜃気楼のように、静かに息づいているのが見えた。
「ああ、あれが夢にまで見たサンブラバムだ。
明日こそ、最初の日本人として、私の足跡が、あの丘にしるされるのだ……。」
そう思うと今までの苦難がしのばれて、ジーンと涙がにじみでてきた。
私はすぐに、部隊へ伝令をおくった。
そしてサンブラバム突入の時期を明後日の朝ときめ、その日はなるべくサンブラバムヘちかづいた場所に宿営した。
翌日はまる一日をついやして、挺身隊を四方にだし、情報を集めることにした。
そして二日ののち、街道上に日本軍部隊が見えたという報告があったので、私たちはすぐサンプラバムをめざして出発した。
みんな緊張した顔をまっすぐ前にむけ、わきめもふらず歩いた。
足がしぜんに早くなっていった。
正午ごろ、私たちはジャングルをぬけて芝生のはえた対の上にでた。
ついにサンブラバムの真上にでたのである。丘の頂上にあるバンガローから見おろすと、町が一目に見える。
芝生の斜面には、石だたみの道が縦横に走り、二キロ平方ほどの区域に七、八十軒のバンガローがちらばっている。
わらぶき屋根のカチンの家は、ずっとむこうの丘の麓に見え、そのさきは切り立ったような、深い深い谷につづいていた。
私たちの真下には、ひときわ目立つバンガローがあり、まえの庭には花壇にかこまれた水泳プールが見え、白くぬった旗ざおがたっていた。
その左に兵舎、病院の建物がつづいている。
病院には「サンブラバム市民用および軍用病院」という大きな看板がでていた。
右下の麓が町の入口で、この町の学校の校長の家だという石づくりの、立派な洋館が見えた。
無人の町は、真昼の太陽にかがやいて、しずまりかえっていた。
突然、町の入口あたりで、耳なれた軽機関銃の杳がした。日本軍が到着する時刻だった。
谷のほうへ逃げていく二、三十人の人影が見えた。
私はプールのある一段と目立つバンガローへかけつけ、日章旗を高くふった。
銃声がやみ、銃に日章旗をむすびつけた日本兵がかけあがってくるのが見えた。
先頭に軍刀をひらめかしてくるのは隊長の窪田中尉である。
私は町の中央まで出迎えて、今までのようすを報告した。
ただちに町の掃討が行われた。
校長の家は、いかにもイギリスふうな城のように頑丈な建物であった。
入口にちかづくと、意外にも、中から女や子供が、泣きながらでてきた。
調べてみると婦人十七名、幼児九名、男子一名で合計二十七名であった。
そのうち婦人一名と幼児六名はインド人の母と子で、ほかはすべてイギリス人とビルマ人、またはイギリス人とインド人妻の混血児であった。
男一名というのは、自動車からころげおちて、頭がへんになったというつんぼの老人だった。
その人たちはみんな、ラングーン・インセン・モールメン付近の小学校の先生とその家族であった。
日本軍におわれたイギリス軍とともに、やっとの思いでここまで逃げのびてきていたのだ。
しかし、ここからさきは、象か馬にのるか、自分の足にたよるかしなければ逃げられない。
そこでイギリス軍は、この人たちを捨てていったのだ。
かわいそうに、みんな栄養失調であった。
サマビルと名のる老婦人が、代表になってこう語った。
「イギリス軍は、フォート・ヘルツヘ着いたら救助隊をよこす。
食糧をおいていくからそれまで待てと、私たちを捨てていってしまいました。
ところが、やがてやってきたのは北からの救助隊ではなくて、南から逃げてきた中国兵でした。
彼らは乱暴をはたらき、私たちの大事な食糧を、残らず奪いとってしまいました。
このままでは、私たちは、みんな飢えて死んでしまいます。
日本軍にとって、私たちは憎い敵であることはしっています。
でも、私たちは日本軍の到着をまちかねていたのです。
見殺しになさるか慈悲をおかけくださるかは、あなた方の決められることですが、どうぞ哀れな女や子供たちを、救ってください。助けてください。」
「日本軍は、軍の邪魔をしないかぎり、非戦闘員は保護します。」
ちょうどそこへ視察にやってきた隊長に、このことを話し、彼らがよけいな心配をしなくてもよいようにしてやった。
私は英印軍が使っていた家で、ちらかっている紙くずの中から、サンブラバムからフォート・ヘルツまでの地図を発見した。
本当のところ日本軍は、サンブラバムまでの地図しかなかったので、これはうれしい収獲であった。
カチン高原地帯へふみこんでから十幾日め、ミッチーナから二百十八キロ、標高千九百メートルのサンブラバムで迎えた第一夜は、谷底からわきあがる霧につつまれて、静かにふけていった。
ひさしぶりに火がともったというランプが、はるか麓の校長の家の窓に、暖かそうにまばたいていた。
5 たった一人で top
|
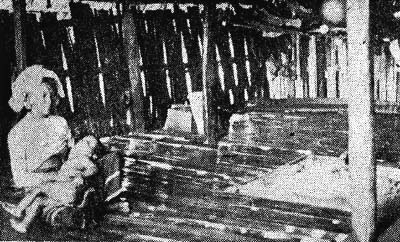
カチン族の家の内部
|

床下には豚が飼(か)われている
|
サンブラバムの周りにはちょうど七つの部落があったので、私はそれを一週間の曜日でよんだ。
ザオバンと相談して、曜日ごとに交替で村から使役の人数をだし、捨てられている死体を始末し、荒されている屋内を清掃するなど、町をきれいにするように命令した。
つまり日曜部落は日曜日に使役人をだし、月曜部落は月曜日の当番になるという具合である。
彼らは命令されたとおり、見事に彼らの町をよみがえらせた。
さて、それからまもなく、私たちの部隊――カチン高原掃討隊に引揚げの命令が下った。
しかしフォート・ヘルツ方面には、まだ数万の敵が残っている。
この敵のようすをさぐるために、誰かがここに残る必要がある、と私は考えた。
そうでないと、ビルマ全体の戦いが日本軍にとって不利になるのは、目に見えていた。
そこで私は自分一人だけ、この蛮地へ残ることを志願した。
窪田中尉は、私の身を心配してくれたが、司令部からは許しがでた。
次々に引揚げていく日本軍を見て、ザオバンたちは心細そうにしていたが、私だけは残るとしって大喜びした。
私は丘の頂上にある家を宿舎にきめた。
ここは、イギリスの統治時代に統治官がすんでいた家で、贅沢な建物だった。
建物はまた、蛮族の襲撃を考えてつくってあって、この官舎を守るように、兵舎や馬屋が官舎を囲んでたっていた。
さらによく注意してみると、目だたないように官舎と他の建物との間には、うまく谷を取入れてへだてている。
また山からひいた清水を水槽にため、そこから各室に水道管がひいてあって、しばらくの間なら、籠城できる設備になっている。
日本軍が食糧をおいていってくれなかったから、私たち総勢十八名は、食糧を自分で手にいれなければならなかった。
そこでザオバンは七つの村の村長を集め、余分の食糧をだすことを命じた。
私はそのほかに、乳のでる牝牛を一頭さがしてくるように頼んだ。
校長の家にすむ人の中に、赤ん坊をかかえて困っている人がいたからだ。
まもなく、米、ジャガイモ、玉ネギなどが、集ってきた。
牝牛も二頭きた。その乳でミイラのように痩せ衰えていた乳飲子たちは、元気な泣き声をたて始めた。
私の仕事は山ほどあった。
まず、フォート・ヘルツ方面の敵軍のようすをたえずさぐり、それを一日本軍に報告しなければならない。
また、サンブラバムの警備、自分らの食糧の入手など、いっさいがっさい、自分でしなければならない。
私は、ザオバンと相談して、次のような計画をたてた。
一、カチン族部隊の編成
二、食糧、兵器、弾薬の収集
三、後方の日本軍との連絡
この計画は、すぐ実行にうつされた。
ザオバンがカチン語でかき、私が署名した召集令状が、近くの村々にくばられた。
手に手に英印軍のライフル銃をもち、肩に弾帯をかけたカチン族が、続々とサンブラバムに集り、召集二日めには総員百四十二名、小銃百六十七丁、自動小銃三丁、水冷式重機関銃四ちょう、速射砲一門、同じく弾丸十三発の部隊ができあがった。
重機関銃と速射砲は、私の部隊がおいていってくれた戦利品であった。
彼らはすべて、英印軍に三年以上もつとめた経験をもつ者ばかりだった。
中には、英印軍が日本軍におわれて逃げていくときに脱走した者もだいぶいたらしい。
私は彼らを三個小隊にわけ、英印軍でサージャント(軍曹)であった男を小隊長に任命し、兵舎の前の庭で部隊の編成式を行った。
小隊長らは部隊のまえで、私のあたえた指揮刀に接吻して忠誠をちかった。
それらの指揮刀は、ザオパンがイギリス役人の家から見つけだしてきたものだった。 |

新たに編成されたカチン族部隊。
彼らは撤退した英印軍の経験があった。
|
「アイズ・ライト。(かしら・右!)」
いろいろの服装をした裸足の兵隊の目が、軍曹の英語の号令にしたがって、いっせいに私に向けられる。
英印軍の捨てていった軍馬二頭を、鞍とともに手にいれたので、私とザオパンとは馬上で彼らの敬礼をうけた。
式につづいて、戦闘演習が行われた。
無帽・腰布・裸足という奇妙な兵隊たちだったが、行動はすばやくキビキビしていた。
戦闘隊形をくずさずに緑の丘に展開して、攻撃したり守ったりしている有様は、さすがに英印軍のビルマ・ライフル銃隊につとめていただけあって、見事なものだった。
とくに私が感心したのは、日本軍でも困難とされている隊と隊との横の連絡が、実によく訓練されていることだった。
私は一度で気にいってしまった。
これだけの大世帯になったので、食糧集めは緊急な仕事となった。
次の日に、さっそく一個小隊をトライアングル地方へやることにした。
top
**************************************** |