|
****************************************
Home 韓国 満州 ベトナム フィリピン マレーシア 台湾 グアム・サイパン
観光コースではない満州
瀋陽・長春・ハルピン・大連・旅順
(文=小林慶二、写真=福井理文 高文研 2005年刊)
1 はじめに
2 おわりに
3 主な参考文献
別ページ
一章 瀋陽(奉天)・撫順・鞍山
二章 長春(新亰)・吉林・延吉・龍井・図們
三章 ハルビン・佳木斯・大慶
四章 大連・旅順 |
小林慶二(こばやし・けいじ)東京に生まれる。東京大学経済学部卒。 1961年、朝日新聞社入社、『朝日ジャーナル』編集部、カイロ支局長、外報部次長をへて、1981年よりソウル支局長。その後、調査研究室主任研究員、編集委員、『AERA』編集部をへて、95年より九州国際大学国際商学部教授などを歴任した。
著書:『新装版・観光コースでない韓国』(高文研)、『新韓国地図』『ふれあい地球社会』(以上、朝日新聞社)。
『金泳三』(原書房)など。
福井理文(ふくい・りぶん)1957年、東京に生まれる。東京理科大学中退、現代写真研究所卒。フリーランス・カメラマン。著書:『高校生紳士録』(私家版)、「東京の山里に生きる・中学生の四季」『観光コースでない東京』『新装版・観光コースでない韓国』 |
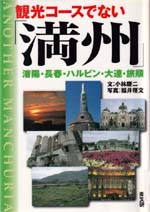
|
1 はじめに
日中戦争からアジア太平洋戦争の時代にかけ、東京の下町で路地裏を駆け回りながら、母の経営する喫茶店の電蓄(電気蓄音機)から聞こえて来る流行歌を“子守歌”として育った私にとり、歌詞によく使われた「赤い夕日の満州」は漠然とした憧れの対象だった。
教科書だったか記憶は定かではないが、「コーリャン刈って広いなあ どっちを見てもひろいなあ」という児童詩の一節も、私の夢をくすぐった。
「狭い日本にゃ住み飽きた、支那には四億の民がいる」という歌を年上の子供から教わり、想像は次第にふくらんでいった。
だが、敗戦と同時にこうした歌は聞こえて来なくなった。
そして「満州」は私の記憶の片隅で冬眠に入った。
その「満州」が再び私の意識のなかに戻って来たのは、新聞社を定年前に辞め、大学に赴任してからである。
大学で「アジア概論」を担当した私は、授業の中心に「日中・日韓関係」と「歴史認識問題」を据えた。
この二項目を十分に理解させない限り、アジアで通用する人材、アジアから信頼される日本人の育成は不可能だと考えたからである。
幸い私か勤務した大学は中国の大連と瀋陽に姉妹校があり、長春の吉林大学には東京で参加していた研究会のメンバーである友人がいて、中国東北三省(遼寧省・吉林省・黒竜江省=旧満州地域)には行く機会が多かった。
日中関係を調べていくにつれ、私は中国人がいう“偽満”(ウエイマン)、つまり「満州国」の建国と崩壊に至る過程が戦前の日本の岐路になっていることに気づいた。
「満州」に関する書籍、資料は多い。
優に数千点を超える。 |
中国東北地域全図
 |
片っ端から乱読し、現地での取材を続けているうちに、専門書になればなるほど「中国側」「日本側」あるいは「会社側」など一定の立場に立って書かれている書籍が多いことがわかった。
そこで私は、中国専門家でないことを承知で、私なりに“客観的”でわかりやすい「満州」を書いてみたいと考え、高文研の「観光コースでない」シリーズに「満州編」を入れることを提案した。八年ほど前のことである。
だが、筆は一向に進まなかった。「満州」は広大で取材に時間がかかり、資料は山ほどある。
満足できるまで調査するにはどれだけ時間がかかるかわからない。
紙数の関係もあり、短い枚数でまとめるには大胆に資料の取捨選択をしなければならない。
その上、私は大学で学部長二期、図書館長一年、初代の広報部長などをつとめ、雑用に追われていた。
二〇〇四年に教授は辞任したものの、同時に「アジア共生学会」を立ち上げたので、相変わらず調査・執筆に十分な時間を割けない。
そうした不十分な条件のなかで、あえてこの本を書き上げたのは、今年(二〇〇五年)が、日本が「満州」を戦場にロシアと戦った日露戦争終結百周年にあたり、読者の「満州」に対する関心が高まるだろうとの予測、平和憲法改正のきな臭い動きが出てきた今日、“いつか来た道”を辿らないためにも「満州」の失敗から何かを学んでほしいと考えたからである。
正直に言って、この本でその意図を十分伝えることができたとは思っていない。
多分に“見切り発車”的な要素が多い。
だが、私が、いや日本人の多くが夢に見た「満州」の実態が、現地の人々にとり、どれほど過酷なものだったかは、ご理解いただけると期待している。
ある中国人学究は「“偽満”(ウエイマン)こそ日中関係の基盤です」と言っていた。
日本のアジア政策が行き詰まり、再軍備への妖しげな兆しが見え始めた昨今、この本がそれを考え直す小さなきっかけになれば、望外な幸せである。
〈注〉近年、中国では開発の進展がめざましく、とくに東北地方では年ごとに景観が変わりつつあります。
そのため、本書で取上げた歴史的建造物が撤去あるいは改築されているケースも見られます。
その点、読者のご了承をお願いします。 (高文研編集部)
2 おわりに top
太平洋戦争でフィリピンを奪還したマッカーサーが司令部を置いたマニラ・ホテルで有名な「マニラ湾の夕日」を眺めたことがある。
上空の薄雲を深紅に染めながら、ゆっくりと沈んでいく夕日は、いかにも大多数の国民がキリスト教徒の国の夕日らしい安らぎを感じさせた。
ボーイスカウトで歌った「今日の業(わざ)をなしおえて、心軽く安すらえば」(ドボルザーク作曲「新世界より」)という歌詞を想い出した。
だが、満州の夕日は違う。大地を真っ赤に染めギラギラとした太陽が沈んでゆくのだという。
まるで明日の活動のエネルギーを保証し、「明日もがんばれよ」と励ますように。
残念ながら一〇回を超える満州取材では、そうした素睛らしい「夕日」を見る機会には恵まれなかったが、「真っ赤な満州の夕日」が日本人、とりわけ冷夏に悩まされた東北の開拓民には素晴らしい自然の恵みと映ったであろうことは十分想像できる。
その豊かな自然と資源、広大な土地を持つ満州を手に入れるため、張作霖爆殺事件(一九二八年)、満州事変(一九三一年)は引起こされた。
最終目標は米国に勝ち、世界を支配することだった。
ちょっと冷静に考えれば、彼我の経済力の差、資源の有無から、勝つことは不可能だとわかるはずなのに、政府と軍部は破滅への道を突っ走った。
石橋湛山の「武力で守らねば暮らせぬような土地へ進出して何かできる」という批判、「満州国は真に五族が平等でなければならない」という石原莞爾の主張は退けられた。
この本を書きながら、なぜ日本はそのような破滅への道を辿ったのかを、何回も考えた。
マスコミの責任も大きい。
日露戦争が、世界中を駆け回って集めた借金で武器を買い、ようやく勝った戦争であることを正確に国民に知らせておけば、その後の軍部の独走は防げたのではないか。
旅順虐殺を正しく報道していれば、南京虐殺は起こらなかったかもしれない、などなど。
中国人は別として、満州国で最大の犠牲者は開拓農民と言われる。
ソ連軍が満州になだれ込んで来た時、皇軍は彼らを置き去りにしたまま朝鮮国境へ退き、開拓民を見殺しにした。
「国体護持」のためだというが、国民を守らない「国体護持」とは一体なんなのか。
満州国は差別の国だった。給料はもちろん食料の配給にさえ、民族によって差をつけた。それで中国人の支持が得られると考えたとしたら、それは民族蔑視と言えるだろう。
中国や韓国に対する日本政府の最近の態度は、その蔑視観を引きずっているように映る。
敗戦から六〇年、今日本は大きな岐路に立っているように思える。
隣国中国、韓国との関係は悪化し、アジアでは孤立を深めている。
それに反発してか、平和憲法を見直す動きも出てきた。日本の侵略を受けたアジア諸国が、日本が経済力もふくめ力で押し切る政策へ、転換する兆しと見ても不思議はない。
現在、日本の置かれている国際環境は、私には満州国建国前夜とよく似ているように思える。
唯一の違いは大国・米国の庇護下にあることだろう。
だが私は、友人である韓国の碩学、李御寧・元梨花女子大教授がかって語った言葉が忘れられない。
日本は隣国の韓国や中国と仲良くできなければ、世界で孤立しますよ。
今日本がどこかの国 から批判された場合、本気で日本を庇(かば)おうとする国があると思いますか。
どこもありません。
せいぜいアメリカがリップ・サービスをするぐらいでしょうが、そのアメリカは自国の利害に反すれば、手を差しのべないでしょう。 |
日本の置かれている立場は、一般国民が考えている以上に深刻だと思う。
こうした時こそ過去の過ちから学び、その教訓を生かして軌道修正をすべすでぱないだろうか。
かって満州で起こったことは、そのための最適の教材と言えるだろう。
最後に、一向に筆の進まない私を叱咤激励してくださった梅田社長をはじめとする高文研のみなさん、カメラマンの福井君、中国から取材に協力してくださった金赫さんなど中国の友人に心から感謝したい。
二〇〇五年一〇月 小林慶二
3 主な参考文献 top
top
****************************************
|