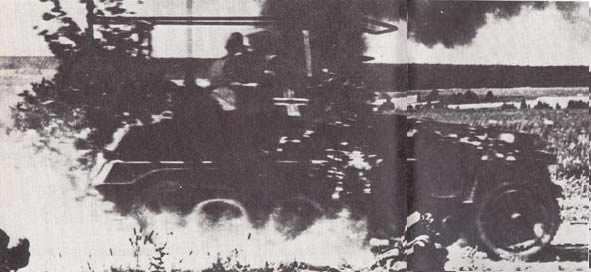|
****************************************
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
市の外郭防衛線突破される(スターリングラード4)
ドイツ軍の爆撃で発生した火災は、一晩中燃えつづけ、翌朝太陽がのぼったときには、あたり一面が焦土と化していた。
一方、街のなかに爆弾が一発おとされれば、それだけ、トラクター工場の北にいるフェクレンコの部隊におとされる爆弾が一発へったことになり、将兵たちは、この余裕を活用して、防備を堅固にすることができたのである。
3 “モロトフのカクテル”で対抗 top
北方で阻止されたドイツ第六軍は、今度は西方から突入をくわだてた。
八月二十五日の朝霧にかくれて、二五両の戦車の一群と歩兵一個師団がカラチの北方でドン川を渡り、スターリングラードの中央部に向って前進を開始した。
これにたいしてスターリングラード方面軍のエレメンコの代理コバレンコ少将の指揮する戦車一個旅団(第百六十九旅団)と歩兵一個師団(第三十五親衛師団)からなる部隊が、立ち向ってこれを食い止めた。この部隊は、さらに進んで、包囲されていた第八十七師団をすくいだした。
この師団のシベリアと極東方面からきた三三人の将兵は、ソ連軍の勇敢な兵士たちと同じく、包囲した七〇両の戦車をもつドイツ軍部隊にたいして、二日間も持ち堪え、戦車二七両を撃破するという勇敢な戦いぶりをみせた。
彼らは、世界中に“モロトフのカクテル”として知られている即製の武器を、うまく使ったのであった。
この武器をソ連の著述家たちは[火炎びん」と味けない表現をしでいる。
この部隊の兵士たちの大部分は、ここで始めて実戦に参加したのであったが、損害はわずか負傷一人であった。
これは、いままでのソ連軍の戦いぶりからすると、全く異例なことである。
一般的にいえば、ソ連軍の損害は不必要に多く、それは小部隊の戦術が、基本的にまずいためであった。
ともかく、この部隊の将兵の戦いぶりは、このあとスターリングラードで戦われた戦闘の見本のようなものであった。
4 エレメンコの反撃ならず top
しばらくでもドイツ軍をスターリングラードの郊外で食い止めたので、エレメンコの考えは、待ち望んでいた反撃にうつっていった。
エレメンコのねらいは、ドイツ軍第十四機甲軍団のボルガ川まで突きだしている回廊を奪回し、できればこの部隊を撃破することにあった。
そこで、ドイツ軍の後方補結線にたいして、北から第二十一軍と第一親衛軍とで攻撃することにした。
二十四日、はやくも第二十一軍の二個師団は、セラフィモビッチとクレツカヤでドイツ軍陣地に偵察攻撃を開始し、第一親衛軍の一部も、ドン川の右岸に橋頭堡をひろげた。
しかし、これに使用された兵力は、第十四機甲軍団の背後を遮断できるほど強力ではなかった。
二十五日、第六十二軍の数個師団がセラフィモビッチの西の方で攻撃を開始し、南に動いてドン川にべつの橋頭堡を占領した。
ゴバレンコ少将の部隊は、これまでに歩兵二個師団と戦車部隊が増援されており、二十六日には、攻勢にでて、ドイツ軍の高地拠点を奪取しようとしたが、砲兵の支援がたりず、攻撃も協同動作がまずく、それにドイツ空軍の威力が非常に強かったため、完全に失敗してしまった。
ついでゴロジシチェとグムラク付近で、シュテフネフ中将が、第六十二軍からえらびだした部隊で攻撃に移った。
この攻撃によって、市の北西方から突入しようとするドイツ軍の企図をしばらく阻止できたが、これもそれ以上のことはできず、ドイツ第六軍の北翼をたたこうというエレメンコの企図は、兵力の不足のため放棄せざるをえなくなった。
しかし、この反撃が、成功の一歩てまえまできていたことを、エレメンコが知ったのは、戦後になってからである。
ドイツ第十四機甲軍団長のビッテルスハイム中将は、ボルガの川岸に孤立して空中補給だけにたよっているユーベの第十六機甲師団の運命を心配して、これを撤退させようと決心したのだが、B軍集団司令官のワイクス大将に制止された、というのが実情であった。
|

ドイツ軍歩兵、スターリングラード郊外へ進出
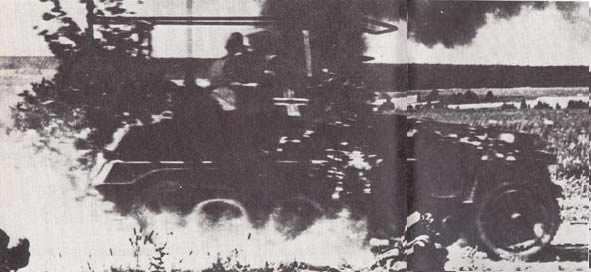
ボルガ川に達したドイツ軍装甲車
|
5 ドイツ第四機甲軍南西地区ねらう top
さて、今度は、新しい脅威が南の地区に起ってきた。
この方面のドイツ第四機甲軍は、八月十九日いらいツンドトポ付近でスターリングラード防衛線の南の一角を突破しようと努力していたが、効果もあがらず損害は甚大で、ことに第二十四機甲師団は、手いたい打撃をうけた。
ソ連軍が守備するボルガ川岸のベケトフカとクラスノアルメイスク間にある高地の防御陣地は、堅固で、うまくつくられており、これに第六十四軍の数個師団が戦車に支援されて配備されていた。
そこで、第四機甲軍は、この攻撃を中止した。
そして、ちょうどエレメンコがスターリングラードの北方、北西方への反撃に懸命になっているころ、第四機甲軍の戦車と自動車化歩兵部隊を、この南の地区から密かに南西の地区に移動して、アブガネロポ付近に集結した。
ここから八月二十九日の早朝、第六十四軍の第百二十六師団にたいして、攻撃を開始した。第四機甲軍ホト司令官の意図は、第六十四軍の中央部にクサビをうちこみ、それから右旋回をして、ベケトフカとクラスノアルメイスク間のソ連軍陣地の背後に進出しようというのである。
こうして、正面攻撃では奪取できなかった拠点を避けてとおり、ボルガ川の岸とスターリングラードの南の高地を占領して、第六十四軍の左翼の部隊を分断、包囲しようというのである。
このドイツ軍の攻撃は、思ったよりもうまく進んだ。
さらに、ハウエンシルド将軍の第二十四機甲師団は、第四航空軍のJu87急降下爆撃機の有効な協力をうけて、ガブリロフカ付近のソ連軍戦線を突破することに成功し、第六十二軍と第六十四軍の背後地域に侵入した。
戦況は、たちまちかわった。
ドイツ軍は第六十四軍の左翼を分断、撃破するばかりでなく、もっと大きいエモノ――第六十四軍の“右翼”――をつかまえることが可能になってきた。
それに、第六十二軍の全部を捕捉できるかもしれない。
必要なのは、第四機甲軍が予定した右旋回をやめて北進をつづけ、第六軍が手をつなぐように南に向って攻撃することであった。
この動きが成功すれば、スターリングラードは陥落するかもしれない。
ソ連軍には、これを防ぐ兵力がないからである。
そのためにもドイツB軍集団は、迅速に行動しなければならない。
だがエレメンコは、すでにこの動きに感づいていた。
6 南北から包囲態勢 top
B軍集団司令官ワイクスは、新しい情勢をみてとって、ただちに動いた。八月三十日正午、彼は第六軍に命令を発した。
「いまや万事は、第六軍が可能な最大の兵力を集中し……進路を南にとって攻勢をとり……第四機甲軍と協力して、スターリングラード西方の敵を撃破することにかかっている」
ワイクスは翌日、第六軍のパウルスに、はやく行動にうつるように催促した。
「この両軍がすみやかに手をつなぐことが、たいせつだ。それからあと、市の中心部に侵入するのだ」
しかしパウルスは、うごこうとはしなかった。エレメンコの北方地区での反撃が、ピフアルスハイムとパウルスに、戦線の北翼が危険な情勢になる、と心配させたのであった。
パウルスは、もし機甲部隊を南におくれば、北翼が崩壊するかもしれないと考えたのである。
九月二日になって、第六軍にたいするソ連軍の圧力が、ようやく衰えた。
そこでパウルスは、すぐに機甲部隊を、ホトの第四機甲軍と手をつなぐように派遣した。
九月三日には、ザイトリッツの第五十一軍団の歩兵部隊も、第四機甲軍の先頭部隊と接触した。
きれいな包囲作戦が行われた。
7 ソ連軍、幸運の肩すかし top
だが、一つだけまずいことがあった。ソ連軍は、今度もまた、脱出してしまっていた。どうしたのだろうか。
エレメンコは、ドイツ第四機甲軍が第六十四軍の“左翼”をねらっているとは知らなかった。
そのために、ドイツ軍が決意を変更する“以前”に、その手を読んだことになってしまった。
だから、B軍集団と第四機甲軍が計画を変更し、北方にむかう決意をしたときには、スターリングラード方面軍の司令部は、すでに、やつぎばやに命令をくだしていた。
つまり、スターリングラードの外郭防衛線を放棄したのである。
そして、第六十四軍の右翼は、八月二十九日から三十日にかけての夜に撤退を開始し、二個師団(第二十九、第二百四)は軍予備として引きあげられた。
第六十二軍は、翌日の夜、戦場を離れて、第六十四軍の北方で中部防衛線の配置についたのであった。
ソ連軍にとって、たしかにこれは勝利ではない。むしろ“ダンケルク”であった。
いまや市の外郭はなくなり、ドイツ軍はいたるところからスターリンダラードに、激しくせまることになったからである。
しかしエレメンコは、早とちりの楽天主義と、あと知恵をはたらかすという奇妙な組みあわせで、彼の部隊の主力を救うことができたのであった。
彼の反撃は、全般的には失敗ではあったが、ただ一つだけ、八月三十日から九月二日までのたいせつな数日間、パウルスの軍をクギづけにする反撃で、成功したのである。
これで、第六十二軍と第六十四軍は、生きのびることができた。
だが、あとどれくらい耐えられるか、今度も、きわどい戦いであった。
ドイツ軍が、南部地区の戦線であらたに攻撃を開始したので、九月二日には、中部防衛線から市の内部の防衛地帯に向って、すぐに撤退しなければならないハメになってしまった。
8 ボルガ川の補給ストップ top
スターリングラードの市街は、おそるべき破壊の姿をみせていた。
八月二十三日いらい連続して空襲をうけており、九月二日の爆撃も、とくに苛烈なものであった。
燃えあがるスターリングラードの大火は、はるかとおくの草原からも望見できた。
軍事的見地からみて、さらにソ連軍をくるしめたのは、ボルガ川の渡船、いまやソ連軍にのこされた唯一の補結路が、たえず航空攻撃と砲撃にさらされていることであった。
夜になると、ドイツ軍は、照明弾で川面を照らし続けた。
すでに、昼間の渡船がほとんど不可能となっているソ連軍の苦境は、増大するばかりであった。
第六十二軍と第六十四軍は、七月中旬いらい、たえまなく戦ってきた。
だから九月のはじめごろには、当然、その兵力も兵器弾薬も不足していた。
それなのに、つぎの戦闘――内部防衛線での戦い――は、もう開始されようとしていたのだ。
top
**************************************** |