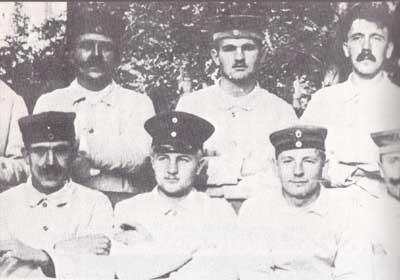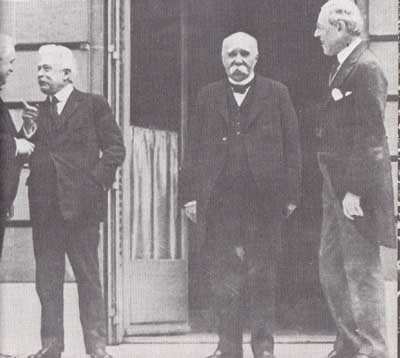|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
2 ベルサイユ体制に反発
ヒトラーは、一九一三年〔大正二年〕の春にウィーンをはなれた。
このころまで、胃をわるくしていたが、これはまさしく、治療していない梅毒の初期の症状であった。
彼も当時、ウィーン市内に広まっていた反ユダヤ感情のとりこになり、ユダヤ人を嫌うようになっていた。
1 ヒトラーの反ユダヤ主義 top
ヒトラーの反ユダヤ主義は、病気をうつしたユダヤ人売春婦ハンナーにたいする、憎しみから生れたにすぎない、と結論するのは、あまりにもこじつけすぎるかもしれない。
このような推論をするのには、二つの前提が必要だ。
一つは、ハンナーがヒトラーと性交渉をもった唯一の女性だった、ということ――とてもそうとは考えられない――もう一つは、当時、この病気にかかっていたことに気がついていたということ――そのようなことはありえなかった――である。
もちろん、時が経つにつれ、ヒトラーも、この病気に気がつき、シュピートホフのような専門家や、モレルのようなあやしげな医者の治療をうけていたのである。
また、ユダヤ人にたいする憎悪の根が、個人的な復讐心からふくれあがっていたことも、確かである。
ヒトラーは執念深い男であった。
しかし、一九一二年には、たんに反ユダヤ主義に夢中になっていただけで、それ以上に独創的な考えをもっていたわけではなさそうである。
当時、ウィーンには反ユダヤ感情が充満しており、おびただしい数の反ユダヤ的な書物やパンフレットが発行されていた。 そのいくつかはポルノ〔わいせつ文書〕調で、残りは気違いじみたデタラメの攻撃文書ばかりで、すべて無分別で侮辱的なものだった。
あまりのドギツさに、ヒトラーも驚くほどだった。
「私は、ユダヤ人のなかに、ただ宗教の相違しかみていなかった。
だから人間的寛容さからいって、ユダヤ人が異なった信仰をもつという理由だけで、攻撃されなければならない、という考え方には反対だった……
ウィーンの反ユダヤ的新間にみられる論調は、大国民としての文化的伝統に相応しくないと思っていた」〔『わが闘争』〕
しかし、やがてヒトラーは、このようなドギツさに驚かなくなったばかりか、ユダヤ人にたいして、激しい憎悪の念を抱くようになった。
2 ユダヤ文化を憎悪 top
「ユダヤ人が新聞、芸術、文学、演劇など各種の文化的活動のなかに入り込んでいるのを発見したとき、私の目に映ったのは、ユダヤ人の罪悪の深さであった。
わいせつ文学、イカモノ芸術、デタラメな演劇は、十中八、九、ユダヤ人の罪として、告発しなければならない。
私はまた、ユダヤ人が一人もいないところでは、とくに文化の面で、不潔さが全くなかったことにも気がついた」
こうした驚くべき発見について、ヒトラーは『わが闘争』のなかで、使い古しの文句でこう書いている。
「ユダヤ人が社会民主主義の指導者だと気がついたとき、私は、誤りをさとった。
長いあいだ心の中にわだかまっていた葛藤に終止符をうつことができた」
ヒトラーは、迷いからさめ、胸のつかえが急におりたように感じた。
ついに、憎悪の念をぶつけるべき相手をみつけたのである。
そのうえ、ヒトラーは、自分の政治観にこの人種的憎悪をもちこむならば、自分の考え方や性格にピッタリするということもさとったのである。
リンツの実科学校にかよっていたころ、大きな影響をうけた“汎ゲルマン主義”思想が、ヒトラーの身体のなかに音をたてて流れだした。 |

ポートレート:1933年に撮影されたヒトラーお気に入りの写真

アドルフ・ヒトラー伍長(右):ヒトラーは第一次大戦に参加し、
鉄十字章を二回授与され、伍長に昇進した
|
3 ゲルマン民族の救済者自負 top
こうした激しい思想のウズのなかから、みすがらをアーリア人種、とくにゲルマン民族の救済者だと思い込むようになり、いたるところで、この確信をぶちまくった。
それは、およそ吐きけをもよおさせるような演説であったが、ヒトラーは一九三八年四月九日、ウィーンで、つぎのような演説をしている。
「この国〔オーストリア〕から、一人の少年をドイツ帝国におくり、育てあげ、祖国をドイツ帝国へ導くことができるような民族の指導者に仕たてあげたのは、神の意思であると信じている……
このような神の恩寵は、私にあたえられた……
祖国をドイツ帝国に統合させるためである……
ドイツ国民はすべて、オーストリア人を受け入れる時と手段をわきまえつつ、この奇跡をもたらした全能者の前にひれふすであろう」
これこそ、ヒトラーの誇大妄想の最たるものであった。
しかし、一九一二年に“救済者”の卵だった男を、一九三八年の誇大妄想狂の総統に仕立てあげるのに、全能者の奇跡はいらなかった。
世の中に才能を認められずに、世をスネていた精神不安定な男、しかも肉体は梅毒の破壊的な活動にさいなまれていた男、ヒトラーの周囲をとりまく情勢は、ベルサイユ条約〔一九一九年に調印された第一次大戦の講和条約〕の調印という厳しい現実にあえいでいた。
“救済者”が登場するお膳立ては、すべて整っていたのである。
一九一三年、ヒトラーはオーストリア軍への徴兵を拒否した。
理由は、薄汚いチェコ系ユダヤ人や、ハプスブルク王朝の残りカスに奉仕したくなかったからだ。
警察は、彼をしつこく追跡し、一九一四年一月、ミュンヘンで逮捕した。
ここで身体検査をうけることを命じられたが、ヒトラーの言によれば“不健康と一般的衰弱”との理由で兵役を免除されたのである。
ヒトラーはさらに、一般的衰弱の原因は「芸術家としてわずかな収入しかえられなかったので、栄養失調になったのだ」と説明している。
しかし、彼は一九三八年、ゲシュタポにたいし、このときの身体検査の記録を見つけだし、すべて破棄するように命じた。
一九一四年に、オーストリア軍から入隊を免除された理由がなんであったかはともかく、同年八月七日、ヒトラーは志願兵として入隊し、第十六ババリア予備歩兵連隊に配属された。
5 キール軍港の反乱 top
革命をよびかけるこれらの水兵は、キール〔バルト海にのぞむドイツの軍港〕の反乱兵の分派にすぎなかったのである。
キールの反乱兵たちは、敗色濃厚になったのに、イチかバチかの攻撃を命じられて、これに反抗していたのであった。
〔第一次大戦中、ドイツ海軍は、イギリス海軍に制海権を握られたため、あまり活躍できなかったのであるが、戦争末期になって、捨て身の出撃を計画し、出動命令をだしたが、水兵たちがこれに反抗した。
この反乱は、まず、ドイツ北部の軍港ウィルヘルムスハーフェンではじまり、キール軍港に飛び火した。
一九一八年十一月四日、キール軍港の水兵たちは、無謀な出動命令に反抗し軍艦などを占拠した。
この動きに、キールの労働者たちがゼネストで呼応し「労兵協議会」を結成した。
この反乱は、敗戦後ドイツ全土に広まった革命運動の口火となったもので、ベルリン革命運動やウィルヘルム二世の退位、共和制、休戦へと展開していった〕
6 敗戦の衝撃で政治家に top
ともかく、このようなことは、ヒトラーの病的偏見の一例といえよう。
彼は、こうしたデタラメな言葉をつらねて、自分は視力が回復したとか、自分はドイツが降伏したとは信じられなかったなどといっている。
「私は、よろめき、つまずきながら、自分の病室にもどり、ズキズキいたむ頭を毛布と枕のあいだにうずめた……
すべてが無駄だった。すべての犠牲と労苦はむなしくなった。
何ヵ月も何ヵ月も続く飢えと渇き。
戦場では、死の恐怖が、我々の魂をつかんでいたにもかかわらず、我々は自分の持ち場にしがみついた。
だが、これもすべてむなしいものとなった」
まだまだ多くの自己憐哀の物語が続くが、これは反面、復讐心にみちたものでもあった。
『わが闘争』は、こうしたヒトラーの性格とはべつに、ただ一つ重要な文句をしるしている。
「そこで、私は政洽家になろうと決心した」
確かに、ドイツ国民はすべて、ドイツの勝利は目前にあると信じていたので、ドイツが降伏することは大きなショックであった。ヒトラーもまた例外ではなかった。
一九一八年十月五日、ドイツは正式に和平交渉をもとめる覚書きを、米大統領ウッドロー・ウィルソンのもとにおくった。ウィルソンは、彼がすでに米国議会での演説で提示した条件で、和平の話しあいに応じる用意があるかどうか、をドイツに問いあわせてきていた。
7 ウィルソンの平和14原則 top
ウィルソンは、議会演説で、有名な一四ヵ条の平和原則を提案していたのである。
〔米大統領ウィルソンは、一九一八年一月八日、米議会で、一四ヵ条からなる平和原則を提唱していた。
これは、民族自決、無併合・無賠償、海洋の自由、秘密外交の排斥、関税障害の撤廃、軍備縮小、国際連盟の結成などをとなえた理想主義的な色彩の強いものであった。
一九一七年十一月のロシア革命で生れたソビエト革命政権も、民族自決などの点では、ウィルソンの提案とほとんど同じことを提唱していた〕
ドイツはこれを認め、まずドイツとアメリカのあいだで「和平交渉は、ウィルソンの提案にもとづいておこなう」との合意に達した。
これは、連合国諸国も、受入なければならないことになっていた。
しかし、ウィルソンの提案は、講和条約を討議する基礎としては不安定なものだった。
他の連合諸国にしてみれば、アメリカがおさきばしりをして、ドイツとの和平交渉の原則をきめてしまって、なんの発言も許されなかったことは、きわめて不満であった。
このため、これらの連合諸国は、ウィルソンの和平の“条件”を耳にしたとき、けっしてこれを受入れようとはしなかった。
フランスのクレマンソー首相、イギリスのロイド・ジョージ首相、イタリアのソンニーノ外相らは、一四ヵ条の一つ一つをあれこれとひねくりまわした。
そして英仏伊三国を中心に連合諸国は、自国の利益をえようと、一四ヵ条の修正をもとめたのである。
これには、それなりの理由もあったのだが“ごりっぱな”理由がおおかった。
しかし、連合諸国の修正要求にたいして、アメリカはかたくなに同意しなかった。
連合諸国としては、ウィルソンの一四ヵ条の原則を“そっくり”受入るか、さもなければ、ドイツと個別に講和をむすぶか二者択一をせまられたのである。
リチャード・M・ワットは『国王たちの死』のなかで、つぎのようにのべている。
「それは爆弾がおちてきたようなものだった。
ロイド・ジョージもクレマンソーも、休戦を拒否してまで、この無意味な戦争をつづけていくわけにはいかなかった。
もし、英仏二大国が一四ヵ条の提案を拒否したならば「海洋の自由」の原則や「秘密外交の排斥」という原則に従いたくないのだろうとカンぐられ、世界中の世論のフクロだたきにあう恐れがあった。
このためロイド・ジョージとクレマンソーは、身動きのとれない立場に立たされていた」
8 ベルサイユ条約調印 top
今度は、連合国側が降伏する番になった。
連合諸国は、ウィルソンの一四ヵ条を受入れ、一九一八年十一月十一日、ドイツと休戦協定をむすんだ。
これによって、ベルサイユ講和会議のドアが開かれることになった。
ベルサイユ講和条約は、五ヵ月にわたる白熱した論議のすえ調印されたのであるが、この会議と条約の悲劇性については、いくたの書物にくわしくのべられている。
いま、その要点だけをとりあげていえば、ウィルソンが提案し、ドイツが受諾した一四ヵ条の原則は、結局、わずか四条項しか条約に取入れられなかったのである。
〔第一次大戦の講和会議は一九一九年一月十八日から、パリちかくのベルサイユ宮殿で開かれた。
この会議の基本原則となったウィルソンの提案は連合諸国の政治的利害のために、国際連盟の結成以外ほとんど実現されなかった。
このため「民族自決」の条項は、アルザス・ロレーヌをフランスに、西プロシア、ポズナュ地方をポーランドに割譲するなどの結果となり、ドイツは約五万七〇〇〇平方キロの領土と六五〇万の人口を失うことになった。
また、アフリカ、アジアなどのドイツ植民地は没収された。
一方、軍備の制限もきびしく、陸軍一〇万人、海軍一万五〇〇〇人におさえられ、航空機、潜水艦などの保有を禁止された。
そのうえ、ドイツは一三二〇億金マルクという“天文学的”な額の賠償を要求されたのである。
このように、ベルサイユ講和条約は、ドイツにとって、苛酷な犠牲を強要したのである〕
敗戦国ドイツは、ウィルソンの平和原則にもとづいて、連合国との休戦協定に署名していたのだが、いまやこの精神はむざんにもねじまげられてしまった。
五ヵ月間の論議のあいだ、各国はしんらつさ、貪欲さ、自己満足的な復讐心をむきだしにしていた。
戦争で多くの犠牲をだした戦勝国としては無理からぬ面もあったろうが、このような態度はたとえ、遠い先のことであるとしても、将来に争いの“タネ”を残すだけのことであった。 |
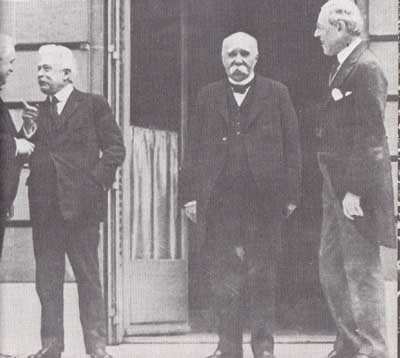
1919年ベルサイユ講和会議に出席した列強首脳:左から
ロイド・ジョージ(英)、オルランド(伊)、クレマンソー(仏)、ウィルソン(米)

プロペラはたきつけに:ベルサイユ条約はドイツの軍事力を警戒して、き
ぴしい制限をくわえた。プロペラのない飛行機で飛べというのだろうか
|
9 苛酷な条約内容 top
ベルサイユ講和会議には、三二ヵ国から特命全権大使が参加したが、ケインズ卿〔英国の経済学者、一八八三〜一九四六年〕はつぎのようにのべている。
「戦勝国にとって、将来、ヨーロッパがどうなるかということは、どうでもよい問題であった。
つまり、暮らしにたいする不安は全くなかったのだ。
このため主な関心は、良かれ悪しかれ、国境とか国籍、勢力均衡、勢力拡大、強大で危険なドイツを永久に弱体化すること、復讐、支払い不可能な財政負担〔賠償〕の要求などにむけられていたのである」
またイタリアのニッチ首相は、このベルサイユ条約を非難して、のちにつぎのような意見をのべている。
これは、近代史上おそるべき先例として永久に記録されるであろう。
いままでの伝統とあらゆる先例に反して、会議中、敗戦国ドイツの代表は一言も発言を許されなかった。
ドイツ代表にとって、祖国は疲弊荒廃し、飢餓と革命の脅威にさらされ、調印どころではなかったのだが、この条約に調印する以外に道はなかった。
教会の古い掟〔おきて〕では、たとえ悪魔でも言い分をきいてやらなければならないとされていた。
しかし、国際連盟の設立を提唱した新しいデモクラシー〔民主主義〕は、暗黒の中世時代ですら神聖な権利として認められていた“被告”の発言権を受入れようとはしなかった。 |
運命の男ヒトラーが“政治活動をしよう”と登場してきたとき、ドイツの情勢は、苛酷な条約によって引き起こされた社会不安、専制政治家の跋扈〔ばっこ〕、暴力団の跳梁など、被征服民族の危険な屈辱感がみちあふれていた。
ヒトラーは、天才的ともいえる特異な才能をもっていた。
それは心理的な洞察力であった。
彼自身のかたくなな性質が原因となって、社会からツマはじきされているという事実を無視して、みずからをドイツ国民と同じなのだ、と考えようとしていた。
ドイツ国民は、名誉ある平和を求めていただけなのに、ベルサイユ灸約によって踏みつけられ、ゴミクズのように扱われていた。
もともと卑屈なところのない国民に課せられた罰のなかで、いちばん危険なものは屈辱感である。
従って、屈辱感にうちひしがれている国民の気持をなんとかして高揚させたいと思う人間は、発言の場をえたいと考えていた。
苦悩する敗戦ドイツの社会情勢は、まさにこれを求めていたのである。
しかし、だからといって、誰でも簡単に発言できるというわけではなかった。
どんな天分をもった人間であろうとも、キッカケを掴む必要があった。
10 ミュンヘンの居酒屋の仲間 top
ヒトラーは、一九一九年、ミュンヘンの居酒屋で、思いがけず、のちに彼の教師ともなり、仲間ともなる連中とめぐりあった。
ディートリヒ・エッカルト、エルンスト・レーム、アルフレート・ローゼンベルグ、ルドルフ・ヘス、アントン・ドレクスラー、カール・ハーラー、それにゴットフリート・フェーダーなどであった。
この連中は、詩人、兵士、建築家、政治家であったが、軍事顧問、錠前屋、ジャーナリスト、多少インチキな科学者兼経済学者になりすまして、敗戦と苛酷な講和条約のために、混乱状態におちいっているドイツを救おうと、法律で禁止されている“革命”という甘い夢にひたっていたのである。
エッカルトは、共産主義者やユダヤ人の勢力に対抗するため「ドイツ市民党」を結成しようと、やっきになっていた。
彼は[ドイツ市民党」の指導者に要求される性格をつぎのようにのべている。
我々は機関銃のまえに立ってもたじろがぬ人間を指導者にしなければならない。
群衆によい意味の恐怖感をあたえなければならない。
群衆はもはや士官を尊敬していないから、士官ではダメだ。
いちばんよいのは兵隊の服をきた労働者で、皮肉たっぷりにものがいえる人間であろう。
とくに頭のキレる必要はない。
政治とは、この世でもっとも愚劣な仕事であり、ミュンヘンの市場をうろつく女も、ワイマ−ルの女も、もっている知識はちっともちがわないのだ。
私は、ガタガタふるえながらすわっている何人もの有名な教授よりも、むしろマヌケで、こましゃくれた人間や、共産主義者にハッキリとこたえ、モノをなげつけられても逃げださないような人物がほしい。
また指導者は、独身でなければならない。
そうすれば、女を味方に引入れることができるだろう。 |
11 ドイツ労働者党からナチ党誕生 top
ヒトラーが指導することになったドイツ労働者党を、実際につくったのはアントン・ドレクスラーであった。
ドイツ労働者党は党員四〇人、出資金七・五マルクで、おとなしくて活気に乏しいスタートをきった。
一九一九年九月十二日、ドイツ労働考究は、あまりパッとしない政治集会を開いたが、この集会に出席したヒトラーは、激しい口調で演説をぶった。
これに目をつけたドレクスラーは、ただちに、彼に六人委員会のメンバーにくわわるよう説得した。
ヒトラーは、ミュンヘンの軍司令部から、破壊的政治活動をさぐるスパイとして派遣されていたのであるが、彼が実際にさぐりあてたのは、自分にとって一生を左右する大きなチャンスがあるのではないか、ということだった。
この集会に出席していたのは、つまらぬ人間ばかりで、ドイツ労働者党は目的も定かでない、みじめな組織にすぎなかった。
ヒトラー自身、とるにたらない人物だったとはいえ、はるかに高い理想をもっていた。
彼は、指導性がなく、エネルギーもなく、全く不安定なこの集団につけこむスキがある、と瞬間的に見ぬいたのである。
ほとんどたった一度の演説で、ヒトラーは指導権を握った。
名目上はともかく、暗黙のうちに実質的な指導権を握り、三ヵ月のうちに宣伝担当に任命された。
ヒトラーは、他のいくつかの小さな運動を統合した。
これらは、いずれもばくぜんとはしていたが、反ユダヤ主義と反共政策の実施を目的とする組織であり、おしつけがましいベルサイユ条約の条項を実行すべきではないと主張していた。 |

パバリア地方独特の皮の半ズボンをはくヒトラー。
ナチ党の指導者になっていた

“指導者は、機関銃をつきつけられても
たじろがぬ人間でなければならない”
|
そしてヒトラーは、党名を改称して、大げさな「国家社会主義労働者党」〔ナチオナルゾ・チアリスティシュ・ドイッチェ・アルバイターパルタイ=NSDAP〕とした。
この最初の二文字をとって、ナチという言葉が生まれた。
その後、二五年以上も続いたナチ党と第三帝国の運命は、とりもなおさず、アドルフ・ヒトラー個人の運命ともなったのである。
top
**************************************** |