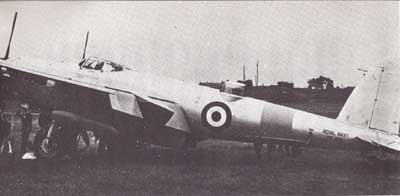|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
10 栄光の翼、消えることなく…
濠にかこまれたソールズベリー・ホールに腰をすえて、「モスキート」の改装や改良計画にとりくみながら、ひたすら実戦での活躍を見まもり続けていた、デハビランド社設計チームの面々は、陸上基地から沿岸防備隊が、「モスキート」を使って洋上哨戒と“潜水艦狩り”を開始するよりずつと以前から、「モスキート」を海上作戦に使用することを考え続けてきた。
1 艦載機としても使用が可能とは top
そこで、ビショップとともに設計の作業に取り組んでいたW・A・タムブリンは、予備的な空母への着艦テストを行って大いに力をえ、これをもとにして、「モスキート」の海軍機化に手をつけたのだった。
「モスキート」は空母の飛行甲板から発着艦が可能である――という最初の申入れにたいして、海軍側は、とても信じられないという面持だったが、一九四四年ともなれば、デハビランド社の面々にとって、そんな反応は、もうめずらしくもなんともなかった。
信じられない! そんなバカな?といった反応は、この“驚異の木製機”のすばらしい経歴に、いつもついて回っていたからである。
そして、そんな疑いぶかい連中をしり目にして、「モスキート」は一九四四年(昭和十九年)の三月、英海軍首席テスト・パイロットであるE・M・ブラウン大尉の手によつて、スコットランド西岸に遊弋(ゆうよく)する空母「インデファティカブル」(二万六〇〇〇トン、「イラストリアス」級空母六番艦)へ、見事に着艦したのである。
これは、洋上の空母に双発機が始めて着艦したケースである、というだけでなく、このとき使用された「モスキート」は、着艦フック取付けのために胴体がわずかに補強された以外、全く改装されていない機体(つまり、完全な陸上機)だったのである。
その後タムブリンは、空母の格納甲板から飛行甲板へあげるさいの便宜をはかって、主翼を上部へおりたためるように改装した。
2 雄図むなしく解隊のうき目 top
一方、このブラウン大尉による「モスキート」の発着艦実験の成功は、海空軍首脳を大いに力づけ、これを太平洋に展開して、メーネ・ダムやエーデル・ダムでみせた「モスキート」の果敢な精密爆撃を、日本海軍の艦艇や船団にくわえようという計画が、立案された。
「モスキート」一個中隊を二隻の空母に分乗させ、バーンス・ウェーリスがダム攻撃のために開発した“ダム・バスター”に似た球形爆弾(ハイポールと呼ばれた)ともども、太平洋に出撃させようというのである。
そして一九四四年十月三十一日、空母「フェンサー」と「ストライカー」(いずれも米海軍から貸与された一万一四二〇トンの攻撃型空母)は、第618中隊の「モスキート」二四機、それに写真偵察型三機をのせ、スコットランドのグラスゴーにあるジョージ五世ドックから、オーストラリアヘ向って出港したのである。
あらかじめ訓練をうけたとはいえ、第618中隊の搭乗員たちは、その任務にいささかたじろがずにはいられなかった。
なにせ、発着艦訓練は、主に単発の「パラクーダ」雷撃機によって行われただけだったからである。
二隻の空母はクリスマスの日にメルボルンへ入港し、訓練が再開された。
そして、搭乗員たちはひたすら待ち続けた……のだが、一九四五年夏、この作戦は、ついに発動されることなく中止になってしまったのである。
おまけに中隊そのものも解隊となり、航空史上に、大きくその壮挙が残されるはずだった機会を失った搭乗員たちの失望は、大きかった。
「モスキート」は、そのままオーストラリア空軍にひきわたされ、搭乗員たちはインドとビルマに転属となった。
3 ひどい状態! 飛べるのが不思議 top
ところで、インドに「モスキート」が姿を現したのは一九四三年のことで、ジャングルの中で日本軍と戦う英陸軍部隊のための写真偵察を主に、非常な悪条件にもかかわらず、めざましい活躍をみせていた。
一九四三年に、始めて「モスキート」がやってきたのは、気象条件による機体各部の試験を実施するためで、いつもイギリス本土、北アフリカ戦線優先でくさっていた実戦部隊の隊員たちは、熱狂的に歓迎した。
気象テストのためおくられてきた、この六機にたいする、搭乗員たちの熱意に圧倒された司令部は、やむなく、これを実戦に使用させることにしたのだった。
「モスキート」の運用状況を、つぶさに調査するために、同機が配置されている全地域をまんべんなく回っているデハビランド少佐は、インドに到着したとたん、見るに耐えないほどの状態で飛んでいる「モスキート」にでくわし、血も凍るおもいにおそわれたのだった。
機体に使われている接着剤が、インドの気候にあわないため、あちこちがはがれ始めており、主翼や胴体のそこここには“キノコ畑”ができているのである。
しかし、とにかくすばらしい性能を発揮してくれることに、満足しきっている搭乗員たちにとって、メーカーの安全規格などというものは、ないも同然であり、デハビランド少佐が事故を防止するため、余りにひどい機体の飛行をやめさせようとすると、猛然たる反対が巻き起こった。
そしてついに、ハットフィールドからやってきたこの少佐は、手荒な強硬手段をとらなければならなかったのだった。
彼は町から木こりの使う大きなノコギリを買ってくると、飛行に耐えぬ、と判断した「モスキート」の主翼によじのぼり、インドの炎天下をものともせず、その主翼をノコギリで切りおとしたのである。
そして、今後も、飛行が危険だと判断した「モスキート」の主翼は、すぐさまちょん切ってしまう――と宣言したのだった。
しかし、そうこうしているうちに、「モスキート」の“熱帯地方むけ(トロピカライズド)”改装が完成し、ビルマにおいて日本軍と苦闘する英陸軍第14軍の作戦に、大きな力となった。
|

「モスキート」は太平洋戦域にも出撃、ヨーロッパや北アフリカとはちがった悪条件に悩まされながらも、まさるともおとらない成果をあげた
|
4 危険をはらむ広大な行動圈 top
あらゆる点からして、東南アジア戦域における「モスキート」とその搭乗員たちの活躍ぶりには、目ざましいものがある。
ジャングルや洋上の偵察飛行は六、七、八時間、ときとして九時間にもおよぶときがあった。
狭い操縦室のなかにつめこまれているパイロットと航法士は、ヨーロッパ戦線と違って、もしもエンジンが不調にでもなったら、生還する可能性はないにもひとしかった。
迎撃戦闘機や対空砲火にやられる危険は、ヨーロッパ上空にくらべて、はるかに少なかったが、東南アジア戦域を飛ぶ「モスキート」には、他とはちがった大きな敵があった。
彼らを常に悩ますのは、不順な気候とモンスーンであり、日本軍は捕虜をかなり手荒く取り扱うという事実は、万が一の事態を予想する彼らの胸を、重苦しくおさえつけずにはおかなかったのだ。
そのうえ彼らは、ビルマ〜タイ間の“死の鉄道”建設(日本陸軍がイギリス捕虜を使って建設したもので、多数の犠牲者がでた)が進行してゆく状況を、いやというほど上空からカメラに収めていた……。
毎月、毎月、「モスキート」の作戦範囲はひろがっていき――不時着のはめになったとき、歩いてかえる距離がのびていき――ついに第684中隊はビルマ全域、インドシナの半分、タイの大部分をその行動圏内に収めたのだった。
あるときなど、ココス諸島(スマトラ南方一五〇〇キロ)からペナン、タイピン(いずれもマレー半島西岸)の写真偵察、全行程四二〇〇キロを、のべ九時間で達成している。
ほかに偵察の手段がない東南アジア戦域のこととて、配置されている「モスキート」に要求されるのは、ひたすらその行動圈を拡げることだった。
ひとつの方法として、ビルマのジャングル内に展開している英第14軍陣地内の滑走路に、いったんおりて、それこそ日本軍の鼻先で給油のうえ、出撃することも行われた。
搭乗員たちは、ジャングルの中の小屋で、眠りづらい一夜を過ごし、夜明けとともに離陸して、さらに遠く離れた地域の偵察へと向かうのだった。
写真偵察中の「モスキート」は、ジャングルにも目を光らせ、地上軍と密接な連携をとりながら、必要に応じて、爆弾を搭載した「モスキート」が出撃し、インド国境(インパール作戦)にせまる日本軍を、ビルマへ押し戻すことにも、大いに力をかした。
5 ここでもかわらぬ熱狂ぶり top
ぞくぞくと到着する「モスキート」を受領する中隊の搭乗員たちの喜びようは、他の戦線と全くかわりはない。
一九四五年二月二十日の第89中隊の日誌には、こんな記事がある。
「ついに我々の『モスキート』が到着した。近来にない大事件だ。
みんなは『モスキート』を、畏敬のまなざしでむかえた。余りにも長く待たされた……」
第45中隊の指揮官であるR・J・ウォーカー中佐は、これまで使っていたアメリカ製の「ベンジャンス」(バルティーA35単発急降下爆撃機)にかわって「モスキート」を使い始めた時期の作戦日誌に、こんなことを書いている。
「木製であることからくる『モスキート』の構造的な弱さも、隊員たちの士気には、全く影響をおよぼしていない。
彼らはみな、この新機に熱狂しており……強引に遠くまで飛ぼうとするのをやめさせるためには、時として、断固たる手段をとる必要があった」
同じような熱狂ぶりをしめす、彼ら東南アジア戦域の搭乗員たちは、出撃となると、ヨーロッパや北アフリカ戦線とは全くちがう経験を、なめさせられたのだった。
爆撃の目標は、軍需工場の屋根やゲシュタポ本部の建物ではなかった。
ビルマ戦線における彼らの相手は、日本軍の砲兵陣地であり、ジャングル内の水路を伝って兵器や兵員を運ぶ平底船であり、ヤシの木陰に隠されている、弾薬を積んだ牛車であった。
それは、極めて原始的な戦いであり“ベルリン急行”に代表される、嚮導機(きようどうき)や目標捕捉機のスマートな任務とは、きわだった対照をみせていた。
とはいうものの、それは非常にスリルにとんだ任務であり、アメリカの原爆によって日本が降伏したとき、「モスキート」搭乗員のなかには、アメリカにしてやられたような、持って行きようのない不満を感じた者も、少なかったのである。
第84中隊の指揮官だったマクスウェル中佐は、VJデイ(対日戦勝記念日、もちろん八月十五日)に感じた気持ちを、こんなふうにのべている。
「その時の気分は複雑だった……。
戦いが終ったのだという、自然に込み上げてくるその喜びは、ややもすると、日本はまだ征服されていないのだ、マレー半島はもちろん、各地の日本陸軍は依然として勝ち誇り、ちょうど一九一八年のドイツ(第一次大戦終結時)と同じく、故国の意気地なさに失望しているに違いない――という思いに満たされるのだった。
そして搭乗員たちの大多数は、“日本撃滅”の夢をさらわれたような感じをいだいたのだ……」
6 最後の一頁を飾るエピソード top
太平洋戦争の終結とともに、インドやビルマに展開していた「モスキート」部隊は、マレー半島各地の飛行場へ集結するよう命じられた。
そんな中のひとつ、第89中隊には、ビッキーと呼ばれるペットのクマがいて、これまで中隊と行動をともにしてきていた。
胸のところにVの字型の、白い模様があるこのビッキーは、中隊の整備員が、カルカッタの市場で手にいれたものだった。
中隊の大部分は、すでにシンガポールヘ向かい、残ったのは飛行不能の「モスキート」三機とその搭乗員、それにビッキーだけ。そこで、三機のうちの一機の搭乗員たちは、残された方法がひとつしかないことを悟った。
なんとかして、自分たちの「モスキート」を飛ばし、ビッキーを乗せてシンガポールヘ向かうのだ……。
彼らは、その修理作業をいそがせ、テストを終ると、操縦室にクマを乗せてラングーンへ機首をむけた。
そして、クアラルンプールで給油のうえ、シンガポールヘむかったのだが、給油のあいだビッキーは、「モスキート」の脚につながれて、作業が完了するのを待った。
その日の夕方、そろそろせまってきた夕闇をぬって、ピーター・ヴァーレイ中尉とケン・ロイド准尉の「モスキート」は、シンガポール飛行場に進入した。
この予定外の「モスキート」の着陸に、基地の高級将校たちも、何事かと、外へ姿を現して、機が定位置へ地上滑走してくるのを見まもっていた。
やがて機がぴたりと停止して、操縦室のドアが開くと、まずひらりととびおりたのは、なんと英空軍の軍帽を、ちょこんとかぷったクマ一匹……。
デハビランド「モスキート」機の輝かしい日々、その最後の一ページを飾るにふさわしい珍事だろう。
7 “驚異の木製機”は思い出の中に top
ヨーロッパと極東両戦域における、圧倒的な勝利に飾られた第二次大戦の終了とともに、「モスキート」は、ジェット機という新しい世代の門口で、名誉ある退役をとげた――と一般には考えられている。
ところが、この双発レシプロ・エンジンつき木製機が、標的曳航という任務を最後に、ひっそりと退役したのは、それからさらに一三年後のことだったのである。
一九五〇年代にはいると、標的曳航という、しがない任務についている「モスキート」が、英空軍の主力基地へ着陸することなど、ほとんどなくなったが、それでも、何かの用件で着陸するようなことがあると「モスキート」は、それこそ熱烈な歓迎をうけたのである。 |
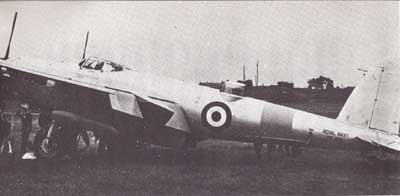
“驚異の木製機”とうたわれ、はなばなしく大空をかけめぐった
「モスキート」も、標的曳航機として退役の時を静かに待つ
|
基地司令官、中隊指揮官など、現役の高級将校の大部分は、大戦中の「モスキート」の働きについて、なんらかの想い出をもっている者ばかりだったからだ。
一方、ジェット機によって育った若い搭乗員たちは、「モスキート」をまるで、他の惑星からやってきた宇宙船でもあるかのように、物めずらしげに見まもり、いまや歴史的な存在となった、木製のその主翼や胴体に、そっと手をふれてみたりした。
そして、かっての「モスキート」搭乗員たちともなれば、もう涙をながさんばかりの表情で、進入してくる「モスキート」の姿に見いり、おそらくこれが最後の再会だろうと、心でつぷやきながら、その操縦室へもぐりこんでみるのだった。
一九五八年に「モスキート」が退役するまでのあいだに、そんな感動的な再会をはたすことができた搭乗員のなかには、かつて「モスキート」による写真偵察に生命を賭けたS・L・リング大佐や、チャーチル・スターリン会談の下準備に、モスクワへの初の連絡飛行を敢行したフランク・ドッド中佐がいた。
二人が基地司令官と中隊指揮官を務めるワディントン基地へ、おもいもかけず、懐かしいこの「モスキート」が偶然たちより、感激の再会となったのだっだ。
一九五八年に、かつて「モスキート」奇襲部隊の基地としても使われていたウィタジング基地で、「バリアント」(ビッカース社製の長距離中型ジェット爆撃機)部隊の指揮官を務めていたイボール・ブルーム中佐も、なつかしの「モスキート」の操縦席に、腰をおろすチャンスにめぐまれた一人である。
バプテスト派の牧師の息子であるこの中佐は、「モスキート」を駆ってベルリン奇襲に何度も参加し、その照準の正確さは、「切手ぐらいの大きさの目標にでも命中させる」といわれたほどだった。
8 記念館に残る試作一号機 top
これら、リング、ドット、ブルームといった、がっての「モスキート」のベテランたちは、その頃、「モスキート」記念館の計画が進行中だったのを知らなかった。
参観者は、このなかにおかれた「モスキート」の操縦室内にも自由にでいりができ、かつての搭乗員たちが自分の子供や孫たちに、この“驚異の木製機”の実物をまのあたりに見せ、さわらせてやれる、というものである。
ジェフリー・デハビランド卿は、死去する少し前に、ハットフィールドの格納庫の片すみに、バラバラにしたままおかれていた、「モスキート」の試作一号機W4050の復元を指示した。
そして英空軍の全面的な協力のもとに、もとの姿を取戻した同機は、なつかしのソールズベリー・ホールへと、出発したときと同じく、陸路をとって帰還したのだった。
ジェフリー・デハビランド卿は、“モスキート記念基金”委員会をつくり、みずから委員長の席についたが、筆者もその設立委員の一人である。
この委員会設立の趣旨は、航空史上まれにみる名機「モスキート」の実物一機を展示する建物を、ソールズベリー・ホールに建設する資金を調達することにあった。 |

「モスキート」の試作一号機は、いまも誕生の地ソールズベリー・ホールにたてられた記念館に展示され、おとずれる人ぴとをむかえてくれる |
そして、この委員会のアピールは、たちまち大きな反響をよび、日ならずして、W4050機を永久的に保存展示するための資金を、集めることができたのである。
いま、ソールズベリー・ホールを訪問する人々は、かつてビショップの秘書が魚を――「魚は脳の栄養になるんです」といいながら――料理した台所や、ビショップが初めて「モスキート」のアウトラインを引いた製図室などを、のぞくことができる。
そして、この“フリーマン大将のお道楽”に寄与したのかどうかは別として、若き日のウィンストン・チャーチルが、ソールスペリー・ホールの濠でつったといわれる“カワカマス”の剥製(はくせい)もまた、これからずっと、ここを訪れる人々を、むかえてくれることだろう……。
top
**************************************** |