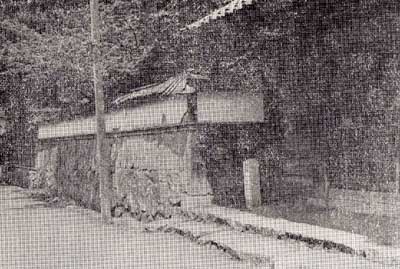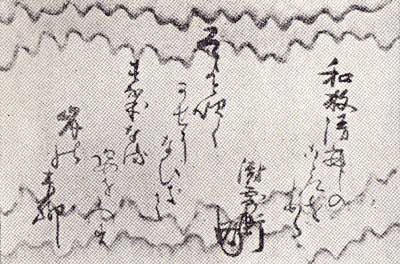|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6
7 8
9 10
略年表
2 今に見ておれ
1 埋木舎(うもれぎのや)の生活
top
槻(けやき)御殿からよく見える佐和山の麓に、清涼寺(せいりょうじ)がありました。
彦根藩第二代の藩主直孝(なおたか)が建てたものです。
曹洞宗(そうとうしゅう)の大きなお寺でした。
このお寺には井伊家代々の幕がありました。
直弼(なおすけ)は父直中に連れられて墓詣りをしたときに、道鳴(どうめい)禅師に引合されました。
直弼が道鳴について手習いをし、また禅学を学びはじめたのは十三歳のときからでした。
直中は道鳴を信頼していましたから道鳴にまかせておけば、元々頭のよい直弼の心の修業は十分だと思っていました。
清涼寺には代々、立派な僧がおりました。
道鳴のあとには師虔(しけん)、師虔のあとには仙英(せんえい)という高僧が出ました。
仙英はその当時の日本で一、二を争うような高僧でした。
直弼が道鳴・師虔・仙英という高僧について修業をしたことは、ただ知識をえただけではありません。
やがて訪れる日本国の危機にさいして、政治の中心にあって事を始末する、心の持ち方を教えられたことになります。
人間、いざというときには知識があるだけでは駄目です。
心の持ち方が大切なのです。
直弼は十五歳になると藩校の稽古館によく通いました。
子供のときから好きであった馬術に磨きをかけました。
剣術や槍術を修業しました。弓術に熱をいれました。
居合術を学びました。 |
 |
射的場で銃術に勢を出しました。父直中があみだした一貫流の銃術です。
父に似て筋骨がたくましくなった直弼は、鼻の下に薄い髭がはえてきました。
母に似て鼻すじがよくとおった美少年ですが、濃い眉に敗けん気が表れています。
父直中の教育方針によって、文武両道に勢を出すことが直弼の日課でした。
稽古館では儒学や国学、さらに和歌の勉強をしました。
武人のたしなみとして、茶の湯の手ほどきを受けました。
今の少年たちのように、レジャーを楽しむような習わしはありません。
テレビやマンガ本を見て時間をつぶすような習わしもありません。
さしづめ野球をやったり、バレー・ボールをやったりするのが、馬術や弓術や銃術にあたるでしょう。
ビデオで英会話の勉強をやったりするのが、四書五経の素読にあたるでしょう。
直弼は文武両道の修業を、嫌々やっだのではありません。
喜んでその道に打ち込んだのです。
槻御殿の直弼の部屋の勉強机の奥にしまってある母の形見の手鏡は、そんなときの直弼の心の支えになっていました。
直弼が十六歳になった年、年号が改まりました。天保(てんぽう)という年号です。
この年、藩校の稽古館(けいこかん)は弘道館と名前が変わりました。
直亮の意見で変えられたものです。
直中が信頼していた清涼寺の道鳴禅師が世を去りました。そのあとは師虔がつぎました。
道鳴が世を去ったあくる年、直中が死んで清涼寺に葬むられました。六十六歳でした。
天保二年(一八三一)五月二十五日のことです。
佐和山の若葉が美しい季節でした。
槻御殿では名君であった直中の思い出が暖められていました。
隠居しておりましたから、直接藩の政治を見ていたわけではありません。
しかし藩主時代のよい政治のことは家臣たちがよく知っていました。
「殿さまになられたとき、領内の士民たちに、たくさんお金を分けられましたな」
「そうそう、財政が思わしくない中で、よくやられました」
「定禄(じょうろく)半額の上納を取止められたのはご立派でした」
家臣たちは口々に直中の政治をたたえました。
直中が彦根藩主になったとき、藩の財政は苦しかったのです。
家臣から禄高(ろくだか)の半分をおさめさせて、ピンチを切りぬけていた有様でした。
そのため家臣たちは暮らしに困ったのです。
直中は藩主になるとすぐに、この定禄(じょうろく)半額の上納を取止めにしました。
家臣たちが感激して、この殿さまのためならば、と奮い立ったのはいうまでもありません。
そのかわり藩の財政は、ますます火の車になりました。
直中は家臣たちの先頭にたって、節約に努めました。
茶を植え養魚をさかんにするなど、進んで産業をおこして収入が増えるようにしました。
そして藩の財政をたて直し、藩校を建て、また佐和山の清涼寺での先祖の供養をねんごろにしました。
「大殿さまに、もっと長生きをしていただきたかった」
「一貫流の銃術こそ、彦根藩の誇りです」
「大殿さまが、苦心してあみだされたお話をうかがったことがあります。」
「また、獄につながれた家臣が、和歌をいただいて釈放されたこともありましたな」
「あれは告げ口をする悪人がいて、大殿さまが一時はそのいうことを信用されたのです」
「告げ口だということがわかった晩、大殿さまは一晩、まんじりともされなかったそうです」
「つくづくと月にあわれぞまさりける 一人居ぬらん人を思えば――大殿さまのお歌は、そのときにつくられたものです」
「月の明るくさえわたった夜だったそうですね」
「このお歌のことは知らない人はありますまい」
「家臣思いのお心が、こんなによく出ているお歌はありません」
「彦根御前さまも、おやさしいかたでした。大殿さまのお心を、お手本にされたのでしょう」
「それにしても、お子さまが生き写しです」
家臣たちの思い出話は直弼の身のうえに移ってゆきます。
顔形はどちらかといえば母親のお富の方に似ています。
しかし性格は、どちらかというと父親の直中に似ています。
そして生まれつき頭がよく利口なのは両親の血を受継いだものでしょうか。
父の直中が死んだとき、直弼は十七歳でした。
父の死によって、直弼の身のうえに大きな変化が生まれました。
生まれたときから住みなれていた槻御殿を出て、北のお屋敷に移りました。
三百俵の扶持(ふち)をもらうことになりました。
いまの言葉でいえば、サラリーマンと同じような生活です。
三百俵のあてがい扶持で生活し、家来も養わなければなりません。
身分にふさわしい交際費も、すべて三百俵のあてがい扶持の中から賄(まかな)わなければなりません。
槻御殿は藩主の別荘でしたから、立派につくられていました。
部屋数も多く地震の間や雷の間と呼ばれるめずらしい部屋もありました。
地震の間というのは地震よけの部屋のこと、雷の間というのは雷よけの部屋のことです。
茶室も整っていました。
槻(けやき)御殿では親がかりの生活でした。
なんの心配もなく多くの家臣にかしづかれて、文武両道の修業に励んでいればよかったのです。
それにひきかえ北のお屋敷は 部屋数も少なく普通の藩士の家と同じぐらいでした。
茶室もありませんでした。
東隣に玄宮園(げんきゅうえん)の広々としてよい景色が眺められた槻御殿にくらべると、北のお屋敷の庭は狭いばかりでなく、荒れ野のようなものでした。
直弼と一緒に槻御殿から北のお屋敷に移ってきた弟の直恭(なおゆき)は、不平たらたらでした。
直恭はまだ十二歳でしたから、父の死とそれに伴っておこった境遇の変化がよく飲込めません。
「兄上、女中たちがへって寂しいですね」
直恭には多くの女中たちにかしづかれていた生活が、夢のように思われました。
「直恭、そちはもう十二だ。父上はもういらっしゃらない。夢を追っていてはいけない」
「夜になると、お化けでも出そうです」
「弱気を出すな」
不平ばかりいっている直恭を叱ってはみたものの、直弼も本心はやはり寂しかったのです。
直弼は北のお屋敷に移ると間もなく、ここを埋木舎(うもれぎのや)と名付けました。
埋木舎という名は世に隠れてひそかに暮らす意味ですが、その反面には実力があればたとえすぐに世に認められなくても、じっと我慢をしていていつかは認められるにちがいない、ということを意味したものです。
埋木舎にも庭はありました。
槻御殿の玄宮園ほど手入れは行き届いていません。
けれども、そんなごちゃごちゃと植えられた庭の木々にも、季節がくれば青い若葉が照りはえています。
「兄上たちのように、一城のあるじになる機会はある。」
直弼は養子にいって城主になっている四人の兄の身の上を考えるのです。
自分の才能も顔かたちも、けっしてその兄たちに劣ってはいない――そう自分に言い聞かせるのです。
「春になれば毎年、木の芽はふくらむ」 |
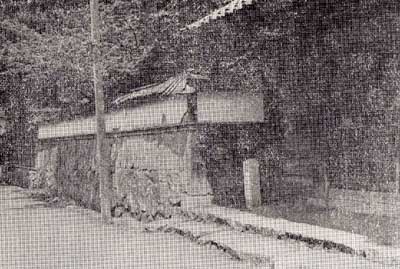
今も残されている埋木舎(うもれぎのや)
|
自分にもそんな機会がないことはあるまい。チャンスがあれば一国一城のあるじにもなれる。
「鉄之介と名付けられた、その鉄の意志を持とう」
直弼は濃い眉を上げました。
「いつまでも埋木でいるものか」
直亮のあとを継いでいずれは藩主になる運命がきまっている兄直元にくらべてみても、歌でも馬でも銃術でも自分はひけをとらない、そう思うのでした。
直元は体が弱いため武術の稽古は ひかえめにしかやっていませんでした。
埋木舎という名前はおさえきれない胸のうちを、屋敷の名前だけでおさえつけたものでした。
本心と屋敷の名前との矛盾を、直弼は自分でもよく知っていました。
埋木舎に移ってから三年めに、チャンスが訪れました。
江戸表(おもて)にいた藩主直亮から直弼と直恭に、江戸に出て来るようにといってきました。
藩主直亮が江戸にいたのは参勤交代のためです。
参勤交代というのは徳川幕府が全国の大名に命じた勤務の仕方です。
石高に見合った数の家臣を引き連れて、きめられた期間は江戸の屋敷に住んでいなければなりませんでした。
国元と江戸と生活が二重になるので、経済的には大変な費用がかかります。
ゆとりを蓄える力もなくなり、謀反などはできないことになります。
直亮からの知らせは大名の養子の口があるから、ということでした。
天保五年(一八三四)七月のことです。
夏の太陽に照りつけられる長い道中をへて直弼と直恭は江戸に着きました。
「さあ、見合いだ」
文武両道にすぐれた直弼の運が開けるかと思われましたが、縁は相手あってのことで、幸運をつかんだのは弟の直恭の方でした。
直恭は見こまれて日向(ひゅうが)延岡の内藤政順(ないとうまさより)の養子となりました。
直恭(なおゆき)は名前を政義(まさよし)と改めました。
そして十月には七万石の城主となりました。
江戸へ出たらチャンスをつかんで、もう彦根の埋木舎に帰ることはあるまい。
彦根の佐和山はもう見おさめだ、そう思って彦根をたった直弼でしたが、世の中はうまくゆかないものです。
直弼はがっかりして、彦根へ帰る気にもなりませんでした。
しばらく江戸の屋敷で暮らしておりました。
やがて冬になりました。彦根よりも寒気がきびしいようです。
冷たい風に吹き乱された粉雪が舞っています。
直弼は筆をとって「埋木舎の記」を記しました。
自分は世を厭(いと)うわけでも、野心があるわけでもない。
ただ埋木のようにひそみ隠れていて、やりたいことをしようと思っている。
その気持ちを埋木舎という名にかこつけたのだ――そんな意味の言葉を、二十歳とは思えないほどの落ち着いた文章で書きつけました。
「埋木舎の記」には
世の中をよそに見つつもうもれ木の うもれておらん心なき身は
という和歌も記されています。
この歌は槻(けやき)御殿から埋木舎に移った頃つくったものですから、三年たっても直弼の心持ちはそう変わっていないことにもなります。
和歌の意味は表面的にとらえれば「埋木舎の記」と同じことです。
直弼はまた、短冊に次のような和歌を書きつけたことがあります。
ざつ事も憂きも聞かじや埋木の うもれて深き思いこそあれ
この歌も世をすてて埋木のように暮らす心持ちをたたえています。
直弼が埋木舎で新しい生活を始めた頃には、自分の実力を頼む気持ちがあったことは先にのべました。
「埋木舎の記」は期待していた養子の口を弟にさらわれて、がっかりしていた時に記されたものですから、微妙な心の変化があります。
埋木舎の名前にはやや拗(す)ねた自分をあざわらう気持ちと、今に見ておれという複雑な負けん気の気持ちが、混ぜられていました。
直弼が江戸をたって埋木舎に帰ったのは、一年ぶりの天保六年(一八三五)八月でした。
2 冷や飯食い十五年 top
直弼の埋木舎(うもれぎのや)生活はなんと十五年も続きました。
兄の直亮は彦根三十五万石の殿さま、江戸で養子の口をえた弟直恭(なりゆき)は、たちまち七万石の大名、直弼だけが取残されたわけです。
そして直弼へのあてがい扶持は三百俵にすぎません。なんという違いでしょう。
あるとき、直弼は彦根の町中で藩主直亮の行列に会ったことがあります。
直亮(なおあき)は御浜御殿で騎射(きしゃ)をして城に帰るところでした。
供先(ともさき)の武士たちが、
「はいれ!」
「はいれ!」
と大声で町人たちを門外から追っていました。
藩主の通行中は門外に出ていることを許さなかったのです。
兄ではあっても直亮(なりあき)は藩主です。
弟ではあっても殿さまの命令には従わなければなりません。
召使い一人をつれて歩いていた直弼は、急いで知らない家の門内に走りこみました。
そのことを知った家人は、兄弟でありながら身分の違いによって、そんなにまで気をつかわなければならない直弼に、たいそう同情いたしました。
封建武士の社会ではごく当り前のことだったのですが。
 |
彦根藩の勘定奉行をしていた三浦十左衛門は誠実で、仕事のよくできる人でした。
直弼の若いときから、これは行く末大者になるぞ、とその人物に惚れ込んでいました。
直弼が槻御殿に参上するとき、横なぐりの風雨が強かったにもかかわらず、輿(こし)にも乗らず傘をさして、わずかな供をつれただけであったのを見て涙を流しました。
十左衛門は直弼が望みをもって江戸に出たにもかかわらず、養子の口をえないで彦根に帰るのを見送った人物です。
直弼と一緒に初めて江戸に出た直恭(なおゆき)は、まもなく一城のあるじ内藤政義となって江戸城に上りました。
十左衛門は藩主直亮とともに江戸にあって、そのさかんな様子をしばしば見ておりました。
初めての江戸ゆきが運命の別れ道になったことを、よく知っていました。
その余りの違い方もまた、十左衛門の心をうちました。
埋木舎時代の直弼は寝るのは、午前一時か二時、起きるのは午前六時から七時の間でした。
一日に四時間も寝れば、十分だといっていましたから、人間ばなれしています。
「豚のように眠ったら、頭が悪くなるばかりだ」
直弼の文武両道は、さらに磨きがかけられました。
江戸の屋敷にいたときに山鹿流(やまがりゅう)の兵学の手ほどきをうけました。
直弼は彦根に帰ってからも研究をおこたらず、手紙によってその続きを指導してもらいました。
天保九年(一八三八)には伝授書をさずけられ、山鹿流の兵学を立派に修め終ったことを認められています。
禅学については清涼寺の高僧について修業しました。
そのことは直弼の人間をつくりあげることに役だっています。
清涼寺で座禅をする直弼の姿がよく見かけられました。
とくに仙英禅師には深く心をよせていました。
仙英(せんえい)は直弼の質問に答えて、「無根水(むこんすい)上の活(かつ)飛竜」という言葉をあたえています。
この場合の「無根水」はかぎりなくこんこんと湧いて出る水の意味で、仏法のことをさしています。
直弼の努力が実をむすんで活きて飛ぶ竜のように悟りの境地に達したことを讃えたものです。
ところで「無根水」は「無根水(むねみ)」とも読めます。
「むねみ」は直弼の号でした。
茶道にはげんだ直弼は「宗観」と号していました。
「宗観」は「むねみ」と読むことができます。
埋木舎(うもれぎのや)には茶室がありませんでした。
直弼は四畳半の茶室をつくってそこで静かなひとときをすごしました。
茶室は樹露軒(じゅろけん)と名付けられました。
樹露軒という名は法華経の法語からとられたものです。
甘露(かんろ)の法雨(ほうう)をそそぎて煩悩(ぼんのう)の燭(しょく)を滅除(めつじょ)す
その意味は仏法のおいしい水をそそいで、つまらない世間的な欲望の火を消してしまうということです。
樹露軒の柱には直弼の和歌がかけられてありました。 |

埋木舎(うもれぎのや)にひっそりと暮らすこと十五年、直弼は茶の湯や
和歌の道にひたりながら、自分の心を磨きあげてゆくのでした。
|
なにをかはふみもとむべきおのずから 道にかなえる道ぞこのみち
朝夕に馴(な)れてたのしく聞くものは 窓のうちなる松風の声
いずれも茶道の心境を明らかにしたものです。
直弼が父直中から手ほどきをうけ、さらに彦根の茶人について学んだ茶は石州流(せきしゅうりゅう)でした。
直弼は持前のとことんまで勉強しなければ気がすまない気持ちから、茶道でも奥義(おうぎ)に達しようとしました。
石州流の宗家の片桐宗猿(そうえん)について疑わしい点を間いただしました。
そのようにして奥義を極めた直弼は、自分の踏み極めた道を入門者の初学心得として、「入門記」に書き残しました。
茶道と禅学とを心の奥底でむすびつけた直弼でした。
その気持ちを直弼は禅学の先生である清涼寺の仙英禅師に、歌で示しています。
茶は茶にあらず
散りかかる池の木の葉をすくい捨て 底の心もいさぎよきかな
ただ茶のみ
いずくにかふみもとむらんそのままに みちにかなえるみちぞこの道
直弼は柳の木が好きでした。
柳の木は母のお富(とみ)の方も好きでした。
槻御殿の玄宮園に柳の木がありました。
母に手をひかれて玄宮園の柳の下を歩いたこともありました。
直弼の柳好きは親ゆずりでした。
直弼は埋木舎に移ってから、玄関の脇に柳を植えていました。
柳は春ごとに柔らかな緑を風になびかせていました。
茶道の深い心は「和敬清寂」(わけいせいじゃく)だといわれます。
心をなごやかにして敬い、わずらわしい考えを去って、静かに落ち着いているという意味です。
直弼はその「和敬清寂」の心を、柳に見ました。
そよとふく風になびきてすなおなる
すがたをうつす岸の青柳(あおやぎ)
直弼の歌ったこの和歌の上の句は「和敬」(わけい)を、下の句は「清寂」(せいじゃく)を表わしています。
直弼は茶室に入るときき この歌をくちずさむのでした。
柳は母の好きな木でもあり、直弼の心のよりどころでもありました。
直弼は自分の号として柳王舎(やぎわのや)・柳和舎(やぎわのや)・緑舎(みどりのや)などを愛用しました。 |
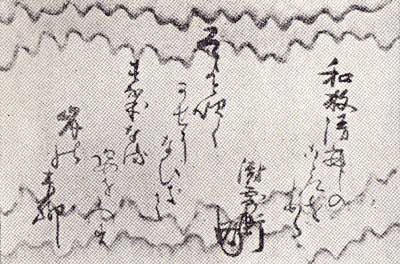
「そよとふく……」の歌を記した色紙
|
直弼が極めた茶道・禅学に通じるものに、居合(いあい)がありました。
居合というのは刀の抜き方による術のことです。
彦根藩には新心流という居合がありました。
木の枠にわらを巻いて人が座っている形につくったものを抜形(ぬきがた)といいます。
抜形は普通、居合坊主とも呼ばれていました。
その抜形をすえて、一人で座ります。
ちょうど座禅をするように、抜形と向き合って座り、静かに心をこらします。
気持ちが落着き充実して腕がなり、抜形が恐れて逃げ去ろうとする間際に、電光石火の勢いで刀をぬき、抜形を切ります。
「やっ!」
切り終ったら静かに元通り座って心を落ち着けます。
気合の充実と緊張、静から動、そしてまた静、あっというまに事が終る、その技術は褝の修業の成果に似たものがあります。
禅によって人間をきたえた直弼は、新心流の師範河西(かさい)精八郎に学んで、居合に磨きをかけました。
直弼は新心流の居合の奥義をきわめてみると、禅の精神をくわえて発展させた一派をたてたい気持ちになりました。
河西(かさい)師範に新心新流という一派をたてたいと相談したこともありました。
直弼が初めて江戸に出たときのことです。ですから二十歳のときです。
このときは遠慮があって、実行にはいたりませんでした。
直弼が居合の一派をたてたのは のちに藩主になってからでした。
直弼が文武両道に励み、数多くなくてきた召使いたちの生活を支えてゆくためには、三百俵の扶持(ふち)は多いとはいえません。
しかも三百俵の扶持は物の値段があがっても、最初きめられたままで増えません。
支出はかさむ一方なのにベース・アップがないわけです。
彦根藩の側評定(そばひょうじょう)・用人格(ようじんかく)の犬塚外記(げき)は、密かに直弼に同情をよせていました。
「お気の毒だ」
犬塚外記は直弼が大人になるに従って、その学問・修業が深まり、武芸一般について個性のある指導者として立派に成人してゆくのを、頼もしく眺めていました。
寒い冬を越せないというので、直弼から、
「金子(きんす)六両をおさげ願いたい」
そのような一時金を出してもらう斡旋を頼まれるたびに、心から同情をしてその願いを取次ぎました。
直弼は貧乏生活にも、けっしてへこたれません。
その人柄をしたって、しだいに埋木舎にやってくるお客が多くなりました。
朝、武士がやってきたかと思うと、入れ代りに儒学者がやってきます。
僧侶もやってきます。夕方には茶人がやってきます。
入れ代り立ち代り、人がやってくるわけですから、出費がかさみます。
「成るようにしか成らない」
直弼は禅問答(ぜんもんどう)のようなことをいって、どんな客にも嫌な顔を見せません。
直弼の付役で、親しい茶友に三居孫太夫(みついまごだゆう)という者がおりました。
ひょうきん者で思ったことを、ずばずばいう男でした。
今日も三居がやってきて、直弼から絵をねだりました。
「お約束です。どんな絵がいただけるか、楽しみにしてまいりました」
「そちのように、せかしても困る。」
「お約束は、お約束です。」
直弼は遠慮なしにずけずけ催促をする三居(みつい)を、少しじらしてから、おもむろに昨夜かきあげた絵を取り出して渡しました。
「ほう、これは鬼の絵でござりますな」
「そちに、よう似とる」
「ひどいことをおっしゃいます。手前は生まれついての善人で、鬼とは全く反対でござります」
「鬼の寒念仏(かんねんぶつ)の絵じゃ」
直弼は 今でいえばマンガを描くようなつもりで、この絵を描いたのです。
三居はしげしげとこの絵を見ていましたが、
「これはしたり、この鬼は足指がみな右を向いています」
「なんと………」
直弼が、三居(みつい)から絵を取戻してよく見ると、なるほど鬼の両足が、いずれも親指から小指まで右向きに描かれています。
直弼が間違えて描いてしまったのです。
「かたわの鬼でござりますな」
三居は直弼の間違いを、容赦なくせめたてました。
直弼はからからと笑って、即座に言い返しました。
「かたわというが、孫太夫、そちはいつ、本当の鬼を見たか?」
これにはさすがの三居も頭をかいて、引き下がってしまいました。
三居は、のちに勤めを辞めてから坊さんになって、直弼に挨拶にきました。
三居の言動はとかく人の意表に出るものが多かったので、直弼はそれをたしなめました。 |

鬼の寒念仏(かんねんぶつ)の絵
|
「鬼面(きめん)、人を驚かすのはよぐないぞ」
直弼は、かつて三居にあたえた鬼の寒念仏(かんねんぶつ)の絵のときの問答を思い出していました。
あのときは直弼の才知が三居に勝って、間違って描いた鬼の絵を三居に押付けたのでした。
「仏門にはいったら、仏徒らしくせねばならぬ。
もし名を改めるなら、ひととおりの名にせよ。奇をてらってはならぬ」
三居はつつしんで直弼のその言葉を受入れました。三居もさる者です。
「かたじけない、幸せにござります。ひととおりの名とおっしゃいました。
そのご命名をそのまま頂戴いたします」
三居(みつい)は即座に直弼のいった「ひととおり」を自分の名として「一通」とあらためました。
一通はその後も直弼に可愛がられました。
直弼が一通にあたえた手紙に、
「ゆずみそ少々ながら、これは紫水軒(しすいけん)老人へつかわし申し候」
という文句があります。
紫水軒(しすいけん)は一通の号です。
ゆずみそを進物にしたのは、まことに風雅(ふうが)なことです。
そしてまた倹約につとめていた直弼の生活がしのばれます。
直弼がのちに井伊家の世継ぎになってからも、一通(ひととおり)は直弼に忠告しています。
「埋木舎時代を、お忘れになってはなりませぬ」
直弼はよくその言葉を守っております。
さらに直弼が彦根藩主になってから一通が老人会を組織して、月々に集会することが直弼の耳に入りました。
「集まってなにを相談するのか?」
直弼の問いにこたえて、一通は直弼の目を見つめながらいいました。
「ほかでもござりません。殿さまのあやまちを非難するだけでござります」
直弼はにっこり笑っていいました。
「よくいった。余(よ)を非難してもよいが、他人の悪口はいうなよ」
そして頼もしそうに一通を見て、つけ加えました。
「余にあやまちがあったら具体的にいってくれ。けっして遠慮するなよ」
3 おない年の師 top
埋木舎(うもれぎのや)に出入りしていた医師に三浦太冲(たちゆう)がおりました。
名医として名を知られている人でした。
直弼はこの三浦太冲から長野義言(よしとき)という国学者のことを聞きました。
長野義言が三浦太冲のところに初めて身をよせたのは、天保十二年(一八四一)のことでした。
義言(よしとき)は色白で、鼻すじのとおった面長の人でした。
額が広く頬がこけ、目はするどくて、背丈は高いほうでした。
なで肩で痩せており、武士というよりはどちらかというと、公家ふうでした。
義言(よしとき)が太冲(たちゅう)の家に身をよせている間に、太冲をはじめ、たちまち十二人の門弟ができました。
義言が伊勢の大庄屋を勤める家柄の、滝野知雄(ともかつ)のところにぶらりとやってきたのは、これよりさき天保十年(一八三九)で、二十五歳のときでした。
滝野知雄は松阪の本居宣長の子春庭(はるにわ)の門人で、国学についての本をたくさん持っていました。
義言が滝野家にやってきたのは、その本が目当てでした。
義言の勉強ぶりは周りの人たちを感心させました。
人柄も立派でしたから、知雄(ともかつ)は妹の多紀(たき)を嫁にやりました。
多紀は出戻りで兄のところに帰っていたのです。
多紀の方が年上で義言は二十七歳、多紀は三十二歳でした。
義言(よしとき)は伊勢の滝野家で、本居国学と妻の多紀を手にいれたわけです。
義言は滝野家を足場にして、いたるところで国学の講義をし、その収入で生活していました。
時々、伊勢の妻の実家に帰りますが、十日間ぐらいでそう長居をしませんでした。
滝野家では多紀を嫁にやりはしたものの、義言の素性がよくわからないと申しておりました。
三浦太冲が直弼から聞かれたときも、太冲(たちゅう)は義言の素性のことは正直に申しました。
「それが伊勢国飯高郡滝野村の滝野知雄の義弟ということははっきりしておりますが、ほかにもいろいろ言われているようです」
「伊勢の出身ではないのだな」
「伊勢の国の神官の子だという説もございます。公家のおとしだねだという説もございます。
またある人は肥後(熊本県)八代の生まれで、紀州藩の家老の養子になったことがあるとも申します」
「なんと………」
「肥後の阿蘇大宮司阿蘇家の一門だという説もございます」
太沖も噂話をそのまま直弼に伝えるほかありませんでした。
「おだやかな性格で、公家のおとしだねということも、まんざらでないように思われます。
静かな物言いで京都と伊勢をつきまぜたような話しぶりです。
もっとも咳き込んでくると肥後弁がまじってまいりますが………」
「よいわ、過去が謎に包まれていようと、忍者ではあるまい。直弼はその義言(よしとき)とやらの学問を買うのじゃ。」
直弼はさっそく義言が国学の講義をしている太冲の住まいに近い志賀谷(しがや)の高尚館(こうしょうかん)に使いを出しました。
高尚館は義言が開いた学館で、ここでも門弟十一人を教えておりました。
直弼の使いは目的を果すことができないでむなしく帰ってきました。
義言がその日の朝、伊勢に出発したあとだったからです。
「くれぐれも日を数えて待ちおり候。心のうち察し給わるべし」
直弼は残念な自分の気持ちをそのようにのべて、義言に手紙を書きました。
義言は自分の著書の「かつみぶり」を直弼に贈りました。
「かつみぶり」は語学の研究書でした。
天保十三年(一八四二)十一月二十日の夜、長野義言は三浦太冲一人を伴って埋木舎を訪れました。
風が冷たく埋木舎の玄関には柳の裸木が、月の光に淡い影をおとしていました。
直弼は義言を樹露軒(じゅろけん)に案内して茶をたてました。
義言は髪が黒く、目がきらきらと光っています。
初対面ながら直弼は これはただならぬ人間だと見ぬきました。
痩せてなで肩で黒羽二重に剣かたばみの紋をつけた縮緬羽織が、恰好よく映りました。
ろ色の大小を腰にして背丈は直弼より、こころもち長身でした。
やや小ぶとりの直弼とは、よい対照でした。
義言は樹露軒(じゅろけん)の柱にかけてある直弼の短冊を読みました。
朝夕に馴れてたのしく聞くものは 窓のうちなる松風の声
彦根三十五万石の御曹司の歌としては、若いのに余りに悟りすましています。
才能ゆたかな人で、機会さえつかめば大名にもなれるだけの力を持った人と聞いていましたから、この歌
はその本心を包み隠したものか、とも思いました。
樹露軒はわずか四畳半の茶室です。
そして、案内されて玄関をあがったときからの、埋木舎の印象は余りにも質素でした。
義言は自分がおくった「かつみぶり」にたいして、ねんごろに礼をいう直弼に、まず好感をもちました。
とおりいっぺんの挨拶ではなく、人扱いになれ、苦労をかさねた人だという印象をもちました。
落ち着いた物言いながら語りかける心の奥には、知恵の泉がこんこんと湧いているような、さわやかさを感じました。
義言は多くの人を教えた経験から、一目で直弼の心を読みとりました。
「天下国家をしょって立つだけの力を持った人だ」
義言は心の中に、直弼の評価をそう刻み込みました。
「よい人にめぐりあえた」
義言(よしとき)はもっと早く、直弼にあう機会をもてばよかったとさえ考えるのでした。
流れ星の夜に生まれた彦根藩のめぐまれない御曹司と、前半生がはっきりしない謎の国学者とは このようにして初対面のときから、心と心でしっかりと結ばれました。
直弼は太冲からすでに、義言が自分と同じ文化十二年(一八一五)生まれであることを聞いていました。
部屋を移して酒の席になりました。
酒席には静江という若い美しい女中がはべっていました。
静江は太冲から、直弼と義言とどちらが年上に見えるかと聞かれると、愛くるしい目を丸くして二人を見くらべました。
武芸の修業をつみ、清涼寺の座禅で精神もきたえている直弼の、がっちりした肩幅を見ていると、なで肩で色白な義言の方が三つぐらい年下に見えました。 |

井伊直弼(いいなおすけ)
|
「もちろん、お殿さま」
直弼と太冲は顔を見あわせて笑いました。義言も、にこにこしています。
「そうか、わしの方がふけて見えるか」
直弼は静江の杯(さかずき)をうけながら、義言を見ていいました。
「おない年で気長野義言どのは、世の中のことにおいては わしの大先輩だ」
「もったいないお言葉でございます」
「静江、お客さまにどんどんおつぎしなさい」
静江は直弼と義言が、おない年だと知ってびっくりしました。
目を丸くして直弼の方を見ていましたが、あわてて銚子を取上げました。
義言は薄紅をはいたように赤くなって酒をすすめる静江をちらと見やりながら、静江は直弼から可愛がられているのであろうと考えていました。
酒の席とはいえ。直弼と義言の話題はむずかしい学問の話になってゆきました。
とくに義言の「かつみぶり」について、直弼の質問が細かいことにまでわたって 話し合いに熱がこもっていました。
夜更けになって静江はもう下ってよいといわれました。
けれども直弼と義言はその後も夜どおし話し合ったのです。
弟子の太冲は かたわらに座って静かに義言の教えを聞いていました。
東の空かしらんできて、暁を告げる鳥の鳴き声がしました。
「もう夜明けじゃ。今日から直弼が弟子入りする」
直弼はみずから杯(さかづき)をとって義言にあたえ、師弟のちぎりを結びました。
義言は「岩橋日記」にその日の感激を、和歌で記しています。
そのとき義言がよんだ歌は、
まつほどのよは辛崎(からさき)のからかりき ついにあうみとおもいながらも
と記されています。
二人が会うことは前からきまっていたのに、待つ身はつらかったという意味です。
この和歌にたいする直弼の返歌は
まつほどのつらきもいまはわすられて あうみの名さえうれしかりけり
と記されています。二人が会えて本当うれしいという意味です。
「あう身」という言葉と「近江」という地名が二重の意味を持ってかけられています。
あけて二十一日に、また夜になって義言は埋木舎を訪れました。
直弼の願いで「皇国の学の道」を講義しました。
直弼は、そのときの心持ちを次の和歌にこめています。
かずならぬもくずなれども神風の ふくにまかせて道ひらきせん
この歌も義言の「岩橋日記」に記されています。
二度めに埋木舎をたずねた時も 鳥の声を聞いて帰りました。朝帰りです。
三日めは義言が題を出してみなで歌をよんでいると、直弼の使いがやってきました。
「今日は風があらく、しぐれがちですから、寂しいでしょう。
今夜、お会いするのを楽しみにしています。日がくれたら早くおいでください。
なかなかにちかく住みぬる君思えば あうを待つまもくるしかりけり
短冊を五ひら、師の歌を何でもよいからしたためてお持ちください」
手紙の文面はそういった意味で、カステラが添えてありました。
いまでこそでカステラはめずらしいお菓子ではありませんが、その当時としてはたいそうめずらしいものでした。
感激して埋木舎を訪れた義言は、ねんごろにもてなされ、やはり朝帰りになってしまいました。
お互いに和歌をやりとりしました。太冲も一緒になって歌をよんでいます。
直弼の和歌に、
わがやどの柳のいとも何かせん わかるる人をつなぎかねては
というのがありました。
義言は埋木舎を出るとき、玄関脇の柳の裸木が暁のさわやかな空気にさらされているのを見ました。
柳のすきな直弼が、別れを惜しんでよんだ歌をいつまでも忘れかねていました。
三晩にわたってお互いに心を傾け、国学を論じ和歌を贈り合った感激を、直弼は手紙にして義言に贈りました。
それには、
「敷島の道(和歌の道のこと)に深く心をよせ、和歌の道にも言霊(ことだま)の道にも詳しく、そのうえ心が誠実であることはこのうえなく、本当にありがたいことです。
私は近年、師と頼む人もなく自分で歌をよんではいましたが、自信のない事ばかり多かったのに、お会いできて幸いでした。
お互いに慕い慕われて、深夜に対面したからこそ、敷島の道を踏み開くことができました。
いまからは義言どのは私の師です。私は義言どのの教え子です」
と、ねんごろに記されています。
直弼は義言の「かつみぶり」だけでなく、そののち「玉の緒」や「末分櫛」(すえわくぐし)などの語学研究書を参考にして「かつみぶり新図」という初学者向きの語学入門図表をまとめました。
また義言の「古学答問録」七巻(かん)について、よく勉強しています。
「古学答間録」は直弼の質問に答えて義言がまとめたものです。
義言には「歌の大武根(おおむね)」「渚の玉」「沢の根ぜり」などの著があります。
義言が学識のある精力家であったことがわかります。
直弼が「柳廼四附(やなぎのしずく)」という歌集を出したとき、歌の師匠の義言は直弼の歌を十分に手を入れて直したりしています。
4 たか女の悲しみ top
埋木舎には多くの人たちが出入りしました。
前半生が謎に包まれた長野義言もその一人ですが、頭がよく美人で評判のたか女もその一人でした。
たか女はやはり埋木舎に出入りした、多賀神社の社僧の般若院(はんにゃいん)慈尊(じそん)に連れられて埋木舎を訪れ、直弼に仕えたことがあります。
多賀神社は彦根からほど遠くないところにあり、慈尊はそのころ直弼から信頼されていました。
たか女はその親類にあたり、三味線が上手で声もよく、歌をうたわせてもほれぼれする節まわしでした。
小柄な女で、色白でした。
色の白いのは七難かくすともいいますが、たか女の面長の顔形のよさは色白であることによって磨きをかけられ、慈尊の自慢でもありました。
若いときに一時、多賀神社にあって慈尊の指導をうけ、和歌のたしなみもありました。
人の噂ですから本当かどうかわかりませんが、藩主直亮にも可愛がられたことがあるといいます。
その美しさと才知からすると、まんざらおかしくもないのです。
たか女は京都のある武士の妻となり男の子もできたのですが、何かのわけがあってその武士と別れ、慈尊(じそん)のもとに頼ってきていたのです。
たか女は、直弼よりも五歳年上でした。
直弼が初めて、たか女を見たのは二十五歳のときでした。
人の出入りはあっても埋木舎の世捨て人のような生活で、文武両道に励んでいた直弼の前に現われたたか女は、直弼に安心して甘えられる女性を感じさせました。
美人でしかも利口そうなたか女の印象が、そうさせたのでしょう。
このとき、たか女は三十歳だったことになります。
直弼の心のなかの女性は、五つのときに死に別れた母の彦根御前だけでした。
母の形見の手鏡は、直弼の部屋の勉強机の奥にしまわれています。
女中たちに接しても女を感じなかった直弼が、三十女のたか女に女性の魅力を感じたのは 普通の女と違った人をひきつける力を持っていたからであり、また芸達者で、和歌のたしなみがあることなどが気に入ったためでしょう。
がっちりした体つきで美男子の直弼を、たか女が誘惑したためではありません。
直弼のほうで、たか女にひかれたのです。
いつのまにか、たか女は、直弼の心をしっかりつかんでしまいました。
世の中は思うようにはならないものです。
たか女の過去が普通の女でなかっただけに、直弼の心がたか女に傾き、それに応えるようにたか女の心が直弼にひかれてゆく様子を、心配したのは犬塚外記(げき)でした。
外記は藩主直亮とたか女のことを知っています。
その後のたか女の結婚のことも知っています。
どんなにすぐれた女性であっても、そのような女が直弼の相手になるのは よくないと思いました。
ましてたか女のほうが五歳も年上です。
直弼のゆくすえに希望をかけ、直弼の身に間違いがないようにと心を配っていた外記は、直弼とたか女の間を裂かなければいけないと思ったのです。
外記は思いきって、直弼にそのことを申しでました。
「こればかりはなんとしても、聞いていただかねばなりません」
外記の言葉を聞いた直弼は額にしわをよせて不満の意をあらわしました。
「世間の噂が耳にお入りになりませんか」
言いにくいことをずばずばいう外記の性格を、直弼はよく知っていました。
しかし、たか女の面長で色白の美しい顔が目の前にちらつきます。 |
 |
直弼は結局外記のいうことを聞かず、外記はあきらめて涙をのんで引き下がりました。
いったんは外記の言葉を退けはしたものの、外記が帰ってしまってから、直弼はあとで後悔しました。
「自分が悪かった」
外記の忠臣ぶりは、直弼が一番よく知っています。
直弼は外記に手紙を書いて、たか女との縁を切ることを頼みました。
じかにたか女に言い渡すことは気の毒だから、慈尊に上手に始末してもらおうという方法をとらせました。
直弼の手紙には 次のようなことが書かれていました。 」
「はなはだよくないことがおこり、般若院のためにもよくない。
そのうえ婦人が当方に居るようなことにでもなれば、重ねがさねよろしくないことになる。」
理由ははっきり書かれておりませんが、般若院の考えひとつで、この事件を始末することを外記に命じたものでした。
般若院慈尊はたか女を埋木舎につれていって直弼に引き合わせた人ですから、直弼とたか女の縁切りについても、始末しなければならない運命になりました。
外記の言う通りにしました。
たか女にとって心の中にふくれあがってきた直弼の姿を、消し去るのはつらいことでした。
「殿さま………」
たか女は、幾晩も夜具の袖をぬらしました。
「これが運命というものでしょうか。」
京都で夫に別れるときにも涙を流さなかったたか女ですが、今度ばかりはつらい別れの涙を流しました。
慈尊をうらんでみたところで、どうにもなりませんでした。
このたか女はのちに長野義言ともねんごろになりました。それには訳があります。
義言(よしとき)は伊吹山の麓の高尚館におりました。
そして義言が多賀神社に身をよせていたこともあるのです。
多賀神社の慈尊が義言とたか女の仲立ちをしたとしても、おかしくはありません。
たか女は義言からも和歌の指導をうけたのです。
義言がたか女と初めて多賀神社であったときに、二人は和歌のやりとりをしています。
そのことを、義言が書き残しています。
「多賀の大御神の社におまいりした夜、般若院(はんにゃいん)に泊りました。
夕方に、使いがきて手紙を持ってきました。
女文字で、あなたさまは私の思っているお方にゆかりのある人だと聞きましたので、昔のことが思い出されて、ますます袖をぬらしました、と書かれておりました。
思いがけないことでありましたので、手紙を持ってきた使いに、この方は柳にゆかりのある人ですか、と聞いたところが、そうですと答えましたので、そのかわいそうな身の上にたいそう同情して、
思うそのゆかりと聞けば青柳(あおやぎ)の しらぬかげにも立ちまどいつつ
という歌をかえしました。」
たか女が使いに頼んで義言に届けた手紙には、直弼を忘れられない気持が示されております。
義言は、「柳にゆかりのある人」として、直弼のことを、それとなくさしたものです。
直弼の柳ずきなことは有名でした。
直弼とたか女の悲しい恋は噂話としても義言の耳に入っていました。
たか女に同情した義言の素直な気持ちと、さすがは直弼が弟子入りしただけに、すばらしい人だと感じたたか女の気持ちとが、二人を結びつけました。
そして和歌がその仲立ちをつとめ、たか女もまた義言の弟子になりました。
義言は直弼と同年生まれでしたから、たか女のほうが五歳の年上です。
たか女が義言の愛を受入れたのは、師弟というあいだがらだけでなく、義言の学識が預かっていたでしょう。
そしてなによりも、義言が悲しい運命を背負って不運な女の生き方をしているたか女に、暖かな男の手をさしのべたからにほかなりません。
直弼はのちに藩主になってから、若い頃の自分のあやまちを反省して、義言に次のような手紙を書いています。
「この手紙は 秘密にしていただきます。
先頃もたいそうお世話になりました婦人のことは、その後いかがなりましたでしょうか。
あの婦人は心得がよくなく、世間にも知られている人ですから、私もたいそう後悔しております。
しかし昔のことはもうどうにもならないことで、悪くすると難儀もかかり、汚名をうけることになるかと心配しております。
身のおさまりをつけたほうがよいと思って、いろいろすすめても聞きいれません。
先生がひとかたならずお心使いをしてくださっておいでのことは、私のことを深く考えてくださってのご親切で、たいそうありがたく思っております」
この手紙によって、義言がたか女の世話をしていたこともわかります。
直弼が体面を考えて、たか女との関係を後悔している気持ちが出ています。
若い日のあやまちは誰にもありがちのことです。
それにしても憐れなたか女の身のうえでした。
たか女が去ってのち、直弼は静江を側室にしました。目の丸い小柄な女性でした。
天保十四年(一八四三)長女が生まれましたが死産でした。直弼が二十九歳のときです。
あくる年の弘化元年(一八四四)には、長男が生まれましたがその日のうちに死んでいます。
子供運にめぐまれない直弼でした。弘化三年(一八四六)に次女が生まれました。
今度は丈夫に育ちました。弥千代と名付けられました。
弥千代はのちに高松藩の世継ぎである松平頼聡(よりとし)のところに嫁入りしました。
top
****************************************
|