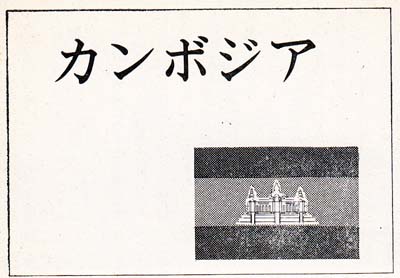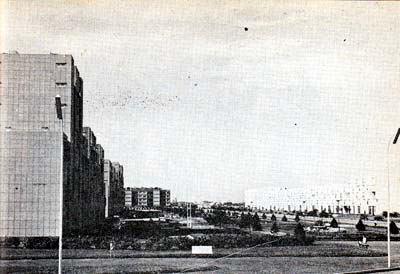|
****************************************
Index
総論(西洋人渡来以前) 総論(西洋人渡来以降)
ベトナム カンボジア ラオス タイ ビルマ マレーシア インガポール インドネシア フィリピン
2 カンボジア
|
カンボジア王国
政体 立憲・君主国
元首 ノロドム・シアヌーク元首
首都 プノンペン
面積 一八万平方キロ(北海道の約二倍強)
人口 六二〇万人(一九六五年発表)
主産物 米、トウモロコシ、ゴムなど
これまで仏領インドシナについて書かれたフランスの文献によると、多くのページがベトナムに割かれ、カンボジア、ラオスについてはほとんどふれず、特にラオスについては記述のほとんどないものさえあった。
これは植民地本国としてのフランスの関心が資源開発に便利な、したがって開発のすすんだベトナムに重点がおかれたことの反映でもあった。
しかし、インド文化の影響をうけ、それを造型に残していることでもわかるように、今のカンボジアの地域は、かってベトナムの一部(ファンラン地方)、タイ、マレーに威勢をほこったクメール族興亡のあとをひめた地域である。
|
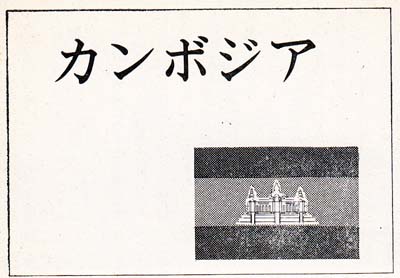 |
① 歴史 top
いま、その興亡のあとを歴史的にたどると、大体つぎの通りである。
① フーナン(扶市)王国時代(一〇〇〜五五〇年)
インド文化はなやかなりし時代で、このフーナンの一国カンブージャが現在のカンボジアの国号の起源である、ともいわれている。
② チェンラ(真臘)王国時代(五五〇〜八〇〇年頃)
いまのカンボジアと、ラオス南部にまたがる地域に興り、コbッボントムの近くにあるイサナプラを都とした。
③ アンコール王朝時代(八〇二〜一一八〇年頃)
アンコールを都として、さきに述べたアンコール・ワット、アソコール・トムなど、数々の堂塔・像碑をのこしたカンボジア最盛の時代である。
王朝の終り頃、隣国チャンパと二度は同盟をむすんでベトナムを攻めた(一二一八年)が、これに敗北し、再度のベトナム攻略にも重ねて敗れ(一一三〇年)、三度目のベトナム攻略に再びチャンパとの協力を申入れたところ、チャッパに拒否されたため、チャンパと戦火をまじえるにいたった。
一一七七年チャンパは海路アンコール王朝に進攻して、アンコールを占領し、これを焼きはらった。
④ 独立時代(一一八一〜一三五七年)
しかし、クメール族の勢いは、ジャヤヴァールマン七世(一一八一〜一二一八年)によって盛り返された。
王は海戦を交えてチャム族を撃破し、アンコール王朝を再建した。
有名なバイヨンやアンコール・トムの城壁は、この王のとき建造された、といわれる。
一三世紀初頭には、チャンバもクメール族の一属州となり、カンボジアの領土は、北はラオス(ビェンチャン)、南はマレー半島、西はビルマに及ぶ広大なものとなった。
ただ、再興アンコール王朝の末期になると、数代にわたって王の名はつたえられているが、その在位年代も治績もあきらかでなく、国威の衰微があらわれている。
一つには多くの寺院や病院の建設に国費をかたむけた後の疲弊と、いま一つには隣国タイに、スコータイ王国が建設され(一二八〇年)、さらに領土を拡張してアユティア王国が建設されるに及んで(一三五〇年)、カンボジアはその重大な脅威のもとにおかれたからである。
これ以後、カンボジアの近世史は、はじめの頃はほとんどタイとの交戦、タイによる征服、終りの頃はベトナムとの交戦、ベトナムによる征服という、苦難の時期に入るのである。 |

アンコール・ワット
|
⑤ 近世史(一三六三〜一八六七年)
カンボジアのポネア・ヤット王(一四〇五〜六七年)は、一四三四年に、アンコールがあまりにタイ国境に近く、タイの侵攻で荒廃させられたことを理由に、都をプノンペンに移して、ここに王宮を建てた。
一六世紀に入って、アン・チャン一世のとき、タイの脅威から脱れるため、さらに都をロベックに遷したが、タイがビルマと交戦し、アユティアがビルマ軍に包囲されたのを好機として、タイを攻撃した。
その後もカンボジア軍は一五七五年、一五七八年の二回にわたってタイに進攻したが、一五九三年には優勢なタイ軍がカンボジアに侵入し、時のカンボジア国王チェイ・チェッタ一世(一五七四〜九五年)は、ラオスに亡命し、カンボジアは事実上タイの支配下におかれるにいたった。
興味のあるのは、このチェック一世復位のために、ポルトガル人(ディンゴ・ペロソ)、スペイン人(ブラス・ルイス・デ・ヘルナブゴンカレス)が登場することである。
二人は当時すでにスペインの領有下にあったフィリピンに行き、太守を説いてスペイン人や日本人キリスト教徒から成る義勇軍を編成し、カンボジアに派遣させた。
この援軍の力でタイ軍を撃退した後、ラオスへ亡命中のチェッタ王の王子が、カンボジアに戻って王位につきチェッタ二世を名乗った。
チェッタ二世は、タイの脅威から脱れるためにベトナムとむすび、南のグェン(阮)氏の娘と結婚した。
しかし、これはカンボジアとベトナムとの間に隷属関係をもたらす糸口になった。
その後レアム・チュプディ・チャン王(一六四二〜五九年)のとき、王弟との間に紛乱を生じ、ベトナムのグェン氏はカンボジアに攻め入った。
その頃からベトナムはカンボジアにたいする発言権を強化し、事あるごとに権益の地歩を固めてきた。
チェック四世(一六七五〜九五年)のとき、副王との間に内乱が生じたのを機会に、再びベトナム軍はカンボジアに攻め入り、当時カンボジア領であったサイゴンに兵を駐留させて、コーチシナをベトナムの支配下においたのである。 |

カンボジアの民族舞踊
|
それから約二〇年後、アン・ニム王(一七一〇〜二〇年)のとき、こんどはタイの侵略をうけて、カンボジアはタイに朝貢した。
こうして、カンボジアはベトナムとタイの二つの国に臣従することになったが、一八一三年、タイとベトナムの間に妥協が成立し、タイはカンボジアにたいするベトナムの保護権を認めた。カンボジアでは、風俗、習慣、宗教にいたるまでがベトナム化されていった。
時代は異なるが、それはベトナムにたいする中国化を小型にしたようなありさまであった。
しかし、その後もタイとベトナムの間には、カンボジアをめぐる対立・和議がくり返され、結局カンボジアはタイの宗主権の下におかれた。
一八六二年、カンボジア王位をめぐって、ノロドム王と伯父ジヴォタの間に争いがおこり、フランスはノロドム王援助の名目でカンボジアに介入した。
カンボジアにたいする宗主権を主張するタイとフランスの間に対立が生じ、ついにフランスがこれに勝利して、一八六三年、フランスはカンボジアにたいする保護権をタイに承認させた。
ノロドムエの死後(一九〇四年)、ノロドム家とシソワット家が王位の継承を争ったが、フランスは一九四一年、ノロドム王の曾孫で、シソワット王の孫にあたるノロドム・シアヌークを王位継承者に決めた。
これが現在のカンボジア国家元首である。
紀元三世紀から二〇世紀にいたるまでの経過のなかで、一つの特徴としてあげられることは、アンコール王朝の最盛期を除いて、カンボジアがたえず近隣諸国からの介入をうけ、文化的・宗教的にもその影響下におかれたことである。
さきにのべたレアム王は、一七世紀にチャンパからカンボジアへ亡命したチャム人たちの感化でイスラムを奉じたが、一九世紀なかばのアン・メイ女王時代には、カンボジアはベトナムの圧力下に大乗仏教への帰依を強制された。
しかし、カンボジアの庶民は、むつかしい原理は別として、朝夕に仏を祀り、仏僧を尊ぶ小乗仏教徒で、いまカンボジアが仏教を国教とし、国王も仏教を保護すべきことか憲法でうたわれているのも、この小乗仏教である。
② 独立への途 top
フランス連邦を構成する一員であったカンボジアの独立が、フランスからの完全な離脱によるものであることはいうまでもないが、ベトナムの場合と同様、ここでも直接・間接に日本が重要な関係をもっている。
一九四〇年九月、カンボジアは日本軍の占頷下におかれた。
四五年三月九日(三・九事件)の「仏印処理」によって、ノロドム・シアヌーク王は「独立宣言」を行ない、当時反仏運動の弾圧をのがれて日本へ亡命中のソン・ゴクタンがカンボジアへ帰って内閣を組織した。
しかし、カンボジアにほんとうの民族独立運動がおこったのは、日本軍の敗北、ベトナムの八月革命に動かされてのことであった。
「自由カンボジア」の独立をめざす急進的な民族主義者の反仏運動が、各地で展開された。
同時に、それはイギリスの援助のもとにカンボジアへの再侵略をこころみるフランスにたいする抵抗の戦いでもあった。
同じ自由カンボジアをめざす民族運動に二つの流れがあった。
一つは、ソン・ゴックミンのひきいる急進民族主義者たちの運動で、これはあくまでフランスのカンボジア再侵略に反対し、「クメール・イサラク」(「自由カンボジア」)を名乗って、ベトミンや、ラオスのパテト・ラオ(「自由ラオス」)と民族共同戦線を結成した。 |

シアヌーク殿下
在位中、過激派のポルポト派に政権を奪われ国民が虐殺される悲劇が
あったがポルポト派の追放で、
今はカンボジアは正常になった。
|
いま一つは、さきに日本から帰国して、首相の地位についたソン・ゴクタンの「自由カンボジア運動」で、彼らは完全独立と共和制樹立をめざしてはいたが、共産主義とはあくまで一線を画し、ノロドム・シアヌークが国王あるいは元首として、中立の名で中国との友好関係をむすんでいることにも強く反対した。
カンボジアは一九四九年一一月八日に、フランス連合のわく内での独立を一応認められていたが、自由カンボジアをめざす運動は依然としてつづけられ、一九五三年一一月九日、ベトナムのフランスに抵抗するとたかいと呼応して、カンボジアは完全独立を宣言した。
この完全独立が一九五四年七月のジュネーブ協定によって裏書きされ、自主独立・中立のカンボジアが名実ともに誕生したのであった。
しかし、一九六〇年スラマリット国王の死後、王位継承者であるシアヌーク殿下は、再び王位につくことを拒否し、国民投票で国民の信任をえた後、憲法を改正して元首(head of
state)をおくことにし、自ら元首の地位についた。カンボジアは王国であるが、正確には国王はなく、シアヌークが元首として、実質的に国王としての地位をもち、国王に属するすべての権限を行使しているのである。
③ カンボジアの中立主義 top
歴史的にも現実的にも、ベトナムとタイとの間にはさまれて、その圧力を受け続けてきたカンボジアが、インドシナおよび東南アジアで独自の地歩を占めているのは、もっぱらその中立主義のゆえである。
少なくともジュネーブ協定以後、カンボジアは一貫して、中立の外交政策を堅持し、一九五七年一一月には永世中立法を公布して、いかなる国との軍事同盟にも参加せず、いかなる国にも軍事基地を提供せず、また、東南アジア条約機構(SEATO)の擁護をうけないことを言明してきた。
中立は、激動のつづくインドシナにあって、わずかに面積で北海道の二倍、人口で東京都の半分にすぎないカンボジアが独立を保持するために必要な最上の路線であることを物語るものであるが、この中立政策を支持する勢力としては、「人民社会主義共同体党」すなわちサンクム(Sangkum)と「クメール王室社会主義青年団」がある。
前者は一九五五年三月に成立、いわゆる政党ではなく、いわば上からつくられた一種の国民組織で、国家・宗教・国王の三位一体を原則とし、もっぱらカンボジアの過去の栄誉の回復を目的としたものである。
後者は一九五七年にシアヌーク殿下が各種の類似団体を統合して結成したもので、全国の州・町村に組織をもち、中立主義、王制を中心とする社会主義の擁護、独立維持を綱領とする青年組緘である。
これをナチスのヒトラー・ユーゲントに似たものとみる人もあるが、シアヌーク殿下としては、カンボジアの壮年層はサンクムに、青年層は「王室社会主義青年団」にもれなく加入せしめたい、というのが理想である。
このような支持勢力のもとに、カンボジアは一九六五年三月にはインドシナ人民会議を首都プノンペンでひらき、これには北ベトナム祖国戦線、南ベトナム解放民族戦線、ラオス愛国戦線党など三八団体が参加した。
また、一九六六年一一月には、アジア・ガネフオ(アジア新興勢力競技大会)を主催して、アジア諸国のスポーツと文化のために大いに新興の気をはいた。
中国を承認し、アメリカとは断交する、というシアヌーク元首の立場は、むしろ「左寄りの中立」ともいわれるが、中立に国家存立の基礎をおいている点で、やはりカンボジアは中立国の典型というべきであろう。
|

11月に催されるメコン河の水まつり
|
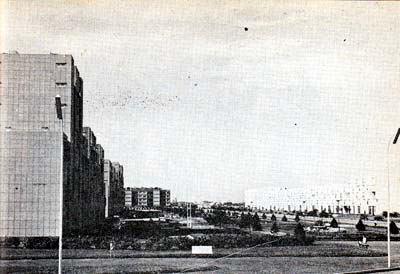
プノンペンのバサ河畔にある近代的なアパートメント
|
④ 社会と生活 top
隣国のベトナム人に比べて、さらにカンボジア人の柔和さ、ときにその無気力さが指摘される。
これは出生から成年にいたるまで、カンボジア人の日常生活を規制している小乗仏教の影響と、いま一つ、歴史的な建造物を遺跡として残した過去の栄光のかげに埋もれた、民衆の長い生活の労苦およびフランス植民地主義の圧制によるものであろう。
いまでもカンボジアの地方農村では、僧侶への喜捨と、寺院・堂塔の維持・新築のために、農民は乏しい収入のなかから、その二〇%ないし六〇%を捧げている。
カンボジアの主要産業は、米、ゴム、トウモロコシ、カポック、コショウ、緑豆、たばこ、木材などの農林産と、淡水・海水魚の漁茶である。
これをみてもわかるように、カンボジア人口の九〇〜九五%は、きわめて零細な農民である。
しかも、商業の流通機構は約五〇万人の華僑に、漁業の網元はベトナム人に完全におさえられている。
一九五六〜五七年の国家建設二ヵ年計画、一九六〇〜六四年の五ヵ年計画でようやく工業化の緒につき、中国やソ連の援助で、ゴム、麻袋、タイヤエ場、ペニア板、紙、織物、セメントなどの工場が起こりかけている。
教育については、カンボジア政府は特に熱心で、小・中学の児童・生徒数も近年いちじるしく増加している。
一九五九年にカンボジア政府は、外人経営の学校にたいして、カンボジア語習得の時間を増加するよう指令した。
大学はカンボジア大学ほか八校がある。
ベトナム戦争をよそに、カンボジアへはアンコール・ワットの観光客が相変わらず押しかけている。
アンコールへの道は三つある。
一つはプノンペン空港から約一時間、シェムリエブ空港で降りて車を利用する方法、
第二は同じくプノンペンから、トンレサップ川を渡って、一路北へ七時間、自動車を飛ばす方法。
第三はトンレ・サップ河を船で約二五〇キロ北上し、トンレ・サップ湖の北岸に出て、ここからジャングルのなかの道を約二〇キロ徒歩でたどる方法である。
首都プノンペンの名は、ペン女王の丘(ブノン)という意味からきたといわれるが、各国からの援助による都市計画で、人口五〇万の首都はその面目を一新しつつある。
ここには、カンボジア人のほか、中国人、ベトナム人、ラオス人、マレー人、ビルマ人、インド人、ヨーロッパ人などが住み、まるで人種見本市の観を呈している。
|
* カンボジアにおける学校数 |
| |
1955 |
1968 |
小学校
中学、高校
大学
学生数 |
2000以下
8
1
|
5000
200
9(37学部)
110万人 |
top
**************************************** |