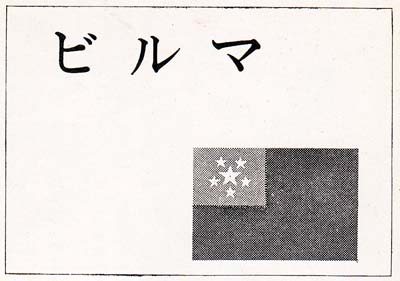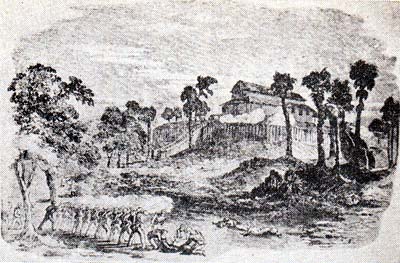|
****************************************
Index
総論(西洋人渡来以前) 総論(西洋人渡来以降)
ベトナム カンボジア ラオス タイ ビルマ マレーシア インガポール インドネシア フィリピン
5 ビルマ(ミャンマー)
ビルマ連邦共和国
政体 連邦共和国
元首 ネ・ウィン大統領
首都 ラングーン
面積 67万8033平方キロメートル
人口 2600万人
主産物 米、落花生、石油など |
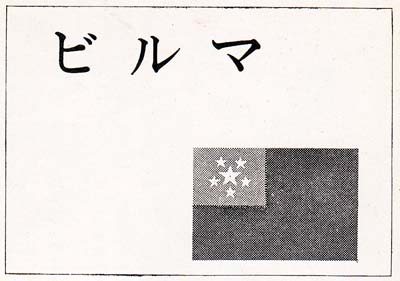 |
① 歴史 top
北はチベット山系、西はアラカン高地、東北はカチン、シャン高原、中央部はベダー高地というふうに地勢がけわしく、それぞれの地域が孤立しているため、ビルマはつねに統一に苦しんできた。
ビルマ統一にある程度作用した要因をあげるとすれば、仏教(小乗)とイギリス統冶の二つをあげねばならないことになる。
しかし、カチン族、カレン族の間にはキリスト教か深くはいりこんでいて、いまもビルマ族との争いがたえず、エギリスの統治も、本当の意味の統一でなかったとすれば、むしろビルマの統一はこれからの歴史的課題である、ということができる。
その地勢のように、ビルマの歴史は起伏の多い歴史であり、起伏はいまもつづいているのである。
① 部族割拠時代 ビルマの占領時代にこの地域に住んでいたのは、インドネシア系種族であるが、北高南低の地勢にそって、紀元前九世紀頃、チベット方面からモンゴル族が南下し、先住種族を追って、それぞれ部族社会を形成した。
主要な種族は、ビルマ族、カチン族、チン族(以上はチベット・ビルマ語族)、モーン・クメール族(非アジア語族)、それにチベット・ビルマ語族よりも早くビルマに南下していたと推定されるカレン族、また、チベット・ビルマ語族よりはるかおくれて(一二世紀)ビルマにはいってきたシャン族などである。
これらの種族の抗争を通じて、モーン族(クライン族)はヘンザダ以南のデルタ地域に、カレン族はシャン高原をこえて南へ流れこみ、その後、上ビルマ地方のシャン族は高原地帯に追いやられ、ビルマ族はイラワジ、サルウィン両河流域の平野に定住することになった。
この対立・抗争は、いまも尾を引いて残っている。
チペット・ビルマ語族のうちピュー族は、ビルマで最初に文字をもった種族といわれ、プロームを首都としてビルマを支配し、中国との間にも雲南地方経由で交流した記録が残っているが、九世紀になって諸部族の対立のためプローム朝は没落した。
このプローム朝のあとに、ビルマ人の王朝として、パガン王朝が出現する。
② ビルマ王朝時代 パガン王朝の始祖アノーラータ王は、中部ビルマにつづいて、東北部のシャン、西部のアラカン地区をも支配下におき、はじめてビルマ全域に統一王国を建設した。
アノーラーター王は、マンダレー南方の未開墾地を開拓して、灌漑をほどこし、小乗仏教を上ビルマ地方に伝えるとともに、一〇五九年にはシュエダゴン・パゴダの建設に着手している。
バガン王朝の末期、一二八七年に元のクビライ(忽必烈)がパガンに侵入し、パガン王朝は滅亡した。
クビライの軍隊は、ビルマに駐留することなく引き揚げたが、敗戦後の混乱のなかからシャン族が支配権をにぎった。
シャン族はパガン王朝の残存勢力が藩王国をつくるのを認めたので、ビルマは約三〇〇年間小王国分立の時代にはいる。
これらの王国はそれぞれアヴァ、ペグー、トンダーを首都として、一三世紀の終りから一六世紀なかばまでつづいた。
このうち、ペグーのクライン王国はヴェニスの商人たちとも交易し、繁栄した。
一方、ドンズー王朝のタビン・シュエティ王は、近隣を合わせて大いに勢威をみせたが、隣国タイとの数次にわたる交戦で、次第に国力がおとろえ、それに乗じて内外からの攻撃をうけ、ついに一七五二年首都アヴァをクライン族に攻略された。
このとき、地方の一世襲支配者(一説には村長であったともいう)アラウンパヤが決起してクライン族を迎え撃ち(一七五三年)、ついにクライン軍をプロームから駆遂して(一七五五年)ラングーンに進出した。
ラングーンは当時ダゴンとよばれ、寒村ではあったが、下ビルマ地方に住んでいるクライン族にとっては信仰の聖地であった。
アラウンパヤは、ダゴンの地名を「戦いの終り」すなわち「終戦」を意味するヤンゴンと改めた。
これが現在のラングーンの名袮のはじまりといわれる。
アラウンパヤ王は、一七六〇年にタイに遠征したが失敗し、帰還の途上病気で亡くなった。
さきのタピンシュエティ王も同じタイ遠征でアユタヤーを包囲したが、帰国後、戦争の疲れと酒毒で精坤が錯乱し、非業の最期をとげている。ビルマにとってタイは一つの鬼門であったのかもしれない。
しかし、アラウンパヤ王の後継者たちは、よく他民族の侵略を阻止し、一八世紀の終りにはアラカン地方を支配下におき、一九世紀のはじめにはインド東北部のマニプール、アッサム地方にまで勢いをのばした。
こうして、アラウンパヤ王朝は一七五二年から一八八五年までつづいたが、その間に第一次ビルマ戦争(一八二四~二六年)第二次ビルマ戦争(一八五二~五三年)があり、ついに第三次ビルマ戦争(一八八五~八六年)で、イギリスによって滅亡させられたのである(第一部「西欧勢力の侵出」参照)。
その経過を簡単にいえば、第一次ビルマ戦争は、すでにタイ北部のチェンマイから、インドのアッサム、マニプール地方に及ぶ広大な領土をもつにいたったビルマと、アラカン国境まで侵略してきたイギリス勢力との正面衝突で、イギリス・インド軍の近代兵器に圧倒されて敗北したビルマは、アラカンとテナセリムをイギリスに割譲し、一〇〇〇万ルピーの賠償を支払い、通商条約を締結することで講和した。
第二次、第三次のビルマ戦争は、イギリスの侵略政策むきだしである。
第二次ビルマ戦争は、ラングーン港に停泊中のイギリス船抑留事件に端を発した。
イギリスはただちに軍艦二隻を出動させて威嚇した。
結局ビルマは敗北して、ペグー地区をイギリスにとられ、イギリスはさきに割譲させたアラカン、テナセリムとベグーの三地区をあわせて、英領ビルマ州をつくった。
イギリスの植民地的侵略のまえに、ビルマの治安は乱れ、いわゆるインド式の強盗「ダコイト」が横行した。
第三次ビルマ戦争は、イギリス系の会社がビルマでチーク材を伐採中に、ビルマ政府がその会社の使用人を逮捕し、チーク材を差し押えたのが、きっかけであった。
イギリス・インド政府の抗議の下心が、ビルマ侵略にあることを知っているビルマ政府は、イギリスの抗議を拒否した。
フランスからの援助を期待する気持もあった。交戦一ヵ月でビルマは早くも降伏した。 |
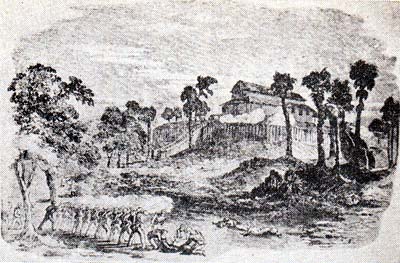
1852年第2次ビルマ戦争・英兵のビルマ・ティンビュウ要塞地略
|
そして、一八八六年一月、イギリスは上ビルマを併合し、つづいて三月、イギリスは「ビルマ全土をインドの一部にする」と宣言した。
ビルマ王朝は滅び、ビルマはインドの一州としてイギリスの植民地になったのである。
これ以後は、イギリスの統治に反対し、抵抗するビルマ人の民族運動の段階にうつるのである。
② 民族運動 top
イギリスの植民地インドの一部となったビルマは、一八九七年四月に正式にインドの一州となり、インド総督がビルマ最高の支配者であった。
一九〇五年、日露戦争で日本が帝制ロシアに勝ったことは、ビルマ(インド)人の民族意識に強い刺激となった。
ベンガルではカーゾン・ラインによる分割反対、国産愛用(スワデシー)の運動がおこったが、日露戦争直後の明治四〇(一九〇七)年ビルマから日本に来た仏僧ウ・オッタマは、京都竜谷大学で教鞭をとり、その見聞にもとづいて帰国後(一九一〇年)「日本に学べ」という運動を提唱している。
ベトナムのファン・ボイチャウによる東遊(ドンズー)運動とほぼ時期を同じくして、この種の運動がおこったことは注目される。その後もオッタマ師は六次にわたって日本を訪れ、多くの日本人がビルマの志士として世話している。
第二次大戦中才ッタマ師のことは、「ビルマ建国の大先覚者」として顕彰されたことがあった。
明治末期の日本へは中国の革命家、インドの革命家たちも亡命してきており、これらアジアの民族主義者たちが、彼らの心琴にふれる何ものかを日本から学びとろうとしたことは貴重な事実であるが、これら志土たちの意識は「祖国復興」の念に燃えたものであっても、イギリス植民地主義を打倒するための社会思想的な立場は不明確で、晩年にはかえって日本のアジア侵略に同調する傾向もあったことは看過できない。
オッタマ師の場合も、その例外ではないようである。 |

ウ・オッタマ師
|
オッタマ師と並んで、ウ・ウィザラという僧正も民族運動の闘士として、一九二九年獄死している。
明確な政治意識と社会思想を育成するのに役立ったのは、ロシアにおける一〇月革命であった。
ビルマの反英運動は、ガンジー時代の非納悦、非協力から、さらに暴動反乱にまですすんだ。
そして、その推進力となったのは僧侶、学生、労働者、農民であった。
一九二〇年代に、運動はさらに前進した。
とくに、一九二九年にはじまる世界恐慌は、植民地住民への大きな重圧と犠牲をもたらし、貪困のなかから民族運動が発展する。
ことにビルマ人は、イギリス植民地主義による圧制のほかに、インド人資本家やインド人地主に搾取される立場にあった。
イギリスから離脱することと同時に、インドから分離することも、ビルマ人の課題であった。
恐慌下の一九三二年、ビルマの青年インテリゲンチャは「タキン党」
*を結成し、労働者・農民によびかけて反英運動を展開した。
*「タキン」党 タキンはビルマ語で「主人」すなわちタキン党員をあらわし、反英独立運動を行なったラングーン大学の学生たちは、自分の名前のまえに好んでタキンをつけていた。
一九三五年のインド統治法(いわゆる三五年憲法)は、ビルマをインドから切り離して「凖自治領」とすることを決めた。
この統治法作成のため、一九二八年に任命されたサイモン調査委は会の報告(一九三〇年)も、ビルマとインドとの即時分離を提案していた。
サイモン卿がとくにビルマに好意をもったわけではなく、人種も、宗教も言語も、習慣も、風俗も異なるビルマとインドを一つにすることに問題があり、イギリスは得意の分割統治で、ビルマを支配したほうが都合がよいと考えたからであろう。
一九三五年の統治法にもとづいて、一九三七年ビルマはインドから分離した。
イギリスは直接ビルマを統治することになったのである。
三五年の統治法によって、三六年(一一月)にビルマでは総選挙が行なわれた。
選挙で第一党を占めた連合党のウ・バ・ベが組閣に失敗したため、一九三七年バー・モー博士が連立内閣を組織した。
三六年は米が凶作で農民が極度に窮乏した。極東では中国にたいする日本の侵略戦争が日ましに拡大するなかで、ビルマでは反英運動が熾烈に燃えあがった。
ストや学生デモの高まりのなかで、三八年バー・モー内閣は瓦解した。
タキン党のなかの革命分子は、一九三九年ビルマ共産党を組織した。
第二次大戦が勃発し、日本軍がビルマを占領した。日本が独立を促進したのではなく、ここでも日本軍の占領支配にたいする抵抗闘争のなかから、迂余曲折を経て独立への途がきりひらかれていくのであった。
③ 独立への途 top
一九四二年三月(八日)ラングーンに「入城」した日本軍は、同五月全ビルマを占領下におき、同六月(四日)軍政を布告し、同八月二日)バー・モー博士を行政長官に任命し、翌四三年八月(一日)、ビルマの「独立」が宣言され、バー・モー内閣が組織された。
ウ・オン・サンは国防相になった。
こうしたなかで、いま一つ別に本当のビルマ独立への坑道がきりひらかれつつあった。
イギリス官憲の目をぬすんで、日本の士官学校に学んだウ・オン・サン以下三〇名の戦士たちは、表面は日本軍と協力するかたちで、ビルマ独立義勇軍を組織して、イギリス軍とたたかった。
イギリスをたたき、日本軍を追っぱらったときに、はじめて、ビルマの独立がくる。
その日のために、ビルマ人は武器を手に入れ、武器の扱いに習熟していなければならないことを、若いビルマ独立の「志士」たちはよく知っていたのである。
それにしても、日本の「大東亜共栄圈」に託したビルマ人たちの夢と期待は無残にうちくだかれた。
目にあまる日本軍の残虐行為、ビルマの宗教や習慣にたいする完全な無視と、ビルマ人にたいする差別待遇、ビルマ人の政治的に自覚した分子、心ある人たちは、ひそかに運動の方向を地下抗日に転じた。
まず日本軍をたたき、そしてイギリスを追っぱらうのでなければ、ビルマ人たちは生きていけないのだからである。 |

ウ・オン・サン夫妻
今のミャンマートップのアウンサン・スーティー女史は、この夫妻の子。
|
四四年七月、日本軍はインパール作戦で完全に敗北した。
同八月ビルマ陸軍の一部、ビルマ革命党(のちの社会党)、ビルマ共産党、その他の諸政党、学生、労働者、農民など、各党・各派・各大衆団体・個人を糾合して、「反ファシズム人民自由連盟」(AFPFL)が結成された。
日本軍にたいする全ビルマ的な総武装蜂起を展開するため、オン・サン将軍やビルマ共産党のタキン・タントンらは、一九四五年三月、ひそかにラングーンから姿を消した。
ビルマ独立軍は、日本軍から手にいれた武器で、ペグー駐屯の日本軍を攻撃した。
四月には日本軍は傀儡のバー・モーらと一緒に、モールメンに都落ちした。
そして、翌五月、イギリス軍は「反ファシズム人民自由連盟」の先導でラングーンにはいった。
一九四五年八月一五目の無条件降伏をまつまでもなく、少なくともビルマでは五月に独立軍が事実上ビルマ独立を回復していたのであった。 |

タキン・ミヤがモールメンで最初に組織したビルマ防衛軍
|
しかし、事実上の独立から、完全な独立にいたるまで、ビルマは貴重な犠牲と流血の代償をはらわなければならなかった。
日本の降伏後、四五年一〇月(一六日)、元のビルマ総督R・D・スミスが、三年半ぶりでラングーンに戻ってきた。
戦勝の実績にもとづいて、「反ファシズム人民自由連盟」は、ビルマの即時独立を主張した。
ビルマ総督は、これに応えないばかりか、当時英領ウガンダに軟禁中のウ・ソー元首相を釈放し、ミョチット(愛国)党を再建させ、全ビルマ人の声望を集めているオン・サンに対抗させようとさえ図った。
伝統の「分割統治が忘れられないのである。
イギリスが新たに設置した行政評議会の樹成について、「反ファシズム人民自由連盟」の主張がいれられず、これに参加を拒否されたオン・サンは旧軍人を組織し、「人民義勇軍組織」(PVO)をつくった。
戦後の不況のなかで、ビルマの国民とくに農民の反英運動が高まった。
「反ファシズム人民自由連盟」をボイコットしたイギリス当局は、反対にビルマ国民からボイコットされるにいたった。
翌四六年、ビルマには依然として不況がつづき、しかも、そのなかで自分の権益ばかりをねらうイギリスの政策にたいして、労働者や学生、ついに警官から官吏にいたるまでが政治ストにたち上がった。
四六年九月、ゼネストを中止させるために、イギリス当局は「反ファシズム人民自由連盟」の代表を大量に新行政評議会に入れ、ビルマには共産党代表をふくむ一種の中間内閣が成立した。
オン・サンは副議長と国防・外務の大臣を兼任した。
「反ファシズム人民自由連盟」は、四六年一一月、①四八年一月以前にビルマに独立をあたえること ②四七年に制憲議会のための総選挙を行なうこと、をイギリスに要求した。
アトリー主相はこれについてビルマ代表と討議する用意がある、とこたえた。
一九四七年一月、オソサンを団長とするビル了代表団は、ロンドンでビルマ独立に関する円卓会議に参加した。
オン・サンとアトリー両代表の間に協定が調印された。
しかし、よくあることだが、ビルマ代表団のなかのウ・ソー(行政参事会員)やタキン・バ・セイン(ドーバマ党総裁)は、イギリスの意向を察し、また、オン・サンの失脚をねらって、反対運動をおこすために、脇定に調印しなかった。
獅子身中の虫である。
はたして、ウ・ソンらは帰国後、協定にきめられた四七年四月の総選挙をボイコットした。
こうした右派政党が不参加のまま総選挙は施行された。
「反ファシズム人民自由運盟」は大勝して、二二〇議席中の一九〇、ビルマ共産党は九を獲得した。
六月(一〇日)から制憲議会が召集された。「ビルマはビルマ連邦と称する独立共和国となるべきこと」が満場一致で可決された。
この制憲議会開会中の七月一九日、評議会の会議室で閣議を開いていたとき、オン・サン将軍以下六名の参事会員が、暴漢に襲われ、右翼のテロで暗殺された。
一味はイギリスによってオン・サンの対抗馬に仕立てられ、ロンドンの円卓会議でも協定に調印しなかったウ・ソーの教唆によって、オン・サンらを殺害したものであることが明らかになった。
ウ・ソーは翌四八年五月絞首刑に処せられたが、右に述べた経緯からみて、オン・サンを殺害した真犯人は、イギリス植民地主義である、といえないことはない。
事実、ビルマ人はこのように考えていたし、この事件後、イギリスとむすぶビルマ右翼政党は人気か失い、急速に凋落した。
オン・サンの死は、ビルマ完全独立への波をいっそう大きく高く盛り立てた。
オン・サンの後継者としては、「反ファシズム人民自由連盟」の副委員長タキン・ヌー(後のウ・フー。ウは英語のサーにあたる名称)がえらばれた。
ビルマ制憲議会は、九月(二四日)憲法草案を満場一致で可決、タキン・ヌーはロンドンに飛んで、イギリスと交渉し、同一〇月(一七日)イギリスはビルマにたいする主権譲渡の条約に調印した。
これにもとづいて、ビルマは一九四八年一月四日、イギリス連邦に属しない、完全独立の共和国となった。
インドが「革命なしに」共和国になり、(インド・パキスタンの分離)独立決定後、ヒンドゥー教徒と回教徒の血の修羅場を現出し、ついに非暴力主義者ガンジーがその血祭りにあげられたのに比べ、ビルマは戦争のなかで独立を戦い、独立前にオン・サンの血をささけて共和国になった、ということができる。
月なみの表現をかりていえば、「もし、オン・サンが生きていて、独立後の建設にそのまますすんでいたら、ビルマのコースは今日とはちがったものとなっていたであろう」。
それほどオン・サンはビルマ人の期待と信頼をうげていた。
いまもオン・サンの肖像写真がビルマの官庁や集会所その他にかざられているのは、そのことをよく物語っている。
こうして、一八九七年に「ビルマがインドの一部となった」ときからの民族運動は、抗英・抗日さらに抗英の過程を経て、ようやく独立のゴールに入った。イギリスのビルマ侵略にたとえていえば、それは第一次独立戦争、第二次独立戦争といってもいいほどの激しい民族解放の戦いであった。
しかし、タキン・タントンらの白旗共産党は、タキン・ヌーとアトリーのビルマ独立に関する協定ならびに付属書の防衛協定は、①イギリス帝国主義の権益を依然として認め、②独立後のイギリス軍に関する規定もあいまいであることなどにより、ビルマの完全独立の要求をみたすものでないとして、独立後の四八年三月二八日、全面的反乱とゼネストを行なった。
しかし、五〇年五月に、反乱は鎮圧された。
④ 社会主義へのビルマの途 ――政治と経済――
top
独立後のビルマは、政治的・経済的に多くの困難に直面した。その第一は政治的不統一の問題であり、第二は少数民族の分離運動の問題であり、第三は社会主義建設途上の問題である。
抗日のための統一戦線として一九四四年に結成された「反ファシズム人民自由連盟」は、ビルマ独立に重要な貢献をしたばかりでなく、四六年(一〇月)に共産党、四七年(一月)に一部右派勢力が離脱したほかは、独立後もひきつづきビルマ政権の支柱であった。
ところが、一九五八年六月、その指導者を中心に主流が二つに分裂した。
ウ・ヌーおよびタキン・ティ派は清廉派とよばれているが、これは「対外的にはひきつづき厳正中立政策をとり、経済面では農業および林業に優先的地位をあたえ、工業計画の実施にあたっては外国からの投資を奨励し、国内平和の問題では、いかなる反乱分子とも交渉を行なわない」ことを主張している。
清廉派の名の出たのは、同派がひきつづき「反ファシズム人民自由連盟」の綱領の一つである官界の粛清をかかげ、ウ・ヌー自身がとくに熱心な仏教信者であるところからきたのであろう。 |

官庁か並ぶラングーン市街
|
一方、ウ・バ・スェーおよびウ・チョウ・ニェン派は安定派とよばれている。
これは「(外交面では)非同盟中立政策を推進し、平和地域を拡大し、経済面では計画にしたがって近代化された農業と工業とを同時に発展させる」ことをかかけている。
外交の中立には変わりはないが、清廉派が農・林業優先であるのにたいし、安定派が工・農同時推進あるいは近代工業化を重視している点が大きな相違である。
清廉派が連邦党と改称してから、安定派が反ファシズム人民自由連盟を称している。
この対立がそれぞれ傘下の大衆団体にまで波及し、政情不安になったことを理由に、五八年九月(二六日)に軍部が無血クーデターを行ない、ネ・ウィン参謀総長が首相の地位についた。
六〇年二月(六日)、軍部の監視下に総選挙が行なわれ、清廉派が圧勝し、その四月ウ・ヌー内閣が成立した。
ビルマ憲法では、仏教の特殊的地位が認められているが(二〇、二一条)、ウ・ヌー首相は、ビルマ社会主義は仏教とマルクス主義(唯物史観)の結合によって実現されるとし、また、仏教の国教化をはかった。
仏教徒以外の人たちから猛烈な反対があったのは当然だが、ウ・ヌー首相はその反対を緩和するために国家の祝祭日の判定その他について反対派と妥協をこころみたので、今度は仏教徒の側から反撃をうけ、騒然たる事態になった。
また、カレン族、シャン族など少数民族の問題が、きわめて深刻な様相をおびてきた。
カレン族はチベットから「赤熱の砂の河」を渡って南下した種族で、イラワジ河下流およびサルウィン河流域の南シャン州方面に住み、民族自衛組織(KNDO)をもって、モーン族の自衛組織(MNDO)とともに反政府運動をつづけている。
シャン族もビルマ人との融合ができない点から、離反の傾向が強く、それにシャン州の土候たちがあるいは民衆に迎合し、あるいは中央政府との利権取引きに分離を画策するなど、複雑な動きを示してきたうえに、タイとの国境山岳地帯には、中国の国府軍残党がいて反共宣伝を行なうなど、中央政府にとってきわめて厄介な問題であった。 |

ウ・ヌー首相
|
少数民族ではないが、ビルマ共産党もタキン・タン・トンらの白旗共産党(いわゆるスターリン派)とタキン・ソーらの赤旗共産党(トロッキー派)に分かれ、武装闘争停止と国内平和確保のための話し合い、あるいは少なくともその対策が独立以来の政治的課題であった。
このような課題が、ウ・ヌー内閣によって少しも解決されない、あるいは解決に着手されないのをみて、一九六二年三月(二日)、ネ・ウィン大将は再びクーデターを決行、ウ・ヌー首相以下全閣僚を逮捕し、軍部首脳(一七名)からなる革命評議会が権力を掌握して、ネ・ウィンはその議長になった。
これは一種の軍部独裁政権である。革命評議会は憲法を停止し、四月には「社会主義へのビルマの途」について声明をだし、同七月には「ビルマ社会主義綱領党(BSPP)の要綱」が発表された。
はじめ、ネ・ウィンはビルマ各政党の統一戦線結成を提案したが、既成政党はこれに賛成しなかったので、革命評議会の指導のもとにこの新党を結成したのであった。
翌六三年一月(一七日)、ビルマ社会主義綱領党は、「人間とその環境の相互関係の体系」という標題で、同党のイデオロギーすなわち革命評議会の理念を明らかにした。
それによると、「社会主義へのビルマの道によって、正義がゆきわたった豊かな社会主義社会を建設する」ために、つぎの三つの目標をかかげている。
①経済的には、人間による人間の搾取を排除し、繁栄するゆたかな社会を築く。
②政治的には、社会主義的民主主義を実現。
③精神的には、国民の道義を高め、精神的幸福を達成する。
そして、「事象と事象、人間の肉体と精神、人間とその環境の間には、つねに相互関係の哲学が存在し、……社会の問題を解決するには、『人間第一主義』のモットーを採用しなければならない」と強調している。
具休的には、この社会主義計画は、農・工業などの重要生産・配給・輸送・通信・外国貿易などの国有化を通じて推進された。
六三年一○月(一八日)に公布された「社会主義経済制度樹立の権限を政府に付与する新法案」は、企業の国有化だけでなく、商品の卸・小売価段の決定権をも政府にあたえたもので、ビルマ鉱山でビルマ石油の接収や各種企業の国有化につづいて、六四年三月から四月にかけて、私営商店も国有化された。
これは商品の国内配給および輸出入を組織的・統制的に行なうことを目的としたもので、国営商店は、「人民商店」(PSC)の名でよばれ、役所と同じように、午前九特に店を開いて、午後四時に店をしめるのである。
ビルマ人口の七〇%が依存している農業にういても同様で、農地の割当権を地主の手から、農民によって編成された農地委員会へ移し、従来の小作料の束縛から農民を解放し保護するとともに、農業の集団化を奨励した。
これらの改革は、ほとんど鎖国的な情況のもとに推進され、中立政策を堅持している関係上、中国・ソ連およびアメリカなどからの援助も受入れていたが、官僚主義的な国有化ということだけでは、生産の安定・向上はかならずしも実現できないようである。
たとえば、ビルマは米とチークの農林国で、農林業生産が工業生産の約二倍といわれるが、かって年間三〇〇万トンの輸出実績をもつビルマ米も、年間一〇〇万トン台に後退している。
人民商店の品物の出回りもかならずしもよくないし、国営貿易の非能率も指摘されている。
また、共産党二派との平和の話合いも成果をあげていない。
最近では、白旗共産党の指導する武裝闘争がビルマ各地に波及しつつある。
土地固有化法によって、インド人不在地主(チェティヤー)のもっていた土地のうち、約三三五万エーカーが小作農に分配され、また、ビルマ最大といわれたイギリス資本によるビルマ鉱山会社、ビルマ・イギリスの合弁によるビルマ石油会社などが国有化され、さらに、これまでインド人、華僑によってにぎられていた企業や商品の国内流通機構にいたるまで、「人民商店」によって国有化したが、一種の国家資本主義的統制であって「社会主義的」改革であるとはいえない。
たとえば華僑の問題をとりあげてみょう。
ビルマにいる華僑は約三五万人程度で、数としてはインドネシア、タイなどに比べて、けっして多くはない。
しかし、ここでは華僑が他の地域にみられない一つの特色をもっている。
それは第二次大戦を契機として、華僑がインド商人にかわって、ビルマの経済機構に大きくのりこんできたことである。
インド人は地理的な関係と、イギリスとのつながりでビルマでは経済的に大きな勢力をもっていた。
耕地(不在地主として)、石油・錫その他の鉱山、金融、貿易面でも、ビルマ人は完全にインド人の下風におかれていた。
ところが、第二次大戦中にインド人のほとんどは、日本軍を恐れて、インドへ引きあげてしまった。
そのあとの空白を埋めたものとして、日本軍の占領下に、華僑はインド人にかわって着々と経済的基盤をきずきあげたのである。
戦後イギリス人と一緒にインド人が、ビルマに戻ってきても、戦争中の失地回復は容易でなかった。
それほど華僑の勢力はビルマ経済に食いこんできていたのである。
ビルマ独立後、潜在的な資本の比率からいえば、インド人資本六〇%、華僑資本三〇%、ビルマ民族資本一〇%とみる人もある。 |

ラングーン市のインド人街
|
いま、ビルマの社会主義経済、国有化のまえに、インド人資本とともに、華僑の経済的支配力も無力化されつつある。
木材、米穀、鉱物、ゴム、茶、製油、タバコなどの企業から流通にいたるまで、国有化がすすむにつれて、華僑資本はビルマ民族資本と結託し、華僑の名を完全にひそめ、ビルマ大資本の名義で、ひそかに活動の分野を見出そうとしている。
それほど経済的な影響は強かったのである。
社会主義国有化のスピード化とともにビルマ政府が華僑および華僑資本に弾圧を加えたのは、中立政策の立場から中国本土への態度を変更したものとみられている。
しかし、ビルマ華僑には、雲南省あたりから陸路南下したものと、シンガポールあたりから北上してきたものとの二派があり、なかにはシャン州辺境の国府軍残党とのつながりをもつものも皆無ではないので、ビルマ政府は一面では、華僑政策に慎重を期している。
さて、最近、鎖国的経済による生産の低下と停滞を打開するため、ビルマのアメリカへの接近なども伝えられているが、「社会主義へのビルマの途」という言葉が示している通り、あくまでビルマ的自力更生を基本としながら、「人間とその環境の相互関係」を積極的に変革・向上させることか、今後の課題である。
最後に日本との経済関係についていえば、戦争賠償と経済協力についての協定が一番早く成立したのがビルマとであった。
賠償の総額は、はじめ賠償二億ドル(七二〇億円)、経済協力五〇〇〇万ドル(一八〇億円)であったが、後から成立したフィリピン、インドネシアにたいする賠償額に比べていちじるしく少額である、というところからさらに第二次の賠償(一億四〇〇〇万ドル)と協力(三〇〇〇万ドル)が追加された。
これにもとづいて、日本はバルーチャン発電所や卜ングー・ロードなどの建設を行なった。
|

シュエダゴン・パゴダ
|

ペグーの夜釈迦(様式は994年にさかのぽる)
|
⑤ 社会と文化 top
ビルマは仏教の国である。仏教が政治理念とむすびついた点でも、また、仏教が日常生活の秩序や習俗にしみこんでいる点でも、仏教の国である。国勢調査によれば、ビルマ人の九五%、シャン人の九九%、カレン人の五〇%、カチン人の四〇%が仏教徒である。 |
カレン、カチンに仏教徒が少ないのは、一九世紀末以来、アメリカ人宣教師が熱心に伝道した結果といわれる。
このように仏教の信仰が広くいきわたり、しかも、ビルマの仏教はセイロン、カンボジア、ラオス、タイなどと同じ南方・小乗仏教なので、生きものを殺さない風習が徹底し、蚊やノミやシラミにいたるまで、生きとし生けるものを殺すのは仏の規律にそむくものとみられている。
男の子は、大体一二~一三歳になると、剃髪・得度して、寺院に入る。
この出家生活は長いのもあれば、ごく数日という短いものもあるが、これはビルマ人が一度はくぐらねばならない人生の門である。
寺院生活では経を読み、托鉢をし、み仏に仕える。これと同時に、ビルマの寺院では男の子供たちに、読み書き、算数を教える風習があり、この寺院生活と寺小屋教育のおかけで、ビルマ人の識字率は、他の東南アジア諸国よりはるかに高く、男子は約七〇%、女子はこれよりかなり低い。
しかし、字の読み書きができるかどうかにかかわりなく、ビルマでの婦人の社会的地位は高い。
寺院へ入るための男の得度式とならんで、女が一二~一三歳になると、耳たぶに孔をあけて、耳輪をつける。
これを穿耳式(ナドウィン)とよんでいるが、このほうには宗教的な意味はない。
仏教・キリスト教のほかに、回教・ヒンドゥー教・精霊崇拝などがあるが、いずれも仏教に比べると微々たるもので、有名な水祭りをはじめ祭日も仏教にちなんだものがもっとも盛大である。
水祭りは、四月のビルマ暦正月を迎えるにあたり、いわば大晦日へかけて、その前の四日間、お互いに「清浄な水」をかけあって楽しむ祭りで、これと七月中旬の花祭り、一〇月下旬の火祭りがビルマの三大祭りである。
花祭りは、きれいな花をたずさえて寺院に詣でるもの、火祭りは雨季が終わって乾季にはいったことを喜び、感謝する祭りである。
仏教の祭日には、仏教的な舞踊と歌謡を組み合わせた「ザツ・ポエ」とよばれる一種の演劇が上演され、また、日本の盆踊りのような民謡踊りもあって、夜通し踊りつづける。
仏教といえば、ビルマの仏塔(パゴダ)はとくに有名である。
ラングーンのシュエダゴン・パゴダをはじめ、パガン、マンダレー、ペグーの各地には古くからの遺跡があり、あるいは白く、あるいは金色燦然と、パゴダの屋根や尖棟が光り輝いているのが、ビルマの風景を代表するものとなっている。
パガン王朝に築かれたものが多い。ベグーのシュエモウドゥ・パゴダの仏陀寝像は寝釈迦として有名である。
全人口の三分の二以上がビルマ語を使っているが、とくに独立後一九五二年からは公用語としての英語を禁止し、外交文書以外の政府公文書、法廷用語もビルマ語である。
ビルマ語はアルファベッドが三三(子音三二、母音一)その配語法は、日本語やモンゴール語と同じで、中国語や英語のように後へかえらない。
ビルマ族のほかのカレン族、シャン族、チン族、モーン(タライン)族、カチン族も、それぞれ自分の言語をもっている。
カチン語には、固有の文字がなかったのを一九二一年、アメリカ人宣教師夫妻がカチン語をローマ字化してつくったといわれる。ビルマ語あるいは英語によるものでも、ビルマの文芸作品には、まだ見るべきものが少ない。
ビルマ人は米を主食として、一日に二回食事をとる。
もちろん、フォークや箸はなく、いわば天然の五本の箸ともいうべき右手の指をつかって食べる。
男も女もロンジーを日本の腰巻ふうに、身体にまきつけている。
高いところに上る建築工事の労働者でも、ロンジーをつけているところをみると、少なくとも着るものについてのビルマ人のナショナリズムはきわめて強いようである。
top
**************************************** |