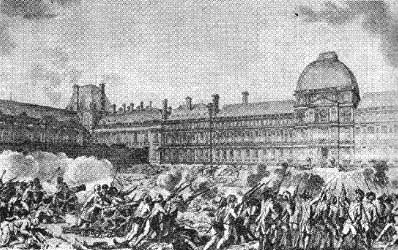|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12
世界の歴史10――市民革命の時代
5 一つの時代の終わり
――ルイ十六世とマリー・アントワネット(2)――
5.1 ラ・マルセイエーズ、フランス国歌
top
一七九一年十月、新しく成立した立法議会は、立憲王政派と共和派とによってしめられていたが、この議会が直面した最大の問題は戦争であった。
さきの国王逃亡事件のとき、王家と関係ができて、これに同情するバルナーブらは、すでにルイ十六世やマリー・アントワネットに忠告をしていた。
「王家の地位はともかく安泰なのですから、不満はおありでしょうが、革命をお受け――入れください。
そして国民の信頼を回復していただきたいと思います。いま王家がきらわれていましても、人心というものはやがて変わってまいりましょう。」
しかし王も王妃も、革命なるものとなんらかの関係がある人物の言葉を、ききいれようとはしなかった。
頼るのは依然として内外の反革命勢力だけである。マリー・アントワネットはおだやかなブルジョワ的な議会をさえ、「無頼漢(ぶらいかん)、気違い、けだものどもの集まり」とよんではばからなかった。
そして宮廷は、戦争こそが世の中をむかしに返す手段であると思うようになっていった。
王も王妃も考える。
「いま外国と戦争すれば、十中八、九、フランスは負ける。
するとフランス人は極端から極端へ走る国民であるから、革命勢力に見きりをつけて、王権をしたってくるであろう。
もしフランスが勝つとすれば、主戦的であった王家は権勢を回復するであろう。
どちらにころんでも外国からの干渉が革命をおさえて、王権をよみがえらせるにちがいない。」
好戦的であったのは宮廷だけではない。
ジロンド派という主戦論のグループもあった。
ジロンドとは県名で、そこから選出された議員たちが加わっているので、そうよばれた共和主義の党派である。彼らは戦争によって、いっきょに内外の反革命勢力を倒してしまおうと考える。
議会の大勢もこの考えに賛成である。またジロンド派は革命をフランスだけにとどめず、その自由、平等を国境をこえてひろめてゆきたい、いまの言葉でいえば「人民解放の戦い」を行ないたいと熱望していた。
ジロンド派の中心人物ブリソー(一七五四〜九三)はいう。
「新しい十字軍の時代がやってきた。世界の自由の十字軍である。」
そしてジロンド派の議員たちは、中流のインテリ・ブルジョワ出身だが、彼らは船主、貿易商、銀行家、大商人など実業ブルジョワと関係があり、したがって戦争はこうしたプルジョワにとって、さらに金をもうけるチャンスであった。
王家がたいせつな立憲王政派のバルナーブなどは、戦争になれば宮廷はかえって外敵と同一視されて国民に憎まれてしまうし、また戦争の混乱は急進勢力を有利にするだろうと、ルイ十六世に進言したが、ききいれられなかった。
同じ立憲王政派でも、人気が落ち目のラ・ファイエット将軍などは、戦争を軍の発言権をます好機と考えていた(彼はやがて敗戦と革命の急進化につれて、祖国をすてて亡命してしまう)。
一方、革命フランスの敗北のみによって救われる亡命貴族たちは、南ドイツのコブレンツを拠点として、しきりに挑発をこころみていた。
112
こうしたとき、あまり戦争を欲しなかった神聖ローマ皇帝レオポルト二世が、一七九二年三月に急死し、その後継者でマリー・アントワネットの甥にあたる二十四歳のフランツ二世は、慎重な父とちがって好戦的である。
ロシアも――参戦はのちのことになるが――軍事干渉に積極的であった。
ついに一七九二年四月二十日、ルイ十六世は議会におもむき、オーストリアに宣戦した。
それ以後、革命の進路を大きく左右し、そしてナポレオン時代にひきつがれてゆく、長い戦争の始まりである。
これよりさき、一つのエピソードがある。
それは国王逃亡失敗後、スウェーデンに帰っていたフェルセンは、愛する女性をもう一度救出するため、「革命史全体を通じてもっとも果敢な冒険の一つ」を演じたことである。
一七九二年二月十三日、変装したこの男は合鍵を持っていたらしく、警戒厳重なテュイルリー宮に「いつもの道をとって」しのびこんだ。
このあたり正確なことは不明であるが、「彼女の部屋はすばらしい、そこへ残った」というフェルセンの手記の一節は、解しようによっては、その夜から翌日にかけての微妙な事柄を推測させるであろう。
一方、フェルセンの報告によれば、十四日の夕刻六時、彼はルイ十六世に会い、新しい逃亡計画を示したようであるが、王は不可能と考え、またパリにとどまるという国民に対する約束から、これを拒否したという。
その夜、この思いもかけぬ来訪者はふたたび変装して、闇のなかに消えていった。
これがマリー・アントワネットとフェルセンの最後の逢瀬であった……。
さて開戦はしたものの、フランス軍は指揮官に亡命する者が多く、兵員も軍備も不十分であるうえに、やがてプロシア軍もオーストリア軍に加わって攻めてきた。
革命側はいそいで国民軍や義勇兵をつのり、「祖国の危機」に対処しなければならなかった。
そして大衆がしだいに兵士として参加するようになったが、彼ら兵士たちがまず歌うようになったのが、いまのフランスの国歌「ラ・マルセイエーズ」である。 |

国民軍の兵士たち、彼らがいまのフランス国歌
「ラ・マルセイエーズ」を歌うようになった
|
こんな血なまぐさく、悲壮な国歌はどこにもないといわれる。
「立て、祖国の子ら、栄光の日はきた、われらに対し、暴虐(ぼうぎゃく)の血ぞめの旗がせまる……」
オーストリアに対する宣戦の知らせは、一七九二年四月二十五日、ドイツとの国境に近いストラスブール市で公表された。
このとき市長は自宅に招いた軍人たちに、適当な国民歌がないことをうつたえ、同席していた工兵大尉ルージェ・ド・リールに、これをつくることを求めた。
市長は、大尉が詩や音楽の才にめぐまれていることを知っていたのだ。
はじめは断わっていたルージェ・ド・リールも、ついに決意し、その夜のあいだ自室にひきこもって、歌詞と旋律とをつくり、二十六日市長邸で発表した。
その原名は「ライン軍軍歌」であったが、南方のマルセーユ方面に伝わり、そこからやって来た兵士たちが九二年夏パリに広めたので、ラ・マルセイエーズとよばれるにいたった。
なお、これがフランスの国歌と確定したのは、七月十四日の国祭日とともに、十九世紀後半第三共和政下のことである。
ところでルージェ・ド・リールはその後、革命の急進化についてゆけず、軍人をやめ、彼がつくった詩やオペラは相手にされず、性格もひねくれ、金に追われ、一八三六年七十六歳でさびしく死んだ。
その時、だれ一人として彼の名をいう者も、知っている者もなかったという。 |

フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」
をつくったルージェ・ド・リール
|
5.2 王権の没落 top
革命フランスの劣勢ではルイとマリー・アントワネットの賭(かけ)は成功するであろうか。
パリの革命勢力にかこまれている以上、それは、つまり王権の復活は、はじめから無理な話であった。
そのうえ王妃はまたもみずから、情勢を悪化させてしまった。
パリの革命家、大衆、地方から集まった連盟兵(国民軍兵士の別称)たちの敗戦に対する反応、すなわち祖国と革命の防衛に必死になっている人びとが抱く、反革命の動きに対するはげしい反感――それらに恐怖をおぼえた王妃は、敵軍の総司令官ブラッシュバイク公に、パリに圧力をかけてくれるように要請する。
「早くしてください。でないと、ルイは二十四時間内に殺されてしまうでしょう。」
ブランシュバイク公はこれを鵜(う)のみにしたらしく、七月二十五日、ある亡命貴族が書いたといわれる宣言を発してしまった。
それは「もし王室に少しでも危害が加えられるならば、パリ全市を完全に破壊して、永久に記念となるような復讐をするであろう」という意味のものである。
これもまた逆効果であり、宣言がパリに伝えられると人民たちは激昂し、恐れをいだいた。
パリの諸区から国王廃位の請願が議会に提出されたが、八月九日の期限がきても、議会はなにも答えなかった。
その夜パリの町には警鐘がなりひびき、各区の代表者たちは市庁に集まり、革命初期にできていた合法的なパリ・コミューンにかわって、「蜂起のコミューン」がつくられた。
|
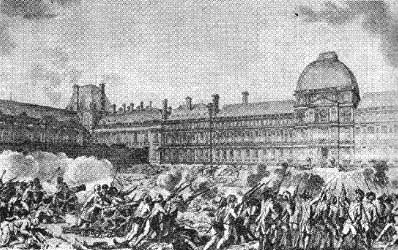
八月十日のテュイルリー王宮襲撃――防備の兵士たちは寝返り、
スイス人の傭兵たちは応戦したが、やがて王命で銃火をおさめた。
|

国王一家はダンブル塔に移された
ダンブル塔のルイ十六世
|
八月十日朝、暑い陽光がきらめきはじめるころ、場末の町などの急進的な民衆とマルセーユなどの連盟兵たちが、テュイルリー王宮攻撃にうつった。
防備の兵士たちは寝返り、スイス人の傭兵たちは応戦したが、やがて王命で銃火をおさめ、攻撃側は王宮に侵入した。
性格上からか、流血にたえられなかった王の弱気は、かえって何百人ものスイス兵の死と、王権の没落を招いた。
少なくともスイス兵は沈着に整然と、勝利の見込みをさえもって抵抗していたのであるが……。
しかも蜂起がはじまるとすぐ、ルイ十六世は王族とともに宮殿をすてて、近くの議場へ難をさけていた。
議員たちのなかには王に対する同情の気持が強かったが、勝ちどきをあげて議場におしかけてくる民衆の圧力をまえにしては、わが身の危険をも感じざるをえない。
こうして、議会はまず「君主権の停止」を宣言した。つづいて国王一家はダンブル塔に移された。
この陰うつな塔に入れられるときいて、王も王妃も恐怖感で思わず身ぶるいした。ダンブル塔は高い石の塔で、もう長いことだれも住んでおらず、また中世的な要塞向きの建物であるから、元来ひとが住むのに適したところではない。
八月十三日、興奮した市民たちの罵声や怒声のなかを、王夫妻と王子、王女、王妹はダンブル塔に護送された。
王にあてがわれた部屋は、大急ぎで掃除されたが、そのむさ苦しさには、ようすを見にきた市長が驚きの声をあげたほどであった。
おわびをいう市長に対して、王はあきらめきっていたのか、なんら不愉快な表情もしなかった。
しかし日がたつにつれて慣れてくると、この生活も不愉快ばかりではなかった。
いや、恐ろしい日もあった。
一七九二年九月二日、ベルダンの要塞が包囲されたという知らせがパリにとどいた。
敵軍のパリ進撃の道が開けるのだ。
恐怖感や焦燥感から群集心理にかられた市民たちは数日のあいだ、そこここの監獄をおそって、反革命の容疑者や無関係なほかの囚人たちを殺してまわった。
この「九月虐殺」の犠牲者のなかに、王妃の親友ランパル夫人もまじっていた。
群衆は彼女の死体を裸にしてひきずりまわし、その生首を槍の先に刺して、ダンブル塔におしかけた。
当時、民衆はとくに武器として槍を使用していた。
王女はのちに語っている。
「母の気力がぬけたのは、このときだけでした。」 |

監獄に乱入した民衆――民衆も敵軍の侵入を恐れていた
|
5.3 ルイ十六世の裁判 top
一方、新しい事態に応ずるため、立法議会は解散し、普通選挙で国民公会が選出された。
一七九二年九月二十一〜二十二日、国民公会は王政の廃止を宣言し、共和政体をとり、ここに八月十日事件による実質上の王政廃止は正式なものとなった。
その直前、九月二十日、バルミーの戦いで、フランス軍は侵入してくるプロシア軍を撃退した。
これは新しい国民的な軍隊が、伝統的な王の傭兵隊に対してえた最初の勝利として重要であるとともに、戦局の転機ともなった。
こう書くと大決戦のようだが、三回ほど砲撃がかわされ、決定的な勝敗はなかった。
敵をあまくみていたプロシア軍は、意外な抵抗にたじろいで軍を返したのだ。
当時プロシアはポーランド分割をめぐって、東方に関心をうばわれており、西方に全力をそそげなかったこともフランスを有利にした。
バルミーの戦いといえば、必ずといってよいほど引用されるのが、プロシア陣営に従軍していたゲーテの言葉だ。
「この場所、この日より、世界史の新しい時代がはじまる。
そして君たちは、その際そこにいたということができるのだ。」
しかしこれが文字となったのは、三十年ものちのことである。
ともかく秋にはフランス軍が国境をこえて、ネーデルラントからライン左岸方面へ進出するようになった。
新しく成立した国民公会は共和主義の議員たちでしめられていた。
なかでも勢力があったのは、まえにのべたジロンド派と、それから山岳派であり、両派に属さない多くの議員もいた。
議場の高い場所にいた山岳派議員はジロンド派と同じように、法律家などの中流ブルジョワーインテリたちであり、またいずれも有名なジャコバンークラブがうみだした革命家たちである。
両者のあいだに本質的な相違はないとされるが、ジロンド派がブルジョワ自由主義、地方連邦主義をとったのに対し、山岳派はパリを中心として、ブルジョワや民衆勢力をくみあげて、革命の進展に対処してゆくのである。
一方、国民公会はまずルイ十六世裁判にとりかかることとなった。
妙なもので、ルイ十六世のような人物にとっては、国王という責任ある地位は重きにすぎたのであろう。
彼はダンブル塔で肩の荷をおろしたような気持になっていた。
九月末、王と王子、王妃と王女との二組にわけられ、彼らの家族的ななぐさみは食事や散歩をともにすることであり、マリー・アントワネットはこの頼りなかった夫に、その不格好さ、きまじめさゆえに、いまとなってはかえって愛情を感じるのであった。
王は読書にふけったり、王太子に知識をさずけたりして、おちついた書斎人、よき父の一面を示した。
ともかく十月、十一月とダンブル塔では単調に時間はうちすぎ、それはこれからいつまでもつづくようであった……。 |

ダンブル塔における王一家の食事
|
しかしコミューン、急進的大衆、山岳派などは、反革命派の中心的存在としてルイ十六世があるかぎり、革命は、共和国はつねに危険物をいだいていることとなる、したがってルイと早く決着をつける必要がある、と考えた。
ルイ十六世の裁判は、国民公会において十二月十一日から行なわれることとなった。
これよりさき、十一月二十日にテュイルリー宮で、ルイ十六世がかくしていた書類が発見された。
これは王の命令によって、宮廷のある壁のなかにつくられていた秘密の鉄の戸だなから出てきたもので、これを作った職人の密告によってわかったのである。
そしてこれらの書類の多くは宮廷の策謀を示すもので、王を不利とした(この点では王妃もテュイルリー宮にいたころから、宮廷がきめた計画についてオーストリアに通告していた)。
しかし問題は王に確かな証拠があるか、どうか、ということよりも、「王が正しいのか、それとも革命が正しいのか」「もしルイが無罪とすれば、人民が有罪であるのか」「ルイ死すべし、そうでなければ共和国は生き残れないであろう」というように、しだいに王か、革命かとオール・オア・ナッシングの問題になっていった。
一七九三年一月十四日、国民公会議員はつぎの三つの質問に答えねばならなくなった。
一、ルイは公共の自由に対する陰謀、国民の安全に対する加害の罪があるか?
一、判決につき国民の承認を求めるべきであるか?
一、いかなる刑をルイに科すべきか? |
議員たちはつぎつぎと壇上にのぼり、あるいは長く、あるいは短く、意見をのべた。
まず若干の棄権をのぞき、全員一致で王の有罪が決定された。
つぎの質問は、二百七十八対四百二十六で否定された。
そして一月十六日夕方から始まったまる一日におよぶ口頭の表決のすえ、王の刑については三百八十七人が死刑、三百三十四人が死刑以外の刑に賛成した。
ただし前者のうちには二十六人が死刑執行猶予を望んでいるので、これをかりに後者にまわすと、無条件死刑をめぐっては 三百六十一対三百六十で、その差わずか一人!
そこで一論争あったのち、「刑の執行は猶予されるべきであるか?」ということが議事となった。
そしてこれは三百八十対三百十で否決された!
5.4 自由か、死かというべきとき
top
死刑賛成者のなかで人びとを驚かしたのは、ルイ十六世のいとこオルレアン公ルイ・フィリップ(一七四七〜九三)であった。彼は自由主義貴族であり、パリの邸宅バレー・ロワイヤルの庭園は革命初期から急進派に解放されてアジ演説の中心にもなっていた。
そして彼はルイ十六世にとって代わろうとする野心があると宮廷側から警戒され、マリー・アントワネットなどとは犬猿の仲であった。
彼は公爵の称号をきらって「フィリップ平等」とよばれることを望み、国民公会議員に選出されていた。
この死刑賛成でフィリップ自身は革命家ぶろうとしたわけであるが、それはかえって山岳派に保身、迎合の卑怯なふるまいともとられた。
その後革命の急進化につれて、ルイ十六世にもっとも近い人物ということが不利であったうえに、取巻きも悪く、一七九三年十一月、国王と同じ運命をたどることとなるのである(なお彼の長子ルイ・フィリップは亡命し、のち一八三〇年の七月革命によって王となった)。
ルイ十六世の死刑は一七九三年一月二十一日であった。
その前夜、王一家は水入らずでひとときをすごしたが、三十七歳のマリー・アントワネットは年齢以上にふけ、髪も銀色に、肌も青ざめており、ルイもまた獄中生活で衰えをみせていた。
王妃は一夜を家族ともどもすごそうと思ったが、ルイは一人で静かに最後の夜を送ることを望んだ。
また翌朝会いたいという王妃の願いにもかかわらず、ルイはあえてこれをさけた。
「私は残酷な別れを彼女に味あわせたくない。」
一月二十一日、ルイはいつもと変わらず朝食を終え、窓がおおわれた馬車で刑場、すなわち革命広場に向かう。
王の断頭命令をうけた刑吏サンソンは、命令を拒否すると自分の命が危ないので、心ならずもこの役目をひきうけたという。
刑の執行は午前十一時ごろ、軍隊がとりまき、兵士たちの背後には群衆が見まもっている断頭台上で行なわれた。
ルイは最期にのぞんで何かいいかけたが、太鼓がなりひびき、その声はかき消された。
刑吏が当時の習慣にしたがい、死者の頭髪をつかんで首を群衆に見せると、「国民ばんざい!」「共和国ばんざい!」の叫びが広場にこだました。
この死刑執行に心を痛めたサンソンは、まもなくその仕事を息子アンリにゆずった。
なおある本によれば、処刑に用いられた断頭の刃は、サンソン家に伝えられたのち人手にわたり、一九三六年競売により百二十五万フランで、ある好事家(こうずか)の手に落ちたそうである。 |

国王の処刑
ギロチンで首を斬ったあと、頭だけを皆に見せる
|
この断頭台(ギョティース)、ふつうギロチンとよばれている死刑道具は、すでに革命時代以前にも利用されていた。
これがフランス革命に関係深い存在となったのは、一七八九年国民議会の議員で医師のギヨタンが、使用を主張してからである。
理由は、すみやかに、かつ苦痛なく処刑できるという点で、したがってこれまでの残酷な死刑の方法に対して、人道主義的な(?)立場にたつというわけである。
むろんギョティーヌはギヨタンの名からつけられたものだが、彼自身はこれをいやがっていた。
ただし断頭台がはじめて登場したのは、九二年四月二十五日である。
なおそれは革命後も、いや、現在まで、フランスの死刑道具として使用されている。
王に同情したのは、サンソンだけではなかった。
なるほどラ・マルセイエーズを歌いつつ、断頭台のまわりを踊りつづけたり、ハンカチや紙片を王の血でひたす者もあったが(これらはのちに売買されたらしい)、しかし処刑のころ、部屋にひざまずいて王の冥福を祈る市民たちも少なくなかった。
すでに国民のなかから、王の処刑にかんするかずかずの抗議の手紙が公会にもきていた。
王政廃止はともかく、王個人に対する敬愛の情は、なお国民のあいだに強く根づいていたのだ。
国民公会のなかでも、王の裁判をめぐってジロンド派は王を助けて、王党派と妥協の余地を残しておくことを考え、とくに王に対する刑についてはあまりにも過激、刺激的であるとして、極刑をさけたかった。
穏和な共和主義者にしてみれば、共和政実現でいわば事が足(た)りたわけだ。
しかし山岳派を中心とする急進勢力は、はっきりと革命の敵を断罪して内外に対し背水の陣をしこうとした。
ジロンド派と目される議員のなかにも死刑に賛成した者もあったのだから、時の成り行き、急進派の勢いがいっきょに事をおしきったのであろう。
それにしてもルイ十六世が一個の罪人として断頭台にあがったことは、絶対王政がもっていた宗教的な威光を傷つけ、神聖さを地におとし、名実ともにその終わりを示した。
しかしそれは革命、反革命の溝を深めるとともに、君主政のヨーロッパ諸国を驚倒させた。
まさしく革命フランスは背水の陣をしいたのだ。山岳派の一議員ル・バは書いている。
「われわれは“さい”を投じた。
われわれの背後の道は絶たれた。
いやでも応でも前進しなければならぬ。
いまこそ自由に生きるか、しがらずんば死というべきときである。」 |
5.5 宿命の六月二十日 top
マリー・アントワネットは夫の死後、しばらくダンブル塔にいたが、一七九三年八月、寡婦(かふ)カペー(カペーはブルボン家の先祖にあたる王家名。ルイ十六世も、最後はルイ・カペーとして扱われた)はコンシェルジェリーの牢獄に移された。
ここにはいることは、当時だいたい死刑になるということであった。
そして母からはなれた王子ルイは一時、残忍で粗野な靴屋のシモンにあずけられた。
王党派のほうではこの王子をルイ十七世としたが、彼はその後またダンブル塔に入れられ、虐待された結果、一七九五年六月に死んだ。
しかし死んだ年月にも異論があるし、また死んだのは身代わりで、本人は獄からつれだされて生きのびていたなどと、いろいろな臆測がおこなわれている(王妹は九四年に刑死、王女は九五年釈放)。
一方、マリー・アントワネットに対する監視はまことにきびしかった。
しかもこのいわば「死の控え室」から、王妃を救い出そうという最後の、ほとんど想像を絶した試みがくわだてられたことが、真相は不明のままに伝えられている。
監獄長とともに獄室にはいってきた王党派の一人物、王妃のがっての知人がひそかに投げて去った一束の、もしくは一輪のカーネーションのなかに、連絡の文書がひめられていた。
ペンもインクもない王妃は、返事の文字を、かろうじて手もとにあった紙片に編み物用の棒でつき刺した……。
これから先のことはますますはっきりしない。
王妃は一人の憲兵を手なずけて連絡に当たらせようとしたが、けっきょくこの男が、あるいはほかの関係者が心変わりして、王妃救出の計画は失敗してしまった。 |

マリー・アントワネットは夫の死後、寡婦カペーとして扱われ、
夫と同じギロチンの犠牲となった
|
そしてこれはかえって彼女の運命を早めることとなった。
王妃はいっさいの私有物を取りあげられてしまい、コンシエルジュリー牢獄のなかでも、もっとも堅固な部屋で、もっとも厳重な監視をうけることとなった。
彼女の生涯で読書らしい読書がおこなわれたのは、じつにこのときが始めてであった。
一日中、せまくて、しめっぽく、うす暗い部屋をほとんど沈黙だけが支配していた。
四十歳にもとどかぬマリー・アントワネットは、いまでは白髪が目立つ疲れはてた姿となった。
126
一七九三年十月、彼女の裁判は開始された。
王の場合とはちがって、憎むベき「オーストリア女」に対して、あらゆる侮辱が加えられた。
母たる彼女が幼い王子を性的にもてあそんだという、信じがたい近親相姦の記録さえつくりあげられた。
けっきょく、共和国に対する反逆罪で死刑が決定するが、革命裁判所における彼女は、体力こそ衰えていたものの、はりつめた気力をもって侮辱とたたかった。
十月十六日、午前十一時、コンシエルジュリーの門は開き、王妃は一種の粗末な荷馬車の固い板の上に腰かけ、うしろ手にしばられ、衆人環視のなかを運ばれていった。街頭は騒然としたありさまであり、ある革命家は敵意をこめて書いた。
「娼婦は最後まで、ともかく大胆で、かつ鉄面皮であった。」
刑吏は例によって頭髪をつかみ、血のしたたる首を高々とさしあげる。
革命広場をうめつくした群衆は例によって叫ぶ――「共和国ばんざい!」十二時もまわった。
刑吏は死体を小さな手押し車にのせ、頭部をその足のあいだに入れ、共同墓地へ運び去る。それから墓掘り人が市庁へやってきて、勘定書をさしだした。
「未亡人カペーの棺桶代六リーグル、墓代と墓掘り人手当十五リーグル三十五スー。」
マリー・アントワネットのわずかばかり残した衣類は、まとめてどこかの養老院へ送りとどけられた。
貧しい老婆たちはそれらが誰のものであったか、夢にも知らなかったであろう。
ルイ十六世の場合とちがって、前王妃の刑死は国民の関心をひかなかった。
もともとあれほど不人気であったうえに、彼女の死の当日、十月十六日にはフランス軍がワッティニーというところで、オーストリア軍に勝利をえた。これは決定的な勝利ではないが、連合軍の進撃をおしとどめ、翌年春から反撃にうつる足がかりとなった。
国民の気持はこの戦争のほうに向いていた。
マリー・アットワネットの死は、外国でも大きな反響をおこさなかった。
オーストリア宮廷はむろん喪に服し、新聞類はパリの革命家たちを口ぎたなくののしった。
しかし宮廷では、なんら救出の策もとらなかったこの「マリー・アントワネット」の話題について、しだいに意識的にさけるようになった。
だが少なくともあのスウェーデンの貴族フェルセンは、終生この女性について忘れることはできなかった。
そして一七九一年六月二十日、あの夜陰にまぎれての逃亡のとき、ルイ十六世の意志にしたがって、途中で一行と別れたことを痛恨した。
彼は日記でいくども、いくども愛する人をおき去りにした責任感、罪悪感に、わが身をせめさいなんでいる。
マリー・アントワネットの死後、フェルセンは親しみがたく、苛酷な性格になるとともに、またスウェーデン第一の権勢家に出世していった。
しかし彼は民衆を愛さず、民衆は彼をきらった。
一八一〇年、スウェーデンの王子が急死したとき、王位をうかがうフェルセンによる毒殺だという噂がひろまった。
葬儀の日、ストックホルムの街頭で、群衆はフェルセンを馬車からひきずりおろして惨殺した。
それは六月二十日のことであった。
フェルセンの日記にしるされているという、自責と後悔の日づけから二十年ちかくもたったその日――。
『なぜ、私のあのとき彼女のために死ななかったのであろうか、あの六月二十日に。』
top
**************************************** |