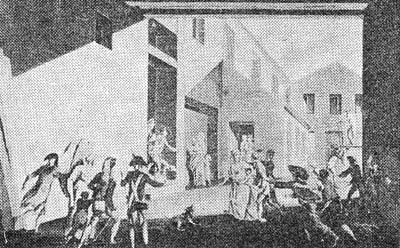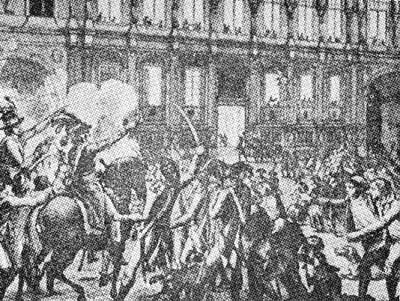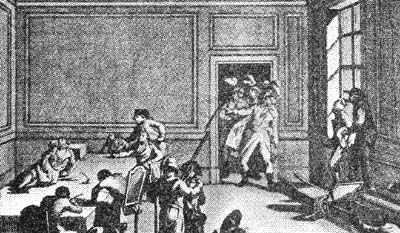|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12
世界の歴史10――市民革命の時代
6 熱月(テルミドール)九日への道
6.1 山岳派の台頭
すでに革命フランスは、一七九二年春からオーストリア、プロシアを敵として戦っていたが、翌年二月以後、イギリス、オランダ、スペインなどを敵にまわすこととなった。
なかでも十八世紀を通じての宿敵というべきイギリスが、つぎのような事情から、またも登場したのである。
九二年秋から、オーストリア、プロシアに対する戦局はしだいに有利となり、フランス軍は国境をこえて、いまのベルギーやライン地域へ進出していった。
この点、九二年十一月六日オーストリア軍を破ったベルギーのジェマップの戦闘は重要で、それはいわば“共和国の軍隊”が交戦し、勝利をえた最初の大きな戦いであった。
国民公会は九二年十一月十九日、自由を回復しようと希望するすべての国民に友愛と援助をあたえると、熱狂のうちに宣言した。これはまさに古いヨーロッパに対する解放宣言であり、挑戦状ではないか。
そしてまた、「(貴族の)城や館には戦いを、(大衆の)あばらやには平和を」という言葉が革命フランスの心意気をしめていた。しかしそうした原理づけの反面には、フランス勢力の他国に対する現実的な進出、国家的野心があった。
ある政治家は書いている。
130
「フランス共和国に限界があるとすれば、それはライン川だけだ。」
こうしてベルギーからさらにオランダ方面もおびやかされるようになったとき、イギリスはその利害にかけて黙視することはできなくなった。
元来、イギリス人は革命初期には、フランスが自国のように立憲王政化したり、また革命の混乱で競争国が弱くなる予想などで、干渉のつもりはなかった。
むしろホイッグ党(のちの自由党)の左派あたりでは、革命を歓迎する声もあった。
したがって伝統と秩序の破壊として革命を非難した、エドマッド・バーク著『フランス革命の考察』(一七九〇)に対する反対論も少なくなかった。
このパークの本は諸外国でも読まれ、いわば反革命のバイブルとなったが、これに対し、たとえばアメリカ独立にも思想的につくしたトマス・ペインは『人権論』(一七九一〜九二)を著わして、フランス革命の味方をした。
また革命の影響をうけて、議会改革などを望む諸団体もうまれた。
なかにはイギリス最初ともいうべき、労働者階級の団体もつくられた。
当時のイギリス首相ピット(一七五九〜一八〇六)も、フランスがイギリス流に自由主義化するものとみて、最初は革命に好意的で、不干渉政策をとっていた。
しかしいまやフランス軍がネーデルラント方面へ進出するにいたって、イギリス政府はフランスを敵視し、オランダを支援するようになっていた。
そのとき起こったルイ十六世処刑(一七九三年一月)は、国論をフランス革命反対へもってゆくのに有利であった。
|

革命フランスは周辺諸国に宣戦布告をし、さらに
国内でもバンデーやジロンドで反革命運動がおこった。
|

サン・キュロットの兵士
長ズボンをはいた小ブルジョワ
|
駐英フランス大使は国外退去の処置をとられ、九三年二月一日、国民公会はイギリスとオランダとに宣戦布告した。 それは革命戦争であるとともに、政治上、経済上の優勢をめぐる国家どうしの戦いとなった。
君主的感情が強いスペインでは、イギリス以上に国王処刑が戦争の原因であった。
三月七日、公会はスペインに宣戦した。
やがてフランスの敵には、当時まだ分裂していたイタリアの諸国が加わり、そしてイギリスを中心として九三年のあいだに、第一次対仏同盟が結成された。
フランス側が「ピットの金(かね)」と表現したように、イギリス政府は同盟諸国に軍資金をばらまくとともに、国内の民主的な諸団体を取締った。
こうして戦局はふたたびフランスに不利となり、ベルギーを失ったうえに、外敵と呼応して、国内でも王党派による反革命内乱がバンデー地方などで生じ、事態は重大となった。
ベルギーにつづいて、ライン左岸地域も失われた。また戦争に勝てば、被征服国から利益がえられると考えていたフランス側の期待もはずれ、アシニア紙幣の乱発からインフレーションが高まってきた。
ところが当時の議会、国民公会で勢力をもっていたジロンド派は、この物価値上がりや戦争を利用してもうけている金持に味方し、大衆の生活を苦しくしている。
そしてこのジロンド派では、大衆動員が必要な戦争遂行をうまく指導できない。
このままではフランスは内外にくずれ去り、革命も失敗に終わるのではないか!
ここでサン・キュロット勢力を背景として政権をにぎったのが、国民公会の山岳派である。
サン・キュロットとはもともと、貴族たちのような短いズボンをつけていない者たち、いいかえれば長いズボンをはいた小ブルジョワや勤労大衆のことで、手工業の親方や職人、小商人、労働者などだが、とくに彼らのなかでも革命的な分子をさすよび名である。
さかのぼれば、一七八九年七月十四日バスティーユ奪取や、九二年八月十日テュイルリー王宮襲撃などに活躍したのも、彼らである。
これに対して山岳派議員ら自身は、いわば中産ブルジョワである。
両者は階級がちがっており、もともとは利害を必ずしも一つにしていないが、いまは共通の目的のために一時的な協力体制がつくられたのだ。
6.2 マラー暗殺
この体制は革命の情況に応じたものであるが、事態の深刻さは、政局をジロンド派の指導にゆだねておくことを許さない。一七九三年五月末からパリの各区のサン・キュロットは蜂起の態勢をととのえ、六月二日、何万というその勢力は公会をとりまいた。
国民軍(元来はブルジョワの市民軍だが、このころは大衆も参加していた)を指揮するアンリオは、数門の大砲をすえつけた。
この威圧のもとに、公会から二十九名のジロンド派のおもな議員たちが軟禁されたり、追放されたりすることとなった。
こうしてジロンド派に対する山岳派の勝利が決定したが、この場合、これら両派以外の公会議員たちの動向を考えておかねばなるまい。すなわち公会には議場の低いほうに席をしめる平原派を中心として、数のうえでは両派よりずっと多い議員たちがいた。
彼らはどちらかといえばジロンド派に近い、ブルジョワ共和派である。
それがこの六月二日には、このジロンド派を見すてて、むしろ山岳派に協力したのである。
それはパリ人民の圧力にもよるが、平原派自身もジロンド派に信頼がおけなくなったのだ。
彼らも革命派であるからには、革命そのものが中途でつぶされてしまっては元も子もなくなってしまう。
いまや革命防衛には、国民大衆の総力の結集が必要だ。
それができる山岳派にここでは権力をゆだね、やれるだけやらせてみようというのが平原派の考えかただ。
だから情勢が変われば、またジロンド的ブルジョワの立場にかえるだろう。だれかが平原派をさしていった。
「沼のひき蛙(がえる)のようなやつらだ。」
そこで平原派は沼沢(しょうたく)派ともよばれる。
九三年六月からはじまる山岳派独裁の背景には、公会外のサン・キュロットだけでなく、公会内のこのいわば日和見派がいたわけである。
|

暗殺された人気のあった革命家のマラー
|

マラーを暗殺した罪で刑場へ送られるコルデー
|
山岳派議員のなかで、とくにサン・キュロットに人気があった革命家はジャン・ポール・マラー(一七四三〜九三)である。
マラーは医者で学位もとっている。小男だが、首がふとく、肩も胸もはばが広く、首にまきつけたハンカチ、はだけたシャツといったところが、おなじみのスタイルである。
天性の大衆政治家、煽動家で、八九年から『人民の友』という新聞を発行し、ジャーナリストとしてパリの市民たちに影響をあたえていた。
このマラーが暗殺されるという、思いがけぬ事件がおこった――。
シャルロット・コルデー、貴族の娘、二十五歳、美人。
尼僧院で教育をうけたのち、読書ずきの彼女はルソー、ボルテールなどを愛読し、自由を愛することを知った。
しかしジロンド派の影響をうけ、これを追放した山岳派を憎み、その中心人物マラーを「自由の敵」と思いこんだようである。
彼女は九三年七月十一日、ノルマンディーのカーン市からパリに着いた。公会でマラーを見つけられなかったコルデーは、彼の粗末な住居をたずねたが、妻シモンヌによって病気を理由に、玄関ばらいをくわされた。
そこでコルデーは、「私はカーンからきた。そこで進行している策謀についてお知りになりたいはず」という意味の手紙を送り、返事を待たず、十三日夜八時ごろ、ふたたびマラーの家を訪れた。
また追い返されそうだったが、コルデーの声を聞いたマラーは、しわがれ声で、「はいってもよし」といった。
そのころ彼は持病の皮膚病のため、浴槽に半身をひたして執筆していた。
皮膚の痛み、かゆみは入浴のときしか去らないので、訪問者にもそこで会うならわしであった。
そして上半身をよごれた毛布でおおいながら、マラーはカーンにいるジロンド派残党について質問した。
コルデーが名をあげた人びとについて、彼が「いずれ、みな断頭台に送ってやる」といつたとき、かくし持たれていた短刀はこの革命家の胸を刺した。
叫び声に、シモンヌがとびこんできたが、それは致命傷であった。
当時、ノルマンディーをはじめ、バンテー地方、リヨン、グルノーブル、マルセーユなどにも反山岳派の動きが活発であった。
これらの鎮圧に強い関心をもつマラーは、この見知らぬ女性の情報にとびついたのだ。
したがってある意味では、内乱的情勢が彼の死の原因ともいえる。
ただちに捕えられたコルデーは、七月十七日に処刑された。
この信望あつい革命家がパリのまんなかで暗殺されたことは、山岳派に反革命を警戒させ、その独裁力を強化させる結果となった。
6.3 清廉(せいれん)の士
政権をにぎった山岳派は、残存の領主権の無償廃止による農民解放、民法典編集および国民教育計画への着手、度量衡の統一、人民主権や一院制、男子普通選挙制などをふくむ民主的憲法の制定……と革命をおし進めていった。
しかし情勢が重大になったので、山岳派はこの憲法の実施を一時延期し、九三年十月から、とくに強い権力をもつ非常体制を整えた。
なかでも大きな実権をにぎったのは、この年四月に設立された公安委員会である。
この委員会は、内政、外交、軍事上などの権限をもち、国民公会にその活動を報告する義務があるというものの、じつは公会をしのぐ勢いであった。
この七月から一年ばかり、公安委員会はほとんど独裁的にフランスを支配するが、その委員の一人で、とぐに実権をにぎったのが、マクシミリアン・ド・ロペスピエール(一七五八〜九四)である。
そしてこの公安委員会のほかに、すでに九二年十月成立していた治安警察権をもつ保安委員会、九三年三月つくられた革命裁判所、これらが今後の政治を動かすものになってゆく。
弁護士出身で、インテリ・ブルジョワの革命家ロベスピエールは、三部会以来の活動をつうじて、いまや山岳派のおしもおされぬ中心人物である。
ほっそりとして、貧弱ともみえる小柄な体つき、手入れがゆきとどいたうすい栗色の頭髪、
少しあばたがある責白い顔、軽い弱視の眼(彼はものを読むとき眼鏡をかけ、それをひたいにおしあげるのが癖だった)、短い鼻、広い口(しかしけっしてみにくい顔ではない)、ときどき猫のような鋭さにかわる表情、ユーモアをあまりもちあわせない男のぎこちない笑い、きちんとしていて、めかしているともいえそうな服装(彼は貴族がもちいるような短いズボン、絹の靴下をはき、しみひとつないシャツを身につけ、急進的な革命家の赤帽子などをかぶることはしなかった)、友人たちにはメランコリックにひびき、敵には傲慢にきこえる日常の言葉使い、方正で質実で小心でさえある性格、そしてあの雄弁、それは派手でたくみな雄弁術によるものではなく、その内容の重大さ、それを発言するときの確信の強さにより、聞く人びとの心を動かさずにはおかない雄弁である…… |
 清清廉の士、ロベスピエール 清清廉の士、ロベスピエール
しかし恐慌政治の主でもあった
|
当時三十代のなかばに達したロベスピエールとはざっとこうした人物であり、とくに金銭上で汚れがなかったところから、「清廉の士」とよばれた彼は、議会やジャコバン・クラブ以外のほとんどすべての時間を、デュプレー家ですごすのが普通であった。
デュプレー家とは、一七九一年夏からロベスピエールが下宿していたところである。
指物師デュプレーは五十のなかばくらいで、ジャコバン・クラブに加入しており、数人の子女があった。
娘たちのうち、長女で一七七一年生まれのエレオノールと、妹で七三年生まれのエリザペートが、革命史をいろどる存在である。
そしてエレオノールは、あまり女を近づけなかったロベスピエールが情熱をそそいだ、いや、許婚(いいなずけ)でさえあった、ただひとりの女性といわれる。
彼女ののぞみも、もっぱらロベスピエール夫人となることであった。
しかし許婚説はむろん、愛人説をも否定する意見もある。
たとえばロベスピエールの妹シャルロットで、彼女はのちに、つぎのような意味のことを書いている。
「ふたつともまちがいだ。ただ兄を自分の娘と結婚させたいデュプレー夫人が、兄の気をひいていたのはたしかだ。」
なおエレオノールの妹エリザペートは、ロベスピエールの仲間のル・パ(一七六五〜九四)という革命家と、一七九三年に結婚する――。
6.4 恐怖と徳と
戦争と内乱――内外の革命の危機に対して、山岳派はひろく国民のなかから兵士をつのり、軍制をあらため、物資を徴発し、老人や婦人たちにもそれぞれにふさわしい任務をあたえ、史上最初ともいうべき総力戦の体制をととのえた。
つまりフランスを一つの要塞のようにして、防がねばならなかったのだ。
自然科学者たちも動員され、共和国軍隊の合言葉は悲壮である。
一方、サン・キュロットの要求に応じつつ、公会は、買い占め禁止、国有亡命者財産の売却、「穀物などにかんする最高価格令」、さらに「生活必需品、労賃の最高価格令」などの一連の経済政策によって、大衆の生活を守り、かつ戦時経済を推進した。
しかしすべての国境で共和国の軍隊は退却し、王党派などによる内乱がつづき、反革命の陰謀は絶えず、経済政策にそむくものも少なくないとき、すなわち、革命フランスが生きるか、死ぬかのとき、これら「共和国の敵」に対して、山岳派はどういう方法をとらねばならなかったか?
それはテロ手段であり、反革命のうたがいがある人たちに対して、一七九三年秋から翌年夏にかけて、断頭台は血しぶきをあげ、いわゆる「恐怖政治」が本格的に展開する。
つまりこれは革命防衛、国家防衛のための非常手段であったわけだ。
九三年十月から十一月、前王妃マリー・アントワネットや、ブリソーやベルニョーらジロンド派首脳部たちは、この恐怖政治の有名な犠牲者となった。
なかでもロラン夫人(一七五四年生まれ)は、その邸宅にジロンド派首脳部を集め、政策を左右し、夫ロランを二度まで内相にのしあげた実力者――「大臣は夫人で、ロランではない」といわれた――であったが、この才媛が死にあたって残した言葉は、革命史の一ページにつねにしるされるものであろう(妻の死を知って、逃亡中のロランは絶望のあまり、みずから生命を絶った)。
| 「自由よ! おまえの名において、いかに多くの罪がおかされていることよ!」 |
まえに死刑廃止を主張していたロベスピエールが、この恐怖政治の実権をにぎっていたということは、歴史の皮肉といえば皮肉であろう。
|

恐慌政治を非難したロラン夫人
|
しかしロベスピエールにとって、恐怖政治とはただ暴力をふるうことではない。
彼はいう。
「革命における人民政府の基礎は、徳と同時に恐怖である。徳なくしては恐怖はいまわしく、恐怖なくしては徳は無力である。」
「……共和国の魂は徳 ――すなわち祖国への愛、すべての個人的な利害を、社会全体としての利害のなかに解消する高潔な献身――である。」 |
こうしてロベスピエールは独裁政治、恐怖政治を、徳性によってささえようとしたのだ。
テロと徳! この一見して相対立している二つのものの組みあわせを、政治や社会の原動力にしようという、彼の構想ははたして成功するであろうか?
その答えがでるまえに、ロベスピエールが恐怖政治のもとで社会改革を実現することを考えていたことも、注目しておくべきであろう。
これには、山岳派のなかでとくにロベスピエールと志(こころざし)を同じくする人びと、すなわちロベスピエール派のなかでも、若きサン・ジュストの協力におうところが多い。
こうして成立したのが「風月法」である。それは一七九四年二月から三月にかけてのことであるが、九三年十一月に採用された共和暦(一八〇六年一月一日廃止)によると、風月(バントーズ)という新しい月名にあたるのだ。
この法律は反革命とみられる政治上の容疑者の財産を没収し、これを「貧しい愛国者たち」に分配しようとするものである。
ロベスピエールたちは、山岳派のなかでもとくに小商人、手工業者、小農などの小ブルジョワ層の立場にたち、それぞれが店や仕事場や土地をもち、自分の家族をやしない、自分の生産物を仲間と交換してくらすような、いわば「小生産者の平等主義の共和国」をつくることを理想としていたとされる。
風月法はこれを具体化し、あわせて民衆をひきつける試みではあったが、こうした社会改革にはさすがに反対も少なくない。
したがって国民公会で成立したとはいえ、この法律は徹底しておらず、またしだいに意味もぼかされ、また実施もはかどらなった。
それはともかく、サン・ジュストとはどういう革命家であろうか? |

ロペスピエールの恐慌政治を
支えたサン・ジュスト
|
ルイ・アントワーヌ・ド・サン・ジュストは一七六七年、父祖の代からかなり豊かな農民の家庭に生まれ、多感な青春を一方ではロマンスに、そして恋破れての家出についやし、一方では古典や自由、平等の新思想へ没頭しつつすごした。
一七八九年、すなわち革命がおこった年の五月、彼が出版した長編詩『オルガン』は、中世紀の騎士オルガンをテーマとしたものだが、秩序破壊やワイセツなところがあって当局に発禁にされ、作者は一時身をかくしたほどである。
やがて革命の波は、彼が住んでいた地方にもおよんできた。
血の気が多いサン・ジュストも、この波に洗われた。
九二年九月、国民公会の議員に選出された彼は、最年少の議員として晴れの舞台をふむ。
十一月彼はそこで、「そもそも王であるということにおいて、罪がおかされている」、
したがって王ルイ十六世が有罪であるということについては、なんの証拠も不要であると、もっともはげしく国王の死刑を主張して、注目をあびた。
端麗な美丈夫で、「火の才気、氷の心」をもつといわれたサン・ジュストは、九三年五月末から公安委員会に加わり、やがてロベスピエール、タートンとともに委員会を支配しつつ、むしろロベスピエール以上に確固とした意志をもって革命にのぞんだ。 |

サン・ジュストが活躍した恐慌政治下のクラブ
|
恐怖政治の必要についても、彼は簡潔にいいはなつ。
「共和国をつくるもの、それは、共和国に反対するものをすべてうち倒すことである。」
「正義によっておさめることのできない人びとをば、剣によっておさめなければならぬ。」 |
恐怖政治はサン・ジュストの理論にもとづいて、組織され強化されるところが大きかった。
しかし彼も恐怖政治における徳を重んじている。
サン・ジュストはまた、フランスにとって輝かしい「勝利の組織者」の一人である。
一七九三年秋、ストラスブールというドイツ国境に近い都市の軍隊に派遣されたとき、電撃的な命令を発して、青二才の文官とあなどっている当局者のドギモをぬいた。
「一万の兵がはだしでいる。ストラスブールの貴族の靴をぬがせ、明朝十時、一万足を司令部に運ぶべし。」
「ストラスブール市民のすべての外套を徴発する。明晩までに共和国の倉庫におさめよ。」 |
そして彼は怠惰や腐敗をふきはらう一陣の風のように、市政関係の改革にあたり、また軍律にそむく将兵たちには、死刑をふくむきびしい処置をとった。
その水ぎわだったやり方には、彼に同行した山岳派の議員ルーバも恐れをいだいたほどであった。
またあるときには戦陣にあって、サン・ジュストはみずから範をしめした。
彼は道のかたわらで兵士のパンをたべ、夜は服装もとかず、兵士の天幕にやどった。
戦闘ともなれば、三色旗になぞらえた三色のかざり帯を軍服にまとい、サーベルの先に三色の羽根かざりがついた帽子をつっかけ、部隊の先頭にたって進んだ。
それは兵士たちにとって、フランス革命そのものが突撃してゆくようにみえた。
6.5 分派闘争
ところで山岳派独裁のあいだに、革命勢力のなかに分派の対立がうまれてきた。
分派の一つはサン・キュロットと関係が深いエベール派である。
ジャック・エベール(一七五七〜九四)は地方のあるブルジョワの家に生まれ、順調(じゅんちょう)に育ったが、やがて境遇が一変し、一七八二年、パリに出たころには父母もなく、遺産もつかいはたしていた。
それから貧しい生活をつづけたらしく、ともかく革命がはじまると、一七九〇年、『ペ・ル・デュシェーヌ』という新聞を発行し、急進的なコルドリエ・クラブやパリ・コミューンなどに勢力をもち、サン・キユロットに人気があり、またこれを煽動していた。
この新聞の名は『デュシェーヌおやじ』という意味で、革命まえから軽演劇などに登場するおせっかいで、粗野だが、お人好しの人物のことであった。この名がしめすように、エベールは大衆の「声なき声」を代弁したといえよう。
しかしエベール派は調子にのって、社会秩序をおびやかすようになってきた。
彼らは当時の食糧難を利用して、サン・キュロットに対する支配力をたよりに、いっきょに政権をにぎろうとする。
九四年三月、エベール派は国民公会にクーデターを計画したが、これは失敗し、ロベスピエールを中心とする公安委員会は彼らを捕えて、反乱罪で処刑した。
革命勢力の仲間われは、これだけにとどまらなかった。
エベール派を左派とすれば、ここに右派、あるいは寛容派ともいうべき一派があった。
それは恐怖政治をうちきり、内外に妥協的な和平政策をとることを主張する山岳派の一部である。
たとえばカミーユ・デムランは彼の『ビー・コルドリエ』紙で寛容を主張し、ロベスピエールを大胆に攻撃した。
この恐怖政治反対派の中心は、なんといってもダントンであろう。
ジョルジュ・ジャック・ダントン(一七五九〜九四)はロベスピエールとほぼ同年輩で、やはり法律家あがりの公会議員であるが、なんという相違であろうか。
牛とたたかって裂けたという鼻と唇、はしかのためのあばたづら、広い肩はば、ふとい首、鋭いまなざし、剛胆不敵なつらだましい、ぜいたくな衣服ながらくずれた着こなし、腕をふりまわして、相手をふるえあがらせるような演説……。
ときはさかのぼるが、一七九二年九月二日、迫ってくる敵軍に対して、彼が議会でおこなった演説は革命史上に残るものであろう。
「勝利をうるため、われわれは大胆であれ、さらに大胆であれ、つねに大胆であれ……」
ダントンは、その容貌や肝ったまにふさわしく、その行ないも度はずれであった。
彼は愛する妻を九三年二月十日に失った。
十七日、彼はもう一度その姿を見ようと、彼女を地中から掘りおこした。
そして四ヵ月たった日も同じ、六月十七日に再婚する……
彼の享楽主義は禁欲的なロベスピエールとあわなかった。 |

恐怖政治反対派ダントン
彼もその犠牲となった
|
ロベスピエールが徳性という言葉を口にすると、ダントンは一笑にふしたという。
しかしこの革命家にとって致命的であったのは、金銭にきたないことであった。
かつて法相をつとめたときには公金を私用に使ったともいわれ、また王党派との関係もうたがわれており、たびたび金をうけとったのみならず、諸外国からもらう金とひきかえに、王家を逃がすことを計画したことさえあった。
そのうえ、類は友をよぶというのか、ダントン派とよばれる政治家たちには、金銭的にだらしない人たちがまじっており、この方面の事件も明るみにでた。
ロベスピエールとダントンは性格上では種々のちがいがあるとはいえ、革命の激動をともにのりこえ、ともにおし進め、てきた友としての情には、深いものがあったにちがいない。
しかしいまダントン派を放置しておけば、恐怖政治のいろいろな組織はくずされ、したがって革命そのものもくずされるのではあるまいか。
ある友人の仲介で二人は会見したが、ロベスピエールはひややかな態度で部屋を出たにとどまった。
妻や友人はダントンに逃亡をすすめたが、彼はききいれなかった。
「どこに逃げるというのか。自由をえたフランスが私を追い出すというのならば、他国で私を待っているのは牢獄だけであろう。靴のかかとに祖国をくっつけてゆくわけにゆくまい。」
九四年三月末、公安・保安合同委員会はダントン派を逮捕し、さすがにこの革命の大立者をめぐって公会は風雲をはらんだが、ついにその逮捕が承認された。
法廷で堂々たる弁論をふるうダントン、彼を救おうとする動き――これらを恐れて、裁判は早くうちきられ、四月五日夕方、ダントンたち十数名は断頭台にのぼった。
そして彼は「ギロチンの刃をせせら笑う」ように死んでいった。
こうして山岳派の独裁の中心はロベスピエール派となった。
しかしロベスピエール派といっても、彼と弟のオーギュスタン、サン・ジュスト、ルーバ、そしてタートン(一七五五〜九四)である。
いずれも公会議員、ルーバはやはり法律家の出で、サン・ジュストと親しく、その命令を忠実におこなった。
エリザベート・デュプレーと結婚したことは、まえにも書いた。
タートンも法曹界から政界にはいり、病気のため両足が麻痺した状態だったが、公安委員会に加わり、ロベスピエール、サン・ジュストとともに恐怖政治のいわば三頭政治家として活躍していた。
彼はとくにロベスピエールを尊敬し、「ロベスピエールの第二の魂」などともいわれている。
エベール派、ダントン派を倒して、ロベスピエール派の勢力は安定したようにみえたが、じつはそうではなかった。
これは当時、世人にみにくく血なまぐさい権力争いとみられ、またこのため、山岳派自体も弱体となり、またエベール派弾圧後、ロベスピエール派はサン・キュロットの動きに対しても、抑圧的になっていった。
指導者をうばわれ、組織をこわされたサン・キュロッ卜たちは、しだいにロベスピエールに反感をもつようになった。
6.6 反ロベスピエールの動き
一七九四年六月八日、「最高存在」の祭典がパリの町にくりひろげられた。
最高存在とは、カトリック教に代えて、新しい信仰をつくりだすために考案されたものである。
革命の急進化につれて、カトリック教会は封建的だと敵視されるようになり、非キリスト教化に向かっていたが、ロベスピエールはそれが無神論、無宗教になってはならないと考えたし、また革命に道徳性をあたえる必要もあったわけだ。
そして、この祭典は文化的に不毛とみられるフランス革命時代に、じつは新しく芽ばえた大衆参加の集団芸術であり、のちのマス・ゲーム、オリンピックなどのひとつの先駆ともみなされている。
そしてこの祭典の考案者、主催者ロベスピエールは、まさしく権力の絶頂にあった。
しかし彼の没落の道は急速に展開するのだ。
ロペスピエールたちの努力が実をむすび、また敵の利害対立もあって、内外の反革命勢力がしだいにおさえられてくると、国民の気分もかわってくる。 |

キリスト教を否定する「最高存在」の祭典
これはロペスピエールの権力の絶頂をしめすものであったが、
彼の急速な没落の始りでもあった。
|
すでに一七九三年末からフランス軍は有利に転じていたが、とくに一七九四年六月二十六日ベルギーのフルーリュスにおけるフランス軍の勝利は、思いきった軍制改革の成功がもたらしたもので、革命の危機をくいとめた戦いとして重要である。
それはまた、新しいナショナリズムの成果であった。
同時に国内の王党派による反乱もおさえられた。
こうした明るい情勢は、恐怖政治にたえてきた国民に解放感をあたえる。
いまや、祖国を救い、革命を守った恐怖政治はその役目を終えたのであり、それはうちきられてもよいのではないか。
……国民はそろそろテロ政治がいやになってきているのだ。
物価や賃銀をおさえられていることも、ブルジョワや大衆の不満をそそる。
九四年六月から七月、労働者の賃上げ要求も高まり、政府はこれを弾圧さえしている。
経済の統制というようなことは、当時の政治家には手にあまる問題だったともいえよう。
ブルジョワたちは、革命があたえてくれた生産と取り引きの自由に、できるだけ早く帰りたい。
「平等な小生産者の国」などは、ブルジョワ勢力がまさに上昇しようとしているとき、つまりは時代錯誤の空想にとどまうたのであろう。
しかしロベスピエールは従来の政策をうちきろうとはしない。いや、なおもつづく政治上の陰謀や経済上の統制違反などに対して、テロは強化されるではないか。
すでに九四年六月十日に成立したある法律は、裁判を簡単にすることによって、ギロチンの活動をますます活発にしていた(六月十日から七月二十七日までのあいだに、千三百七十六人が死刑になったという)。
ロベスピエールはこれを最後のしめくくりと思ったのかもしれないが、ともかく彼は「テロ」と「最高価格」のシンボルとしてきらわれだしたうえに、彼がルイ十六世の生き残っている王女マリー・テレーズ・シャルロットと結婚して、王位につくつもりだというようなバカバカしい噂さえうまれた。
こうしたとき、反ロベスピエールの動きがたかまってきた。
ロベスピエール派以外の山岳派議員たちは、内外の敵に対抗するために恐怖政治を肯定したとしても、ロベスピエールの道徳論や風月法の財産再分配策などには、あまり関心がなかった。
そして、強大なロベスピエールの権勢がねたましく、気がかりであった。
いつ、だれが、エベールやダントンの運命をたどるかもしれないのだ。
しかも山岳派議員のなかには、「清廉の士」ロベスピエールに告発されそうなやましさをもつ人びとがいた。
たとえば、その地位を利用して私腹をこやしたり、その権限を乱用して地方で残忍な行為をしてきたテロリストのバラス、フレロン、タリアン、フーシェなどの徒輩である。
彼らは自分たちの失脚を防ぐために、先手をうってロベスピエールを倒そうと、彼の独裁に反感をもっている他の山岳派の革命家たちとむすんだ。
それから彼らは山岳派以外の公会議員たちをだきこんでいった。
これがあの日和見的な平原派で、まえにも書いたように、彼らはともかく革命を守ってもらうために、かならずしも考え方が同じでない山岳派を支持してきた。
だがいまはそうではない。
革命が一応の勝利をえられそうだとわかってくると、平原派はロペスピエール派の独裁や恐怖政治がいやになってきた。
すねに傷もつ山岳派の連中は、たくみに彼らにさそいかけたのである。
6.7 むなしい日々
こうしたとき、ロベスピエールはいったいどうしていたのであろうか?
九四年五月のある夜、デュプレ一家を訪れたひとりの娘が、家人にあやしまれて捕えられた。
この女性はセシル・ルノー、二十歳、小さな二本の短刀をしのぼせており、ロベスピエール暗殺のうたがいがあった。
このほかにも、彼の暗殺未遂事件がおこっていた。
そのころ、ねらわれた当人、ロベスピエールは思わずもらしたという。
「私はもう生きるのはたくさんだ。」
このセシル・ルノーをふくめて、「ロベスピエール暗殺の陰謀」に関係ありとされた五十人をこえる人びとの処刑が行なわれた。
被告たちは、「国家の父」を殺害しようとしたというので、親殺しのしるしの赤いシャツを着せられて刑場にひかれていった。 |
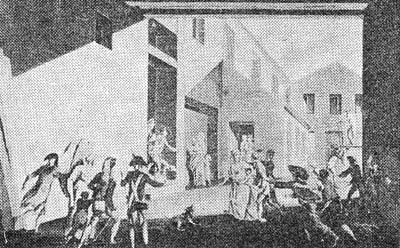
ロベスピエール暗殺のうたがいで逮捕されるルノー
彼も刑場にひかれていった
|
それは大がかりな行進であったが、ロベスピエールの勢威を示すよりも、むしろ「独裁者」の印象を一般にあたえるために利用されたようであった。
反ロベスピエールの動きは、保安委員会のなかにもうまれていたのだ。
この治安警察権をもつ委員会は、じつは公安委員会に反感をもつようになってきた。
というのは恐怖政治の効果をあげるため、公安委員会は直属の一般警察局をつくったが、これは保安委員会の職権を侵すことになったわけだ。
「カトリーヌ・テオ事件」は――結果的には、ロベスピエールはなんとか切りぬけたが――保安委員会のバディエが、彼を困らせてやろうと取りあげたものだ。
カトリーヌ・テオとは八十歳にちかい狂気じみた老女で、いまでいえば、いかがわしい新興宗教の教祖的存在、信者たちからは「神の母」と奉られていた。
ところがこの「神の母」はロベスピエールを「救世主」とあがめていたので、反対派では利用価値があったわけである。
そこへもってきて、公安委員会そのものにも内紛がうまれていた。
山岳派の策謀家たちは、この委員会のなかでロベスピエールの権勢に反感をもっている者たちに、たくみに働きかけていった。
委員の一人で、フランス軍の再建につくし、「勝利の組織者」とよばれたカルノー(一七五三〜一八二三)も、戦争指導上でサン・ジュストと対立し、ひいてはロベスピエールに「独裁者め!」とくってかかるありさまとなった。
この公安委員会の仲間割れは、ロベスピエールにとってたいへん不利であった。
その点、政治家としてある意味ではもっともたいせつな妥協性が、彼に欠けていたことも指摘されよう。
この重大なときに、最高存在の祭典――これも反ロペスエピール派には、独裁者をたたえるものとして反感をかった――ののち、六月の中ごろから一ヵ月半ものあいだ、ロベスピエールはあまり公的生活に姿を現わしていない。
このあいだ彼は一度も公会で演説せず、ジャコバン・クラブでもわずかの演説にとどまり、公安委員会に出席することも少なかった。
これはロベスピエールの肉体上、精神上の疲労によるものであろうか。
革命がはじまって以来、数年にわたる日夜の活動、とくに恐怖政治となってからの緊張の連続、それらは彼の体や神経をすりへらした。
しかも彼の思想や諸政策を理解してくれる人は少なかった。
疲れはてて気むずかしくなった彼は、このもっとも重大な時期に反対派の陰謀が進むままにまかせたのだ。
そしてあれほど行動力にとんだサン・ジュストが、陰謀に対して積極的な策をたてようとしなかったことも、ロベスピエール派の大きな手ぬかりであったといえよう。
6.8 遺言
一七九四年七月二十六日、ロベスピエールは六週間ぶりで公会で演説する機会をあたえられた。
政敵はこれによって、彼を不利にしようともくろんでいた。いつものように、彼はひややかにとりすまして演壇にたった。
一瞬、満場は静けさにつつまれる。
いまなお最高の権力をにぎる男、いまなお自分の思うままに人びとの生死をあやつることができる男……。
演説は二時間つづいた。
それは彼の数多い演説のなかでも、もっともすぐれたものの一つであり、政敵に対する最後の挑戦であり、革命に対する彼の信念のゆるぎない表現であった。
そして彼はこの「人権と正義の諸原則とにもとづいた最初の革命」が、共和国の生命が、裏切り者や陰謀家によって腐敗させられていること、恐怖政治のゆきすぎは、議員のなかの裏切り者や過激なテロリストたちの責任であることを論じ、彼らを処罰する必要を説いた。
演説は満場を圧し、ロベスピエールはふたたび公会を支配するかのようにみえた。
政敵のもくろみとは逆になったのではないか。
そのとき、議席から声があがった。
「あなたはだれを非難しているのか、その人びとの名をあげなさい!」
多くの議員たちが、これに賛同した。
だがどうしたわけか、ロベスピエールは彼らを満足させるだけ、はっきりと答えようとしない。
これは失敗であった。
重苦しい圧迫感のなかで、身におぼえがある議員たちは、「裏切り者」のなかに自分もふくまれているのではないかとうたがい、ロベスピエールに対する恐怖を強くした。
すでに彼を敵視して、これを倒そうと計画していた人びとは、ますます結束し、まだ態度をきめかねていた人びとも敵にまわることとなった。
その夜、ジャコバン・クラブに姿をあらわしたロベスピエールは、熱狂的な拍手をもって迎えられた。
ここで彼は、その日午後公会でおこなった演説をくりかえし、つぎのようにむすんだ。
「いま述べたことは、私の遺言である。
悪人どもの陰謀はきわめて強力なので、私はそれからのがれることはできまい。
私は悔いることなく、これに屈するであろう。
諸君にかたみを残すが、諸君はそれをたいせつに守りつづけてくれるであろう……」 |
クラブはいきどおりの声でわきかえり、その場にいた反ロベスピエール派の人びとは、身の危険を感じて逃げだすほどであった。
ロベスピエールはおそらく、陰謀に対する勝利の夢をえがいたことであろう。
ジャコバン・クラブのありさまは、ただちに公会につたえられた。
早くしないと、ロベスピエールにやっつけられるかもしれない――反ロベスピエールの山岳派議員たちは、その夜、必死の策謀にとりかかり、平原派議員たちを陰謀にひっぱりこんだ。
翌日、一七九四年七月二十七日(革命暦では共和国二年熱月九日)、暑さでむせかえるような国民公会の議場は、いつになく緊張していた。
これまでは報告を聞き、法令に賛成投票するだけであった議員たちも、今日は何かがおころうとしていると感じていたのである。
そしてサン・ジュストが公安委員会を代表して演説をはじめたばかりのとき、陰謀の中心の議員たちはこれをさえぎり、われがちにロベスピエールをののしりはじめた。
これは予定の行動である。さらにロベスピーエールが演壇に進もうとしたとき、やはり予定されていた叫びがあがった。 「暴君を倒せ!」
やっと演壇にたどりついたロベスピエールは、他の議員に訴えようとする。
彼はおよそ十一回も、自分の演説を聞かせようと試みたが、政敵の協力は彼が評価していた以上に強かった。
妨害作戦による長い五時間にもわたる混乱ののち、ついに一つの叫びがあがった。
一瞬、議場は息をのむ。
ふたたび騒然とするうちに、彼の逮捕が決定し、つづいてサン・ジュスト、タートンの逮捕が決議された。
弟オーギュスタンとルーバはロベスピエールに忠実なあまり、自分から逮捕された。
すべてが終わり、「共和国ばんざい!」という叫びのなかで、公会におけるロベスピエールの最後の声がきこえた。
| 「共和国だって! 共和国はなくなった。強盗どもが、凱歌をあげているのだから。」 |
6.9 ある革命家の最後
しかし、五人の逮捕に驚いたパリ・コミューンのはたらきかけによって、どの監獄もロペスピエールたちをうけいれることをためらったので、彼らはパリの市庁へ逃げてくることができた。
当時この市庁に、市政の自治組織コミューンの本部がおかれ、そこではサン・キュロット、すなわち急進的な民衆が勢力をふるっていた。
このコミューンは公会でのできごとを知ると、ただちに公会に対抗することを決意し、パリの諸区によびかけた。
しかし革命に疲れ、恐怖政治にあき、経済統制をきらい、風月法のなりゆきにも失望し、あるいはロベスピエールの専制に反感をもつ大衆は、かつてのように動かなかった。
パリのサン・キュロットを指導していたエベール派をきりすてたことが、ここにきてひびいてくる。
それでもあちらこちらから、国民兵たちが市庁前の広場に集まった。
しかし彼らには、はっきりした目標をかかげた指導者がいなかった。
ロベスピエールも、公会に対して反乱をくわだてる決心はつかない。
いままで法をおこなう立場にあったものが、にわかに公会に対する暴動の先頭に立つ気になれなかったのかもしれない。
一方、ロベスピエールたちが市庁に集まったという報をうけて、国民公会は驚きあわてた。
陰謀派の議員たちは失敗したとさえ考えた。
ともかく、彼らはロベスピエールたちに対して法の保護をとき、また兵力をもってコミューン側に対抗することとした。
夜はふけた。
二十八日午前一時ごろ、市庁前に集まっていた国民兵たちは、はっきりした指示がないままに、待ちあぐんで疲れ、あきらめて家路についた。
|
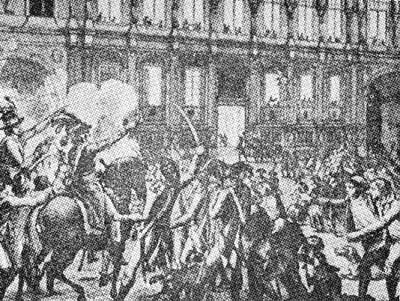
市庁をおそう国民公会側の部隊
|
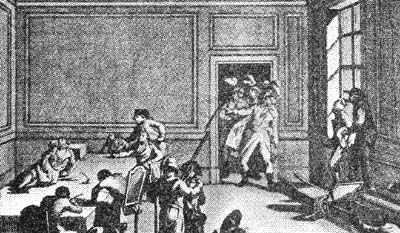
傷ついてテーブルの上に横たわるロペスピエール
彼は拳銃で自殺したが未遂で、ここで捕えられ刑場に送られた
|
これに対し公会はロベスピエールを憎む諸区からの国民兵を集めて、行動にうつった。
ある議員はうながした。
「ただちに市庁に向かって進むべきだ。
でないと、コミューンに、われわれののどをかききる時間をあたえるようなものだ。」 |
午前二時ごろ、人影もない深夜の町を通り、なんの抵抗もうけず、部隊は市庁をおそった。
彼らは密告者から、「ロペスピエールばんざい!」という合言葉を知らされていた。
このころ市庁内部はすでに混乱しており、絶望からか、ピストルで自殺したル・パにならって、ロペスピエールもみずからピストルを放ったが、あごをくだいただけであった。
オーギュスクンもタートンも傷ついて、サン・ジュストはなすがままに、捕われた(このときロベスピエールを射ったと主張した憲兵メルダは、公会に賞せられ、士官に昇進した)。
公安委員会のひかえの間にはこばれたロベスピエールは、夜があけるまで、うめき声ひとつもらさず苦痛にたえた。
十時ごろ医者がはじめて手当てをしたが、それは彼を「処刑できる状態にたもつ」ためであった。
それから彼は獄にうつされ、革命裁判所で形式的な尋問をうけたのち、刑場にひかれていった。
彼とその仲間をのせた荷車はジャコバン・クラブや、デュプレー家のまえを通って、断頭台がある広場につく。
三十六歳になったばかりのロベスピエールが「最高存在」の祝祭行列の先頭に立って、同じ道を通ってから、二ヵ月とたっていなかった。
そのとき彼に歓声をあびせた同じ群衆が、いまは、「暴君を倒せ!」と叫んでいた……。
これがフランス革命史上でも有名な「熱月(テルミドール)の事件」である。
ロベスピエールの死は革命において、一時期を画することとなる。
この事件を起こした山岳派の一部や平原派は、その後「テルミドール派」として政界を左右し、そこでは金持たちが――これまでの王や僧侶や貴族にかわって――支配する世の中になってゆくのである。
ところでロベスピエールの死後、彼と親しかった人びとの運命はどうなったか?
まず家宅そうさくをうけ、捕えられたデュプレー夫妻のうち、デュプレー自身は無罪として釈放され、それからは静かに生活して、一八二〇年に死んだ。
しかし夫人は、ロベスピエールの処刑を知って、獄中で首をくくって自殺した。
一方、エレオノールは愛人を失ったのち、ロベスピエールという姓を名のりかえなかったがゆえに、生涯を通じて他の男の姓を名のろうとしなかった。
そして彼女はまるで「未亡人」のように、一八三二年六十四歳まで、すぎ去った愛の思い出のなかに生きつづけた。
エリザペート・デュプレー、すなわちルーバ夫人は、六週間もたたない幼児をかかえて半年ばかり投獄された。
獄を出てからもいろいろと苦労し、その後、ルーバの弟と再婚した。
不幸にもまた未亡人となったが、かつての幼児がりっぱな学者に成長したため、やっとおちついた晩年をむかえて、一八六〇年、九十歳ちかくで世を去った。
このルーバ夫人はオームを飼っていたが、だれかが近づいて「ロベスピエール」というと、「脱帽! 脱帽!」と答え、また、「マクシミリアン」と問うと、「殉教者! 殉教者!」と応じ、「熱月(テルミドール)九日」に対しては、「不吉の日! 不吉の日!」と、さらに、「聖者マクシミリアンはいずこに」と語りかけると、「天に、イエス・キリストのかたわらに!」と答えたということである。
一方、ロベスピエールの妹シャルロットは、わずかのあいだ逮捕されただけで自由の身となり、知人のもとに身をよせたが、のちナポレオン・ボナパルトが政権をにぎると、年金をうけることとなった。
一八三四年、七十四歳までのシャルロットの後半生は、エレオノールとは性質はちがっているかもしれないが、ひたすらロベスピエールの思い出にささげられた。
そして誤解されている兄のために、抗議の心をこめて、彼女はその回想録を後世に残した。
彼女の葬儀には、一八三〇年七月革命のバリケードで戦った人びとが、あの「兄」への追憶を抱いて参加したという。
top
**************************************** |




 清清廉の士、ロベスピエール
清清廉の士、ロベスピエール