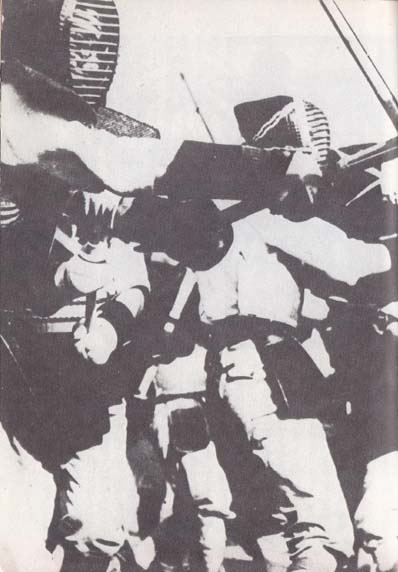|
****************************************
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
自決と武士道の特攻(神風特攻隊 2)
日本は一九四五年に、歴史はじまって以来の大変貌をとげたが、日本ほど自殺が慣習的になっている社会はない。
1 慣習的な自殺 top
今日、東京での自殺者の数は一日七人〔注〕といわれているが、これはアメリカとくらべて、けっして大きな数字ではない。しかし、日本人の自殺の特異な点は、その動機であり、また自殺音が、ふつう喜びにひたりながら死んでいくことである。
〔注〕東京都の自殺者数は、都当局の統計によると、昭和四十五年度は一日平均二・九人、昭和二十四年いらい最高の数をだしたのは昭和三十三年で、一日平均六・一人である。
恋愛におちいった若い男女が、結婚が絶望的になると、来世で一緒になるという意味の遺書をのこし、互いに身体をしばりあわせて噴火口に身をおどらせる。
あるいは、二人一緒に情死ができないときは、それぞれ別のところでも自殺するのである。
そして、このようなロマンチックな自己犠牲が世に宣伝されると、おそらくこれが口火となって、同じような自殺があいつぐことになるだろう。
一例をあげると、かつて一青年が大島の三原山の噴火口で劇的な最期をとげた、と新聞が書きたてたことがある。
するとそれ以後の一年間に、一四九人が噴火口に飛込んだと伝えられている。そのほか六八八人が警官の制止により自殺未遂となっている。最年長は六五歳の男、最年少は一五歳の少女であった。
自殺原因の調査では、家庭不和と病気が大部分をしめていたが、二〇歳から三〇歳までの自殺者のほとんどが、自殺ヒステリー症にかかっていた。
西欧と戦争をはじめた一九四一年〔昭和十六年〕から一九四五年〔終戦時〕に、日本人のとりつかれたヒステリー症は、日本の尊厳と天皇とにむすびついたものであった。
一九三〇年〔昭和五年〕のロンドン海軍軍縮会議で、日本が米英の主張に屈服したことに抗議して、草刈英治海軍少佐は、列車の寝台のなかで寝衣のまま軍刀で割腹した。
これが、そもそも騒動のきっかけとなり、それからは内閣の崩壊、満州占領、国際連盟脱退、そして万一にそなえて、米国、英国およびソ連に対する戦争準備へと発展していったのである。
ロンドン軍縮会議の海軍首席委員であった財部彪〔たからべ・たけし〕海軍大将が帰国すると、一人の右翼愛国者がやってきて、うやうやしく短刀を贈呈した。この短刀で切腹せよとの意味であった。
その後、政治学専攻の二六歳の学生が海軍省を訪れ、ロンドン条約を不満とする過激な抗議文を朗読したのち、海軍大臣秘書官の面前で切腹をはかるという事件もおこった。
2 軍人、右翼のテロ top
これら一連の事件は、やがて首相をはじめ政財界の有力者、あるいは自由主義者に対する暗殺へと発展していった。
このような右質的感情のたかまりは、一九三二年〔昭和七年〕の陸海軍青年将校と民間愛国者たちのクーデター事件で最高潮にたっした。
〔明治いらい、日本の政党政治と自由主義はしだいに成長してきた。
しかし昭和初期の経済恐慌と生活不安に対し、ときの政党内閣はなんら効果的な対策をたてることもせず、いたずらに政権争奪に熱中した。
そのため、保守的な右翼主義者や職業軍人の不満が増大し、それが日本にファシズムを急速に育てあげることになった。
一九三〇年〔昭和五年〕十一月、浜口雄幸(はまぐち・おさち)首相が東京駅頭で狙撃されたのは、このファシズムによるテロ行為のはじめであった。
それ以後、政財界の巨頭があいついで暗殺された。
五・一五事件=昭和七年五月十五日、海軍士官六人、陸軍士盲学校生徒こ一人が犬飼毅首相を射殺し、牧野伸顕内大臣邸、警視庁、政友合本部、日本銀行などを襲撃した。
また同夜、農民決死隊の青年たちが東京市内の変電所数ヵ所を襲撃したが、首相殺害以外は失敗し、全員自首した。
五・一五事件によって、政党内閣は否定され、軍部、官僚による挙国一致内閣が生れた。
しかし、軍部の発言がいよいよ強くなり、また軍人の一部には、武力にうったえて国家革新をはかるべきだ、という過激な意見がたかまった。
二・二六事件=一九三六年〔昭和十一年〕二月二十六日、陸軍の青年将校に指揮された反乱部隊が、重臣たちを襲撃し、斎藤実内大臣、高橋是清大蔵大臣、渡辺錠太郎陸軍教育総監らを殺害した。
この事件以後、日本のファシズム支配が決定的となり、民主主義者や自由主義者に対する弾圧が初められた〕 |
この暗殺事件は、単発的なものではなく、一九三〇年代には右翼的感情の激発による多くの事件が起った。
これら一連の事件は、日本の国民感情に深く根をおろしていたし、日本の過去の諸事件にならって支持されていた。
また日本の大部分の新聞からも、何百万人もの陸海軍将兵からも、さらに多くの一般大衆からも支持されていたのである。
上海事変〔昭和七年、上海での日本軍と国民政府軍との衝突事件〕では、陸軍の三人の下士官兵がダイナマイトを背おって、中国軍陣地の鉄条網に突入して、体あたりでこれを爆破した。
〔陸軍工兵隊の江下、北川、作江の三人は「爆弾三勇士」ともてはやされ、東京・芝に銅像がたてられた〕
彼らは軍神としてあがめられ、彼らの母親たちが特別仕立ての列車で国内をまわったとき、群衆は彼女たちに近寄って、着物のたもとに接吻した。またペルー在住の日本人は、感激して三勇士の記念碑建立の資金をおくってきた。
3 井上千代女の遺書 top
また、こんな話もある。
井上千代という婦人は、軍医の夫が満州へ出征する前日、結婚衣裳をつけて、頚動脈をかききって自害した。
夫へあてた、つぎのような遺書が残されていた。
「御主人様へ……私の胸は、喜びでいっぱいです。あなたにお喜びを申しあげる言葉もないほどでございます。
明日あなたが出発されるのに先立って、私はこの世を去ります。どうぞ後顧のうれいなくご活躍くださいませ。
もはやご心配をおかけするものはなくなりました。
私は無力ではありますが、あなたとあなたの部下の方々が御国のために力いっぱいお働きくださるようにと、私のできうるかぎりのことをいたします。
これが、私の願いのすべてです。私の人生は幸福でした。深くあなたのご好意に感謝いたします。
この世は、はかないけれど、つかの世は永遠のものときいております。
いつか、あの世でお会いできることを楽しみにお待ちしております。
満州は寒さのきびしいところとのよし、なにとぞお身体を大切になさいますよう。
なお、ここに四〇円を封入いたします。
戦地につかれたときには、これを部下の方々におわけくださるようお願いいたします。
御武運の長久を草葉の影からお祈りいたしております」 |
4 “花は桜木、人は武士” top
ここにかかげたいくつかの事例のような中世的情緒主義が、一九四○年に世界に雄飛しようと決意した全体主義国家日本の背景をなしていたのである。
日本国民は、民族の優秀性と、西洋支配から東洋民族を解放するという、彼らに課せられた神聖な使命とについて、教えこまれていた。
日本の軍事指塀者たちは、以前から、欧州で戦争が起れば、東洋で自由に活動できる機会がくると見越していて、時機到来すれば、ただちにこれに応じうる用意をしていた。
国民は、何年間も戦時体制優におかれていて、軍は米英両国に対する必要な戦争準備を完了していた。
二五〇万の将兵は、天皇のお召しがあれば武器を手にして、アジアから太平洋をこえて、抑圧された民族を解放しようと待機していた。
ラジオ放送局からは、聖なる使命を強調する宣伝文句が、つねにながされていた。
将軍や提督たちは、あるいはオーストラリアを指向し、あるいはインドに目をかけていた。
あるものは、ロンドンやワシントンで戦勝パレードをすることを夢みていた。
陸海軍の将兵は、このような未来の予測を、生まれつきの東洋的宿命観で冷静に受入ていた。
この時代の日本の詩人たちは、これら「戦士」たちを日本に咲きほこる桜の花にたとえていた。
日本人は桜の花を、純潔と忠誠心と愛国心の象徴として考えていたのである。
花の盛りは短いので、日本の兵士たちの命も、桜花のように短いものといわれていた。
花は桜木 人は武士
これは、兵士の生命は国に奉げられていて、時がきたならば桜花のごとくいさぎよく散るであろう、という意味である。
5 陛下の御為に top
日本の小学校は、愛国心について、西欧人には理解できないような情熱をもって教えこんだ。
日本の兵士は、誇りをもって天皇につかえ、鉄の規律をあまんじてうけ、なんら疑うこともなく、サムライ精神を受入たのである。
「たおれてのち止む――恥辱をうけんよりは死を」とは、兵士たちのおきてであり、武士道の基本でもある。
国民は軍隊を信頼し、また尊敬もしていた。
もし将軍たちが世界を征服するのだといえば、国民は喜んでそれに乗り出したであろうし、兵士たちは、その戦いで死ぬことを辞さなかったであろう。
日本は、その発展を兵士たちに大きく期待していた。
欧米では日本軍兵士のことを軽蔑して「蟻」や「海狸」〔ビーバー]や「昆虫」などにたとえてきたが、ビルマ戦線の英第十四軍司令官として有名なスリム元帥は、日本兵についてつぎのように述べている。
「我々は最後の一兵、最後の一弾となるまで戦え、としばしばいうけれども、日本兵こそは、これを真に実行しうる唯一の兵士である」
日本兵に対しては、最後の一兵、最後の一弾となるまで踏みとどまれと命令する必要は、少しもなかったのである。
それどころか、場合によっては、名誉をすてて撤退せよ、と命令しなければならなかった。
敵にうしろをみせるのは卑怯なことであり、家名を汚すことであった。
兵士が望む最大の名誉は、天皇のために死ぬことであった。
以上のようなことから、日本軍の高級司令部では、すべての兵士は平等に勇敢であり、それゆえに、イギリスのビクトリア十字勲章やアメリカの議会名誉勲章のような、勇敢な行為にむくいるための勲章は必要としなかった。 |

若き日の昭和天皇:
日本帝国陸海軍の最高統帥者、大元帥であった
|
日本の勲章は、作戦への参加徽章か、あるいは長期または顕著な業績に対する勲章だけであった。
〔日本の金鵄(きんし)勲章は、武功勲章ではあるが、他国の武功章のように個々の勇敢な行為に対し、即座に与えられる性質のものではなく、累積した功績や、年功なども加味されていた〕
陸軍法規には、降伏は認めておらず、降伏は恥ずべきものとされていた。
戦時捕虜についてのジュネープ条約はこの見解と矛盾するので、日本は、ついにこの条約に参加しなかった。
日本軍は、捕虜に対しては一般に、全く軽蔑の感情をいだいていた。
このため日本軍での捕虜の権利は、しばしば無視されたのである。
欧米の兵士は、最後の一弾まで戦ったのち降伏することは、べつに不名誉とは考えない。
しかし日本軍の兵士は、最後の一弾は自決用にのこしておくのである。
あるいは自決ではなく玉砕攻撃によって自らの命を断つのである。万一負傷したり人事不省でやむなく捕虜となれば、故国にかえっても小さくなっていなければならず、しばしば自殺をこころみることがあった。
6 「軍人勅諭」の精神たたきこむ top
日本軍の兵士は、前述のように世界に類のないほど死をおそれぬ勇猛さをもっていたが、死に対して宿命的なあきらめをもつということは、けっして日本人本来の気質ではなかった。
当時、日本でも青年たちのなかには、欧米諸国と同様に、徴兵を忌避するものもいたし、兵役をのがれようとして、いろいろな工夫をするものも少なくなかった。
だが、ひとたび軍隊にはいれば、彼らもたちまち精兵となったのである。
新兵は、三ヵ月のきびしい初歩訓練をうけるが、これによって、彼らは天皇と祖国と、連隊の名誉のためにはいつでも死ねるようになる。
ピンタをくい、足げにされる苛烈な訓練は、彼らを精強な兵にきたえあげるのである。
「なぐって、さすって、一人前にする」という言葉は、新兵教育係りの下士官が始終口にするモットーであった。
また新兵は「おまえたちが、きたえあげられたときは、平然と敵を殺せるようになるだろう」と耳にタコのできるほど聞かされた。
「天皇のために一命を捨てることこそ、最高の名誉である」というスローガンが、徹底的に叩きこまれたのである。
陸軍の兵営では、毎夕兵士は皇居を遥拝し「……義は泰山よりも重く、身は鴻毛〔こうもう〕よりも軽し……」と「軍人勅諭」を暗誦させられた。
「軍人勅諭」の暗誦は、兵士たちに、神聖なる任務遂行と光栄ある報酬、すなわち戦死を、心に深くう植付る有効な手段であった。
軍隊内の教育と同時に、兵士の家族に対する教化も、忘れられることはなかった。
新兵が入営すると、すぐに指揮官から家族へ手紙がだされた。
それは、名誉ある御奉公をけっして妨害しないようにと要請していた。 |

在郷軍人、国防婦人会員に見送られて
戦地に赴く出征軍人
|
このような宣伝、教育の効果は、さきの井上夫人の遺書にもハッキリとあらわれている。
また多くの軍人は、戦地へ出征するまえに葬儀をすませて「一死もって君国に報いん」の心意気を示したのであった。
日本の軍歌には、つぎのような悲壮な歌がある。
海ゆかば、水漬(みず)く屍(かばね) 山ゆかば、草むす屍(かばね)
大君の辺(へ)にこそ死(し)なめ かえりみはせじ
7 悠久の大義に生きる玉砕 top
日本の兵士たちは、このような心構えできたえられていたので、決死隊の志願者をつのると、死地におもむく覚悟のできたものが、いつも大勢名乗りでた。
しかし、人間にとっては、死よりも生の方が好ましいのは当然で、日本国民といえども例外ではなかった。
そのため軍隊は、前述のような教育を行っていたのであるが、これに加えて戦死をさらに魅力的にするために、ある種の恩典が約束されていた。
陸軍の典範今には「天皇の御為に死すことは、永遠に生きることである」と書かれている。
この思想が、死をかえりみない“バンザイ突撃”すなわち玉砕攻撃の常用化へと発展していったのである。
戦争における死について、東京の某新聞は、つぎのような意見をかかげたことがある。
「どんな悪人であっても、またこれまで、どれほど悪事を重ねてきても、彼らが一たび戦場に立ったときは、過去のいっさいの罪悪はつぐなわれ、彼らは無垢〔むく〕となる。
日本の戦争は、つねに天皇の名において戦われ、それはまさに聖戦である。
この聖戦に参加するすべての将兵は、天皇の代理者である……戦場において死をとげた人びとは、善人であろうと悪人であろうと、すべて神としてまつられるのである……」
しかし、このような軍官民あげての宣伝にもかかわらず、全国民の生への執着を断ち切ることはできなかった。
戦場におもむく兵士たちの多くは、 「千人針」――木綿の腹巻きに、千人の婦人がぬいこみをしたもので、これは弾丸よけのお守りといわれた――を身につけていた。
この風がわりなお守りは、大変人気があったので、出征軍人の身内や愛人は、街頭で、とおりすがりの婦人たちに一針ずつぬいとりを請うたものである。
|

靖国神社に参拝される天皇
|
8 合い言葉“靖国神社で” top
日本軍の兵士は、不幸にして戦場の露ときえても、このときすでに神々の列に加わり、霊魂は靖国神社にまつられていると考えていた。
「靖国神社でまた会おう」というのは、戦争中の日本人の合い言葉であった。靖国神社にまつられた英霊は、神聖な日本をまもる護国の神となるのであった。
このように教えこまれ、これを信ずることによって、日本軍の兵士たちは喜びいさんで死地におもむいたのである。戦死者は神々の列に加わることを考慮すると、戦闘後の死体回収は、日本軍にとってかなりわずらわしい問題であった。
死体処理は火葬を原則としたが、それができないときは、死体の一部を骨にするか、爪をきりとるかして、遺骨として故郷の家族におくるのが例であった。
戦争中は、年二回靖国神社で丁重な祭興が行われた。
そのときには、戦死者の名前がひつぎに納められ、たいまつをかかげた行列で祭壇に運ばれて、そこで神としてまつられたのである。神となった戦死者は、永久に日本を守護すると信じられた。
日本軍における敵捕虜の取扱いは、日露戦争当時は申し分なかったが、一九三〇年代後半以後〔日華事変以後〕は変化した。
捕虜たちは、日本兵に野獣のような手荒い扱いをうけた。
日本兵たちは、捕虜たちが生きながらえたことは幸遅だと認めながらも、その事実によって、彼らに対する扱いぶりは、少しの容赦もなかった。
これと同じような態度で、日本軍は、占領したアジア各地の住民に対してものぞんだ。
このため、大東亜共栄圈に加えられた住民たちが、彼らの“解放者”によせた期待も、夢にすぎなかったのも当然であった。
このことは、日本政府が、アジア人のナショナリズムについてなんら理解していなかった、ということではない。
しかし、東京から占領地に派遣された文官の司政官たちも、そこでは軍の指揮官の補助的役割りにすぎなかったので、軍人たちから、文官は部下とみられていたのである。
|

日中戦争で中華民国の首都南京を城壁に一番乗りして凱歌をあげる陸軍の将兵
|
9 防御はなく攻撃一本槍 top
日本兵の能力は、多くの点で称賛される価値があった。すべてが計画どおり進んでいる場合には、彼らはすばらしい戦士であった
開戦当初、英軍も米軍もビルマやフィリピンでの苦しい戦闘体験を通じて、日本兵のやり方を学んでいたので、日本兵が利口で技量が優秀であることを重視していた。
日本軍が夜襲がうまいこと、策略にとみ、狂信的な勇気をもっていることなど、すべてが、英米の兵士たちのあいだに、劣等感を生じさせる効果があった。日本兵の優れた資質が、新聞に劇的に報道された場合に、とくにそうであった。
日本軍兵士は、防御された地点に座り込んで、ノンビリしているような連中ではなかった。
彼らの成功は、全く攻撃によるものであった。
日本軍が戦線で、おとなしくしているときは、たいてい側面にまわって、奇襲をかける準備をしているのであった。
この戦闘上の特質は、たんに、彼らが戦街上の原則に従うというようなことではなく、いかなる危機にも即応できる、しっかりした心構えによるものであった。
一例をあげると、ある戦闘部隊の記録につぎのようた一節がある。
「……生存者僅少、兵器もすべて損傷せり……部隊は残存全兵力をもって、明朝四時を期して、突撃を敢行せんとす……」
この文章のなかには“防御”という語句は見当らない。
また日本軍の参謀は、部隊の停止地点を表現するとき“前進のため確保せる”地点というのである。
日本軍は、他国の陸軍に先例がないほど狙撃兵を活用した。日本軍の陣地を撃破したとき、あるいは日本軍の攻撃を撃退したときでも、その後しばらくのあいだ、戦場は日本軍狙撃兵の脅威にさらされるのが常であった。
狙撃兵は地形地物を利用して、何時間でも根気よく適当な獲物をまった。 |

中国の戦闘で敵陣に迫る海軍陸戦隊員
|
階級章や態度などで将校と判断されたものが、よい目標となった。
しかし、狙撃兵の射撃はあまりうまくなかった。
しかし、見えざる狙撃兵の脅威は、経験不足の連合軍将兵の心に、深い恐怖心を植付たのであった。
この状態は、連合軍が狙撃兵対策を確立するまで、かなり長いあいだ続いたのである。
|

渡河訓練中の陸軍部隊

皇紀2600年記念観兵式に参加した陸軍士官学校生徒隊
|
10 得意の夜襲 top
日本軍部隊が、ジャングルのなかを夜間巧妙にくぐりぬけたことは事実である。
しかし“音もなく”とか“姿もみえず”という表現が、よく新聞紙上にみられたが、これはあたっていない。
一般に信じられているのとは反対に、日本軍は、マレー作戦がはじまるまえには、ジャングル戦の訓練をほとんどやっていなかった。
しかも一九四四年〔昭和十九年〕ころでさえ、彼らの動きは“音もなく”どころではなかった。
日本軍の哨兵の存在は、しばしば、彼らのたえまない無駄口や会話から暴露したのである。
だが、夜襲は日本軍の伝統的なお家芸で、これによって連合軍が多いに悩まされたのは事実である。
日本軍は暗闇の中を、道路のないところでも斥候があらかじめつけた白布の目印をたよりに、藪をぬけて襲いかかった。
突撃のまえには相当の音もだしたし射撃もした。ついで喊声〔かんせい]をあげ「バンザイ」を連呼しながら突進してきた。
そしてしばしば、英語で罵声をあびせたり、あるいは指揮をあやまらせるような言葉を投げかけてきた。
日本軍の突撃はたいていの守備兵の抵抗を粉砕したが、つねに身を危険にさらし、熱狂的な勇気を発揮して、攻撃のためには犠牲をいとわなかった。
機転がきいていて、耳にした名前をすぐ使っては、暗闇から呼びかけてきた。
また、英米軍の合い言葉を、それが日本人の声だとバレるので――日本人にはBとV、LとRの発音を区別することがむずかしい――呼びかけてきた。
11 傷病兵は邪魔扱い top
日本兵の特質の一つとしてよくいわれたことだが、彼らは一袋の米と池の水で一週間は生存できた。
しかし連合軍の兵士たちは、そのような環境においこまれると、すぐ病気になるといわれた。
日本兵は、肉体的な困難には英米人よりも強いといわれたが、スタミナの点では大差なく、雨に降られてぬれれば、連合軍の兵士と同じように、マラリア、赤痢、チフス、その他の熱帯病にかかったのである。
大きな相違は、連合軍の病兵はあくまでも貴重な人として治療されるが、日本兵の場合は、死に近づくまでは病人として取り扱つかわれることは、まれであったことである。
まさに死がせまって病人とみなされたときでも、そのようなものは、情けない弱者としてみられたであろう。
そんなわけで、連合軍の傷病兵に対するいたわりは、輸送上の障害になったが、日本軍には、このような問題はおこらなかった。
その報いとして、連合軍の傷病兵は戦線に復帰できたが、日本の傷病兵の大多数は、文字どおり餓死に追いこまれたのである。 |

故郷の人びとにむかえられる戦死者の英霊
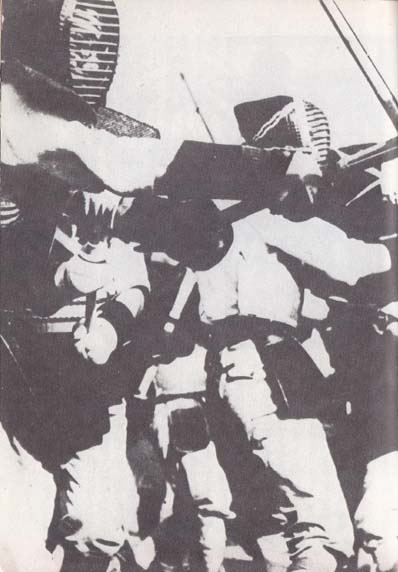
襲撃剣訓練に励む海軍陸戦部隊 |
日本軍のジャングルに対する態度は、連合軍よりも、もっと真剣なものであった。
日本軍は、ジャングルの有利な特徴を研究して、すぐそれに適応し、その利点を活用するように、装備と戦術とを改善した。
これが、これまで宣伝れてきた“日本兵は超人間的なジャングルの戦士”という評判を高めた原因であったのだ。しかし日本兵も、他国兵と同じく、人間的な弱点をもっていた。
暗闇で道にまよい、戦闘で混乱におちいることがあるのは、欧米の軍隊と全く同じことであった。
日本軍の一小隊長が書き残した日記によると、彼らの問題は、敵にも問題になる事柄であった。
「日没がせまるとともに、我々は敵の七〇メートル以内に接近した……
わが隊形のあやまりと豪雨にさまたげられて、攻撃の実施は不可能となった……夜襲を決意したが、人員を予定どおり集合できない……貴重な時間は容赦なくすぎていく……班長さえも集めることができない……広瀬一等兵は、敵弾で戦死した。浜田伍長は暗闇のため、部下を集めることができない……暗闇のために、我々は進む方向をあやまった」
|

訓練のあいまに肩をたたきあう兵士たち
|
12 真の勇気に欠ける top
日本軍は、パレードの技術よりも実績に重点をおいた。服装はおそまつそのものだった。
だが将校は、ときおり兵士たちのまえで赤い懸章を肩からかけたりして、おめかしをした。
軍刀をブラさげてくることもあったが、これは場所にそぐわないばかりでなく、ズングリした体格には大きすぎて、時には道化芝居の役者を思わせた。
彼らは、兵士を無慈悲に駆りたてて、連合軍兵士なら行けそうもないようなところへも行かせた。
ときには、人間の耐久力の限界をこえると思われるようなこともさせた。
それでも日本兵は、ためらいもなく、それに服従した。
不潔と食糧不足に加え、きびしい罰則が軍隊勤務にはつきまとった。
彼らの生活は、ときおり日本人の慰安婦がいる施設をおとずれるとき以外は、およそ快適とは縁の遠いものであった。
その慰安所でさえ、階級による差別があった。
“無敵の”、“不沈の”あるいは“不敗の”などという言葉は、東京の軍指導部お気に入りの形容詞だった。
日本帝国陸海軍のものの考え方は、”攻撃”という字句を中心に形成され、あまりにも攻撃精神に重点をおきすぎていた。 従って日本軍が、ひとたび防御に直面させられたとき、彼らは敗れた。
彼らの勇気はめったにはくずれない。しかし、その勇気を理性的に活用できないのである。
日本の軍人にとって、戦闘に敗れることは不名誉であったが、戦闘で多数の兵を死なせることは不名誉ではなく、むしろ勇敢さの証拠であった。
日本の前途に敗戦の影が濃くなってきた一九四四年〔昭和十九年〕には、自決と武士道――名誉ある殉国――とを組合わせて、大々的な特攻作戦に突入するのが、理にかなったことのように思われたのである。
top
**************************************** |