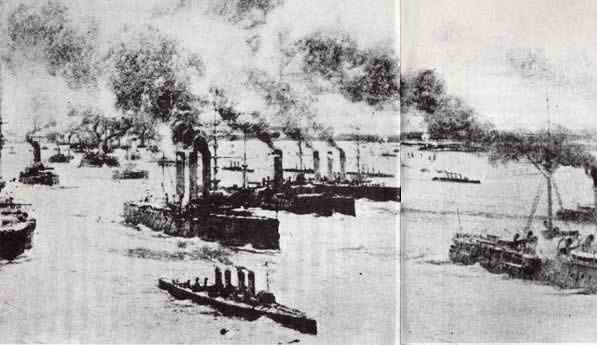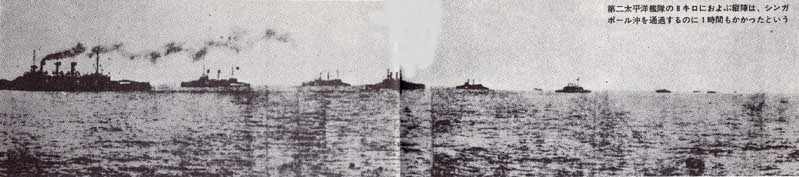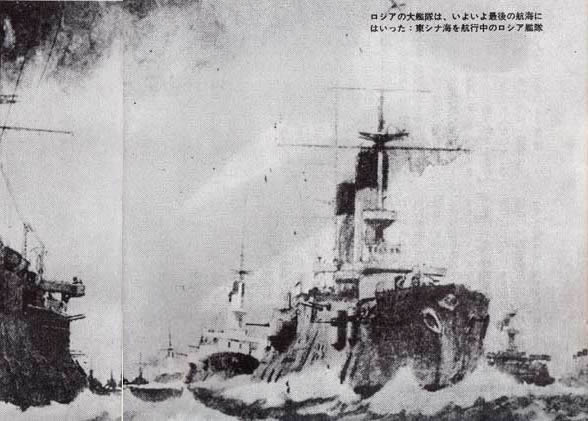|
****************************************
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ロシア司令長官、快速北進を断念(日本海海戦6)
第二太平洋艦隊の消息について、次にはじめて世界が知ったのは、三週間後にマラッカ海峡に出現したときである。黒煙は濛々と厚い雲をつくり、まばらなその縦陣は、八キロにわたってのびており、シンガポール沖を通過するのに、一時間ちかくもかかった。
|
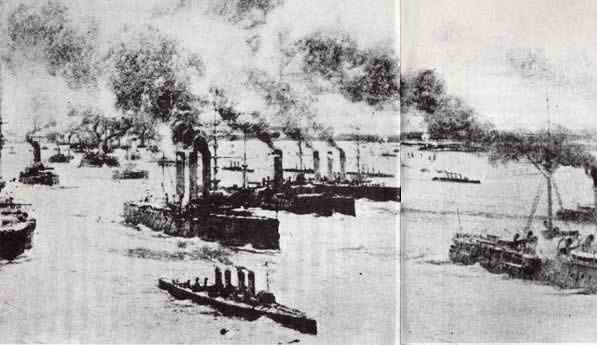
ついに、ロシアの大艦隊が、その姿をアジアにあらわした:マラッカ海峡に入る第二太平洋艦隊
|
1
奉天陥落、ますます事態は悪化 top
四月七日の午後、シンガポール沖を通過中に、ロシア国旗をひるがえした汽艇が、ロシア領事を乗せて急行し、提督に重大な情報を伝えたい、と信号した。
旗艦は停止するのが危険だから、情報は駆逐艦「ベドウイ」へ手渡せ、と返信した。「ベドウイ」にメッセージを渡すと、領事は再び旗艦「スウォーロフ」の舷側へちかづき、メガホンで大声を出した。
「奉天〔現在の瀋陽〕は陥落……クロパトキン将軍は解任され、リネヴィッチが後任に任命されました………ネポガトフ提督の第三艦隊は、貴官に合流すべく、いましがたジプチを出航しました………」
夕方、ペトログラードからのメッセージを読んで、提督はさらにくわしい指令を知ったが、それによると、コーチシナ〔いまの南ヴェトナム〕沿岸のカムラン湾へ進航し、そこでほしくもない増援艦隊を待てという。
ネボガトフがすでにジプチ〔アフリカ東岸、紅海の南端〕を出航しているとすれば、三週間かそこらでカムラン湾へ着くはずである。
この面白くもない命令のあとに、さらに提督を不愉快にするくだりがついていた。
東郷艦隊を撃破したあとウラジオストクヘ着航したら、艦隊の指揮権は、鉄道でやってくるピリレーフ提督へ引渡すべし、というのである。
ところが、その後の数日、艦隊が、マレー沿岸沖から、さらにフランス領インドシナ〔いまはベトナム、カンボジア、ラオスにわかれている〕沿岸沖を北進するあいだに、ロジェストヴェンスキーは、一つの大胆な決意に達した。
それは、カムラン湾で後続第三艦隊を待って、きたるべき会戦の勝機をのがすよりは、あっさりカムラン湾をとおりぬけ、あとは停止せずにウラジオストクヘ向けて北進する、というものである。 |

増援艦隊(ロシア第三太平洋艦隊)の司令長官ネボガトフ少将
|
おそらく東郷は、第三艦隊増援のことを知っており、ロジェストヴェンスキーがそれを待っているものと予想しているにちがいないから、彼のこの計画は、東郷の意表をつく公算があった。
それに、ネボガトフのおいぼれ艦隊にペースをあわせて遅れたりしなければ、大きな遭遇戦をせずに逃げ切れるかもしれない。
そして、いったんウラジオストクにたてこもったら、日本の満州との交通を妨害することができるだろう。
この艦隊の重みを、きたるべき和平折衝(それが間違いというみこみはいまのところないが)のテコに使うことができないまでも、これが、彼の艦隊のいまのぞみうるせめてもの奉公であろう。
しかし、中央政府の命令に不服従ではあるが、きわめて実効性のあるこの計画を、ついに彼が強行できなかったのは、えてして歴史的大事件の方向をきめるものがそうであるように、ごく小さな出来事のためであった。
四月十二日、カムラン湾南方九七キロのところで、ロジェストウェンスキーは、心にひめた新計画にのりだし、まず給炭のため停船した。
これから一気に目的地へ北進できるわけである。
その朝、いつもの例で、各艦艇は手もちの炭量を信号で報告した。
一昨日の手もち量から昨日の消費量をひけば、すぐに計算される。
ところが、あつまった数字の正確さを調べるため、長官は異例の指示をだした。
現在の手もち量を実際に計量してすぐ報告せよ、というのである。
各艦艇は、その朝、給炭がはじまったときの量よりも、約一〇〇トン多くを報告した。
ただ一艦だけ「アレクサンドル三世」が、はじめはまるで報告してこなかったが、催促されて、その日はやく報告した手もち量より四〇〇トンすくない、という信号をおくってきた。
ブハウォストフ艦長がひそかに心配していたにもかかわらず、「アレクサンドル三世」は、これまても全艦隊のなかで最優秀艦であることをしめしてきた。
機械的な故障はいちばんすくなく、給炭ではいつも最高能率賞をもらっていた。
ところが、いま「アレクサンドル三世」が、この信望を維持しようとして無理をし、給炭のたびにその量をじっぞいよりは数トン多く報告してきたことの積みかさねが、発覚したのである。
だから、いまの手もちではウラジオストクまでの直行は無理である。
サイゴンから給炭船を何隻かよび、まるまる二日間かけないかぎり、この不足は埋合わせようがないのであった。
ロジェストヴェンスキー提督は、上司にたいしてもそうだが、部下にたいしてもあまりものをいわぬ司令長官であった。
だから、二日のおくれが、敵の意表をつく計画を駄目にしたと考えたのか、あるいは、たんに「アレクサンドル三世」の不始末を不吉な前兆と考えたのかは、彼が、誰にも語っていないのでわからない。
ただ「アレクサンドル三世」が、四〇〇トンの不足は計算の間違いではない、という信号旗を掲揚すると、司令長官は、無言で立ったまま、信号旗をみつめていた。
両手でてすりをぐっと握り、両顎が例のクセで神経質に動き、苦々しい顔をしていた。
しばらくして彼は、ド・コローニュ大佐にふりむき、新しい命令をだすように指示した。
「本艦隊はカムラン湾へ行き、ネボガトフの到着を待つ」というものだった。
|
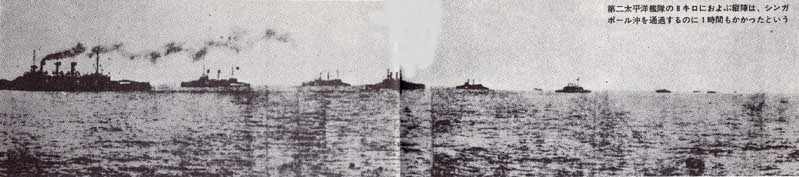
第二太平洋艦隊の8キロにおよぷ縦陣は、シンガポール沖を通過するのに1時間もかかったという
|
2 悪夢のような復活祭 top
カムラン湾における復活祭滞留は、一種の悪夢であった。
ノシベ滞留よりはみじかかったが、ここでは、とくべつの災難があった。
フランス的きまぐれと無頓着さというのか、ノシベでは、三ヵ月ちかくものんびりと滞在がゆるされ、中立条約の厳密な解釈などというやっかいなものに悩まされないですんだ。
ところがカムラン湾では、満州戦線での最近の戦況に影響されたのか、寛容さは少しもなかった。
四月十四日、艦隊がひろい湾内に投錨してから数日すると、ロジェストヴェンスキー提督は、フランス極東艦隊副司令官のド・ジョンキエール少将の訪問をうけた。
人を魅了するていねいで礼儀正しい士官であった。
彼は、うやうやしく歓迎のことばをのべただけで、巡洋艦「デカルト」で帰っていった。
ところが、四月二十二日になると、ド・ジョンキエールは再びあらわれ、今度は新しい指示をたずさえてきた。
「はなはだいいにくいことではあるが、中立法の規定があるから、二四時間以内に出港をお願いせざるをえない」
という。ロジェストウェンスキーは指示にしたがったが、わずか数キロさきのつぎの港ヴァンフォンまでしりぞいたにすぎなかった。
今度は、この地区の行政官が、同じ退去要求をもってきた。
そしてそれ以後は、ロシア艦隊は、まるで警官の目をかすめて入口を出たり入ったりする泥棒のように、日中は低速で巡航し、夜間は港内へまぎれこんだ。
ロシア人にとってクリスマスよりも大切な復活祭は、悲しむべき状態で祝われた。
航行中しょっちゅう乗組員がトラブルをおこした戦艦「アリヨール」では、カムラン湾で積みこんだ家畜類のなかに、一頭、やせて病気らしい牝牛がいた。
土曜日(十六日)は復活祭の前夜だったが、牝牛が死にそうだと知らされた副長は、あわてた決定をくだした。
「すぐ屠殺しろ。水兵らの明日の晩餐になる」
ノーヴィコフ・プリボイが記述したように、コック長が士官食卓のためにニワトリの丸焼き、ケーキなどをつくっていることを知っている水兵たちは、待ちのぞんだ復活祭のご馳走が病気の牛だときくと、当然の反応をしめした。
それは、やがて全水兵の抗議集会へと発展した。不平分子は後甲板になだれこんで行き、ディナーに上肉をよこせと要求し、また、禁固室にぶちこまれている水兵一人を釈放せよと要求した。
艦長代理から報告をうけたニコライ・ユング艦長は、禁固兵を釈放し、上等の牛二頭を屠殺しよう、とおれてでた。
だが翌日、反乱にちかいこの騒ぎを耳にしたロジェストヴェンスキーは、「アリヨール」に乗りこみ、上甲板へのぼって、全将校と全水兵をどなりつけた。
「きさまらは、海戦で自分の血を流さなければ、その罪を洗いきよめることができんぞ。それができない奴は、生皮をはいでやるからそのつもりでいろ!」 そして、士官、兵隊のなかから無造作に八人をえらび、囚人船として就航していた輸送船「ヤロスラーウリ」へ送り込んだ。
復活祭には、もう一つ暗い話がある。まえからあまり頑健ではなかったフェリケルザム提督の容態は、ノシベ到着いらい急速に悪化し、いまは瀕死の状態で船室に横たわっていた。
一方、司令長官は、ペトログラードヘ「カムラン湾に到着。命令を待つ」と打電したが、すぐ返ってきた回答は、「第三太平洋艦隊到着まで滞留せよ。なお、動静を逐次報告されたし」というつれないものであった。
3 増援艦隊到着士気も高まる top
昼間は沿岸沖を徘徊し、夜間はヴァンフォン湾にかくれる、という行動を数日続けているうちに、ようやくネボガトフの艦隊がちかづいたことがはっきりしてきた。
第二太平洋艦隊には、新式無線装置が装備されていたが、いままでは、ほとんど役にたたなかった。
ところが五月九日、強力なその受信機をそなえた通信傍受艦「ウラール」が、傍受した通信のなかに、ネボガトフの第三太平洋艦隊が五月五日了フ″カ海峡を通過した、という情報があったのである。
その午後はやく、南の空に黒煙がみえ、五時ちかくになると、スエズ経由で一万六〇〇〇キロの航程を三ヵ月たらずで航行したネボガトフの艦隊が、ゆっくりと水平線上にうかんできた。
二つの艦隊は、いずれも長い単縦陣形をつくり、ちかづくと礼砲をとどろかせ、水兵たちは立って帽子をふった。
やがて第三艦隊は大きく旋回し、第二艦隊の右舷真横に整列した。
やがて汽艇がネボガトフを「スウォーロフ」へ運んだ。
丸顔に湿疹のできた小柄で太鼓腹の姿が舷梯をのぼって行くと、上ではロジェストヴェンスキーが待っていた。
両提督は、幕僚をともなって長宮室へ消えた。ネボガトフは、あとでこう書いている。
私のはじめの印象では、提督は幕僚のいるところでは計画をあかす気持はなく、すぐに二人だけで話す機会をつくってくれるのだろうと思った。
しかし、三〇分ばかり一般的な会話をしたあと、旗艦へ戻ってよいといった。……
私が全航程中提督にあったのは、このときだけである。
彼は二度と私を招かなかったし、彼から「ニコライ一世」へきたこともない。
我々は作戦計画を論じあったことは、一度としてなかった。彼は私に指示も助言もあたえなかった。 |
増援艦隊の到着で、また四日おくれた。第三艦隊がヴァンフオンで給炭し、水や糧食をつみこみ、緊急修理をやっているあいだに、ネボガトフは、彼の上司の司令長官の艦隊命令や戦闘指令などの部厚い書類に目をとおした。
こうしてついに五月十四日、いまや倍強されたロシア艦隊は、驚くべき航海の、最後の旅程へと発進していったのである。それは、海軍史上まったく前例のない航海であった。
マダガスカルからカムラン湾まで、えんえん七二〇〇キロというもの、いかなる港へもよらずにこの犬航海に成功したことは、イギリスでさえ感嘆の念をよびおこした。
“狂犬艦隊”という罵倒は、第一級の海洋的偉業をたたえる率直な賞賛へとかわった。
アメリカでは、一九〇五年四月二十二日の「サイエンティフィック・アメリカン」紙が、長文の記事をかかげ、ロシアはけっきょく世界第三の大海軍国であり、ロジェストヴェンスキーの艦隊は、隻数において東郷のそれをかなり上まわるものだと指摘し、冷静な客観的評価をこころみた。
その結論には、耳を傾けるべきものがある。
「ロジェストヴェンスキーが敵を粉砕し制海権をにぎり、大山とその陸軍を日本から孤立させるならば、敗戦を転じて勝利となし、ロシアのために、まさにその手からこぼれおちようとする帝国の栄光を救うことにもなるであろう」
艦隊内部でも、決断の日がちかづくにつれ、司令長官への忠誠心と、艦隊そのものへの信頼感とが新にわいてきた。
インド洋を横断しながらの艦隊運動訓練は、射撃訓練とあいまって艦隊の能力を非常に高めた。
|
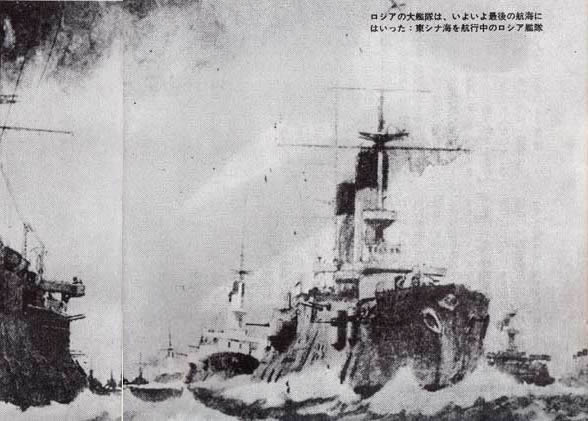
ロシアの大艦隊Jは、いよいよ最後の航海にはいった:
東シナ海を航行中のロシア郷隊
|
4 針路を対島海峡にとる top
ヴァンフォン出航後七日間、艦隊はフィリピンと台湾のあいだをぬけて、黄海へ向けてのろのろと北航した。
ネボガトフの旗艦「ニコライー世」と、第二艦隊が“鏝(こて)”とニックネームをつけた海防艦三隻とが、第三戦艦部隊としてフェリケルザム艦隊につづいて単縦陣をつくり、「モノマーフ」はエンクィスト指揮の巡洋艦群といっしょだった。
このものすごく巨大な大艦隊が、日本がわの哨戒艦に発見されることもなく、やっかいな事故ひとつなく、琉球列島わきを無事通過できたとは、なんという驚きであろうか。
五月十九日、英商船「オールダミア」が艦隊と出合い、禁制貨物をもっていることを発見された。
提督はこれを拿捕(だほ)しウラジヴォストークヘ護送すべし、と命ずる一方、その船長と英人乗組員四人を病院船「アリヨール」へうつして保護させた。「アリヨール」はこまって、「閣下がよこされた五人の健康なイギリス人をいかに処遇すべきか」ときいたが、提督は、「港につくまで健康のまま保護すべし」と信号をかえした。
二十一日には、二隻の仮装巡洋艦 「タバーニ」「テレーク」が、日本列島の東岸へ派遣された。
さもバルチック艦隊が後続しているような印象をあたえるための陽動作戦である。
二十三日、最後の給炭をした。
二十五日、上海から一四〇キロの海上で、ロジェストヴェンスキーは、もはや用のない給炭船二隻をふくむ六隻の雑役船を、上海へかえした。
二十五日の朝までは、艦隊では誰一人として、日本海へ入る三つの入口のどれを提督がとるつもりなのか、知らなかった。ネボガトフですら例外ではなかった。雑役船を上海へおくったあと、ロジェストヴェンスキーは、針路を北東七〇度にかえ、対馬海峡を通ることを明白にした。
日本と朝鮮をへだてる海域は、対馬で東西二つにわかれる。〔東が対馬海峡、西が朝鮮海峡である〕
二十五日の夜は気温がさがった。気温の変化は、雨と、それに幸運にも震を発生させた。
これで対馬海峡を発見されずに通過できるかもしれない。
二十六日の朝、太陽は時々雲間からもれた。
正午ちかく、「スウォーロフ」は、全艦艇に速力を五ノット〔時速約九・三キロにおとせと信号して艦隊をおどろかせ、ついで、艦隊機動訓練を命じた。夜の敵魚雷攻撃の危険をすくなくするための計算であった。
五月二十七日正午ごろに艦隊が海峡の最狭部にさしかかるようにするためには、四時間ちかくの時間があまるから、この時間を利用しようというわけである。
これがおそらく、第二、第三艦隊が合同して艦隊機動をする、最初で最後のチャンスであろう。
二十六日午後、調度類や木製艤装類は海へすて、甲板をホースで洗い、聖水をまいた。
そしてぬれたハンモック、石炭袋、防水布などを手すりにまきつけた。
弾丸の破片を防護するためである。
5 いまだ日本艦隊と遭遇せず top
その夕刻、霞はこくなって霧になり、下弦の月は霧でぼかされ、視界は数百メートルにおちた。
夜半にめざめたセメノフ中佐は、艦内を巡視した。
無人の士官室を一つのぞいたあと、艦橋へのぼると、そこに艦長がいた。
ワッサリ・イグナチウスというひどく気のいいこの艦長は、ねむけはなく、上きげんだった。
「なにをしているんだ。散歩か?」イグナチウスがきいた。
「ちょっと見まわっているだけです。眠っていらっしゃるんですか?」
セメノフは、籐椅子でまどろんでいる長官のほうへ、ちらとアゴをしゃくった。
「そうだ。眠りなさいともうしあげたんだよ。今夜はもう無事にすぎたと考えていい。 まだ発見されていないし、それにあと二時間で夜もあける。 やつらの水雷艇がこのちかくにいるとしても、集結はできまいよ。
第一、こんな天候じゃ、我々を発見するなんて、とんでもないこった。ほら、艦隊のずっとうしろはぜんぜん見えんだろ? たとえ偶然でも、誰かが我々にぶつかるなんて、万に一つもありはせんよ。……
明日もこうだったら、やつらに完全に肩すかしをくわしたことになる。
やつら、ヤキモキして気が狂いそうだろうな!ああ愉快だ!」
大声で笑いかけ、しかし艦長は、あわててハンカチを口にあてた。長官をおこしては大変だからである。
しかし、イグナチウスは、いくつかの点で間違っていた。絶対発見されないだろう、という予想も違っていた。
その夕方、艦隊は航海灯以外は消灯するように命じられていたが、はるか後尾にいた病院船「アリヨール」は、旗艦からはずっとはなれているから、とタカをくくり、この命令を無視していたのである。
しかしイグナチウスは、一つだけ完全に正しかった。
それは、第二太平洋艦隊の到来にそなえて数ヵ月をすごした日本艦隊は、ここ数日、そしていまも、確かにあせりいらだっていたのである。
あらゆる準備、あらゆる努力にもかかわらず、彼らは、まだ敵を発見できないでいた。
しかし彼らの計算によれば、敵はとっくに来ていなければならないのである。
top
**************************************** |