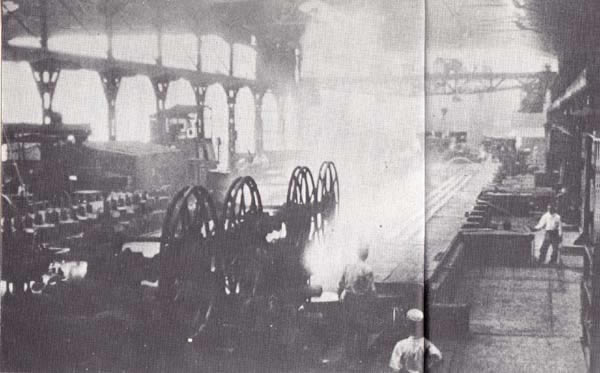|
****************************************
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ないないずくめの銃後(天皇の決断 3)
戦争による日本の食糧不足は、はやくからあらわれていた。
日本では、その人口の約半分が農業に従事していたが、それでも戦前から米の二〇パーセントは輸入しなければならなかった。
1 餓死しないだけの食糧配給 top
戦争がはじまると、集約農業で増産にはげみ、高い収穫率をあげたが、食糧の総供給量は、生存に必要なカロリー摂取量を、わずか六・四パーセント上まわるにすぎなかった。
一九四二年〔昭和十七年〕はじめ、政府当局は、米の供給量がさがったため、米穀配給の一部を小麦、大麦で代用しはじめたし、のちには、サツマイモとジャガイモを代用品としてくわえた。
主要食糧の貯蔵はしだいに減少して、一九四五年〔昭和二十年〕には一日あたりの食糧は一五〇〇カロリーをわるようになった。
餓死しないまでも、これは健康を維持し、仕事をしうる最低必要量の約六五パーセントにしかあたらない。
有名な話だが、神奈川県葉山のある家族が政府の配給食糧だけで暮らしていたが、栄養学の専門家が調査したところ、家族全員がひどい夜盲症にかかっていたという。
一九四四年八月、島田俊雄豊商務相は、日本は“太く短く”生きるか、“細く長く”生きるか、どちらかの政策をえらばねばならない、と述べたが、けっきょく後者の道がとられたのである。
飢えと病気が、日本国民にしのびより、彼らの関心は、ただ食物にだけ集中するようになった。
ある疎開学童は、あたたかい陽光のさすお寺の軒下で、飢えの苦しみからのがれるために、ハミガキ粉をのみこんだし、べつの学童は、ぬすんできたサツマイモを、なまのままかじったりしたことを回想している。
先生たちは、手に食器をもって、農家を次々に回って、子供たちのために、塩やトウフをわけてくれるように頼んだ。
子供たちは、ユリの根を掘ったり、桑の実を食べたり、蛇をつかまえて焼いたり、野草や沢蟹などをあさったりしたが、そのため、慢性的下痢やシラミやカイセンに悩む子供がたくさんでた。
都市の居住者は、イモ、野菜、果物などを手に入れるために、何万人もが農村へ買出しに出かけた。
日曜日には、東京から約九万人が出かけたという。
2 ヤミ値は公定の40倍 top
ヤミ値は、目が飛び出るほど高く、市民はなけなしの持ち物や衣料を、わずかの食糧と交換しなければならなかった。
そして個人が食糧を運ぶことは、法令で禁止されていたけれども、その法令は、終戦までついに励行されなかったのである。
吉田茂・元首相は次のように書いている。
「ヤミ市を利用した経験、またサツマイモやキャベツを求めて、混んだ列車で田舎に買出しにいった経験は、この憂鬱な時代を生きぬいた都市生活の記憶に、いつまでも生々しく残るであろう」
日本銀行の推定によれば、ヤミ値と公定価格をくらべると、次のようになっていた。(一九四五年七月)
| 米 七〇倍、大豆 三〇倍、サツマイモ 二二・五倍、ビール 一六・六七倍、砂糖 二四〇倍、鰹節 三五・六倍、木綿 四〇倍、綿 一〇倍、作用革靴 四四倍、石鹸 二〇〇倍、マッチ 二〇〇倍、靴下 七五倍、木炭 四〇倍、薪 二〇倍、鉄ビン 三〇倍、フライパン 四〇倍、自転車 一六倍。 |
この数字は、あらゆる人の回想や、その当時の記録によって確認されている。
たとえば、ある作家は一九四四年七月十三日の日記に、「コップー杯の食用油が、公定価格では百二銭だったが、ヤミ値では七円した」と書いている。公定価格の約三〇倍である。
平均して大部分の消費物資のヤミ値は、公定価格の四二倍であった。
もっともひどい打撃をうけたのは、空襲で焼けだされた都市の住民である。
彼らは、最低限の生活必需品を手にいれるために、ヤミ市に走らねばならなかったのである。
|

占領下のフイリッピンで、日本軍の監視下に、田植えをするフィリピンの女たち
|
3 まぜもので食いのばす top
そんな状態にもかかわらず、軍がますます多量の米を要求したので、民間の米の配給は、開戦当時にくらべ、平均四割もへらされてしまった。
そのうえ、食糧問題をさらに悪化させたのは、小麦、大麦の不作であった。
それは、洪水と暴風雨による打撃と、肥料や労働力の深刻な不足によるものだった。
一九四五年六月十日の議会での秘密の質疑応答で、柴山陸軍次官は、食糧事情の悪化により、一九四六年の春まで戦争をひきのばすことは不可能であると言明した。
事実、一九四六米穀年度(一九四五年十一月一日から開始)に、繰り越しできるのは、一三万二〇〇〇トンとわずか四日分しかなかったのである。
一九四一年に、一一七万八〇〇〇トンの繰り越しがあったのに比較してみるとよい。
しかも一九四五年の米の収穫は、みじめなもの(一九〇九年以来の最低)で、さらに四月以後、台湾からの米の輸送もできなくなったので、配給量はいよいよ引き下げられていった。
ドングリの実をひいて漂白した粉や海草、それに、時にはまずくて栄養のない物までが、米にまぜあわされた。
また果物、野菜、魚、大豆製品左ども配給制になった。
労働力と肥料の不足で、野菜の生産は八一パーセントにさがった。
輸入に依存していた飼料がなくなったので、食肉の生産量は、開戦時の七〇パーセントにおちた。
4 砂糖、塩も底つく top
砂糖の消費量をしめす数字は、一九四四年以後の、日本の食糧事情悪化の状態をよくしめしている。
戦前の日本の砂糖消費量は、一人あたり年平均一三・六キロであったが、終戦の年にはわずか一・三六キロになった。
日本政府は、全国で四五八三トンの砂糖をもっているにすぎず、配給もできるどころではなかった。
(一九四二年には、一六万七〇〇〇トンの在庫をもっていた)
塩は、おそらくもっと危険な状態にあったといえよう。
塩は食事に欠かせぬばかりでなく、化学工業、精油、爆薬製造などにも必要である。
その塩の生産量が、一九四五年には、日本の最低必要量六〇万トンの三分の一におちていた。
一九四五年五月下旬に行われた戦争能力に関する会議で、大蔵省の代表は次のように報告している。
「今の状態が改善されなければ、家畜用の塩配給は、秋には打ちきらざるをえません。
秋には本州での塩の生産は殆ど不可能となり、来年になると人間の消費用の塩さえ満足にあるかどうか疑問です。 家畜にふりかかった運命が、人間にはふりかからないという保証はなにもありません」 |
政府は「欲しがりません、勝つまでは」という標語をかかげたが、日本の経済担当者は、もし連合軍の封鎖がさらに強化され、陸上輸送線が破壊され、収穫のすまない田畑が空から攻撃されるようになると、飢饉が、特に人口密集地域に発生するおそれがあると、ひそかに警告した。
5 栄養失調で病人が続出 top
そこで、工業原料がノドから手がでるほど必要ではあったが、外務省は、塩、雑穀、大豆を輸入するために、できるかぎりの船舶を確保するよう努力し続けた。
それは、輸入の優先権が、それまでは鉄鉱石、石炭、銑鉄、その他の非鉄金属にあったのを、放棄することを意味していた。
船舶は、最後の一袋の米まで本土に運ぶために、軍のもつ貴重な燃料を使うことをゆるされた。
そんな努力をしても、一九四五年の米の輸入量は、平年の一一パーセントにへり、まもなく、全くとだえてしまった。 大豆の輸入は、一九四一年当時にくらべて三一パーセントほど減少した。
栄養不良や疲労、体重の減少によって、特に工場労働者は肺結核にかかった。
また神奈川県鶴見のある工場では、労働者の三〇パーセントが脚気になっていることがわかった。
しかも医療関係者は、空襲が激化してからは、ますます少なくなり、東京の例でいえば、医者の数は、一九四五年八月までに、八九〇〇人から二二〇〇人に、看護婦は二万六二〇〇人から三六〇〇人に減ってしまった。
医療施設も、医者や看護婦の技術も、みじめで幼稚なものになった。
血清、薬品、人工血液は極度に不足し、手術衣は、十分な洗濯や殺菌もせずに、何回も繰返し使用されるありさまだった。
6 地震と寒波の追い打ち top
窮乏はこれだけではなかった。
一九四四年十二月、激震が東海地方を襲い、東海道線の天竜川にかかった長い鉄橋をこわし、また名古屋市とその南東郊外に被害を与えた。
巨大な三菱と愛知の飛行機工場は、一ヵ月間も操業不能におちいり、その後も地震の影響から完全に立ちなおることができなかった。
また天竜川の鉄橋の復旧は、開通までに数週間かかった。
そのうえ、一九四四年から四五年にかけての冬に、異常寒波が日本各地を襲った。
各都市の水道管が、夜ばかりでなく日中にも凍った。
ある人は日記のなかで「三〇年間、東京に住んでいたが、屋内の水道が凍ったのは、初めてである」と書いている。
東京その他の主要都市では、電車が雪と水のため何回も運転中止になった。
このようなきびしい寒さのなかで、あいかわらず市民は、薪や燃料を手にいれることが困難だった。
もしある家庭が、一冬に、一俵の木炭を公定価格で入手できたとすれば、それは幸運というべきだった。
骨も凍る寒さに耐えるには厚着しかないが、衣料もまた不足していた。
一般市民が入手できる綿布、毛織物の量は、一九三七年から四五年になると、八パーセントに減少した。
民間の衣料の最低必要量に対して戦時中の生産量は、綿布は二四パーセント、毛織物は一九パーセント、絹布は三〇パーセントにすぎなかった。
石鹸も戦前の四パーセントに紙は八パーセントにさがってしまった。
7 大騒ぎして松根油わずか10トン top
また、原油がとりわけ不足していた。一九四二年の第一・四半期には、一四万八〇〇〇キロリットルの貯蔵があったが、一九四四年末には五万八八〇〇キロリットツに、一九四五年四月には二万四〇〇〇キロリットルにおちた。
そのため、テレビン油、魚油、植物油、木炭などが燃料として使用され、アルコールが航空用ガソリンの代用に使われた。
化学者たちは、石油の代用品をつくるために、はかない努力を続けだし、老人や子供や婦人は、松の木の根を掘りおこして、油をとろうとした。
そして、一年間の努力でえられたものは、わずか一〇トンの松根油(テレビン油)であった。
またサツマイモからアルコールをつくる計画が一九四五年の初めに、タールを燃料とする研究は六月に始められた。
化学肥料工場は、カリウムの代用品を、非常に能率の悪い原始的な方法でつくった。
竹が金属容顔の代用品になり、ミョウバン石がボーキサイトの代用品として試用されたが、これはある程度成功した。
プラスチックは、木材やガラスで代用された。
米英両国の空軍では、透明なプラスチックが、飛行機の各部品に使われていたが、日本では、強化されていない普通のガラスが、軍用機の操縦度や窓、銃座にひろく使われていた。
飛行機工場は、金属のかわりにほとんど一〇〇パーセント木材を使用することを計画し、操繊度にあるノブやハンドルや、普通プラスチックで造られている小さな操縦器具なども、木材で造られた。
8 貧弱だった鉄道 top
戦前、目本の鉄道敷設距離数は、かなり少なく、その交通量も比較的かぎられたものだった。
わずか二本の主要幹線が本州の屈曲した海岸線にそって走っており、本州を横断する線は少なく、またあまり重要でもなかった。
九州と北海道では交通網は、港、渡船場やトンネルなどの多い線からなりたっていた。
トンネルは二二八五、渡船場は四八、橋梁は四百二八八二あった。
こうした状態から、貨物輸送は大部分は短距離のいろいろな方法、ついで沿岸や海上輸送であった。
従って鉄道は、第二次大戦中、長距離の輸送をした貨物船にかわって、不慣れな重荷を背おわされたのである。
一方、旅客輸送力は、絶対的にさがったわけではないが、非能率さをハッキリとしめした。
長距離の切符を入手することは、個人にとって極めて困難だった。(とんでもないほどのプレミアムがついていた)
それでいて一九四四年の春や夏頃、宇都宮や軽井沢や、それに驚くなかれ東海道線にも、カラの客車が走っていた、と当時の旅行者が語っている。
そのうえ、都市をむすぶ高速道路も十分でなく、また道路網も幼稚で、舗装もしていなかった。
一九四四年末には、燃料不足のため貨物自動車は四〇パーセントしか動かず、しかもその多くは木炭車だった。
つまり日本の運輸は、牛車や馬車などに、大きく依存していたわけである。
しかし馬は、陸軍でも極めて不足していた。本土の第十二方面軍は、一二万頭の馬が必要であるとの計画をたてたが、入手できたのは、わずか二七〇〇頭であった。
一九四五年七月のはじめ米軍は、日本の軍隊の移動を阻止するために、南九州の鉄道施設今橋に対して、戦術的空襲を開始した。
同じ月に、米空母機は、本州と北海道をむすぶ青函連絡船一二隻のうち一〇隻を破壊し、二隻に損害を与えた。
津軽海峡をとおって北海道産の石炭の三〇〜四〇パーセントが本土へ送られていたのだが、この攻撃で、八二パーセントも減少し、九ヵ月というもの回復する見込みはなかった。
日本本土の鉄道に対する戦略爆撃は、ちょうど終戦の八月十五日にはじまる予定だった。
|

生産をいそぐ日本軍爆撃機
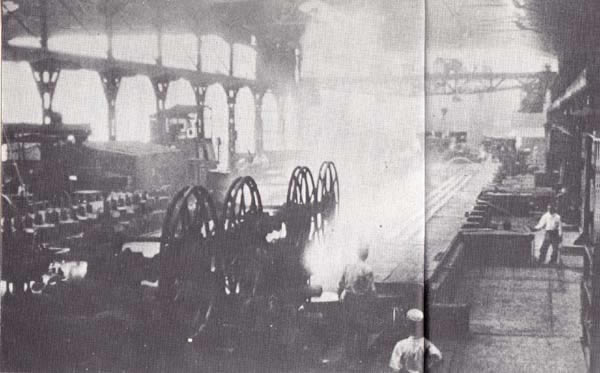
すべての重工業は兵器生産に転換した:稼動中の鋼鉄圧延工場
|
9 海運力もガタ落ち top
日本の海運力について、企両院は一九四一年に、もし戦争が三年続けば、日本は五二五万トンの船舶を必要とするだろうと推定していた。
ところが、実際には、四五年三月に、日本は二二六万六〇〇〇トンの船舶をもっていたが、このうち、動くのはわずか一五六万トンにすぎなかった。
八月なかばには、運行できる船舶は五五万七〇〇〇トンにへり、沈没に対する建造の割合は一七パーセントにすぎず、日本はいまや開戦時にもっていた船舶の一二パーセントを保有するにすぎなかった。
しかも、残ったのは小さな、速力の遅い、非能率な船ばかりである。
船舶不足の重要な影響の一つは、鉄鋼生産に必要な銑鉄、コークスなどの原料が、一九四四年中頃に、三分の一に減少したことである。
主な港湾の活動も、一九四五年夏には、ほとんど停止してしまった。
一九四二年、船舶によって取り扱われた貨物のトン数の月平均を一〇〇とすれば、四五年の月平均は次のとおりである。
東 京 一・二(五月二十七日以後)
横 浜 四・三(五月二十三日以後)
名古屋 〇・九(四月二十七日以後)
大 阪 九・五
神 戸 一一・二 |
東支那海と、太平洋に面した港は、全く息の根がとまり、一九四五年七月には、本州の海岸の沖合いで、かなりの数の船が沈められた。
本州東北部六隻、日本海方面一五隻、九州周辺一一隻、下関海峡一二隻、瀬戸内海二〇隻、朝鮮沖二〇隻、北海道沖六隻であった。
船舶喪失の打撃の一つとして、日本は食生活の柱ともいうべき漁業を、大幅に縮小しなければならなかった。
一九四五年の全漁獲高は、戦前の半分にへり、魚肉製品は二二パーセントにさがった。
10 天皇、アルミ 回収に御警告 top
日本の軍需品の生産高は、最高のときでも米国の一〇パーセント以上には、決してならなかったが、東京大学のある教授は
「軍需産業に必要な殆どすべての原料を輸入に頼っていた日本の戦時経済は、孤立化によって死の打撃をうけた」
と語っている。
また、ある日本の経済専門家は、近衛公の個人秘書に
「日本の産業全体は、資源不足のため一九四五年に破滅してしまうだろう」
と密かに語っている。
一九四五年の初めに、飛行機の生産が、予定のわずか三分の一におちたので、政府当局の関心は、にわかにアルミニウムの不足にむけられた。
船舶の減少は、アルミの原料ボーキサイトの供給に、甚大な影響を与えたのである。
一九四四年には、船積みされたボーキサイトの七〇パーセントが、海中に消えてしまった。
しかも、せっかくアルミになったものも、その五五パーセントだけが飛行機生産にむけられたにすぎないことがわかった。
そこで、国内の非軍事用のすべてのアルミをただちに回収する運動が開始されたのだが、天皇は、その運動に困惑され、家庭用品までは没収しないようにと、注意されたそうである。
ところで、驚いたことには、憲兵隊が、アルミ回収運動に関係したのである。
ある憲兵は、ヤミ市のブローカーと取引きせざるをえなかったし、
「我々は、クズ広いのようなものだった」
と述べているほどだが、それほどアルミの必要性は痛切だったのである。
一九四五年には、アルミ生産高は、四四年の最高時のわずか九パーセントでしかなかった。
回収されたアルミは、航空機産業に供給されたアルミの八〇パーセントをしめたが、質は極度に悪くなった。
ボーキサイトの輸入は、一九四五年一月以後はバッタリとだえてしまった。
三週間にわたるアルミ回収に、憲兵がかなりの成功をおさめたので、彼らはクズ鉄回収にも動員された。
日本の鉄鋼生産は、米国の三分の一にしか達しなかったが、一九四五年には、前年のさらに半分におちてしまった。
アルミ回収運動から知識をえた憲兵は、ヤミブローカーを“顧問”として利用した。
そして約一ヵ月にわたる活動ののち、憲兵は、一〇個戦闘師団を支えるにたるクズ鉄を、民間から回収することができた。
11 各省上層に悲観論 top
しかし、一九四三年に、大東亜省がたてた基本的な予測が、今や現実となってきた。 それは
「もし海外からの原料の供給が遮断される時がくれば、我々は、この近代戦の継続がほとんど不可能になると予測せざるをえない」
というのだった。
このように、日本の原料物資の弱点を知る地位にある日本人は、戦争の前途について、増々悲観的になっていた。
軍需省の幹部たちは、勝ち目はないということから、さらに発展して、条件つき降伏を考えるようになっていた。
これらの気配を察知した憲兵隊は、軍需省の敗北主義者に、監視の目を光らせはじめた。
思想警察(特高)も、軍需省の幹部が、怠惰と士気低下に毒されていることを探知した。
ある情報将校は次のように述べている。
「この国家非常時にあたり、戦時生産の大本山(軍需省)は、著しく勝利への意志を欠いている。
さもなくとも、彼らはすでに戦争を放棄しているのだ」
軍需省の課長をつとめていた海軍大佐は、一九四五年の新年の挨拶で、部下に
「今年は日本の敗北の年だから、いつでも逃げだせるようにしておけ」
としゃべったという。
陸軍は、この将校になにも手出しができなかったが、海軍省に連絡して、処罰をもとめた。
一九四五年二月に、すでに退役していた東条は、
「食糧事情が厳しくなってから国民の戦闘精神が低下し、インテリが敗北感を抱き始めたことは、極めて重大である」
と、密かに語った。
そして六月に、彼は陸軍省にでかけて阿南陸相に会い、米内海相と東郷外相はいつでも降伏に同意しそうな印象を与えているが、陸軍はしっかりしなければならない、と激励した。
同盟通信社の加藤満寿男記者は、
「日本の抵抗が成功することは、もはや不可能であり、日本は国民性からか、または、止める方法がわからないためかで、戦争を続けている」
と確信した。
彼は、一九四五年の夏までに、戦争に敗けるだろうと判断した。
そのことは、国民はなにも知らなかったが、指導者たちは、意見の衝突や、優柔不断さにあがきながらも、よく知っていたのである。
12 国民の反抗 top
おどかされたり、無知のままにされたりしていたが、国民は、すべてがうまくいっていないことを“肌で感じて”いた。
しかし最後まで、“神州不滅”という神話の世界に、絶望的に、そして、余儀なくしがみついていたのである。
だが、彼らの軍部に対する不満は、敵機が本土上空を自由に飛び回るようになってくると、激しくなってきた。
一九四五年三月、東京が大空襲をうけたあと、疲れきり、気おちした避難民は、二台の自動車で厚かましくも視察にきた陸軍の将校たちに、罵声をあびせて迫いかえしてしまった。
一九四五年の春、連合軍の空襲がしだいに激しくなってからの国民の士気についての、最高戦争指導会議がおこなった詳細な調査がある。
この極めて率直な調査で、軍と民間の分析家は、国民の士気の低下、ヤミ市、汚職、指導者への増大する不信、軍および政府への批判などの、動かしがたい事実を指摘している。
それによると、国民は、もともと愛国的ではあったが、いまや利己主義、敢闘精神の欠如、失望、あきらめ、不安、平和への渇望、そしてさらには、革命的な傾向さえ、しめしていたという。
御前会議で、原嘉道枢密院議長は、
「国民の士気は明白に低下しており、祖先の名誉ある伝統をまもろうという意志は、“ある情況の下”でぐらついている」と発言している。
同じく重要なことだが、七月二十五日の本土全軍の参謀副長の会議で、陸軍参謀本部の一員(大佐)が、
「インテリは、反戦、反軍、反政府的である。これは戦争の末期的症状を反映するものである」
と率直に述べていたのである。
top
**************************************** |