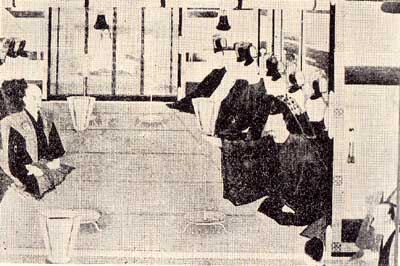|
****************************************
Index 岩倉・大久保 木戸 板垣 大隈・松方 伊藤 陸奥 星 川上・山本 山県 桂 西園寺・原
1 政界登場の仕方
岩倉具視は文政八年(一八二五)に生れ、大久保利通は、その五歳年下、天保元年(一八三〇)の生れである。
具視は前権中納言堀河康親(やすちか)の子で、岩倉具慶(ともやす)の養子となった。
彼は、朝廷の制度改革、公卿の気風一新の自説をとりあげてもらうため、関白鷹司政通(たかつかさ・まさみち)の和歌の弟子に志願した。
その効あって、安政元年(一八五四)侍従となった。
この地位を具視と競ってやぶれた滋野井公寿の父実存は
「嗚呼今日は、執柄家にイン縁(いんねん=手づる)するに非らざれば立身栄達を計ること能はざるなり」(『岩倉公実記』)となげいた。
同じような話が、大久保利通についても伝えられている。
大久保家は薩州下級藩士の家、父の次右衛門は、御家騒動の高崎崩れ(お由羅(ゆら)騒動)に関係して島流しの処罰をうけた。
利通は、岩下方平・伊地知正治(いじち・まさはる)・有馬新七・海江田信義らと精忠組と名づける尊攘派を結成したが、彼の行き方は、同志の西郷隆盛や有馬新七とちがい、藩権力と正面から抗争するという危険な道をとらなかった。
藩主の父で、その実権をにぎる島津久光に接近する機会を求め、久光の囲碁の相手の吉祥院のもとに通って、碁の稽古をはじめ、ついに久光の知遇をえて出世の緒口をつかんだ。
既成の秩序に歯向かわず、それを利用し、具視の場合は関白、利通の場合は藩主の父に接近し、その信任をえ、それによって自己の志の実現をはかるいき方は、似かよっていた。それだけに両者ともに、漸進的な改革派であった。
具視の改革意見は、安政五年(一八五八)孝明天皇に内奏した「神州万歳策」に明らかである。
結論は、幕府が要請していた日米通商条約の勅許に反対し、攘夷の武備充実に全力をつくせというにあるが、その特色は、幕府排除の動きに反対し、公武一和を主張した点にあり、みだりに王政復古を夢み、あるいは雄藩大名の力に依頼することに反対の意を表明している。
利通も、久光を通しての上からの改革という線を崩さず、先輩で親友の西郷が、久光とぶっかり、主君の措置に不信と不満の言をもらしていたのとちがって、同志の過激派の抑制につとめる「忠臣」ぶりを発抑し、その功で異例の抜擢をうけ、文久元年(一八六一)、小納戸(こなんど=調度係)役の重職についた。
両人とも、このままでいけば、危ない目にあわずにすんだかもしれないが、同時に維新変革の波にとりのこされたにちがいない。
ところが時勢の激流は、彼らを危ない橋を渡らさずにはおかなかった。 |

岩倉具視

大久保利通
|
2 公武合体をかかげて
大老井伊直弼は、尊攘派および将軍継嗣に一橋慶喜を擁立する幕政改革派にたいしていっせいに弾圧を強行した。
この安政大獄の嵐は、朝廷内にも吹き荒れた。
安政六年(一八五九)幕府の強請によって、対幕強硬派の前関白鷹司政通・左大臣近衛忠照(このえ・ただひろ)・右大臣鷹司輔煕(すけひろ)前内大臣三条実万(さねつむ)は、官を辞し剃髪引退することとなった。
具視の出世の手引をしてくれた政通が処罰されたからには、彼の運命にも危険はあった。
しかしたくみにこの危機をのりきった。
彼は持説の公武合体論を看板に、政通らの処罰の緩和を求める孝明天皇の信任と依頼をうけるとともに、所司代(しょしだい=御所の幕府側責任者)酒井忠義(ただよし)に接近しその信頼をえた。
万延元年(一八六〇)、井伊大老は、桜田門外で水戸浪士の襲撃をうけ殺された。
老中安藤信睦(のぶまさ)・久世広周(くぜ・ひろちか)を中心とする幕閣は、反幕運動の鋒先をそらすため、公武合体政策をとり、皇妹和宮(かずのみや)と将軍家茂(いえもち)の結婚を実現しようとはかった。
天皇の反対と幕閣の熱望、その間の斡旋にあたったのが幕府側では所司代酒井忠義、朝廷側では具視と千種有文(ちぐさ・ありぶみ)であった。
具視は、和宮の婚儀を天皇にすすめた。
彼の説く理由は、幕府には内憂外患を解決する力がないから、朝廷に政権を回復する計画を立てるべきだが、それには天下の大乱をひきおこす急進策ではいけない、皇妹の婚儀を許す条件として、幕府に条約破棄を誓約させ、幕政を監督する実を獲得すべきであるというのであった。
攘夷は熱望するが、倒幕には反対だという天皇の意向にまったく一致した、巧妙な説得であった。
かくて文久元年(一八六一)、和宮が江戸におもむくにあたって、中山忠能(ただやす)ら公卿の一員に加わって供奉した。
このころになると具視は、朝廷における対幕折衝の実力者になっていた。
当時彼の綽名(あだな)は、守宮(やもり)であった。
すばしこくて、出没を予測できぬ策謀ぶりを評したのであろうが、陰険冷血の感がこい。
文久二年(一八六二)三月、一〇〇〇人の大兵をひきいて、島津久光は上京の途についた。公武合体を実現し、これによって中央政局での薩藩の地位を確立するのが、久光のねらいであった。
具視は、久光に公武合体の実現と、折から京都に集まって挙兵を策していた尊攘激派志士の鎮圧とを期待し、議奏中山忠能・同正親町(おおぎまち)三条実愛(さねなる)らとともに、斡旋にはたらき、久光に賜わるべき勅旨案を相談した。
彼は公然朝議に関係する地位になかったが、この枢機に加わる隠然たる実力をもっていた。
すでに薩藩側の対朝廷折衝を担当した堀次郎・大久保利通らと連絡をもっていた。
その後利通との十数年にわたる密接な関係がはじまった。
具視らと利通らが画策した筋書きに従って、久光は四月入京し、安政の大獄で処罰をうけた公卿の赦免と幕閣人事の更迭を建言し、これにたいし不穏の企てある浪人を鎮静するようにとの勅諚が下った。
ときに薩摩の有馬新七、久留米の真木和泉(保臣)、筑前の平野二郎(国臣)、豊後の小河一敏、長州の久坂玄瑞らの激派は、久光の入京を機会に尊王擅夷の兵をあげようともくろんでいた。
大島に流されていた西郷は、許されて久光の一行に加わることを命ぜられると、さっそく無断で京都に先行し、志士の中にとびこんだ。
彼は「私死地に入らず候では、死地の兵を救ふ事出来申すまじく」というつもりで、志士の蜂起を鎮めるために、志士の仲間に入った。
しかし久光の眼には、彼が暴徒を煽動していると映じた。
そこで久光は、西郷を無断上京の罪で、徳之島に流した。西郷は罪のないのに「国賊」あつかいされたのを憤り、「馬鹿らしき忠義立」てはやめたと、はげしい不満を書簡に吐露した。
西郷は、同志が久光の弾圧をうけるにしのびなかった。
しかし利通は、冷静に、忠実に、主人の命に服し、迷いなく忠義立てをつづけた。
久光は激徒の鎮圧にのり出し、家臣をして、有馬新七ら薩藩激派八人を「上意」の名で不意打ちに斬らせた。
これが寺田屋騒動である。
利通は、同志と藩府との和協をのぞみ、その努力もした。
しかしそれができぬと見きわめると、躊躇なく久光の措置を支持した。
骨肉同様の人々を、事の真意を問わず罪におとしいれるとは何事かと憤りなげいた西郷とは対照的であった。
島津久光は勅使大原重徳(おおはら・しげとみ)を擁して、江戸におもむき、幕制改革の勅旨を伝え、一橋慶喜と松平慶永が中心とする幕閣を実現させた。
利通はこれに随行し、江戸政局の晴れの舞台で活動した。
ときに具視も、六人の競望者をおしのけて、左近衛権中将に昇任した。
両人ともに得意の時節であった。
3 波瀾の政局
島津久光が江戸におもむいている間に、京都では薩州藩の競争相手である長州藩と土州藩の尊攘派が、一層強硬な勅旨を幕府に下す策謀をめぐらした。
彼らは、佐幕派公卿の排撃運動をおこし、和宮の婚儀に尽力した内大臣久我建通・左近衛権少将千種有文・中務大輔富小路敬直と具視、および少将掌侍今城重子・右衛門掌侍堀河紀子を「四奸二嬢」として、これに「天誅」を加うべしと脅嚇攻撃した。
紀子は具視の実妹である。
そこで朝廷では、具視・有文・敬直らに内諭して、近習の役を辞退させた。
しかし尊攘派は追求の鉾先をゆるめず、一三人の少壮公卿は連署して、幕府に「阿諛(あゆ=こびる)」した罪をもって処罰されたいと建言した。
この一三人の中には、のちに維新政府に具視とならんで柱石となった右近衛権少将三条実美も加わっていた。
こうした圧力によって、朝議はついに具視ら三名に蟄居・辞官・剃髪を命じ、建通・重子・紀子も同様の処罰をうけた。
しかも尊攘派の攻撃はやまず、天皇毒殺を意図したとして、二日以内に洛中を退去せねば、首を四条河原にさらすであろうとおどした。
そこで具視は知行地である洛北岩倉村の民家に身をひそめることとなった。 |

岩倉村・岩倉具視隠栖の庭
|
岩倉らが屏息(へいそく=ちじこまる)したあとの朝廷は、尊攘派志士と手をむすんだ三条実美・姉小路公知らの天下となった。
文久二年一〇月、三条と姉小路は勅使となり、土州藩主山内豊範をしたがえて幕府にのぞみ、攘夷実行を督促する勅書を伝達した。
浪人志士は次から次と強硬策かうち出し、これが朝議で決定され叡慮となった。
彼らに反対する者は、誰でも佐幕派の「奸物」と非難され、「天誅」のおどしの対象とされた。
翌年三月将軍は上京参内するを余儀なくされた。
天皇は関白以下の公卿、将軍以下の大名をしたがえて賀茂社に行幸、攘夷を祈願した。
将軍は攘夷実行の期日を奏上するのやむなきに至り、五月一〇日と定めた。
尊攘派は、この攘夷実行を機会に、王政復古を実現することを夢みた。
しかし孝明天皇は、強い攘夷主義者であったが、倒幕は好まず、まして浪人・志士勢力をもって「下より出る叡慮」という事態をひきおこすことに不満をもっていた。
この天皇の意向をもとに、中川宮(朝彦親王)らの公武合体派公卿と会津藩・薩州藩とが提携し、文久三年(一八六三)八月十八日の政変を起した。
クーデターは美事に成功した。これまで京都政局を左右していた長州藩は、三条実美ら尊攘派公卿を擁して、京都を退かねばならなくなった。
朝廷側では、中川宮・前関白近衛忠熈、武家側では島津久光、会津藩主で京都守護職の松平容保、将軍後見職一橋慶喜らが京都政局の中心となった。
かねて具視が主張してきた公武合体策に賛同する勢力の天下がやってきた。
しかし具視らの勅勘は解けず閉居生活が続いた。
4 逆境に立ちむかう具視
具視がふたたび政治活動をはじめたのは、慶応元年(一八六五)になってからである。
彼は薩人井上石見が来訪したので、「叢裡鳴蟲」と題する意見書を示し、小松帯刀と利通の見解を求めた。
この意見は公武一和説であるが、将軍は常時京都にあり、国是は、朝廷と幕府が施政の大綱を起案し、諸藩主にこれを諮問し、その答申をまって宸裁(しんさい=天子の考え)をもって天下に布告するというのだから、公武合体の形式をとった漸進的王政復古策だといえよう。
ついで「続叢裡鳴蟲」を草して、これまた利通に示した。
これは、島津久光の偉材であることをたたえ、征長問題について、薩藩が幕府と長州の間に立って斡旋・調停すべきだとうつたえたものである。
さらに九月には、「全国合同策」を中御門経之に渡し、叡覧に供してほしいと頼んだ。
これは、列国が合力して我にせまる状勢にかんがみ、全国合同をはからねばならぬとし、これには叡慮終始一貫せず、聖断前後齟齬しか弊か改め、朝廷が幕府・薩長両藩および志士に御沙汰書を下し、上下が一新協和することが必要だと論じたものである。
具視はあせっていた。
急迫した内外状勢を座視するに忍びぬ衷情からかも知れない、あるいはかつて大原勅使東下の際に交渉のあった薩州藩の中央政界での復帰に、自己の政界復帰を賭けていたのかも知れない。
しかしこれらの意見書が、希望する大久保・小松や天皇の眼にふれるより前に、意外な不幸の結果をもたらしてしまった。
というのは、具視ら和宮降嫁に関係し処罰された四人の公卿を宥免(ゆうめん=赦免)する問題が朝廷に起ったが、具視が薩州藩士の出入りを許しているという理由から反対され、実現を見なかったのである。
反対論者の中心は中川宮であり、「岩倉は中々六箇敷(むつかしき)者にて必ず天下を引くり返す程の事も可致(いたしかねない)」と疑惑の眼をもって見ていた(『岩倉公実記』)。
しかし具視は、落胆もしないし、謹慎することもしない。
親友六条有容に書を送り、公卿はたかいに猜疑を去り嫉妬の念を棄てて同心協力すべきだと堂々論じたものであるが、書中、近来公卿で時局につき建白し、その書の朝廷に達せぬうちにすでに世間に流布するものあり、その多くは建白者の本人が流している、それは愛君憂国の至誠より出るか、己の才名を売り己の智力を誇るための行為か、前者であることはほとんど稀だとのべている。
一体彼の場合は、どちらなのであろうか。
前記した「全国合同策」は、中御門経之に託して叡覧に供せんと願ったものであるが、他方でこの謄本は井上石見の手によって島津久光に提出され、この実現の報をえて具視は喜んだと『岩倉公実記』は記している。
自分の場合だけは例外だというのだろうが、第三者から見れば、具視いうところの己の才名を売りこむ行為だと考えられても仕方のないことではないか。
しかし具視は、めあての薩藩の支持がえられなかった。
彼は井上石見に、薩藩への依頼の熱意を語り、もし自分が貴藩に到底容れられぬというのであれば、腹蔵なくありのまま知らせてくれとのべ、その模様によっては禅門に帰するか、風月を楽しむかの覚悟を固めるであろうと衷情を披瀝している。
これは具視だけの嘆きではなかった。
数年前の朝廷と幕府との関係が一変しようとしていた。
幕府の権威は、第二回征長の役での幕軍のみじめな敗北で、一気に失われた。
幕府の権威の失墜は、公武合体により朝威の強化をはかってきた朝廷の権威が同時に失われる危険をふくんでいた。
幕府に代わって依頼すべき実権あるものが必要であった。
兵力をもつ雄藩、兵力を動かす実権をもつ雄藩指導者の力に頼ることによってのみ、朝廷・公卿の権威の維持・強化、王政復古の実現を企てることができた。
それならば、雄藩指導者の側は、どう考えていたのか。
5 権力奪取の謀略
当時利通は京都にあり、西郷とともに大活躍をしていた。
彼らはすでに単純な尊王攘夷論者ではなかった。
利通は第二回征長の役に反対であった。
征長を行ない内乱となれば、清国の轍をふむであろう。
独立を達成するには攘夷では駄目で、開国による富国強兵が必要だとはっきり自覚していた。
慶応二年(一八六六)四月、利通は薩藩の出兵拒絶建白書を書き、これを留守居木場伝内の名で幕府に提出したが、老中は、その書面が藩主の名でなければ受理できぬと拒んだ。
そこで利通は家老岩下方平と相談し、藩主忠義の署名に改めて提出し直した。
老中は、藩主のいる鹿児島と往復するには数十日を要するはずであるのに、このように速かに再提出したのは、在京藩臣の専断に外ならぬとなじった。
これにたいし岩下は、重役の意見はすなわち主人の意見だと突っぱった。
このエピソードが物語るように、利通や西郷や小松や岩下ら指導層は、すでに藩政の実権をにぎっていた。
必ずしも藩主の決裁を一々仰ぐ必要はない。
いな、公武合体論の島津久光の意向を無視して、倒幕の方向に藩の進路を決め、藩主の名を使っていた。
利通は、もはや三、四年前までのような、久光に忠実な家来ではなかった。それだけではない。
利通は、幕府の征長の奏請が勅許されても、「非義の勅命」は勅命でないのだから、従う必要はないとのべている。
尊王絶対ではない。
勅命は彼らが正義と考える価値を体現する故に尊重されるのだと考えるのである。
この考えをもう一歩すすめれば、天皇の権威は、彼らの政治目的に役立つが故に、尊敬に値することになるのである。
岩倉も、大久保同様、従来の限界をふみこえていた。
慶応二年(一八六六)八月、彼の背後での画策にもとづいて、中御門経之・大原重徳ら二二人の公卿が列参し、諸藩召集のこと、具視らの赦免のこと、征長解兵のこと、朝政改革のことを建言した。
朝政改革の要求には、征長勅許の責任を問い、関白二条斉敬と中川宮の辞任を要求することが含まれていた。
この結果、両人は一度は辞表を提出したが、孝明天皇はこれを許さず、かえって一〇月には、列参関係者の「徒党建言」にたいし処罰をおこなった。
かくて具視ら一派の画策は、天皇によって阻まれた。
このとき、一二月二五日天皇は、突然天然痘で亡くなられた。
当時薩長志士と密接な連絡のあった英国公使館員アーネスト・サトウは、数年後に、裏面の消息に通ずる一日本人から毒殺だと確言するのを聞いたと記した(『一外交官の見た明治維新』)。
毒殺説は、天皇の死と同時に宮中内部に流れていたことは、明治天皇の祖父にあたる中山忠能の日記に載せられている宮中勤仕の老女浜浦の書簡にも記されている。
誰が下手人か、疑惑の眼は、具視とその周辺に向けられていた。 |

孝明天皇
|
毒殺か病死か、事実をつきとめる的確な史料は不足している。
しかし毒殺説が宮中内部に流れたことが物語るように、天皇の死がもたらす政治的意味は大きかった。
没年三六歳、まだ壮年の天皇が、もしこの後数年生き永らえたとしたら、後述する具視の活動も、倒幕の「密勅」も円滑には実現されなかったであろう。
天皇の死から最大の利益をえたものが、彼であったことは事実である。
具視は、文久二年の排斥運動をうけたときも、天皇毒殺を計画した罪が非難され、その雪寃(せつえん=無実にする)のため苦心した。
その彼がまたこの噂の主となったのである。
6 専制政治家への成長
毛利家の歴史編纂にあたった中原邦平は、往年の志士と親交のあった人であるが、具視を評して「時と場合に拠ると、二枚の舌を使ひ兼ねまじき御方」とのべた(『坂本龍馬関係文書』第二)。
具視は「権謀術数」を得意とした。慶応二年九月薩藩側に提示した「時務策」にこうのべている。
――直道のみにより公明正大に事をはこべば、労多くして、功は少ない。また障害も多い。
たとえば、屏風を立てるのに直立させれば、必ず倒れるから、これを屈曲せねばならぬようなものだ。
だから「権道」をもって、要路その他二、三の公卿、心志堅固の者と極密に熟計熟議して、内外相応じ、陰陽並び行なう時は、力を用いることがきわめて少なくして、功を収むることが速かである。
権謀術数を用い、大事をなすことが大切である――。
少数同志との熟計による極密の権謀術数、具視の本領発揮は、まだ年少一五歳の明治天皇の践祚(せんそ=天子になる)によって、俄然有利な道が開かれた。
処罰をうけていた親王・公卿がいっせいに赦免され、具視も入洛を許された。
朝廷内の状勢は一変した。具視の政治活動は、慶応三年(一八六七)に入って公然化した。
彼は大久保・小松・西郷をはじめ、中岡慎太郎・坂本龍馬ら志士と会談し、大宰府にいる三条実美とも連絡をとり、中山忠能・正親町三条実愛・中御門経之ら公卿とともに、王政復古の謀議にあたった。
この年後半期における大久保・西郷の権謀術数は、具視のそれを上廻っていた。
兵力のない朝廷にとっては、実力者である薩長両藩の提携に依頼せざるをえない。
また勅勘のとけていない長州藩にとっては、薩州藩に頼って、中央政界に復帰する機会をねらう以外にはない。
薩州藩は、実力もあり、中央政界に地歩もしめており、己の一挙手一投足如何で、天下の状勢も左右できる位置にあった。
まさに西郷・大久保の謀略の腕を存分にふるうことができる条件があった。
両人を中核とする薩州藩指導者は、薩長同盟をむすび、さらにこれを出兵盟約に発展させ、これに芸州藩を引き入れ、土佐藩倒幕派板垣退助とも提携を約束しながら、他方では後藤象二郎ら土佐藩主流派の大政奉還運動にたいしても協力を約した。 長州とむすんで幕府にたいし武力行使に出るか、士佐とむすんで幕府と平和的妥協をぱかるか、この両刀を適当に使いかけて、長土両藩を牽制し、ひとまず土佐の主張する将軍慶喜の大政奉還建白を実現させることを支持した。
しかしその裏では、その成果を無にするよう、薩長両藩主に幕府討伐の密勅を降下する工作をすすめた。
この密勅降下は、具視が得意とする権謀術数をめぐらす独壇場であった。
一〇月一三、四日薩長両藩主に倒幕の密勅が出たが、これは具視が玉松操をして起草させ、中山忠能が密奏し、宸裁を経たと『岩倉公実記』は記しているが、地の文の記述であり、「密奏」「宸裁」を証拠だてる史料は見あたらない。
今日島津家・毛利家に現存している密勅原本の写真から判定すると、勅旨伝宣の奏者として名を列ねる中山・正親町三条・中御門の三名は、その職務をもつ地位にもなく、かつ誰の花押もなく、形式上からいえば、きわめて異常なものといわざるをえない。
幕府側の史書、たとえば福地源一郎の『幕府衰亡論』も『徳川慶喜公伝』も、婉曲ながら、その真偽に疑いをさしはさんでいるのは、当然のことである。
しょせん真偽の判定は無用であろう。それが密勅の密勅たるゆえんであり、権謀術数を本領とすると自称する具視の功績なのである。
38
この倒幕の密勅は、一四日に慶喜が政権ならびに位記(いき=位書き)の返上を奏上するに一歩先んじたことによって、絶大の政治的効果をもった。
なぜなら、密勅の出ることが一日おくれれば、倒幕の名義は失われたからである。
7 維新指導者の政治手腕
一二月九日の王政復古大号令も、天皇と藩主を完全なロボットにした大久保・西郷・岩倉らの大芝居であった。
この計画は、文久三年(一八六三)八月一八日の政変の「故智」を踏襲した、宮中クーデターである点は同じであるが、決定的に異なる点は、五年前の政変では、天皇や松平容保・島津久光ら藩主が主体的に行動したのだが、今回は藩士出身の倒幕派や具視ら一、二の公卿にイニシアティブがまったくにぎられていたことにあった。
一二月九日、勅使千種有任が具視の邸に行き、蟄居宥免の宣旨を授け、具視が王政復古の勅書をもって宮中におもむき、かねての手筈で突如参朝した王政復古派の公卿・藩主を集めた小御所で、摂関・幕府の廃止を宣言する王政復古の大号令が天皇から言い渡された。
西郷は諸隊を率いて宮中周辺を警備し、利通は宮中に入って、計画の進行を監視し、激励した。 |
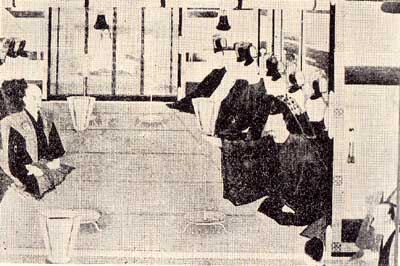
小御所会議のクーデター
|
この間、利通は、厳重な機密の保持、意外と思わしめる英断、そして人心をして戦慄せしめるほどの権威の発揮というクーデター方式を強硬に主張し、これなくては朝廷の基礎は確立しないと力説した。
この方針を朝廷内で十二分に実行したのが具視であった。両人は、人心が二百余年の泰平の旧習に汚染しているから、戦争をおこすことで、天下の耳目を一新し、天皇政権を樹立できるのだとのべ、無理を承知で、徳川家の厳罰論を唱え、徳川氏と一戦を交える機会を待ちのぞんだ。
そして思惑どおり、鳥羽・伏見の戦から戊辰戦役にもちこみ、天皇政権の樹立に成功した。
公卿の実力者岩倉、藩士層倒幕派の実力者大久保、この二人のコンビを基軸に、王政復古は実現した。明治維新の功績者は多い。
大久保とならんで「維新の三傑」と称された西郷と木戸がいる。公卿の中で三条の名を逸することができない。
中道で倒れた武市瑞山・高杉晋作・坂本龍馬たち、また勝海舟ら幕府側の人材も数えなければならない。
いや無名の全国草莽の志士の力こそ評価せねばなるまい。
それならば岩倉と大久保の、余人と異なる独自の活動とは一体何であるか。
結論を先にいえば、大政奉還から王政復古という、維新変革の決定的瞬間に、宮中クーデター方式の政変を実行したことであった。
それは権力の交替を最少限の規模の内乱をもって実現したこと、しかも内乱が小規模かつ短期であった割りに、なしくずし的変革の効果を大きくし、旧幕権力の残存を最少とし、新しく創出された天皇権力の強化をもたらすという効果かあげた。
そのことは、東アジアに向けての列強の侵略が進められつつある国際状勢の下で、歴史が必然たらしめた封建的分立国家から近代的な統一国家への移行の基礎をきずく、最短かつ安全な路線をたどったことを意味するといえよう。
彼らはクーデターの名手であった。
その策謀の手腕は、幕末政局の中で養われた。
古代以来の因襲の強い宮中、中世的ともいうべき、おくれた土地制度をもつ薩州藩、およそ開明的な空気とは縁遠い場で、育ちきたえられ、かつ維新後の政治的権威のより所もそこにおかれていた。
しかも両人の視野は、そうしたせまい世界から、他人に先がけてぬけ出ていた。
岩倉の場合は、対幕折衝にあたった経験から、大久保の場合は、藩の代表として江戸・京都の中央政局で活動した閲歴(えつれき=経歴)からえた識見であった。
広く国際状勢の中で、日本全体をどう導いていくか、その損得勘定を冷静にできる現実主義のナショナリストであった。
その政治活動は皇室の権威と藩の実力に依拠しながら、公卿の利益、藩主・藩士の利害だけを代表しなかった。
天皇・公卿・大名・藩士の古いあり方を否定することに容赦はなかった。
新しい国家体制の中での、新しい彼らのあり方を指示し、その限りでのこれら封建支配者の利益を擁護した。
この絶対主義政治家としての方針と、衆と行を共にせぬクーデター政治家の資質と相まって、彼らにとり、心を許す同志は少なかった。
ある意味で、盟友を次々と裏切ることで、明治政府の最大の指導者となったともいえよう。
三条実美は太政大臣の栄職にありながら事実上ロボット化され、薩の西郷、長の前原一誠、土の板垣・後藤象二郎、肥の江藤新平らの同僚は、彼らのために追われ、また殺され、数少ない味方の木戸も、大久保に裹切られるという不安をぬぐい去れなかった。
しかしそれは岩倉・大久保の個人的責任ではない。
なしくずし的変革としての明治維新の性格、一九世紀後半東アジアでの日本の近代化という歴史的条件の要請には、こうした冷酷無惨な政治行動の他には応じ切れなかったと見るべきだろう。
盟友・後輩の忠実な友、信頼される親分であり続けようとする努力において、最後まで鹿児島の小天地から脱却できなかった西郷の行き方とは対照的である。 |

渡米した大久保のマンガ
|
8 大久保の予見と岩倉
岩倉と大久保は、官僚政治家の原型を創り出した。
両人のコンビになる政権が、明治初年、天皇制国家の建設に果たしたはなばなしい業績は、彼らに指導された維新官僚陣の有能さを物語っている。
それは世界の大勢を知り、国家の進路に見とおしをもっていたからである。
これは、当年では、欧米の情報と文化を摂取する独占権をもっていた中央政府首脳の特権であった。
在朝政治家と在野政治家との識見のへだたりは、一層ひろがった。
自分だけが日本を富強の国たらしめる針路を知っているという自負の強さと、自分だけが国家社会の運命に責任をもっているという責任感の深さがあった。
これが彼らをして、終始政敵の非難にさらされながら、自己の歩みに迷いをもたず、勇断の政治を行ないえた精神的支えであった。
明治一一年(一八七八)五月一四日、大久保は馬車で参朝の途中、麹町清水谷で暴漢におそわれて死んだ。
犯人は石川県士族島田一郎ら六名で、士族的自由民権派であり、大久保の専制の罪を弾劾した斬奸状をもっていた。
時に数え年四九歳。
兇刃に倒れた日、彼は福島県令山吉盛典にこう語った。
明治元年から一〇年に至る第一期は、兵事多くして創業の時であったが、一一年から二〇年までの第二期は、内治を整え、民産を殖するもっとも大切な時期であり、その後の一〇年の守成期は、後進賢者の継承修飾を待つものであると。
軍事中心政策から内治中心政策への転換、同時に従来の専制政治の形態に修正を加える必要を予感していた。
そのことは一一年三月地方会議の設置をふくむ地方自治制についての大久保の建議にあらわれていた。
大久保の死後、岩倉と伊藤博文のコンビが明治政府の大黒柱となった。
しかしこのコンビは、前代ほどしっくりいかなかった。
大久保のいう第一期の・目標、中央政府の強化と統一国家の確立に代わる第二期の目標は、決して迷いない確信あるものではありえなかった。
在野の要求に機先を制して、上からの文明開化政策を遂行するのとはちがった、在野の自由民権運動に譲歩しながら対抗することであったからである。
自由民権運動は、一二年から、国民運動としての性格をもつ本格的な盛りあがりを見せ、一四年(一八八一)北海道開拓使官有物払下げ事件という政府の汚職問題を契機に、最高潮に達した。
このとき、岩倉は、腹心の井上毅(こわし)の助言をえ、伊藤の協力をえて、己が本領とするクーデターの手腕を存分に発揮した。
彼は、今回もまた舞台裏で秘密にお膳立てをととのえた上で、一気に国会即時開設と自由主義的憲法を主張する大隈重信の参議罷免を決定すると同時に、来る二三年をもって国会を開くとの詔勅を発して、民権派の攻撃の鋒先をそらした。
それ以後、彼は、天皇の大権を維持した憲法を実現すること、議会開設前に皇室制度の基礎を固めることに全力を傾けた。
彼のもくろみは美事に成功したといえる。
明治二二年(一八八九)発布された大日本帝国憲法は、天皇の権力を実質的には制限するのではなく、逆にこれを法的に確立するものであった。 |

サンフランシスコの雑誌に
のった岩倉具視のマンガ
|
しかし彼は、死の直前、明治八年の漸次立憲制度を採用するとの詔勅を発布したことを後悔し、すでに開かれていた府県会の中止を求めたように、歴史の進歩、日本の前進を指導したと自負しえたかつての立場から、自らの行動に自信を失い、そして歴史の進歩をおしとどめようとする反動の立場に転落していた。
それは岩倉個人の問題というよりも、近代天皇制それ自体の歴史的位置と役割とが変わっていたからである。
彼は明治十六年(一八八三)七月二〇日、数え年五九歳で死んだ。
参考史料・文献
勝田孫弥『大久保利通伝』 『大久保利通文書』 『大久保利通日記』(共に史籍協会叢書の内)
『岩倉公実記』 『岩倉具視関係文書』(史籍協会叢書の内)
top
****************************************
|