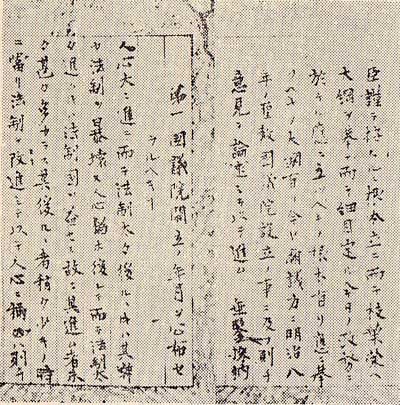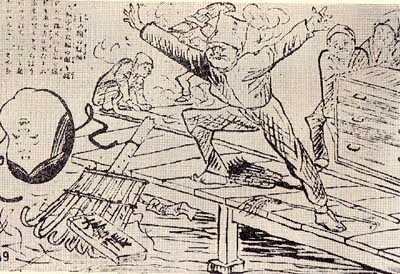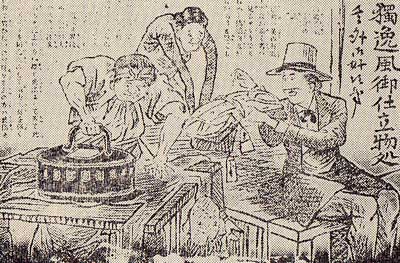|
****************************************
Index 岩倉・大久保 木戸 板垣 大隈・松方 伊藤 陸奥 星 川上・山本 山県 桂 西園寺・原
1 伊藤博文の地位 top
伊藤博文の家はもともと百姓の出で、父が下級藩士の家の養子となったためにかろうじて士分の列に加えられた。
その博文が六九歳にしてハルビン駅頭の兇弾に倒れたときは、枢密院議長従一位大勲位公爵、国葬をもってほうむられた。
彼の栄達は幕末・維新の騒乱とともにはじまり、彼の栄光は明治国家の栄光とともにあった。
明治国家の建設者、明治憲法体制の創設者、おそらく大久保利通を除いては、伊藤を明治の政治家の第一に挙げることに異論は少ないのではなかろうか。
伊藤は明治政府の最初から開明的な官僚としてその才識をあらわした。
いわゆる「大久保体制」の下では大隈重信とともに大久保をたすけた。
だが、彼が明治政府の事実上の首領の地位を占めるようになるとは、明治一〇年(一八七七)以前には予想しがたいことだった。
時勢が伊藤にさいわいし、伊藤は的確にそれをとらえた。
征幃論の争いによる西郷・板垣らの下野が工部大輔だった三三歳の伊藤を参議兼工部卿たらしめ、そして木戸の死は彼を長州藩閥の重鎮とし、また大久保の死は彼を内務卿としてその後継者の地位にもっとも近い地点に立たせた。
その彼が次第に政府の主流になり中心となり、ついに第一人者としての地位にたつのが、ここで扱う「明治一四年政変」から憲法発布にいたるプロセスである。 |

伊藤博文
|
それは明治憲法の制定・明治国家の確立の過程であるとともに、最初の内閣総理大臣、最初の枢密院議長、そして最初の貴族院議長伯爵伊藤博文を生み出す過程でもあった。
議会開設のとき伊藤は五〇歳、つまり、ここで取扱う時代は、彼の四〇代の躍動期に当る。
この一〇年間、伊藤は明治政府を背負って立つ決意と反対者にたいするはげしい闘志と、そしてまた政治状勢にたいする慎重な配慮とをもって、明治国家の構築に智力を傾けたのであり、その成功が彼の名に重みと輝きを与えたのである。
この一〇年間のスタートの地点では、伊藤の地位はまだ約束されたものではない。
薩摩閥の首領黒田清隆、そして内閣参議の首席大隈重信、いずれもその声威は伊藤に勝るとも劣らなかった。
どのようにしてその地位が逆転するか、その大きな画期はやはり「明治一四年政変」にもとめられねばならない。
2 熱海会議 top
明治一四年(一八八一)の正月、伊藤と井上薫と大隈重信はともに熱海に遊び、たがいの宿舎に往き来しては時事を談じた。 世に「熱海会議」といわれるものである。
このとき伊藤らがなにを語り合ったかは明らかでないが、憲法と国会を設けること、政府の新聞を発行すること、開拓使の処分などが話題に上ったことはたしかであろう。
このとき三人の意見が対立したとか、争ったとかいう様子は見えない。
伊藤と井上は長州閥であって幕末いらい生死をともにした仲であるが、大隈は肥前の出身で藩閥の背景をもたない、むしろ政府の中では孤高の位置にあった。
しかし、伊藤も井上も明治初年から大隈の下で大蔵省にあってともに開明化に力を合せてきた間柄であり、世間もこの三人を大久保なきあとの明治政府の進歩派のグループと見なしていた。
そしてまたそれだけに、彼らにはそれぞれ自負と競争心があったとみていいだろう。
とくに伊藤と大隈の間には微妙な空気が流れていた。
この前年、内閣と諸省の分離問題がおこったとき、伊藤が分離を提案したのは参議にして大蔵卿を兼ねた大隈の力をそぐためだとも言われた。
とはいえ、黒田清隆に代表される薩摩閥や、佐々木高行や元田永孚らの保守的宮廷派(彼らは薩長閥に強い反感をもち、自ら中正派と称するようになる)にくらべれば、ひとしく開明的な意見をもち、内外の状勢にも通じていた。
当時、伊藤・大隈・井上の三参議から新聞発行の相談をうけた福沢諭吉の目にも、三人は共同の戦線をはっているものと映っている。
だが、このとき国会の開設や開拓使の処分について、三人の間でどれだけ具体的な一致をみたかは疑わしい。
それからわずか半年ののちには、国会開設問題をめぐって伊藤は大隈とはげしく対立し、ついで開拓使官有物払下事件の激動をへて大隈を閣外に追う立場に立つからである。
当時の最大の政治問題であった国会開設について、三者の一致点は、民間の国会開設運動を政府も傍観せず、憲法と国会について積極的な態度を示すべきだという程度のもので、その時期や形態については、おそらくそれぞれの思惑を秘めていたと思われる。
実はその点こそが問題だったのである。
3 国会意見の対立 top
明治一三年(一八八〇)を頂点とする民間の国会開設運動に対応して、諸参議は国会に関する意見書の提出を求められ、伊藤は二二年の暮に次のような意見書を提出した。
維新いらい藩を廃し兵制を変じ士族の祿を失ふもの全国に幾十万、ややもすれば不平を鳴らす情があるのは必然である。
気節議論の士は多く政談に従ふことを好むゆへに、その向背は庶民の方向を決定し、天下の禍機をはらんでいる。
また欧州の文物がとうとうと我国に入るに及んで欧州政体変革の説もまた士族の間に行はれ、これを防ぎとめることはできない。
これらは皆時勢の致すところであって、政府のなしうることは、緩急をはかりこの勢を操って漸進の方向に誘導すること以外にはない。
そのために、まづ元老院を拡張し華士族公選の議員をえらんで上院の基礎をつくり、また公選検査官を設けて人民の疑惑を避ける途を講ずべきである(『伊藤博文伝』中巻)。 |
伊藤はまた、詔勅をもって漸進の主義を天下に示し人心を皇室に帰向せしめることを先決とするとも言った。
人心をしずめておいて国会の開設はできるだけひきのばし、その間にうつ手はあるだろうというのがその戦略であった。
一方大隈はなかなか意見書を提出せず、ようやく一四年三月になって左大臣有栖川宮(ありすがわのみや)にひそかに意見書を奉った。
その内容は伊藤の意見とは相当なひらきがある。
その一つは、大隈が翌一五年(一八八二)に憲法を定め、一六年に議会を開くと主張しているその時期の問題であり、一つは、議会多数の衆望をえた政党の首領を首相に任ずるという議院内閣制の主張であった。
大隈はこれをほかの大臣参議に秘することを願ったが、急進的な内容に驚いた有栖川宮はこれを右大臣岩倉具視に示し、その内容はさらに伊藤に洩れた。
伊藤はこのとき大隈との避けられぬ対立を決意したに相違ない。
憤激した伊藤は大隈を責めた。 |
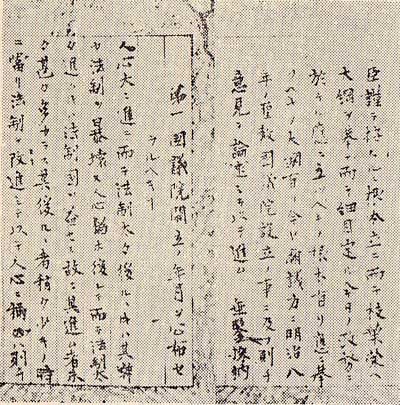
大隈の密奏(有栖川宮の手元のものを伊藤がうつしとったもの)
|
大久保が倒れたとき、われわれは心を協せて難局に立ち向おうと誓ったのに、このやうな大事を一言の相談もなしに上奏したのはなぜか。
政府の要職を公選に委ねることは君主の権を人民に棄てるにひとしい。
君の建白は福沢の憲法私案と同じではないか。
政府の情実は君も知る筈だ。君と左大臣とだけでことを行へると思ったら大変な間違ひだ(『佐々木高行日記』)。 |
伊藤は病と称してひきこもり、大隈は閉口した。
伊藤と大隈の憲法論にこのようなへだたりをもたらした原因の一つは、それぞれのブレーンの差であろう。
伊藤は憲法論については井上毅(こわし)の意見を重んじ、大隈は矢野文雄らの意見をきいた。
伊藤の意見書は井上の起草であり、大隈の意見書は矢野が起草し小野梓が手を加えたといわれている。
当時、憲法や議会の組織はもっとも先端的な知識に属し、福沢らの紹介したイギリス流の議会制度がむしろ世論の常識であった。
矢野は官吏ではあったが福沢門下であり、大隈が福沢の代弁をしていると伊藤が疑ったのも、まったくのまとはずれではなかった。
これにたいして、早くから英仏のとちがったドイツ流の国家体制のあり方に注目し、研究を重ねていたのが井上毅である。
井上は熊本藩士、フランス・プロシャに学んだのも大久保に見出され、この当時太政官大書記官の地位にあった。
謹厳にして鋭敏、病弱の身に烈しい意志をひめた官僚であるが、その彼が全力を挙げて支持したのが伊藤であった。
伊藤における井上毅に類するものとして、大隈にたいする小野梓があげられるかも知れない。
井上毅はまた福沢一派に強い敵意を示していたから、伊藤の福沢にたいする疑念には井上毅の影響が強かったとみてよいであろう。
井上にせよ矢野にせよ小野にせよ、当時の中堅的な官僚であり、伊藤と大隈の対立は、その背後にある憲法論の差のみでなく、当時の新進官僚群相互の対立でもあったのである。
伊藤と大隈との対立は大臣らの斡旋によって一応表面的にはおさまった。
しかし両者の和解がなったと思われる明治一四年の七月一〇日前後から、半月たつかたたぬうちに、あたらしい事件がまきおこって、政府内に底流した諸対立を表面化し、ついに政府の分裂をもたらすことになる。
それが「北海道官有物払下事件」であった。
4 明治一四年の政変 top
「官有物仏下事件」の発端をなしたのは、一〇年以上にわたって北海道の開拓に力を注いできた開拓使の諸事業、その工場や船舶をふくめてすべてを、三八万円、三〇年賦で開拓使の官吏に払下げるというプランであった。
北海道の開拓は、ロシアにたいする防衛の意味からも巨額の国費を割いて行なわれてきたが、経済的には国庫の支出を償うものではなく、明治一〇年以降の財政困難のもとにおいては、事業の縮少、開拓使の廃止はやむをえないと考えられるにいたった。
ここで、黒田の下に開拓使を独占していた薩摩系の官吏が、払下げを受けて事業を継続しようとしたのがこのプランである。
政府部内には大隈をはじめ反対論が強かったが、開拓長官黒田清隆の強引な主張によって押切られた。
一五〇〇万円に上る国費を投入した開拓事業の成果を、このような条件で一派閥に払下げるということは、これはいかにも暴挙であった。
世論は沸騰し、藩閥の横暴をなじり、このような政府を粛正するためにこそ議会の開設が急務であると主張した。
そして大隈が国会急設の建議をたてまつり、かつ払下げに反対したことが伝えられると、新聞は、大隈をのぞいて政府に人なしと叫び、大隈を外部から支援激励する形となった。
大隈が閣外の力を借りて野望をとげようとするのではないかという伊藤の疑惑は、ここにたまたま現実的な根拠をもつことになった。
大隈が福沢を参謀とし、岩崎(三菱会社)を資金源として、陰謀を企てているという流説は政府部内にも真剣に信じこまれた。
大隈はのちに「これがいわゆる贔屓(ひいき)の引き倒しで迷惑千万なのは我輩一人……我輩はとうとう謀叛人になってしまった」(『大隈侯昔日譚』)と回想している。
外に払下げをめぐる烈しい批判に直面し、内には薩派・中正派・大隈派など、さまざまな対立をはらんだ明治政府は危機にひんした。
この危機を切り抜けるだけでなく、この機会に閣内の空気を大隈排撃に統一し、薩派をも抑えて長派の指導権を確保し、あわせて国会に関する政府の方針を統一することに成功したのが伊藤であり、これを助けた井上毅の才腕であった。
彼らはすでに立憲論の上で右大臣岩倉を推服させたが、この事件の処理にあたっても岩倉についてはなれず、岩倉〜伊藤〜井上のラインを確保した。
大隈の声望と、薩長藩閥への非難は、かえって薩長派の反省と団結を生み出し、官有物払下げの中止と、大隈の免職という線で中正派をもふくむ政府の大部分は一致した。
騒ぎの最中、大隈は東北・北海道の巡幸に供奉して北地にあったが、帰京した彼を待っていたのは内閣からの辞職の勧告であった。
大隈の辞職とともに、矢野・小野ら大隈系の官瞭はすべてその職を兔ぜられた。
この措置が「明治一四年政変」とよばれるのだが、伊藤や井上がもっとも精力的に働いたのは、憲法制定の方針を定め、詔勅をもって天下に公布し、政局の指導権を政府にとりもどすというかねてからのプランをこの際に実現することであった。
彼らは岩倉を動かし、中正派を説き、ついに国会開設に関する勅諭を公布することに成功した。
史上に有名なこの勅諭は、漸進の主義をとることを明らかにし、憲法は天皇自らが定めること、一〇年ののちに国会を開くべきこと、そして最後に、事変を企てるものは国典をもって処断するという決意を表明した類例のない勅諭である。
この方針は全く伊藤〜井上の構想であり、この勅諭は、伊藤をその後一〇年間の憲法制定の中心者たらしめることを約束するものであった。
この勅諭の政治的意義もまた絶大であった。
政府が、払下げの中止と大隈の免職を行なうに止まったならば、民間の国会開設運動は容易に衰えず、岩倉〜伊藤を中心とする部内の統一もまたはるかに困難だったにちがいない。
伊藤自らの指導権と、国会論における政府の指導権を同時に確立した手際は、彼らの政治として資質をものがたるのである。
伊藤の成功と大隈の失脚と、この二つの運命を分ったものは、伊藤がかつて大隈を批判したように、政府の情実にたいする認識の如何であり、開拓使の事業にこだわって勢威を失った黒田と、伊藤とを分ったものは、時勢にたいする洞察の有無であった。
5 ヨーロッパでの調査 top
明治一五年(一八八二)三月から、翌年八月まで、伊藤は憲法・議会制度・政府の組織・地方制度などを調査するという使命をおびてヨーロッパに派遣された。
五月、ベルリンに到着、憲法学者グナイストの講義をきき、さらにウィーンでスタインに教えをうけた。
ドイツをえらんだのはもちろん、ビスマルクの下に強力な君主主義・国家主義をもって、強国への途を歩んでいたドイツに学ぼうとしたからである。
伊藤はとくにスタインに傾倒し、これを政府顧問に招いて大学の指導・学校制度の改革を行なわせようとしたが、スタインは老齢を理由にこれを断わった。
伊藤は一六年(一八八三)二月ドイツを離れ、ベルギー・ロンドンに遊び、さらにロシア皇帝の戴冠式に参列して帰朝した。
病の床に伊藤の帰国を待ちかねていた岩倉具視は、伊藤の横浜入港に先立つこと二週間、一六年七月二〇日に没した。
しかし、帰朝後の伊藤は、すでに岩倉の力を借りることなく国家体制の構築に当るだけの見通しと実力を備えていたのである。
外遊が政治家の識見を高め、それでなくとも政治的地位を重からしめるという現象は、明治四年(一八七一)から六年(一八七三)の岩倉使節団の例に徴するまでもなく、明治のころには著しかったことである。
伊藤の場合も憲法調査というそのことだけで内閲における伊藤の地位を重からしめたのだが、それにしても伊藤は、ドイツでなにを学び、なにを得て帰ったのだろうか。 |
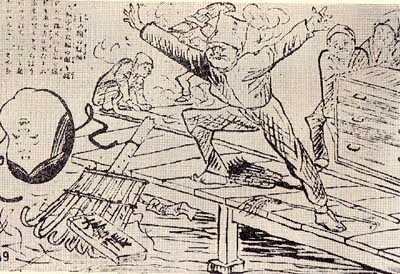
上の間のすす掃き(大熊手は大隈重信、福の面は福沢諭吉をあらわす) |
伊藤は、八月にウィーンから送った手紙の中で早くも、
グナイスト、スタインの両師について、国家組織の大体を了解することができ、皇室の基礎を固め君主の大権を堕さぬだけの大きなねらいは十分立てられた。……
まことに英米仏の自由過激論者の著述だけを金科玉条のやうに信じこみ、国家を傾けかねぬ勢にあるのが今日のわが国の現状だが、この形勢を挽回するだけの道理と手段を得た。……
心ひそかに死処を得た心地がする(『伊藤博文伝』中巻)。 |
と、満々たる抱負と決意を示した。
伊藤は心の底から天皇と政府の権力を強め、民権論者と戦わねばならぬと思っていたに相違ない。
そのための国家と政府の組織と理論づけを、滞在わずか三ヵ月で獲得できたと信じたのである。
それはスタインらの国家学のおかげだけではない。
ドイツの現実が、伊藤の意図にぴったりだったからである。
伊藤は一五年夏のある夕、皇帝ウィルヘルム一世に陪食した。
席上「国会を開くとは、日本皇帝のために残念なことだ」という皇帝の言葉に驚かされたが、まさしくそのようなドイツの権力政治の現実に、伊藤は強くひきつけられたのである。
憲法は君主の主権を確立するためのものであり、議会を設けるのはやむをえざる譲歩であり災厄にすぎないという観点、それは彼の一三年いらいのものであるが、ヨーロッパの現勢とドイツの興隆の事実によって、強められ裏づけられたわけである。
井上毅は、留守政府に復古主義の傾向か強まったことを憂慮し、それは伊藤が手紙でしきりにドイツ主義を鼓吹するからだとなげき、また、帰朝後の伊藤はドイツかぶれで、ビスマルクを気どっているともかげ口された。 |
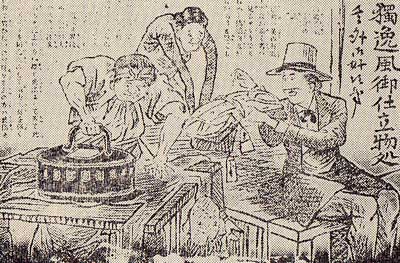
「頭はそのままで下の方はドイツ風に仕立ててくれ」、
伊藤の外遊を風刺したマンガ
|
伊藤がドイツで絶大な自信をえて帰ったのとは全く対照的に、同じころヨーロッパに旅した板垣退助は、自由民権の祖国フランスの現実に失望した。
板垣の感想はヨーロッパでは生活社会は驚くほど進んでいるが、政治社会は少しも進んでいないということ、彼らがアジアを蔑視し奴隷視するのは、かつて自ら破壊した貴族の特権をアジアにたいしてむけかえているに過ぎないこと、などであり、自由民権は文明の大義であるという彼の信念に、かえって動揺と混乱を負わされて帰朝した。
もともと板垣の七ヵ月のヨーロッパ旅行は、伊藤らが板垣の民権論を矯めようとしてひそかに斡旋したものなのだから、その意図のなかばは成功したわけである。
しかし、板垣を政府の側に改宗させようという試みは、伊藤らが滞在中しばしば板垣に接触して説得工作をしたけれども、成功しなかった。
板垣はパリの宿舎にとじこもって、哲学めいたことばかりに熱中していると、伊藤の随員西園寺公望が報じている。
伊藤が、現実政治の世界に生きがいを見出した政治的なリアリストだったのに反し、ヨーロッパに正理公道の実現と、志士的な政治家の理想像とを期待した理想主義者板垣の幻滅は大きかったわけである。
6 初代の内閣総理大臣 top
伊藤が憲法や議会の組織を決定する準備として、まずとりかかったのが政府そのものの組織の改革であり、いわば政府の体質改善であった。
その大きなポイントは華族制度の創出(明治一七年〈一八八四〉七月)と内閣制度の樹立(明治一八年一二月)という二つの点にあった。
当時の太政官制度のもとでは、行政府である各省(その長官である卿)の上に、太政・左右の三大臣と参議(卿を兼ねることが多かったが)による正院があり、さらに天皇の側近には宮廷の勢力があった。
このような多元的な合議機構を改めて、行政府の長としての内閣総理大臣に政務の全責任を負わせ、これを天皇に直結するという、行政を中心とした統治の一元化が内閣制度のねらいであった。
また当時の華族はもとの公家と大名であり、古い特権身分の名残りをとどめた伝統的な貴族だったが、これに維新の功臣や勲功ある官僚を加えてあたらしい貴族をつくり出し、これを国家機構の一部に編入・統制して政党勢力への防塞にしようというのが新華族制のねらいであった。
これらの改革をすすめるにあたって、伊藤はみずから推進力となり、その結果としてみずから政府の中心とならねばならぬこと、それだけの自負と見通しはもっていたにちがいない。
しかし、伊藤のやり方は、たいへん慎重だった。
政府組織の近代化の必要を説くことはやさしいが、政府の人的構成はやはり薩長のバランスの上にのっており、また薩長を敵視する宮廷派の勢力や、大臣の職責は公家の任であるという観念も無視できないことを知っていたからである。
伊藤は帰朝後、人に語っていわく、
帝室と内閣の中間に憲法の相談局を置くやうなことはしない。
自分は天皇の大臣であり、天皇と大臣とは一身同体である。
このたび創定しやうとする憲法は、自分は進んで天皇と協議してつくり上げるつもりだ。
さまざまな流派の人を容れるとよい作品ができないのは、詩を作る場合でも同じではないか(『伊藤博文伝』中巻)。 |
伊藤がまず手をつけたのは、自分と天皇を結びつけることであった。
明治一七年(一八八四)三月に宮中に制度取調局をおき、伊藤は自らその長官となり、局員には井上毅・伊東已代治(みよじ)らを配して皇室典範・帝国憲法の起草に当らしめ、一方宮内省を改革し参議をもって宮内卿を兼ねうることとして、自ら宮内卿に任ぜられた。
このとき伊藤は天皇にたいして、憲法制定にあたっては天皇みずから十分勉強されリードしていただきたいこと、伊藤にたいする疑いが起こったら、なにによらず直接に叱責していただきたいと申し述べた。
後年、山県有朋がうらやんだような天皇と伊藤との信頼関係はこのころからはじまるのである。
宮内卿としての伊藤によってつくり出された新華族は、公侯伯子男の五等の爵位を天皇から授けられ、同時に戸籍・身分・結婚などは宮内卿の管理をうけることになった。
爵を授けられたもの五〇〇余名、公家華族・大名華族のほかは薩長出身の臣が多く、伊藤もまた勲功によって伯爵を授けられた。
内閣制度の確立は、伊藤のもっとも苦心を払ったところだったと思われる。
明治一八年(一八八五)に入って、伊藤は太政官制を廃止し、新しい中央政府をつくることを太政大臣三条実美に進言した。
これは三条に引退を勧告するにひとしかったから、よほど言い出しにくいことであったにちがいないが、三条もこのプランには尻ごみして、さしあたり岩倉なきあとの右大臣に伊藤を推そうという妥協案を示した。
伊藤は内閣制の主張を引込めたが、自分の右大臣就任は固く拒み、黒田を強く推した。
また伊藤・黒田を左右の大臣にして薩長のバランスをとろうという案をも頑固に拒絶した。
しかし、黒田がその任でないことは明らかであった。
黒田も一度は右大臣就任を承知したが、佐々木高行らから酒癖の悪さを種にしての反対をうけ、ついに辞退せざるをえなくなった。
こうして妥協的なプランはすべて流産し内閣制が日の目をみることになる。
総理大臣にあげられた伊藤は、諸参議と黒田に参集を求めたが、黒田は酒をあおっていて参会せず、翌日説得にきた井上薫にも、ピストルをふりまわすという酔態を演じた。
非難を集中された黒田は辞職を申し出て、これはみとめられなかったが、ついに最初の内閣には参与せずに終った。
伊藤のこのあたりの進退は見事である。
薩派の巨頭としての黒田の感覚が、すでに時代おくれであったこともたしかであるが、結果からみれば黒田は内閣制度を生み出すための道具として踊ったにすぎないことになる。
伊藤が、どこまでこのようななりゆきを予想したかはわからないが、宮廷の中に黒田への強い反感があったことを知らぬはずはない。
黒田の右大臣が実現したとしても長く政府を統率しうるものでもなく、果実は結局伊藤の手に落ちたにちがいない。
伊藤にしてみれば、藩閥寄合いの人間関係の中から統一的な政治組織をつくり出すためのやむをえない廻り道だったわけだが、その過程で持ち上げられたり突き落されたりした黒田もいい面の皮である。
酒をのまないときの黒田はむしろ穏やかな人柄で古風な情誼の持主であった。
大宝令いらいの古制と、藤原氏の後裔による最高官職の独占に終止符をうち、最下級の武士だった伊藤が内閣総理大臣に就任したことは、なによりもあたらしい時代を象徴するでき事であった。
伊藤は官紀五項を各省に達して官吏の選抜・規律・責任・倹約を要請し、ここに近代的な行政組織が誕生したかにみえ、世論もまたこの改革に大きな期待をよせた。
しかし、組織の近代的な形式は、ただちに内実の近代化を意味するものではなかった。
第一次伊藤内閣が、長派四、薩派四、土佐一、幕臣一で構成されたように、薩長藩閥による支配という実体は、それまでとほとんど変らなかった。
伊藤の特質は諸勢力のバランスをよく考え、一つの方向に誘導する才能にあって、反対派を抑え切る力の政治家ではなかった。
またその性格や素行からしても、一世の徳望をあつめるというタイプの政治家でもなかった。
総理大臣と宮内大臣を兼務したことで、伊藤が宮中と行政府の別をみだすものだという攻撃をうけたとき、伊藤は、宮中と行政府の一体化は立憲君主国の常道であるが、自分は平生の品行から衆望に協わず、この点はビスマルクが英略あってしかも徳行に富むのに比して恥ずかしいと思う、と語った。
伊藤の才腕のみをもってしては、藩閥支配の現実を動かすことができず、条約改正問題の難航などによって、わが国最初の内閣はこれといった成果もみることなく終るのである。
7 欧化主義 top
伊藤が、その平生の品行から徳望を失ったといっているのは、彼が美しい花を愛する点でまことに天衣無縫だったからでもあるが、この当時の最大の非難はその欧化主義に浴びせられていた。
鹿鳴館の舞踏会に象徴される洋装・洋食・洋楽、そして夜を徹した舞踏、政府高官を中心とするわが国上流紳士は欧化熱にとりつかれ、世にいう鹿鳴館時代を現出した。
その張本人と目されたのが伊藤博文である。
日本がヨーロッパの富強にならって、その技術や制度をとりいれたのも、もっとひろい意味でのヨーロッパ文化の導入(文明開化)もいずれも明治初年いらいのことであって、このときにはじまったことではない。
伊藤内閣の時代がとくに鹿鳴館時代とよばれる欧化主義の風潮をつくり出しだのは、条約改正の必要から、政府が西洋風の生活様式の採用の先頭に立ったためである。 |

鹿鳴館の仮装舞踏会
|
とくに、二〇年四月の伊藤主催の仮装舞踏会は世人を驚かすに足るものであった。
伊藤や外務大臣井上馨の考えは、日本が文明国となったという印象を外国に与えて欧米からの信用をえようとするところにあった。
宗教の異なるために蔑視されるのを痛感した伊藤は、ドイツでキリスト教に改宗し、帰朝後井上馨をもすすめて改宗させた。
舞踏会と信仰とは同じ次元で語りうるようなことではないが、彼らは条約改正の必要、欧米列強と対等の地位に立つことへの熱望から、その手段としてあらゆることを辞さなかったのである。
欧化主義にたいする反発は、その後、条約改正案が世間にもれたことにともなって、猛烈な条約改正反対運動をよびおこした。
とくに、治外法権の撤廃とひきかえに、外国人を判検事に任用するという点は、独立国の名誉を傷つけるものとしてはげしい非難をよんだ。
政府の圧迫と社会状勢の変化によって、しばらく停滞ぎみだった自由民権運動も息を吹きかえし、欧化主義の風潮を苦々しく思った保守派と力を合せて藩閥打倒の叫びをあげた。
政府の内部には、谷干城らの薩長藩閥に反感をもつ軍人や、憲法起草の中心だった井上毅もまたこの条約改正案に強く反対した。
政府は明治一四年いらいの危機に直面し、明治二〇年(一八八七)の暮、ついに有名な保安条例を発して在京の民権派の人々を追放し、翌春には井上外相が辞職して条約改正を中止せざるをえなくなった。
井上の代りに外務大臣となったのは大隈重信であるが、伊藤がこのとき大隈を起用したのは、改進党系の反政府運動を緩和するためであり、またすでに大隈の入閣によって動揺しないだけの主導権を握っているという自信をもっていたからでもあった。
伊藤は、井上の外相辞任とともに宮内大臣の兼任をやめ、やがて憲法審議のために枢密院議長に転出する。
8 憲法制定 top
条約改正をめぐる世論がようやく動きはじめたころ、井上毅がレースラー・モッセなどの外人顧問の意見をただしながらまとめ上げた憲法草案が伊藤の手もとに提出された。
伊藤は草案の内容が世間にもれることを防ぐため、政府攻撃で騒然たる首都をはなれて、夏島(神奈川県)の別荘にこもり、伊東已代治・金子堅太郎・井上毅と四名だけで草案の検討をつづけた。
明治二〇年の夏である。修正案はふたたびレースラーの意見を徴して、二一年(一八八八)の春までに最終的にまとめ上げられた。
起草の推進力となったのは井上毅であるが、伊藤をふくめた四名は起居をともにしながら討論し、しばしば激論をかわすこともあったという。
伊藤自身の憲法についての意見が強く反映していることはいうまでもない。
伊藤が憲法起草の基本方針としたのは、天皇の大権を不可侵のものとして確保すること、そしてその範囲のなかで議会の権限と臣民の権利義務を明らかにする点にあった。
伊藤らは反動的な国学者などとちがって、欧米の憲法理論にも通じ、立憲政治のなんたるかを心得てはいたが、わか国の国体を歴史的な天皇の絶対不可侵性にもとめ、その上、行政府と君主とは一体であるべきものという考えを貫いたから、君主と行政府の権限は強力になり、議会の権限はいちじるしく弱体なものにならざるをえない。
とくに、夏島草案とよばれる初期の草案にはその色が濃かった。
議会が天皇に上奏し、政府に質問し、人民の請願を受理し、みずから法案を提出する権利、これらの権利は、夏島草案にはなく、それ以後の修正や審議の過程でしだいにとり入れられてきたものである。
議会がせめてこの程度の権利をもつにいたったことは、その後の憲政の運用の上に無視できない役割りをはたすのだが、この修正は、一つには井上毅やレースラーの立憲政治の本質論からする批判により、一つには条約改正問題などによる政府内外のはげしい攻撃と藩閥不信の念を考慮せざるをえなかったという事情によるのである。
伊藤は憲法草案を天皇に上奏し、天皇自ら取捨裁決して神聖不可侵の法典を定められるように願った。
天皇の顧問機関としての枢密院が、元勲や練達の人を集めて設けられ、天皇親臨の下に伊藤を議長として憲法の審議に当ることとなった。
もちろん憲法草案を国民会議にかけよとか、元老院で審議せよというような意見がなかったわけではないが、伊藤は政府にたいして批判的な元老院を避け、また天皇の将来の顧問機関の必要を考えて、あらたに枢密院を設けたのである。
枢密院の憲法制定会議に、天皇はかかさず臨席された。草案をめぐる論議でめだったのは、一方に議会の承認とか臣民の権利とかを明記するのは不穏当だという保守的な意見があり、一方に議会は政府を弾劾する権限をもつベきだという批判的な意見があったことである。
伊藤は前者にたいしては立憲政体を設ける以上、君権を制限することはある程度やむをえないといい、後者にたいしてはこの憲法は君権を強固にするためではないかと反問した。
君主の主権は絶対的であるというたてまえと、立憲政治の木質との間にはやはり矛盾があった。
伊藤は、矛盾した要素をともにみとめながら、憲法の運用においては、政府の自制と議会の操縦によってこれを調和させうると信じたのである。
このとき、外務大臣として会議につらなった大隈重信は、会議中ほとんど発言しなかったので、その心中をさまざまに噂された。
憲法論ではとても伊藤らに太刀うちできないと考えたからだという見方も、条約改正の事業に専念するつもりだったという見方も、いずれも事実であろうし、また、この憲法をもってしても議会政治を実現できないことはないという見通しをもったこともたしかである。
明治憲法の下においても、議会と政党の力を無視できなくなっていくことは、その後の歴史が証明した。
明治二二年(一八八九)のはじめに、憲法の最終的な審議が完了し、二月一一日憲法発布の式典が挙行された。
全国各地で祝賀会が催され、国民は歓呼をもってこれを迎えた。
憲法全文を通読して、ただ苦笑するのみであったといわれる中江兆民のように、憲法の内容に批判的な意見をもつ人も少なくはなかったが、その声には力がなかった。
憲法発布を絹布の法被と間違えたといわれるような民衆は問題外としても、多年立憲政治の樹立に身命をかけてきた民権派の人々も、やはりこの日を迎えて感激を抑えることができなかったのである。
「緩急をはかり、勢を操って漸進の方向に誘導する」という一〇年前の伊藤の作戦は成功したと見なければならない。
万機献替すること二十年
典憲編成って御前に奏す
眼を泰西に放って得失を明らかにし
心を上世に馳せて精研を極む
(『伊藤博文伝』中巻) |

外人の描いた憲法発布式典
|
憲法発布の日の喜びを、伊藤はこのようにうたった。
たしかに、明治憲法の誕生は伊藤の努力に負うところが大きい。
欧米の憲法理論と、古来の天皇の伝統的権威とをたくみにとけ合わせたところに作者伊藤の苦心があり、一方に民権派を力と策謀をもって抑圧し、一方には保守中正派と妥協し、薩長のバランスを保ちながらみずからは天皇の信任をえ、時勢をあやつってここに導いたところに政治家伊藤の才能があった。
しかし、同時に、このような調合の見事さと、操縦の鮮かさが、果して日本の君主と国民にどれだけの実質的なプラスをもたらしたか、それを審判しうるものが歴史のみであること、これもまた事実である。
参考史料・文献
春畝公追頌会『伊藤博文伝』上・中・下巻
小松緑編『伊藤公全集』一・二・三巻
平塚篤榻『伊藤博文秘録』『続伊藤博文秘録』
稲田正次『明治憲法成立史』上・下巻
大久保利謙「明治一四年の政変」(明治史料研究連絡会編『明治政権の確立過程』所収)
top
****************************************
|