|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6
7 8
9 ハリス年表 クロウ著ハリス伝
第二 ハリスの下田時代
一 渡来の目的
一八五六年八月二十一日(安政三年七月二十一日)に、ハリスはサン・ジャシント号で下田へ到着した。
当時、五十一歳十ヵ月であった。
安政元年の大津波
この伊豆の南端の港は、安政元年七月四日の地震と大津浪の惨害から、まだ完全には立ちなおっていなかった。
そのときの津浪は、人口八千から一万をかぞえていたこの町を一瞬にのみこんでしまった。
大浪が去ったあとには、十四軒の家がのこっていただけだったという。
だから、家々はその後にたてられたもので、まだ木の香も新しく、復興の鑿(ノミ)の音があちこちから聞こえていた。 |

安政の下田の津波――ロシア人のスケッチによる
|
上陸止め宿を拒否
ハリスの来朝は、幕府にとって寝耳に水であった。
下田奉行岡田備後守(忠養=ただやす)は、おどろいて江戸へ急報した。
幕府の命令で、あわてて江戸からもどってきた同僚奉行の井上信濃守(清直=きよなお)と力を合わせて、ハリスを退去させようとした。
先にのべたように、ペリーの条約(神奈川条約)第十一条の英文には、
「この条約調印の日から十八ヵ月の後には、合衆国政府は何時なりとも、下田に居住する領事または代理官を任命することができる。ただし、両国政府のいずれか一方が、この配置を必要と認めた場合にかぎる」
とあった。
ところが、日本文の方には、「両国政府において、拠(よんどころ)なき儀これあり候模様により云々」と書かれていたのである。
つまり、アメリカの使臣の下田駐箚(駐在)の必要は、あらためて両国政府の合議できめるというのであった。
妙な行きちがいであるが、両国がたがいに相手国の言葉を理解せず、オランダ語の媒介で意思を通じあっていたために、訳文上の重大な手違いがあったのに双方とも気づかなかったのである。
ハリスが到着すると同時に、「上陸する」「いや、居住のための上陸はまかりならぬ」で、面倒なことになってしまった。
ハリスは、退去の要求を頑(がん)としてききいれなかった。
「こうした問題の解決は、両国政府間の交渉で行わるべきもので、一総領事である自分の知ったことではない。
自分は大統領の命令できたのだから、その命令がなければ帰るわけにはゆかない」
というのだった。
上陸して玉泉寺に入る
上陸をこばめば、そのまま軍艦で江戸へ行きかねないので、下田奉行も困ってしまった。
そこで、居住の問題は後まわしにして、ひとまず上陸をゆるすことにし、下田在、柿崎村の玉泉寺(ぎょくせんじ、曹洞宗)を仮りの宿所とした。
これは、ペリーの艦隊が下田に寄港したときにアメリカ人の休息所にあてられた寺だった。
安政三年八月五日に、ハリスはヒュースケンとシナ人の従僕五名(一名は後に送還)をしたがえて上陸した。
柿崎
「柿崎は小さい、貧寒な漁村だが、住民の身なりはさっぱりしていて、態度もていねいだ。
世界のあらゆる国で貧乏につきものになっている不潔なところが、すこしも見られない。
彼らの家屋は、必要なだけの清潔をたもっている。
土地は一インチもあまさず開墾されている。
地面は起伏が多く、熔岩の峰、あるいは火山から噴きだされた固い粘土となって聳えたっており、耕作には適しないほど嶮しいのであるが」。(『ハリスの日記』) |
これが、ハリスの上陸第一歩の印象だった。
その夜は、興奮と蚊のためによく眠れなかったという。
|
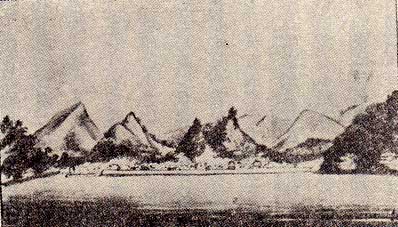
ヒュースケンの描いた下田の遠景
|
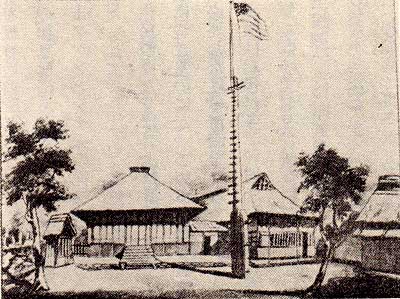
ヒュースケンの描いた下田領事館の図
|
日本における最初の領事館
その翌日、日本における最初の領事館である玉泉寺の前庭に、桿頭(かんとう=ポール)高く星条旗をあげたのである。
この日の午後二時半に、この帝国における“最初の領事旗”を掲揚する。
厳粛な反省――変化の前兆――疑いもなく新しい時代がはじまる。
あえて問う! 日本の真の幸福になるだろうか。
その日の夕方、サン・ジャシント号は無事に任務をはたして、出港した。
ハリスの目的
復興途上の下田は、まだ人家が千戸ばかりで、人口も四〜五千にすぎなかった。
それに、もともと外国の大船を相手にするような港ではなく、付近は山地ばかりで、物資にもとぽしかった。
ハリスは着任して間もなく、下田が開港場として不適当なことに気づいたが、とにかく、この土地を足がかりにして江戸へのぼり、皇帝(エンペラー)(注)の政府と直接の談判をやって、まず日米間に互恵(ごけい)的な通商条約と、従来の条約よりも幅の広い修好条約をむすび、そのあとで世界の各国をこの条約に均霑(きんてん=行渡る)させる、つまり世界にさきがけて日本を名実ともに本当の開国の姿にあらためさせようとするにあった。
(注=当時の西洋人は、将軍を政治上の最高主権者であるエンペラーと考えていた。そして京都の帝(みかど)は、単に宗教上の主権者、すなわち神主の親方ぐらいにしか考えていなかった)
薪水条約の改定
さきに締結されたペリーの和親条約(注)は、日本の開国に先鞭をつけたものではあったが、これは要するに薪水条約・欠乏条約の範囲をです、肝心な通商の規定には少しもふれていなかった。
(注=合衆国の船に薪水(しんすい)・石炭・食糧などの欠乏品を供給するために下田と箱館の二港を開く)
だから、せっかくアメリカの貿易船がはるばる太平洋を越えてやってきても、日本の官憲に追いかえされる始末で、一時はペリー提督の成功を謳歌していたアメリカ人の間にも、貿易のできない条約では意味がないという不平や不満の声がやかましくなっていた。
ところで当時の日本は、資本主義諸国と通商関係をむすんで自由に交際するということは困難な状況にあった。
理由はいろいろあった。
両者の社会構成や制度に根本的な相異があり、貿易を通じて国民の間に浸透する自由主義の風潮は幕府集権下の封建制度の基礎を危うくするおそれがあったし、貿易の利益はみとめても、二百年来「祖法」の二字で徳川幕府の威権を維持してきた関係上、祖法の一つである鎖国政策を根本的に改めること自体が幕府や諸大名にとって重大な問題だったのである。
ぶらかし政策
しかし、お隣のシナが頑固な鎖国政策で阿片(アヘン)戦争をひきおこし、さんざんに敗れた結果、屈服的な五市開港の条約を余儀なくされたことをよく承知していたので、外国と勝ち目のない戦争をすることは、これまた封建的支配の崩壊の原因となることを恐れていた。
そこで、外国との紛争は出来るだけさけて、おんびんな回避策、すなわち、“ぶらかし政策”をとろうというのが、当時の幕府の腹であった。
そこで、ハリスを怒らせず、しかも下田に釘づけにしておくつもりで、幕府はハリスに「邪教伝染これなきよう相心得」させた上で下田駐箚の正式許可をあたえたのであるが、しかし中央との直接の交渉はあくまでも避けて、要求事項については出先機関である下田奉行をして応接にあたらせることにした。
一時のがれの空(カラ)返事で責任のある回答をさけさせ、あくまでも遷延策をとって、ハリスが手を空(むな)しく帰国するようになることを期待したのである。
ハリスは奉行たちの不正直と不誠意をなじって、「日本の役人は地上における最大の嘘つき」であると罵った。
“うそつき”と呼ばれることは、武士にとっては最大の侮辱であった。
彼らは胸中無念に徹しながらも、役目の手前こうした罵声(ばせい)に堪えなければならなかった。
出府を要求
出先機関の属僚を相手にしていたのでは何時までたっても埒(らち)があかないと思ったハリスは、安政三年九月二十七日に手紙を幕府の閣老にあてて送った。
「大統領の親書を日本の皇帝に呈し、あわせて日本の安危に関する重大事件について直接日本政府に知らせるために」 出府(しゅっぷ)、すなわち江戸へ行きたいと申しこんだのである。
この要請にたいして、幕府ではハリスに返書さえもおくらず、下田奉行に命じて口頭でことわらせた。
ハリスは、はげしく抗議した。
和親条約をむすんだ国の使臣の書簡に対し、口頭の返事だけですまそうとするのは合衆国を侮辱するものである。
某国(イギリスを指す)の日本に対する企図を知らせて、おそるべき戦禍から日本を救うためには、ぜひとも早急に出府することが必要であるという意味の手紙を再び閣老あてに送ったが、幕府は、
「所要の件については下田奉行に申し出で、大統領からの書簡は下田奉行に渡すように」
という老中連署の返事を送って、再びハリスの要請をことわってしまった。
しかし幕府としても、こうした一片の返書だけでハリスの要求をおさえることが出来るとは思わなかったので、この上ともに重ねて強請してくる場合には出府許可も止むをえないだろうと観念し始めたのだが、
ハリスの焦燥
それとも知らぬハリスは、容易に事のはこばぬのに焦慮し、その面貌には日増しに苦悩の色がこくなった。
それに、健康のすぐれないのが、なおさら気持を苛(いら)だたせた。
時として、無暗に役人たちに当たりちらすこともあった。
本国政府からは、着任以来一片の音信もなかった。ハリスは国務省の怠慢と無責任さに憤慨したが、その理由が故国の政情の変化によるものではないかと臆測すると、これまた不安で心が暗くなった。
「あれから十八ヵ月以上もたっている。
私をこの土地に孤独のまま捨てておくには、あまりに長い期間である。
私との通信をもっと頻繁にするように、国務省に注文をつける必要がある」。
「私は本国政府へ送りたい重要な情報をもっている――
その情報は、日本とアメリカとの通商に直接の拍車をかけるであろう。
しかるに、来る月も、来る月も、わが政府へそれを通信することができずにいる。
一隻の軍艦もいないことは、日本人に対する私の威力を弱めがちである。
日本人は今まで、恐怖なしには何らの譲歩をなしていない。我々の交渉の将来のいかなる改善も、ただ力の示威があってこそ行われるであろう。
この明らかな閑却は、ここへ来ないアメリカの海軍司令官たちの無頓着や怠惰によるものとは思いたくない。
そこで、私は遅延の原因についてあらゆる想像の虜(とりこ)となっている」(『ハリスの日記』) |
と、彼は『日記』に、憤懣(ふんまん)やら不安やらの思いをこう書きつけた。
二 下田の風土と生活 top
こうした傷心の日々を慰めてくれたのは、この土地の美しい景色と、「これまでに経験したことのないような」温和な気候とてあった。
下田の住民
ハリスは素朴な下田の住民がとても好きだった。
ことに、「耕して天に至る」式の、高い、せまい段々畑でせっせと立ち働いている農民の姿は、世界のどこの人間よりも勤勉に見えた。彼はこの人たちを、「喜望峰以東の最も優れた人民」と評した。
「この土他の住民は、いずれも豊かではなく、ただ生活するだけで精いっぱいで、装飾的なものに目をむける余裕がない。
それでも、楽しく暮らしており、食べたいだけは食べ、着物にも困っていない。
家も清潔で日当たりがよいし、気持もよい。
世界のいかなる土地においても、労働者の社会の中で下田におけるよりもよい生活を送っているところは他にあるまい。」(『ハリスの日記』) |
住民たちが自分に対して無言の好意を示してくれていることが、ハリスにはよくわかった。
この土地の住民は、明らかに外国人との交際を望んでいる。
ただ、専制的な支配と苛酷な法律に対して抱いている恐怖の念が、あからさまな表現を封じているだけだと思った。
領事館の環境
上陸したのは秋の初めだったので、草ぶかい寺院の境内では夜ふけて虫の声がやかましかった。
コオロギの声は、速く走る豆機関車のように奇妙にきこえたという。
以前は寺の本堂だった薄暗い大広間の片すみに蝙蝠(コウモリ)がぶらさかっていたし、大きな髑髏蛛(どくろぐも)も這いまわっていた。
鼠があまりたくさん走りまわるので、よく寝つかれなかったという。
こうした寂しい環境に、いくぶんでも潤(うるお)いをもたせるために、ハリスは玉泉寺へ入ると直ぐに古い鐘楼を鳩舎に改造させて、四番(四つがい)の鳩を飼った。
だが、これらは一夜のうちに猫に噛まれてしまったので、江戸から六羽の鳩を至急に取りよせてもらった。
また、カナリヤや鷽(うそ=雀科の鳥)などの鳴禽(めいきん)類や、それに鶏なども飼って自分で世話をした。
領事館の人数は、ハリスとヒュースケンのほかに、召使頭・料理人・その助手・洗濯夫(以上シナ人)・少年二人(助蔵・滝蔵)・水運搬人・掃除夫・園丁・馬丁の都合十名だった。
日本人の中には通勤の者もあった。このうち、少年の助蔵と滝蔵はハリスに特に可愛がられて、後年の江戸出府のときには行列の駕籠わきにつきそった。
番士の撤去を要求
これらのほかに、ハリスの着任以来数名の役人(番士)が館内に詰めきって、領事館の警護にあたった。
ハリスは、自分を囚人同様に監視するためのものだと抗議して、しきりに彼らの退去をもとめたので、これらの者は四ヵ月ほどで引きあげてしまった。
自分に危害を加えるような者はこの土地には一人もいないという信念をもっていたからであったが、幸いに下田滞在中には一度もそうした不祥事はおこらなかった。
根が潔癖な人で、それに何事にも几帳面な性質だった。
朝起きると、かならず冷水をあびて身体をきよめた。
これは酷寒の季節になっても止めなかったので、周囲の人々はおどろいた。
食料や酒類(ハリス自身は禁酒していた)は当分の生活に差支えないほどのものを本国から持ってきていたが、それにしても新鮮な野茱や肉類の入手は必要だった。 |

玉泉寺境内の警備――ロシア人のスケッチによる
|
野菜の方は役人に厳談して、必要なだけの畠をかりうけ、自作することにした。
本国から持ってきた種子をいろいろ播いたが、芽が出なかったので、がっかりした。
日本人の世話で馬鈴薯・玉蜀黍(とうもろこし)・胡瓜(きゅうり)・茄子(なす)なとを作ったが、こうした野菜作りは彼の健康と慰藉(いしゃ=なぐさめ)に大いに役だったようだ。
嗜好物
日本の果物は好んで食べた。ハリスの注文に、役人は無い、無いと言いながらも、ときどき葡萄・柿・梨・栗・蜜柑など、季節の果物を持ってきてはハリスを喜ばせ、その代わりに西洋の珍酒などをご馳走になるのであった。
四つ足の動物を食べない国のこととて、生鮮な肉の入手にはほとほと困ったが、それでも日本人が天城山中でとれた猪や鹿・野兎・野鳥などの肉を時々とどけてくれるので助かった。
ことに猪の肉はたいへん気にいったようだ。
「日本人は猪の肉を、今まで三度私にとどげてくれた。
たいへん軟らかく、汁気があって、すぐれた芳香をもち、美味な仔牛の肉と豚の腰肉の中間あたりの味がする。
寒い季節の間十分に供給してくれる約束をしてもらった。
それは私の家事に大きな助けとなるであろう」
と『日記』に書いている。
付近の散歩
神奈川条約の規定により、七里外の遊歩は禁じられていたが、それでも付近の景色は豊かであった。
ハリスはこのあたりの自然を愛して、よく付近の海岸や山野をあるきまわったり、馬で駆けまわったりした。
これは、健康のためでもあり、風景探勝のためでもあったが、また、この地方の動植物や住民の生態を知りたいという欲望からでもあった。
動物にかけては、後にパリの動物学協会の会員にえらばれたくらいであったが、植物の知識にかけても該博(がいはく=博学)だった。
路傍の一木一草に目をとめては、それぞれの名称をあてたり、これまで見たものと比較したりした。
そして、せっかく植物の宝庫に足を入れながら、植物学の知識が足らなかったと言って、いつも悔んでいた。
森の中で、ふと一株の矢車菊を見つけて、急に故国のことを想いだし、しばし郷愁にかられて足を留めたこともあった。
ある日の散歩で、ハリスは下田の谷地を松崎の方へ上ってゆき、その辺の温泉をおとずれた。
硫黄の嗅いが鼻をついた。
ふと、浴槽をのぞくと、一人の女が子供をつれて湯にひたっていた。
女は少しの不安気心なく、ハリスを見て「オハヨー」と言った
日本人の淫習
ハリスは、日本人が風呂好きな国民であることを知ったが、同時に男女混浴の風習には眉をひそめた。
「労働者はみんな、男女・老若とも同じ風呂にはいり、全裸になって身体をあらう。
私は、何事にも間違いのない国民が、どうしてこのように品(ひん)の悪いことをするのか、判断に苦しむ」といっている。
そして、風呂のことはとにかく、日本人のような礼儀作法のやかましい国民の中に、信じがたいほどの淫(みだ)らな風習のあるのは、どうしたことかと訝(いぶか)る。
ヒュースケン君が日本の風習について奇妙な例を報告する。
今日、彼は相当な身分の日本人の家へいった。
その日本人は親しい態度で迎え、茶などをご馳走した。
それから、その日本人は色々なもの――人体の各部分についての英語の名称をききはじめた。
そこには、その男の母親や妻女や娘もいた。
いろいろな物についての多くの名称をたずねてから、その男は着物の前をひらき、陰部を手に持って――女たちが見ているところで各部分の英語の名称をきいたという。(『ハリスの日記』) |
世界のどの国の女性よりも内気(うちき)で、控え目で、はずかしがりやの日本の女が、風習とは言いながら、こうしたことを恥ずかしがらないのは、どうしたことか。
西洋人、しかも厳格なクリスチャンの家庭で育ってきたハリスには、これは信じがたいことであった。
こうしたことは。日本が僧侶や神官、寺院や神社の非常に多い国でありながら、本当の意味の宗教がないからではなかろうかと、ハリスは考える。
ことに、この国の上層階級の人々は、実際に皆、無神論者であると。
戒律の生活
ハリスはキリスト教の戒律をまもって酒を飲まなかったし、煙草も健康に悪いので、やめてしまっていた。
日曜日には、安息日の戒律をまもり、訪問者の面会もことわって、静かに一日を祈祷と瞑想ですごした。
日本では、まだキリスト教の禁令は解かれていなかった。
いずれは、この国でもキリスト教の行われる時代がくるだろうが、それまでには、どれだけの歳月がかかることかと、そんなことを『日記』に書いている。
健康状態
彼は、長い間太平洋の波濤を股(また)にかけて往来し、東洋の未開の国々を方々歩きまわってきた人であるから、もともと身体は頑健で、健康には人一倍の自信があったにちがいない。
ところが、日本へきてからの身体の調子はまことにミゼラブブルであった。
それは、彼の『日記』の方々から知ることができる。
一八五七年 一月八日 木曜日
身体がひどく悪い。
一八五七年 一月十五日 木曜日
病気。肉がたえず痩せてゆく。私は去年の四月二日にペナンを出発したのだが、今はその当時よりも四十ポンド(20kg)も少ない。
一八五七年 三月十五日 日曜日
七年の間、今日ほど身体の具合の悪いことはなかった。多量の鮮血を吐いた(訳注、胃病による、吐血と思われる)
一八五七年 四月十八日 土曜日
いつも身体がだるい。私は、あのフリゲート艦が到着して、診察してくれることを望んでいる。
一八五七年 四月三十日 木曜日
私の健康は、きわめて不満足な状態にある。私には、消化不良に起因する胃酸過多を治すことは不可能である。
私は食物をパンと米、それに当地で入手する屠肉だけにとどめ、バター・油・果物、それに馬鈴薯以外の野菜をすべて断(た)っている。
それでも私の不健康はつづき、相変わらず痩せる一方である。
一八五七年 五月十一日 月曜日
私はつとめて運動をするようにしているが、私の肝臓にはききめがない。
それが心配のたねである。良医の乗っている外国船が当地にくるのを鶴首している。(『ハリスの日記』) |
旺盛な気力
こんな具合で、病気には悩みながらも、いざ仕事となると、いつも別人のように旺盛な、たくましい精力ぶりを発揮した。
ことに、役人たちを前にした談判の席では、いつも相手はハリスの気力と頑張りに辟易(へきえき)しなければならなかったのである。
さて、再び外交の本舞台へ立ちもどろう。
三 下田協約 top
最初の出府(しゅっぷ)要求は、すでに述べたように、下田奉行の口頭の返事で拒絶され、二度目の要求は閣老連署の返書で断わられてしまった。
三度目の出府要求
ハリスは閣老の返書を不満として、安政四年三月七日に三度目の要求書を提出した。
これは、「大統領の親書を下田奉行をもって受け取らせようとするのは、合衆国の元首を軽視するものである。
すべからく態度をあらためて、ぜひとも出府を許容してほしい」という強硬な抗議書だった。
そこで幕府も、ハリスの出府の意思を抑えがたいことを知り、「出府を許すことに決定はしたが、準備の都合もあるので、すぐというわけにはゆかぬ」と、宥(なだ)めにかかった。
それと同時に幕府は、これまでハリスが下田奉行に要求していた件々(貨幣交換の問題、下田と箱館におけるアメリカ人の居住権、補給港としての長崎の開港、領事の旅行権などをふくむ七ヵ条)については、従来のたぶらかし的な態度をあらためて、誠意をもって交渉にあたるように下田奉行に訓令した。
これは、なるべく局地的交渉で事をすませて、江戸出府を食いとめようという魂胆から出たのであったが、ハリスとしては、出府は出府、局地的交渉は局地的交渉と割り切って、二兎を追う作戦にでたのである。
これについて、両国全権の間で数回の交渉がおこなわれた。
下田協約の調印
日本側はハリスの要求を全面的に容れ、安政四年五月二十六日に全権委員たる下田奉行井上信濃守(時万=岡田出羽守の後任者)とハリスとの間に、九ヵ条からなる条約が下田の御用所(ごようしょ)で調印された。
これが、いわゆる「下田協約」The Convention of Shimodaである。
これはペリーの和親条約(神奈川条約)を改訂して、いくぶん間口を広めたものにすぎなかったのだが、それでもハリス外交の一歩前進であり、安政五年の大条約の先駆けをなしたものであった。
協約文書
規定書和文(注=安政四年五月二十六日調印、同年閏五月五日批准書交換)
帝国日本に於て、アメリカ合衆国人民の交りを、猶所置せんために、全権下田奉行井上信濃守・中村出羽守と、合衆国のコンシュル・ゼネラール・エキセルレンシー・トウンセント・ハリスと、各政府の全権を持て、可否を評議し、約定する条々次の如し。
第一ヶ条
日本国肥前長崎の港を、アメリカ船のために開き、其地に於て、其船の破損を繕(つくろ)い、薪水・食料或は欠乏の品を給し、石炭あらば、又それをも渡すべし。
第二ヶ条
下田並箱館の港に来るアメリカ船必用の品、日本に於て得がたき分を弁ぜむために、アメリカ人をこの二港に置き、且合衆国の下官吏を箱館の港に置くことを免許す。
但、此箇条は、日本の安政五午(うま)年六月中旬、合衆国一八五八年七月四日より施すべし。
第三ヶ条
アメリカ人持来るところの貨幣を計算する時は、日本金或は銀一分を、日本分銅の正しきを以て、金は金、銀は銀と秤(しょう)し、アメリカ貨幣の量目を定め、然して後、吹替入費のため、六分だけの余分を日本人に渡すべし。
第四ヶ条
日本人がアメリカ人に対し法を犯す時は、日本の法度(はっと)を以て日本司人が罰し、アメリカ人が日本人へ対し法を犯す時は、アメリカの法度をもって、コンシュル・ゼネラール或はコンシュルが罰すべし。
第五ヶ条
長崎・下田・箱館の港において、アメリカ船の破損を繕い、又は買うところの諸欠乏品代等は、金或は銀の貨幣をもって價(つぐな)うべし。若し金銀とも所持せざる時は、品物を以て弁ずべし。
第六ヶ条
合衆国のエキセルレンシー・コンシュル・ゼネラールは、七里堺外に出づべき権あることを、日本政府に於て弁知せり。然りといへども、難船等切迫の場合にあらざれば、其権を用うるを延す事を、下田奉行望めり。此に於て、コンシュル・ゼネラール承諾せり。
第七ヶ条
商人より品物を直買にする事は、エキセルレンシー・コンシュル・ゼネラー並びに其館内に在るものに限り差免(さしめん)じ、尤も其用弁のために、銀或は銅銭を渡すべし。
第八ヶ条
下田奉行は、イギリス語を知らず、合衆国のエキセルレンシー・コンシュル・ゼネラールは、日本語を知らず、故に真義は、条々の蘭語訳文を用うべし。
第九ヶ条
前ヶ条の内第二ヶ条は、記する処の日より、其余は、各約せる日より行うべし。
右の条々日本安政四已(み)年五月二六日、アメリカ合衆国一八五七年六月一七日、下田御用所において、両国の全権調印せしむるもの也。
井上信濃守 花押
中村出羽守 花押 |
日米通貨の比率問題
前記の協約書の第三条(日米貨幣の比率)については、ハリスが渡米以来談判に談判を重ねた問題で、経済史の上からも重要な箇条であるから、ここに特記して説明する必要がある。
安政元年五月、ペリー提督の艦隊が下田に寄港したときの談判で、日本側は日米貨幣の比率を、アメリカの銀貨一ドルについて銀十六匁(ほほ一分金一つに相当)、あるいは銭(ぜに)千六百文と定めた。
ところが、アメリカ側では検査の結果、一ドルの銀の目方は一分(ぶ)銀(当時一分金の代わりに通用していた)の約三倍あることを知ったので、不審を訊(ただ)したが、日本側は、日本では貨幣の価値は政府の極印(ごくいん)次第できまるのだから、外国のように目方の比較では論じられないと弁解した。
もっとも、当時の日本の貨幣制度は鎖国の立場で行われ、品質や量目も幕府が勝手に国民に押しつけていたのであるが、相手が外国人となると、そんな無茶なことは許されない。
しかし、アメリカ側では差し当たって大した金額でもないので、この問題の解決を後日にのこすことにし、その割合で支払いをすませて立ち去った。
ハリスの主張
ハリスは、本国政府の命令もあり、着任早々この問題で奉行と談判をかさねた。
ハリスの主張は、一ドル銀貨は目方からいって日本の一分(ぷ)銀三個、あるいは銭(ぜに)四千八百文(もん)に換算されるべきであり、従来の比率では日本が二倍も不当に利することになると言うのであった。
奉行も、これには抗弁の言葉がなかった。
幕府に指示を仰ぎ、回答の引きのばしに汲々たる有様であったが、ついにハリスの主張を容れて、アメリカ人の持参した貨幣は、金貨は日本の金貨をもって、銀貨は日本の銀貨をもって、重量対重量で計算することを認め、その代わりにアメリカの貨幣を日本の貨幣に改鋳する費用(吹替入費)として、ある程度の割引をもとめた。
ハリスもこれを承諾したが、日本側は六パーセントの割引を主張したのに対し、ハリスは五パーセントを固持して譲らず、なお数回の討議をへたのちに、ハリスの譲歩によって問題の解決を見るにいたった。
なお、安政五年六月十九日に調印された日米修好通商条約の第五条(後文に掲出)では、日本側からの申し出によって改鋳費(吹替入費)は出さないでよいことになり、大いにハリスを喜ばせた。
四 「唐人お吉」の説 top
唐人お吉の登場
人口に膾灸(じんこうにかいしゃ=世間に知れ渡る)しているお吉という女性が登場したのは、この頃(下田協約調印の直前)である。
前述と重復するが、ハリスが日本へきた使命というのは、ペリー提督がむすんだ「日米和親条約」の規定によって領事としての職務を執行する一方、この条約を改訂して「通商条約」をむすぶための全権委員の資格をも兼ねたものであった。
しかし、当時の日本の支配階級にとっては、ハリスの渡来は迷惑千万であった。
既成の条約にしたがって渋々ながら上陸はゆるしたものの、新規の条約は一切みとめないことにし、直接の交渉をあくまでさけて、出先機関である下田奉行に命じて、程よくあしらわさせていた。
幕府の考えがこんなふうだったから、下田奉行の態度に誠意のあるはずはなかった。
ハリスは、いつまでたっても責任のある返事がえられないので、こんな役人どもを相手に日を送るよりも、江戸へいって直接幕府の高官と談判した方がよいと考え、再三閣老へ手紙を送って江戸出府の許容をせまった。
奉行の懐柔策
飽くまでこれを拒めば、ハリスは軍艦来航の機会をとらえて、これに乗って江戸へ押しかけて来るおそれがあった。
そこで幕府は下田奉行に対し、ハリスを下田に引きとめておくために、従来の態度をあらためて懇切に応対するように訓令した。
奉行の岡田備後守はハリスの気勢をやわらげようとする下心から、同僚の井上信濃守と謀(はか)ってハリスを自邸にまねき、大いに歓待した。
備後守は酔いにまぎらせ、酒をのまないハリスに向かって女を周旋しようと言いだした。
副奉行(支配組頭)の一人は、もし好きな女があったら、それを世話するのは自分の役目であると言った。
しかしハリスは、「東洋流の蓄妾制度ほど理解しがたいものはない」という考えから別段相手にならなかった。
その後、貨幣の比率問題や出府問題などの交渉がうまくゆかなかったので、ハリスは業(ごう)をにやし、この上は便船を待って江戸へ急行するだけだと言いはなって、奉行との交渉をうち切ってしまった。
もし、そんなことになれば、下田奉行は職責上免職か、あるいは切腹をまぬがれない。
ところで、ハリスの激しい気魄(きはく)にひきかえて、その健康状態は前にも述べたように、まことに惨めなものだった。
痼疾(こしつ=持病)の胃病が昂じて、ついには吐血するようになった。
身体は痩(や)せる一方で、病床につくことも多かった。
万一の場合を考えて、秘書の年若いヒュースケンに後事を託するという有様であった。
病気看護
ハリスの病床の世話をしていたヒュースケンは、たまたま出入りの役人に看護婦の周旋をたのんだ。
同時に、自分もこれに便乗して侍女を得ようとした。
西洋流の看護婦について皆目(かいもく)知識のなかった役人たちは、これを情事と解し、待っていたとばかりに、ハリスとヒュースケンのために、閨房(けいぼう)の秘事の相手をつとめる女性を下田の町家からさがしもとめた。
その頃は、女は異人に接すると生血まで吸いとられるという俗説があったので、異人相手の女を手に入れるのは困難だったが、ようやくのことで、
お吉とお福
ハリスにはお吉、ヒュースケンにはお福という女を見つけることができた。
ハリスに配された“お吉”(斎藤きち)は、老母の“きわ”と共に、下田に寄港する回船の船頭の着衣の洗濯などを表向きの稼業とし、その実は船頭や船大工などの間に媚(こび)をひさいでいた貧しい女であったが、役人の説得と、二十五両という大枚の支度金につられて、総領事館であった玉泉寺の門をくぐった。
その日時についてははっきりしないが、関係文書の日付から見て、安政四年五月二十四日前後のことと思われる。
ハリスは極端なまでに潔癖な性質だったので、お吉が酒色にすさんだ淪落(りんらく=だらく)の女であることを感知し、また脂粉(しふん)にかくされた腫物を見て、非常に不潔感をいだき、これを傍へ近づけなかった。
そして、腫物の治療を口実に、わずか三日で家へ帰してしまった。
お吉の解雇
その後、お吉の方から、腫物は全快したから再勤させてくれと願いでたが、ハリスは取りあわず、支度金をそのままにして解雇を申しわたした。
お吉の方からは、一度異人館の門をくぐった以上は、世間にうとまれ、今後の洗濯稼業にもさしつかえるとの理由で、
「なにとぞ格別の御仁恵(ごじんけい)を以て、御慈悲の御沙汰を懇願」
し、慰藉金をもらいたいという歎願書を七月十日付でさし出したので、ハリスは、八月までの定めの給金に相当する三十両の金を解雇手当としてあたえた。
お吉の方から出したその金の受取証文の日付が八月二十二日となっている。
| これらの事実は、下田の玉泉寺の先代住職、故村上文機師が昭和八年に下田役場保管の古文書類の中から発見した証文や歎願書などによって明らかとなった。 |
ハリスは役人の不信な行為に憤慨したが、問題にするのはかえって自分の不名誉となるので、これを不問にしてすませた。
そして、むしろ、これが機縁で、孤独にたえかね、ややもすれば帰心にかられている若いヒュースケンに、気に入りのお福(経師屋(きょうじや)平吉の娘ふく)を配することができたことを喜び、「オフクメ、オフクメ」とよんで、伜(せがれ)の嫁のように可愛がったといわれる。
こんなことから、若干の風説もあったようだが、お吉をハリスの妾(めかけ)と断定した資料は一つもない。
この種の風説の記録に、「亜人下田滞留中囲媚風説」(『嘉永明治年間録』)、「米国総領事出府道中井府甲動静に就て」(『高麗環雑記』)中の一節、などがあるが、いずれも二〜三行程度のもので、特に風説とことわっている。
「アメリカ国官吏等召仕候女の儀に付申上候書付」は、下田奉行から老中に宛てた上申書(公文)であるが、これには明らかに、「病気看護」と書かれている。 |
ハリスとお吉の関係が今日のように言いはやされるようになったのは、ずっと後世になってからのことで、昭和三年以来作家の十一谷義三郎があの有名な、いわゆる「唐人お吉」ものの小説数篇を、「お吉」の研究家村松春水蒐集の史料にもとづくと袮して、発表してからのことである。
十一谷氏は、下田の郷土雑誌『黒船』を見てから、村松氏のお吉研究に興味をもったのであった。
これらの小説は、当時の沈滞をきわめていたわが国の文壇にエキゾチックな生新味を投じたものとして歓迎され、ついで、当時のアンチ・アメリカニズムと頽廃的ナショナリズムの風潮のなかに不況の打開を見いだそうとした興行資本家たちによって、演劇・映画・レコードなどにとり入れられた。
しかし、村松氏の研究なるものは、実は史実のせんさくを目的としたものではなかった。
同氏は下田で医業をいとなんでいたが、若いころから小説家を志望していた。「唐人お吉」の研究なるものも、実は小説の材料として書きためておいたものであった。
たまたま十一谷氏がそれを借覧するや、史実と銘うって取材し、前記の小説を書いた。
また、『実話唐人お吉』という標題の本を村松氏の名前で出版したが、「実話とは、十一谷氏が勝手にうたった文句で、自分としては迷惑に思っている」と、村松氏は生前にそう述懐している。
小説のお吉
とにかく、史料の発見によって、いわゆる「唐人お吉」は史実の座から引きおろされたが、それにしても「小説」や映画などのお吉は、春雨にうたれて散ってゆく椿の花にも似て、まことに哀艶(あいえん)きわまりない。
これは、幕末の世情に思いをはせ、南国の情緒を愛する世間の人々の心に深く刻みこまれているが、それはいわゆる「伝説」であって、我々の問題としている「歴史」とは、また別なものである。
五 出府問題の解決 top
ハリスは下田協約の締結によって条約改訂の目的の一端を果たしたが、これは前にも言ったようにペリー提督の「薪水条約」を一歩進めただけのものに過ぎない。
彼の本来の使命と抱負は、そんな生易しいものではなかったのである。
ハリスの日本開国感
ハリスの観察によれば、日本は東洋で最も統一的な政府と優秀な民族とを有している国家である。
しかし残念ながら、歴史的な理由によって外国との交際をよろこばず、通商関係を頑固に拒(こば)んできている。
ところで、蒸気機関の出現による東西交通の発達と、西洋資本主義の必然の趨勢(すうせい)として、日本の鎖国を打破し、これを国際市場の一環として開放することは、十九世紀の世界外交の最大の課題の一つとなってきている。
しかし、このためには、シナに向かってやったと同様に大艦隊を差しかけて日本の政府を威嚇するか、戦争をしかけて屈服させるかしなければ、目的は達せられないのではないかと思われていた。
ハリスはこの世界的な課題にいどみ、他の資本主義諸国にさきがけて、しかも平和的な外交手段でそれをやってのけようと考えていたのである。
同時に、ハリスはこう考える。正常な国家間の通商関係は、国家相互の友愛と信頼によってのみ結ばれ、相互の間に富と繁栄とをもたらすものでなげればならない。
このような貿易の正道を無視して、シナに阿片と戦争とを持ちこみ、戦果として貿易をかちとったアングロサクソン流の政策を、ハリスは宗教的感情とヒューマニティの立場から憎悪していた。
西洋資本主義諸国の東洋市場開拓の歴史は、イギリス人の犯した罪悪行為でけがされたと思った。
阿片の禁輸を説く
彼は、ひ弱い日本を貪欲(どんよく)な「阿片商人」の手からまもるために、阿片の禁輸を考えていたし、阿片を入手したシナ人召使を叱責して、これを取上げ、またシナにある取引の商館に対して阿片を送りこまないように頼みこんだ(注)。(注=安政五年の「日米修好通商条約」では、ハリスは特に阿片禁輸の一項をもうけた。東洋諸国につきものの「阿片亡国」から日本をまもろうとしたこの事実を銘記する必要がある)。
時あたかも、イギリスとフランスは「アロー号事件」をきっかけに連合艦隊を広東(カントン)へおくりこみ、シナ市場の拡大をはかって第二次の対シナ戦争をはじめていた。
そして、イギリスの対シナ政策の本拠であった香港の総督ボウリングは、この戦争がおわり次第、戦勝の余威をかって日本へ迫まり、武力をもって通商を強要するであろうと自ら公言していた。
イギリスの対日企図
このイギリスの企図は、日本の運命にかかわる重大問題であったばかりでなく、新興国として東洋へ進出してきたアメリカ合衆国の貿易にとっても脅威であった。
太平洋航路によるアメリカの東洋貿易は、その地理的条件のために、日本を中継国として確保する必要があった。
換言すれば、日本と協力関係をむすんで、日本を他国、とくに競争相手であるイギリスやロシアの専有的支配からまもることが、アメリカの東洋における貿易権益をまもる道でもあったのである。
ハリス外交の眼目
だから、ハリス外交の主眼とするところは、他国の日本に対する独専的支配勢力を防ぐことにあったのだが、また、その外交の機微(きび)とするところは、他国による眼前の脅威を利用して頑迷な日本の支配者を覚醒させ、完全な開国、すなわち国際貿易断行の急務であることを彼らに悟らせるにあったのである。
「平和の使者として来た一人の人間の、公正にして、妥当な要求をききいれるか。武力による不当な圧迫に屈するか。
世界の情勢は日本の通商開国を避げがたいものにしている。
問題は今や、いかなる形でこれを行なうかにある」と説いてまたも強引に出府問題をもちだしたのである。
またも出府を要求
日本側では、下田協約の締結によって出府問題は当分立ち消えになると思っていたから、この矢つぎばやの要求に全く期待をうらぎられた恰好だった。
下田奉行は茫然自失(ぼうぜんじしつ)の体(てい)で、止むなくこれを幕府に報告した。
しかし、ハリスに下田駐箚をゆるしたことさえ、徳川斉昭(なりあき=水戸)一派の諸大名の烈しい反対を招いていたこととて、これを将軍の膝元へよんで条約を議するなどということは、攘夷論者の反感を増大して、内乱を惹(ひ)きおこす不安さえもあった。
そこで幕府は、ハリスの出府の不可避を観念して具体的な凖備に着手するとともに、一方ではできるだけその時期をのばして、反対派の説得に当たることになった。
取りあえずハリスにぱ出府許容の決定を伝えたのであるが、しかし時期の明示がなされなかったので、ハリスはこれを日本の役人の常套(じょうとう)的な欺瞞(ぎまん)であるといって聞きいれなかった。
砲艦ポーツマス号の下田に入港
その頃である。
ハリスの日本上陸からちょうど一年をへた安政四年七月二十日に、アメリカの砲艦ポーツマス号が下田に入港した。
絶えて久しく見ることのなかった故国の船影を、ハリスが狂喜して迎えたことは怪しむに足りない。
「この艦の訪問は、私をはげしい興奮に投げこんでいるが、それはよく想像されよう。私は号砲の発射が艦の接近を知らせてから、三時間と連続した眠りをとっていない」と日記に書いていることからも、それが知られる。
この砲艦の入港は、ハリスに外交上の飛躍の好機をあたえた。
下田奉行は幕府に急信をとばせた。ハリスが「龍の雲を得た勢で」この軍艦にのって江戸へ直航するおそれのあることを報じ、それを防ぐためには、速かに出府の期日を通告する必要があることを進言して、幕府の決断をうながしたのである。
出府許容に決定
そこで幕府は直ちに三家・諸大名を営中に集めて、「使節」の礼をもってハリスに出府・登城・謁見を許すことになった旨の将軍の内意を達したのである。
これより先に、幕府の顧問格である溜間(たまりのま)詰の諸大名は斉昭一派の反対説を支持してアメリカ国官吏の強請に屈して出府を許可するのは国辱的処置だとの意見書を提出していたのであるが、時の老中筆頭(ひっとう)兼外国掛(首相兼外相に相当)堀田備中守(正睦=まさよし)は、最早これらの反対に頓着することなく、将軍の裁可を得て、これを正式に公表した。
この堀田は佐倉十一万石の城主で、大名の中では最も外国の事情に通じていた人物であった。
もともと他の諸大名のように開国通商を拒否するものではなかったが、ただ、事が重大なので容易に踏みきれないでいたのである。
堀田の決断には、海防(外交)掛の進歩派の連中の強い献言が大いにあずかって力があった。
ことに目付(めつけ)の岩瀬肥後守(忠震=ただなり)は当時最も進歩的な能吏として知られていたが、下田でハリスに接したこともあり、この際むしろハリスの意を迎えて積極的に開国貿易策をとるべきであると主張して、閣老たちの尻をたたいていた。
また井上は、ハリスの人格に傾到して、何時しかその「親友」となっていたのである。
ハリスの出府の日取りが決定した。
いよいよ、その抱懐する「十九世紀最大の外交手腕」をふるうため、確固たる信念と抱負のもとに、江戸訪問の途につくことになった。
これは、日本の歴史に新しいページをはじめる、最も重大な事件であった。
時に五十三歳。彼は、「神よ。私の残りすくない生命を、有用に、そして立派に使用せしめたまえ」と念じながら、晴れの出発の日を待ったのである。
top
****************************************
|

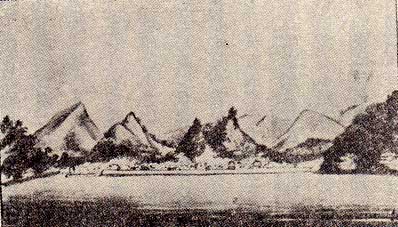
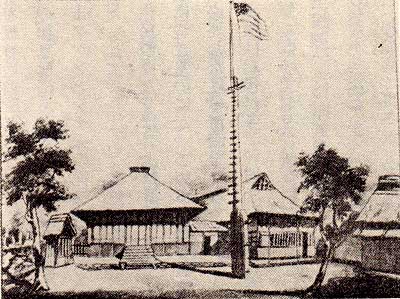



 ”
”