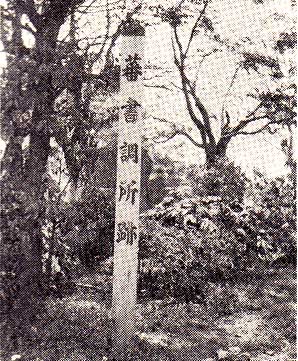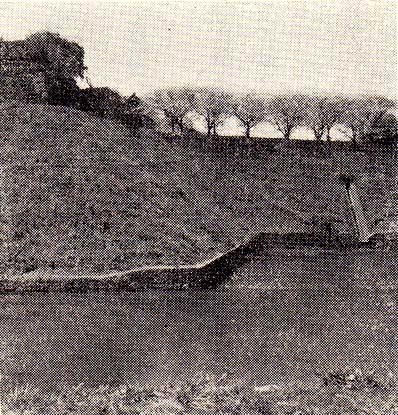|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7 8
9 ハリス年表 クロウ著ハリス伝
第六 条約談判のいきさつ
一 第一回談判
全権委任状の提示
堀田訪問の二日後に、蕃書調所の一室で両者の委任状提示が行われた。
日本側の出席者は井上清直・岩瀬忠震(ただなり)の両全権と若菜三男三郎、書記二名。
ハリスは礼服を着用し、ヒュースケンを従えて、この席にのぞんだ。
両者は、起立したまま、たがいにお辞儀をした。
ついでハリスは、全権委任状をヒュースケンに手渡し、ヒュースケンはそれを井上に渡した。
井上は、大統領の署名をたしかめてから、岩瀬へまわし、岩瀬もそれを確めてからヒュースケンに返し、ヒュースケンはそれをハリスに返した。
ついで、日本側の委任状がハリスに渡され、ハリスはエンペラー(将軍)の印と署名を確めてから、それを返した。
委任状の提示がすむと、ハリスは自分の起草した条約草案のオランダ訳を日本側に手交した。
日本側は、それを翻訳して内容を検討するのに数日を要する旨をつげた。
第一回談判
こうして、安政四年十二月十一日(新暦一月二十五日)に、いよいよ第一回の談判が開始された。
場所はやはり蕃書調所の一室。午後の二時に両国の全権が顔を合わせた。
この談判で、日本側は一応ハリスの要求を容れた上で、その内容を出来るだけ狭いものにしようとした。
これは幕府の対外的な根本政策で、そうすることによって一応相手国を宥(なだ)めて戦争の回避をはかり、他方国内の条約反対論者の怒りを最少限度に食いとめようとするものだった。
井上・岩瀬の両全権は、この趣旨に従ってハリスと折衝するように閣老たちから厳命されていたのである。
ハリスは相手の胡魔化(ごまか)し的な態度を激しく非難した。
冒頭から、こうしたことで論争が繰りひろげられた。
『ハリスの日記』から、それを見ると、 |
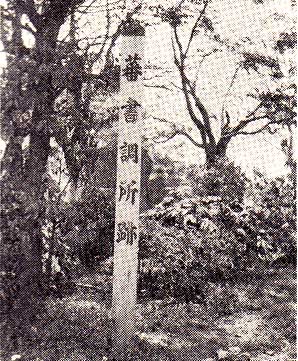
番所調所の跡(九段坂下)
|
日本側の主張
条約の前文は承認され、また、公使と領事を迎えることに同意するという限りでは、第一条も承認された。
しかし、彼らは、公使の居住を神奈川と川崎の間に局限して、用務のある場合だけ江戸へくることにし、公使あるいは領事は、実際の用務を帯びる場合を除いては、日本の如何なる場所にも旅行させないようにすることを希望した。
彼らは、こう言いはじめた。
我々は、貴下が我々にあたえた条約の草案を注意ぶかく検討した。
日本は国がせまいので、三港以上は開かぬことに決めた。
下田は閉鎖して、その代わりに、もっと大きな一港を提供することになろう。
ペリー提督に港を開いたことは大きな譲歩で、それは大きな困難をおかして行なったものである。
下田の代わりに、彼らは神奈川・横浜を申し出た。
そして、大名全部が貿易の結果について満足するようになってから、他の港を開くことにしよう。
貿易は、オランダやロシアとの条約の規定通りに行なわるべきこと。
アメリカ人の日本における旅行は許すわけにはゆかぬし、厳重な制限をうけなければならないと。
ハリスの反駁
私は、こう反駁(はんぱく)した。
神奈川条約の第九条によれば、他の国に許された事柄は直ちにアメリカ人にも適用される。
それゆえに、なんら条約の規定を要しない。
ロシア・オランダの両条約について言えば、それらの条約は、それらの締結にしたがったあらゆる関係者にとって不面目なものであり、貿易に関するかぎり、それらの文書は、それらの書かれた用紙にも値しない。
もし、私がこのような条項に署名するならば、大統領は私に不名誉な召喚を命ずるであろうと。
公使を江戸の居住、あるいは公使の好きな場所から閉めだす提議は、きわめて無礼である。公使の迎接にこのような条件をつけるよりは、公使の迎接を拒否する方が遙かによかろう。
公使と領事は、国際法の下においてかかる人々の享受するあらゆる権利を持たなければならない。
私は、それらの権利以上の何ものをも求めないが、それ以下のものを承知することはできないと。
彼らは、「日本は二百年以上も鎖国されていたので、日本国民は貴下の提言するような大変革に対する用意がない。
日本国民は漸(ぜん=徐々に)を追って導かれなければならない。
国民が貴下を一層よく知るようになったら、その時には、我々は一層自由に行動することができる」などという陳腐(ちんぷ)な議論を繰返した。
私は、諸君の提出するような規定の下においては、、貿易は不可能であって、アメリカ人は五十年間日本に滞在しても、これ以上に親睦の方向にむかって進行ことはなかろうし、こうした事情の下に交際すれば、偏見を去るどころか、それを増大するであろう。
なぜなれば、日本人は、彼らがオランダ人を蔑視(べっし)してきたと同じ程度に、アメリカ人を軽蔑することをおぼえるだろう。
しかし私か日本で観察したあらゆる点よりして、日本の国民は実際我々との自由な交際を切望しているものと確信する。
もしどこかに反対があるとすれば、それは大名と武士にかぎられているが、この二つの階級はどこの国においても、大多数の国民の状態改善に反対するものであると反論した。
アメリカ人が日本の貨幣をうけとり、日本人がアメリカの貨幣をうけ取る要求は、きわめて決定的な態度で拒否された。
また、日本の役人の手をへなければ、売ることは一切ならぬと、はっきり言明された。
彼らは、こんな態度で、第八条を除いては、条約草案の全部を拒否し去った。
この第八条は、それが通るという目当てをほとんど持たずに、私か挿入しておいたものだった。
踏絵の廃止
それは、アメリカ人が適当な礼拝堂を建てる権利と、アメリカ人がその宗教を自由に行使し得ること、ならびに、日本人が踏絵の風習を廃止することを規定したものだった。
私が驚き、そして喜んだことには、この箇条はそのまま承認されたのである! |
日本側は、このように、「人心居合(おりあ)わず」という理由を唯一の楯(たて)として、ハリスの要求を極力狭めようとした。
草案第一条の「アメリカ公使の江戸駐箚と旅行の自由」については、江戸は外国人にとって危険だから、六郷川(多摩川)と神奈川との間にすることを主張し、また、その旅行をも制限したので、ハリスはアメリカの使臣を侮辱するものだと反駁した。
第三条の「開港の場所と自由貿易」については、日本側は、約三ヵ月前に長崎でオランダおよびロシアと結んだ条約の振り合いで、長崎・箱館・神奈川の三港におさえ、また自由貿易(勝手の交易)を拒否したが、ハリスはオランダやロシアとの条約は一片の価値なきものと一蹴し、そんな胡魔化(ごまか)しの不自由貿易で甘んずる位なら、わざわざ江戸へ来る必要はなかったのだと言って、江戸と大坂を含む八つの港市の開放と、完全な自由貿易とを要求した。
日本側はまた、第五条の「貨幣交換」について拒否の態度を示し、第七条でも、アメリカ人と日本人との雑居を認めず、旅行にも厳重な制限をつけたが、ただ、第八条の「信仰の自申」については、ハリスの予想を裏切って、日本におけるアメリカ人の信仰の自由を保障し、教会堂の設置をも認めたのである。
とにかく、幕府の態度は、「人心居合(おりあ)わず、諸事漸(ぜん=徐々に)を追って取り計らうつもり」というのであったが、ハリスは日本の国益と、差し迫った「危難」の回避のために、本当の開国を行なうべきことを強く要求し、日本側の態度の根本的な変更を迫ったのである。
二 ハリス暗殺の陰謀
top
攘夷論の火元
「人心居合(おりあ)わず」とは、人心が不穏であるという意味であった。
攘夷論の火元は、御三家の長老、水戸の隠居斉昭(なりあき)であった。
水戸では、藩士の間に秘かにハリス暗殺の陰謀団が組織されており、すでに数名の者が江戸へ向かって出奔した形跡があるとの届けが、藩庁から幕府へ出されていた。
こうした風潮は諸藩へも蔓延(まんえん)する気配があった。
また、外国事情に全く無知な朝廷に攘夷論をたきつけて、朝・幕の離間を策する運動も盛んであった。
幕府の対外的処置の如何によっては、内乱を惹き起こす危険さえもあったのである。
井上は第一回談判の途中で、攘夷論者の消息をハリスにこう伝えた。
武士階級の次三男
「武士階級の次男や三男は官位も定職をも有しない。
それでも軍事教育をうけ、兵法や武器の使用をまなんでいる。
彼らは、俸禄もなく、生涯立身の見こみがない。
ただ、家長に養われているのだ。唯一の特権は両刀をおびることだけである。
このような怠惰の風習により、彼らの多くが悪の道に転落し、放蕩(ほうとう)者・酒乱者・乱暴者となる。
素行があまりひどくなると、親にも勘当され、家族からも見放される。
こうした状態から、浪人と称する一つの階級が生まれた。
これは、兇漢・暴漢・無頼の徒・浮浪者に相当する」と前置きして、「実は、幕府は目下、貴下の暗殺を企てている一味の者を摘発中である。
首謀者の逮捕
今朝その中の三名の首謀者を逮捕し、これらを投獄したが、この事件で幕府は非常に憂慮している。
もし、アメリカ全権の身に禍いがおこれば、文明諸国の眼前に日本政府の失態を暴露(ばくろ)し、合衆国との間に重大な紛争をまねくことになる。だから、宿所の警戒を厳にし、貴下の外出をも制限しているのである」と。 |
井上は、公使の江戸居住は必ず騒擾(そうじょう)の原因になるから、川崎か神奈川にした方が公使自身にとっても好ましいに違いないと言った。
ハリスは、井上の言葉を半信半疑できいていた。と言うわけは、江戸滞在五十五日間、そういう話は全くなかったし、公使の江戸居住問題が論議された第一回目の談判の朝になって突然逮捕者が出たというのは、どう見ても疑わしいと思った。
だから、井上にむかって、「たとえ三名が三千名にしたところで、浪人の騒ぎぐらいで外国公使が江戸へ近づかなくなると思うなら、それは外国人の性質を知らぬもので、真面目に返事をする気にはなれない」と言って、突っぱなした。
ハリスの疑問
ハリスにして見れば、日本人が恨みも何もない外国人を矢鱈(やたら)に殺害するということは、容易に理解のできぬところであった。
「右の者は、私を一目撃もいたし候義はこれあるまじく、私よりも悪事等相施し候ことは曽てこれなく候。若し一時面会いたし、一体の理合を説示候はば、右等の邪念は、忽ち相解け候ことにこれあるべしと存じ奉り候」
というハリスの天真爛漫さには。井上も、
「右は其許に意趣こ退恨等これありての所為にては毛頭これなく、理非・善悪の差別もこれなく、外国人を忌み嫌ひ候情より、右樣の企ていたし候儀」と答えるほかはなかった。
逮捕された首謀者三一名とは、水戸藩の堀江芳之助・信田(しのだ)仁十郎・蓮田藤蔵であった。
ハリスの出府以来、これを暗殺しようと、水戸藩士を中心に浪人を加えた一味十名ほどがこの謀議に参画した。
十一月十九日に前記の三名が水戸を出奔し、江戸へ来てハリスの身辺をつけ狙ったが、警戒が厳重で目的を果たすことができず、水戸藩庁の追捕の手と幕府の厳重な探索により進退に窮して、同月二十七日に江戸の水戸屋敷へ自首したのであった。
だから、同人らの逮捕の時から、井上がそれをハリスの耳に入れた日までを数えると、すでに二週間たっていたことになる。
幕府は、これら三名の者を伝馬町の牢獄につないだ。
犯人の釈放を要求
『ヒュースケンの日記』によれば、ハリスはそれらの者の釈放を幕府にもとめたが、聞きいれられなかったという。
蓮田と信田は間もなく獄中で病死した。堀江芳之介(克之介ともいう)は後年出獄したが、文久元年(1861)五月二十八日の水戸浪士による東禅寺のイギリス公使館襲撃にも参加した。
すなわち、骨の髄からの攘夷論者で、こうした者の多かった時代であった。
蓮田・信田両名の遺詠
蓮田藤蔵(安政五年正月五日、江戸において獄中死、年二十六歳)
武蔵野の あなたこなたに 道はあれど 我が行く道は ますら男の道
信田仁十郎(同年五月十七日、前同断、三十六歳)
大君の 身をけがさじと 賤(しず=いやしい)が身を なき人かずに いれてこそおれ(『殉難後草拾遺)。 |
三 第二回〜第九回談判
top
第二回談判
第一回談判の翌十二日午後二時半から第二回の談判が行なわれた。場所は、やはり蕃書調所の一室。
日本側は草案第一条の公使江戸駐箚の件を渋々(しぶしぶ)ながら承認したが、その代わりに公使を派遣する時期をおくらせてくれといった。
その理由は、物議の沸騰(ふっとう)している現状において外国公使を江戸へおくことは、攘夷論に油をそそぐ結果になる
というのであった。
ハリスはこれを、幕府の常套手段である遷引策を弄するものとして容易に同意しなかったが、ついに日本側の切望を容れて、草案の期日よりも一年半遅らせた一八六一年一月(万延元年十一月に当たる)まで公使を派遣しないことを固く口約した。
また、公使と領事の国内旅行の自由については、日本側は諳大名の反対をおそれて公務以外の場合の領事の旅行を承認せず、この件では両者が互いに譲らなかったので、次回へ持ちこすことにした。
第二条の「大統領の仲裁、アメリカ軍艦の日本船援助」は、日本側の希望する条項でもあり、ハリスもそれを予想して挿入したものであるから、これは即座に妥結した。
つぎに、この条約の要(かなめ)ともいうべき第三条「開港・開市」の場所の件が採り上げられたが、この問題でぱ激しく議論がたたかわされた。
日本側は相変わらず神奈川・箱館・長崎の三港以外を拒否、これに対しハリスは江戸・大坂・京都を含む十ヵ所を要求し、貿易の港市が多ければ多いほど、それだけ日本の国益は大きくなり、関税による政府の財源も増大すると説いた。
日本側は、一時に多数の港市を開くことは、現下の国情が許さない、「それは漸(ぜん)を追ってなすつもり」と言って、ハリスの舌鋒(ぜっぽう)をかわした。 |
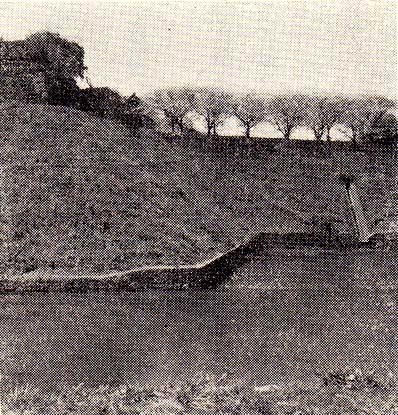
番所調所の跡より田安門を望む
|
討論は暗くなるまでつづいたか、そのとき日本委員は、貴下の議論は非常に重要なものであるから、それらを熟考するために一日を必要とする。それ故に、明後日まで貴下と会見することはできないと語った。
166
かくて、私が前に記したこと――すなわち、実際上、私は政府全体を相手に折衝しているのであって、日本委員は単に彼らに告げられたことを復言し、私の言うことを報告することができるだけであるということが確証されたわけだ。
二人の日本人書記は、一言一句をも書きとるため、たえず働いた。(『ハリスの日記』) |
第三回談判
十二月十四日、午後一時半から第三回の談判が行なわれた。
この談判では、第三条の「開港」の件がもっぱら議題となった。
新潟港
日本側の主張は、大体前回の蒸(む)しかえしであったが、西海岸に面する新潟を開港してもよいと言った。
これは人口六万を擁する都会で、信濃川という大河がこの町を貫流している。
その影響で港には泥が充満していて、大型船の入港は不可能だが、もし西海岸に新潟よりも良い港が発見されるなら、それに変えてもよい、ともいった。
また、石炭は長崎から三里以内のところで発見されているから、九州では長崎以外の港を要求する必要はない。
京都
ミアコ(京都)は貴下の想像するような繁栄の都市ではなく、僧侶と寺の町にすぎない。
大きな製造業もないし、絹を織る家も二十軒以上はない。
天皇(ミカド)の都として有名な場所だが、ミカドには金も政治的な力もないし、国民に尊敬される何ものでもなく、一介の価値なき人物に過ぎないと言った。
これはハリスに、京都は貿易の価値のない場所であると思いこませるための放言だった。
対外政策の鬼門
この京都こそは攘夷論の本源地で、いわば幕府の対外政策の鬼門であるから、ここだけは断じて食い止めなければならなかったのである。
ハリスは短刀直入に、江戸・大坂・新潟・神奈川・長崎の期限つき開放を要求した。
私は次の場所の開市・開港をつぎのように定めたいと言った。
江戸は一八六三年一月一日に開く(品川と共に)。
大坂は一八六一年七月四日に開く。
新潟は一八六〇年七月四日に開く。
神奈川は一八五九年七月四日に開く。
下田は一八六〇年一月一日に閉鎖し、長崎を一八五九年七月四目に開く。
日本委員は、江戸と大坂の開市はとても困難で、この困難は克服されそうにも思えないと語った。彼らは、それは不可能なことと考えていた。それ故に彼らは、それについて一日考えさせてくれと言い、今月の三十日、土曜日に私と会見しようといった。(『ハリスの日記』) |
日本側委員はこの席上、このような重大問題は幕府の一存で決することはできない。
武士階級の反対
もし幕府が諸大名の意見に反してこの問題を処理しようとすれば、騒擾(そうじょう)――すなわち謀叛(むほん)をひきおこすだろう、商人や一般庶民は開国に賛成と思うが、大名や武士階級の反対は非常に大きいので、我々は貴下の意見に賛成しながらも、これを実行することができないのだと言った。
これは、その通りだったが、それで済む問題でぱなかった。
ハリスは例によって、
| 「御拒(こば)みなされ候へば、自然御危難出来仕るべく、右は合衆国より事起り候儀にはこれなく、他の国より仕向け候よう相成り申すべく、江戸・京都・大坂の三港御開きの儀、斯く繰返し申上候に、御危難を除き申すべき為に御座候」(『幕末外国関係文書』の十八) |
と、どこまでも突っ張ったのである。
第四回談判
一日飛んで、十二月十六日に、四回目の談判を行なう。
この談判で、日本側は江戸と品川の開市・開港を承認したが、アメリカ人の居住を神奈川と横浜とに限ることにすると申し出た。
これに対しハリスは、アメリカ人の江戸居住が認められなければ、江戸が開市されても貿易の実行は不可能であり、「アメリカ人が神奈川から江戸へ行き、その日のうちに戻り、しかも江戸で用事をたすことを期待するのは、肉体的にも不可能なことであり、このような取極めはアメリカ人が江戸で品物を売るのを防止するものだ」と反対した。
品川については、同所は浅瀬で、開港場として物にならないのを知ったので、ハリスの方から要求を撤回したが、その代わりに、「江戸と大坂――すなわち、日本の二大都市からアメリカ人を閉めだすかぎり、自由貿易を云々するのは愚かも甚だしい」といって、江戸と大坂を強硬に要求した。
勝手の貿易
日本側はこの談判で役人の仲介なしの貿易(勝手の貿易、すなわち自由貿易)を認めたが、それに付言して、「日本には問屋と称する大商人の階級があるから、それらが神奈川で店舗をひらき、アメリカ人はそれを相手に売買するようにしたい」と申しでた。
ハリスはこれに対し、「アメリカ人の販路を問屋に限ることは、そうした階級を保護するために専売制度を設けるに等しい」と反対したが、日本側は問屋に定数はないので専売のおそれはないと陳弁した。
とにかく、この日の談判で日本側が自由貿易ヘー歩踏みだしたことは、ハリスにとって大きな収穫だった。
第五回談判
十八日に第五回談判。日本側委員はハリスの前回の議論に屈して、「神奈川をアメリカ人の居住の場所にすると共に、一八六三年一月一日以後商用で江戸へきたアメリカ人の一時的逗留(とうりゅう)のために、江戸市中に一街を設ける」ことで妥協を申し入れた。
しかし、この居住と逗留の区別で議論が紛糾して、容易に意見の一致を見なかった。
ハリスとしても、アメリカ人と日本人との雑居は強いて求めず、居留地制度に甘んじたのであるが、しかし妻子との同居を許されぬ一時的な逗留には承服しかねる旨を明らかにした。
そして、「一八六三年一月一日(文久二年十一月十二日に当たる)以後に、アメリカ人の商用のために江戸を開市し、その目的で居住する場所は、後日アメリカの代表と日本政府との間で取りきめる」という文句を条約に明記すべきことを要求した。
日本側としては、条約反対論者、ことに外国人の江戸「居住」に反対する諸大名の手前、なるべく「逗留」の文字を使いたかったのだが、ハリスは、江戸「居住」を条約文に明示しなければ江戸での商売は半身不随も同様だといって、承知しなかった。
第六回談判
翌十九日の第六回談判では、主として京都と大坂の開市が問題になった。
日本側委員は、京都の開市は国情の到底許さぬところと前置きして、その理由をこう語った。
京都をアメリカ人に居住地として開くことは絶対に不可能である。
それは日本人の宗教と結びついている。
これは至難であるというよりも、実際上出来ない相談である。
それに、京都は商用の土地柄ではない。そのことは、アメリカの公使がそこを訪問すれば直ぐにわかることである。
また、京都を外国人の常住地として開こうとすれば、謀叛(むほん)を惹き起こすことになろう。
貴下がこの由を大統領に申し送るならば、大統領は日本に対して極めて親切な友人であるから、実際上の価値がなくて、同時に日本に無秩序と流血とをもたらすようなことを主張するはずは決してない。(『ハリスの日記』) |
京都の開市を断念
ハリスは、京都が商業都市でないこと、および京都の開市が日本全土の人心に刺激をあたえる危険のあることを感知したので、これを断念することにしたが、大坂には飽くまで食いついて離さなかった。
日本側は、京都に近いという理由で大坂の開市・居住を拒み、これに代えるに堺か兵庫をもってしようと申しでた。
飽くまで大坂を要求
ハリスは、どこまでも大坂を要求した。
| 「大坂は江戸につづき候好き地にて、川筋四通五達、商売都合宜しく、船具その外取扱うにも便利、地も広く人も多ければ、商いも随って盛に相成るべく、此地を除き候ては、商法狭少に相成り、外の地所にて御開にては、十分の一と相成り、商売も又十分已の小商売に相成り申し候(『幕末外国関係文書』の十八) |
というのだ。
この問題をめぐって、長い間論議が戦わされた。
日本側は、それならアメリカ人を堺に居住させ、そこから大坂へ行って商売し、またその目的で家を借りる権利をも与えるが、しかし大坂に宿泊することは許さないという、条件づきの開市を申しでた。
ハリスはそれを一蹴し、大坂に宿泊できなければ、もし急病になった場合にどうするつもりか、無理に堺へ送り帰して途中で死んだら人道問題になると、そんな例えにかこつけて無理やり自説を通そうとした。
日本側はまた、草案第七条の「アメリカ国民の旅行の自由」について、公使および総領事をのぞく一般アメリカ人には自由を認めることはできぬと強く主張した。
そして、この問題と京都開市の件は二つとも絶対に不可能であり、それらを許せば必ず日本に叛乱が起こると言った。
議論は白熱し、激しい言葉のやり取りがあった。
日本側委員は、「もし諸外国がこの二つの件を理由に日本と戦端を開くなら、我々も最善の努力をもって応戦する覚悟だ。内乱は外戦よりも恐ろしい」と口走った。
条約成否の分岐点
夕暮になったので、ハリスは洋燈(ランプ)の用意を命じた。
日本側委員は、貴下の頑張りにはすっかり閉口した、今日のところは、これでご免をこうむりたいと言った。
ハリスは彼らに、「今こそ条約成否の分岐点である。
一歩あやまれば、これまでの苦労は水泡に帰する」といって、真剣な考慮をうながした。
第七回談判
このように、ハリスは「日本の国益と、危難の回避」を矛(ほこ)として論法鋭くつめより、日本側は「国情の許さぬところ」を楯(たて)にとって、互いに譲らなかったのである。
井上の苦衷
その翌日早朝、井上はハリスをその宿所に訪ね、今や江戸城内では保守派の間に猛烈な条約反対論が湧きおこっており、人々は幕府の譲歩に激昂していると言って、自分の苦衷をうち明けた。
そして、「貴下が京都や大坂の開市とアメリカ人の国内旅行の自由をあくまで要求するならば、条約の全部を打ちこわす恐れがある。
日本側のこれまでの譲歩は、当初においては夢想もしなかったところである。
無価値なものを望んで、条約全体を失うよりも、これまで獲得したものを確保する方がよくはないか。
これらの二つの問題にしても、幕府がいつまでも拒否するものではなく、いずれ人心の居合(おりあ)いがつけば自然に解決される問題だ」
と言って、ハリスの翻意(ほんい)をたのみこんだ。
ハリスも井上の衷情(ちゅうじょう)を容れて、「もし、条約の他の部分が全部こちらの思い通りになるならば、貴下の希望に応ずるようにする」とこたえた。
こうした事前の了解のもとに、十二月二十一日に第七回の談判が行なわれたのである。
この談判では、草案の第三条(開港・開市)・第四条(関税、アメリカ海軍の食糧・弾薬等の貯蔵に関する規定)・第五条(貨幣交換)・第七条(開港場の境界、旅行・居住の自由)について論議され、談判はようやく妥結にむかって進みだした。
対抗意識を去る
日本側委員は当初に見られた対抗意識を去って、愚問を恥じずに率直にハリスの教示を乞うようになり、ハリスもまた相手の手を取るように教え、たがいに誠意をもって談判の進捗(しんちょく)をはかったのである。
ハリスは、大坂をアメリカ人の居住地として開放するならば、日本側の鬼門とする京都の開市とアメリカ人の旅行の自由を撤回しようと申しでた。
第五条には、日本人に支払われる外国貨幣に対して六パーセントの両替手数料を日本政府に支払い、また日本貨幣の輸出を禁止する事があったが、日本側はその六パーセントを放棄し、また日本貨幣の自由な輸出を認め、外国貨幣を日本において自由に通用させることにすると言明して、ハリスを大いに喜ばせた。
日本側はまた第四条をも承認したが、これもハリスにとって大きな収穫だった。
この第四条は、合衆国政府に対し神奈川・箱館・長崎に、アメリカ艦隊の使用する必需物資を無税で陸揚げする権利を認めることであった。
この承認によって、アメリカは世界で最も健康にめぐまれた気候を有する国において、東洋の合衆国海軍のために三つの良港を物資補給地とすることに成功したのである。(『ハリスの日記』) |
従来東洋におけるアメリカ艦隊の補給は、その競争国たるイギリスの主権下にある香港に依存してきていたので、一朝両国間に紛争のおきた場合には直ちに閉鎖される運命にあったのである。
第八回の談判
十二月二十三日に、第八回の談判が行なわれた。
大坂の開市の件をめぐって、再び激論がたたかわされた。
日本側は、大坂は開くが、アメリカ人の居住地は堺とするという主張を依然として堅持した。
そして、万一アメリカ人が大坂で急病になった場合を顧慮して、大坂と堺の間に病院を設けることにすると言った。
ハリスが前回発言した急病人発生の場合云々は、ただ論証の手段として一例をあげたまでで、その主意はあくまで大坂の完全な開市(すなわち居住を含む)にあったのだから、その裹をかくような病院設置の提言には、彼はかんかんになって怒った。
再び大坂を拒否
日本側は例によって、「大坂は皇居最寄りの地、殊に人心居合わざる当節」云々(うんぬん)を主張して譲らず、ハリスは、それなら前回撤回した京都の開市と国内旅行の自由の二件を蒸しかえすことにすると言いだした。
日本側委員は、
「しばらく訥(ども)ったり、まごまごしたりした。そして、この提案は自分らの本意から出たものではないので、城中へ帰って報告した上、再考することにしようと、折れて出たのである」。(『ハリスの日記』) |
ついで、日本側から他の箇条を採りあげることを提議して、第六条(領事裁判の件)に直ちに同意を示した。
第七条(開港場の境界、旅行および居住の自由)は、第三条(開市・開港の場所)の解決を見るまで保留することにしたが、第八条(信仰の自由)から第十五条(条約の施行)までは、いずれも若干の修正を行なっただけで異議なく通過したのである。
批准書交換使節の派遣
第十六条(批准書交換の件)では、日本側委員が意外な発言をして、ハリスを歓喜させた。
彼らは、もし貴下が希望するならば、批准書の交換のための使節を日本の蒸気船にのせて、カリフォルニアを経由してワシントンに派遣することにしたいと提議したのである。
私は、私にとりこれ以上の喜びはないと述べた。
そして、合衆国は日本が条約らしい条約をむすんだ最初の大国であるから、最初の日本使節を、合衆国に送ることは、私の欣快にたえぬところだと告げた。(『ハリスの日記』) |
思うに、二人の日本側委員、ことに岩瀬忠震は、当然自分が使節の役目をおびて、批准書交換のためにワシントンへ派遣されるものと思い、また自分でもそれを希望していたのであろうが、条約調印直後の政変で堀田正睦が失脚するや、岩瀬自身も井伊大老のために退けられてしまった。
そのために、万延元年(1860)の遣米使節の大役は、遺憾にも他の人々にこれを譲らなければならなかったのである。
第九回の談判
十二月二十五日に、第九回の談判。
ハリスの強硬な申入れにより、幕府はこの回において大坂の完全な開市を認めたのである。
ハリスの日記によれば、
約束の通り、午前八時に会見する。日本側委員は大坂の件について色々な箇条を提出したが、結局、彼我の間でつぎのように意見の一致を見た。
すなわち、一八六三年一月一日に江戸の市、一八XX年×日に大坂の市を居住と貿易のためにアメリカ人に開くこと。
これら二市のいずれにおいても、アメリ力人が家屋を賃借できる特定地と遊歩しうる距離を、アメリカの外交代表と日本の政府によって設定すること。(『ハリスの日記』) |
これに気をよくしたハリスは、さらに堺と兵庫の開港をも要求したが、日本側は、大坂の代わりになら兵庫を開いてもよいが、大坂を開いた以上は開くわけにはゆかぬと、きっぱり断わった。
そこでハリスは、「それなら兵庫は撤回するが、これは良港だから、いずれは開港する日が来るだろう」といって、堺だけで我慢することにした。
兵庫の良港に着目
兵庫の良港であることに着目したハリスは、さすがに烱眼(けいがん)であった。
彼は、草案にはこれを入れていなかったのだが、談判の途中から兵庫は貿易港として大坂以上に有望であることを洞察していたのであった。
結局、後の談判で、日本側からの申し出により堺をやめて兵庫を開くことになったのであるが、この兵車の開港実施は、後年に至って国論紛糾の種となり、幕府の存亡をかける大問題にまでなった。
大坂の開市
それはとにかく、日本側の譲歩によって、条約の最大難関と目された大坂開市の問題もここに落着を見たのであるが、これは井上・岩瀬両全権の説得が幕議を動かしたからであった。
両人もハリスに対して、「大坂を江戸同様に開き候は、実にもってむつかしき儀のところ、過刻(かこく)も申し入れ候通り、両人とも格別力をつくし、種々評論を重ね、稍(やや)其方の申し条も相立て候儀故、右等の辺、得(とく)と推考斟酌(しんしゃく)これありたく候」(『幕末外国関係文書』の十八)と、大いに恩をきせている。
こうして談判もようやく峠をこし、これまでに決まった開市・開港の場所について、その実施の期日がつぎのように定められたのである。
神奈川―一 一八五九年七月四日。
長崎 ―― 同上。
新潟 ―― 一八六〇年一月一日。 |
江戸
―― 一八六二年一月一日。
堺 ―― 一八六三年一月一日。
大坂 ―― 一八六三年一月一日。 |
四 第十回〜第十四回談判
top
第十回の談判
十二月二十六日に、第十回の談判が行なわれた。
この日の談判では、貿易の具体的な規定(貿易章程)が採りあげられ、関税の方法、荷物の改めかた、過料、各税法の利害得失などについての質疑・応答があった。
日本側の質問に対するハリスの応答は、むしろ生徒に対する教示に近かった。
日本側委員もこれらの回題について、知らざるを知らずとする率直な態度に出た。
日本側委員は、こう言った。
我々は、このような問題を取り扱った経験がないので、こうした事には全く暗いと。
また、こう言った。
貴下は疑いもなく、今我々のために大きな苦心をはらって、貿易の規定を作成されている。
我々は、貴下の親切に感謝する。当方では、貴下の廉潔に全幅の信頼をおいているので、それらを原案のまま認めようと。(『ハリスの日記』) |
貿易章程
こうして作られた貿易章程七則は、ハリスの草案を骨子として出未たものだが、世に誤って伝えられているような、ハリスがこれらを強要して、日本の関税自主権を犯したというような事実は全くなかったのである。
第十一回の談判
日本は、こうして安政五年の新たな年を迎えることとなった。
これは、対外的に、また国内的に、徳川幕府にとって最も多難な年となったのである。
条約談判は、すでに終わりに近づいていたが、それが終末に近づくに従って、諸大名はじめ保守主義者の条約反対論は、ますます激しくなってきたのである。
幕府の外交当局者はこの事態を憂慮して、反対論者の慰撫(いぶ)や説得に努力したが、幕府の藩屏(はんぺい)ともいうべき御三家の長老、水戸の斉昭が反対論の先鋒を買って出ているので、始末が悪かった。
正月の蟄居
江戸で迎え九日本の正月を、ハリスは蕃書調所の一室にとじこもったままで過さなければならなかった。
屋外は登城の大名行列や着飾った民衆でにぎやかだったが、正月の混雑に紛れて刺客が入り込むおそれがあったので、幕府から外出をとめられていたのである。
ハリス自身も、時節がら余計な刺激や摩擦を人心にあたえてはとの遠慮から、もっぱら屋内に蟄居(ちっきょ)していた。
正月の三日は終日物凄い吹雪だった。それはハリスに故郷ニューヨークのきびしい冬空を想いおこさせた。
正月も三ヵ日を過ぎた一月四日に、前回の後をうけて第十一回の談判が行われた。(注)
(注=この日の談判については、日本側の記録がない。これは、談話の内容が機密にわたったので、筆記者を席から遠ざけたからだと思われる)
日本側、調印不可能を発言
もう一息で条約は妥結(だけつ)・調印というところまできていたのだが、この日の日本側委員の発言はハリスにとって大きなショックだった。
条約反対論が非常に激しくなってきているので、たとえ談判が妥結しても、このままでは調印は不可能だと言い出したのである。
彼らの話によれば、幕府は条約の実体を諸大名に示した。
ところが、城中は忽ち鼎(かなえ=大なべ)の沸くような大騷動となった。
若干の最も過激な分子は、このような大変革の実行を許す前に、自分の生命を投げだすと言いだした。
そこで閣老たちはこれらの人々の啓蒙につとめ、皇土(キングダム)の滅亡をさけるためには、条約の締結は止むをえないことを諭(さと)したが、大部分の者は依然としてこれに応じない。
幕府は、流血の惨事を見ることなしに、今直ちに条約に調印することが出来ない状態にある。
そして、大統領としても、日本にこうした災害をもたらすことは欲せぬものと確信する、などと言った。
精神的皇帝への特使
彼らは最後に、閣老会議の一員が「精神的皇帝への特使」として京都へおもむき、皇帝の認可を得ることができるまで条約の調印を延期したいと言った。
その認可がおり次第、大名たちは反対を撤回するに相違なかろうし、そうなれば調印は円満に行なうことができるが、それには約二ヵ月を要するというのである。
この重大な話がおわるや、私は彼らに、もし天皇(ミカド)が承諾を拒むなら、諸君はどうするつもりかと訊ねた。
彼らは直ぐに、断乎たる態度で、幕府は天皇の如何なる反対をも受けつけぬことに決定していると答えた。
私は、単に儀式だけと思われることのために、条約を延期する必要がどこにあるかと問うた。
彼らは、この厳粛な儀式そのものに価値があるのだと答えた。
そして、私の了解したところによると、天皇(ミカド)に対して荘重に上奏し、天皇の決定が最後の切り札とたって、あらゆる物議が直ちにおさまるであろうというのであった。 |
ハリスの憤懣
ハリスはこの陳述を、言いようのない失望と憤懣(ふんまん)の気持できいていたが、聞き終るとこう言った。
諸君が私に話したことは、談判の歴史に先例のないことであり、それは児戯(じぎ)に類し、日本を治めるような賢明な政治家のなすべきことではない。
それは重大事件を軽視するもので、大統領に甚だしい憂慮をあたえるにちがいない。
そんな些細(ささい)な理由のために、非常に大きな労力を費してきた条約に調印することを拒むよりは、全然談判をしなかった方がましたった、と。 |
複雑な政情
日本の政情に疎いハリスの眼から見たら、天皇(ミカド)へ上奏などという儀式的行事は「児戯(じぎ)に類した」ことであったろうが、怪物の斉昭が今や朝廷と通謀して、朝威をかりて諸大名の反対熱を煽(あお)っていたのだから、幕府としてもそれを押し切って調印することは出来なかったのである。
堀田正睦を初めとする幕府の開国論者は、この上はこちらも朝廷に働きかけ、勅命をかりて反対論者を承服させる以外に手はないと考えた。
そこで井上清直に命じて、条約の勅許を得るまで調印の実施をのばすことをハリスに懇請させたのである。
六十日間の調印延期
ハリスは、意外な障害を知って当惑したが、幕府が当面している事態の重大さ知ったので、止むなく六十日間の調印延期を承諾した。
ハリスの日記によれば、
そこで私は、信濃守(井上)にこう提言した。
我々は条約をできるだけ速かに進捗させ、完了の上、それを清書させて、調印を待つばかりにしよう。
それから、彼我の委員は条約の仕事を完了して、今や調印するばかりになっているが、ある重要な理由のために調印は六十日間延期する必要があり、その期間が満了したら(或はそれ以前に)、条約は現在のままで調印するという一札を、閣老会議か外国事務相から私に入れさせることにしよう。
その後私は直ちに、合衆国政府へおくる書信を用意するために下田へ戻ろう。
五十日の終りごろ(それ以前でないならば)、幕府は条約調印の目的をもって私を再び江戸へ連れかえるために日本の汽船を下田へ派遣する、ということにしては、と。
信濃守は大いに安心し、早速この旨を幕府につたえ、そのことで明日私に話そうといった。(『ハリスの日記』) |
ハリスは目をつぶった。
そして、おだやかでない自分の胸に、「止むを得ない」と言いきかせた。
自分の置かれている特殊の状況において、これ以上の策はとることができないと考えたのである。
第十二回の談判
ようやく妥結の寸前まできたとき、これまで日本の唯一の政府と思ってきた江戸の政府以外に、さらに京都に朝廷なるものがあって、その承認なしには条約の調印が不可能だとは、全く自分を、そしてアメリカを馬鹿にした話だと思った。
やり場のない憤りと不安を交えた気持で、ハリスは一月六日の第十二回の談判にのぞんだのである。
この目の談判では、草案第一条の[外交官の国内旅行の自由]が議題になった。
日本側は、公使と総領事については旅行の自由を認めたが、普通の領事の場合はこれを拒否すると言った。
ハリスは国際法の通義を引いて日本側の主張を非難したが、日本側委員は特殊な日本の国情を理由に頑として拒否をつづけた。
日本側としても、故意に外国人の内地旅行を妨害するつもりはなかったのであるが、幕府の直轄地はいざ知らず、外国人が自由に大名の領地へ入る場合には生命の保証ができず、そのために国際問題をおこしては困るので、あくまでも拒否することにしたのである。
ハリスもついに断念して、これに従った。
勅使奏請の使者
一月八日に、幕府は外交事情を朝廷に奏上して条約調印の勅許を仰ぐため、堀田に京都ゆきを命じた。
すでに前月(安政四年十二月)に、儒者林大学頭(かみ)(韋)と目付の津田半三郎を京都へのぼらせて、外交事情を奏上させていたのであるが、いよいよ条約談判も終わりに近づいたので、幕府官僚の首脳者であり、外交問題の最高責任者である堀田が自ら出むいて、勅許奏請の衝(しょう)にあたることになったのである。
随員は、談判委員の一人であり、俊秀・機敏をもって鳴る目付の岩瀬肥後守(忠震)と、井上信濃守(清直)の兄で老巧をもって聞こえた勘定奉行の川路左衛門尉(聖謨)であった。
幕府の対京都政策
当時、堀田をはじめ幕府の外交当事者は朝廷を甘く見すぎていた。朝廷は権力を持たず、かつ貧乏であったから、幕府の対京都政策の常套手段である威圧と買収、すなわち「黄白(こうはく)を撒(ま)く」ことによって、勅許は容易に得られるものと考えていたのである。
幕府の上奏は朝廷を重んじてのことではなく、その真意は斉昭一派の反対を抑えることにあった。
『昨夢紀事』によれば、斉昭は、「備中と伊賀(老中、松平忠固=ただかつ)には腹を切らせ、ハリスは首を刎(は)ねて然るべし」と怒鳴ったという。
『ハリスの日記』には、「狂人のように喚(わめ)いているそうだ」とあるが、多分これらを言ったものだろう。
斉昭の京都手入
こうした斉昭の、いわゆる「京都手入れ」(朝廷に策動して、条約を葬ろうとする)は、将軍家の藩屏(はんぺい)でありながらその頸(くび)を絞めようとするものだったが、一方これを抑えるために軽々しく朝廷を利用しようとしたことは、堀田およびその一派の失脚の原因をなしたばかりでなく、幕府権力の失墜の元ともなったのである。
この点では、岩瀬や井上などにも誤算があった。
朝廷に対する誤算
彼らは朝廷を軽蔑して、「目下多額の黄金が天皇の諸役人の間にまかれているから、朝廷の認可は間違いない」と、繰返してハリスに言っていたのである。
それほど軽蔑している相手、すなわち朝廷のために、なぜ条約の調印を延期する必要かあるのか! これがハリスの大きな疑問であり、不安のまとであった。
彼は『日記』に、こう書いている。
天皇(ミカド)に対して、二種の意見書が提出されるということだ。
その一つは条約の提案に賛成し、他は反対するものである。
天皇は両者を審査した上で、その一つを認可するであろう。
その認可には、すべての者が承服しなければならない。
最も激しく条約に反対している人々でも、(天皇が大君の方に賛成するならば)、「神宣(のたま)う。われ従わん」というであろうと。
「しかし、これは、日本側委員が私に天皇のことを話すときの、ほとんど軽蔑的な態度とは、あまりにも一致しない」。
そして、「彼らが私に話すことには、どうしても全幅の信頼がおけない」と言い、
「私は、条約について全く失望し、意気銷沈(しょうちん)している。
私は大統領の承認をうるような条約の締結に全く失敗するのではなかろうか。大いに気がかりである」 |
とのべている。
日本人のオランダ語通訳者や、来訪した井上に対する八つ当たり的な言葉を『日記』の中にならべているが、それから五日して重症の床にたおれたところから見ると、この頃からすでに健康状態がわるく、条約に対する焦燥感から精神的にも自制の域をこえていたように思われる。
第十三回の談判
一月十日に、ハリスは最後の締めくくりとして、第十三回の談判にのぞんだ。
堺の代わりに兵庫を開く
この談判で特記すべきことは、先に決めた堺をやめて、その代わりに兵庫を開港することを日本側で提案したことだ。
これは、堺が地理的に大和(やまと)の御陵に近いところから、幕府が朝廷に気がねして、兵庫と取りかえるに至ったものと思われる。
堺の港が貧弱なのに反して、兵庫は今日の神戸が示しているように関西第一の良港であったから、もちろんハリスはこれを応諾した。
また、長崎と箱館の開港場の区域は、ハリスの提案をそのまま日本側が認め、長崎はその周囲の御料所(幕府直轄地)、箱館は四方およそ十里の境界内ときまった。
新潟の開港については、もし同港が開港場として不都合な場合は、西海岸の他の一港をこれに代えることにし、その決定は後日に延ばすことになった。
条約本文の妥結
日本側から各条文の用語についての修正案がだされ、それが終って午後五時に条約本文の妥結を見た。
輸出税
ついで付属規定である貿易章程がとりあげられた。日本側は、罰金の件や噸(トン)税を課さないという点ではハリスの教示を採択したが、しかし輸出税については、これを課することにしたと通告した。
ハリスは前回にイギリスとアメリカの先進国を例にひいて、輸出税は日本の産業の発達を阻害するから、輸入税だけにした方がよいと、経済の原則を説明して忠言したのだが、日本側では課税することに決定したというので、不満ながらこれに従った。
ハリスは『日記』の中で、「このような輸出税は如何なる繁栄の貿易をも粉砕するであろう」と残念がっているが、幕府としては、日本の産業の発達よりも、枯渇した幕府財政の救済の方が焦眉の急だったのである。
そこに封建制度の矛盾があり、そうした矛盾が重なりあって、ついに徳川幕府は亡びるのである。
ボウリング総督への手紙
この日、条約本文の妥結に安堵したハリスは、香港のイギリス総督ジョン・ボウリングに長文の手紙をおくったが、その中で、日本人との談判の困難さをのべ、満足すべき条約がむすばれて、日本との商業関係が従来と異なった基礎の上に打ち立てられるならば、世界の国々も満足するであろうし、日本にとっても平和と繁栄と永久の利益になるであろうと書き、(イギリスの企図しているような)大艦隊の威圧を借りることなしに、自分が単身ここまで漕ぎつけたことに、いささか得意の口吻(こうふん=言い方)をもらしている。
だが、ハリスのそうした気持は、まだ早かった。なるほど条約の妥結は見たが、目指す調印は「攘夷」の激浪のため遙かな沖へ押し流されていたのである。
朝廷は元来攘夷の本源地であったが、斉昭の「手入れ」以後は謀略的な策源地と化していた。
幕府の必死の工作を全く無視して、調印に反対の気構えを少しも変えようとはしなかったのである。
ハリスには、京都の事情はさっぱり分らなかった。知らされてもいなかったし、むしろ、その反対のことが聞かされていた。
第十四回の談判
一月十二日に第十四回の談判が行なわれたが、この日は前回に間に合わなかった関税率の表が日本側から示されただけてあったから、談判は事実上十三回目で終わったものと考えてよい。
関税率の決定
なお、関税率についてハリスは、「私は如何なる輸出税をも課することのないように切望してきたのであるが、私はこの考えを放棄しなければならない」といっているが、その代わりに日本側でもハリスの要望をも容れて、原案の十二・五パーセントを五パーセントまで引き下げたのである。
top
****************************************
|