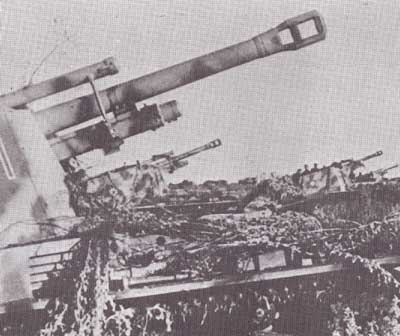|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7 8
9 10
11 12
7 経験を重ねて
独裁者の“持ち駒”のなかに機甲部隊があることによって、独裁者は、自分が大きな力をもった、と思い込むようになるものらしい。
それは多分、戦車部隊というものが、少なくとも表面的には、独裁者の意思を押し通すための道具として、適当なものであったからだろう。
とにかく、ロシアの冬の寒さがやわらいで、一九四二年〔昭和十七年〕の春になると、今度はスターリンが、前年の夏にヒトラーがやったと同じ過ち――敵の力をあなどり、自分の戦車部隊の力を買い被る――を犯す、という廻り合せになった。
|

ロシアの草原を越えて:スターリングラードにむかうドイツ機甲部隊
|
1 戦車生産が最優先 top
新しい作戦期が始まったころ、ソ連戦車部隊の編成は、まだ独立戦車旅団を主体とする考え方に基いていた。
旅団の編成は、通常T34とKV1重戦車の混成で、約五〇台からなっていた。
こうした旅団は、一九四二年になると急速にその数をまして、五月の初めには、約二〇個旅団が作戦に使用できる状態にあった。
だが、ドイツ軍は、この年の末までに、一三八個旅団を確認したと発表している。
とにかく、T34を製造するほうが、その乗員をえらんで訓練するよりも、早く、簡単で、やすあがりだった。
新しい戦車旅団のために、訓練された戦車乗員の予備を急いで準備することが困難なことによって、旅団の使用法は、限定されるのである。
つまり、多くの場合、戦車旅団の任務は、歩兵支援の任務にかぎらざるをえない状態であった。
機甲師団は、一夜にしてできるものではない。ソ連戦車部隊の指揮構造は、上は軍団長から下はT34の砲塔内にいる過労の兵士にいたるまで再検討し、彼らが適切に動けるように、修正をくわえる必要があった。
旅団という編成は、打撃部隊として使うには、余りにも小さすぎる編制である。
だが、ソ連軍の司令官たちは、戦車部隊を、攻勢作戦で大部隊として使用する経験を、十分にはもっていなかった。
ジューコフは、このことを知っていた。
しかし、スターリンは知らなかったのだ。
2 スターリン、大攻勢を主張 top
いまやスターリンは、大規模な攻勢作戦によって、彼が前年におかした失敗をつぐなおうと考えていた。
三月末に開かれた国家防衛委員会の席上、ソ連の軍事指導者たちのあいだで、活発な論議がかわされた。
ジューコフは、すでに自分の見解を明らかにしていた。
彼は、ルジェフ〜ビャズマ地区でモスクワをおびやかしている、危険なドイツ軍の突出部をとり除くために、限定された攻勢を開始することを提案していた。
しかし、スターリンと参謀本部の一部の者は、もっと南方地域での作戦に関心をもっていた。
スターリンは、ハリコフの奪還という、大きな作戦にしか目をむけなかった。
だが、こうした大きな作戦のためには、苦労して再建した戦車部隊のT34とKV1の大部分を必要とするのである。
このときの国家防衛委員会には、ウォロシーロフ、ティモシェンコ、シャポシニコフ〔参謀総長〕、ワシレフスキー、バグラミアン、ジューコフ、それに、スターリンが出席していた。
この出席者のうちで、シャポシニコフは、新しい攻勢については、ジューコフの意見にちかかった。
彼もまた、ソ連軍がもっと強力になるまでは、活発な防勢的方策をとるべきだと考えていた。
だがスターリンは、奇妙にチャーチルをおもわせるような態度で、即座にこう言いきった。
「我々は、守勢にたって、ドイツ軍が攻撃してくるまで手をこ招いて待っていることはできない。
我々は、先手をとって攻撃しなければならない……」
これは、南西戦区の作戦指揮をとっている、ティモシェンコの考えでもあった。
彼は、自分の部隊は攻勢の準備を整えている、と発言した。
彼はさらに、こうした攻勢は、ドイツ軍が考えている計画を打ち破るための、予防対策として立案されるべきである、と主張した。
シャポシニコフは、スターリンの危険な視線が注がれるのを感じていたろうが、この重大な時機に黙ったままだった。
これで“さい”は投げられた。 |
国家防衛委員会のメンバー |
|

ヨセフ・スターリン

ワシレフスキー元帥
|

シャポシニコフ元帥

パグラミアン元帥
|
3 敵をみくびったティモシェンコ top
四月に、ティモシェンコは命令をうけた。ハリコフ地区のドイツ軍を攻撃し、この町を奪還せよ、というのである。
ティモシェンコは、いまや、この命令でさえ容易でないのに、さらに作戦を拡大して、ドイツ軍をドニエプル川に撃退する作戦を目ざすというまでに、気が大きくなっていた。
彼は、敵にたいする最も有効な打撃は、戦車部隊を、攻撃準備中のドイツ軍の集中地域に投入することである、と信じていた。
この目的のために、彼はその指揮下に、当時使用可能だった戦車二〇個旅団のうちの一四個をもっていたのである。
このティモシェンコの攻勢は、融通性のないまずいものであったが、当初は、その戦車の推進力のおかげで成功した。
彼の南西方面軍は、パウルスが率いるドイツ第6軍の戦線を、二三キロから三二キロにわたる深さに突破前進した。
だが“復讐の女神”が待ちうけていた。
それはクライストのドイツ第1機甲軍であった。
ちょうど、ティモシェンコが攻撃している突出部の首の部分にあたるクラマゴルスクで、攻勢の準備に集結していたのだった。
この集結地域は、ティモシェンコの当初の攻撃では、手の届かないところであった。
そこで、結局このドイツ第1機甲軍は、最もおそるべき機甲予備部隊、ということになった。
その戦車は、燃料や弾薬を満載して、いつでも動ける準備を整えていた。
だが、ジューコフの回顧録によると、スターリンでさえも、この部隊を心配していたのに、ティモシェンコは、この脅威を無視していたようである。
事実、ティモシェンコはスターリンに、クラマゴルスクのドイツ第1機甲軍は“張り子の虎”みたいなものだ、と報告している。
彼の見解は、このときティモシェソコの軍事委員であったニキータ・フルシチョフからも、支持されていたのであった。
数日もたたないうちに、クライスト指揮下の、よく訓練された戦車兵が、二人の判断が誤っていたことを証明してしまった。 |

草原の夏:攻勢をかけるT34と歩兵

掃討戦:ドイツ軍をかりたてるソ連軍戦車
|
4 なけなしの戦車旅団を失う top
五月十七日、クライストの攻撃が始まった。
その兵力は、機甲二個師団、装甲擲弾兵一個師団〔車載歩兵師団をこうよんだ〕、歩兵八個師団からなっていた。
軍事的見地からすると、ソ連軍の態勢は奇妙なものになっていた。
ティモシェンコの主攻勢を担任するゴロドニャンスキー中将のソ連第6軍は、方向を北にとってハリコフに向った。
そしてクライストが、そののびきった側面に向って、南から攻撃したのである。
一方、ソ連戦車部隊は、命令に基いてハリコフ方面に向っていたため、実際には、この主戦場から離れていた。
そこで、たちまち大混乱となってしまった。
とくに、クライストの攻撃を真先にうけたハリトノフ少将のソ連第9軍は、包囲され、撃破されてしまった。
ソ連軍には、もう予備兵力がなかった。戦車部隊は、すでに戦線に投入されてしまっており、混乱を起している状況となっては、ティモシェンコには、事態を建直す手だては、もうなにもなかったのである。
五月十八日に、ティモシェンコの幕僚はソ連大本営〔スタフカ〕に電話をかけ、西に向う攻勢を中止する許可を求めたが、スターリンは許さなかった。
“あくまで”攻撃を続行せよ、という命令がかえってきた。
防勢にうつってもよい、という命令がだされたのは、一日おいた十九日の午後になってからであった。
だがこのときまでに、すでにソ連軍は大損害をだしていた。
次から次へと包囲され、撃破されて、敗北をうけてしまったのだった。
第6軍司令官のゴロドニャンスキーと、第57軍司令官のポドラス中将の二人が戦死し、二万をこすソ連軍将兵が捕虜になった。 |

東へ東へ…:ロシアの大地を進撃するドイツ軍三号戦車

インスタント装甲増強:キャタピラーを使って
装甲を強化したドイツ軍三号戦車
|
そして、さらに重大なことには、貴重な戦車一四個旅団の大部分が撃破されてしまったのである。
ジューコフは、のちにこれを、次のように批評している。
「この失敗を分析してみると、失敗の根本的原因は、南西戦区軍〔当時ティモシェンコは、南西、南の二方面軍を指揮している〕の南の正面にあった、敵の大兵力を見くびっていたことと、大本営予備をこの方面に配置しなかったためであることが、容易にわかる。
もし数個の予備軍が、この戦線の後方にあって、使える状態になっていたならば、ハリコフ攻勢での大惨事は避けられたであろう」 |
5 技量不足のソ連指揮官 top
このハリコフでの大敗北は、ロシア人の自信に大きな傷跡をのこした。
それから二四年後の共産党第二〇回大会で、フルシチョフが、“スターリン絶対の神話”にとどめをさそうとした有名な演説のなかで、スターリンが、いかに“常識はずれの”行動をとったかを、明らかにしている。
しかし、一九四二年当時のこの惨たんたる流血の物語から、軍事的にはっきりと結論づけられることは、ソ連軍の戦車部隊は、数のうえではたくさん造られたけれども、まだまだ多くのことを学ばなければ駄目だ、ということであった。
なぜなら、駄目なのは、必ずしもティモシェンコのレベルの者たちだけではなかった。
さらに下の階級の者にも、重要な資質が欠けていたのである。
カツコフのような、有能な指揮官がたりなかったのである。
ソ連戦車部隊の下級、中級の指揮官の能力についてのドイツ軍の評価は、
「一九四二年の夏には“下”であり、す早く決定する能力を欠き、中隊や大隊のレベルでも、戦術的センスがない。
それに、わが機甲部隊の将兵のような、騎兵的勇敢さなど、全くない」というものであった。
あるドイツ機甲部隊の幕僚将校は、次のように書いている。
「彼らは、ドイツ軍の主陣地帯のなかで、大きな集団に固まったままウロウロと動き回っている。
その動きはおずおずとしていて、なんの計画ももっていない。
お互いの進路上にでて妨害しあい、我々の対戦車砲の前にノコノコと現れる。
我々の戦線を突破しても、その戦果を拡大しようとはせずに、動かず、ただぼんやりしているだけだ。
このころは、わが軍の対戦車砲や八八ミリ砲にとって、かきいれどきであった。
一門の火砲で、一時間に三〇台以上のソ連軍戦車を撃破したこともあった。
そのころ我々は、ソ連軍はうまく使いこなせもしない部隊をつくったものだ、と考えたものだが、それが一九四二〜三年の冬になるころには、もう腕前のあがった兆候が現れてきた……」
|

ソ連軍に恐れられた88ミリ対戦車砲
|
6 ドイツ軍、破竹の進撃 top
これより先、カツコフはツーラの郊外で、能力と決意と、そしてT34とがあれば、どういうことができるかということを示している。
だが、彼のような動きを、大規模に再現できるようになるまでには、ソ連戦車部隊は、苦難と損失の夏に直面しなければならなかったのである。
ハリコフでの敗北に続いて起ったソ連軍の危機は、前の冬のモスクワ前面での危機よりも、もっと重大なものであった。
ドイツ機甲部隊にとって、作戦期の気候はおあつらえむきだった。
そしてこれを食い止めるためには、ソ連戦車部隊は、その数でも、その指揮能力でも、余りにも弱かった。
ハリコフの戦線にブチあけられた穴から、クライストのドイツ第1機甲軍がなだれこみ、全く、思うがままに暴れ回ったのだった。
数週間のうちに、この部隊は南にくだって、コーカサスの西にある油田地帯のマイコプに達していた。
だが、ソ連軍にとってこれよりも大きな脅威は、ホト将軍のドイツ第4機甲軍であった。
この軍は、ハリコフとクルスクのあいだに突破口を開き、ポロネシでドン川に達し、それから南進してロストラに向うように命令されていた。
一〇日間でホトの機甲軍は、大草原をこえて二〇〇キロ前進し、戦車の巻き上げる褐色の砂煙が、その進撃のゆくてをしめすのであった。
クルスクとポロネシとの中間で、ホトの機甲軍は、ソ連軍の必死の反撃にあった。
だがソ連軍の戦術はまずく、T34は、ドイツ軍の対戦車砲の前に、頭から突っ込んでくるのだった。
そのため、ソ連軍は側面と背後から、ドイツの戦車部隊に攻撃されてしまった。
こうして、残るソ連軍の部隊をけちらしたドイツ第4機甲軍は、七月三日にボロネシに入った。 |
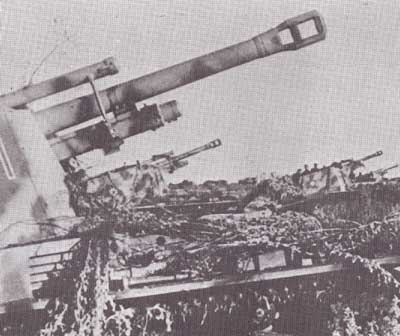
ドイツ軍105ミリ自走榴弾砲「ワスプ」

やったぞ!:ドイツ軍88ミリ対戦車砲は、
独・ソ戦でもその威力を発拝して大活躍した
|
7 ミスを犯したヒトラー top
しかしこの重要なときに、ヒトラーは致命的な戦略上の過ちをおかした。
これは彼の生涯で、初めてでも最後でもないのだが、彼はこの会戦初期の“電撃戦”の成功で有頂天になっていて、戦争で必要なのは、急いで動きまわることだけのように考えたのである。
クライストを、なんとか早くコーカサスに進出させようとあせったヒトラーは、第1機甲軍のドン川渡河を支援するため、ホトの第4機甲軍を一時南に向ける、と決心したのだった。
ところが結果的には、このホトの機甲軍は、クライストにとって助けになるどころか、むしろ妨害になってしまった。
ソ連軍の抵抗は弱く、いくぶん混乱させられた程度にすぎなかったからで、二つの機甲軍が渡河点でまじりあってしまったことは、実際には第1機甲軍の前進を妨害しただけに終ったのである。
七月二十九日になって、ホトは新しい命令をうけた。
彼は方向をかえて、パウルスのドイツ第6軍の目標になっているスターリングラードを、南西方向から攻撃することになった。
ホトの機甲軍は元々、この町に向うパウルスの軍の先鋒として動いていたのである。
そして、彼が第1機甲軍支援のためにいなくなったので、パウルスの軍には先鋒部隊がなくなってしまっていた。
いま、ヒトラーの新しい命令がきたが、これは余りにも遅過ぎた。
パウルスの第6軍は、まだスターリングラードヘの進路を前進し続けていたが、その前進は、機甲部隊がないためにひどく遅れていた。 |

ドイツ機甲部隊のベテラン:ルーマニア軍の
ドラガリナ将軍と握手をするヘルマン・ホト上級大将(左)
|
パウルスもホトも、スターリングラードに着くのが遅過ぎたのだ。
このヒトラーの過ちについて、クライストは戦後になって、その意見をこうのべている。
「第4機甲軍は、私の軍の左に並んで前進していた。
彼らは、七月末には戦わずに、スターリングラードを占領できたことであろう。
しかしその第4機甲軍は、私のドン川渡河を援助するために、南に向けられた。
だがその応援など、私には不必要だったのだ。
それは、私が使っている諸道路を、混雑させただけであった。
二週間たって、再び彼らが北に向けられたとき、すでにソ連軍は、これを食い止められるだけの兵力を、スターリングラードに集結させてしまっていた……」
8 教訓となったスターリングラード戦 top
ドイツ第6軍によるスターリングラード攻撃と敗北については、この本の主題ではない。
しかし、ソ連戦車部隊にとって、この会戦は非常に重要なものであった。
〔スターリングラード戦については、本シリーズ17巻『スターリングラード』にくわしい〕
それは、二つのことを意味したからである。
第一は、ホトやクライストがロシアの大平原で行った“電撃戦”というものは、成功はするがただそれだけで、勝利にはつながらないということを、薄々ではあるが、証明したことである。
第二は、ドイツ軍のボルガ河畔での挫折、さらにこれに続く大敗北の影響をうけて、ソ連戦車部隊の士気がかわりつつあったことである。
スターリングラードを護り抜いた将軍として、名声をあげたチュイコフ元帥は、一九四二年の夏の感想を、こう書いている。
「私は、敵の砲兵と歩兵や戦車部隊とのあいだの緊密な協同作戦、つまり正確な砲兵の弾幕射撃、砲撃と戦車攻撃との機敏な移動を予期していた。
しかし、実際はそうでなかった。
私がぶつかったものは、新しい戦法どころか、古くさい、ノロノロした、塹壕から塹壕への活気のない戦闘法であった。
……敵の戦車は、歩兵と飛行機の支援がなければ、戦闘をしかけてこない。
戦場では、外国の新聞が書きたてたような、ドイツの戦車兵のあっぱれな腕前や、勇敢で素早い行動などは、全く影をひそめていた。
実際は、全くその反対であった。
彼らの戦いぶりはのろく、非常に用心深く、そして断固としたところがなかった……」 |
9 かわりゆく戦車戦 top
スターリングラード戦をさかいにして、戦車部隊の戦闘はかわった。
両軍とも、新しい手法や戦法について、それぞれのやり方を学び取っていた。
ドイツ側では“電撃戦”の時代は終りをつげていた。
クライストが第1機甲軍を率いてコーカサスヘ進撃したのが、その最後のものであった。
どうみてもそれは、当初考えられたほどの成功ではなかった。
クライストは、マイコプをすぎてから、燃料の欠乏のためにゆきづまってしまった。
そしてスターリングラードでのドイツ第6軍の壊滅後は、ソ連軍がドン川を南下してきたため、左翼から致命的な脅威をうけることになった。
だが、ロストラを通って退却したために、“危機一発”のところで、クライストは壊滅だけは免れることができたのである。
“コーカサス、行ったり来たり”――これは、ドイツ軍将兵がこの作戦を皮肉っていった言葉である。
一方ソ連軍は、“電撃戦”戦法というものを、十分に自分のものにしたことは一度もなかった。
それは単に、彼らがこれを学ぶ時間がなかったからである。
この分野での、ティモシェンコのシロウトじみた冒険は、全くの災厄〔さいやく〕を招いてしまった。
この当時のソ連軍の指揮官は、多分上から下まで、グーデリアンやホトが、フランスでの作戦や“バルバロッサ”作戦の初期に行ったように戦車部隊を動かす能力など、もっていなかったであろう。
だからソ連軍の側からいうと、いまやドイツ機甲部隊の将兵が直面している機甲兵精神や戦法、兵器についての変化などを再検討しなければならないという不利など、全くかかわりのないことであったのだ。 |

沈む夕陽を浴びて進むドイツ軍歩兵部隊

潜望鏡型望遠鏡で射弾観測をするドイツ軍砲兵
|
10 機械化兵器にも変化が top
ところで、機甲部隊の戦闘の質をかえてゆくものは、なによりもまず兵器であった。
新しい重戦車――「ティーゲル」戦車と「スターリン」戦車は、三号戦車やT34とは違った世界のものであった。
しかし、これらのものよりもさらに大きな影響をあたえる変化が、両軍の機械化のうえで起りつつあったのである。
この変化とは、戦車というものが、もはや、無敵の“装甲した馬”ではなくて、弱い“動く大砲”でしかないということが、暗に認められてきたということである。
機械化兵器に、新しい種類のものが造り出されたのだ。T34や三号戦車の車体に、火砲を搭載した“自走砲”がこれである。
これは、グーデリアンよりもジューコフに適した兵器であった。
そしてドイツ機甲部隊の衰えてゆく精鋭たちよりも、腕前をあげつつあるソ連軍将兵によって、より上手に使われる兵器なのであった。
top
**************************************** |