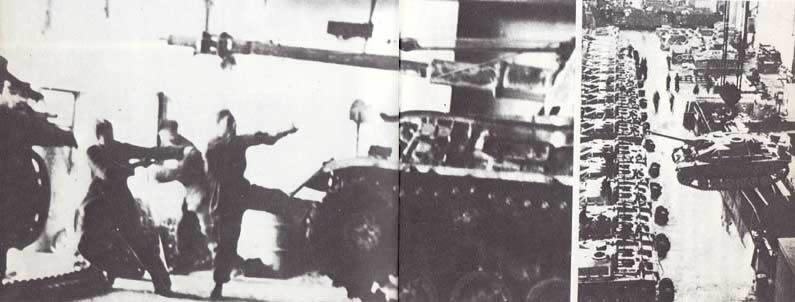|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9 10
11 12
8 グーデリアン、機甲軍を再建
ドイツ機甲部隊は、ナチ党の発展とともに、組織が拡充され、あれよあれよというまに、晴れの舞台に登場してきた。
しかし、その進展もドイツの政治上、経済上の分裂からくるシワ寄せをうけて、複雑な形に変ってしまった。
ヒトラーが、側近としてナチの取巻き連中を重用したため、結果として破廉恥〔はれんち〕な連中に、過大な権力をあたえることになってしまったのである。
そのよい例が、SS地上軍である。
ヒトラーのボデーガードとして生まれたSS〔親衛隊=シュッツシュターフェル〕は、急速に権力と組織がふくれあがり、ついにその一部が軍隊化した。
これがSS地上軍〔ワッフェンSS=武装親衛隊〕である。
この部隊は、エリート中のエリートと目されるようになり、ドイツ国防軍よりもはるかに多くの人的、物的資源を手に入れることができるようになった。
ゲーリング〔国家元帥、ドイツ空軍最高司令官〕も、これを真似て、空軍のかかに陸上戦闘部隊を編成するまでになっていた。機甲師団は、このようなドイツ軍内部の変動の波を、まともにうけてしまった。
|

機甲師団の突撃
|
1 SS地上軍も機甲師団編成 top
当初、SS地上軍は、数個の自動車代歩兵師団と戦車一個連隊をもっているにすぎなかったが、一九四三年のはじめには、SS地上軍自体で数個の機甲師団(最初の機甲三個師団は、SS地上軍の自動車化歩兵師団と装甲擲弾兵〔てきだんへい〕師団からつくった)を編成するまでにいたった。
これらのSS機甲師団は、SS機甲軍団として、前章にのべたように、ロシア戦線で、マンシュタイン将軍がハリコフで反撃に成功したとき、先頭をきって戦っていた部隊なのである。
SS機甲師団は、普通の陸軍の機甲師団よりも多くの戦車をもち(SS機甲師団の戦車大隊は戦車五九両をもっていたが、陸軍の機甲師団の戦車大隊は四八両しかなかった)、しかも最新型の戦車をほぼ完全定数だけ保有していたのである。
そのうえSS地上軍の指揮官たちは、ヒトラーの無茶な命令にさからって行動するときでも、陸軍の指揮官にくらべて、敢然として任務を遂行できる立場をとることもできた。
このような傾向は、ドイツ軍部の組織を政治的忠誠をもった“エセ軍部”のエリートで固めようとするヒトラーの悲願を具体化したものにほかならなかった。
ヒトラーのこの意図を拡大していくのに、最もふさわしい試験場は、野戦軍の中核である機甲軍であった。
2 ヒトラーの歓心かう設計家 top
ヒトラーのお気にいりの設計者や技術者のなかには、余りにもとっぴな計画をもっているため、実際に設計を担当している技術者たちのまともなやり方と意見を異にする連中がいたが、この中にはポルシェ博士〔スポーツカーのポルシェ、フォルクスワーゲン、ルノーPAなどの設計者〕のような者もいた。
ポルシェ博士の案は採用されなかったが、彼は「ティーゲル」重戦車から巨大な一八〇トン重戦車まで考えていたのである。
またグローテとハッカーの二人は、重量が一〇〇〇トン以上の戦車を造るように提案したりした。
ポルシェ博士のような連中は、ヒトラー(彼は技術にたいする関心が強かった)の歓心を買おうとして、風がわりな設計を考え、もっと緊急かつ重要な諸計画に必要な、ドイツのかぎられた資源、開発、生産施設を横どりしてしまったのである。
3 三軍バラバラに兵器を生産 top
さて一九四二年までは、工業界にたいする兵器生産の要求は、軍統帥部から直接だされていた。
陸、海、空三軍は、それぞれ独自の立場で生産工場を育成していた。
これらの工場は、慣例として、他の軍の仕事は一切やらない建前になっていたので、ドイツが各分野で資材の不足という事態に直面すると、やっかいな問題が起ってきた。
ある軍の専属工場は、注文量がへって、完全に操業するだけの仕事がなくなり“あそびが出る”という始末だった。
もちろん、戦車生産部門は、全体としてみれば、注文量がへって完全操業ができなくなることはなかったが、誤った指導による被害をかなりこうむったのである。
たとえば、補給部品を生産しているときに、古い型の戦車の改造要求が出されて混乱をまねいたり、さらに今度は、試作段階にあった新型戦車が、直接生産へと持ち込まれるということもあった。
このようなときに、大量の突撃砲の生産命令が出されたので、戦車の生産は縮小されてしまった。
適切な中央統制機関がないために、一九四二年には、ドイツの戦車生産部門は大混乱におちいっていた。
この間、ドイツ国防軍は、戦車と突撃砲の発注を続けていたが(しばしばヒトラー自身の命令で、変更されたり、取り消されたりした)、生産部門としては、盲目的に、この矛盾だらけの命令にしたがう以外に道はなかったのである。
ただSS地上軍だけは、このような混乱とは無縁の組織であり、陸、海、空三軍の要求よりも絶対的に優先させるという鉄則だけは、兵器生産部門にとって、けっして忘れてはならないことであった。
しかし、このような兵器生産面での無秩序な状態が、いつまでも続いたというわけではなかった。
4 シューベアが生産統制 top
アルベルト・シューベアが軍需相になったからである。彼はヒトラーのお気にいりとして、巨大なドイツ工業界と取組み、ヒトラーが誇大妄想からつくりあげた中央集権的国家組織の枠のなかで、良識と健全な権力分散化政策をたくみに織り交ぜて、驚くべき成果をあげたのである。
一九四二年には、ヒトラーは、シュペーア軍需相の進言どおりに命令を出すようになっていた。
スターリングラードの惨敗で、ドイツ機甲師団は大量の戦車を失ったが、シュペーア軍需相は、このまえから陸、海、空軍の各省にまかされていた兵器生産の統制という任務を一本化し、兵器資材の統制についての命令は、軍需省をとおさなければならないというシステムにあらためていた。
シュベーアは、この方法として、タテの組織として、一連の中央生産委員会制度を設け、このトップレベルの委員会に主要な兵器生産を統制させることにするとともに、ヨコの組織として中央生産連合を作り、原材料の管理に当らせることにした。
そして、この中央生産委員会と中央生産連合は、すべて民間の産業界の手にまかされることになったのである。
このようにして、SS地上軍を除いて、シュペーアは、ドイツ産業界にたいし、自らの手で自らの運命を決すべき立場をとらせるようにしたのである。
さて、ヒトラーは、スターリングラードの敗北によって、一時、自分の軍事的判断に自信を失ったかのようにみえた。
このヒトラーの“自信喪失”という変化は、ハリコフの戦いのときに、マンシュタイン将軍が、ヒトラーの意向にわずらわされることかく、自由自在に作戦を指導することができたという事実にハッキリ現われている。
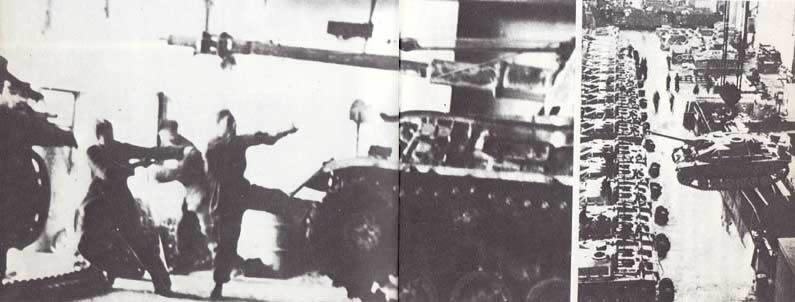
4号戦車の75ミリ砲搭の回転テスト 量産される突撃砲 |
5 グーデリアン機甲軍を再建 top
しかし、ドイツ機甲軍にとって、最も重要な変化は、ヒトラーがグーデリアン将軍をカムバックさせたということである。
グーデリアン将軍は一九四一年の末にヒトラーの信頼を失って解任され(ヒトラーはグーデリアンを許すことをしぶっていた)、一九四二年には心臓を悪くして休養していたのであった。
この起用は完全な方針転換であり、機甲軍の再建が当面の大問題となっている証拠でもあった。
一九四三年一一月、ヒトラーは、グーデリアン将軍を機甲軍総監に任命し、グーデリアン自身が起草した機甲軍憲章をみとめた。
このねらいは、ヒトラーが自らの手でつぶしてしまったような、機甲軍の再建にあった。
ヒトラーは、グーデリアンに、機甲部隊の組織と訓練に関する完全な指揮権をあたえた。
SS地上軍の機甲部隊も、ゲーリングが、ドイツ空軍のあまった兵員をつかって“私兵”としてつくろうと努力していた機甲部隊も、グーデリアンの指揮下におかれることになった。
グーデリアンはまた、シュペーア軍需相とともに、兵器の技術開発計画と生産計画を作成する権限もあたえられた。
これによって、共通の利益のうえにたち、しかも愛国心についてはなんの疑いもないこの二人の指導者が完全に協調して、分裂の激しかった兵器生産部門に、秩序を回復することになったのである。
グーデリアンは、機甲軍兵士をきびしく訓練して、本来の姿に引き戻すことと、機甲軍にたいし、真の勝利者にふさわしい兵器――戦車――を十分装備させることに、全精力をうちこんだ。
しかし、グーデリアンをうんざりさせたことは、国防軍の砲兵部門が、戦車よりも突撃砲が優先的に生産されている現状を、グーデリアンにチェックされまいとして、突撃砲は機甲兵力とは関係なく砲兵部隊のものだと主張して突撃砲をぶんどってしまったことである。
このような状況のなかで“合理的な統制”をするのはむずかしかったが、グーデリアン将軍は、戦車、突撃砲などあらゆる戦闘車両の生産、配備の割りあいをかえてしまったのである。
見方によっては、突撃砲の生産を優先するというやり方は、複雑な構造の戦車が生産されるのを待っているよりも、ドイツ軍にたいして、新型で、強力な火砲を簡単に配備しうる方法だといえるかもしれない。
突撃砲は基本的に防御用の兵器であったが、この新兵器ができたとき、ヒトラーは、これでドイツ軍はあらたな侵略が可能になったことを直観的にさとり、満足感にひたったのである。 |

ドイツ機甲軍の再建者:ヒトラー総統とならぶグーデリアン将軍(左端)

ドイツ軍Sd234型重装甲車
機甲師団の生まれたときから、装甲車は偵察任務などをうけもつ重要な兵器であった。初期の装甲車は軽武装でオートバイ部隊と協同で軽快な活動をした。のちにはこの型のような重武装のものがあらわれたが、360度旋回する砲塔ではなかった。戦車とくらべて装甲車の利点は、音のしずかなこと、高速なこと、機械的信頼性のたかいこと、走行距離が大きいことなどであるが、路外走行では戦車におとった
重量:8トン 武装:75ミリ砲1 乗員:4 最高時速:80キロ |
とにかく、グーデリアンは、あり余るほどの任務をかかえていたが、どの型の戦車を生産すべきかという問題に、早急に結論を下さなければならなかった。
三号戦車は一九四二年末には生産が中止され、車体は突撃砲搭載用に使われていた。
新しい軽戦車をという提案もあったが、中戦車、重戦車にたいする要求が強いので、放棄せざるをえなかった。
〔突撃砲(シュツルムゲシュッツ)は、ドイツ軍の創案した一種の自走砲である。
野戦用の火砲は、はじめ人力や馬でひいていたが、第二次大戦の頃にはしだいに機械化され、自動車またはキャタピラーつきの車両で牽引されるようになっていた。
これをさらに発展させ、これらの車両に直接各種火砲を装着したものが自走砲で、前面側面などに簡単な装甲をしたものが多かった。
自走砲をさらに進歩させ、戦車の車体に砲塔なしに直接、砲を取付け、戦車と同等以上の装甲をしたものが突撃砲である。
回転式の砲塔をもたないので、左右の射角が制限され、射撃方向の大きな変更は車体全体を移動させねばならぬ欠点があったが、反面、砲塔がないため内部の空間が大きく、戦車よりも大型の砲を装備でき、また製作工程も簡単であるという利点があった。
ドイツ軍は、旧式戦車の車体を利用し、また損傷した戦車を再生して突撃砲を生産した。
初め突撃砲は砲兵の兵器であったが、のちに戦車が不足してからは機甲部隊もこれを使用するようになった。
なお「パンテル」「ティーゲル」戦車が出現してから、これらの車体に一段と強力な新型の砲を取付け、対戦車突撃砲ともいうべき「ヤークトパンテル=八八ミリ砲」「ヤークトティーゲル=一二八ミリ砲」が造られた。
これらは駆逐戦車とよばれた。突撃砲も駆逐戦車も、広い意味では、ともに自走砲であるといえよう〕
|

生産中の「ディーゲル」戦車

鉄道輸送中の「パンテル」戦車
|
6 「ティーゲル」「パンテル」両戦車 top
「ティーゲル」〔虎〕戦車は時期尚早であったが、ごく少数が一九四二年九月レニングラード戦線で、その後チュニジア戦線でも使われた。
「ティーゲル」戦車はロシア戦線で初登場したが、軟弱な土地にはまりこんで数両を捨てさる結果となり、ソ連技術者たちに性能を調査されることになってしまったのである。
「ティーゲル」戦車は大急ぎで部隊に配備されたが、このときにはまだ技術面に不安が残っており、車体も大きすぎて扱いにくい面もあり、戦法も変えなければならなかった。
乗員たちが“家具運搬車”とよんだのも無理からぬところである。
「パンテル」〔ひょう〕戦車も実用をいそぎすぎた。
当初、三二五両のうち回収できたもの全部がドイツ本国に送り返されて、大きな欠陥、とくに照準装置、発動機、操縦装置などを改造しなければならないという、みじめな結果となってしまった。 |

ドイツ軍「パンテル」戦車
この戦車はソ連軍のT34/76型や米英軍の新型戦車に対抗するためにつくられ、三号、四号戦車にかわるべきものであった。新型強力の75ミリ砲を装備した
重量:45トン 武装:75ミリ砲1(初速毎秒935メートル)、7.9ミリ機関銃2 乗員:5最高時速:46.5キロ
|
戦車の生産体制がひどい混乱におちいっていたというととは、「パンテル」戦車がまだ実戦に投入されないうちに四号戦車(これだけが当時生産されていた唯一の戦闘能力のある戦車だった)の生産を中止してはどうかという提案がなされたという事実に、端的にあらわれている。
この問題は、一九四三年五月に四号戦車の生産中止要求が撤回されるまで、延々と議論されたのである。
7 突撃砲を緊急配備 top
こうした状況のなかで、戦車の絶対数は不足し、スターリングラードでの大損害がこの傾向に輪をかけた。
このためグーデリアン将軍も、ついに自己の信念をまげ、正反対の方策をとらざるをえなくなってしまった。
すなわち、いくつかの機甲師団に戦車の代用品として、一時的に突撃砲を装備することになったのである。
このような応急処置をしないことには、ただでさえ、少なくなっているドイツ機甲師団の装甲車両の数を増やすことはできなかった。
グーデリアン将軍にとって、わずか四八両の戦車しかもたない戦車大隊二個で、ドイツ機甲師団が行動しているという現実は、当初、五六一両の戦車をもっていたドイツ機甲師団の姿からみて、全くみじめなものに感じられたことであろう。
かっては、栄光につつまれたドイツ機甲師団は、最悪の状態にあえいでいたのである。
突撃砲は旋回範囲がかぎられているため、機甲師団の指揮官たちの戦術に制約をくわえることになった。
たとえば、前進中(機甲師団はスピードにものをいわせて前進し、攻撃するものなのだ)、突撃砲は三六〇度、全局旋回できない大砲なので、最前線でおきる予期せぬ状況に、間髪をいれずに対応することはむずかしかった。
このため、突撃砲は後方の歩兵部隊と共に行動し、先頭を突進する戦車に火力の支援をあたえる役目をするにすぎなかった。
このようにして、ドイツ機甲師団にとって、戦車はかけがえのない貴重なものとなり、敵に捕獲されかかった戦車を救出することは、将兵の生命を救うことよりも大切なのだ、と主張する指揮官も現れるほどだった。
さて、ドイツ機甲師団は、大損害をうけ、戦力は低下していたが、無力になったというわけではなかった。
ドイツ機甲師団はえぬきの将兵たちで、まだ生残っている者は、疲れ切ってはいたものの、戦意に燃えており、彼らの比類なき体験と技術を、新入の徴募兵に叩き込むことはできたのである。
ただ“機甲師団魂”を吹きこみ、厳しい訓練をほどこす時間のゆとりがないのが問題だった。
機甲師団を戦線から引きあげて、長いあいだ後方におくということは、まず無理であったし、事実、一九四三年以降は、南ヨーロッパ、西ヨーロッパにむけて連合軍の重圧が厳しさを増していたので、よく訓練された将兵は各地の戦線に分散されていったのである。
8 奮起する機甲師団の将兵 top
しかし、祖国ドイツの名誉をまもるために、国防軍の全戦闘部隊の将兵たちの心のなかに、必死ともいえる愛国心がめばえていた。
もちろん、ドイツ機甲師団の将兵たちも、グーデリアン将軍のすぐれた統制力、指導力のもとに、あらたな決意に燃えて立ちあがろうとしていた。
だが、ドイツ軍将兵たちは“野蛮なソ連軍の大群”が巻起した恐ろしさを身にしみて味わわされていたので、将来に不安を感じ、心配するようにもなっていた。
このため、絶望の淵から立ちあがりつつあるドイツ軍将兵の士気をたかめて、不安をぬぐいさるのに、何か大きなショックが必要とされていたのであるが、一九四三年一月、アメリカ大統領ルーズベルトが、カサブラン力で「無条件降伏」の方針を明らかにした。
〔一九四三年一月、米大統領ルーズベルトと英首相チャーチルがモロッコのカサブランカで会談し、米英軍の作戦計画を検討した。このとき日独伊の枢軸国とは、妥協による講和はせず「無条件降伏」を要求するだけであるということが確認された〕
これをきいたドイツ機甲師団の将兵たちは、強い衝撃をうけ、猛烈な闘志を燃えたたせたのである。
グーデリアン機甲軍総監は、わずか数ヵ月間に、失われていた秩序を回復し、機甲兵力を再建するという大仕事をやってのけた。
グーデリアンは、祖国の存亡にめざめて戦意を取戻した機甲軍の将兵たちが、改善された兵器をもち、強力な随伴歩兵(いまや、名誉のために装甲擲弾兵とよばれていた)とともに戦場にのぞめば、連合軍を粉砕できるのではないかと信じていた。
グーデリアンは、これからの戦いはドイツ軍の“質”と連合軍の“量”の勝負になることは十分承知していたが、正しい戦闘原則にもとづいて戦うならば、ドイツ軍が最終的な勝利をおさめうると確信していた。
ドイツ機甲師団を支えていたのは、この必勝の精神にほかならなかったのである。
top
**************************************** |