|
****************************************
Home ドイツ空軍 ドイツ海軍 Uボート 機甲師団(日本 ドイツ ソ連 米英) コマンド 空挺作戦 秘密兵器(ドイツ 米英ソ)
ドイツ機甲師団 電撃戦の立役者
(『Panzer Division』ケネス・マクセイ著、加登川幸太郎訳)
ポーランドを席巻し、ついでドイツ軍はオランダ・ベルギーを踏みにじり、フランスへ雪崩込んだ。
この第二次大戦初期のヒトラーの電撃戦の主役をつとめたのは、空軍とならんで、地上では機甲師団であった。
ドイツ機甲師団は、その後、中東、アフリカ、ロシアと広大な舞台を縦横に暴れ回った。
そして、彼らは序幕から終幕まで主役をつとめたのである。
 |
〔著者〕ケネス・マクセイ
1941年以来、英陸軍将校として戦車連隊、機甲師団に勤務、最近少佐で退役。
その間、ヨーロッパ、アジアで戦闘に参加し、MC勲章をうける。
退役後、軍事評論に専念。
著書に英国戦車部隊小史「青い草原のかなたへ」西部戦線の英軍機甲部隊奮戦の物語「ピミー丘の暗い影」本シリーズ「ロンメル戦車軍団」などがある。 |
 |
〔総編集長〕バリー・ビット
英国の著名な戦史・軍事評論家。ブリタニカ百科事典の海戦項目の執筆者、サンデイ・タイムス・マガジンの戦史関係顧問、ハーネス社版「第二次世界大戦史」編集者、BBC放送局制作「大戦」シリーズの監修者である。 |
はじめに バリー・ピット(総編集者)
top
第二次世界大戦がはじまってから三〇年もたった現在、“戦車”は全くなじみぷかいものになっている。
しかし、第二次大戦の直前には、当時の権威ある軍事評論家でさえも、きたるべき戦争では、機動力として、馬がいぜん重要かつ決定的な役割りをはたすであろうと予言していたのである。
このように、今日ではほとんど信じられないような風潮のなかで、すぐれた洞察力と創造力をもったごく一部の軍人たちは、“戦車”のもつ無限の可能性と将来性を信じ、機械化された装甲兵力を重視せよと、新しい戦術理論を提唱していた。
だが、頭がかたく、保守的な軍首脳は、これらの進歩的軍人の意見に耳をかそうともせずに、彼らを邪魔ものあ使いしていたのである。
今日、その功績を高く評価されているイギリスの有名な軍人たち――フーラー、マーテル、ホバート、ブロード、パイル各将軍やジデル・ハート陸軍大尉〔第二次世界大戦ブックスシリーズの総監修者〕――も第二次大戦前は“新しがり屋の戦車キチガイ”というレッテルをはられて、さんざんな目にあわされていた。
フランスのシャルル・ドゴールも、戦車を活用すべきことを積極的に主張していたが、彼の理論も、フランス軍首脳には全くうけいれられず、先駆者の悲哀をかみしめていた。
しかるに、ドイツでは、第一次世界大戦末期のにがい経験から“戦車”については、全くちがった評価をしていた。
一九一八年〔大正七年〕第一次大戦でドイツが降伏においこまれたとき、連合軍戦車にじゅうりんされた記憶がなまなましく、戦車が破壊的威力をもった驚異的兵器であることを、体験的に知っていたのである。
二〇年後、ドイツは、この経験をいかして、どの国にもおとらぬ戦車部隊――機甲兵カ――を創設した。数量の点では、連合軍におよばなかったものの、すぐれた技術、独特の戦術理論をもち、この点では、連合軍にくらべてはるかに強力なものであった。
しかも「ドイツ機甲師団」は、体力気力ともにすぐれた、えりぬきの将兵からなっていた。
彼らは、猛訓練にたえつつ、ベルサイユの恥辱をはらし、祖国の誇りを取り戻そうという熱意にもえていた。
彼らは、戦士中の戦士であり、その素質は、ドイツ空軍将兵にまさるともおとらぬ優秀なものであった。
このドイツ陸軍の“サラブレッド”ともいうべき「ドイツ機甲師団」がどのようにして誕生し、育てられ、戦場のスターの座についたか、ということは、第二次世界大戦の物語のなかでもとりわけ興味ぷかいものがある。
「ドイツ機甲師団」は、まさに電撃戦の立役者であった。彼らは、ドイツ軍の先鋒として、北ヨーロッパを駆けめぐり、ポーランド、オランダ、ベルギー、フランスをひきさき、雪のロシア戦線、灼熱のアフリカ戦線にも、キャタピラーをきしませて、縦横無尽にあばれまわった。
そのスピードと破壊力は、軍事技術上の“革命”とさえ思われた。
本書の著者ケネス・マクセイは「ドイツ機甲師団」をひきいたルントシュテット、マンシュタイン、グーデリアン、ロンメルなどの名将の活躍をいきいきとよみがえらせるとともに、「ドイツ機甲師団」が、その能力と理論を余りにも過信したために、やがて“栄光の座”をすべりおちて“悲惨な末路”をたどっていく姿を、あますところなく描きだしていくのである。
|
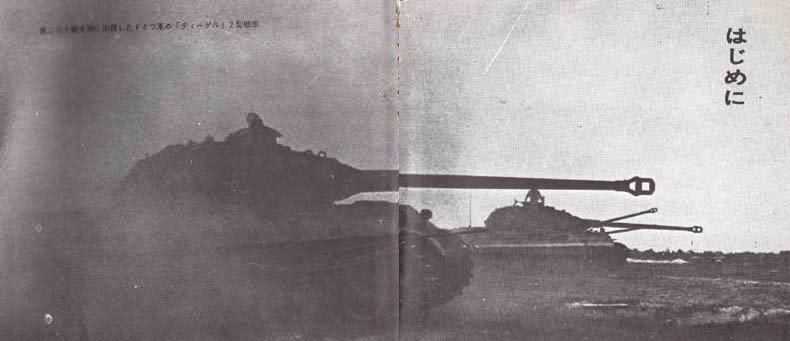
第二次世界大戦末期に出現したドイツ軍の「ディーゲル」2型戦車
|
訳者あとがき top
本書『ドイツ機甲師団』の語るドイツ陸軍興亡の歴史は、ドイツだけの物語でばない。
新軍建設期の摩擦や抵抗などは、どこの国にもある例であるし、既存の軍を、科学技術の発達と他国との競争に遅れぬよう、編成装備や戦略戦術をたえず改変していくことのむずかしさを述べている。
独特の機甲師団をつくって四年目、“電撃戦”で世界を驚倒させたドイツ陸軍も、五年後には競争に負けた。
一応の軍備をもつことは、さしてむずかしくないが、その威力を三年、五年とたえず改善維持していくことは、並大抵のことではない。
日本海軍の例で、巨大戦艦「大和」や「武蔵」が航空攻撃のまえに手も足もでなくて沈んだ軍事界の変化は、設計開始からわずか一〇年後の出来事であった。
ドイツ機甲師団の電撃戦に蹴ちらされた国々の軍備など、なんのためにもっていたかといわざるをえない。
“兵”はがんらい凶器であるが、時代おくれの軍備など、存在すること自体が犯罪である。
なんにもならないのに力をもっていると錯覚させるおそれがあるからである。
ドイツ機甲師団の連続電撃戦のころ、私は北支那方面軍参謀として北京にいた。
ポーランド戦のころ、我々の関心は、ソ連軍機械化部隊によるノモンハンの敗戦にあったので、ヨーロッパどころではなかった。
ノモンハンが第二次大戦での電撃戦に先だつ、旧式軍と新式軍との戦いの見本であった。
日本陸軍は、その教訓を十分に汲み取らぬうちに、また汲み取ったとしても、なんともできぬままに大戦に突入した。
大部分が、前近代的兵備のまま戦い続けたのであった。
敗戦の混乱のなかで知られずにすぎたが、降伏直前に満州にとびこんできたソ連軍の大機甲集団は「祖国戦争」満四ヵ年のみがきのかかった精鋭であり、ドイツ機甲師団の比ではなかった。
そして、これがドイツ軍の創始した電撃戦の大戦最終版であった。
戦後版でいえば、一九六七年六月の、イスラエルの中東戦争であろう。ともに威力は決定的であった。
訳出にあたって、原文にある註と訳者の注を、それぞれ( )と〔 〕で区別した。
日本語版監修者のことば 中野五郎 top
第二次世界大戦こそ、人類史上で空前のグローバル・ウォアであった。
しかもそれは独・伊両軍対英・米・仏・ソ連合軍の欧州決戦と、日本軍対米・英‘中国連合軍の太平洋決戦という二つの巨大な顔をもった、双頭の阿修羅王(戦争を好むインドの悪神)の荒れくるった最大、最悪の戦争であった。
日本軍が一九四二年八月から六大月にわたり、ガダルカナル島で悪戦苦闘していたとき、ドイツ軍は、スターリングラードで血戦死闘を重ねていた。
また日本軍が一九四四年六月、マリアナ沖大海戦を戦っていたとき、欧州戦線では、ノルマンジー上陸作戦が決行されていたし、さらに一九四五年二月、連合軍のヤルタ会談が開かれた直前に、日本軍は硫黄島で玉砕した。
このように、第二次大戦を正しく理解するためには、太平洋戦と欧州戦の二大正面を総合的に把握し、その千変万化の実相をパノラマ的に展望、批判することが肝要である。
そこに、日本最初で唯一の「第二次世界大戦ブックス」の貴重な価値と、いま全国的に大反響をまきおこしている理由がある。さらに大きな特色は、このシリーズがいわゆる多項目、分冊形式の便利な『戦争百科事典」の役目を果していることである。
これこそ国民必読の「戦争と平和の書」である。
この原本(バレンタイン社版)の総監修にあたった、英国の世界的な軍事評論家リデル・ハート卿の「平和を欲するならば、戦争を理解せよ!」という警句には、我々日本国民にもしみじみと考えさせられるものがある。
 |
翻訳 加登川幸太郎(かとがわ・こうたろう)
1909年(明治42年)北海道生まれ、陸軍士官学校42期、陸軍大学校卒。陸軍戦車学校教官、北支那方面軍参謀、陸軍省軍務局軍事課員を歴任。第2方面軍、第35軍、第38軍、第13軍参謀として、ニューギュア、レイテ、仏印、中国を転戦、終戦時中佐。昭和22〜25年、GHQ戦史課勤務。昭和27〜42年、日本テレビ勤務、編成局長。「風雪二十年」の制作を担当。
訳書に本シリーズ「零戦」「B29」「沖縄」がある。 |
 |
日本語版監修 中野五郎(なかの・ごろう)
1906年(明治39年)7月東京日本橋生まれ。東大法学部卒。朝日新聞社に在勤18年。本社社会部、仏印特派員、ニューヨーク特派員、太平洋戦争開戦によりアメリカに抑留され、1942年、野村・来栖両大使 一行とともに交換船で帰国。 1942年、朝日新聞退社 後第二次大戦の調査、研究、執筆に専念。主な著書 「タクワ」-「サイパン」「硫黄島」「カッパ版太平洋戦争」「モリソン太平洋戦争史」など多数。 |
|