|
****************************************
Home ドイツ空軍 ドイツ海軍 Uボート 機甲師団(日本 ドイツ ソ連 米英) コマンド 空挺作戦 秘密兵器(ドイツ 米英ソ)
米・英・ソ秘密兵器――レーダー、ミサイルから原爆まで
(『 Allied secret weapons
』ブライアン・フォード著、野田昌宏訳)
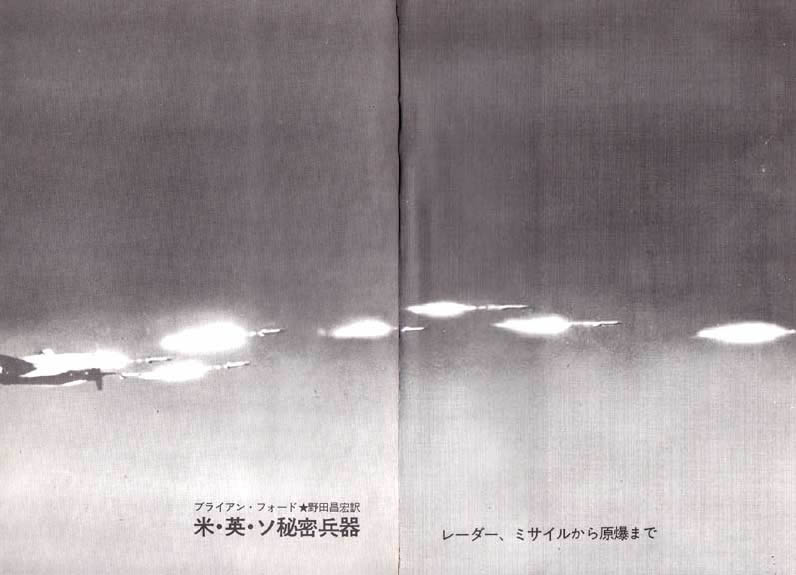 |
はじめに 科学の戦争 バリー・ピット(総編集者)
top
原子爆弾をただ一つの例外として、第二次世界大戦で使われた秘密兵器は、事実上すべてドイツが独占していた――という結論をだすのは、別に抵抗を感じるほどのことではない。
もちろん、あまりにも安易な考えだと言われるのを承知なら――のことである。
おそらく、この種の俗論が大手をふってまかりとおっている最大の原因は、こんにちの宇宙開発の基礎となっているのが、例のまことにドラマチックなA4兵器体系〔V2号のこと〕であること、そしてドイツ人という国民が、新しい兵器を考えだしたり、いま使っている兵器を改良したりするときにみせる、あの全くカケネなしのすばらしい創造的才能にあるのだと思われる。
そしてさらに、このシリーズに入っている一冊――『V1号V2号』〈恐怖のドイツ秘密兵器〉――が、ドイツ軍の恐るべき秘密兵器の全貌を白日のもとにならべてみせたことも、やはり大きな原因の一つとなっているに違いない。
そこでその本の著者であるブライアン・フォードが、今度はそのテーマを全く逆の角度から眺めてみよう――というねらいでペンをとったのがこの本である。
第二次世界大戦中、連合軍が極秘のうちに必死で積み重ねた様々な努力は、ドイツ軍が繰出してくる新兵器にたいして、すかさず打てる巧妙な手を大いそぎで考えだすことに、かなり大きな比重がかけられていたといってもよいだろう。
それもできることなら敵に気づかれないように、敵が活用している技術そのものの盲点をつき、それを逆手にとって、相手の陣営を混乱させ、ひっくり返してしまおうというわけである。
この、いわば高度な“柔道”的技術がすばらしい成功をおさめた例の一つに、ドイツ空軍の無線誘導システムの裏をかいて、それを全く無力にしてしまったケースがある。
それも、妨害電波をだしてドイツ軍の方位電波をひっかきまわすといったあらっぽいやりかたではなく、本物とみわけのつかない偽の方位電波をだしてドイツの爆撃機をひっかけ、満載されている大量殺戮〔さつりく〕を目的とした“お荷物”を“ちがった番地”に配達させてやろうという寸法なのである。
著者も本書のなかで書いているように、見事にこの手にひっかかったドイツ空軍の爆撃機のおかげで、可愛そうに縁もゆかりもない北海地方〔イングランドの北西岸〕の人里はなれた荒地が、それこそ徹底的な猛爆をくらった、などという例もあるくらいなのだ。
ところで、戦時下の医学についても、当然、秘密兵器の中に組入れられるべきものがある。
たとえば、あのすばらしい妙薬「ペニシリン」などがそうだ。
ペニシリンのおかげで、何千何万の連合軍兵士の生命がすくわれ、前線に復帰してあらたな戦力となったのだ。
兵器といえば人殺しの能率を競うという、まことに不快な感覚がかならずつきまとうのだが、この秘密兵器ばかりはべつである。
それはそれとして、やはりここで戦闘用の兵器を見逃すわけにはいかないだろう。
いわゆる通常兵器のたえまない改良努カ――たとえば、より高速でより操縦性のよい戦闘機、より強力な装甲とより大きな爆弾搭載量、そしてより大きな航続距離とより高い上昇限度をねらう爆撃機などの開発――を繰返しているうちに、とんでもないアイディアがふと浮かび、それが具体化してついには連合軍をすばらしい勝利へと導いた――などという例もたくさんある。
これらのなかでも、バーンズ・ウェーリス博士の、ほとんど伝説的とさえいえる様々な業績は、特筆に値するものだろう。
本書の中にもくわしく書かれているが、飛行機の最短縮構造、地震爆弾、跳躍爆弾(ダム破壊爆弾として有名)なども彼の業績の一部である。
しかし秘密兵器中の秘密兵器――もしもこれが五年早く開発されていれば、おそらく第二次大戦は、はじまる前に終っていただろう、とまでいわれている究極の秘密兵器は、いまやすっかりなじみのものになってしまっているが、その開発にまつわる秘話の価値もうすれてしまったというわけではない。
原子爆弾の出現をめぐって各国が政治や軍事面でみせた疑心暗鬼の姿は、この二十世紀半ばという時点を、いわゆる“力の政治”の新しいスタイルが現れた時期とみなすきっかけとなったのである。
もはや軍事大国といえども、なにかをねらって自国を全面戦争にまきこむような真似はできないのだ。
最悪の事態でも、局地的な軍事衝突がやっとだろう。
アラモゴード〔アメリカ、ニューメキシコ州〕の実験場で、完成した原子爆弾の第一号が炸裂したそのときから〔一九四五年七月十六日〕、人類はひどくまわりくどい道をたどって、その結論を探し続けている。
しかし、重大な危険は依然として我々につきまとっており、この爆弾が果して究極の“平和の維持者”たりうるか、それとも、交戦国のどちらが生残るかをきめる手段にしかなりえないのか、という疑問にたいする解答はまだ出されていない。
さて、秘密兵器として十分に取上げて価値がありながら、これまでほとんど問題にされたことがない分野についても、この本は取り扱っている。
たとえば、そのアイディアが当時の科学技術の水準よりもはるかに先行していたために実現しなかった超兵器、あるいは基本的な科学の原理を堂々と無視していることには当人は全く気がつかず、せっせと実験を繰返し続けた珍兵器、はては理論上うまくいくはずなのに、ついに失敗に終った“幻の新兵器”……などの悲しくも愉快なコレクションの数々である。
これらは着想そのものは面白いのだが、実質的には奇抜すぎるものが大部分である。
しかし中には現在になって初めて実現の可能性がチラリときらめく、すばらしいアイディアも確かに含まれているのである。
この本は連合軍とドイツ軍との秘密兵器開発計画のありかたについて、いくつかの大変興味のある質問を我々になげかけている。
たとえばその一つは、実際により多くの戦果をあげた秘密兵器を、よりたくさん開発したのは一体ドイツ軍か、それとも連合軍か?
また生産能力、労働力(もちろん頭脳もふくめて)、使用された経費の額から考えたとき、ドイツ軍は、たとえばV2号などの贅沢な報復兵器の開発にうつつをぬかすのと同じ程度に、通常兵器の改良にも努力していた、といえるかどうか?
さらに、とくにイギリスの場合だが、どうみても可能性ゼロのはかない虹を追って時間や労力を空費することを許していたのは、一体どんな組織だったのか?
これらの疑問にたいする解答は、双方の国民の政治的・文化的背景と複雑にからみあっている。
ナチ・ドイツのような独裁政権のもとでは、その権力者によってえらばれた計画には必要なものがふんだんにあたえられ、倹約を心がけたり無駄使いを恐れたりすることなど、全くないのである。
もちろん、それはそれでよい。
ただし、一体誰がその計画をきめるのか? 問題はここである。
ナチ・ドイツの場合、それは高度な軍事専門家のグループなどというものではなく、単にヒトラー総統の気まぐれにすぎなかった。
そしてさらにその気まぐれは、もっと効果的でもっと重要な計画を無神経に修正したり、あっさりと破棄したりすることになってしまったのである。
そして、この総統の気まぐれに異論を唱えることのできる者がいたとしたら、よほど度胸のすわった人物だったに違いない……。
ドイツではこのような状態だったので、ドイツ軍の秘密兵器という大行列が、鳴りものいりで華々しくまかりとおったそのあとには、”破棄された計画”という名の恐ろしく高価な死体や、まだヒクヒクしている貴重な計画の断片が、辺り一面に散乱していたというありさまだった。
その点、連合軍は、全く対照的であった。
確かに連合軍の秘密兵器の開発計画には“料理人が多過ぎた”という批判はあたっている。
多くの部門がそれぞれ対立する意見を論じあい、言いたい放題のことを言いあったことによって、有効な開発計画が足をひっぱられた例もないとはいいきれない。
しかし、それよりもっと大切なのは、このために実現不可能な計画がそのまま突っ走って貴重な軍費を無駄使いするのを最小限に食い止めたという事実だろう。
現実にこの行方のために大損失をうけたという例はないし、誰にも言いたいことを言わせるというしきたりは、ある意味で、デモクラシーというものがもつ、じれったい側面でもあるのだ。
しかし第二次大戦中、秘密兵器の開発にそそがれた努力は、はかりしれない利益を戦後の世界にもたらした。
とくに医薬品の分野に関しては、全世界が心から感謝をささげなければならないだろう。
だがそれと同時にその努力は、同じくらい大きな、新しい脅威を、この世界に巻き散らしてしまったのも否定できない事実なのだ。
そしてそれらの秘密兵器の大部分は、こんにちもなお“秘密”として存在し続けているのである。
訳者あとがき top
考えてみると、ちょうど私などが、新兵器と聞いただけで反射的に胸をときめかす世代の末端に属しているのであろう。
真珠湾の特殊潜航艇に始る我が国新兵器ヘの期待は、戦局の深刻化とともに祈りにも似た思いにまで高まり、耳かき一杯で敵兵三人が殺せるウラニウム火薬や「レキシントン」そっくりの制式空母〔呉で学友が目撃したというのだから、被雷直前の「信濃」だろうか〕、校庭をかすめた葉巻〔一式陸攻〕が胴体につっていたというロケット弾〔はたして本当に「桜花」だったのだろうか?〕などのことを、声をひそめて話しあったものである。
九州帝大の工学部の教授であった父親の研究室には、戦争の進展とともに様々な敵の兵器――きれいな懐中電灯の形をした「おもちゃ爆弾」、米潜が宮崎沖であげたラジオ・ゾンデ、撃墜されたB29の電探の残骸など――が持ち込まれていたが、昭和二十年に入って機雷投下による港湾封鎖が始ると、なんとかこれを爆発させずに回収する方法はあるまいか――という難問を西部軍がもちこんできた。
その機雷の火薬を、本土防衛斬込隊用の爆雷に転用したいという裏悲しい話なのである。
一方、持ち込まれた不発の音響機雷を分解した父親は父親で、信管を作動させる感知機構の増幅器の精巧さに舌をまき、製造元であるRCA社のネームプレートに、おもいもかけず戦争でとだえていた旧友の見事な出世ぶりを知ったという状態で、小学生の息子にまでその感激を吹聴する始末だからどっちもどっち、本書の英対独のような技術戦争の火花など散るわけもなく、日米技術力の格差の大きさを思い知らされるばかりである。
広島に続いて長崎に新型爆弾が投下された翌日、爆弾と同時に投下されたというパラシュートつきの、一〇〇ポンド焼夷弾ぐらいの装置が、正体を調べてくれと持ち込まれてきた。
これが、原爆の炸裂したさいの爆風を感知してマリアナの基地へ送信する爆発確認用の、いわゆるテレメータリング装置だったのだが、父親がそのときズバリと正体を見破ったのかどうかは聞きもらした。
戦後、進駐軍にみつかると重労働刑で沖縄送りになるというので、近くの井戸か何かに放りこんでしまったが、ロンドンの戦争博物館にでも売ればいい金になったのに――と惜しくてしかたがない。
訳出にあたって、原文にある注と訳者の注を、それぞれ( )と〔 〕で区別した。
翻訳 野田昌宏(のだ・まさひろ)
本名、宏一郎。1933年福岡県生まれ。学習院大卒。フジテレビ・ディレクター。
SF翻訳家、軍事・航空研究家。SF関係の著書・訳書が多い。 |
日本語版監修 中野五郎(なかの・ごろう)
1906年東京生まれ。東大法学部卒。朝日新聞仏印・ニューヨーク特派員。1942年交換船で帰国。48年朝日新聞退社。
第二次大戦関係の執筆に専念。主な著書「タラワ」「サイパン」「硫黄島」「カッパ版太平洋戦争」
「モリソン太平洋戦史」訳書に本シリ−ズ「パールハ−バー」など多数。 |
top
**************************************** |