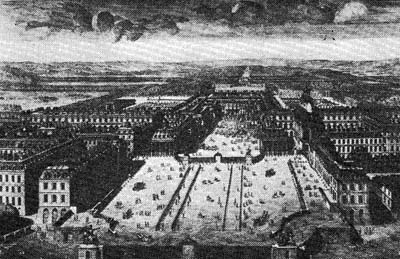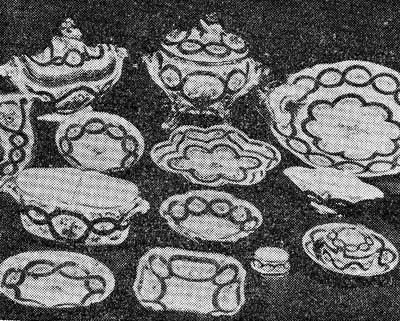|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11 12
13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰
10 ルイ十五世の寵姫の生涯――ポンパズール夫人の時代――
1 幼い王妃 top
ジャンヌ・アントワネット・ポワソン、将来のポンパズール夫人(女侯爵)は、一七二一年十二月パリにうまれた。
ルイ十五世(在位一七一五〜七四)がまだ幼少で、オルレアン公フィリップ(一六七四〜一七二三)が摂政をしていた時代である。
父フランソワ・ポワソンは、当時の有名な富豪パリ兄弟のもとにつとめていたブルジョワで、母は美人のほまれが高かった。
ジャンヌ・アントワネットが三歳のとき、父はある事件にまきこまれ、責任をとるようなこととなり、八年ほど国外にのがれた。
夫の不在中はポワソン夫人が家政をきりもりしたが、身を入れて世話したのは徴税総請負人で金持ちのル・ノルマン・ド・ツルヌエムであった。
彼がジャンヌの父だとも、うわさされた。
ジャンヌの幼年時代については不明のようだが、九歳のとき、ある女占い師が予言したという。
「このお嬢さまは、いつか王さまのお気に入りになりましょう。」
家族たちはなかば疑い、なかば期待したが、彼女はそのころ「幼い王妃」とよばれるようになった。
そしてこの予言が実現したとき、ポンパズール夫人は、この占い師にむくいたと伝えられる。
彼女は大きくなるにつれて、ダンス、歌、芝居などを教えこまれた。
ツルヌエムも金にあかせて、この点で力をいれた。
また彼女は絵筆もとり、めずらしい鳥を飼ったり、植物に関心をもち、多芸多才であった。
女性としての魅力にもあふれ、一年ほどいた修道院では、そこを去ったあとあとまで、尼僧たちがなつかしんだという。
ただ健康だけにはめぐまれず、病身だったらしい。 |

ポンパズール夫人(=デティオル夫人)
|
パトロンのツルヌエムのおかげて、彼女はふつうの娘ではむつかしい邸宅のサロンに出入りができ、さらに才芸にみがきをかけた。
結婚適齢期に達したとき、すでにパリの社交界では、ポワソン家の娘は王さまの愛人にふさわしいとうわさされた。
しかしこれまで王が貴族でない、ブルジョワの女性を寵愛したためしはない……。ともかく一七四一年三月、十九歳の彼女は、パトロンの甥、同じく徴税請負業のル・ノルマン・デティオルと結婚した。
デティオル夫人は結婚前からの社交生活をつづけ、当時の高名な上流失人たちのもとを訪れるとともに、自宅にもサロンを開き、モンテスキュー、ボルテールなどの名士もここに姿を現わした。
ルイ十五世の王妃、ポーランドの王女であったマリー・レクザンスカは一七二五年、二十二歳で、十五歳の王と結婚した。彼女は素直で気立てがやさしく、信心もあつく、十年ほどのあいだに七人の子をもうけ、夫に、「いつも寝て、いつも妊娠して、いつも産むのですこと!」と抗議していた。
やがて年上の王妃は、夫婦生活をいやがるようになった。
それだけに王は、王妃とちがった若い女性に心をひかれるにいたった。
そして一七三三年ごろから、キール侯という貴族の娘たちがつぎつぎと寵姫に選ばれた。
パリの人びとがはやしたてたように、
「一人はほとんど忘れられ もう一人もくず同然
三人目はいまが盛り 順を待ってる四人目もいずれ末っ子にゆずるだけ
一族あげて選ぶとは実があるのか、不実なのか」 |
というわけだ。
まずマイイー伯夫人、つぎにバンティミーユ侯夫人、ローラゲ夫人、それから彼女たちの妹ラ・ツルネル夫人、すなわちシャトールー女公爵の称号をえた女性とつづいた。
このシャトールー夫人が一七四四年十二月、二十六歳で死去したとき、王は心から悲しんだ。
しかし翌年春、王は早くも新しい女性に夢中になるのである。
その女性、デティオル夫人(後のポンパズール夫人)はすでに、狩りの途次のルイ十五世に注目されるようにつとめていたが、宮廷にしのびこんだこともあると推測されている。
これについては、彼女の母ポワソン夫人のいとこが、王太子につかえており、その手引きによったのではあるまいか、というわけである。
だがルイ十五世とデティオル夫人との出会いのまえに、少しルイ十五世時代について書いておこう。
一七一五年、年少で即位したルイ十五世に代わって、前述のようにオルレアン公フィリップが摂政となった。
その政府がとくにとりくんだのは、ルイ十四世時代にあらわれた財政難の処理であった。
この点で有名なのは、ジョン・ロウ(一六七一〜一七二九)をめぐる金融恐慌であろう。このスコットランドうまれの財政家は、国富の増進には貨幣が必要であり、また貨幣よりも紙幣のほうが便利と考えた。
彼はこの構想を摂政政府にうりこみ、許可された私立銀行は王立銀行に改組された。
一方でロウは、北アメリカ貿易上の独占権をもつルイジアナ会社を設立した。
これは翌年東インド会社をあわせて、両インド会社となった。
異常な投機熱のうちに株価は上昇し、「旭日昇天の勢い」にあったロウは一七二〇年、この銀行と会社を合併させた。
この年、彼は財務総監にもなった。
しかし会社の経営は散漫であり、紙幣は乱発され、同じ一七二〇年、株価の暴落、紙幣価値の急落によって恐慌となった。払い戻しをもとめて銀行に殺到する人びとは「死人がでるさわぎ」をくりひろげた。
十二月、ロウは国外にのがれ、二九年三月、貧窮のうちにイタリアで世を終えた。
ロウによって政府は債務を軽減することはできたが、この事件は経済上フランス人を臆病にし、銀行や信用制度の発達をおくらせたといわれる。
そして事件のほとぽりがまださめきらないうちに、一七二三年摂政フィリップが世を去った。
脳出血の恐れがあり、医者から放蕩をつつしむようにと注意されていたオルレアン公は、「退屈な生活よりも快楽を選んで」悔いなかった。
それから国政をうごかしたのは、すでに七十歳をこえる老フルーリー枢機卿(一六五三〜一七四三)であった。
彼は有能な政治家で、まず重商主義的な保護統制政策によって、経済の発達をはかった。
北アメリカ(カナダやルイジアナ)、インド、アンティーユ諸島におけるフランス植民地との貿易や、近東貿易が発展した。
マルセーユ、ボルドーなどの海港諸都市は繁昌し、貿易商、船主などのブルジョワは富み栄えた。
農業生産も発達し、資本主義的経営を行なう富農層もあらわれてきた。
外交上でもフルーリーの政策は大過なく、イギリスと協調して平和を保つことにつとめた。
しかしフルーリーの死の少しまえから、フランスはオーストリア継承戦争(一七四○〜四八)に関係する。
これは元来、マリア・テレジアのオーストリアと、フリードリヒ二世のプロシアとの戦いであり、オーストリアと同盟したイギリスに対して、フランスはプロシアとむすんだ。ヨーロッパ大陸の勢力争いのうえで、多年オーストリアと対立してきたフランスは、このときも同じ政策をとったのである。
もはや九十歳に近く、年のせいか、万事なりゆきにまかせていたフルーリーは、一七四三年この戦争中に他界した。
2 愛しき君 top
ルイ十五世は長じて容姿端麗、気品に富み、教養も豊かであったが、一面、臆病で、意志が弱く、人前に出ることを奸まず、非情であり、陰性で、スパイを放ったり、私信を検閲したりするようなところがあった。
聡明でありすぎて懐疑的、快楽に徹しすぎて無為、そしてしだいに人間嫌いにもなっていった。
とくに狩りが好きな王は――それは退屈(アンニユイ)をまぎらわすためでもあったが――これに使用する犬や馬の訓練に熱心であった。
こうした王に対して、皮肉な言葉が残っている。
「王は犬馬のため、まったく犬馬の労をいとわない。」
また王は「秘密情報部」のようなものをつくり、外交上などで工作をしたらしいが、有効な成果はあがらなかった。
一七四三年、フルーリーの死により、みずから政治をとることとなった三十三歳のルイ十五世は国民の期待を集めた。
しかし王は「平身低頭」と「阿諛追従(あゆついしょう)」しか知らず、「君主のつとめ」について学んでいなかった。
翌年、オーストリア軍がアルザス地方に侵入し、これに対してメッスに出陣した王はこの地に病んだ。
その全快を祈って、国民は各地で教会に行き、パリのノートル・ダム寺院だけでも六千のミサが行なわれた。
人びとがルイ十五世のことを、「愛しき君ルイ」と名づけたのは、このときのことといわれる。 |

ルイ十五世
|
しかし王は怠けぐせからぬけだすことができず、国民の期待を裏切ってしまった。
「愛しき君」というよび名も、皮肉なものとなった。
そして王が新しい寵姫を見つけたのは、このころのことである。
一七四五年二月、ルイ十五世の王太子ルイとスペイン王女との婚儀がとり行なわれた。
この月をつうじて、これを祝する舞踏会がにぎにぎしく開かれたが、最高潮はベルサイユ宮におけるそれであった。そこへは民間からも参加できた。二月二十五日夜、仮装舞踏会のうちに夜もふけてゆく。
王は暑くなったので、ふとマスクをとった。
そして身近にいる女性――いきいきとした声の女性と言葉をかわす。
その女は月の女神ダイアナの仮装をしていた。
彼女もまたマスクをとる。ジャンヌ・アットワネット・デティオル夫人にほかならない。情事がはじまったことは、だれの目にも明らかであった。 |
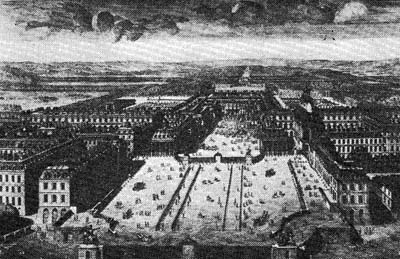
1772年頃のベルサイユ
|
その後、パリ市庁における舞踏会に出席した王は、ふたたび夫人の姿を見つけた……というよりも、再会は約されていたのであろうか。
夜食をともにし、それから彼女の家まで送っていったといわれる王は、翌朝九時、ベルサイユ宮に帰り、ミサののち夕刻まで眠りをとった。
夫人が王に身をまかせたのは、この夜か、それとも少しあとのことか、それは明らかにされていない。
ともかくデティオル夫人は、ルイ十五世の新しい寵姫としての道をあゆむ。
一七四五年四月、夫人は宮廷の劇場のボックスや夜食会に姿を現わし、廷臣たちはこの女性が宮殿に寝起きしていることを、うたがえなくなった。
宮廷では、「まさか王が、ブルジョワから寵姫を選ぶことはあるまい」と思われていた。
ところが、そうではなかった。
ブルジョワたちは、これこそ日ごろ威張(いば)っている貴族に対するしっぺ返しと喜びあい、一方、貴族たちは王がベルサイユに、町方の女性をつれこんだことを、信じられぬようすであった。
夫人はその良い趣味にもかかわらず、貴族階級にはパリのブルジョワどもを代表しているようにみえた。
とくに貧乏になりつつある貴族たちは、新興成金のブルジョワたちに敵意をいだき、したがってそれに属している彼女をきらった。
しかしそうはいっても、大宣教で、政府にも用立てているパリ兄弟が背後にひかえているデティオル夫人の実力には、貴族たちは到底およばなかった。
つまり彼女の登場は、当時のブルジョワ勢力のあらわれとも見ることができよう。
一方、夫のル・ノルアン・デティオルはなにも知らず、地方に旅行しているあいだに、ことが決定的になっていったらしい。妻を愛し、尊敬している夫は、ぜひ帰ってくれと望んだが、効果はなかった。
ピストルをとりだし、ベルサイユに行って妻をとり返してこようと、いきまく一幕もあったが、結局、ル・ノルマンは泣き寢入りした。
当時の上流社会では、妻にそむかれる夫はめずらしいことではなく、デティオル夫人のほうも、とくに心を苦しませたようすは見えない。
なお二人のあいだには、一男一女があったようである。
3 ロココの女性 top
一七四五年五月十一日、ルイ十五世が王太子とともに出陣したいまのベルギーのフォントノワの戦いで、フランス軍はイギリス・オランダ連合軍に勝利をえた。
この戦いののち、デティオル夫人は、ポンパズールの領地をえて、ポンパズール候夫人(女侯爵)と袮し、いまや名実ともに、ルイ十五世の寵姫となった。
王はこれまでになく幸福そうであった。
ポンパズール夫人は小柄ではあるが、均整がとれ、上品な顔だち、つぶらな瞳、きれいな歯ならび、甘美な微笑、かがやくような皮膚をもって、人びとを魅了せずにはいなかった。
夫人をきらった廷臣さえ、彼女よりも美しくあることはむつかしいといい、またその才芸を認めざるをえなかった。
ポンパズール夫人がルイ十五世の「寵姫」であったのは、正確にいえば、一七四五年から五〇年ころまでの約五年ほどである。
五一年から五二年、王と夫人の関係が変化してゆき、二人はべッドをともにすることをやめたらしい。
つまりそれ以後、彼女は王の一種の「女友だち」となっていった。
それは王に、これまで経験しない「家庭的雰囲気」をあたえることでもあった。
夫人は性的に淡白であり、そこで刺激をうるためにめずらしい食事や媚薬を用いたが、こうした食事は彼女を肥満させ、またこの種の悩みは、美しさの大敵である“しわ”をもたらしたといわれる。
それにしても「肉体」にたよらず、「才芸」だけにたよらねばならぬ彼女の地位は、たいへんな疲労、神経の消耗をあたえるものであったらしい。
とくに連日連夜、饗宴の役にあたるような場合は、不眠と不消化をきたし、肺結核といわれ、ただでさえ丈夫でない夫人を苦しめた。
彼女はできれば少し距離をおいたところから、王に楽しみをあたえようとし、浮気や情事の手つだいさえしている。
たとえばベルサイユの一隅、「鹿の園(パル・コー・セール)」には、夫人の黙認のもとに、王のひそかなお相手、すなわち若い女性たちが集まった。
上流の家庭はその子女を送りこむことに懸命であり、娘を推せんする父の手紙も残っている。
夫人の死後、「二十年は処女、十五年は娼婦、七年は女衒(ぜげん=遊女の斡旋を仕事とする者)」などといわれたのは、この事実によるものであろうか。
ポンパズール夫人の会話はひじょうに機知に富んでおり、おもしろい話題が豊富であった。
また彼女はパリ警察の記録類を読んで、そのなかの興味深いニュースを伝えたり、また廷臣あての手紙類をかってに見て話題にした。
王のために楽器をひき、かつ歌った。芝居のせりふをいくらでも暗誦してみせ、そのために、王はそれまで無関心だった演劇を見はじめたという。
若いときから歌や踊りを習っている夫人は、アマチュアとしてはすぐれた俳優でもあり、また当時の貴族たちは一般に歌舞音曲につうじていたので、夫人がタレントをもとめれば、それに不自由はしなかった。
夫人は種々の規則をもうけて、劇団さえつくった。
ベルサイユの座席十四にすぎない小劇場は彼女の考案になるもので、最初に演ぜられたのは、一七四七年一月、モリエールの『タルチュフ』であったという。
夫人みずからもいろいろな劇で主役をつとめ、五年間で六十一の芝居、オペラ、バレエが、総計百二十回余演じられたという記録もある。
そしてこの小劇場を絵筆をもって飾ったのがブーシェ(一七〇三〜七〇)である。
当時の美術は軽快、繊細、優美、典雅に情緒や官能をゆすぶり爛熟(らんじゅく)した生のたのしさを感じさせるロココ様式である。
ブーシェは彼が傾倒したワトー(一六八四〜一七二一)、彼の弟子フラゴナール(一七三二〜一八〇六)らとともに、このロココ美術を代表する画家であり、とくにポンパズール夫人の保護をうけた。
夫人はまた建築で王を喜ばせた。
しかしこれは一面では、宮殿をかえるというルイ十五世の一つの趣味を助長することとなった。
たとえば一七五〇年には三百十三夜、五一年には三百二夜、王がベルサイユ以外ですごした記録があり、年平均しては百七十三夜を数えるという。
そして夫人が関係した建築では、エブルー邸、すなわち現在のエリゼ宮(大統領官邸)は有名であろう。
建造物といえば、貴族の子弟のため、一七五一年パリにつくられることとなった士官学校(エコール・ミリテール)にも、ポンパズール夫人の創意があずかっている。
これには王はむろん、金融家パリ・デュベルネが協力し、建築はガブリエル(一六九八〜一七八二)があたった。
開校したのは一七六〇年で、八四〜八五年ナポレオンが学んだ。
なおバンセンヌにあった王立磁器工場が、一七五六年セーブルにうつされたが、夫人はこの産業を保護し、磁器愛好の風潮を助長したことも忘れられない。
ポンパズール夫人が啓蒙思想家を保護したことも、有名である。ディドロの『百科全書』の刊行が、イエズス会(ヤソ会)を中心とする保守勢力によって妨害されたとき、彼女はその刊行を助けている。
王がなにか知りたいときには、夫人はこの「禁断の書」を持ってこさせた。
まえから夫人のサロンの客であったボルテールに、彼女はオペラを書かせた。
重農主義者で侍医のケネーはその著『経済表』(一七五八)を、王室の印刷所でつくることができたし、自然科学者ダランベールは年金をあたえられた。こうした夫人の態度は、彼女が当時の啓蒙思想の地盤であるブルジョワと関係があることを示している。
そのうえで、彼女は啓蒙思想を真に理解していたとも、また一種の人気取りにすぎなかったともいわれている。
趣味がひろい夫人は家具、陶器、銀器、衣裳、宝石、絵、本、酒など、すばらしいコレクションをもつていた。 |
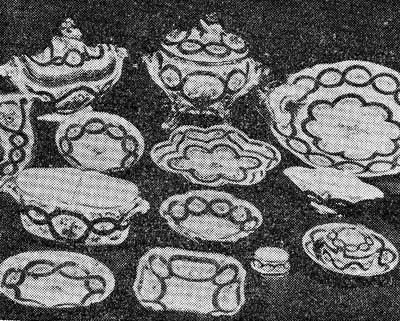
セーブル焼き
|
それは彼女の死後、在庫品しらべに二人がかりで一年以上も要したほどであり、また三千五百二十五冊の蔵書が残されたという。
「エレガントな夫人は、当代のすべての美術に影響をあたえた」というような言葉もあるが、彼女のこうした収集は美術上の生産をうながしたといえよう。
4 外交革命 top
前述のオーストリア継承戦争は、その後、両交戦諸国ともに疲れ、決定的な勝敗かつかないままに、一七四八年アーヘン(エクス・ラ・シャベル)条約で講和が成立した。
それは原則としてすべての占領地をたがいにもとに復したが、個々の点ではプロシアがシュレジエンをうるなど、利をえた国もあった。
得るところがなかったフランスでは、パリの物売り女たちは口論で相手をののしるときにいった。
「講和のような、おバカさんめ!」
ともかくこの戦争のあとも、オーストリア対プロシア、およびイギリス対フランスの対立はかわらず、とくにオーストリア女帝マリア・テレジアはプロシア王フリードリヒ二世を深くうらみ、軍備などの充実をはかるとともに、外交上、プロシアを孤立させようとした。
そのためオーストリアはフランスへ接近をこころみる。
前にオースリトアがむすんだイギリスは、自国の利益を追求し、信頼できる同盟国ではなかったのだ。
しかしフランスとオーストリア、ブルボン王家とハブスブルク王家はすでにヨーロッパにおける優越をめぐって、抗争することひさしい。
したがって両国の提携はすぐには成立しがたいであろう。
ところでイギリス、フランスの植民地における戦いは、オーストリア継承戦争中も行なわれているが、一七五五年ごろ、北アメリカにおいて再びはじまった。
両国間の全面的な戦争の危機もせまっている。
こうした情勢はイギリスとプロシアを接近させ、一七五六年一月、それはウェストミンスター条約の成立となった。
これよりさき、オーストリアの政治家カウニッツは駐仏大使としてパリに行き、マリア・テレジアの命によってフランス側と交渉していた。
しかしまだフランスには、オーストリアとの同盟は戦争にまきこまれるとして反対の声もあった。
カウニッツは友好をあたためたのちウィーンに帰り、宰相の地位につき、これまでどおり対フランス政策をつづけた。
そこヘイギリスとプロシアの接近である。
これはフランス側のためらいを一掃させた。
なお反対はあったが、フランスにとって孤立はなによりも危険ではあるまいか。
こうして一七五六年五月、フランス・オーストリア間にベルサイユ条約が成立し、相互の防禦的な援助などを約することとなった。これはヨーロッパ国際関係上の大変動であり、「外交革命」ともよばれる。
この外交革命におけるポンパズール夫人の役割は、しばしば大きく評価されている。
なかには、夫人を軽蔑しているフリードリヒ二世が、自分の牝犬を「ポンパズール」などとよんでいたことに対して、彼女がうらみをもった結果だというような見解もある。
しかし一方では、外交革命を推進した中心はルイ十五世であり、夫人は交渉の仲介をつとめたにすぎないとされている。
それはともかく一七五六年夏、オーストリアの機先を制してプロシアは攻勢にでた。
いわゆる七年戦争(一七五六〜六三)のはじまりである。
そしてプロシアは重大な苦境にたったものの、よくこれをきりぬけて、この七年戦争も結局戦前の状態にかえる形で終わりをむかえた。
しかしフランス軍は一七五七年十一月、ドイツのロスバッハでプロシア軍に大敗し、その後も不振をつづけ、植民地戦争でもイギリスに完敗するなど、はなはだかんばしくなかった。そして一七六三年二月、英仏などのあいだにむすばれたパリ条約は「フランス史上、最高にみじめな条約の一つ」といわれる。
これによってフランスは、北アメリカ植民地の多くを失い、インドでもわずかな根拠地を残すのみとなって、イギリスに屈服してしまった。
この責任はだれにあるのか?
こうなってくると、オーストリアとの同盟が伝統にそむいた政策であっただけに、非難の声も高くなった。
真の責任は王と国務会議にあり、あるいは戦いの不手際は軍人の責任であるが、矢面(やおもて)に立たされたのはポンパズール夫人であった。
それは夫人にとって痛手であった。
一人になると、彼女は泣きくずれ、夜も眠れなかった。
王は狩りで気をまぎらし、その疲れから熟睡もできたが、いつも屋内で、もの思いに沈むことが多い夫人は、気持ちが救われるときがなかった。
「私が死ぬとすれば、悲しみからです」
と、彼女は苦しさの一端をもらしている。
事実、パリ条約から一年と少しして、一七六四年四月十五日、ポンパズール夫人は心身ともに疲れはてて世を去った。
肺の病いのためといわれる。四十二歳。
十七日午後おそく、ルイ十五世は宮殿のバルコニーに立った。
つめたい雨が庭園に降りそそぐたかを、小さな行列が門を通ってパリに向かう。そこのある教会に眠りたいというのが、夫人の願いである。
行列が視野から消えさるまで、王は身うごきもせずに見送っていた。
「かわいそうな夫人、パリヘの出立に、この悪天候とは……。」二筋の涙がその頬(ほほ)をつたわった。 |

ポンパズール夫人(1764年)
|
5 国民の墓場 top
ポンパズール夫人は政治問題には積極的でなかったようであるが、ルイ十五世の身辺にもっとも近い者として、少なからぬ影響をあたえたと考えられよう。
いわゆるポンパズール派が形成されていたが、彼女の背後にあったパリ・デュベルネと弟モンマルテルの金の力は、戦争、外交、宮廷にとって必要であった。
また夫人は個人的に、ペルニス(一七一五〜九四)やショワズール(一七一九〜八五)などを寵愛した。
前者は外交革命に一役を演じ、後者はそのあとをうけて外相となり、さらに陸海軍大臣をもかねて、七年戦争中および戦後のフランスを指導した。
公的な面で夫人が責任をとわれたのは、この七年戦争とともに、宮廷の浪費――建築、旅行、饗宴、贅沢な私生活など――である。
これについては夫人を目の敵(かたき)にする側から、過度の非難もよせられている。
しかし貧富の差がはなはだしかった当時のフランスにおいて、都市下層民や農民たちの困窮をよそに、宮廷の浪費は改善されず、戦費の増大とあいまって、財政の混乱がつづき、これに夫人が関係していたことは否定できまい。
つぎのような言葉は、大革命前の十八世紀フランス、旧体制(アンシャン・レジーム)フランスの実情の一端を物語るものであろうが。
「宮廷は国民の墓場である。」
「フランスでは人口の十分の九は飢餓で死に、残りの十分の一は飽食で死ぬ。」 |
財務総監マショー(一七〇一〜九四)による財政改革――すべての収入に課そうとする「二十分の一税」のこころみも、ポンパズール夫人たちの支持はあったが、とくに僧侶階級のはげしい反対によって成功せず、マショーもその地位をしりぞいた。
一七五七年一月五日の夕方、ダミアンという男が短刀をもっておそい、王を傷つけた。
王に反省をうながすためとも、発作的な精神状態からともいわれる。
とらわれたダミアンは三月二十八日、四時間にわたる身の毛もよだつ責苦ののち、息絶えた。
ルイ十五世の言葉として、つぎのようなものが伝えられている。
「自分のあとには大洪水がくるだろう(あとは野となれ、山となれ)。」
じつは王はこの言葉を口にしていない。
しかしルイ十四世の「朕は国家である」がその時代をあらわしているように、これもまたルイ十五世晩年の風潮を物語るものであろう。
|

デュ・バリー夫人
|

マリー・アントワネットと子供たち
|
この晩年のルイ十五世はデュ・バリー夫人(一七四一〜九三)を新しい寵姫として、あいかわらずの生活をおくっていた。
それでも大法官モープー(一七一四〜九二)は、保守・反動勢力の中心であるパリ高等法院に対する司法改革から政治・社会改革まで、ひろく着手しようとした。
それは、近代化された啓蒙専制君主政の道を志向していたともみられよう。
改革が根をおろすまえに、一七七四年五月、ルイ十五世は天然痘で世を去った。
王太子ルイはすでに一七六五年、父王に先んじて死んでいた。
孫のルイ十六世(在位一七七四〜九二)は側近にあやつられて、モープーをその地位から追い、改革をこわしてしまった。そしてこのルイ十六世がまだ王太子のとき、一七七〇年結婚した相手が、オーストリア帝室ハブスブルク家の皇女マリー・アントワネット(一七五五〜九三)である。
あるときルイが、太陽王の時代から生き残っていた老元帥と語ったというエピソードがある。
「将軍は三代を見てこられたが、それについてどうお考えになるか。」
答えはつどのようであった。
「ルイ十四世の御代では、一語もさしはさむ者はございませんでした。
ルイ十五世時代には、人びとは私語いたしておりました。
陛下(ルイ十六世)のもとでは声高にもの申しております。」 |
たとえばボーマルシェ(一七三一〜九九)の『フィガロの結婚』(一七八一)では、下僕のフィガロが侍女シュザンヌをめぐり、知恵才覚において主人アルマビバ伯爵をへこましてしまうのだ。
これは当時の僧侶・貴族・平民という身分制社会からすれば一種の危険思想であろう。
しかもこの芝居は一七八四年四月、パリの異常な興奮のうちに上演されたのである。
そしてそのころまでに、アメリカ合衆国も成立し、、自由と平等の新風が旧大陸へも吹きこんでいた。この独立戦争にアメリカを援助したフランスは、イギリスに対する勝利の快感に酔ったものの、さらに財政難を深めた。
いろいろな面で国民の、とくに実力をそなえたブルジョワの不満は高まり、フランス絶対王政の危機は深まってきた。
しかし狩りと錠前いじりにだけ情熱をもち、優柔不断でおよそ王らしくないルイ十六世は、「赤字夫人」とよばれるような浪費家の王妃とともに、破局へ進んでゆく。
ルイ十六世即位の一七七四年、財務総監となった重農主義者テュルゴーが試みようとした自由主義的改革、それはフランス絶対王政が革命をさけながら、近代国家へ移行するチャンスであったかもしれない。しかしこうした王家と反動的な貴族勢力は、テュルゴーの政策を理解できず、支持せず、彼は七六年早くも失脚した……。
たしかに、「大洪水」がくるのである。
一七八九年、フランス革命がはじまり、その激動のうちに、九三年、ルイ十六世とマリー・アントワネットはともに刑死するであろう。
top
**************************************** |