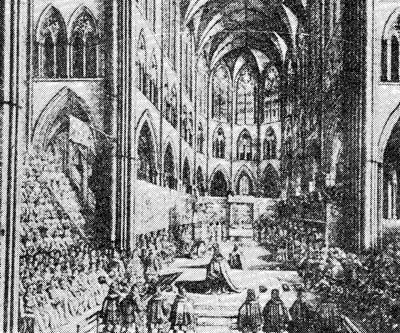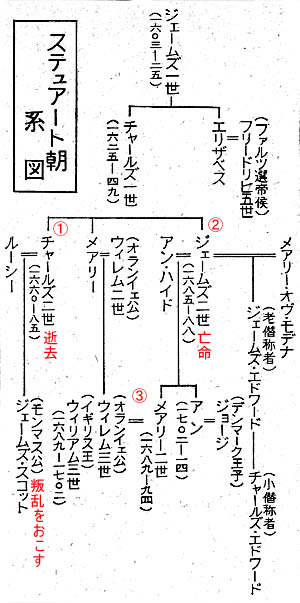|
****************************************
Index 1
2 3
4 5 6
7 8
9 10
11 12
13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰
4 イギリスの王政復古から名誉革命へ
1 チャールズ二世の帰国 top
イギリスでは護国卿オリバー・クロンウェルの死(一六五八)後、事態は共和制から王政復古にむかった。
一六六〇年五月二十五日、たくさんの人びとがドーバーの海岸に集まっていた。帰ってくるチャールズ二世(在位一六六〇〜八五)を一目でも見るためである。
船から下りたった王の肉欲的な厚い唇、頑丈な鼻、人を茶化すような目は、今までのピューリタンになれていた国民感覚には、まったくそぐわないものであった。
チャールズは国王軍の敗北後大陸に走り、一六五〇年スコットランドからイギリスに侵入することに失敗してからは、王政復古まで亡命をつづけた。
彼は放縦な生活をおくり、オランダで若い女と関係して一人の庶子をもうけ、これをモンマス公(一六四九〜八五)に叙した。のちのモンマスの乱の主人公である。
亡命中チャールズを忠実に補佐したのが、バイト(のちのクラレンドン伯、一六○九〜七四)で、一六五八年大法官の称号をあたえられた。
チャールズの帰国前、イギリスでは四月に選挙が行なわれ、暫定議会が召集された。新議員には国王派や長老派が多く、九〇パーセントは、王の復位を支持していたといわれる。 |
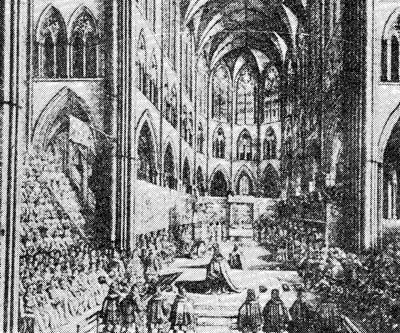
亡命先オランダから帰国したチャールズ二世の戴冠式
|
この議会に対して、王の使者が復位のための条件を提示した。
これが「プレダの宣言」で、バイトの筆になり、王がオランダの同市で声明したものである。
この宣言はピューリタン革命中の行動に対する大赦、土地購入者の権利、信仰の自由の三点を確認し、しかも絶対君主の復活ではなく、王と議会という伝統的体制の復活を約束していた。
そこで議会はただちに宣言の受諾を決定し、王のイギリス上陸が実現したわけである。
復位した王は、三つの約束に忠実であったろうか。
大赦については、主としてチャールズ一世の裁判に参加したものが除外され、十三名が処刑された。
クロンウェルの墓が十二年目にあばかれて、遺体を刑場につるしたのち、首をウェストミンスター・ホールでさらしものにした。
革命中に没収された王や教会の土地は、もとにかえった。
国王派で土地を没収されたものは特別の請願もしくは普通の訴訟で、これをとりもどす権利をあたえられた。
しかし自発的に土地を売り払ったものには、補償がなかった。
土地をえた側では長老派は国王派が売り払った土地を手に入れていたので、所有権をみとめられた。
ところが独立派は王や教会の没収地を購入したので、無償で土地を旧所有者にかえさなけれぜならず、大打撃をうけた。
宗教問題では、王政復古に大きい役割を果たした長老派が期待をよせたが、王は彼らをイギリス国教会のなかへ包括しようとした。
しかし一六六一年五月ひらかれた議会は「騎士議会」とあだ名されたことからもわかるように、長老派が減少して国王派が大多数を占め、ピューリタンに竍する弾圧立法を行なった。
第一の「都市自治体法」(一六六一)は、「イギリス国教会の儀式にしたがって聖餐(せいさん)の聖礼典をうけないものは、都市の公職に任命もしくは選出されない」と規定している。
都市が、ピューリタンの勢力の中心であったからである。
第二の「礼拝統一法」(一六六二)によって、ピューリタニズムを国教とすることには終止符がうたれた。
すべての聖職者や教師に、国教の一般祈祷書の使用が命ぜられ、約二千名の聖職者が追放された。
第三の「宗教集合法」(一六六四)は、同一家族に属しない五名以上のものが、イギリス国教会の方式によらない宗教上の集会に出席することを禁止し、累犯(るいはん)者を七年間植民地に追放することにした。
最後に「五マイル法」(一六六五)が制定され、「本王国の法律に違反して非合法な宗教集会において説教しようとするものは、従来、牧師、副牧師、牧師補であった都市の五マイル以内にきてはならない」ことになった。
これは彼らを、支持者である大衆から隔離するものである。
2 ドーバーの密約 top
一六六〇年、チャールズ二世はクロンウェルの航海法を更新、拡充した。
当時はロンドンの実業界ばかりでなく、宮廷も貿易には熱心で、親王、大臣や上流社会のめんめんが貿易会社に出資した。たとえば王の弟で、海軍総司令官であったヨーク公ジェームズ(一六三三〜一七〇一)が、王立アフリカ会社の初代総裁となり、東インド会社の株を買っている。
一六六四年、イギリスはアフリカ西岸のオランダの根拠地を占領し、アメリカ大陸でもニュー・ネーデルラントをとって、ニュー・アムステルダムをニュー・ヨークと改めた。

戦争とペストに痛みつけられて、さらにロンドンに大火事が起った |
そして、第二次イギリス・オランダ戦争(一六六五〜一六六七)がおこったのである。
ところが戦争の最中、一六六五年の春から六六年末にかけて、猛烈なペストがイギリスをおそった。
西アジア方面からオランダをへてきたものである。
ロンドンが中心で、ひどいときには死亡者が、一週間に七千名におよぼうとするありさま。
人口五十万のうち、七万が死んだという。
宮廷はハンプトン・コートからソールズベリーに避難し、少なからぬ聖職者が信者たちを見すてて逃げだした。
このときピューリタンの牧師が生命の危険をおかして、そのあとをうめたが、だれも法律違反であるとして訴えうるものはなかった。
悪いことはつづくものだ。ペストがおとろえだしたころ、大衆にとって、「神の怒り」の証拠とも見られる不幸がおこった。
一六六六年九月の第一週、東風のもとでロンドンに火事がおこり、四日間で一万三千戸を焼いたのである。
この大火によって、イギリスの戦時財政は極度に悪化した。
一六六七年六月、オランダの艦隊がテムズ川河口に攻めこみ、ケント州のチャタム港をおそって四隻を焼き払い、旗艦を曳き去り、イギリスはブレダの和を講ずることをよぎなくされた。
このように戦争指導がうまぐゆかなかったことから、クラレンドンは議会の攻撃をうけ、ペストや大火まで彼のせいにされ、一六六七年八月辞職した。
そのあとはクラレンドンのような一人の大臣ではなく、一団の大臣が王をたすけて政治を指導することになった。
この一団は彼らの頭文字をとって「キャバル」とよばれ、一種の内閣であった。
しかし連帯責任ではなく、大臣が個々別々に王と交渉をもち、王からの信頼度もさまざまであった。
王は「キャバル」を利用して、外交の二面政策を実行した。
一方ではフランスのルイ十四世に対抗するため、一六六八年オランダ、スウェーデンと三国同盟をむすぶとともに、他方では一六七〇年ルイ十四世と「ドーバーの密約」をむすんだ。
これは正規の外交ルートをとおさず、王の極秘の個人的交渉にもとづき、「キャバル」のなかでも知っていたのは、カトリック教徒の連中だけであった。
この条約によって、イギリス王はルイ十四世の対オランダ戦争(一六七二〜七八)に参加するとともに、カトリシズムの真理を確信するむねを宣言し、イギリスの事態がゆるせば、カトリシズムに改宗することになり、フランス王はこれに対して友情をあらわすため、金を支払い、必要がある場合は、軍隊を派遣することを約束した。
チャールズはルイ十四世との密約にしたがって、国内ではカトリシズムを復活させるため、宗教上の寛容というかくれみのを利用した。
すなわち王は一六七二年、寛容宣言を発したが、議会は王の真意を見抜いて、七三年これを撤回させた。
そして「審査法」を制定し
「文武の官職をもつものは、いかなるものも国王至上権をみとめ、国王に対する忠誠を誓わなければならない。
上記の官職にあるものは、イギリス国教会の慣例にしたがって、聖餐(せいさん)の聖礼典をうけなければならない」
とし、カトリック教徒を官職からしめだした。
3 政党のはじまり top
こうしてチャールズは、王権の基礎としてカトリシズムを利用することを断念し、イギリス国教会のアングリカニズムにのりかえた。
「キャバル」に代わって、新しく任用されたダンビー伯トマス・オズボーン(一六三一〜一七二一)は、クラレンドンの政策をうけつぎ、国教会とむすびついて王権の伸張につとめ、国王の政策を通過させるために、機密費をばらまいて議員を買収した。
しかし反対があった。イギリスには依然として、国王絶対主義を悪とする一種の政治的なピューリタニズムがあり、この考えの人びとは革命を恐怖したけれども、極限情況のもとではこれを是認した。
ただし彼らはピューリタン革命時代の父祖のように、国教会や王室を廃止することを考えず、カトリシズム以外のすべての宗派に自由をみとめることによって、国教会の独占を破壊し、議会の権限をひろげて、王権を制限しようとした。
これを指導したのが、「キャバル」の一員だったアシュリー(一六二一〜八三)である。
彼は明敏な人物で、チャールズ一世、長期議会、クロンウェルといつも主流にくっつき、チャールズ二世の復位にも重要な役割を果たした。
彼は宗教上ふかい信仰がなかったから、寛容の観念をたやすくうけいれることができたし、絶対主義をきらったのは、そこでは自分の明敏さを発揮する機会がなかったからである。
彼は王の真意を知らずに寛容宣言を支持したが、実情を知るとともに、議会で果敢に王に反対し、審査法の通過に尽力した。そしてアシュリーはシャフツベリー伯に叙せられ、一六七五年、国王絶対主義と国教会に反対するものを集めて、ブリーン・リボン・クラブを組織した。
ところがその後、タイタス・オーツ事件がおこった。
タイタス・オーツ(一六四九〜一七〇五)はまえにイエズス会士であったが、一六七八年つぎのような教皇派の陰謀を暴露した。
すなわちイギリスの教皇派が、国王を殺害してカトリックの王弟ジェームズを王位につけ、カトリシズムを復活する謀議をめぐらしているというのである。
この根拠のない捏造(ねつぞう)は、一般にひじょうな衝動をあたえた。
シャフツベリー派はこれを利用して宣伝を行ない、彼らこそ真に国民の味方であることを示そうとした。
こうして争いはダンビーがひきいる宮廷党と、シャフツベリーが指導する地方党とのそれとなった。
その最大の争点は王位継承問題である。
チャールズ二世には男子がない。法定相続人になっていた王弟ジェームズは、カトリックであったから、シャフツベリーらの地方党は、彼を法律によって王位継承から排除しようとする。
チャールズはこれを阻止するため、一六七九年から八一年のあいだに開かれた議会を、次々に解散した。
第一議会で、王位継承排除法案は第二読会を通過しただけであったが、この議会では有名な「人身保護法」が制定された。
これは容疑者の理由のない拘束、または長期の拘束を防止するため、人身保護令状を発して、拘禁の理由を明らかにし、正式の裁判にかけることを規定したもので、チャールズ二世はしばしば理由なくして、拘禁を行なっていたのである。
第二議会では王位継承排除法案が庶民院を通過したが、貴族院で否決された。
この第二議会の解散後、国内に不穏な空気がみなぎった。
チャールズはロンドンの大衆の圧力を避けるため宮廷党の拠点オックスフォードに、第三議会を召集した。
王は、いったんジェームズが王位を継承してからイギリスを去り、娘のメアリーおよび夫のオランイェ公ウィレム三世が摂政に就任することを提案した。これを拒否した地方党のシャフツベリーは、王の庶子モンマス公をジェームズの代わりに王位継承者とすることをもとめた。
チャールズは、「私は屈服しない。私は脅迫されない」と答えて、数時間後議会を解散し、地方党を唖然(あぜん)たらしめた。宮廷党と地方党との対立が激化するうちに、前者はトーリー党、後者はホイッグ党とよばれるようになった。
これはたがいに相手を嘲弄(ちょうろう)してよんだあだ名である。
トーリーは「アウトローとなり、イギリスの植民や兵士を掠奪、殺害して生計をたてている無産のアイルランド人」のことであり、ホイッグは「主教を殺し、王に対して反乱をおこし、長老主義や共和主義を推進したスコットランド西南部の厳粛同盟の輩(やから)」をさした。
そしてトーリー党が王の世襲権と王権に対する無抵抗を主張したのに対し、ホイッグ党は宗教上の寛容と王権の制限を主張したが、両党の社会的地盤もちがっていた。
トーリー党は、貴族、ジェントルマンが中心で、うしろには、国教会やおくれた農民大衆がいた。 |

民衆を扇動するホイイグ党
|
これに対し、ホイッグ党は、大商人や新興の金融家と、これに関係のふかい貴族、ジェントルマンを地盤とし、その背後には都市のピューリタンで中産階級の下層のものがいた。
一六八一年の議会解散後、ルイ十四世から財政上の支持をえたチャールズは、議会を召集せず、絶対主義をつよめ、ホイッグ党をおさえてトーリー党を優遇した。
これに対し、ホイッグ党員の過激派は武装抵抗を計画する。同時にクロンウェルの老兵たちのあいだでも、チャールズ二世および王弟ジェームズの暗殺計画が進められた。
しかし、一六八三年、これが暴露し、その結果、捕えられたホイッグ党員を、ロンドン塔が待ちうけていた。
ホイッグ首脳部のなかで、シャフツベリーは、これよりさきオランダに亡命、そこで死亡、エセックス伯は剃刀でのどをきって自殺、ラッセルおよびシドニーは裁判をうけ、暗殺計画には積極的でなかったにもかかわらず、処刑された。
4 モンマス公の乱 top
一六八五年チャールズ二世が没し、カトリックの王弟がジェームズ二世としてあとをついだ。
即位後まもなく召集された議会は、トーリー党が優勢で、六一年以来のどの議会よりも宮廷に対して好意をもち、たとえばそれが承認した予算は、チャールズ二世の即位当時の約倍額であった。
ところが議会の会期中に、ジェームズの夢を破るような事件がおきた。それはチャールズの庶子、モンマス公の乱である。
彼は前述のようにシャフツベリーによって王位継承者にかつがれたこともあったが、このパトロンの死後、オランダで、おちぶれていた。
八五年六月、彼はアムステルダムの大商人の援助によって船を借り、百五十名ばかりの一隊をひきつれて、イギリス南西部に、上陸した。
しかしホイッグ党の貴族やジェントルマンは田舎の屋敷にこもって動かず、公のもとに集まったのは、サマセットやデボンなど南西部諸州、とくにサマセット州のターントンの毛織物業地帯の下層民約六千名であった。当時毛織物業は、アイルランドの低賃金と廉価羊毛の競争のため不況にあえいでいた。
ピューリタン弾圧立法によるピューリタンの苦痛も、反乱の一要因となった。彼らの目的は教皇派の王のみならず、イギリス国教会を廃止することであった。
しかし、モンマスの部下は烏合(うごう)の衆である。
指揮はなっておらず、武装は不完全、棒に大鎌をくくりつけて進軍する者も多かった。
反乱がおこった諸州の民兵や、正規軍は王に味方した。
ロンドン市、議会、都市、地方の役人やジェントルマン、さらに国の世論も、王と法とを支持する。モンマスの運命は決した。王軍に破れ、捕えられた彼は、王の前にひざまずいて涙とともに嘆願したがゆるされず、処刑された。三十六歳。
モンマスの部下のうち、数百名は兵士の手によって、また「血の裁判」で処刑され、八百名以上のものが奴隷としてバルバドスに売られた。このとき捕虜を奴隷として売る認可をもらったのは、宮廷の寵臣たちであった。
モンマスの反乱は、「旧イギリス最後の人民の反乱」といわれている。 |
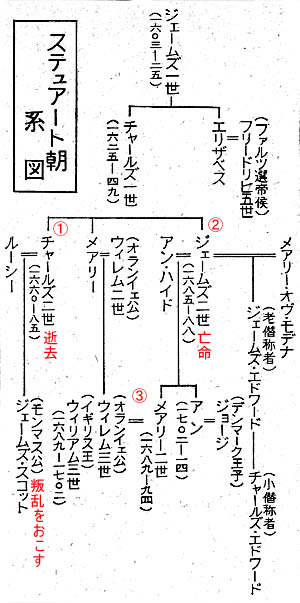
|
ジェームズはこの反乱の深さにおどろき、常備軍を増強した。前王の大常備軍設置の計画が反対をうけたにもかかわらず、ジェームズは兵数を三万にふやし、一万三千の兵をロンドン市の西部に駐屯させて、市に圧力をかけた。
常備軍は、イギリス人にもっとも肌のあわないものである。
そしてカトリック教徒のジェントルマンが、この軍の将校に任命された。
兵士たちはカトリック教徒ではない。そこで、彼らを改宗させようとしたが、いたずらに憤慨をまねいたにすぎなかった。
一六八七年四月、ジェームズは「寛容宣言」を発布してカトリック教徒や非国教徒に対して礼拝の自由をあたえ、彼らが公務につくことをさまたげていた法律を全部廃止した。
非国教徒は最初は感謝したけれども、やがてこの自由が奴隷化に通ずることに気づき、これを拒絶した。
一六八八年六月、第二の「寛容宣言」が発せられ、カトリック教徒が文武の公職に就任した。
非国教徒たちは「寛容宣言」が、「審査法」を廃止し、悪魔の権力、すなわち教皇およびカトリック教会を復活する狡猾(こうかつ)な手段であるとにらんだ。
そこで彼らは国教徒とむすんで、王に反対した。
5 王の交替 top
王と国教会との争いは、「寛容宣言」をめぐって最高潮に達する。
一六八八年王は、六月の第一日曜と第二日曜に、教区教会の説教壇の上で、「寛容宣言」を読みあげることを命じた。
しかし聖職者のなかには、良心にもとづいて、「寛容宣言」を拒否するものがあらわれた。
カンタベリーの大主教サンクロフトほか六名の主教が、聖職者に「寛容宣言」を読み上げることを強制しないように請願した。
王は、他に対するみせしめとして、この七名を煽動(せんどう)罪で訴える。
しかしロンドンの陪審員は無罪を宣し、彼らが釈放されたとき、ロンドンの民衆の興奮はすさまじいものであった。
こうしてジェームズは、ホイッグ党はもとより、カトリシズムとむすびついたことで、トーリー党、さらにイギリス国教会まで敵にまわすことになり、王権の地盤は極度に狹くなってしまった。
しかし当時、革命がおこらなかったのは、ジェームズには王子がなく、王のあとには、オランダ総督で新教徒のウィレム三世に嫁している王女メアリーが即位し、ジェームズがカトリシズムのために行なったことを、全部廃棄するであろうと考えられたからである。
ところが一六八八年六月十日、王太子が出生したのだ。
これは、完全に人びとの希望をうちくだいた。
一六八八年六月三十日、七主教が釈放されたと同じ日、おもな国教徒、トーリーおよびホイッグ党員の署名のある招聘(しょうへい)状が、ウィレム三世に送られた。
「我々は日ましに悪い状態におちいり、みずからの立場を守ることが困難になっております。
人民はみな、その信仰、自由、財産にかんし政府のいまのやり方に満足しておりません。
二十名の人民のうち、十九名までが変化を欲しております。貴族やジェントルマンの大部分も同じように不満であります。我々は殿下が上陸されるとき、かならず殿下のもとに馳(は)せ参じ、全力をつくして、殿下をお迎えする準備をさせておきます。」 |
一六八八年十一月五日、ウィレム三世はイギリス西南部、デビンシアのトーベーに上陸した。
軍にもみすてられたジェームズ二世は、情勢に望みがないことをさとるとともに、亡命を決意した。
しかし王はケント州で捕えられ、ロンドンに送りかえされてきた。
当時ウィンザーにいたウィレム三世は、むしろジェームズが亡命してくれるほうが好都合であった。
そこで彼は王と会談することを拒否し、王が漁船に乗ってフランスにのがれることを黙認したのである。
翌八九年一月十二日、召集された暫定議会は、
「ジェームズ二世王は政務を放棄し、そのため王位は空位である。」と宣言する。
ウィレム三世は、メアリーを傷つけてまでも王冠をうける気持ちはなく、共同統治が望ましいと考えた。
それで事態はつぎのように進んだ。暫定議会は「権利宣言」を起草し、ジェームズを非難した――
「新教および王国の法律と自由とを破棄し、根絶しようとくわだてた。」
そしてウィレム二世およびメアリーが、「権利宣言」中の王権に対する制限を承認したのち、議会は両者に共同統治者として王冠をささげた。
これがイギリス王ウィリアム三世(=ウィレム二世)とメアリー二世の即位である。
一六八八〜八九年のこの変革は、一滴の血も流されなかったので「名誉革命」とよばれる。
そこではトーリー党とホイッグ党とが結合し、革命が社会の深層におよばず宮廷を中心とする上層部の勢力交替にとどまったが、立憲王制への道がひらかれることとなった。 |

ウィリアム三世
|
トーリー党とホイッグ党とは、ジェームズ二世の絶対主義、カトリシズムに対する反感と、モンマスの乱にみられるような人民蜂起に対する危惧によって、結ばれていたといえよう。
top
**************************************** |