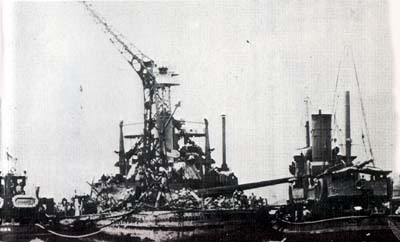|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12
11 奇襲の原価計算
|

カネオエ付近で撃墜された日本軍パイロットは、
軍礼をもって手あつく葬られた
|
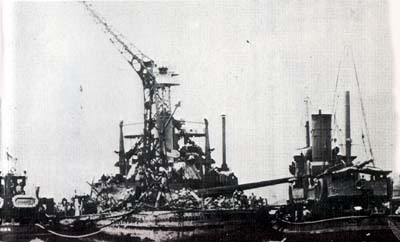
ドックに曳航される戦艦「カルフォルニア」には、
すでに星条旗がひるがえっていた
|
一時間五〇分つづいたパールハーバー攻撃で、日本軍はアメリカ軍のキモをつぶすような大勝利をおさめ、アメリカ太平洋艦隊に圧倒的な大打撃を与えた。
一九四一年(昭和十六年)十二月七日、米国時間の正午までに、パールハーバー軍港は無力化されて、もうもうとたちこめる爆煙のなかにつつまれていた。
その大損害の見積りは、戦艦八、巡洋艦三、駆逐艦三、補助艦艇八、総計二二隻二〇万トンにたっしていた。
これにくわえて、ヒッカム、ホイラーその他の飛行場が破壊されて、ハワイ駐屯の米航空部隊二三一機のうち九六機が撃破された。
しかも残りの飛行機のなかで、すぐとびたって反撃できるものは、わずか七機にすぎなかった。
結局、オアフ島の米海軍機の半数以上もまた撃滅されてしまった。 |

海岸に漂着した日本軍パイロットの遺体
|
軍艦の乗組員の損害だけでも、総計一七六三人の士官、水兵がやられたが(一般市民をのぞく)この数字は日本軍の奇襲直後の計算であり、それは陸上での人的損害をくわえると、あとでは二三三五人にふえた。
しかしこの数字は戦死者だけのもので、さらに大勢の士官、水兵が負傷した。
そのうちの多数は数日後か、数週間後に死亡した。
しかし一部の人々は戦傷がなおってから、再び戦楾にもどり、また他の人々は年金と傷痕をみやげにして家郷にかえった。
いったい、どうしてこのようなおそるべき大損害がおこったか、その理由をどう説明すべきであろうか?
その回答はきわめて簡単ながら「奇襲」であった。
すなわち警告もなしで、三五三機の飛行機による攻撃によって、日本軍はオアフ島に駐留する米海、空軍部隊を撃滅したのだ。
しかも米軍側が、それを容易にさせたのである。
米太平洋艦隊のほとんどすべての戦艦は軍港内に在泊し、また多数の飛行機は攻撃されるに都合よいように、各飛行場にたばになって集結していた。
全く警戒態勢を欠いていたことは許せない。
特に一九三二年(昭和七年)にハリー・E・ヤーネル提督(米海軍大将、はるか北東海上から空母二隻によるパールハーバー奇襲成功の可能性を予見していた)の海軍演習以来、ハワイに接近する飛行機をレーダーで捕える技術は、おおいに進んでいたからであった。
1 山本長官の新戦術成功 top
だが、このパールハーバーの大破壊の大半は、山本五十六によって、めざましくも開発された航空戦の新戦術がもたらした直接の戦果であった。
米海軍の提督連中は、パールハーバー軍港の水深の浅い水域では飛行機が空中から首尾よく魚雷を発射することができるとは、だれも信じていなかった。
しかし日本軍はそうは考えていなかったのだ。そして、彼らの主張を実証したわけである。
また米海軍の提督たちは、爆弾がはたしてとてつもなく厚い戦艦の甲板をつきやぶれるかどうか、疑わしく思っていた。
またしても日本軍は、そのような考えが誤りであることを証明した。
しかし日本軍の大勝利は、けっして完全なものではなかった。彼らは米艦隊の航空母艦を一隻も撃破できなかった。
それはやがて、彼らの破滅の原因となる強力な兵器を助けてしまったわけである。
またパールハーバーでおこった大惨害は、米海軍の古い作戦計画の全部をご破算にすることになった。
あとからの回想ではあるが、一部の米海軍軍人は、日本軍がたくさんの屑鉄のような旧式軍艦を撃沈しただけでなく、古くさい戦艦第一主義(いわゆる大艦巨砲主義)まで効果的に打破してくれた、と認めたであった。
何故なら、米太平洋艦隊に所属した空母「エンタープライズ」「レキシントン」「サラトガ」三隻は在泊しておらず攻撃をまぬがれたので、やむなく戦艦にかわって太平洋艦隊の主力艦になったわけだ。
そしてこの空母機動部隊は自動的に主要な海軍兵器になり、たちまち米海軍はそれをおおいに、また、たくみに使いこたすようになった。
すなわち珊瑚海でもミッドウェーでもガダルカナルでもラバウルでもマーシャル群島でもトラック諸島でも、空母機動部隊はよくたたかった。
空母「エンタープライズ」の場合は、危機一髪のところであった。
すなわち同艦は、ウェーキ島へ飛行機を輸送した帰航の途中であったが、護衛の駆逐艦が荒天の洋上で給油中の故障から手間どった天佑神助のおくれによって、日本軍の攻撃から救われたのだ。
それでも同艦は、パールハーバー攻撃隊の総指揮官淵田美津雄中佐(当時)が攻撃隊の第一波をひきいてオアフ島へ突撃したとき、わずか二〇〇マイル(三二〇キロ)の沖合を航行中であった。
2 地上の油槽群を見のがす top
さらにまた日本軍は、オアフ島にある米海軍工廠その他の施設をたたきつぶさなかったという、もう一つの大失策をおかした。
これらの機械工場施設は、軍港で撃沈破された軍艦を修理するのに、はかり知れないほど貴重なものであることがわかった。
そのうえに、太平洋艦隊の生命を維持する血液をたくわえた油槽群(オイル・タンク)も手をつけず残した。
これらのタンクはすべて地上にあり、したがって、きわめて攻撃されやすかった。
もしもこの油槽群が爆破されて喪失したら、太平洋艦隊の残存艦艇は米本国へ追いかえされることを、余儀なくされたであろう。
そうしたら日本軍は数ヵ月もの長い間、太平洋を完全に支配したことであろう。
その数ヵ月間こそ、東南アジア方面における日本の地位をおおいに強化して、現実の状況に重大な変化を与えたにちがいなかった。
(この点について、幸運は米軍側についていたといえるだろう。
湾内にあるフォード島の燃料用の油槽地帯付近に停泊していたタンカー「ネオショー」に爆弾が命中していたら、そのすぐちかくに繋留されていた四隻の戦艦「メリーランド」「テネシー」「オクラホマ」「ウェストバージュア」は大爆発をおこし地獄のような状態になっていたばかりか、おそらく油槽群にも引火して猛炎につつまれていたであろう。
淵田中佐の指揮した日本機のパイロットたちは、より大きな獲物(戦艦群)に熱中していたので、この小さな油槽船を見のがしたのである。)
そして米太平洋艦隊のうけた大損害は、実際の被害よりもっとひどいものになったかもしれないが、それでもこの航空攻撃は日本軍の成功とみなされねばならない。
パールハーバー攻撃の二十五周年記念日にあたって、当時の第一航空艦隊参謀源田実中佐(戦後に航空自衛隊空将、現自民党参議院議員)はこのパールハーバー奇襲こそ「世界軍事史上で永久不滅の大成功である」とのべた。
それから彼は「しかしそれは政治的には大きな誤りであった。何故なら、それは最後には日本の降伏をもたらしたからである」と付言した。
3 無能だった潜水艦隊 top
だが、それと同じことは、日本軍の潜水艦部隊の役割についてはいえないであろう。
伊号級の大型潜水艦二七隻と小さい特殊潜航艇(日本海軍の正式名称は甲標的)五隻がオアフ島周辺に配置されていたが、それは任務をほとんど果していなかった。
この豆潜航艇は、パールハーバー軍港内で損傷したどの軍艦にも、とどめをさせなかったし、また大型潜水艦も港外へ出航した米艦船を撃沈しなかった。
またおりから帰航中だった米空母「エンタープライズ」と、その護衛用の駆逐艦三隻は、特に絶好の攻撃目標になったが、日本軍の潜水艦部隊はあまりよく訓練されていなかったし、また淵田中佐のひきいた飛行士たちのように、はりきってもいなかった。
伊号級の潜水艦一隻と、豆潜航艇のうちの四隻は撃沈され、のこる五番目の豆潜航艇は座礁して投降した。
(これら五隻の豆潜航艇でその生命をうしなった乗員のなかで九人だけが栄誉をあたえられた。
すなわちこの九人は死後に、それぞれ勲章を授与され、二階級特進して、軍神としてあがめられた)
このように「Z作戦」は、この局面では大失敗であったといわざるをえない。
その結果、日本軍の潜水艦部隊はその面目をうしない、開発をすすめるための財源をもらえなかった。
そして戦争の後期には、潜水艦の多数は、ソロモン群島で孤立した日本軍の守備隊に物資を輸送する補給船の役割をするまでにおちぶれてしまった。
きわめて用心深い南雲忠一中将(真珠湾攻撃機動部隊最高指揮官兼第一航空艦隊司令長官)は作戦の目的がすでに達成されたと決断したとき「油断大敵」という日本のことわざを引用したというので有名である。
いったんその仕事がすんだら、彼の関心はそのひきいる艦隊を無傷のまま日本へ帰航させることであった。
このような南雲中将の用心ぶかさは、あるていど、日本が軍艦を失うような、ゆとりがないという事実に原因していた。
すなわち米軍側ではたとえ軍艦をうしなっても、また別の軍艦をすぐ建造できたが、日本の限られた産業能力は戦略物資の欠乏と技術者の不足によって制約されていた。
日本人は貧乏人の戦争をたたかっていたのだ。
それで日本はアメリカ産業の巨人を相手に撃ちあいをかわすゆとりは、到底なかった。
また日本軍側の入手した諜報によると、米軍側では、いぜんとして多数の作戦可能の態勢にある爆撃機を保持していたので、南雲中将は米軍の陸上基地航空隊の攻撃圏内にぐずぐずして、いのこるのは無謀なことであるように思われた。
4 南雲長官の慎重さに不満の淵田 top
淵田中佐は、上官である南雲奇襲部隊最高指揮官の慎重さにたいして腹を立てて、部下パイロットたちがもう一撃を敵に加えることを許可しなかった上官の決断を嘆くことを、いつまでも、けっして止めなかった。
「もしわが軍がパールハーバーを無力化して、空母「エンタープライズ」か「レキシントン」かの一隻を、あるいはその両方とも撃沈していたならば、太平洋戦争は大いに違ったなりゆきを見せたことだろう」
と、彼は戦後に回想しながら言明した。
米海軍の提督たちの多数も、この意見に賛成していた。
たとえば、当時のキンメル海軍大将の後任として、アメリカ太平洋艦隊司令長官に就任したニミッツ海軍大将は、つぎのように書いている。
「将来、太平洋戦争におけるわが海軍戦史を研究する人々は、日本軍の空母機動部隊の指揮官が、パールハーバー攻撃をたった一日だけの作戦に限定して、しかもその攻撃目標をきわめて制限された範囲にかぎったことによって、せっかくの黄金のチャンスをのがしたと、必ずや結論を下すであろう」
当時、米海軍長官フランク・ノックスは、どんなことがパールハーバーで起こったのか、彼自身の目で見届けるために、ただちに現地へ急行した。
5 パールハーバー空襲の急報 top
その日曜日(米国時間で十二月七日)の朝、日米両国間にあわただしく展開中の重大危機の情勢について、国務長官コーデル・ハルと陸軍長官ヘンリー・スチムソンの両人は密談を交していた。
一方、その日午後、二人の訪問官がハル国務長官に会見するため、長官室外の応接室で待っていた。
それは独眼の野村吉三郎大使と日本から急いで飛来した「特使」の来栖三郎大使(元駐独大使、夫人はアメリカ人)であった。
緊急会議がおわって、ノックス海軍長官がその自室にもどってきて、その椅子におちつくやいなや、海軍作戦部長(日本の軍令部総長に相当する)ハロルド・スターク海軍大将が、ホノルル海軍航空基地作戦士官ローガン・ラムゼー中佐のドラマチックな急電を、わしづかみにしてとびこんできた。
その電文はつぎのとおりであった。
「パールハーバー空襲、演習ではない」
ノックス海軍長官はそれを見て、
「これは大変だ! まさか本当ではあるまい! これはフィリピンの間違いじゃないのか!」と叫んだ。
「いや、ちがいます、閣下。これはパールハーバーであります!」とスターク海軍大将は答えた。
時刻はおよそ午後一時四十五分ごろであった。
ノックス長官はすぐパールハーバー現地へ緊急電話を申し込んだ。
それから、彼はホワイトハウスに直通定話をかけて、大統領に報告した。
ノックス長官は後日、その当時を思い起こしてつぎのように語った。
「私は大統領がどんな言葉をのべたか、はっきりと覚えてはいない。
もちろん彼はビックリしたよ。たしか彼は、信じられない様子だった、と私は思っている……」
ルーズベルト大統領が電話を切るや、ノックス長官はパールハーバーと海軍専用電話を通じて、第十四海軍区司令官ブロック海軍少将と話をした。
ブロックはノックス長官にくわしい損害状況を知らせた。
それはすでにこのときには、たしかに本当であると信じられた。
この重大な通話をおわると、ノックス長官は大統領が緊急閣議をひらくため、ホワイトハウスに急行した。
それは大統領が議会へ送るべき開戦教書を討議し、さらに翌日、全米国民へ向ける教書を検討するために、非常召集されたのであった。
大統領に向ってノックス海軍長官は、
「私はパールハーバーで、いったいどんなことが起こったかを知らねばなりません。
私はすべて詳細を知りたいのです。私はいますぐ現地へ出向きます」と言明した。
6 日本の通告文 書を手わたす top
さてこの間に、日本の野村、来栖両大使は午後二時五分に、ハル国務長官の長官室の外側の応接室に到着していた。
この両人が長官室に招じ入れられる以前に、ルーズベルト大統領はハル長官に、つぎのように告げていた。
「コーデル君、いまノックス長官からジャップがパールハーバーを攻撃したという報告を知らせて来たところだよ」と、大統領の語気はするどかった。
「それは確認されていますか」とハル長官は、きちょうめんにたずねた。
「いやまだだよ。私は、たったいま、ノックス君から報告を受けたばかりだ」と大統領は答えた。
「私は野村と来栖に会う前に、それを確認したいと思います。彼らはこの室外の応接室で待っています」とハル長官はいった。
ちょうど午後二時二十分に、その二人の日本人は国務長官室に入室を許された。
彼らはおじぎをして、日本政府の通告を提出した。
野村大使は、それを午後一時かっきりにとどけるように訓令されていたところが、暗号電報を解読、清書するのに、てまどったためにおくれたことを、わびながら説明した。
ハル国務長官は野村大使から、その文書を受けとるや、眼鏡のぐあいを直してから、それを読みはじめた。
(しかしその通告文の内容は、もちろんかれにはすでに知らされていた。
しかし彼が後で語ったように、彼はその全文がいかなるものであるかを知っている気配を全く見せなかった。
そしてこの通告文をはじめて読んでいるような振りをせねばならなかった。)
それは十一月二十六日のハル国務長官の覚書き(いわゆるハル・ノート)にたいする日本側の回答であった。
その内容は、米国側の提案をきっぱりと拒否たもので、日本の自己正当化と、ののしりの寄せ集めであった。
それは、つぎのようにのぺていた。
7 対米通告文の内容 top
「――東亜の安定を確保し世界の平和に寄与し、もって万邦をして各々その所を得せしめんとするは帝国不動の国是なり。
さきに中華民国は帝国の真意を解せず、不幸にして支那事変の発生を見るに至れるも、帝国は平和克復の方途を講ずると共に戦禍の拡大を防止せんがため、終始最善の努力を致し来れり……
しかるにアメリカ合衆国政府はつねに理論に拘泥し現実を無視し、その抱懐する非実際的原則を固執して何ら譲歩せず、いたずらに交渉を遷延せしめたるは帝国政府の諒解に苦しむ所なり……」
「――合衆国政府は世界平和のためなりと称して自己に好都合なる諸原則を主張し、これが採択を帝国政府に迫れるところ、世界平和は現実に立脚し、かつ相手国の立場に理解を持ち、相互に受諾し得べき方途を発見することによりてのみ具現し得るものにして、現実を無視し一国の独善的主張を相手国に強要するが如き態度は、交渉の成立を促進するゆえんのものにあらず」
「――よって帝国政府はここに合衆国政府の態度にかんがみ、今後交渉を継続するも妥結に達するを得ずと認むるの外なき旨を、合衆国政府に通告するを遺憾とするものなり」(外務省公表、対米通牒原文による) |
ハル国務長官の両眼はまるで怒りに燃えるように、日本人の神経質な二人の使者を見あげた。
「私の五十年間にわたる公職在職中に、かくも破廉恥な虚偽と歪曲に満ちた文書を見たことがなかった。
その破廉恥な虚偽と歪曲たるや、あまりに大がかりであり、私はこの地球上のいかなる政府もこのようなウソを吐くことができるとは、今日まで、けっして想像もしたことがなかった」 |
と、ハル長官は告げた。
野村、来栖両大使は、青白い顔つきで黙々と国務長官室を出ていった。
彼らの仕事はもう終ったのだ。この両大使は、有効な引き延ばしの仕事を遂行したのだ。
それはパールハーバー奇襲のために道を開く手伝いをしたわけである。
彼らは日本が対米戦争に突入しようとしていたことを、充分に承知していた。
しかし両人は最後まで、ハワイ攻撃の詳細を全く知らなかったこと、また「Z作戦」計画が彼らの対米交渉の最中にそのクライマックスにたっするとは知らなかったことを戦後あくまで主張した。
しかしながら野村と来栖が、はたして日本外交の謀略の手先であることを承知していたか、それとも自ら知らなかったかどうかにはかかわりなく、対米通告を手交するのが予定時刻(十二月七日午後一時)より遅れたことは、天皇が希望していた「開戦前の正式通告」をご破算にしてしまった。
しかも世界中にあまねく「だまし討ち」として認められたように、日本軍の第一撃は、当時はなはだしく世論が分裂して、反戦・他国不干渉の気運が強かった米国を、たちまち一致団結させた。
その米国側に与えた損失と、日本側がこのパールハーバー奇襲作戦からえた利益とを相対的に比較、評価すると、おそらくこのアメリカ国民を団結させたという要因が、結局はいちばん高く計算されるだろう。
8 奇襲成功にわきたつ内地 top
パールハーバー奇襲部隊の第五航空戦隊(空母「翔鶴」「瑞鶴」の二隻)司令官原忠一少将(当時)は戦後に、苦笑しながら、
「ルーズベルト大統領は我々に勲章を授与すべきでしたよ」と語った。
過去十年間にわたり、日本は弱い敵にたいする勝利だけしか経験していなかった。
それでパールハーバー奇襲のニュースは日本国民をあっと驚かせた。
それはアメリカ国民を驚かせた度合いに劣るものではなかった。
東京にある大本営が、「帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり」と発表したとき、日本国民大衆の興奮はものすごく高まった。
そしてパールハーバーの大勝利のニュース速報は、軍艦行進曲がなりひびくなかで、ラジオ放送で全国に流された。
ひしめく群衆は町通りに立ちどまって、国歌「君が代」を歌いまくり、数千、数万の市民は宮城前の広場に出かけて、いっせいにおじぎをして、皇祖皇宗の神霊の加護を祈願した。
新聞の号外売りの少年たちは、振り鈴と拍子木を鳴らしながら町中をけたたましくかけまわり、朝日、読売、東京日日、各日刊新聞は特別勝利版の臨時発行を知らせた。
「日本はもはや『持たざる国』ではない!」
「歴史は、いまや枢軸側に立っている……五二億総勇士だ!」
「わが一億同胞の大行進の日ついに到来す」
「我々が待望して止まなかった日が来た!」
と各新聞の大見出しは豪語、編集者は大いに気勢をあげた。そして東京日日新聞の編集者は
「今日わが合い言葉は“帝国陸海軍は無敵なり”である」といっていた。
それは全国民の愛国的ムードをなまなましく反映していた。
この初戦の勝利から、自信過多におちいり、それはやがて日本の暗い敗勢の数年間に「勝利病」とよく呼ばれたものだ。
うぬぼれと、これまで彼らがみとめていたものにたいする、ごうまんな過小評価は、ついに最後には日本軍を破滅へみちびいたわけである。最終の分析によると、日本の敗北の原因は、この「勝利病」のビールス菌にさかのぼることができる。
9 以後傾きかけた日本の武運 top
日本人の国民性の奥深くには、不合理性と衝動性の一脈の気性がひそんでいて、それは強烈な、ご都合主義の感情に結びついている。
日本人はしばしば優柔不断で、ためらいながら、たやすく、うぬぼれになりやすい。
しかも合理性に欠けているために、たびたび熱望と現実を混同しがちである。
その結果、彼らはイチかバチかの危険のときにも、適当な思慮分別もなしに物事をおこなう。
いかにも理性的に考えている態度をとる。それはいつも失敗にたいする言いわけを見つけるためのゼスチュアだ。
パールハーバー奇襲の恐るべき大バクチは、最大の勝利の戦果をおさめた。
だがそれは日本軍の武運もやがて尽きることを意味するものであった。
一九四一年(昭和十六年)十二月に、日本の昇る旭日は、これ以上めざましく光り輝くことがけっしてなかったくらい、見事であった。
それはただちに沈みはじめはしなかったが、落日に傾くことは避けられなかった。
長くつづいた戦争は、あらゆる熟練と勇気と、非常識な残虐を発揮しながら戦いぬかれたが、それはまた複雑な日本人の性格の構造につながるものである。
しかし日本帝国海軍はそれからさき、淵田中佐のひきいた飛行士たちがパールハーバーで達成したような成功を再現することは、けっしてなかった。
top
**************************************** |