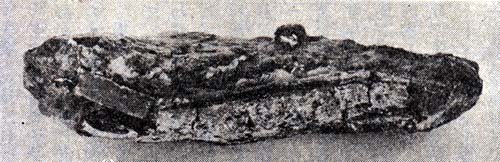|
****************************************
Index 1
2 3
4 5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
4 文明の誕生
1 文明の発生と原始農村
top
十九世紀から二十世紀はじめにかけては、文明の発生についていろいろな考え方があった。
そのうちの一つは、温暖で、大きな平野を有している大河の流域に、文明がおこるという説である。
それは今日でも、必ずしも全面的に間違っているわけではない。
しかし、それならなぜミシシッピ川やヴォルガ川の流域には、文明がおこらなかったか。
ミシシッピ川も、ヴォルガ川も今日では、その流域が世界的な大穀倉地帯になっている。
しかも、それらの大河の流域は文明の発生地にはなっていない。
それでは昔は、そこに人が住んでいなかったのかというと、そうではない。
ミシシッピ川流域には、イモ農業は早くからおこなわれていた。
ヴォルガ川流域にも、旧石器時代後期に当時としてはかなり発達した狩猟採集生活を営んでいる人々が住んでいた。
またその後も人が住んでいた確証がある。
つぎに、気候のよいところ、すなわち湿潤温暖なところで文明がおこるという説がある。
しかし、それならば南太平洋やカリブ海の島々など常春で、この世の極楽のようなところで当然文明はおこってよいはずである。
が、そういうところに文明はおこって、いない。
他方、けっして温暖でも湿潤でもなく、むしろ気候の厳烈な、砂漠地帯や乾燥地帯に文明がおこっている。
こういうぐあいで、大河や気候だけでは、文明の発生はどうしても解けない。
ところが新旧両大陸をとおしてみて、文明がおこったところは、すべて穀物農業地域であったことが留意されるようになって、文明を生みだした根源は穀物農業にあったことが知られるようになってきた。
すなわち農業といっても、穀物農業のないところには、必ずしも文明はおこらない。
穀物はすべての食物のなかでもっとも保存がきき、しかも生産が容易で、収量もイモなどにくらべてずっと多い。
それで穀物はひじょうに多くの人口を養うことができるので、穀物農業地に文明の発生地が限られていることがわかってきた。
つぎに同じような意味で、家畜のうちでも食用になる肉のとれる牛、羊、山羊、豚などを飼う牧畜が重要で、穀物の農耕と、肉畜の飼養――この両方をあわせおこなった地方に文明がとくに早く発生したのである。
今日でも食生活と文明との関係はぜんぜん変わっていない。
文明世界では穀物なしにはやってゆけないし、肉畜の種類も、紀元前三、四〇〇〇年ころからほとんどまったく変わっていない。
文明のほかの要素はいちじるしく発達・変化したのに、主食のみは変わらず、いちばん伝統的である。
そのことは逆に穀物農業と、肉畜牧畜が、文明の創造を可能にし、その存続を保障するうえにもっとも根源的な役割を果たしたことを物語っている。
|

野生大麦、小麦の分布地域
|

野生ヒツジの分布地域
|
このように見てくると、人間がもっとも容易に耕作しうる穀物の野生種があり、容易に家畜化しうる肉畜の野生種がいたところが、文明の母胎になったに相違ないということになろう。
そういうところはどこかというと、オリエント地方ということになる。
オリエント地方、とくにイランからアナトリア、北イラクからシリア、レバノンといった地域は、大麦、小麦の野生種が多く、野生の羊、山羊、豚、牛なども早くからたくさんいた。
そこでオリエントの、それらの豊富な地域で狩猟採集生活をしていた人々が、野生種の穀物をみずから栽培し、野生の肉畜をみずから飼養して、食料を生産することを学びとったときに、生活上の大変化がおこり、文明への道が闊然(かつぜん)としてひらけた。
そういう革命的な大変化がおこったという理屈になる。
実際にもそのような大変化が、オリエントの問題の地域でおこったのである。
その具体的なことはあとで述べるとして、もっとも大きな変化は、放浪から定住へ、生活の仕方が変わったことである。
狩猟採集の場合は自然を対象としているから、放浪性をまぬがれない。
また多くの場合、人々は分散的に住むほうが、獲物の取得に有利である。
したがってそこには恒常的な社会が発達しない。
ところが人々が農耕牧畜をするようになると、それに都合のよいところにある期間定住するようになり、しかもかなりの人数がいっしょに生活することもできるようになる。
むしろそのほうが農耕牧畜の生活には効果的なことが、おのずからわかってくる。
こうして定住と集住がおこなわれるようになって、固定化し、恒常化した人々の集まりができ、社会が形成される。
そこにおのずから協力と分業が可能になり、狩猟採集時代には食料の獲得にのみ全エネルギーを費やしていたのが、農耕牧畜の生活にはいって、食料の生産蓄積が容易になり、ほかの方面にもエネルギーを向ける余裕がでてくる。
その顕著(けんちょ)な表われが、新しい定住生活を便利にするための発明となる。
農耕牧畜をやることがすでに一大発明であったが、この新しい生活様式とともに生活に必要なものを創造していくというアイディアがますます旺盛になって、比較的短期間にいろいろなものが創造されるようになった。
すなわち土器を作るとか、衣食住関係の基本的生活用品を作りだすことが、まっさきにおこった。
こうして生活文化、物質文化の内容が急激に豊富になり、人間の増殖もさかんになった。
物質方面ばかりでなく、精神方面にも発展がみられた。
とくに農耕牧畜の順調な運び、収穫の盛大をねがう宗教的な動きが活発になった。
これは当時としてはきわめて自然なことで、雨が降らなかったり、家畜が病気になったり、草がなくなったりするような異変がないように祈願し、また彼らにとってはまことに不思議な、自然の増殖力、再生力に感謝した。
こうしたものから、地母神や家畜神などの宗教的な観念や信仰が生じてきた。
また死後の世界についての観念も発達した。
こうして集落の人々はいっぽうでは住む場所、共同で働く場所とともに、神を祀るところ、死者を葬るところなどをもつようになった。
人々は村落をつくって、ある一ヵ所に定住し、同じところを耕作して何年かたつと、作物が育たなくなるので、別のところに移動しなければならなかった。
また人々は耕作をやって何年かたった土地は、ふたたび農耕に適するようになることを知った。
こうして移動と耕作がくりかえされた。
放棄された村落はいったん廃墟となったが、何年かのちにはまたそこに人々が来て、土地をならし、新しい村落をつくった場合が多い。
村落の造営と放棄が同一箇所でくりかえされ、そこが廃墟の重層した遺跡になって、だんだんと小高くなっていった。
オリエントにはこのような遺跡が意外に多く、この小丘状の遺跡を現地の人はテペとかテルと呼んでいる。
これまで述べてきた穀物農耕、肉畜飼養の開始や、原始農村の成立のことなども、そのようなテペ、テルを考古学者や人類学者が発掘して、近年しだいにわかってきたことなのである。
世界最古の文明の発祥地といわれるメソポタミアの考古学的調査は、約百三十年前にアッシリア帝国の首都址にはじまった。
その後、バビロン王朝の都城址やシュメル都市国家の諸遺跡にすすみ、ついに今から四十年前ごろから文明時代をつきぬけて、より古拙(こせつ=素朴)な文化の遺跡にむかった。メソポタミア南部では、ノアの洪水伝説の起源になったろうと思われる大洪水があったしるしの河水の沈澱物の厚い堆積層の下に、彩文土器をもった農村の遺跡が発見された。
しかし、さらにそれを掘りさげると処女層になってしまい、これらの農村より、より古い農業発生当時の状態はわからなかった。
それは、そのころ南メソポタミアの大部分はまだ陸地になっていなくて、人々がまだ住んでいなかったからだろうと考えられた。
そこで学者たちは、どこから彩文土器をもった農村文化人たちが南メソポタミアに来たのだろうか、ということを問題にして、テイグリス、エウフラテス両川のより上流の地域や、イラン高原に近い丘陵地帯が問題の土地ではないだろうかと予測した。 |

原始農村の遺跡の分布図
|
この予測は適中した。ティグリス川流域のハッスナやテル・サラサート、イラク東部の丘陵地帯のジャルモ、マタッラー、カリム・シャヒルなどで、ひじょうに古い原始農村の遺跡が見いだされた。
もっとも有名になったのは、アメリカのシカゴ大学の調査隊がロバート・ブレイドウッド夫妻の指導下に一九四八年以後、発掘したジャルモの遺跡である。
ジャルモは東イラクのクルディスタン地方にある農村で、その近くにある小丘で原始農村の遺跡が見つかった。
その遺丘(テベ)は十六の層からなっていたが、上の五層からは土器が出土したが、下の十一層からはその出土がなかった。
つまり後者の層は、土器以前の集落址であったのである。
集落の住居は多くても二十か二十五で、人口は百五十人ほどだったろうと思われる集落である。
住居は粘土でつくられ、煉瓦はまだ使われていない。
上層の村落では家屋に石の土台が使われているが、下層では使われていない。
泥壁はしっかりと塗り固められており、床も葦の茎を厚くしいた上を粘土で塗ってある。
部屋の大きさは小さく、一メートル半から二メートルほどの長さしかないが、どの家も数室あった。
屋根も葦でふいてあり、その上を厚く粘土で塗ってあった。 |
 |
中・下層には土器はなかったが、石製の容器は使われていた。
これは長く石器生活をしていたために、石をくりぬいて器物をつくることを、まず考えついたのだろうと思われる。
また籠をアスファルト(ビテュメン)で固めたものや、皮をはって容器として使っていたらしいものなども見いだされた。 |
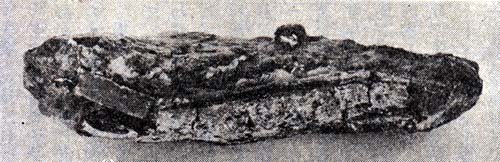
ビテュメンで固めた石鎌(テル・サラサート出土)
|
はじめ土器はなかったが、そのさきがけとなるような段階のものが、中層から発見されていて、興味ふかい。
それは粘土を厚く塗った床の一部を深く掘りくぼめ、それを火で焼き固めたものである。
つまりこれは、うごかない土器であった。
ジャルモの原始農村の人々は、こうして土器以前の時期にうごく石製容器と、うごかない土器をもっていたわけであり、また粘土は火で焼くと固くなることも知っていた。
したがってつぎの段階に、これが土器の製造となることは必然であった。
実際にもさきに述べたように上の五層では、土器が出土している。
彼らは第一層の集落時代にすでに、羊や山羊、犬などの家畜を飼っていた。
豚やカモシカ、野牛などは狩猟で手にいれた。カタツムリも食べたらしく、たくさん殼が見つかっている。
野生に近い小麦・大麦や豆類も栽培されていたらしく、炭化したその実物が検出された。
また麦を刈るための石製の鎌の刃や、麦を粉にするための石臼などが見つかっているから、彼らが穀物の農耕をしていたことは、まず疑いない。
石鎌の刃の材料としては燧石(ひうちいし)がおもに使われているが、東アナトリア地方から交易によってえたと思われる黒曜(こくよう)石も使われている。
これらの石の小さな刃は木や骨の柄にはめこみ、アスファルトでうごかぬようにとめて、鎌として麦などの穗を刈るのに用いたのである。
これらが動物の皮はぎや、肉切り用の小刀でなく、麦刈りに使われたことは、石の刃に、禾本(かほん)科の堅い茎ですれた跡が光沢を帯びてのこっていて、明らかである。
骨製の錐(きり)、へら、指輪、かざり玉などもある。
また粘土製の小さな地母神像、動物像などもあり、子供の玩具にでもされたらしい粘土の玉などもある。
このことから宗教的なものも作られていたことがうかがえるが、遺体は村の外に葬られたらしく、ほとんど発見されていず、埋葬のしかた、来世に対する考えかたなどはわからない。
ジャルモ遺跡の年代は、まだはっきり定まっていない。ここを発掘したシカゴ大学の人々は、紀元前六七五〇年ごろといっているが、おそくも紀元前五〇〇〇年を下らない遺跡とされている。
このジャルモからあまり遠くないところにあるカリム・シャヒルという遺跡も、彼らによって発掘された。
ここはジャルモよりさらに古い土器以前の遺跡だった。住居らしいものがあったらしく、石がしきつめられた床が見いだされた。
また石臼や石鎌(いしかま)、石鍬(いしくわ)などが出土している。
麦類の実物は検出されていないが、それらの農耕用の石器から考えて、おそらく麦類などを栽培していたと考えられる。
出土した動物類の骨をみると、のちに家畜化された羊、山羊、豚などのものが大部分で、狐や鹿など、狩猟獣の骨は比較的すくない。
この集落の人々は、狩猟もしたであろうが、おそらく家畜類の飼育に向かっていたと思われる。
石器の利器は打製だが、容器は磨製、あるいは半磨製だった。土器はなく、地母神像や装身具類と思われるものも出土していない。
これらの遺跡の発掘にさきだって、イラク政府のフアド・サファールとイギリス人のセトン・ロイドが、一九四三年に北メソポタミアのモースル市に近い、ハッスナの遺跡を発掘した。
ここの最初の層は炉の跡はあるが、家屋をつくらず、天幕生活をしていたらしい。
ところが、定住していたかどうかもわからないこの時期に、はやくもプリミティヴな土器はあった。
また麦を刈ったり粉にしたりする石器類、土を掘る石鍬、など明らかに農具と思われるもの、また動物の土偶(どぐう)も出て、これは家畜類を写したもののようである。
ハッスナ遺跡のもっとも古い層は紀元前五八〇〇年ごろとされている。
ジャルモとハッスナのどちらがより原始的な農村かということはむずかしい。
おそらくごく初期の農村は、ところにより家屋のほうが土器よりさきに作られ、またあるところでは家屋より土器のほうがさきに現われるというように、その農村の成立した事情や環境の相違によって、文化内容もちがっていたらしい。
その後、原始農村遺跡は、東イラクや北メソポタミアばかりでなく、イランの中部から西南部、トルコの中部、キプロス、シリア西部、レバノン、ヨルダン、エジプトのナイル川流域にわたってたくさん見いだされ、ブレイドウッドは、その分布地域を「豊穣な三日月地帯」とよんだ。
それらの遺跡の調査によって、オリエントにおける原初の農村のあり方がしだいに解明されはじめ、農耕牧畜の起源についても、その事情がようやく明瞭になりつつある。
その間にセンセーショナルな発見が、ヨルダンのイェリコと、トルコのチャタル・ヒュユックの二遺跡でなされた。 |

豊穣な三日月地帯
|
2 奇怪な頭蓋骨 top
死海に流れこむヨルダン川の谷に、「テル・エ・スルタン」とよばれる丘があり、一九五三年に、キャスリーン・ケニヨン女史を隊長とするイギリスの考古学調査隊がここを発掘した。
このテル・エ・スルタンの丘は、ひじょうに昔から何度もくりかえして町が建てられたために高くなったところで、おそらく九千年以上も前から、人々が居住したところだった。
町ができては壊れ、できては壊れることをくりかえしたために、遺跡の層位はひじょうに複雑になっていた。
近年の考古学的発掘は、この丘のように何度もくりかえして住居ができ、住居址が何層にもかさなっているような遺跡を調査する場合には、まず垂直の試掘溝を頂上から処女層まで掘り、層位を明らかにしてから、発掘範囲を拡大して、上から下ヘ一層ずつ調査をすすめて行くのを普通としている。
テル・エ・スルタンでは、人々が垂直の試掘溝を掘っているときに、その断面に、頭蓋骨が一部分でてきた。
しかし試掘溝の断面に何かが見つかっても、水平に掘り進んではいけないことになっていた。 |

北方から見たテル・エ・スルタンの丘
|
それぞれの層の特色をしめすために、試掘溝の断面は垂直のままにしておかなくてはならなかったのである。
したがって断面から何かを取り除いたりしては、いけないのであった。
そのため頭蓋骨は試掘溝の断面から一部分外につきでたままに、この年の発掘シーズンの間中、ほうってあった。
やっと層位の記録が全部終わり、頭蓋骨は特別なものなので、例外的に、断面から掘りだされることになった。
掘りだしてみると、それはたいへん変わった頭蓋骨だった。
それはただの頭蓋骨ではなく、特殊な加工がしてあった。
頭蓋骨に石膏をかぶせて、耳、眉、鼻、口、まぷたなどを巧妙につくり、その頭蓋骨の持ち主の生前の顔の特色を表わしてあったのである。
目には貝殻がはめこまれ、そのまん中には縦の切れ目が入れられ、ひとみが表わされていた。
しかもこの頭蓋骨が新石器時代に属することは、その層位からみて確実であった。
この頭蓋骨を垂直溝の断面から掘りだすと、そのうしろに同じような頭蓋骨が二つあった。
これを取りだすと、そのうしろにさらに三つ、その奥にもう一つと、つぎつぎに合計七つも頭蓋骨が出てきた。 |

テル・エ・スルタン出土の頭骸骨
特殊な加工がなされていた
|
なかには全体に肌色に着色してあるものもあり、また一部分に彩色の残っているものもあり、かつてはそれらが生き生きと、生前の似姿をよく表わしていたことが察せられた。
ひじょうに繊細な細工で、美術品といってもよいほどのできばえだった。
しかしもちろん美術品であるわけではない。
いったい何のために、頭蓋骨にこんな細工を、テル・エ・スルタッの大昔の住人たちはしたのだろうか。
ケニヨン女史は、おそらく祖先の頭蓋骨を細工したもので、何か宗教的な聖物のようなものだろうと考えた。
学者のなかには、この説に反対して、これは戦勝記念物で、戦争で手に入れた敵の首に加工したものだと考える者もある。
文化人類学者の報告によると、現代のニューギニアのシペク川の岸に住んでいる首狩り種族のあいだにも、頭蓋骨に同じように加工して、顔形を作っているものがある。
その場合には、祖先の頭蓋骨も、敵の頭蓋骨も使われているのである。
とにかく、今のところでは、テル・エ・スルタンの住民が何のために、このように頭蓋骨に細工したのかは、わかっていない。
このテル・エ・スルタンの丘は、ヨルダン王国にあり、旧約聖書のヨシュア記に、ラッパを吹いただけで、石の城壁がくずれ落ちたと伝えられるイェリコの町の遺跡である。
そしてこの遺跡は、ケニヨン女史の発掘により、九千年も前から連続して、女史のいわゆる町がつくられたところであったことがわかった。
「町」という表現が適切であるか否かはべつとして、とにかく大規模な石築の城壁をめぐらした集落として、イェリコは今日まで発見されたもののうち、たぶん世界最古のものである。
ここに最初に集落をつくった人々を、ケニヨン女史は、彼らの使った煉瓦の曲面平底形(プラノ・コンヴェックス)から、「豚の背煉瓦の人々」と呼んだ。
彼らは紀元前六五〇〇年ころ、つぎの「漆喰(しっくい)床の人々」に征服されてしまったらしい。
この両者はいずれも土器以前の新石器時代人で、「漆喰床の人々」が、奇怪な頭蓋加工をした人々だった。
彼らはなかなか宗教的な人々だったらしい。卵形の石を立てた輪のようなものがあったり、神殿だったと思われる建物もみつかっている。
その神殿らしい建物の広間の中央には、火を焚くために使った壇が置かれていた。
一九五六年の発掘のとき、この「漆喰床の人々」の作ったある家の床下から、大事にしまわれていたらしい二つの頭蓋骨がみつかった。
そしてこの家の下にある、より古い家の床下には、三十体の人骨がみつかった。
彼らは家の床下に、死者を葬ったらしい。この人骨のなかには、頭蓋骨のないものが幾つかあった。
ケニヨン女史は、頭蓋骨だけとり去ってべつのところに祀ったのだろうと推測している。
「豚の背煉瓦の人々」は、その遺物・家屋の構造・町のプランその他から、「漆喰床の人々」とはぜんぜんちがう人々だったことがわかるが、彼らも頭蓋骨に対して、特別な祀りかたをしていたらしい。
頭蓋骨だけ切りはなして、たくさん集め、幾つかのグループにわけ、みな同じ方向に向けて並べたり、内側を向かせて円型に並べたりしてある。
テル・エ・スルタンの住民には、こうして最初の人々から、頭蓋崇拝があったようだが、ふしぎなことに、ずつとのちの住民のあいだにも、それが見られる。
「漆喰床の人々」のあとに、いろいろの人々が町をつくって住み、紀元前三二〇〇年ころからは、ケニヨン女史が「原始都市時代」と名づけた段階にはいる。
このころの人々は、もはや死者を床下には葬らず、べつに墓をつくった。
ある墓の中には、頭蓋骨が百十三個みつかったが、それはみな内側を向いて円型に並べられ、まん中には焼いた骨が積み上げられていた。
その墓のようすから見ると、死者はいったん風葬にされ、ばらばらになったころに骨を集めて、墓に運び、頭蓋骨はべつにして、ほかの骨はみな火葬にしたらしい。
テル・エ・スルタンの丘に町をつくった人々は、何度も交替したし、それぞれの人々はそれぞれに異なった文化をもっていた。
それにもかかわらず、頭蓋崇拝だけはつづいているわけである。
これも頭蓋骨の奇怪さに負けないふしぎなナゾである。
3 原始農村から「タウン」へ top
原始農村はあくまで原始農村である。
オリエントの各地にたくさん原始農村はできたけれども、はじめから町邑(ひ=村)のようなものはない。
しかしなかには特別な事情によって、例外的に大きな集落になった場合もある。
今ここに書いたテル・エ・スルタン=イェリコやトルコのチャタル・ヒュユックなどは、そのような例外と認められる。
イェリコでは、まだ土器が発明されていないころに、すでに大きな石を積んで作った城壁のようなものが集落のまわりにめぐらされていた。
また見張り塔のようなものもある。
どうしてそのような例外的なことがイェリコではおこったかというと、おそらく当時から現在まで数千年にわたってイェリコを特徴づけた、湧水のひじょうに豊富な泉の存在と関係がある。
そこは海面下三〇〇メートルの盆地内にあって、釜の底のように常にひじょうに暑く、しかも豊富な水に恵まれて、一年中農業生産が可能なところである。
したがって灌漑農業が、無土器時代にあったとは思われないが、そこの原始農耕は灌漑農耕と同じくらい生産性が高かったとしてもふしぎはない。
それで、そこには「タウン」といってもよいほどの規模の集落が、無土器の新石器時代に早くも出現しえたのであろう。 |

イェリコの見張り塔
|
ケニヨン女史はイェリコを「タウン」と呼んだが、ブレイドウッドはこの場合でも「タウン」というべきでないといって、大議論になった。
けっきょくこの論争は「タウン」の定義いかんに係(かか)わるもので、物別れとなったが、人口の多寡や、したがって労働力の大小、建築技術の水準、永住性、防衛施設の有無、宗教的儀礼いかんなどの点からみて、イェリコが原始農村のうちでも、格段に進歩、発達したものであったということは認めないわけにゆかない。
とくにイェリコの場合、なんのために防衛したかがわからないが、あのすばらしい石築の城壁をつくるためには、そうとう大きな労働力が必要だし、かなり多くの人口の住民が永続的にそこに住んでいることが必要であったに相違ない。
それは天然の降雨による掠奪(りゃくだつ)農法で、数年ごとに新しい農地をもとめて転々せざるをえない普通の原始農村のカテゴリーから、はみでたものであることは確かである。
また最近トルコのコニア盆地で、やはり紀元前六〇〇〇年ごろにさかのぼるという原始農村の跡が発掘された。
そこにもたくさんの家屋が密集しており、数千の住民の集住が推定されている。
また多数の神殿があり、そのうちには壁画や彫刻などで異様に飾られたものもある。
なかでも禿鷹が首なしの人間を襲っている場面の壁画や、豹か山猫のような獣の彩色された浮き彫り壁飾りや、丸彫りの女神像や抱きあった男女の偶像など、驚嘆すべき美術的作品が豊富に出土した。
そのようなことからオリエントの原始農村は、けっして一様なのではなく、いろいろな可能性をもっていることがわかってきた。
たとえば原始農村のあるものは、建築や土木の方面で進歩をしめし、あるものは土器の製作ですばらしい才能を表わしている。
また宗教や美術的造形の方面に主力がおかれたようなものや、商売、交易の方面に目を向けて、仲継ぎ商業みたいなものをはじめ、外来文化を取り入れているものもある。
いっぽう封鎖的な原始農村の状態を、そのままずっとつづけているところもある。
このように一口に原始農村といってもいろいろな型が、ひじょうに早くからオリエントでは現われたのではないか。
従来考えられていたように、原始農村というものを、一つのタイプとしてとらえるのは間違っていたのではないかという反省がなされるようになった。
しかし、まだ灌漑農業がおこなわれず、天水によって乾燥農業をやっていた時代には、一ヵ所にいつまでも農村がとどまっていることは、不可能でないまでも、効率的でない。
農耕地が痩せていってしまうからである。それで原始農村の場合、原則として移動したり分散したりしたほうが合理的なので、おのずから分村という形で発展していった。
そして、だんだんたくさんの村落ができてくると、耕地の争奪や物資の掠奪の問題もおこってくる。
村落は、ある程度の防衛施設が必要になってくる。それで周辺に濠(ほり)をめぐらしたり、土壁を築いたりするようになる。
またそのころになると、内部的にも経済的・社会的発展がみられ、とくに所有権の観念がでてくる。
すなわち穀物や家畜などは村落員全体の協力の所産として共有であっても、土器や服飾品など自分でっくり、自分で使っているものは自分のものという観念が明確になっていった。
ことに身を飾るということはいつの世にも女性の最大関心事であるらしい。
首飾りや耳飾りなどは、個人がもっともたいせつにした私有物だった。
またいつの世にも美しい石や、めずらしい貝など、容易に手にはいらない物は、人々の虚栄心を満足させるらしい。
それらのいわば宝物が、石器の材料としてとくべつ重要な黒曜石などとともに、もっとも早くから原始農村のあいだで交易された。
それらの宝物は加工されて、首飾りや耳飾りになった。
また黒曜石は、その打ち欠いた部分がとくに鋭利な刃をあたえるということから、石器の材料として特別によろこばれ、ひじょうに早くから交換の対象とされた。
オリエントの原始農村における分布の広さから、当時の交易圈の意外に大きかったことが推定できる。
いっぽうその原産地は、アナトリア高原のヴァン湖付近とパレスティナの一部にかぎられていた。
このようにして手に入れたものは自分のものということになり、自分のものであることを明示する必要がおこった。
そこで印章ができた。しかし多くの場合、印章として最初から特別につくったのではなく、首飾りの石などを印章の代用とした。
つまり必要なときは首飾りの刻み目のある石などを粘土に押して、印の役をさせた。自分のものは壺に入れ、それに粘土で蓋をしてそこに首飾りの石などで封印し、自分の所有物であることを明示したのである。
そのために首飾りの石や貝に、いろいろな文様の刻み目をほどこすことが、いっそうすすんで、だんだんにいわゆる印章になっていった。
したがって首飾りは、首飾りであると同時に、印章でもあった。
印章には二種類あった。平たいボタン状のものはスタンプのように押して使い、管玉のようなものはころがして、その表面の刻文を粘土の上に展開して印した。
このように、はじめに印章として使われたものは、主として首飾りの玉であった。
私有という観念がはっきりしてくるにつれ、共同体生活をしながらも、個人の権利がだんだんと明確になって、個人がある程度独立した存在になる。
これは普遍的な現象であった。また他方では、集落と集落の関係がはっきりしてきて、それぞれ使用する農地の範囲、いわば繩張りがきまってくる。
そこから自分のところにあるものと、自分のところにないものを、有無あい通じさせる物資の交換が必要になってきて、交易圈、文化圏ともいうべきのものが成立した。
こうして原始農村における外の関係と内の関係が、だんだんすすんでいった。
そうした原始農村の発展をあとづけ、さらに一般的な意味の町邑や都市になっていった過程を認識するために、メソポタミアで多くの遺丘が発掘調査された。
北メソポタミアのガウラ、アルパチア、テル・サラサート、南メソポタミアのウバイド、ウルク、ジェムデッド・ナスルなどの遺跡は、その主要なものである。
わが東京大学のイラク・イラン遺跡調査団は、テル・サラサートの遺跡を中心に発掘をおこなった。
4 テル・サラサートの発掘 top
原始農村から町邑や都市への発展の過程を知るために、各国が競ってオリエント地方に調査団を派遣したが、最古の原始農村から都市文明までの推移を一貫してみられるのは、メソポタミアだけである。
東京大学イラク・イラン遺跡調査団の最大の目的も、そのような文明の起源と、その初期の発展の様相の解明にあった。
一九五六年からはじめられた東大の調査は、まずティグリス中流域のテル・サラサートを発掘の場所として選んだ。
この遺跡は大小五つの遺丘からなっていて、大きなものは高さ二〇メートルもあり、小さなのは高さわずか四~五メートルのものである。
いったいに低い遺丘のほうがこの地域では年代がさかのぽる。 |

テル・サラサート遺跡全景
|
大きく、高いものは、そのような古い遺跡の上にのちの時代(アッシリア時代ごろまで)のものが覆いかぶさっており、そのために大きくなったものである。
したがって、このように大きいものから小さいものまであることは、ひじょうに古い原始農村から大帝国時代までのいろいろな文化層がふくまれている可能性を示している。
そういう意味で考古学的調査にとって、きわめてよい条件の遺跡と思われたのである。
しかし、五つの遺丘よりなるテル・サラサートの遺跡全体を発掘調査するには、そうとうの年月が必要なことは、一見して明らかであった。
ここで東大の調査団がまず手をつけたのは、第二号丘という比較的小さな遺丘で、高さは約八メートルほど、長軸約八〇メートル、短軸約六〇メートルの楕円形のものであった。
その丘は表面調査の結果では、ごく上層に原始農村から町邑に移ってゆくころの文化層があるほかは、大部分が原始農村時代に属し、その下層にジャルモやハッスナに相当するような原始農村成立当初の文化層が見いだされるのではないか、という予想であった。
その発掘結果はだいたい予想どおりであった。やや意外であったのは、ウバイド期という原始農村文化の一時期に属する文化層がここではひじょうに厚く、六メートルにも達している。
そこには何層も住居址がかさなっていて、最初の二シーズンではついに、その層の全部の発掘が終わらなかった。
これまで、ウバイド期はメソポタミアで原始農村がもっとも充実した時期で、その文化の分布範囲も、南北メソポタミアばかりでなく、遠くイラン西北部や、シリア西部におよんでいたことが知られていた。
しかし実のところ、くわしい調査は一、二ヵ所の遺跡についてのほかは実施されていなかった。
北メソポタミアでは、アメリカの調査隊がおこなったテベ・ガウラの調査が一つあるだけであった。
そこで東大の調査団は「ナッシング・ロスト(何物も失わず)」をモットーに、精密このうえない科学的方法で、この厚いウバイド期の文化層にとりくんだ。
この発掘法は、見学にきた各国の調査団を感嘆させたものである。
第二号丘では、その東南斜面に原始農村が立地していた。
そこには広い中庭を囲んで住居が建てられ、中庭は共同作業場で、パン焼きかまどや、土器焼きかまが据えられていた。
住居は四角いプランの日乾し煉瓦づくりで入口には木の扉があったらしく、その扉の軸をうけるための、石の丸い軸受けが見いだされた。
住居の床は土間で、時にはアンペラ状の編み物や、わらをしいたものが検出された。
屋根は残っていないので、どんな状態であったかわからない。
たぶん現在のこの地方の民家と同様、陸屋根であったろうと推定される。
住居のあまり壊れていない部屋から、土器や石器その他さまざまなものが出土した。
土器はウバイド期を特徼づけたきれいな幾何学文の彩文土器であったが、日常の土器には無文の粗製のものが多い。
大きい水がめから、小さなコップ形のものまで、器形もさまざまである。
みな手づくり製で、たぶん女の手で作られたものであろう。
やさしく、あたたかみのある文様や、小ぎれいにまとめられた器形などが、そのような印象をあたえる。
石器は磨製の石斧や石のみ、石臼、石杵(きね)など、打製の鎌の石刃が主要なものであるが、磨製の環石あるいは石棒頭の類もある。
これらはまん中の孔に棒の頭を貫通して、畑の地面を掘る土掘り棒のおもりとしたもので、このようなおもりのある棒で掘ると、堅い地面に種をまく穴をほりやすいのである。
これらの石器によってもわかるように、彼らは農耕生活をしていた。
作物は麦で、炭化した麦粒の実物が穀物倉から出土した。この麦粒は石臼と石杵で製粉され、パン焼きかまどで、いまのイラク農民のパンと同じく分厚いせんべいのようなパンに焼かれたに相違ない。
穀物倉は第二号丘の西北斜面やその東側で、三ヵ所円形のプランのものが発見された。
いずれも横に入口がなく、なかから麦粒がたくさん出土したので、穀物倉と考えられた。
これらの倉が住居群から離れて孤立していることは、それが特定の人のものでなく、村人共有の穀物倉であることを暗示している。
農耕とならんで牧畜も重要な生業であった。 |

彩文土器、杯(上)と碗(下)
テル・サラサート出土、ウバイド期
|
このことは、羊などの形を表わした土偶が多く発見されたばかりでなく、その毛をつむいで織物をつくるためのソロバン玉や、半円錐形の紡錘車が少なからず見いだされたことからわかる。
また狩猟もおこなわれていた。
そのことは紡錘形をした投弾がひじょうにたくさん、ところどころにしまってあったことから疑いない。
紡錘車も投弾も、ともに粘土製であった。石器も多く、きり、へら、針などがあった。身を飾るためには、石、貝、骨、粘土などで種々の玉類をつくった。
管玉も、平玉も、垂玉もあり、一面に刻み目の文様をつけて、印章として使用するようにしたものもある。
羊を模したらしい土偶や地母神像とみられる女人の土偶などは、家畜の繁殖、穀物の豊穣などを祈願してつくられた、宗教関係の作品に相違ない。
このウバイド期の集落には外敵をふせぐための施設も、また武器として役に立つような石器も見いだされなかった。
当時、人々は平和な生活をたのしんでいたことがわかる。
村民は死ぬと、おとなは自分の家の床下に屈葬され、幼児は壺のなかにいれられて、いわゆる甕棺(かめかん)葬にされた。
ここでは特別の墓地はなかったようである。
神殿もウバイド期の層からは見いだされなかったが、当時それがあったことは、テペ・ガウラの例などから確実である。
この時期になると、農耕文化が物質面でも精神面でもいちじるしく充実してきており、その集落の安定性、持続性もひじょうに大きくなっていた。
そのことが厚い文化層や重層した住居址となって表われているものとみられる。
一九五八年以後、イラクの革命で東大の発掘は一時中断されたが、一九六四年再開され、第二号丘は最下層まで掘りすすめられた。
ウバイド期の文化層は第十四層までつづき、そこで急に変わって、ハッスナと同じような原始的土器をもった層になった。
そこには住屋がまだあったが、その下の最下層になると、土器は上の層と同じだが建物はなくなり、竪穴住居址が見いだされた。
その竪穴住居址は、かつてブレイドウッドがマタッラーで発見したものに似ていた。
こうして京大の調査団は、ついに原始農村成立当初ごろの遺跡を掘りあてたのである。
ハッスナ、マタッラー、テル・サラサートなど中部メソポタミアでは、土器は早く現われたが、家屋のほうは比較的おそく出現したようである。
これに対し、カリム・シャヒル、ジャルモなど東イラクのクルディスタンでは、家屋のほうが早くて、土器が遅かったことは前述のとおりである。
しかしこれらの原始農村成立期の遺跡は年代上は大差ないものとみられる。
以上のように、テル・サラサートの第二号丘では、ジャルモ・ハッスナ期の住居址のある二層の上に、すぐウバイド期の住居址が重層した厚い層がある。
これは直接つづくのではなく、時間的なギャップがあって、その間にサマッラ・ハラフ期というひじょうに美麗な彩文土器で特徴づけられた一時期があったことは、他の遺跡の例で疑いない。
ここではその期間に人が住まず、ウバイド期になってから、ジャルモ・ハッスナ期の廃墟の上に人々がまた住むようになった。
それから以後は、ひじょうに長時間人々が住みつづけたことが、厚いウバイド文化層の存在によって確実である。
そうしてその後に、ウルク期の人々がここに来て住んだ。
その遺跡は、第二号丘のごく上層に見られるが、住居址のほかに、神殿址があった。
その神殿址は、保存状態のよい点でめずらしいものである。
約三メートルに七メートルの中庭を中心に、西側に五部屋、東側に三部屋をもち、とくべつ大きな日乾し煉瓦で頑丈に造られていた。
中庭の一方には祭壇と思われる壇があり、西側の一室には奉納品と思われる土器、投弾、紡錘車があり、ほかの一室からは動物土偶が見いだされた。また別の一室には犠牲を焼いたのではないかと思われる青い灰がつまっていた。
この時期の土器はウバイド期のものと異なって、彩文土器がない。全体に芸術性が稀薄になり、そのかわりに実用性が増しているようにみられる。
このウルク期の文化は北メソポタミアより南メソポタミアで栄えた。そこでは土器もろくろ製のものが一般的になり、集落の規模も町邑的に大きくなり、神殿なども立派なものが造られた。 |

神殿址(テル・サラサート)
|
これらのことが、ウルク――それにちなんでウルク期といわれる――などの遺跡の調査の結果、明瞭になった。
そうしてその後半期は、つぎのジェムデッド・ナスル期と合わせて「原文字期」などとも言われる。
そのころからジュメル文字のもとになった絵文字が使われるようになり、このころシュメル文明の基礎が南メソポタミアに確立したという解釈にもとづくのである。
この南メソポタミアの原文字期あるいはジェムデッド・ナスル期に、北メソポタミアでそれにあたるものがニネヴェⅤ期である。
東大の調査団は、一九六五年にテル・サラサートで、もっとも低い遺丘、第五号丘を発掘して、ニネヴェⅤ期のひじょうにめずらしい遺跡に掘りあたったのである。
それは大きな共同穀物倉と土器焼きかまなどのある作業場の遺跡であった。
穀物倉は南北二〇メートル、東西六メートルぐらいの細長いプランの、日乾し煉瓦建てで、煉瓦でつくられた根太(ねた)の上に、高床式に建てられていた。
建物の内部は、中央を南北にはしる厚い壁で、東側と西側の二つの部分にまず区分し、その両区をさらにいくつもの部屋に区画している。
それら各室は個々に独立していて、たがいに入口がないばかりでなく、穀物倉全体としても常用の入口をもたないのが特異であった。
各室にはそれぞれ東西の外側から梯子によって出入りしたのに相違ない。
これはネズミの侵入をふせぐための工夫であろう。
同様な工夫は床についてもなされていて根太の上の高床は、まず葦、よしの幹をしきならべて、その上に粘土を張ったものである。
このようにしておくと、葦、よしの幹には硅素がふくまれているから、これをネズミがかじると歯をいためるため、けっしてかじったりしないということである。
この方法は現在でもイラクの農村の穀倉にみられる。
この穀物倉は火事にあって崩壊したので、壁の日乾し煉瓦は焼成煉瓦のように堅くなってよく原形を保っており、部屋のうちに貯えられた麦粒も壺のなかに入れられたまま、あるいはアンペラのような敷き物の上に盛り上げられたままの状態で、炭化しておびただしく発見された。
ここは住居でないので、日常生活に必要な道具類はほとんどなかったが、穀物をいれるための甕(かめ)や壺、枡(ます)の用途をもったのではないかとみられる大小のコップ形土器が部屋のなかで見いだされた。
そのコップ形土器は、緻密な水洗粘土で、ひじょうに精巧に焼かれた陶質の土器であった。
器形は、無縁、尖底なのが特徴的であり、普通のコップのように使用されたものとは思えない。
東大の調査団員たちは、これは枡(ます)ではないだろうかと見当をつけた。
その容積は必ずしも正確ではないが、一・三・六あるいは一・二・三・六などの単位を示すようで、だいたい六進法と思われる。
もしこのコップ形の土器が枡だとすると、これは世界で最古の枡ということになるわけで、重大な発見である。
じつはこの高床式穀倉自体が紀元前三〇〇〇年ごろにさかのぼるもので、そのように古い時代の穀倉の類例はインダス文明のハラッパーの遺跡にただ一つあるだけで、ハラッパーのものは紀元前二五〇〇年ごろである。
それよりサラサート第五丘のものは五百年ぐらい古く、世界最古の高床式穀物倉ということになるのである。
なお、この高床式の内部で円筒印章(シリンダーシール)が三、四点みつかった。その印章に刻された図文は、ここで見いだされた彩文土器の彩文と同様なものである。
それは南メソポタミアのジェムデッド・ナスル期の円筒印章の刻文とひじょうに似たもので、両者の文化的交流関係、年代的併行関係を明示する貴重な資料である。
この高床穀倉に接して、パン焼きかまどがあり、また大きな円形の土器焼きかまが見いだされた。
土器焼きかまは、それから出火して火事になることをおそれて、外側に円形の日乾し煉瓦の厚い壁をめぐらしていた。
また土器焼きかまのわきには、高さ一メートルにちかい大きな水がめがそなえつけてあった。
そこに粘土と水をいれて両者を攪拌(かくはん)し、水を入れて撹拌(かくはん)して、無砂の精選された粘土をつくり、それで土器をつくったらしい。
土器にはネズミ色の堅緻(けんち)な陶質のものと、赤や黒の顔料で幾何学文や奇怪な動物文、行列する鳥文などを表わした彩文土器などがあった。
後者は、一方では南メソポタミアのジェムデッド・ナスル期の彩文土器に酷似している。
他方、イラン高原の同時代の彩文土器ともあいつうじる特色をしめしていて、当時の広い範囲の文化交流を示唆している。
このように東大の調査団は、第五号丘でニネヴェⅤ期――南メソポタミアのジェムデッド・ナスル期にあたる――のめずらしい遺跡に遭遇したが、そこに住居址はなかった。
それで、ここは他のところに住居をかまえた人々の共同作業場、共同倉庫のあった地区と推定された。
それでは人々の住居のある集落はどこにあって、どのような規模のものであったろうか。
それらのことは、第一号丘や第三号丘を発掘してみなければ正確なことはわからない。
試掘の結果ほぽ推測されていることは、それらの両丘に、ひじょうに規模の大きな、町邑ともいうべきミネヴェⅤ期の集落があって、しかもたいへん長い期間繁栄したらしいことである。
将来これらの遺跡が完全に発掘されれば、北メソポタミアにおける原始農村から町邑へ、町邑から都市への推移が明瞭になるであろう。
top
**************************************** |