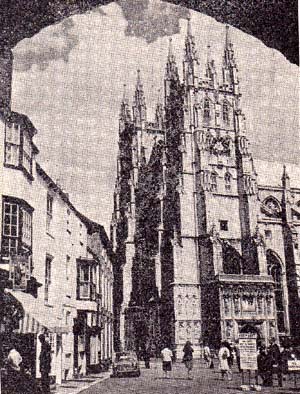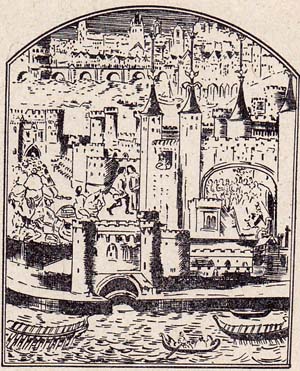|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9 10
11 12
13 14
世界の歴史7 ルネサンスの時代
1 「カンタベリー物語」の世界
1 物語への招待 top
|
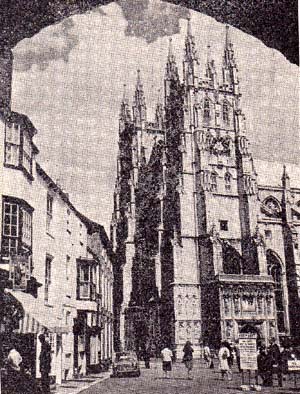
ロンドンの東100キロのカンタベリー大聖堂、
ここは古くからのイギルス人の巡礼地になっている。
|
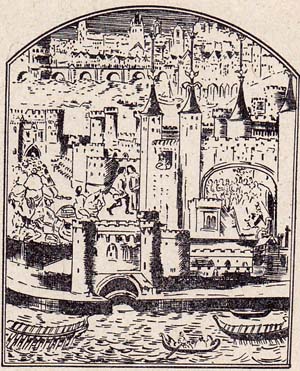
12世紀のこの聖堂のトマス・ピッケット大司教が、カトリックの
権勢をかけて時の国王と対立し暗殺された。
上はピッケットの殉教の絵画。
|
読者よ、巻頭のひとときに、イギリス十四世紀の詩人ジェフリー・チョーサーとその代表作 『カンタベリー物語』について知られるのも、無益ではあるまい。
読者はあまり聞かれたことがたい名前かもしれないが、このチョーサーはイギリスが生んだいわば最初の国民的詩人であり、また近代的な文学の先駆者として、イギリスのみならず、ヨーロッパの文学史にユニークな地位をしめている。
十四世紀といえば、イタリアにこそルネサンスの花が咲いているが、まだ文化がおくれていた西ヨーロッパにおいて、とくにイタリアやフランスの文化のまねが多いイギリスにおいて、チョーサーははじめてイギリスの土に根がはえた文学を書いたのである。
と同時に、生き生きとした個性をえがき、当時のイギリス社会の一断面をしめす人間劇をつくりあげた点において、彼は、「イギリス・ルネサンスの父」ともよばれているのだ。
そしてチョーサーにこうしたよび名、こうした地位がささげられるのも、『カンタベリー物語』という作品のためである。
このカンタベリーはケント州の一都市で、寺院があり、いまはイギリス国教会の中心地である。
しかし当時は宗教改革以前のカトリックの時代のことで、そこには聖トマス・ペケットの墓所があり、イギリス人のもっともポピュラーな巡礼圸であった。
トマス・ペケット(一一一八〜七〇)は十二世紀のカンタベリー大司教で、カトリックの勢威をかけて国王ヘンリー二世(在位一一五四〜八九)と対立し、暗殺された人物であり、それ以来、殉教者として尊敬されていた。
『カンタベリー物語』の巡礼たちも、ときは四月、春の日ざしにめぐまれ、こころよいそよ風に吹かれ、小鳥のさえずりを聞きながら、やわらかい新芽がふく木々のなかを、この寺院へ進んでゆくのである。
そして巡礼たちが往復の道すがら話をするという物語の構想であったが、これは実現せず、巡礼の一行がカンタペリー寺院を望見したところで、この作品は永遠に未完に終わることとなった。
一つ一つの話のなかには、作者がすでにまえから書いていたものもあり、なかには中世から流行したいろいろな話もふくまれていて、貴族社会のラヴ・ロマンスや宗教的な信仰・奇蹟物語から、庶民的な世俗の話にまでおよんでいる。
チョーサーは全体としては一三八七年ごろに着手し、一四〇〇年の死まで十余年筆をとった。
しかしついに完成できなかったのである。
この本のはじまりは、巡礼を思いたったチョーサー自身が、ロンドンのある宿屋にとまって支度をしているとき、同じ目的の一団がドヤドヤと入ってくるという趣向である。
登場人物は三十人ばかりで(なかにはほんのつけたりの人物もある)、話をするのは二十三人、物語の数は二十四、これは巡礼の一員であるチョーサー自身が、二つの話をしているからだ。
そしてこれらの物語のうち、二つだけがふつうの文章、つまり散文で、他の話はみな詩の形式をとっている。
それらのなかには、若干の未完や中断のものもある。おもな登場人物は、巻頭についている全体の「プロローグ」、すなわち「総序の歌」のなかで(それぞれの話のまえにも、短いプロローグがついている場合が多い)、つぎつぎと巧妙に紹介されている。
そして登場人物の顔ぶれは、じつに多方面な社会層からなりたっている。
まず騎士とその息子である騎士見習い、および従者は貴族や武士階級を表わし、尼僧院長とそのお伴(とも)である尼僧と三人の僧、それから修道僧、托鉢(たくはつ)僧、免罪符(めんざいふ)売りたちは僧職をしめし、さらに司祭もいる。
知識階級からは医者とオックスフォードの学僧と高等弁護士が登場し、新興階級としては地主、貿易商、料理人をつれた五人の市民たち(大工、小間物商、織物商、家具装飾商、染物商)が選ばれ、異色ある存在としては、船長、宿屋の主人、機織りに長じたバース(地名)のおかみさんがいる。
また領主の土地などを管理する家扶(かふ)や粉屋もおれば、教会裁判所への召喚吏(しょうかんり)、司祭の弟の農夫なども顔を出し、まことににぎやかな巡礼の一行である。
そしてこの多彩な顔ぶれには、おそらくチョーサーの実生活のゆたかな体験が生かされたものと思われる。
ではこの詩人はどういう生涯を送ったのであろうか。
2 詩人チョーサー top
チョーサーは一三四〇年ごろ(これには異説もある)、ロンドンの葡萄酒商の家に生まれた。
一三五七年ごろから、チョーサーは父が関係していたエドワード三世の宮廷につかえ、まず小姓となった。
フランスとの百年戦争に従軍し、捕虜になったこともある。
宮廷生活のあいだに、エドワード三世の王子で、政界の実力者ジョン・オブ・ゴーント(一三四〇〜九九)の寵(ちょう)をうけることとなり、チョーサーの公的生活における浮沈は、この人物のそれと密接にむすびついていたらしい。
またチョーサーは一三六六年ごろ、王妃の女官フィリパと結婚した。
一三七〇年代から彼は、王命によって商談や外交上の仕事で海外に出張し、イタリアをも訪れた。七四年にロンドン港の税関監査官、八五年にケント州の司法官となった。
この間、七七年からリチャード二世が即位したが、チョーサーの官吏としての地位には変動はなかった。
八六年にはケント州の議員として下院に出た。
八九年ごろ、土木工事監督官に任ぜられ、九〇年代には、王室関係の林務官をつとめたようである。そして一四〇〇年十月、彼はおよそ六十年の生涯をとじた。
このチョーサーの生涯をかえりみるとき、それなりに時代を反映していることがわかるだろう。
商工業や貿易が富をまねき始めたころに、典型的なブルジョワである酒商の家に生まれた彼は、商人たちのあいだで成長することによって、新興階級の息吹きに接したといえよう。 |

14世紀に、雑多な人物からなる
カンタベリー巡礼者の旅行記
『カンタベリー物語』を書いた詩人チョーサー
|
それから彼は上流貴族社会、さらに宮廷において成熟し、フランスの影響が強い文化のなかで青春の血をわかしたのである。
そして国民的大事件ともいえるフランスとの戦争も体験した。
イギリスの国際的地位が高まってきたとき、たびたびの外交的使節が彼の仕事となった。
議会の地位がしだいに固まりつつあったとき、わずかなあいだとはいえ、議員としてその実情を味わった。
また種々の官職につき、まじめな役人としての一生をすごした。
しかしそのあいだ、詩がけっして忘れられたのではない。むしろこうした実生活を通じての豊富な観察、体験のうちに、彼の詩心がはぐくまれたのである。
詩人チョーサーはふつう三期に分けて考えられている。
第一期はいわば「フランス期」で、宮廷においてフランス文学、ラテン文学に感化された時代である。
一三六九年、ジョン・オブ・ゴーントの最初の夫人が世を去ったが、若い詩人は故人を追悼して、『公爵夫人の書』という題の長い詩を書いた。
これはチョーサー最初の大作で、黒衣の騎士とその愛人の恋物語であり、中世フランス文学の影響が強く現われている。
このいわば 「パリふうのマントをまとったイギリス人」にとって、イタリアへの旅は決定的であった。
イタリア・ルネサンスはすでに展開しており、その影響のもとに、第二期の「イタリア期」におけるチョーサーの詩作はめざましく、傑作『トロイルスとクリセイデ』などが生まれた。
これは中世ふうの恋愛詩であるが、そのなかには性格や心理の描写などにおいて、すでに近代文学的な傾向がみうけられる。
しかし真の詩才はついにその国の土壌に花開くものであろうか。
第三期「イギリス」期」、チョーサーの詩才はやがて独自の境地に実をむすぶ。
彼の社会や人生に対する観察が深まり、さまざまな体験やいろいろな人びととの接触が、その円熟した心境にとけこんだとき、先進イタリアやフランスの文芸の模倣をこえて、イギリスは最初の国民的な詩人をもちえたのだ。
そしてチョーサーの諸作品が英語――むろんいまの英語とはちがった古いものであるが――で書かれていることに注目しなければならない。
彼はラテン語、フランス語がよくできたし、またそれらが使用されている上流階級のなかで詩作したにもかかわらず、英語、とくにロンドンの言葉を使用した。
それはイギリス人が外国語の支配を脱し、いろいろな方面で英語を使用するにいたった事情を反映しているし、またチョーサーの詩作そのものが、この英語の確立に影響しているのだ。
母国語の発達!
それは一国のナショナリズムの発展にとって大きな意味をもつ。
この点でもチョーサーは国民的詩人とよばれるにふさわしいであろう。
ではその代表作にかえることとしよう。
3 人間劇の誕生 top
『カンタベリー物語』の根本の構想――高級の貴族およびもっとも卑賤な階級をのぞいては、ほとんどすべての十四世紀イギリスの諸階層から人物を登場させ、これにそれぞれの性格にふさわしいような物語を語らせたということ、それは簡単な思いつきのようにみえるかもしれない。
しかしこれについては、「たんなる文学上の革新以上のもの、知的態度の変化にほかならない」とか、「ヨーロッパ思想史における一つの転換点」というまでの評価さえあるのだ。
チョーサーはまず諸性格を観察する。彼らの相違を認識する。
そして生き生きとした個性を描写しようと努めるのだ。このような群像、とくに庶民的な群像が文学にあらわれたこと自体、すでに新しいことであった。
まして各人物がそれぞれに信ずるところを、だれにもはばかるところなく、いかにも自由に大胆に発表してゆくありさまは、たしかに若々しく新しい精神のめざめかもしれない。
チョーサーは「総序の歌」の一節で、巡礼たちの言葉や振舞を忠実に、できるだけ正確に語るという意図を、キリストさま御自身も聖書のなかであけすけにお話しなさったなどとユーモアをまじえて述べているが、ここに近代リアリズムの芽生えが見られるであろう。
こうして描きだされた巡礼たちは、当時のもっとも貴重な人間記録の一つとなった。
彼らは彼らの人生のみを生きている。国家、社会の動きにはあまり心をとめない。
関心はもっぱら財布や情事にある。国王よりも隣の亭主のほうが、王妃よりも隣の細君のほうが、ずっと気になるのだ。
簡単である。あらゆる時代に共通するであろう大衆の生き方を、彼らもまた示すだけだ。
それゆえにこそ、我々は、彼らが実在し、呼吸し、彼らが無関心だった当時の歴史をつくっていたことを感ずるのである。
つまりチョーサーは、「真実」に忠実であろうとしたのだ。
しかしこの場合、彼はそのみにくい面を強調しようとはしなかった。
彼は人間に対する深い愛情をもっていた。
人間性とはふつう想像されているよりは、はるかに複雑なものだと知っていた。
この人間に対する共感は、一種のユーモアをもった楽天主義となってあらわれた。
人間の弱点や悪を皮肉にユーモラスに暴露しながらも、心から人生を肯定してやまない態度である。
そしてこれに加うるに中庸を失わない円満で健全な常識――ここに我々は感じないであろうか、イギリス的な考え方の一つの典型があると。
さて『カンタベリー物語』は戯曲ではないが、一種のドラマ的構成をもっているとも考えられよう。
諸性格は見事なリアリティーをもつとともに、思考や言葉つきなどで、それぞれの社会層にふさわしい人物に書きわけられている。
さらに各人物にわりあてられた物語はたんなる独白ではなく、他の人びとに話しかけ、返答をまねき、批評をよび、ついには会話とさえなっている。
こうしていろいろな動機や局面にみちびかれつつ、個性がたがいに働きかけ、巡礼者たちは劇的な操作を始めてゆく。
いわばここに一つの小社会がつくりあげられているのだ。
カンタベリー詣でという共通の目標をもって――。
その中心に登場人物の一人、巡礼たちがとまった宿屋の主人ハリー・ヘイリーが立っている。
彼が「総序の歌」の最後に紹介され、たがいに物語をして、いちばんすぐれた話をした人に、あとで晩餐会を開いてみなでおごってやろうという、『カンタベリー物語』の主旨を示すのも、この人物にふさわしい役目であろう。
彼は巡礼たちのリーダーをもって自認し、かつ案内役や審査役をかってでる。
そしてなるほどこれに適している。がんらい宿屋の主人であってみれば、人びとをもてなし、楽しませる方法を十分に知っているはずだ。
一面識もない巡礼たちのあいだにあって、彼はみなをくつろがせる中心人物である。
彼はおだやかな良識のたすけをもって、この大役を演じて手腕のほどを示し、また自分があつかっている人びとになみなみならぬ理解力を示している。
彼は相手の身分によっておもねったりはしない。
その人の真価に頭をさげるだけだ。
したがって巡礼たちをみな平等に取り扱っている。
騎士や医者から粉屋や船長にいたるまで、みな同一視して自分でリードしてみせるではないか。
そして彼はなんの遠慮もなく、自分の意見をあたりかまわずしゃべりまくる。
こうして「話しっぷりはあけすけだが、分別をそなえ、物知りでもあり、男らしくて、陽気でユーモラスな」この宿屋の主人は、いわば当時の新しい市民のタイプではあるまいか。
チョーサー自身も書いている。
「我々の宿の主人は、ひじょうに目だつ男で宴会の接待役にしてもふさわしい。
眼は鋭く、柄も大きくロンドンのチーフサイドの町人のなかで、こんなにりっぱな男はまたとあるまい。
その話しぶりは大胆で賢明、機転にとんでいる。
また男らしさも満点であった。 |
この町人が貴賤貧富の一団を、臨機応変に統率してゆくありさまをみるとき、『カンタベリー物語』という小社会に、一つの形容詞をあたえることはできないであろうか。
デモクラティック――そうである。
『カンタベリー物語』を評価する糸口が、たしかにこの人物のなかにあるはずだ。
4 聖職者の群れ top
『カンタベリー物語』は直接に国家、社会を論ずる本ではないが、それが時代を代表する書であれば、おのずからそこに主題が存するであろう。
それは宗教と僧侶、女性と結婚生活の問題である。
これらはこの作品に登場するような諸人物にとって、いつでも関心のまとであるとともに、当時としてもとくに注目された問題であった。
中世盛期その勢威を誇った教皇も、十四世紀後半にはローマと南フランスのアビニョンに両立、分裂するありさま、宗教界全体の堕落もようやくいちじるしいものがあった。
十六世紀宗教改革運動の先駆者であるジョン・ウィクリフ(一三二〇ごろ〜八四)と、その一派ロラーズの活動は、チョーサーと同時代に展開しており、あのジョン・オブ・ゴーントは、このウィクリフと関係したこともあった。
この点において『カンタベリー物語』はまたそれなりに、時代の影をやどしているにちがいない。
すでに巡礼ということ自体が、昔とはちがった意味をもっているではないか。
むろん、カンタベリー詣でという一つの目的で、巡礼たちは結びつけられている。
しかしそれは殉教者の霊にひざまずくための旅というよりも、気ばらしのハイキングとでもいうべき光景ではあるまいか。
いかにもそれにうってつけの修道僧がいた。大意を紹介してみよう。
「……
めだってりっぱなお坊さんで、
馬を乗りまわし、狩りが大すき
男らしい男で、修道院長にもなれそうだ
よい馬をたくさん飼っており
風をうけて手綱を鳴りひびかせながら、乗ってゆく……
むかしの聖者さまがきめられたおきては
ふるくさく、きびしいので
そんなものをすててしまい
当世風によろしくやっている
狩りをする者は聖職者でなく
勤めをおこたる修道僧は、水からでた魚にひとしい
というような文句を
彼はまったく相手にせず
そんな文句は、牡蠣(かき)一つのねうちもないと思っている……」 |
托鉢僧はもっとひどい。
まことに陽気で、むだ口とおせじがうまく、自分が手をつけた若い娘に、自腹をきって結婚をとりもったり、金持ちの女房たちとも親しかった。
よい収入になると思えば、すぐに罪の許しを与えてやるし、泣いたりお祈りするかわりに、托鉢僧に銀貨をくれたほうがよいと思っている。
彼の外套には、かわいい娘っ子にやるための品物がつめこんである。
またこころよい声をもっていて、楽器にあわせてうたう歌もうまいものだ。
病人や貧乏人を相手にせず、金持ちにとりいって金もうけにも余念がない。
貧しい後家さんでも、彼のたくみな言葉にひっかかり、財布の底をはたいてしまう――。
のちにルターの宗教改革運動でにくまれ役となる免罪符売りの僧も、すでにチョーサーの筆によって、見事に典型化されている。
ローマからまっすぐにやって来たこの男は、大声で「こちらへおいでよ、恋しいひと」と歌っているありさま、見たところは貧弱だが、悪知恵にかけてはこれほどの男はちょっと見あたらない。
彼は枕かけを聖母さまのベールだとか、聖ヘテロさまのゆかりの品があるとか、弁舌さわやかに善男善女をありがたがらせ、貧しい司祭の二ヵ月分よりもたくさんの金を、一日で手にいれたりする。
一方、尼僧院長はどうであろうか。彼女はもっとも同情的に描かれ、チョーサーの理想の女性の型とさえ考えられている。
たとえば彼女をめぐる描写は礼儀をわきまえ、しつけがよく、愛らしくて慈悲深く、しかも態度は堂々としているというような文章である。
しかしこのチョーサーの筆のはこびは、理想の女性像というよりも、なにか笑いをふくんで軽く揶揄(やゆ)しているような感じがないでもない。
それにしても当時の教会のおきてによれば、修道僧にせよ、尼僧にせよ、僧院を離れることには問題があり、したがって「尼僧院長はそもそも『カンタペリー物語』に顔をだすべきではなかった」のではあるまいか。
なぜであろうか?
この身分がよい尼僧院長が共に巡礼する仲間、そして彼らが語る話の内容を思えば、その答えはやさしいであろう。
なるほど、三人の僧と一人の尼僧とが彼女をまもっている。
しかし彼女の目と耳とをだれがふさぎえようか。
そうでなくてさえも、すでに俗世の波ははげしく僧院の壁を洗っていたのである。
彼女もまた、十四世紀に数が多かった「水からでた魚」の一人なのだ。。
巡礼たちの物語に登場する僧侶階級も、けっしてかんばしい姿を示してはいない。
年とった大工の美しく若い妻と関係したり、金持ちの商人の有閑マダムを誘惑したり、ゆすりを働いたり、金をまきあげようとして悪魔に地獄につれてゆかれたり……したがってあの宿屋の主人が、聖職関係者たちに反感をいだくのも当然かもしれない。
彼は僧侶などなんとも思わない。彼は船長がその話で、僧侶を攻撃したことを喜び、召喚吏と托鉢僧がいさかいを起こすと、ぴしぴしたしなめている。
免罪符売りの僧とはみずから口論を始めるありさまだ。
また彼は僧侶の性生活についても、遠慮のない言葉をはいている。
これは宿屋の主人一人にかぎられたことではなく、当時の庶民大衆の声であったのであろう。
チョーサーはただ見たままを、耳にしたままを筆にしたのみであろうが、それが、彼の望むと望まざるとにかかわらず、イギリス人のローマ・カトリック教会への反感や失望をもたらしたとは考えられないであろうか。
5 女性論 top
一方、『カンタベリー物語』における色欲のとりあつかい、それにともなう女性への不信、結婚生活への皮肉は有名である。
この点では、ダンテの『神曲』に対して『人曲』といわれ、人間の赤裸々な描写でイタリア・ルネサンス文学を代表するボッカチオの『デカメロン』(『十日物語』、十四世紀中ごろの作)と、『カンタベリー物語』はよく似ている。(ただし、この両者の関係の有無については議論が多い)
女の忠言は多くの男の身をあやまらせるとか、女性は秘密をかくしえないから、自分の妻にもそれをうちあけるべきではないとか、女は魔性でその性は悪であるとか、いろいろ示されているが、とくに妻の不貞にあざむかれている夫へあびせる笑いは、『カンタベリー物語』にもよくみうけられる。
あの宿屋の主人も自分の女房は苦手とみえる。
「ご存じなかろうが、じつのところあの女と縁組みしたのはまことにもって残念至極、
女房の欠点をいちいち数えたてたらおれは大馬鹿ということになろう。
なぜって、この席のだれかさんによって女房めにしゃべられてしまうからさ……」
そして妻が忠言をもって夫をいさめたというある話を聞いて、宿屋の主人はいうのだ。
「ああ、いい話だ、酒の一樽(ひとたる)よりもこの話をうちの女房に聞かせてやったほうが、
おれの身にはありがたいんだが……」 |
それはともかく、『カンタベリー物語』の女性といえば、バースのおかみさんについて語らなくてはなるまい。
織物を得意とする点で当時の新しい産業をあらわし、頭巾(ずきん)から靴にいたるまで上等な品々を着こなし、ローマやエルサレムまで巡礼し、色白で、あだっぼいこの女は、その社会的地位において、その物の考えかたにおいて、宿屋の主人と時代をともにするものといえいう。
そしてなによりも現実的なのは、彼女の結婚観であろう。
若いころの情夫は別としても、十二のときから結婚し、正式に五人も夫をとりかえた彼女は、まあ、よくもそんなになんども結婚したものだと、自分でもあきれながら、それについて、むかしの聖人さまの言葉を的確に引用しつつ、よどみなく弁明してゆく。
彼女は堂々と自分の結婚に対する主義と抱負をのべ、五人の夫にかこつけて、男性の弱点、短所を暴露し攻撃してやまない。
けっきょく、女房こそ一家の長であり、夫がこれにしたがうのがあたりまえで、それによってのみ結婚生活は幸福になりうるというのが、彼女の信念にほかならない。
そして彼女が語る話――かつて若い騎士が一年と一日のあいだに、「女がもっとも望むものはなにか」という難題の答えをさがさねばならなかったとき、ついに「女は夫をも、恋人をも、思うままにすることを望んでいる」という解答に達するところの彼女の話は、いかにもその持論にふさわしい。
このバースのおかみさんは、ある人びとがいうようにフェミニズムの代弁者であろうか。
それともほかの人びとがみるように、女性と結婚とに対する諷刺の集大成であろうか。
だがそうした解釈をうち忘れるほど、彼女のとうとうたるおしゃべりの交響楽は読者を唖然(あぜん)とさせるのだ。
おそらくシェークスピアやラブレーのような作家が創造したわずかな大物のみが、彼女に匹敵しうるであろう。
彼女はまさしくルネサンス的な人間であったのだ。
そういえば、バースのおかみさんだけのことではあるまい。
宿屋の主人をはじめとして、良心の苦しみもなく、荒仕事でかせぎまくる船長、おもしろおかしく暮らすのがその主義で、四季に応じて美食のかぎりをつくすというエピキュリアンをもって自認する地主、外国産の衣裳に身をかため、営利商売の才にかけてはならぶ者がなく、つねにどうしたらもうかるかと考えている貿易商、自分たちで専属の料理人をつれ、りっぱな服装で、財産も収入もあふれんばかりの五人の市民たち、そして前述した修道僧、托鉢僧、免罪符売り等々、いずれもふるくさい道徳性や宗教性をこえて、むせ返るような人間臭を発散する――。
ルネサンスが「人間の発見」であるならば、『カンタベリー物語』もこれに無関係ではないはずである。
そうであれば、我々が卑猥(ひわい)と感ずるたぐいの物語も、思えば地上の歓楽を、禁欲的な中世から奪いかえしたルネサンス人の高笑いかもしれない。
むろん、『カンタベリー物語』をイギリス・ルネサンス文学そのもののなかにいれるわけにはゆくまい。
またチョーサーは聖職関係者をこっぴどく諷刺はしているが、けっして宗教改革を望んだわけではなく、敬虔なカトリック精神や騎士道を尊重しており、前者の代表は巡礼たちのなかの司祭に、後者は騎士にあらわれている。
そしてチョーサーは女性と結婚については、けっきょくは貞節と愛をおもんじているが、もしチョーサーに哲学があるとすれば、いわばこうした中世的なものであろう。
しかしそうした世界観にもかかわらず、「ルネサンス」という言葉が、フランス語で「よみがえり」を意味するとすれば、そしてこの「よみがえり」が、中世文化のなかで神中心のために忘れられ、ゆがめられた人間観を再生させ、新しい文化や精神を創造するということであれば、チョーサーはこのルネサンスのひとりの先駆者といえるのではあるまいか。
イギリスのルネサンスそのものはチョーサーから一世紀以上ものち、十六世紀に、とくにその世紀後半のエリザベス女王の時代におとずれる。
そして文学のうえだけに限るならば、チョーサーに見いだされる「人間の発見」が、その真の意味で高められ、深められるのは、あのシェークスピア(一五六四〜一六一六)においてであろう。
彼は新しい人間の価値をたたえた。
「なんという傑作であろう、人間とは。理性はじつに気高く、能力はじつに限りがない。」
そして『ハムレット』『ベニスの商人』『ロミオとジュリエット』『オセロ』『マクベス』『リヤ王』『真夏の夜の夢』『ウィンザーの陽気な女房たち』『じゃじゃ馬ならし』……といったおなじみの悲劇と喜劇、それに歴代のイギリス王をあつかった歴史劇は、あらゆる階級の人間をいきいきと、人間らしくあらわしている。
思わずドキンとするような芝居の筋の強いもり上げかたは、現代の劇作家さえ手本とするところだ。
「楽しい(メリー)イングランド」という言葉がある。その光がさしかけたところをチョーサーが歩み、その光を一身にあびてシェークスピアが登場する。
シェークスピアについては作品の邦訳や評論の類も多い。
ここではあまり知られていないチョーサーの紹介にとどめておいた。
top
**************************************** |