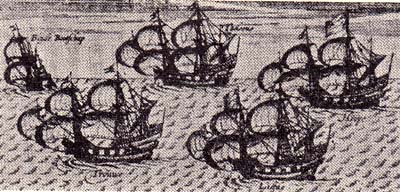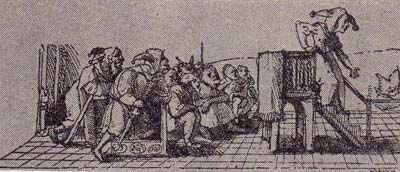|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9 10
11 12
13 14
世界の歴史7 ルネサンスの時代
8 ヒューマニストの運命――イギリス宗教改革とともに――
1 日本にいたエラスムス
top
栃木県の西南、佐野市上羽田(旧足利郡吾妻村)にある竜江院(りゅうこういん、禅宗)の山門をくぐると、左手に小さな観音堂がある。
この観音堂に江戸時代の初期から大正時代の末期まで、観音さまとともに「貨狄(かてき)さま」と呼ばれる木像が安置されていたが、それは高さ一メートルばかり、大黒帽に似た頭巾をつけ、右手に開いた巻き物を持った立像である。
この「かてき」については、カテキスム(カトリッ教の教理を問答体で書いたもの)、またカテキスタ(信者と教理問答を行う役僧)から出たとか、あるいは中国で大むかしにはじめて舟を作ったと伝えられる人のことだとか、いろいろと解釈されている。
この木像の存在が日本でも注目を集めはじめたころ、その写真が、大正十三年のクリスマスからバティカン市で開かれた世界宗教博覧会に、「在日本キリスト教聖人像」として出品され、西洋の学者も関心を抱くにいたった。
そして東西の学者たちの研究の結果、大正十五年に、これはオランダがうんだ大学者エラスムスの木像であることがわかった。
そういえば、木像の顔つきは、オランダの画家ハンス・ホルバインなどが描いたエラスムスの肖像によく似ており、また木像が持っている巻き物に、かすかに残るローマ宇は「エラスムス・ロッテルダム」と判読され、一五九八年という銘(めい)も見られる。 |

竜江院のエラスムス像
|
そしてそれはリーフデ号というオランダ船の船尾像として、日本に迷いこんだものである。
リーフデとは英語のチャリティー、すなわち慈愛という意味である。
オランダはその商品の販路拡大のために東洋探検を試み、一五九八年六月末、このリーフデ号をふくめて五隻の船団が西に向かって出発した。
しかし遠征隊は大西洋や太平洋でさんざんな目にあい、リーフデ号だけがやっとのことで日本に漂着した。
この船が豊後の海岸、いまの大分県臼杵(うすき)市佐志生(さしゆう)に流れ着いたのは一六〇〇年四月、日本暦によれば慶長五年三月のことで、ちょうど関が原の戦い(九月)があった年である。 |
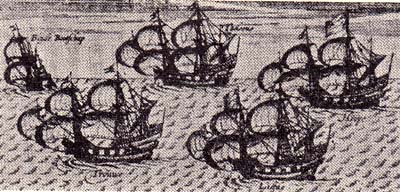
リーフデ号とその船団
オランダ船リーフデ号は大分県臼杵市に漂着した。その知らせを
聞いた家康は浦賀へ回航させ、その船長を徳川家の家臣とした。
|
リーフデ号の乗組員百十名の多くは飢えと病気で倒れ、日本に着いたときに生き残っていた者は約二十五名、しかも歩行にたえうる者は僅かに六、七人にすぎなかったという。
彼らは臼杵城主太田飛騨守一吉によって保護されたが、病気の船長の代理として、航海長でイギリス人のウィリアム・アダムズらが、大坂におもむいて徳川家康に引見され、いろいろと取り調べを受けた。
一方リーフデ号は家康の命令によって、まず堺へ、さらに浦賀へ回航された。
この船には商品や大砲のほかに、小銃、火薬などが積んであり、徳川氏がこれらを利用したことは想像できるところであろう。
なおこのウィリアム・アダムズはその後、家康の寵(ちょう)をえ、江戸日本橋に屋敷を与えられ、三浦按針(あんしん)と称し、外交顧問として対外交渉につくしたことは有名であろう。
三浦は領地の相模三浦郡にちなみ、按針は航海士の意味である。
また彼は本国に妻子があったが、日本人とも結婚し、一男一女をもうけ一六二〇年に世を去った。
さてこのリーフデ号の船尾像が、どうして無関係な栃木県の寺の所有になったのであろうか?
これについては異説もあり、詳細は不明であるが、通説によればつぎのとおりである。
リーフデ号が堺に回航されるまえ、臼杵で船体の修理をしたとき、取りのぞかれたエラスムス像は記念として城主太田一吉に贈られた。
ところが関が原の戦いで、石田三成に味方した一吉は、隣接の徳川方の城主中川氏に攻められ、像を城に残したまま敗走した。
そこで新たに稲葉氏が臼杵城主となつたが、その後一六三七年島原の乱が起こったとき、稲葉氏はこの情報を当時、府内(大分市)にいた幕府目付の牧野伝蔵成純を通じて、幕府に伝達した。
このため稲葉氏は幕府から賞されたが、牧野成純が江戸に帰るにあたって、稲葉氏は彼にエラスムス像を贈って感謝の気持ちを示した。
この牧野家の菩提(ぼだい)寺が竜江院で、成純がここに像を納めたというわけである――。
なおこの像は昭和五年国宝に指定され、同時に東京国立博物館に寄託されて現在に至っているが、昭和二十五年重要文化財に指定替えとなった(以上は主として『臼杵史談』第五十八号三浦按針特集号によった)。
こうしてわが国と奇妙な因縁を持ったエラスムスは、これから彼とともに登場するであろうトマス・モアなどと同じく、ルネサンス時代における西欧ヒューマニストを代表する古典学者、人文主義者でもあった。
2 モア家の客人 top
一四六〇年代の中ごろ、オランダのロッテルダムに私生子として生まれたエラスムスは、僧侶になるため、パリ大学神学部で勉強していた。
しかしゆきづまった神学の空虚な権威主義に不満をおぼえて大学を去り、ギリシア古典の研究を進めていた。
そのうち、弟子の一人であるイギリス貴族マウントジョイにさそわれて、一四九九年夏のはじめ、三十歳を少しこしたころ、海峡をこえることとなった。
十五世紀末、イギリスでは三十年にわたる「ばら戦争」(一四五五〜八五)もおさまり、テューダー王朝を始めたヘンリー七世(在位一四八五〜一五〇九)のもとに、王権が強化し、国内秩序の安定、産業の発達、対外的発展が進んでいた。
そのころからイタリア・ルネサンスの影響のもとに、オックスフォード大学を中心として「新しい学問」が始まった。
イギリスへ着いたエラスムスはオックスフォードで、有名なジョン・コレットに接して感化をうけ、またコレットが学生として受講したウィリアム・グローシン、トマス・リナカーなどの学者たちとも交わったようである。
すでにこの大学で「新しい学問」に浴していたトマス・モア(一四七八〜一五三五)は、十歳ほど年下ながら、エラスムスの親友となった。
当時エラスムスはある友人へあてた手紙に、「イギリスで咲き誇っている古代学芸研究の成果が、いかにみのり多く、広範囲のものであるかは驚くべきものだ」と書いた。
学問のことだけではない。エラスムスはまたほかの手紙で、スポーツのおもしろさや、イギリスの乙女たちのすばらしい美しさや、どこへ行っても、だれからも接吻で迎えられたり別れたりする、すてきな風習などにふれている。
一方イギリスのヒューマニストたちも、エラスムスの才気と古典学者としての学識に感嘆するとともに、これに刺激された。
こうしてコレット、グローシンたちはギリシア語による聖書原典の研究、ギリシアの古典哲学とキリスト教精神との総合の試みなど、ヒューマニストとしての学問的研究を活発にすることができた。
そのころオックスフォードを中退して、ほかの学校で法律を勉強していたトマス・モアも、このありさまに動かされて法学よりも古典学に熱中したため、心配した父の判事ジョン・モアは学資を絶つことによって、息子をもとへもどそうとしたといわれる。
しかしエラスムスは、自分にふさわしい地位をイギリスで発見できなかったためか、一五〇〇年はじめ、この国を去って行った。
それから彼はパリそのほかで、貧苦に耐えつつ勉学や著述生活をつづけ、五年後の一五〇五年から翌年まで、ふたたびマウントジョイに招かれて渡英した。
そして彼は旧友たちと再会の喜びにひたったが、このときにはロンドンのモア家の客人となっている。
モアは一時、下院議員になるなど、実生活にはいっており、また結婚したばかりのところであった。
エラスムスは名こそあげていないが、明らかにモア夫妻とわかる新婚夫婦について書いている――
家柄はよいが田舎出で無教養な妻、十歳年下で十七歳のこの若い妻に対して、夫は読書や音楽の教養を身につけさせようと試みるが、妻はこれについてゆけず、泣くばかり、死んだほうがましだと思うほどのありさま、しかし夫はこれをきたえあげていったと。
このトマス・モアが下院議員に選出されたのは、一五〇四年、ヘンリー七世時代末期の議会であったが、この王は一五〇九年に世を去り、十八歳のヘンリー八世(在位一五〇九〜四七)が即位した。
若さにあふれる王は均整がとれた姿態に恵まれ、ラテン・フランス・イタリア語に通じ、音楽の才もあり、スポーツにも秀でていた。
文学、科学にも興味をもち、ルネサンス的教養を身につけたこの若々しい王に、ヒューマニストたちが大きな期待をよせたことは当然であろう。王は彼らに、「学識がない人生は生きるに値しない」とまで語ったではないか。
マウントジョイがエラスムスにあてた手紙には、つぎのような文字さえ見うけられる。
「……おお、エラスムスどの、世に満つるこの喜びを、わが国民が新しい王をどんなに誇っているかを、あなたが見ることができれば、あなたは満足して落涙するでしょう。
天はほほえみ、地は歓喜し、すべては希望と豊かさにあふれています……」 |
ヘンリー八世自身もエラスムスに、イギリスをあなたの家郷としていただきたい、というような手紙を送ったこともあった。
ともかく一五〇九年秋から数年、エラスムスはおもにイギリスに滞在することとなった。彼はロンドンで一時モア家に身をよせたが、モアは前途有望な法律家として認められ、前述の若く美しい妻ジェーンと子供たちにかこまれて、幸福な家庭をつくっていた。
弁護士となったモアは、弁護を依頼されたときには、正しいと確信がある事件だけを引き受け、不当な事件の場合には訴訟をやめるように忠告し、それが容れられないと、他の弁護士に譲った。こうして彼はひじょうに人気をえたという。
さてこのモア家に着いたエラスムスは、まだ本が届いておらず、また腰の神経痛にかかっていて、まとまった仕事ができず、そこで一週間か十日間で一冊の本を書き上げた。 |

ヘンリー八世――即位時には
周囲に期待されたイギリス王であった
|
だいたい神経質なエラスムスは暑さに苦しみ、霧にあえば気がめいり、ちょっとした寒さにもこごえ、風が吹けば不快になった。しかし必要とした睡眠時間は三、四時間ともいわれ、残りは読書、議論、執筆にうちこみ、休むことなく知的活動をつづけた。
彼は旅の途中の馬車のなかでも書き、どこの宿屋の部屋でも、テーブルはただちに彼の仕事机となった。
モア家で書かれた本は、エラスムスの数多い著作のなかでも有名な『痴愚神礼讃(ちぐしんらいさん)』であり、それは「ロッテルダムのエラスムスより、その新しき友トマス・モアに」捧げられている。
この本は痴愚女神を通じてユーモアと皮肉のうちに、人間全体の欠点を指摘し、痴愚の種々相を展開する。
とくに当時のカトリック教会の形式化、僧侶たちの腐敗や堕落がするどく風刺されているとともに、人間の愚かさを正したいというヒューマニストの願いがこめられていた。 |
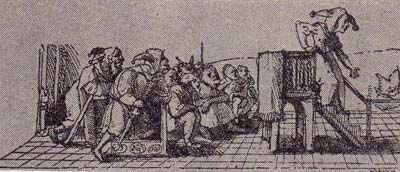
モア家で書かれたエラスムスの著作『痴愚神礼讃』の挿し絵
|
愚鈍や邪悪に対してたたかう場合、もっとも効果的な方法は諷刺であり、エラスムスはこれを巧妙に利用した。
そして彼自身が驚いたほど効果は大きく、非難や攻撃もまきおこった。
おもしろいことに、ローマ教皇もこの本を愛読し、大笑いしたという。
3 君主教育・女子教育 top
一五一一年、パリで出版された『痴愚神礼讃』は、千八百部と伝えられる第一刷がただちに売りきれ、十六世紀だけでも五十八度も版を重ねたといわれる。
この点エラスムスは印刷という新しい技術とともに成長した世代の人であり、この印刷という方法で、彼のまえのだれもが及ぼしえなかったほどの影響を、ヨーロッパ知識人に与えた。
印刷術といえば、十五世紀中ごろドイツ人ヨハン・グーテンペルク(?〜一四六八)によって、取りはずしができる鉛の活字で、能率的な印刷の方法がすでに発明されていた。
これによって、過去数百年間に筆写されたものよりも、はるかに多くの書物が印刷されることとなったし、またこれまでの木版印刷は不鮮明であるうえに、費用も高くついたのである。
そして書物の普及は、教育や学問を僧侶、貴族、金持ちの独占から大衆化するきっかけでもあった。
その後エラスムスはイギリスと大陸のあいだを往来し、一五二六年、『新約聖書』および『キリスト教君主教育』という重要な著書を世に出した。前者は聖書のギリシア語原典の校訂、註釈とともに、新しいラテン語訳をおこなったものである。
この仕事は学者としてのエラスムスの名声を高めたが、なにしろ聖書をとりあげたのだから、一方では批判もおこった。
そのなかに宗教改革運動を始めるまえのルターがいて、若干の不満をもらしているのも注目されよう。
エラスムスはこの本を当時の教皇レオ十世に献呈しているが、これは非難に対処するためだったという。 |

オランダ人学者エラスムス
|
『キリスト教君主教育』のほうは、彼が名誉顧問となっていたスペイン王カルロス一世に捧げられたものである。
ヒューマニスティックなキリスト教的貴族をつくりあげること、それがエラスムスの願望であり、彼は貪欲で乱暴な支配者層をつくり変えることをめざした。
君主が正しい教育のもとに真のキリスト教徒になることにより、理性、友愛が動物的本能や暴力をおさえ、キリスト教世界全体に平和が訪れることを、エラスムスは熱望したのだ。
あのマキアベリの『君主論』が一五二二年に完成されたことを思うと、対照的な二つの君主論が同時代に存在していたわけである。
一方、エラスムスの名声は高まり、たとえば彼が滞在していたスイスのバーゼルは、ヨーロッパの精神的中心となり、貴族や学者たちはその記念帳にサインしてもらうために、何日もかけて遠くから旅をしてきた。
彼から手紙をもらっただけで、人気の的になるありさまであった。
エラスムスは一五二六年にもイギリスへ渡っているが、短い滞在にすぎなかった。
ヒューマニストたちがヘンリー八世にかけた期待は、どうやら過大にすぎたようだ。
王は即位当時にくらべて、しだいにエネルギーに満ちた男臭い人物となり、フランス大使は王に近づくと、暴力を振るわれそうな恐怖感を覚えることを伝え、また王に会った人びとは、狩りや宴会や外出が好きで、子供を愛し、スポーツに興ずる愉快な王の一面と、冷酷で寡黙、ぬけめがなく野心的な反面とを感じている。
しかも王は学芸よりも、対外的な勢威の拡大や戦争をこのんだ。
エラスムスはまた、「近代最初の平和論」といわれる小品『平和の訴え』(一五一七)を書いている。
この彼にとって、ヘンリー八世の変貌は大きな失望であった。
エラスムスが定住してくれたらと願っているイギリス・ヒューマニストたちの期待もむなしくなった。
このエラスムスに対して、その無二の友トマス・モアは実務上でちゃくちゃくと地位をきずいていたが、私生活のうえでは大きな変化があった。
一五一一年、結婚生活六年にして、モアの妻は子供たちを残して、世を去った。
しかし彼はまもなく、年上の女性アリス・ミドルトンと再婚した。
彼女はロンドンの織物商の未亡人で、先夫とのあいだにできた女の子をつれてきたが、モアは残された子供たちに母を与えるために、そして家事をとらせるために、この結婚を選んだらしい。
この妻は美しくはなかったが、家政のやりくりは巧妙で、モアは先妻をしこんだように、新しい妻にも音楽などを教え、彼女に毎日楽器をひかせた。
彼は子供たちの教育に熱心で、ギリシア・ラテン語をはじめ、種々の学問を男女平等に教えこんだ。
彼の古典研究に対する熱心さは、その子女の教育にもあらわれたのである。 |

トマス・モアの家族
|
当時はまだ婦人が学問をすることは軽視されていたので、この点モアが女の子を多くもち、彼女たちの教育に努力したことは、ルネサンス・ヒューマニズムの実験でもあり、またイギリスにおける女子教育の発展にプラスすることとなった。
長女マーガレットはとくに父に似て学識に秀でた女性に成長し、モアのお気にいりとなった。
聡明な彼女のもとにはいろいろと忠告を求める友人たちが集まり、適切な意見を与えられたが、こんなことができるのは、そのころの女性としてはたいへん珍しいことであった。
そして彼女の夫ウィリアム・ローパーは、のちに尊敬する義父の伝記を書いた。
ところでモア家には、、エラスムスが利用できるように一室が用意されていた。
しかし彼は親友の二度目の妻と、どうもしっくりゆかなかったらしい。
彼はあるとき、こっそりもらした。
「私はイギリスがいやになり、モア夫人は私がいやになっている。」
しかしモア夫人にとっても、まったくあつかいにくい客であった。
エラスムスは酒にうるさく、イギリスのビールはのまないし、魚のにおいを嫌うし、フランスふうの野菜サラダをお望みだし、そのうえラテン語でドンドンしゃべるので、モア夫人はこれについてゆけなかった。
4 『ユートピア』 top
エラスムスの重要な著書が出版された一五二六年は、イギリス・ヒューマニズムにおいても忘れることができない年である。
それはこの年の末、モアの名著『ユートピア』が発行されたからであり、一五一六年は期せずして、十七年前に始まった二人のヒューマニストの交友の最終的な実りであり、「エラスムス的改革者の勝利の年」と呼ばれるにふさわしいであろう。
『ユートピア』はイギリス社会に対する批判をふくむ第一部と、理想国ユートピア(どこにもない場所という意味)の地理、政治、軍事、宗教、経済、家族制度、風俗などについて書かれた第二部とからなっている。
この構想自体が新大陸、新航路の発見に由来するものと思われ、モア自身もロンドン市民の出身として、イギリスの海外発展、植民活動について少ながらぬ関心を抱いていた。
そして物語はモアが、アメリゴ・ベスプッチの航海に参加したラファエル・ヒスロデイという船乗りから聞いたものとして展開している。
ヒスロデイとは、おしゃべりが得意な人というような意味である。
またいろいろな知識のみなもとは、ふるくはギリシア・ローマの古典、同時代ではこのベスプッチの本などに求められているが、モアはある船乗りから、日本についての知識もえていたといわれる。
『ユートピア』は第二部が先に、一五一五年、モアの国外出張(ネーデルラント)のときに書かれ、つづいて第一部が一五二六年ロンドンで、「睡眠と食事とから盗みとった時間だけ」で書きあげられた。
ともにラテン語である。
第一部はものの見かた、考えかたがよく似ているので、エラスムスの作ではないかと疑われたという。
またラテン語で書くということはイギリスだけでなく、ヨーロッパの知識人として発言することを意味しており、この点、ヒューマニストのインターナショナルな性格がうかがわれよう。
この第一部では国家悪、社会悪というべきものが指摘されており、その実例としてモアが生活しているイギリスが取り上げられている。
ヘンリー八世時代は、王の即位当時にヒューマニストたちが期待をよせた「天がほほえみ、地が喜ぶ」ような時代ではなかった。
たとえば毛織物工業の発達はイギリスの海外貿易を盛んにしたが、一方、農地が「囲い込み」によって牧羊場とされたため、多くの農民が耕地を追われて浮浪人、泥棒などにならざるをえず、しかもわずかな盗みに対しても重刑が科せられるありさまであった。
この事情について、モアは登場人物の口を借りて、「羊が人間を食い殺す」という有名な表現を使った。
「……以前はたいへんおとなしい、小食の動物だったそうですが、このごろでは、なんでも途方もない大食いで、そのうえ荒々しくなったそうで、そのため人間さえもさかんに食い殺しているとのことです。
……そのわけは、、もし国家のどこかでひじょうに良質の、したがって高価な羊毛がとれるというところがありますと
……その土地の貴族や紳士や、そのうえ自他ともに許した聖職者である修道院長までが
……百姓たちの耕作地をとりあげてしまい、牧場としてすっかり囲ってしまうからです。」
「そういうとき、彼らに残された道としては泥棒を働き、そしてその結果正しい法の裁きを、そうです、正しい法の裁きをうけて絞首台の露と消えるか、それとも乞食をして歩くか、そのいずれしかありません。
しかも乞食をすればするで……浮浪人として牢獄にぶちこまれます。
彼らだってどのくらい仕事につきたがっているかわかりません。
ただだれも仕事を与えてくれないだけの話なのです……」(平井正穂氏訳による) |
モアはこうした状態に対して痛烈な批判を加えるとともに、フランスの国王とその重臣たちを例にあげて――この点でイギリスに言及することは、さすがに遠慮したとみえる――政治上の奸策(かんさく)や野望をあばき、さらに政治や社会の欠陥の根本的な原因を私有財産制に求め、金銭が絶大な力を持つところでは、国家の正しい繁栄はないとまでいいきっている。
エラスムスはモアの『ユートピア』出版の目的は、諸国家の邪悪な状態の原因を追求するところにあるとしているが、注意すべき発言であろう。
『ユートピア』第二部では財産共有の理想国が描かれており、これによってモアは近代社会主義、共産主義の先駆者ともみなされている。
しかし彼の財産共有論は経済論よりも道徳的な目的をもつもので、それによって人間の悪の根源に対する反省をうながしたものと解すべきであろう。
そういえばユートピア島そのものも、現実にこれを作るというわけではなく、搾取のない生産や分配、快適な労働、教育の男女平等、幸福な市民生活、平和主義、信仰上の寛容などの共同体を論ずることによって、当時のイギリス人に、またひろくヨーロッパ人に――といっても、むろん支配階級であるが――道徳的反省を求めたものであろう。
そしてそこには理性的な教化をもつて、人間を幸福に導こうというヒューマニストの理想があったのだ。
5 忍びよる嵐 top
こうして一五二六年はいわばヒューマニストの蜜月(みつげつ)であったが、あのルターの宗教改革運動がおこったのは翌一五一七年のことである。
ルターはその改革運動が進むにつれて考えた――これまでのエラスムスの聖書や教会に対する態度から判断して、いまや全ヨーロッパで高名なこの大古典学者を自分の陣営に加えれば、改革運動を有利にすることができると。
そこでルターは直接、エラスムスに手紙を出して、その支援を求める。その結果はどうであろうか。
なるほどエラスムスは、当時の教会や僧侶の堕落したありさまには批判的であった。
しかしエラスムスはカトリック教会から分かれたり、教皇権を否定しようなどとは少しも考えていなかった。
そしてこれは彼のみならず、ヒューマニストたちの多くに共通した態度である。
したがってエラスムスはルターに、その信仰上の熱意には敬意を表するが、実践の方法には賛成できないと答えた。
さらに彼の返書のなかには、あなたがきちがいじみた罵言(ばげん)をつつしみ、自分の立場だけを主張していたならば、あなたに憤慨する人たちはもっと少なかったでしょう。
あなたの抑制がきかない性格のため、いささか取り返しがつかない混乱におちいることを心配する、などという文字が見うけられる。
それでもエラスムスはドイツ諸侯にあてて、ルターの言動には賛同できないが、温情をもってこれを遇してほしいといっているし、またローマ教皇に対しても慎重な処置を要望した。
さらに彼は諸君主にも宗教上の寛容政策を進言したり、平和的解決のために新旧両教徒との談合にあたったりした。
しかしこうしたエラスムスの努力にもかかわらず、ルターは破門され、その説は異端とされるなど、事態は進展するとともに、ルター派の勢力も増大して、宗教改革運動も急速に発展していった。
この運動に関連して、一五二四年にはドイツ大農民戦争が展開する。
この年、エラスムスははっきりとルターの説に反対の見解を示し、それからこれに対するルターの反論、またエラスムスの反論と、両者の決裂は動かしがたいものとなった。
一方カトリックの側でも、この大古典学者を味方につけようとして、ローマ教皇はいろいろと働きかけた。
しかしエラスムスはこれに応じないで、新旧両教徒の争いのなかにはいろうとはしなかった。
彼は「世界の市民」として一党派に与(くみ)することを拒否したが、こうした態度はかえって相手を刺激し、彼は新旧両派から攻撃されることとなった。
カトリック側では、「エラスムスが卵をうみ、ルターがこれをかえした」と非難し、パリ大学神学部などはエラスムスの思想を異端視するようになった。
一方ドマス・モアは実務家として、ますます才能を発揮していた。
これにほれこんだヘンリー八世は、彼に宮仕えさせたいと切望する。
ただでさえヒューマニストたちをもって、自分のまわりをかざりたい王である。
モアははじめは王の誘いに応じなかったが、生活上のこともあって、一五一八年ついに受け入れた。
これについてエラスムスは、王がモアを宮廷にひっぱりこんだと表現し、親友の前途について、なにか不安の念を抱かざるをえなかった。
それはともかく、モアの活躍は司法、外交、財務、行政など、多方面にわたり、また下院議長の地位にもついた。エラスムスとちがって、どこでも楽しみを見つけられるモアにとり、才能ある人びとが集まった宮廷の生活は、それなりにこころよいものであった。
なお外国からの賓客(ひんきゃく)をむかえるときのラテン語のあいさつに、彼の才能はとくに重宝がられた。
そしてモアは一五二九年十月、大法官(大法官庁裁判所の長)となり、司法官として最高の地位についた。辞退する彼に向けての王の言葉は、「モアこそ最適の人物と認める」という返答であった。 |

イギリス国内での地位が上っていくトマス・モア
|
そのころ大法官庁には多くの未決の事件があった。
しかしモアの在任中にこれらはすべて解決され、二年半あまりで辞任したときには、未決の事件は一つもなかったといわれ、つぎのように語り伝えられている。
「ここ二年のあいだ、モアが大法官だったころ、未決でのこった訴訟はなかった。
同じことは二度とあるまい、モアがもう一度つとめるまでは。」 |
ところでモアは異端に対しては、きびしく取りしまっている。
彼はエラスムスと同様に、カトリック教会や僧侶の現状には批判的で、おだやかな改革を望んだが、ローマ教皇から分離したり、カトリック教会のなかに分裂をつくることには反対であった。
この点、宗教改革の進行につれて、かつてモアが『ユートピア』に示した信仰上の寛容、自由な態度も変わってきたようである。
彼は改革運動を一種の有害な流行病のようにみなした。
前述のように二年あまり勤めた後、モアは一五三二年五月、「彼以上に適任者はかつていなかった」とまでいわれる大法官の地位を退いた。
彼自身はエラスムスへの手紙のなかで、この理由は病気のためといっているが、真の理由はもっと深いところにあった。それはイギリス宗教改革に関連していた。
6 六人も王妃をかえた国王 top
話はさかのぼる。
一五〇九年、即位後まもなく、十八歳のヘンリー八世は兄アーサーの未亡人、スペイン王女で二十四歳のキャサリンと結婚した。
一五〇一年兄嫁の晴れ着のすそを捧(ささ)げたのは、十歳のヘンリーであったが、この結婚後五ヵ月とたたないうちに、アーサーは病死したのである。
そして兄嫁と弟の結婚は、イギリスがスペインとの友好を求めた政略結婚であるが、広い教養、優雅な性格を持ったこの姉さん女房に、若い王はすっかり満足しきっていた。
しかしキャサリンが二十年近くヘンリーの側近にあるあいだに、この政略結婚の意味は失われていった。
しかもキャサリンは女子メアリーを一五二六年に生んだだけで、すでに四十二歳となった。
ヘンリーが待望する男子を生む見込みはないであろうし、また王はこれを、兄弟の妻をめとったことに対する天罰と思った。
そこで国王の気持ちはしだいに王妃の侍女で、フランス帰り、二十歳ばかりのアン・ブリンにひかれていった。
この若々しい肉体こそ、男子をヘンリーに与えてくれるであろう。
アン・ブリンはそれほど美しくはなかったが、ほっそりしたからだつきで、しんが強く、王妃になることを要求した。
近親結婚であるため、むりやりに教皇から許可をえて王妃としたキャサリンではあったが、一五二七年のいまでは、王は彼女をむりやりに離婚しなければならなくなった。
そこでカトリック教徒としてヘンリー八世は、ローマ教皇にキャサリンとの結婚無効宣言を求めた。
かつて一五二一年、ルターに反対する書を著わして、教皇から「カトリック信仰の守護者」の名を与えられたヘンリーは、この業績に対しても、自分の願いはかなえられるものと信じていた。
しかし一五二七年五月、神聖ローマ皇帝カール五世の軍はローマを占領し、ときの教皇クレメンス七世はその支配下にあった。
また教皇は宗教改革が進行するなかで、カトリック勢力の最大の支柱であるこのカール、キャサリンの甥(おい)にあたるこの皇帝との関係を悪化させるような離婚を認めるわけにはいかない。
そうかといって「カトリック信仰の守護者」を袖にしたくはない。 |

アン・ブリン
|
意志薄弱なことでは定評がある教皇はどうしたらよいか、当惑してしまった。
ヘンリーが二人の妻を持ってくれたらとか、自分に責任なく新しい結婚が成立するのであれば、どんなにうれしかろうなどというような教皇は、イギリスへ使者を送って、ヘンリーに離婚を思いとどまらせようとするとともに、一方ではキャサリンに尼僧院にはいることをすすめた。
なるほど、これで自然に離婚となるわけだ。
しかし王は承知しなかったし、キャサリンは「四肢を裂かれても」そんなことはしないと強硬で、教皇の窮余の一策もむなしかった。
そして王も王妃も、教皇庁の正式の決定を望んだ。
ますますカール五世に屈した教皇クレメンス七世は、ついに一五二九年七月、ヘンリーをローマの法廷によぶための使者をイギリスに送る。
教皇のこの処置は、ヘンリーに離婚を強行させるきっかけを与えた。
外国の法廷によびだされて裁判されることを、王はがまんできない。
王の側近にいて重用されていたトマス・クロムウェル(一四八五ごろ〜一五四〇)も入れ知恵した。
「めんどうだからローマ教皇と手をおきりなさい。」
一九二九年、王はのちに「宗教改革議会」とよばれる議会を召集し、ローマ・カトリック教会から分離するための立法を進めた。
そしてヘンリーはすでに身ごもっているアンと、三三年はじめひそかに結婚する。
生まれてくる子供は、合法的なあとつぎでなければならない。
王の意を体したカンタベリー大司教クランマー(一四八九〜一五三六)は、キャサリンとの結婚無効、アンとの結婚の有効を宣言した。
六月、アンは王妃として戴冠する。
しかし九月に誕生したのは皮肉なことに男子ではなく、王女であった(のちのエリザベス一世)。
一方、教皇がイギリス国王の要求に従わないことは、いよいよ明確になってきた。
のみならず、教皇は一五三三年クランマー、ヘンリー八世をあいついで破門した。
こうしてローマとの断絶が決定的となる。
一五三四年「国王至上法」が議会を通過し、王みずから「イギリス教会の地上における唯一最高の首長」となった。
これがイギリスの宗教改革であるが、それはルターやカルバンの改革のような新しい信仰内容をもたらしたものではなく、これまでイギリスの教会を支配していた権力、つまり教皇権を、ほかの権力、すなわち王権にかえたという点に特色がある。
またそれはこうした政治性とともに、経済的意味をももっていたが、それは一五三六年から四〇年にかけて、ヘンリーが多くの修道院を解散させ、その財産を収奪して国庫財政を豊かにした点にあらわれている。
ヘンリー八世はたいへん派手好みで、浪費では人後に落ちなかったし、そのうえ好戦的で戦費もかさみ、したがって王室財政は悪化していた。
そこで王は修道院がその堕落や特権のため、当時イギリス国民に評判が悪くなっていたところを利用したのだ。
「陛下を、キリスト教国の王さまのなかでいちばんのお金持ちにしてさしあげましょう。
修道院の財産を没収するのですな」
と王を喜ばせたトマス・クロムウェルは、全国の修道院を調査して、財産没収の口実をさがしだすとともに、多くのスパイを全国にばらまき、私語さえも記録させ、ひそかな反対や非難でもさがしだして、これを弾圧した。
彼のもとにイギリスでは一種の恐怖政治が行なわれ、エラスムスはそのありさまを評していった。
「イギリスでは、人びとはサソリがあらゆる石の下にひそんでいるような感じをもった。」
トマス・クロムウェルは小柄でがっちりした男であった。
顔つきはみにくく、目は半分閉じていて、なにを考えているのか、わからなかった。
ヘンリー八世は彼を軽蔑しながらも、有能なので利用した。
しかしのちにクロムウェルは王の怒りにふれて、死刑にされてしまった。
ところでイギリスの国民は成りあがり者で高慢なアンをきらい、貞淑なキャサリンに同情していたので、王の離婚そのものには賛成ではなかった。
しかしローマの離婚反対は国民感情を刺激し、すでに国民のなかに生じていた反教皇、反教会の気持ちを強めるにいたった。
そして金にこまっているヘンリーは、没収した修道院財産を、都市や農村の新興ブルジョワなどに売りとばした。
そこで彼らはこの宗教改革や王権の支持者となった。
こうしてイギリス宗教改革は、一種のナショナリズムを背景としていたといえよう。
ヘンリー八世の勝利のかげで、静かに「祈りと針仕事」に余生を送っていたキャサリンは、一五三六年一月、五十一歳で病死した。
彼女の地位を奪ったアン・ブリンは、この年五月彼女よりもはるかに不幸な死をとげた。
専制君主とは、なんという気まぐれな存在であろうか。男子を生まなかったアンに対する王の愛情は急速に失われ、彼女は姦通などの罪状で逮捕、処刑されてしまったのだ。
結婚のとき一役買ったクランマー大司教は、こんどは無効だと宣言した――
「それは魔力によって誘惑されたものであるから。」
ヘンリー八世の女性遍歴はその後もつづき、アンの刑死後一週間もたたないうちにジェーン・シーモアと結婚、彼女は平凡な女性だったが、待望の男子エドワードを生んだ。
一五三七年シーモアは病死し、その後一五四〇年ドイツのクレーフェ公ヨハンの娘アンが王妃となったが、数ヵ月で離婚された。
離婚後二ヵ月目に迎えられたという五番目の王妃キャサリン・ハワードも、四二年姦通罪で処刑され、その翌年結婚した六番目のキャサリン・パーにいたって、ようやく王妃の座も安定した。
一五四七年一月の王の死まで、美しく、教養があり、温和な六番目のキャサリンは、この専制王にかなりの影響をさえ与えたのである……。
それはともかく、このイギリス宗教改革がトマス・モアの運命を決したのだ。
7 ある終末 top
トマス・モアが大法官となった前後から、ヘンリー八世は彼に対して、「わが重大事」について考慮してくれるように、「まず神を仰ぎみて、つぎに余を仰げ」といいながらも、「されどわが大事については再考せよ」と、たびたび要求していた。
しかしモアは王のキャサリンとの離婚を認めず、認めた場合には、世俗的な名誉や利益をもって報いようという王の申し入れに対しても、まったく応じなかった。
王にしてみれば、国論を統一してローマに対決しなければならぬとき、大法官という重要な地位につくような人物の支持こそ、まずもって必要だったのであろう。
こうした大問題の進行中、こうした要職についたことは、モア生涯の大失敗であったという見解もみられる。
しかし宮仕えの身とすれば、選択の余地はなかったのであろうし、また当時はヘンリーはなお個人の意見の自由を許しており、事実、大法官在職中、彼の意向を知っている王は、モアを離婚問題の件に関係させることをしなかった。
それにしても、「宗教改革議会」がローマからの分離を用意していくにつれて、彼は職にとどまっておれば、自分の良心に反して行動しなければならないか、改革に反対すれば、王の不興をこうむるか、いずれかになることを知り、ついに辞職にふみきったものと思われる。
モアはヘンリー八世の宗教政策をどうしても認めることはできなかった。
なぜなら彼は現在のカトリック教会に欠陥を認めつつも、カトリック世界の統一を乱すことに、専制王を中心とする国家主義が宗教の分野に介入することに、反対だったからである。
モアは退官後、学問と著述とに没頭して静穏な日々を送っていたが、イギリス宗教改革の進展は、こうした生活がつづくことを許さなかった。
すなわち一五三四年四月、モアは「王位継承法」に宣誓することを要求される。
これはこの年、「国王至上法」に先だって制定されたもので、王位継承をヘンリー八世と新しい王妃アン・ブリンの子孫に認めるものであり、また継承法を守ることを全国民が宣誓するように定めてあった。
そしてモアのような人物の不同意は、だれの反対よりも王には痛手であろう。
しかもモアは教皇の権威否定を意味することどなる宣誓を、最後まで拒否したのである。
絶対君主は自分の意に従わない者を許してはおかなかった。
それでもなんとか妥協点を見出そうという努力もはらわれたが、寵臣トマス・クロムウェル、それから王妃アンは強硬であった。
こうしてモアを待ちうけていたのは、まずロンドン塔への投獄である。
そこへ面会にくることを許された妻のアリスは、夫にうったえた。
「これまでほんとうに賢いおかたでしたのに、なぜネズミたちといっしょにこんなところにいらっしゃるのです。
早く自由の身になって、王さまのお気にいるようにしてくださいませ。」
元来、モアが大法官をやめたことに反対だったアリスは――なぜなら、「大法官の奥方」は誇り高い地位であったから――彼の考えかたを理解できなかったのだ。
およそ一年ほど、モアはこのロンドン塔で著述の筆をとってすごしたのち、しばらくのあいだきびしい尋問をうけた。
一五三五年七月モアは起訴され、有罪となったが、適用されたのはやはり前年に成立していた「反逆罪法」などである。
彼の気持ちはつぎのようであった。
「すべてのキリスト者は教会の共同性を守るように義務づけられているが、あなたがたの法はこの統一を破壊しようとしている。
私はカトリック教に対する信仰のために、不倫な結婚に同意をこばむものである……』
まさにモアにとって、「王の臣下ではあるが、神こそがなにものにもまさる存在」であったのだ。
刑の宣告は「五体引き裂き」による死刑であった。
しかし王の特赦によって斬首刑とされた。
モアは一五三五年七月六日、ロンドン郊外のタワー・ヒルで処刑された。
五十七歳。長い幽閉のため、すっかり痩せ衰えたモアが刑場に行く途中、ひとりの婦人が進みよって葡萄酒をすすめたが、彼はこれを辞退した。
この女性はモアの身内の者ではなかったかとも、推測されている。 |

モアと娘
|
この大ヒューマニストの死は、「法の名のもとで行なわれたイギリスでもっとも暗い犯罪」であった。
なお一九三五年、四世紀後モアは聖者と認められた。
もうひとりの大ヒューマニストがこの友の死をスイスのバーゼルで知ったとき、過労と失意と病気とによって疲れはてていた。
彼はある友人に書き送った。
「モアが死んで、私は自分が死んだような気がします。私たちの魂は一つだったのです。」
それからエラスムスの健康は急速に衰えてゆき、一年の後、一五三六年七月、モアのあとを追うように世を去った。
そしてそのすこしまえ、同年三月バーゼルで、シャン・カルバンの『キリスト教綱要』が発表され、宗教改革運動はまた新しく強力な人物を迎えたのである――。
top
**************************************** |