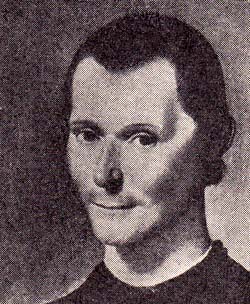|
****************************************
Index 1
2 3
4 5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
世界の歴史7――ルネサンスの時代
5 斜陽のイタリア半島――イタリア・ルネサンスの片影Ⅱ――
1 一修道僧の怒り
top
フィレンツェの繁栄は、思えばこのロレンツォの時代を絶頂としていた。
彼の治世の晩年、奢侈(しゃし)、悦楽(えつらく)のフィレンツェのただなかにおいて、激烈な言葉で神を説き、終末の日、裁きの日が近いことを警告するひとりの修道僧があらわれたのだ。
彼、ジロラモ・サボナローラは一四五二年、フェラーラの平凡な中流階級の家庭に生まれ、周囲は医学の道に進ませようとしたが、彼は孤独を愛して、世俗的生活をきらい、二十二歳のとき、ドメニコ派のある修道院にはいってしまった。
「私を教団に走らせたものは、この世のみじめさ、堕落、人びとの愚劣である」と、彼は父母への別れの手紙に書いたという。
それから修道僧として修行すること幾年か、サボナローラはやがてその破壊的で、予言的な説教をもって有名となった。
弱々しく小柄で、胸はくぼみ、鼻はわしのようで、大きく黒い眼がランランと輝くこの僧は、一四八二年フィレンツェのサン・マルコ修道院に移籍された。 |

フィレンツェで説教する修道僧、サボナローラ
|
彼はこの都市の享楽(きょうらく)的生活を非難し、その責任者としてロレンツォの独裁を攻撃するとともに、素朴な神への信仰にもどることを説いた。
たとえば、早朝から席をうばいあい、場に溢れた聴衆の前でおこなわれる彼の説教を、速記でもするように書きとめたある市民は、「感動と涙のあまり」たびたび筆を中断し、あるひとはこの説教を「最後の審判(しんばん)の日の雷鳴(らいめい)」のように感じ、また聞き終わった人びとは「ひとことも発せず、死人のように帰って行く」ありさまであった。
トルコ人など異教徒の侵入を恐れる不安感、退廃(たいはい)的なムード、そしてロトマ教皇をはじめとするカトリック教会の堕落――そこに、サボナローラの痛烈な叫びによって、人心がゆり動かされる理由があった。
そして僧侶階級の腐敗を非難し、ローマを「傲慢(ごうまん)な娼婦(しょうふ)」とよぶ彼の言動は来るべき宗教改革運動のひとつの先駆とさえも、考えられるかもしれない。
ロレンツォは、メディチ家の持病ともいうべき痛風に悩まされていた。
しかし一四九二年春、まだ四十三歳の彼を臨終の床に追いやったものは、おそらくはガンであったろうと推測されている。
サボナローラはメディチ家をおそう災難について、すでに予言していた。
当時正体不明のガンが死因であったとすれば、この難病にとりつかれたロレンツォは、まさに不幸にみまわれたといえよう。
パッツィ陰謀(いんぼう)事件後十四年、この一四九二年に世を去るまで、ロレンツォの政権は安定であったが、じつはメディチ家本来の銀行業は、彼の時代に衰えていたのである。
それは中近東方面におけるトルコの進出、貿易の不振、フィレンツェ全体をささえていた毛織物業の衰えなど、外的な理由も考えられる。
しかしひとつにはロレンツォが人文主義的教育をこそうけていたものの、「眠っていては金にならない」式のきびしい実務教育を身につけておらず、彼自身も実業に興味をもたなかったためであり、またこうしたロレンツォがさばききれないほど、メディチ家の金融網が複雑多岐になりすぎたためともいわれる。
94
またメディチ家銀行の若干の支店がつまずいたことも影響した。
元来支店はそれぞれ支配人に管理かゆだねられ、彼らは独自の決定をすることができた。
これは支配人に人材をうれば、臨機応変にことを処理できて有利であるが、全体的な統制がないだけに、彼らの選択をあやまると、思わぬ結果をまねくこととなった。
こうしてメディチ家の財がかたむいてくると、ロレンツォの幅が広い活動に要する経費はフィレンツェ市民たちの負担ともなり、このため市の財政がやりくりされたことは、市民たちのロレンツォに対する強い不満のたねであった。
ロレンツォはメディチ銀行の損失を補うために、公金に手をつけたともいわれる。
ロレッッオのもと、フィレンツェ市民たちは享楽的な生活に明け暮れたが、これは政治上の専制から人心をそらすための彼のねらいだったともいわれ、そうだとすれば、意識的にも人心のゆるみが助長されたこととなろう。
なおロレンツォ健在の一四八〇年代から、フィレンツェの誇る天才たち、たとえばレオナルド・ダ・ビンチ、ラファエロ(一四八三~一五二〇)、ミケランジェロなどが、他の諸都市や諸国に、出かけたり、招かれたりして、一種の「頭脳の流出」が行なわれている。
こうしたことも、フィレンツェ文化をしだいにさびしいものにしたことであろう。
そして経済上の不振は、ロレンツォの学芸保護を不自由にした。
しかもロレンツォをついだピエロ二世(一四七一~一五〇三)は、性格も精神も弱く、軽薄、衝動的で、「快楽と女性とを熱心に追いかける」だけの頼りない人物である。
おりしもフランス王シャルル八世(在位一四八三~九八)の軍が、フィレンツェめざして進軍してくる――。
2 イタリア戦争をめぐって top
当時ヨーロッパ第一の文明と富とを誇るイタリアに対して、ヨーロッパ諸国はそれぞれ野心を抱いている。
しかもフィレンツェとベネチアの両共和国、ナポリ王国、ミラノ公国、ローマ教皇領などのイタリア諸勢力はたがいに政治上、経済上にあくことのない争いを展開し、果てしない分裂がつづく。
ロレンツォが健在なころには、各国のメディチ銀行を通じて――その支配人は一種の大使でもあり、スパイでもあったから――彼は情報をつかみ、イギリス、フランス、ドイツなどのあいだに均衡(きんこう)をつくり出して、どこか一国がイタリアに進出するのを防ぐことにつとめた。
同時に彼はイタリア諸国に対しても、にらみをきかせていた。そのロレンツォもいまはいない。
ミラノ公国の支配者ルドビコ・スフォルツァは仲が悪いナポリ王を負かすために、フランス王シャルル八世の力をがりようとした。
騎士道物語のなかに育ったシャルルは、ルネサンス・イタリアにあこがれるとともに、ナポリ王国を併合し、そこからギリシアに出て、コンスタンティノープル(イスタンブール)の異教徒トルコ人を追いはらい、さらに聖地エルサレム奪回の夢をもっていた。
フランスのブルジョワにとっては、イタリアの富こそ最大の誘惑(ゆうわく)である。
狡知(こうち)にたけたルドブイコにしてみれば、この二十四歳の青年王を誘うことは容易な業であった。 |

ルネサンス時代のイタリア半島略図
多くの国に分れ、ヨーロッパ第一の文明と富を誇るイタリアには、
ヨーロッパ諸国は野心を抱いていた。
|
こうしてシャルル八世は一四九四年夏、軍をイタリアに進めた。
神聖ローマ(ドイツ)皇帝、ハプスブルク家のマクシミリアン一世(在位一四九三~一五一九)は、はじめはシャルルの外交工作もあってこれを見送ったが、利害上、うちすてておけなくなる。
96
そしてマクシミリアンはその王子の結婚によって、スペイン王家と緊密な関係をむすんでいる。
しかもナポリ王は、スペイン王家の分家である。
ここにフランスに対して、やがてドイツとスペインの両君主は同盟して対抗した。
この協力態勢はフランスとの関係において、十五世紀末から十六世紀前半、ヨーロッパの情勢上に重要な意味をもつ。
そしてシャルル八世のイタリア侵入は十六世紀中ごろまでつづく、いわゆる「イタリア戦争」の始まりともみられる。
シャルルの軍は北イタリアを通り、フィレンツェに迫ってきた。
フィレンツェの一時的な契約による傭兵群にくらべて、イタリアにはいったシャルル八世の軍は、人数、訓練、統制という点て、はるかに優れている。
当時の傭兵たちは敵味方ともできるだけ命を落とさないように、負傷をしないように、武器をそこなわないように、いわば八百長戦争をしていたのである。
なすところを知らないピエロは、フランス王のもとにおもむいたが、和をこうのみで、フィレンツェにとってたいせつないくつかの要塞(ようさい)を譲りわたしてしまった。
いまや市民たちはピエロに反抗して立ちあがる。
彼はかつてメディチ家を支持した下層民たちに、金をばらまいて援助を求めたが、むなしかった。
一四九四年十一月メディチ家は追放され、これにかわって、シャルル王がフィレンツェにはいる。
金をちりばめた天蓋(てんがい)、純白の帽子、金の浮き織りの胴衣、青いマント、見る目にもあざやかな征服者の姿であった。
そして王は、「フランス王、ばんざい!」の叫びのうちにアルノ川を渡り、花の聖母寺に達して、何千という燭台(しょくだい)に輝く祭壇の前にひざまずいた。
しかしフィレンツェ市当局者との交渉のすえ、シャルルは金銭とひきかえにフィレンツェを去っていった。
98
だれのおかげであろうか?
フィレンツェの安泰をはかって、シャルルを説きふせたのはだれであろうか?
彼らはそれを、かねてからフランス軍の侵入を予想していたサボナローラだと信ずる。
一四九四年末から、フィレンツェはこの僧の支配に服する。
説教壇上の彼は叫ぶ。
「神はなんじフィレンツェに、なんじを支配するひとりの王を与えようと欲したもう。
その王こそ、キリストである。」
市民たちは声をかぎりに唱和する。
「われらの王、キリストばんざい!」 |
サボナローラはフィレンツェの政治・財政上の改革にあたったのみならず、当時の腐敗した宗教界の粛正にも努力した。これはローマ教皇アレクサンデル六世(在位一四九二~一五〇三)を刺激し、サボナローラの活動に対して圧迫が加えられたが、彼はこれに屈せず、教皇を無視した。
一方、サボナローラは市民生活にも、きびしい統制を加えた。
華美をきそった服装も地味となり、居酒屋は夕刻になると店を閉じ、断食や精進の日が多くなったので、肉屋のなかには破産する者があいついだといわれる。
市民たちの集会といえば、祈るためであり、屋外の行事といえば、宗教上の行列であり、歌といえば讃美歌であった。
ぜいたく品の取り引きは禁ぜられ、いかがわしい絵や本は「悪魔の作品」として押えられた。
また子どもたちが監視役をつとめ、婦人のはでな服装をとがめたり、賭博(とばく)師を追いはらったりした。
「がきどもがやってくるぞ」という声で、賭博師たちはいっせいに逃げだすありさまであった。
ほとんどが十四歳をこえないこれらの子どもたちは、棍棒のかわりに十字架を持ち、どこの家へでもはいりこみ、楽器、絵、香料箱、書籍などを没収してまわった。
一四九七年の謝肉祭のとき、サボナローラは没収された品々――装飾品、装身具、楽器、裸婦像、裸体画、いかがわしいとされる本(そのなかには、ボッカチオやペトラルカの作品もあった)などを大広場に集め、信仰のさまたげとなる「虚飾(きょしょく)」の焼きはらいを行なった。
ある商人は品物がつまれたとき、それらを買いたいといったため、すぐさまその肖像画が描かれ、悪魔の代表として焼かれることとなった。
市民のなかには自分の所有品を火のなかに投げこむ人びともいたが、躍動感と生命感とにみちた人体を描いた画家ボッティチェリも、その作品をみずから焼いたといわれる。
舞いあがる焔(ほのお)、鳴りわたる鐘やラッパの音、そのなかで僧たち、少年隊、熱狂した群衆が讃美歌を唱和した。
しかし翌年、焔はサボナローラ自身の肉体を焼きつくすのである。
フィレンツェ市民の、というよりも人間なるものの狂信性は、熱しやすく、さめやすい。
サボナローラの過激な干渉は、ときがたつにつれて、がんらい悦楽を好む市民たちの反感をまねく。
彼は説教をするだけで、メディチ家が与えたように現実に市民大衆にむくいるところはなかった。
金持ちの市民たちはこうした禁欲的な市民生活では、なによりもまず商売にならない。
市政改革も固まり、彼の雄弁で市民たちを啓蒙(けいもう)する必要もなくなった。
彼が接近していたフランス王シャルル八世は、一時はナポリ王国にまで侵入したが、教皇を中心とするドイツ・スペイン勢力の連合にあい、故国に軍を返した。
また教皇アレクサンデル六世がサボナローラの急進性を非難して、一四九七年五月破門したことは、彼をねたむ僧侶たちの反対を有利にする。
こうして反サボナローラの陰謀は進み、彼を異端とする罪状がつくりあげられた。
一四九八年五月、裁判によって有罪と認められたサボナローラは、市庁舎前の広場につくられた火刑台上で、首つりにされて火で焼かれた。
100
群衆のうちのだれかが叫んだ。
「予言者よ、いまだ、奇蹟を行なうのは!」
一瞬、火勢は衰えるかのようであった。群衆はざわめく。
「奇蹟だ!」
しかし火はふたたび燃え上がり、予言者の肉体は焼け落ちた。灰は集められて、アルノ川へ投げすてられた。
勇をこして広場に集まったサボナローラの信奉者は、わずか二、三人にすぎなかったといわれるが、処刑後、その場所にひざまずく婦人たちの姿も見うけられた。
3 チェザレ・ボルジア top
一四九八年五月二十三日、サボナローラの火刑を目撃したひとりの男がいたという。彼は、ついこのあいだまでサボナローラに狂喜していた民衆が、いまはあざ笑い、ののしり、非難しているありさまを見たし、また人肉がこげる恐ろしいにおいをかいだであろう。
彼はのちに書いている。
「武装した予言者はみな勝利をしめ、備えのない予言者は滅びる……」
この男、ニッコロ・マキアベリは一四六九年五月フィレンツェに生まれた。
ちょうど父ピエロの死によって「豪華王」ロレンツォが権力をにぎったころである。家庭は裕福ではなかったが、父は学問ずきの法律家であり、母は詩作をするなど、かなりの才女であったらしい。
彼の若いころについてはあまりよくわかっていないが、早くからラテン語を学び、ローマの古典に親しんだようである。
そしてサボナローラの死ののち、一四九八年六月ごろ、マキアベリはフィレンツェ政庁の第二書記局につとめることとなった。
当時のこうした官職は、たんなる小役人のそれではない。
古典の教養が深い者がえらばれ、いわば知的エリートの集団であり、マキアベリの仲間にもすぐれた人文主義者たちがいた。
そしてその仕事も静的なものではなく、十五年ほどのあいだに、彼はイタリア諸都市や諸外国に出張して、外交・軍事問題で活躍した。
しかし彼自身は外交官らしい風格ではなく、両眼ばかりがきらきら輝いている小利口そうな顔、青白い肌、質素な身なりで、あまり風采(ふうさい)はあがらなかったといわれる。外交使節マキアベリとして特筆すべきことは、一五〇二年、あのチェザレ・ボルジアと交渉をもったことであろう。 |
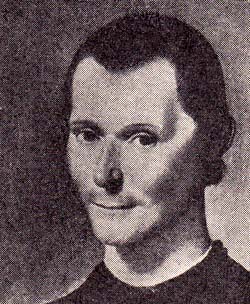
思想家マキアベリ――彼はフィレンツェ
再建に立ち上がるが失敗し、苦境の
中で不朽の著『君主論』を書き上げる。
これは交友のあったチェザレの
政治的才能から学んだものであった。
学校での歴史教育では『君主論』
の中身まで教える時間がない。
|
チェザレは、スペインの名家ボルジア家の出である教皇アレクサンデル六世と、名もない一女性――手練于管(てれんてくだ)にたけた女とも、素朴な女とも伝えられるが――とのあいだに、一四七五年ごろ生まれた庶子(しょし)で、弟や妹があった。
この一事でも推察されるように、当時の教皇は聖職者らしくなくて、きわめて世俗的であった。
それはアレクサンデル六世に先立つシクストス四世(在位一四七一~八四)のころからいちじるしい。
この教皇は甥などの自分の一族を要職につける「縁者びいき(ネポテイズム)」を始めたり、経済上の目的からさかんに「聖職売買(シモニー)」を行なったりした。
しかし一方では、シクストス四世はバティカン図書館やシスティナ礼拝(れいはい)堂などをつくり、画家ボッティチェリらが招かれて、この礼拝堂を飾った。
こうしてこのはなはだ世俗的な教皇はまた、はなばなしいルネサンス期教皇の先駆者であったのだ。
シクストス四世から一代おいたアレクサンデル六世も、サボナローラが非難したように盛んな権力意志、陰険(いんけん)な権謀術数(けんぼうじゅくすう)、悪辣(あくらつ)な聖職売買などで悪名が高かったが、一方では大建築家ブラマンテ(一四四四~一五一四)、ラファエロ、ミケランジェロなどを保護した代表的なルネサンス期教皇であった。
その子チェザレは父にもまして、典型的なルネサンス期専制君主のタイプである。
彼は自分の権勢をますためには、父の寵愛(ちょうあい)をうけていた弟カンディア公をおそらく暗殺したり、妹ルクレティアを政略結婚の犠牲にしてかえりみなかった。
しかし一面では、彼は美術家を保護し、レオナルド・ダ・ビンチとも親しかった。
チェザレはフランス王やアレクサンデルの支持のもとに、イタリア統一の野心を抱き、まず北イタリア方面を勢力下におこうとした。
一四九九年から着々と効果があがり、一五〇二年フィレンツェがおびやかされる形勢となった。
そこでフィレンツェ当局はチェザレと交渉し、これと友好関係を結ぶことにつとめたが、この外交に関係したのがマキアベリである。
彼はチェザレの非凡な政治的能力に驚かされ、いわゆるビルツの権化(ごんげ)をそこに見たのである。
ビルツとは人間の行動を生みだす活力であり、政治指導者には不可欠のものと考えられた。
マキアベリはチェザレのなかに乱世に処する政治家の素質を見ぬき、これは彼の代表作『君主論』に大きく影響したといわれる。
一方チェザレは北イタリア方面を押え、いまやイタリア統一にのりだそうとする。
このとき事態は急変、一五〇三年アレクサンデル六世が急死した。
流行の熱病にかかったとの説が強いが、一説によれば、枢機卿(すうききょう)たちを毒殺するために用意していた毒入りぶどう酒を、まちがえて自分で飲んでしまったとも伝えられる。
召使たちは一つのびんから教皇とチェザレのさかずきに酒をつぎ、もう一つのびんで枢機卿たちのさかずきを満たした。
教皇はそのまま飲み、チェザレは水でうすめて飲んだ。
チェザレは熱病にもかかっているが、心身の強さが生命を救ったものと思われる。
ともかくローマの市民たちは、この「野望、裏切り、残虐、色欲、貪欲(どんよく)」のかたまりのような教皇の死を、一種の安心感をもって迎えたという。
こうしてチェザレは最大の後援者を失ったのみならず、一代おいて、つぎの教皇ユリウス二世(在位一五〇三~一三)はボルジア家と仲がわるく、彼自身イタリア統一の野心をもっていただけに、チェザレを敵視した。
威光と権勢がなくなった風雲児は哀れである。
諸外国を巧みにあやつるユリウス二世の追及のまえに、ついにチェザレは捕われてスペインのある城に幽閉されてしまう。 そしてここを脱出した彼は、スペイン王にいどまれた戦いに加わり、ある小都市の包囲戦で、一五〇七年三月、あれほど利己的であった男におよそふさわしくない無意味な死をとげた――。
4 マキアベリズム top
一四九八年はじめ、まだ二十八歳のフランス・シャルル八世は事故で世を去ったが、つぎのルイ十二世(在位一四九八~一五一五)もイタリアの誘惑からのがれることはできず、出兵をくり返した。
教皇ユリウス二世は、みずから馬で戦場を疾駆(しっく)するような軍人教皇で、これまた前任者たちとはちがった意味で、「もっとも世俗的で聖職者らしからぬ」人物であり、ある同時代人にいわせれば、「血なまぐさい剣闘士の親分」であった。
この教皇が、フランス軍の侵入を黙視するわけはない。
一五一一年、彼は神聖ローマ皇帝、スペイン王などと結んで、このフランス軍に対抗しようとする。
フランスと友好関係をつづけてきたフィレンツェは、連合軍の脅威にさらされるにいたった。
これより先、マキアベリは戦乱のイタリアに処するために、フィレンツェの軍制改革が必要と考えた。
傭兵(ようへい)は無統制、無規律で、ただ給料を目あてに戦場に行くにすぎない。
すぐれた傭兵隊長とは、できるだけ兵員や武器を損傷しないもののことである。
マキアベリは、イタリアの弱点は長年にわたって傭兵に依存してきたことにあり、君主は自国の軍隊を養成しなければならないと考えた。
そこで一五〇六年彼の努力によって、フィレンツェにぞくする町村から兵士が徴集され、国民軍の編成となった。
しかし一五二一年八月スペイン軍がこの都市国家に迫ったとき、その国民軍はほとんど役にたたないで敗走してしまう。
これまでの無責任な傭兵にかえて、愛国的な軍隊を養成しようというマキアベリの考えも、実質がともなわず、構想倒れに終わってしまった。
そして外国勢にあと押しざれて、一五二一年九月メディチ家がふたたびフィレンツェに帰来したのだ。
当時のメディチ家の中心は、「豪華王」ロレンツォの三男ジュリアーノ(一四七九~一五一六)と孫ロレンツォ二世(一四九二~一五一九)である。
それからおよそ二ヵ月後、マキアベリは職を追われ、フィレンツェ領内に禁足され、さらに翌年、反メディチ家の陰謀(いんぼう)に加担したという疑いで投獄された。
教皇レオ十世(在位一五一三~二一)の即位による大赦令で、まもなく釈放されたが、彼は市の郊外に隠棲(いんせい)することをよぎなくされる。
失意のうちに、しかし思いを祖国イタリアと愛するフイレンツェにはせながら、マキアベリは一五二二年の後半、不朽の著『君主論』を完成した。
ヨーロッパ諸国からたえず侵略されているイタリアをどうして救うか、そのためには有能な君主が出現してイタリアを統一するよりほかはない、ではどうすれば君主は強力な統一国家をつくりあげることができるか。
マキアベリは論ずる――
君主権は絶対的であり、宗教や倫理から独立しているべきこと、
国家の利をすすめ、自分の地位を確保するためには、君主は詐欺(さぎ)、賄賂(わいろ)、暗殺などのいかなる手段にも、どのような権謀術数(けんぼうじゅつすう)にも訴えてよいこと、
政治においてはなにが正しいか、なにが悪いかを問うべきではなく、なにが有効か、なにが有害かを問うべきであること、
そして政治においてただひとつの徳は実行力あるのみと。
たとえばマキアベリは書いている。
「……君、王は野獣の性質を適当に学ぶ必要があるのであるが、そのばあい、野獣のなかでは狐とライオンに習うようにすべきである。
というのは、ライオンは策略のわなから身を守れず、狐は狼から身を守れないからである。
わなを見抜くという点では、狐でなくてはならず、狼どもの度胆(どぎも)を抜くという点では、ライオンでなければならない……」
「……名君は、信義を守ることがかえって自分に不利をまねくばあい、あるいは、すでに約束したときの動機が失われてしまったようなばあいでは、信義を守ることをしないであろうし、また守るべきではないのである。
もっとも、この教えは、もし人間がみなよい人間ばかりであれば、まちがっているといえよう。
だが、人間は邪悪なものであって、あなたに対する信義を忠実に守ってくれるものではないから、あなたの方も人びとに信義を重んずる必要はない。
そのうえ、信義の不履行を合法的にいいつくろうための口実は、君主にはいつでも見いだせるものである。」
(池田廉氏訳による) |
この理想や空想をしりぞけて、現実の効用をねらう徹底したリアリズムは、その論者の死後、いわゆるマキアベリズムとして生きつづける。
『君主論』はヨーロッパじゅうで読まれ、七十五年たらずのうちにマキアベリズムという言葉が、イタリアをはじめ、イギリス、フランス、スペインで会話のなかでも使用されたという。
しかしこのときからもはや、その創造者の憂国の情はどこかにうちすてられ、目的のために手段をえらばない悪辣な政治上の手段になっていった。
しかもマキアベリの憂いもむなしく、十六世紀のフィレンツェは、もはやむかしの面影をとり返すことはできない。
イタリア・ルネサンスの中心はローマにうつり、諸都市が戦乱に右往左往するなかにあって、今日は神聖ローマ皇帝、明日はフランス王と通じて、権力の伸長につとめたのはローマ教皇であった。
5 ローマの掠奪(りゃくだつ)
top
軍事的であるという点で非難されたユリウス二世は、その剛毅果断な性格をもって、聖職売買のような悪習を禁じ、腐敗堕落を正した。
そしてミケランジェロにシスティナ礼拝堂の天井画を描かせ、ブラマンテにイタリア・ルネサンス最大の記念物、聖ピエトロ寺院の改築を行なわせ、ラファエロにバティカン宮の壁を飾らせたのも、この気宇(きう)雄大な教皇であった。
ユリウス二世のあとをついだのは「豪華王」ロレンツォの次男で、ピエロの弟にあたるメディチ家のジョバンニ(一四七五~一五二一)であり、一五二二年教皇レオ十世となった。
彼は政治的野心においても、文化の保護においても、アレクサンデル六世やユリウス二世の後継者として、ルネサンス期教皇の名に恥じなかった。
彼は独仏抗争を利用してその地位を保つとともに、芸術の保護に熱中したが、彼が教皇の地位につくことを喜んだのも、それによって、美と豪奢(ごうしゃ)に対する好みを満足させるための財源を、手に入れることができたからだともいわれる。
レオ十世は、イタリアが誇る有名な彫刻家や画家を身辺に集め、とくにラファエロを愛した。
そして神が与えたもうたからには、教皇権をできるだけ享楽しよう、と語ってはばがらぬこの教皇をいただいて、バチカン宮殿の楽の音はたえずローマの空にひびきわたり、教会はいわば社交上のクラブと変じ、そこではつねに美や芸術について談笑されたが、キリスト教については論ずる人も少なかったという。
レオ十世の生活も栄華をきわめたもので、その食卓の費用だけでも、ユリウス二世の出費のおよそ十倍に達し、そこには山海の珍味がもられ、会食者もおびただしかった。
教皇は会計係に財政状態を聞かず、金の出所を確かめることなく使いまくったので、財政はいつも乱れていた。
レオ十世は四十七歳で一五二一年末に世を去ったが、これについては毒殺も噂された。
教皇は多くの方面に惜財をつくっており、しかも教皇庁の金庫はまったくカラで、その柩(ひつぎ)を買う金すらこと欠くありさまたったそうである。
そしてこのレオ十世のとき、聖ピエトロ寺院の改築に金がたりず、大がかりな免罪符(めんざいふ)の販売となり、それがルターの宗教改革運動の発端となったことは、後述されるであろう。
一五一五年から、フランス王フランソワ一世(在位一五一五~四七)はシャルル八世、ルイ十二世と同じようにイタリアに軍を進めていたが、一五一九年より、これに対抗したのは神聖ローマ皇帝カール五世である。
この一五一九年、メディチ家ではロレンツォ二世が世を去りフィレンツェを統治するのは枢機卿(すうきけい)ジュリオ(一四七八~一五三四)である。
彼は「豪華王」ロレンツォの弟で暗殺に倒れたジュリアーノの庶子であるが、一五二三年、彼は選ばれて教皇クレメンス七世(在位一五二三~二四)となり、フィレンツェとローマに君臨することとなった。
彼は同じメディチ家の出身ではあるが、レオ十世にくらべると、その生活ははるかに地味であった。
しかし当時やはり芸術家や文人はローマに集まったが、じつはこの教皇の時代にそのローマは致命的な打撃をうけたのだ。
すなわちカール五世の権勢の強大化を恐れる教皇は、勢力均衡上からフランスに接近し、このためカールの軍はローマに迫ることとなった。
それはアルプスの南の豊かな富をめざして駆り出されたドイツ、スペインの凶暴貪欲(きょうぼうどんよく)な軍隊であった。
ドイツ傭兵のなかにはルター派で、カトリックに反感を持つ者が多く、スペイン傭兵はまったく無秩序な烏合(うごう)の衆である。
そのうえ給料支払いも十分でなく、また食糧も不足していた。
こうして一五二七年五月、「永遠の都」ローマは史上まれな掠奪と暴行のまえにおののいた。
それは都市や文化を破壊したばかりでなく、時代の精神そのものにも大きな打撃を与えた。
人間なるものが行なった暴虐のかずかずを眼(ま)のあたりにしたとき、人間尊重のルネサンス・ヒューマニズムの精神がたちなおりうるであろうか。
このいわゆる「ローマの掠奪」は、イタリア・ルネサンスの末期を画する重大な事件といえよう。
ローマにいたクレメンス七世はかろうじて避難したが、この事件に呼応してフィレンツェには反メディチ家の暴動が起こり、その支配から脱するにいたった。
そしてフランスも劣勢となったとき、教皇はこんどはカール五世に接近して、その力によって自分の権勢およびメディチ家の再興をはかった。
一五二九年、皇帝と教皇との軍はフィレンツェに迫る。
このとき、フィレンツェの防塞(ぼうさい)をつくることに関係したのがミケランジェロである。
ところが九月、彼は恐怖心から逃亡し、実現はしなかったが、フランス王フランソワ一世の保護を求めたほどであった。
彼は思いなおして十一月に帰来したが、敵の攻撃はすでに始まっており、フィレンツェは一五三〇年八月ついに降伏する。
フィレンツェ市民に対する処罰はきびしかったが、ある教会の鐘楼(しょうろう)に身をかくしていたミケランジェロは、クレメンス七世の保護のもとに身の安全をうるとともに、彼の傑作である諸像(昼と夜、朝と夕)をメディチ家の廟にきざむことにかえった。
弱さというか、逡巡(しゅんじゅん)というか、この大天才の性格と生涯におけるひとつのエピソードであろう。
降伏したフィレンツェでは、メディチ家を世襲の君主とする公国の成立となり、ここに伝統あるフィレンツェ都市共和国は姿を消すにいたった。
その後コジモ一世(一五一九~七四)は近隣を征服し、一五六九年教皇の許しをえて、トスカナ大公国を成立させた。しかしそれはもはや輝かしいルネサンスのメディチ家ではなく、君主としてのメディチ家の繁栄であろう。
また通説によれば、イタリア・ルネサンスの背景をなしていた経済上の発展は、しだいにこの半島を去り、ほかの半島――あのかずかずの大航海をなしとげ、新大陸アメリカやアジアからの成果にうるおうイベリア半島に移行していった。
こうしてフィレンツェ、ローマの文化が衰えたのち、イタリア・ルネサッス絵画の主流となったのはベネチア派であった。
これを代表するティチアーノ(一四九〇ころ~一五七六)は長い生涯を通じて制作をつづけ、華麗(かれい)な官能と色彩の美を確立した。
最後に、メディチ家はフランスの歴史に二人の女性を送ったことに注意しておこう。
一五三三年、当時フランソワ一世の王子、のちのアンリ二世の妃となったカテリーナ・デ・メディチ(カトリーヌ・ド・メディシズ、一五一九~八九)、一六〇〇年、アンリ四世と結婚したマリア・デ・メディチ(マリー・ド・メディシズ、一五七三~一六四二)である。
ともに夫王に先立たれ、ともに幼少な国王の摂政(せっしょう)となり、前者は宗教戦争時代のフランスに、後者は絶対主義発展期のフランスにその名をとどめた。
メディチ家の歴史を完全なものにするためには、この家名にふさわしく、権勢を望み、策謀にふけり、美を愛し、そして誇りに生きたこれらふたりの女性を、無視することはできない。
そしてこのうち、とくに重要なカテリーナは、本書中の十二章『聖バルテルミーの虐殺(ぎゃくさつ)』に登場するであろう。
top
**************************************** |