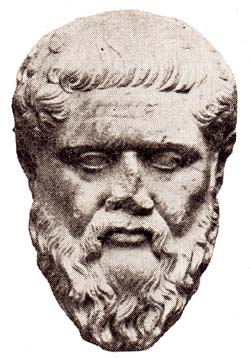|
****************************************
Index 1
2 3
4 5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
5 アテネの民主政とソフィスト(賢者)
――ソクラテス――
1 アリストファネスの『雲』 top
|

ギリシアの壺と杯の形
|

アテネのアクロポリス出土の
コレー(少女像)
|
ペルシア戦争より四、五十年前ごろ、アテネはペイシストラトスという僭主(タイラント=非合法的な独裁者)が治めていたが、そのころからしだいに商工業が発達し、文化にも見るべきものが生まれた。
貨幣がつくられるようになり、「アッティカ様式」といわれる陶器がさかんにつくられるようになって、アテネはギリシアの製陶業の中心地となった。これらの壺はイタリアや、黒海の沿岸などでもたくさん発掘されており、アテネの陶器が広く売られていたことがわかる。
ギリシアの壺には、神話伝説などや、日常生活の寸景(すんけい)などが描かれ、彼らが神様をどのような姿で考えていたかとか、どのような衣服をつけていたか、どのような髪型をしていたか、どんな愛情生活をしていたかなどなど、書物からはわからない、いろいろなことを具体的に知ることができる。
これらの壺絵には画工のサインがしてあって、アマシスとかエクゼキュアスなど三十名ほどの名が知られている。
サインがしてあることは、壺を買う人に、壺絵画家についての好みがあったことを教えている。
陶器はもちろん陶器そのものが商品として需要があったが、そればかりでなく、ギリシアの重要な輸出品である香油やぶどう酒の容器としても売られた。
こういう意味で、ギリシアでは陶器の製造販売と、商工業の発達とは密接な関係があった。
ペルシア軍がアテネ市に侵入し、破壊を行なったために、ペイシストラトス時代の建築や彫刻はみなこわされてしまった。
アクロポリスの神殿を飾っていた彫刻類の破片は、ペルシア戦争後、地中にうめ込まれて地ならしされ、その上に新しい神殿が建造された。
今世紀になって、アクロポリスの発掘が行なわれ、これらの損傷をうけた彫刻類がたくさんみつかった。
ギリシア彫刻というと、白い大理石像を思う人が多いだろうが、かつてはそれに彩色がしてあったのである。
長い年月のあいだに、彩色は消えてしまった場合が多い。
しかしアクロポリスの土中から発掘された彫刻類は、土中にあったために、美しい彩色をよく残しているものもあり、昔の姿を思わせている。
これらは今アテネのアクロポリス博物館に陳列されているが、それらを見ると、ペイシストラトス時代には、アテネの彫刻はまだ古拙(こせつ)な固さ(アルカイックという)を持ってはいたが、素朴な美しさを表現している傑作を生んだことがわかる。
アテネで劇の上演が盛んに行なわれるようになり、三大悲劇詩人(アイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデス)が現われたのは、ペイシストラトスより五十年ほどあとで、ペルシア戦争中から戦後にかけてのことだった。
しかしアテネで劇の上演をはじめたのは、ペイシストラトスだった。
悲劇よりおくれて、喜劇が発達し、アリストファネス(紀元前四四五〜三八五年ごろ)という喜劇作家が現われた。
彼は四、五十編の作品を書いたが、今は十一編残っている。
その中に『雲』という作品がある。
アテネではディオニュソスの神様のお祭りのときに、劇の上演は国の行事として行なわれた。それはコンクール形式で行なわれ、喜劇の場合は、三人の作家が一編ずつ上演して競争した。
そして一等、二等をきめるのだが、『雲』は三等、つまりビリだった。
これから『雲』の筋をお話しするが、なかなかおもしろい劇である。これがビリだったとすると、一等のタラティノス作『酒瓶』や、二等のアメイプシアス作『コンノス』などは、どんなにすぐれた喜劇だったろう。
それらが失われてしまって、残っていないことは残念なことである。
『雲』は紀元前四二三年に上演されたが、現在残っている台本は、上演されたものに作者がそののち手を入れたものである。
主人公はストレプシアデスという田舎紳士である。
彼にはペイディッピデスというのら息子がある。
この息子は競馬きちがいである。
競馬きちがいといっても、当時は馬券があったわけではない。 |

喜劇作家アリストファネスと伝えられる像
|
|

アテネのディオニュソス劇場跡
|

喜劇の一場面を描いた壺
|
自分で馬を買って、その馬に乗ったり、戦車を引かせたりして競争するのである。
なにしろ馬は高価だった。この劇には一二ムナ(五分の一タレント)の馬が出てくる。
当時一ムナあれば、最低五十日は暮らせた。
高価な馬に凝るのでペイディッピデスは借金だらけになり、せめて利息だけでも払えと、毎日借金取りにせめたてられる。
そこでストレプシアデスは、息子にソクラテスの塾(プロンテステリオン)にはいって雄弁術を学び、借金取りを追い払えという。しかし息子が断わるので、おやじは自分でソクラテス塾にはいる決心をする。
塾に行ってみると、ソクラテスの弟子(でし)たちはのみの足型をろうでとり、それを物尺(ものさし)にして、蚤(ノミ)は足の長さの何倍とぶかを調べたり、蚋(ブヨ)は口でなくのか尻でなくのかなどと論じている。
かと思うと体育場に出かけ、砂場に大きなコンパスで円を描いて、幾何を勉強するふりをして、ぬいである衣服をコンパスにひっかけて、ぬすんだりしている。
そして先生のソクラテスは、籠にのって、天井からぶら下がっている。
天文の観測をしているのだった。
「借金取りを追いかえす術を教えてくれれば、神々に誓ってお礼はします」とストレプシアデスがたのむと、「神々なんかいるか」と一喝される。
「では雷を使うのは」「それはゼウスではなくて、空の渦巻(デイノス)だ」と教えられる。
かんじんの雄弁のほうは、ストレプシアデスは老人で頭が固く、ぜんぜん覚えられず、トンチンカンばかり答える。
やはり若い息子でなくてはということになり、ペイディッピデスが、かわってソクラテスに弟子入りする。
そしてすぐ雄弁術をものにする。
息子がどんな議論にも勝てる雄弁術を手に入れたからには、ストレプシアデスは気が強くなり、払わなければ訴えるぞとおどかされても平気で、借金取りをみな追い払ってしまう。
「元金が払えなければせめて利息だけでも」といわれれば「利息とはなんぞや」とひらきなおり、「時が流れるにつれてふえる金だ」といわれれば「川がいくら流れこんでも海は大きくはならぬ」などと、先生のところでききかじりの議論で、借金取りをいいまかしてしまう。
こうして借金取りを追い払い、一杯のもうということになり、親子は酒盛りをはじめた。
ところが酒を飲みつつ歌うことになって、喧嘩(けんか)になってしまった。
父親がシモニデスとか、アイスキュロスなどの歌を歌えというと、「そんな古くさいものが歌えますか」と息子はエウリピデスの歌を歌ったための喧嘩だった。
つまり父親が謡(うたい)を歌えというと、息子がフォークソングを歌ったというようなところである。
喧嘩になったあげく、息子はおやじをなぐる。
「息子のくせにおやじをなぐる法はない」というと、
「ではおやじはなぜ息子をなぐってよいか」
「息子がかわいいし、息子のためを思ってだ」
「私もお父さんがかわいいし、おためを思うからです。それに老人は子供にかえるというじゃあありませんか」
「そんなことをいうと、おまえもいずれ息子になぐられるぞ。おまえも息子をなぐればよいのだ」
「もし息子が生まれなかったらどうします。なぐりそこなうといけないから、今のうちになぐっておきます」と、どういっても息子は負けていない。
くやしがった父親は、「これもみなあのソクラテスめが悪い議論を教えたのがけしからんのだ」と、ソクラテスの塾に出かけ、火をつけるところで劇は終わる。これが『雲』の荒筋である。
2 ソフィスト(賢人) top
『雲』の主役は田舎紳士のストレプシアデスだったが、主題のうえからはソクラテス批判が劇のねらいで、ソクラテスは実際にそのころいた哲学者だった。
それではソクラテスはなぜ批判されているのだろうか。
この劇では、彼は当時新しい教育をしていた「知恵のある人(ソフィスト)」の代表として考えられているのである。
「ソフィスト」というのはどのような人たちだったのだろうか。
『雲』が上演されたのは紀元前四二三年三月のディオニュソスの大祭のことだったが、そのころアテネ市にはソフィストとよばれる人々がたくさんいた。
そのなかでも有名なのは、アブデラの人プロタゴラス、レオンティノイの人ゴルギアス、エリスの人ヒッピアス、ケオスの人プロディコスなどであった。
彼らの一人のゴルギアスは、自分たちが教えるのは、「裁判所では陪審官を、評議会(プーレ)では評議員を、民会(エクレシア)では出席者を、そのほかのどんな政治的な集まりでも、言葉で人々を説得できる」雄弁術だといい、「この雄弁術こそ、本当にもっとも良いものである。
つまりそれは人々自身に自由をもたらし、また各人が自分のポリスで、他の人を支配できるみなもとになるものだ」と自信をもっている。
彼らはこの雄弁術を教えるのに授業料をとった。
それもたいへん高い授業料で、プロタゴラスは一科目に二タレントとった。一タレントで軍艦一隻が建造されたのだから、たいへんな金額だった。
このためプロタゴラスは当時の第一流の彫刻家だったフィディアスの十倍以上も金をかせいだと伝えられている。
キュレネの人アリスティッポスの授業料は一〇〇〇ドラクマ(一タレントの六分の一)だったという。
またヒッピアスは若いころシチリア島に行き、またたくまに二タレット半もかせいだといわれる。
このほかに、授業料にいろいろ種類があって、高い授業料を払うと、より良い雄弁術を教えるという先生もいた。
プロディコスがそれで、いちばん安いのは一ドラクマで、いちばん高いのは五〇ドラクマだった。
ソクラテスはためしに、いちばん安い授業料を払ってその講義をきいてみたことがあったという。
もっともソフィストが高い授業料を取って、大金持ちになったという話はデマで、ゴルギアスには妻子もいなかったのに、死んだとき、たいして財産を残していなかったといっている人もある。
しかし、あとになってソフィストがたいへん悪くいわれるようになった原因の一つに、彼らが授業料をとったことがあげられているから、かなりの授業料をとり、なかにはそれで金持ちになったソフィストもいたことは、たしかであろう。
彼らは高い授業料をとったが、弟子入りする者はなかなか多かった。
それは彼らから雄弁術を学ぶと、ゴルギアスが誇っているように、あらゆる人々を説得して、ポリスの人々を支配できるからだった。
ちょうどストレプシアデスがペイディッピデスに、ソクラテスの塾にはいることを熱心にすすめたように、わが子の立身出世を望む当時の教育パパたちは、わが子をソフィストの弟子にした。
高い月謝を払っても、もとをとってあまりあることになると親たちは考えたのだった。
ソフィストから雄弁術を学ぶと、なぜ立身出世が保証されたのだろうか。
そのためには、当時のアテネの民主政のことをお話ししなければならないが、それはもうすこしあとのことにしたい。
とにかく民主政ではことをきめるとき、多数決の原理が支配しているので、おおぜいの人に賛成してもらえるように話ができることが大切だった。
したがってうまく話せる人は、国の重要な役について、思うように他人を支配することができたし、また人から攻撃されることがあっても、うまくいいのがれることができる自信があれば、思い切ったふるまいもできるわけだった。
そのうえ当時のアテネ人は雄弁に動かされやすく、美しい声で、きれいな言葉で、うまく話せる人の話には、その話の理屈が少しへんでも感心して、賛成するような傾向があった。
レスリングで反則をおかして噛みついた男に、「女のように噛みつくなんて」と悪口をいうと、「いや、ライオンのように噛むのだ」と答えたという話がある。
アテネではこうすぐうまく言葉を返せる男には、人気が集まるのだった。
『雲』のなかでストレプシアデスは、ソクラテスの塾では「金さえ払えば、正しいか正しくないかはおかまいなしで、弁論で勝つ術を教えてくれる」といっている。
ゴルギアスは「何も知っていなくても、自分の弁論術はたいへん便利なもので、これさえ知っていれば、どんな専門家と問答してもけっして負けることはない」といい、「だれでも、なんでも、好きなことを質問してみろ、すぐ答えてみせる」と誇った。
「どんなことにもけっして負けない雄弁術」「何にでも即座に答えられる弁論術」そんなものがいったいありうるだろうか。
ゴルギアスの作といわれる『ヘレネの弁論』というのが残っている。
「ヘレネ」というのは、ギリシア神話のなかに出てくる有名な美女で、あのスパルタのメネラオス王の妃のことである。
彼女がトロイアの王子パリスにさらわれたために、ギリシアの国々が連合軍をつくって、とりかえしに行ったのが、トロイア戦争ということになっている。
彼女のために十年にもおよぶ大戦争が起こったので、彼女はたいへんな悪女ということに、のちのちまでなった。
ゴルギアスは、この悪女「ヘレネ」を、彼女はけっして悪女ではないと弁論するのである。
しかし、もちろんこの弁論はまじめなものではなくて、人をおもしろがらせるための、たわむれの議論なのだが、彼の弁論のしかたの見本として、そのあらましを書いてみよう。
ヘレネがトロイアにさらわれていったのは、
1 運命や、神々の意志で、必然的にそうなることになっていた。
2 暴力によってむりやり連れて行かれた。
3 言葉で説きふせられた。
4 愛欲のとりこになったなどのためである。
しかし、
1 神の意志や運命を人間はあらかじめ知って、避けることはできない。
2 暴力はふるう者が悪いので、ふるわれた人はむしろ同情されるべきである。
3 言葉は神にも近いようなもので、人の深奥くはいりこみ、心をとらえ、逆らいがたくしてしまう。
これも形こそちがうが、一種の強制で、暴力と同じように、説得は説得する者に罪はあっても、された者には罪はない。
4 愛欲(エロス)は神の一種で、人間の意志ではあらがいがたい病気のようなもので、これにかかるのは罪ではなくて、不幸なのだ。 |
ざっと、こんなふうである。
プロタゴラスには著書が残っていないが、彼の流れをくむものといわれている『両論(ディツソイ・ロゴイ)』とよばれる、著者も書かれたときもわからない一文が残っている。
これは、「これについては両論がある」という書き出しで、善悪、美醜、正邪、真偽などについて、それは異なるものだというのと、同じものだという二つの論を並べた変わった一文である。
死は一般の人間にとっては悪だが、墓掘り人には善である。
また靴がこわれるのは一般の人には悪だが、靴屋にとっては善である。したがって善と悪は同じである。
とすれば親にたくさん良いことをしてもらった者は、親にたくさん悪の借りがあることになる。
したがって善と悪を同じものとは考えられない。こんなことが対話の形で書かれている。
『ヘレネの弁論』にしろ『両論』にしろ、先にも書いたようにたわむれの論議だったかもしれない。
しかし、ソフィストの論議の方法は、こんなものだった。
絶対の悪も、絶対の善もない。少し見る立場を変えれば、善は悪になり、悪は善になる、というのが彼らの考え方だった。
これを利用して彼らは議論に勝つわけである。
『雲』は喜劇で笑いをねらって誇張や、とりちがえなどをたくさんふくんでいるが、ソフィスト的な議論のしかたが反映している。
借金とりを追いかえす問答や、息子が父をなぐることを正当化する議論などは、そのよい例だろう。
ソフィストが議論に強いのは、彼らが絶対を信ぜず、この世のことは相対的なものだと思っていたからだった。
ソフィストの名をあげたところに、その出身地を書いておいたように、彼らは外国生まれで、いろいろな事情で故郷を捨てて、アテネに集まって来た者が多かった。
彼らは旅行しているあいだにたくさんの国々を見、風俗や習慣が国々によって違うのを知った。
『両論』には次のようなことが書かれている。
「スパルタでは少女が体操をしたり、下着を着ないで歩くのを美しいとするが、イオニアではそれをみっともないと思う。 ……マケドニアでは結婚前なら娘は恋をしても、男と交わってもよい。しかしギリシアでは両方とも許されない。
……マッサゲタイ人は親を殺して食べるのは、子の腹へ葬るのだからこのうえもない立派な葬り方だが、ギリシアではそんな恥ずかしい恐ろしいことをすれば、国外に追放されてみじめな死に方をする……」
こんな例がたくさん並べられ、「すべての人が醜(みにく)いと考えるものをもちよって、それから各人が美しいと考えるものを取れば、何も残らないだろう」と書いている。
こういう考え方は広く各地を旅行したヘロドトスなども持っていて、彼の『歴史』には、国によって習俗がかわり、あるところで良しとすることが、他のところでは悪であることがしきりに説かれている。
ひろく各地の習俗を知って、絶対の善も悪もないことを知ったソフィストたちには、白を黒と、黒を白といいくるめることも容易であったのである。
ソクラテスは、『雲』ではこのような弁論の師であるソフィストの一人とされ、批判されたのだった。
こんな議論のしかたを若い者たちに教え、古い神々も信じないし、年長者も尊重しない生意気な青年たちを育てたと、彼は批判されたのだった。
3 アテネの民主化 top
アテネの国ができたころは、王政だった。
そして伝説に近いが、アイゲウスやテセウスなどの王の名が伝わっている。
王政はやがて、貴族たちの政治にとってかわられた。
貴族たちは政治の権を、自分たちだけで独占したばかりでなく、裁判権も彼らだけが持っていた。
このため貴族と一般の人々とのあいだに争いが起こると、貴族たちは自分たちに有利なように裁判を勝手にとりしきった。
平民たちはこのことに強い不満を持っていた。
ヘシオドスという叙事詩人が、彼の作品『仕事と日々(エルガ・カイ・ヘメライ)』のなかで、鷲(わし)とうぐいすの物語にたとえて、強い者が弱い者をいじめ、力が正義のように見えることを強く怒り、裁判の不正に強い怒りを向けている。
ヘシオドスの歌ったのは、アテネより北のボイオティアの農民の生活だが、貴族が勝手に不正な裁判をするのはアテネでも同じことだった。
そのうえそのころは、文字に書いた法文はなく、慣習法が行なわれていた。
法律が文字にはっきり書かれていないので、そのあいまいさを利用して、貴族はこれが慣習だと勝手な判決をし、一度そういう判決が行なわれると、それは慣習になってしまい、貴族にはしだいに有利に、平民にはしだいに不利になる傾向があった。
民衆の不満はしたがって裁判に集中した。
貴族と民衆の争いは絶えず、民衆の不満はますます強まるばかりだったので、アテネではドラコンが紀元前六二一年に、とうとう成文法を作ることになった。
このドラコンの法律はたいへんきびしい法律で、たいていのことが死刑になることになっていた。
そのため「血で書かれた」といわれたほどだった。
また貴族に有利で、今までよりも民衆に特別に有利になったような規則があったわけではなかった。
しかしとにかく書かれた法文ができたので、あいまいさを利用して、むやみなことはしにくくなった。
一応成文はできたが、これでアテネの政治・経済状態が改善されたわけではなかった。
土地は少数の貴族の手にしだいに集中した。
これに対して民衆は貧しくなり、彼らのなかには土地を失い、さらに自分のからだを抵当にして借りた負債のために自由を失って、奴隷になってしまう者も多かった。
こういう傾向は強まるばかりだった。
こういう状態だったから、貴族と民衆とのあいだには争いが絶えなかった。
その争いを調停するために出てきたのがソロンだった。
ソロンはたいへん賢い人だとされており、とくに金持ちでも貧乏人でもなかった。
そのため彼に調停をまかせても、金持ちにばかり有利になるように事をきめたり、貧乏人にばかり味方することもないだろうと思われた。
そのため紀元前五九四年に富裕者からも、貧者からも支持されて調停者として選ばれた。
彼は調停者になると、まず、あらゆる借金を棒引きにしてしまった。
これは「重荷おろし(セイサクティア)」とよばれた。
この情報をいちはやく知った人々がいて、あちこちでたくさんの借金をし、金もうけしたという。
ソロン自身もそれをやったという噂もあったらしい。
つぎに彼は借金が返せないために奴隷になっていた人々をみな解放し、もとの自由人に返した。
そのなかにはずっと前に外国に売られていたために、自由になって帰って来ても、アテネの言葉がしゃべれない者までいたという。
彼はまた人々を、その財産収入の額によって四級に分け、財産収入の多い人ほど政権に多くあずかれるようにした。
しかし最下級の「テーテス」とよばれた無産者でも、民会に出席し、裁判に参与することができた。
この制度で、貴族の家に生まれても、財産収入のない者はあらゆる政治に参与することができるわけではなくなった。
それに反して平民でも収入の多い者は、重要な政治にも参与できるようになった。
そのためこの制度を「金権者政治」とか、「富裕者政治」などとよぶ人もある。
ソロンはこのほか貨幣や度量衡(どりょうこう)制度も改め、ドラコンの法律を殺人に関するもの以外はやめ、新しい法律を作った。
ソロンの新しい法律はその後ずっと長いあいだ、アテネの国法となった。
彼はこのように諸改革を行なったが、金持ちは貸し金がゼロになってしまったことでソロンを恨み、貧民は土地を再分配してもらえると思っていたのに、土地はもらえず不満だった。
これらの不満にうかがえるように、ソロンの改革はアテネの社会の矛盾を徹底的に改革するものではなかった。
そのため、貧富の争いはなおやまず、彼らはそれぞれ党派を作って争いつづけた。
こうした党派争いのあいだから、ペイシストラトスは親衛隊を率いて、紀元前五六一年アクロポリスを占領して僣主(タイラント)になった。
彼はタイラントで、非合法的に権力を握った独裁的支配者だったが、けっして暴君ではなかった。
彼の時代にはむしろよい政治が行なわれ、アテネの商業や工業が盛んになり、美術・文学その他の文化も起こったことは、前に書いたとおりである。
しかしペイシストラトスの死後(紀元前五二七年)、彼の息子のヒッピアスがタイラントになってからは、しだいに暴政になった。
人々はヒッピアスを倒そうとしたがなかなか成功しなかった。
しかしスパルタの力を借りて、紀元前五一〇年にとうとうヒッピアスを国外に追放することができた。
ヒッピアスの追放後、アテネはごたごたしたが、紀元前五〇八年に、クレイステネスが改革を行なって、アテネの民主化をすすめた。
彼は古い氏族制的な区分「部族(ピユレー)」を改めて、新しく政治的、軍事的な区分にした。
これによって、貴族たちの権力のもとはなくなり、民主化はすすんだ。
貴族にかわって、ソロンが財産収入で四級に分けたなかの第三級の「農民(ゼウギタイ)」級の人々が、政治的に重要な役割をするようになった。
彼らは胸甲や丸楯などの重武装を自弁できるほどの収入のある人々だった。
ペルシア軍が攻めて来たときに、マラトンで勇敢に戦って勝利を得たのは、この重装歩兵(ホプリタイ)たちで、彼らの密集戦術が、ペルシアの騎兵たちを打ち負かしたのだった。
マラトンの勝利で、アテネ人は自分たちの政治体制に自信を持った。
何十倍という敵の大軍を、わずか一万人の重装歩兵で、独力で破ることができたのは、「自分たちの民主政のおかげだったのだ。
もし負ければ自分たちはこの自由を失って、ペルシア人王の奴隷になってしまうのだ」と考えて必死になって戦ったのだが、もともと大王の奴隷のようなペルシア兵には、失う自由がないのだから、彼らは勝っても負けてもよいという気持ちで戦ったから敗けたのだ。
こんなふうにアテネ人は考えた。
そしてマラトンの戦勝後は、重装歩兵の階層の人々の政治的発言力が強くなった。
つぎのサラミスの海戦の勝利は、アテネの民主化をいっそう強めることになった。
ギリシアでは参戦するときには、武器を自分で買いととのえねばならなかった。
国で支給してくれるわけではなかった。したがって武器を買う力のない人は、戦争に行くことができなかった。
戦争に行くことができない人は、政治上の発言力を持つこともできなかった。
しかし軍艦を漕ぐことは、力さえあればよかった。
よろいなどをつけて乗船することは、むしろ重くてじゃまだった。
したがって武器を買えないような「無産者(サーテス)」でも水夫になって、海戦に参加することはできた。
アテネは、その無産者たちが乗り組んで戦ったサラミスの海戦に勝ち、ペルシアとの戦争に勝つことができた。
自分たちの力が祖国の国難を救ったのだという自信を無産者たちは持ち、彼らは政治に参与することを要求するようになった。
こうしてアテネの民主化は、ペルシア戦争の勝利とともに、無産者にまで徹底していくことになった。
徹底した民主政では、民会(エクレシア)が最高・最終の議決機関になった。アテネの民会は、市民ならみな出席することができた。
当時のアテネ市民の数は三万人といわれるが、三万人全部が出席することは、ほとんどなかった。
六千人出席すれば、定足数だったが、それも集まらないことがよくあったので、出席者には日当を出すようになった。
しかし、とにかく六千人でもたいへんな数である。
大きな美しい声で上手(じょうず)にしゃべることが大切になってきたわけである。
雄弁の先生のソフィストに、高い授業料を払ってでも、弁論術を学ぼうとしたのは、そのためだった。
民会で民衆の心をとらえることができれば、自分の思うように国の政治をうごかすことは容易だった。
4 ソクラテスの裁判 top
アテネで民主政が徹底すると、治める者と治められる者のあいだに区別がなくなってしまい、役人は希望者のなかから、くじで定められた。
任期は一年で、同じ役に二度つくことはできなかった。
任期が長かったり、重任を認めると、同じ役に長くつき、そのために役得などを振りまわしたりするようになることを警戒したのだった。
役人はそのうえ、任期が終わると、執務報告を書かなくてはならなかった。
役人の仕事や、執務報告に不正があった場合には、市民ならだれでもそれを摘発して、告訴してよかった。
アテネには検事はいなかったから、不正なことを見つけた人はだれでも告訴できるようになっていたのである。
検事ばかりでなく、職業的な裁判官もひとりもいなかった。
裁判は陪審制だった。アテネの裁判制度はソロンがきめたと伝えられる。
陪審制といっても、今日アメリカで行なわれているような、七人から二十三人というような少数の陪審官が、法廷に列席するというようなものではなかった。
四、五百人が一法廷に列席し、重要な事件のときには二千人も列席した例がある。
こんなに多数の陪審官が裁判をするので、「民衆裁判」とよばれた。
ソクラテスの裁判は紀元前三九九年に行なわれたが、そのときの陪審官は五百人だった。
ソクラテスが法廷で、陪審官たちにした「弁論」(法廷でしたものそのままであるかは疑問があり、学者のあいだで異論がある)を、ソクラテスの弟子のプラトンが書きしるしたものが残っている。
それによると、ソクラテスを訴えたのは、メレトス、アニュトス、リュコンという三人の男だった。
メレトスは詩人、アニュトスは金持ちの皮なめし屋だった。
リュコンは職業的な「演説家」といわれるが、よくわからない。
彼らのソクラテスに対する訴状は、「彼はポリスの認める神々を認めず、別に新しい神霊的な行事をはじめた。また青年を腐敗させた。この二つの点で有罪であり、死刑に処すべきである」というものだった。
しかし実際は、これは表向きの理由で、ソクラテスを死刑にしたいと考えていた人々の理由は、もう少し別のものだった。
アテネは紀元前四三一年に、スパルタその他と「ペロポネソス戦争」とよばれる戦争をはじめた。
戦争は二十七年間もつづき、紀元前四〇四年アテネの敗戦に終わった。
スパルタは軍隊をアテネに駐在させ、圧力をかけ、アテネの民主政をやめさせ、わずか三十人の人に政治をやらせた。
ながく民主政の自由を享受(きょうじゅ)していたアテネ市民のなかには、民主政を支持して、三十人の寡頭政治に反対する者が多かった。
三十人は反対者をまたたくまに千五百人も死刑にした。
財産を没収されたり、国外追放された者もおおぜいいた。
そのため三十人は「暴君(タイラント)」とよばれ、彼らの政治は「恐怖政治」といわれた。
彼らの恐怖政治は、かえって反抗を強くし、民主派の人々は、アテネの外港ペイライエウスにたてこもって戦い、三十人の支配者を倒した。
しかし民主派と寡頭派にわかれたアテネの混乱はすぐにはおさまらなかったので、スパルタ王のパウサニアスがやって来て、調停をはかった。
その結果アテネはふたたび温和な民主政にかえることになり、反対派の寡頭派の者はアテネから離れて、エレウシスというところに別の国をつくることになった。
しかし寡頭派の人も、いざ別に国をつくることになってみるとたいへんなので、けっきょく民主派に妥協することになった。
寡頭派は民主派に妥協することにはなったが、かつて三十人が反対者をやたらに殺したように、民主派が自分たちを処刑してはたまらないので、過去の政治的立場は今後いっさいほじくらない、それを理由にしては人々を処刑しないという約束をした。
こういう約束で妥協はできたが、三十人の暴政にうらみを持っていた民主派の人々には、寡頭派の人がにくくてならなかった。 |

ソクラテス(大英博物館蔵)
500人の陪審員の民衆裁判で
死刑となった
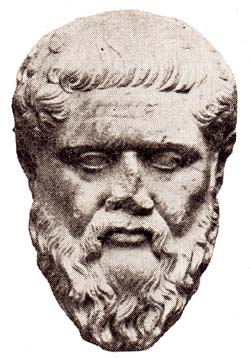
ソクラテスの弟子のプラトン
ソクラテスの裁判の経過を書き残している
|
ソクラテスもその憎い人の一人だった。
ソクソテスは寡頭主義的な考えを持っていたわけではなかったが、民主制度のわるい点も遠慮なくあばいた。
ことに役人をくじで定めることなどには反対した。
「息子の馬術の先生をきめようとする父親は、なるべく馬術のうまい人のなかから熱心にさがすくせに、ある意味では息子の先生より大事な国の運命をまかせる役人を、希望者のなかからくじで選んで平気でいるのはおかしい」こんないいかたで彼は攻撃した。
こういうことからソクラテスは反民主主義者ととられたのだった。
そのうえ、人々に大きな恐怖感を与えた「三十人」のなかには、クリティアスとカルミデスというソクラテスの弟子が二人もはいっていた。
「三十人」に対する恨みが、ソクラテスにふりかえられた。
ソクラテスを訴えたアニュトスは、「三十人」の支配した時代に一時財産を没収されて、国外追放されている。
したがって彼の恨みはとくに深かったわけである。
しかし、先の約束があるので、ソクラテスを反民主主義者として訴え、処刑するわけにはいかなかった。
そこで、二十四年も前に上演された『雲』のソクラテス批判が、訴訟の理由として借りられたのだった。
『雲』のなかではソクラテスは「ゼウスなぞいない。この世を支配しているのは『渦巻(デイノス)』だ」といっている。
ポリスの認める神々を信じないで、新しい神霊的なものを持ち出しているわけである。
それにペイディッピデスは父をなぐって、それは正当だと父親をいい負かしている。青年を腐敗させたわけである。
ソクラテスは『弁明』のなかで「自分は金をとって人を教えたことはない。自分には弟子はない」と自分がソフィストでないことを強調している。
ぼろを着てはだしでアテネを歩きまわっていたソクラテスは、たしかに授業料をとったりはしなかったろう。
また善や美など、絶対が存在することを信じていた。
したがって相対しかないと信じていたソフィストとは確かにちがう。
しかしプラトンの対話編のなかでソクラテスが、多くの人々と対話をして、賢いと思われていた人が、じつは無知であることをあばいたり、死は悪いものではなくて良いものであることを教えたりしている話し方には、当時の人々に彼をソフィストと思わせたのもむりはないと考えられるようなものが感じられる。
しかし『雲』が上演された当時には、人々はソクラテスのことを、そう真剣に考えていたわけではなかった。
多くのソフィストとはちがって、ソクラテスはアテネ生まれで、アテネから外に出たことはほとんどない生粋のアテネっ子だった。
そのため、劇を見物するアテネ人はソクラテスに親しい感じを持っていた。
ソフィストを材料にして笑う喜劇の主人公に、他のソフイストでなくソクラテスが選ばれたのは、そんなことからだったろう。
『雲』が上演されたときに、見物席にいたソクラテスは立ち上がり、舞台の上のソクラテスが自分に似ているかどうかを人々に比べさせた、という話が伝わっている。
こういう話があるように、ソクラテスも見物人も、事態を真剣には考えていなかった。
見物人は、喜劇作家がおもしろくゆがめたソフィスト流の会話を、笑ってきいていただけだったろう。
それに『雲』はそう好評ではなく、上演のコングールでは、ビリの三等で、作者をくやしがらせたほどだった。
彼がその後『雲』を改作して、再上演しようとしたことから、それはわかる。
しかし、『雲』の効果は案外にあった。
このごろもよくきかれる「近ごろの若者は生意気だ」という老人のいい方は、ギリシアの昔でも同じだった。
そういう感じ方に、『雲』の気分はぴったりだった。若い者は生意気だ。
へりくつをいう。へりくつを教えたソフィストが悪い。ソクラテスが悪い。
こういう考え方が、だんだんに多くの人々の心の奥に深く根をおろしてしまった。
メレトス、アニュトス、リュコンの三人がソクラテスを訴えたのは、『雲』の上演から二十年以上もたっていた。
しかし彼らは、ソクラテスを反民主主義者と訴えられないので、二十年のあいだに深く広く、人々のあいだにひろがっていた『雲』のソクラテス攻撃を、訴訟の理由として借りたのだった。
ソクラテスは法廷で、これをあばこうとした。
そして三十人の支配していたときには、自分もいのちがあぶなかったとか、自分には友人はあるが弟子はいないといっているのは、自分が反民主主義者でないことを証明するためだった。
彼の弁明をきいて五百人の陪審官は投票した。
原告のいうとおり有罪だとしたのは、二百八十一票だった。わずか三十一票が、ソクラテスの運命をきめた。
有罪だと判決された被告は、どういう処罰が自分の罪にふさわしいかを法廷でいうことが許されていたらしい。
「自分はあくまで罪はないと思うが、諸君が有罪だというから、判決に服そう。まあ罰金くらいが適当だと思う。
私はびんぼうだから、罰金を一ムナくらいしか払えない。
しかし友人たちが三十ムナくらいなら出してくれるというから、それくらいの罰金ではどうだろう」
ソクラテスが陪審官にこういうと、彼らはソクラテスのいい方はパカにしているとふんがいした。
二度目の投票では、三百六十一票と、大半の人が彼の死刑に賛成した。
こういう判決がおりてからも、ソクラテスの弟子たちは、ソクラテスに国外に逃げることをすすめ、牢番買収その他の費用を出そうとした。
しかしソクラテスは、「あくまでも自分は無罪だが、国の命じることには従わなくてはならない。国が誤って命令を出したときには、誤りを教えて、改めさせるようにしなければならないが、どうしても改めない場合には、誤った命令でも服さなくてはならない。なぜなら子は親に育ててもらった恩があるが、国がなくては、自分たちは存在しないのだから、親以上に恩がある」といって、弟子たちのすすめをしりぞけて、判決どおり死刑になった。
アテネの裁判はこのような民衆裁判だったので、法廷でも雄弁は大事だった。
うまく自分を弁護できる者は罪を免れることができた。そのため、法廷でする弁論を上手な人に書いてもらって、読む人もいた。
このために金をとって法廷弁論を書く職業的な雄弁家が、のちにはアテネに出てくる。
またおおぜいの陪審官がことをきめるため、ソクラテス事件の二度目の投票の際のように、気分や群集心理が作用した。
被告のなかにはこれを利用して、家族を法廷につれ出し、自分が処刑されると、家族たちがこまりますと、泣き落とし戦術を使う者さえあった。
フリュネという美人があるとき訴えられたことがあった。
雄弁家たちが彼女のために弁護してくれたが効果がなく、有罪になりそうになった。
そのときフリュネは法廷でパッと裸になった。
すると陪審官たちは、「こんな美しいからだに悪い心が宿っているはずはない」といって、彼女を無罪にしたという。
心とからだは一体だ、美しいからだには美しい心が宿っているというのは、ギリシア人の考え方で、我々とはちがう。
フリュネの話は、こういうギリシア人の考え方から出ているのだが、同時にアテネの法廷が気分で動きやすかったことを教えている。
こういう法廷のありかただったから、雄弁は大事だった。
したがって、ソフィストが大事にされるわけだった。
たくさんのポリスからアテネをめがけて、弁舌の巧みな人々が、集まって来たのも当然だった。
top
**************************************** |