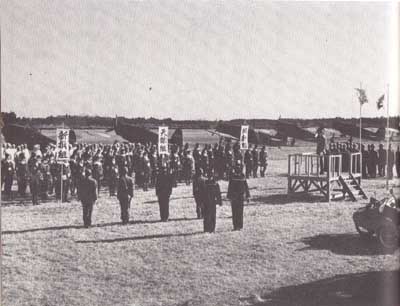|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14
12 紫電改、四国上空の凱歌
昭和二十年一月、初の紫電改部隊である三四三空か、松山で着々その形を整えていた頃「紫電」改は「紫電」二一型(N1K2-J)として制式採用になった。
「烈風」の遅れから、零戦にかわる次期主力戦闘機の本命として「紫電」改に期待をかけた海軍は、これより先の昭和十九年秋に、すでに大量生産計画をたてていた。
それによれば、川西の鳴尾、姫路両製作所はもとより、三菱水島製作所、昭和飛行機および愛知航空機、さらに呉の第十二大村の第二十一、厚木、高座など三つの海軍航空廠を含め八ヵ所で生産し、二十年夏には月産一〇〇〇機にしようという、大変な計画だった。
実際には十八年十二月一機、十九年六七機、二十年一月〜七月三三二機、合わせて四〇〇機しかつくられず、計画自体は無理もいいところだったが、反面、それほど「紫電」改への期待が大きかった、ということになろう。
1 ホープ「紫電」改、関東上空に善戦 top
松山に「紫電」改の量産機二一型が、しだいにそろいだした頃、横須賀軍港に近い追浜(おっぱま)飛行場には、空技廠所管の黄色く塗った増加試作機を含めて、十数機の「紫電」改があった。
ここには、横空の戦闘機隊長・指宿少佐、先任分隊長・塚本祐造大尉(のち伊藤忠航空機部)、それに横空審査部(十九年七月十日、空技廠飛行実験部は廃止された)の「紫電」改主任部員・山本重久大尉(前出)、昭和十九年十一月末にフィリピンから帰ったばかりの岩下邦雄大尉(のち大尉、野原産業株式会社社長)ら、いずれもそうそうたるパイロットたちがいた。
昭和二十年二月十七日、冷えこみの厳しい日だった。
飛行場の中央にある指揮所で指宿少佐、塚本大尉、岩下大尉らが警戒待機中、突如、空襲警報が発令された。
優秀なパイロットぞろいの横空戦闘機隊は、さすがに行動が早い。
すぐに近くの飛行機にとび乗って、どんどん上がってゆく。
岩下も、負けじと目の前にあった「紫電」改に乗り、列機三機をひきいて空中に上がったが「紫電」改は、これまで地上でコクピットをのぞいてみた程度で、乗ったのは初めてだった。 |

第701戦闘飛行隊長だった
岩下邦雄大尉
|
空技廠側でも、黄色の「紫電」改で山本大尉が増山上飛曹、平林一飛曹ら三機をひきいて緊急発進した。
雲が低く、局地的には雪がかなり降っていた。
この時、横須賀から上がったのは「紫電」改と「零戦」「雷電」あわせておよそ三〇機、厚木上空で編隊を組んで待ちかまえているところへ敵編隊が低空でとび込んできたからたまらない。
優位の態勢から、次々に攻撃開始、北は八王子上空から南は藤沢上空まで追いまくり、来襲したグラマンF6F「ヘルキャット」など四、五〇機の一梯団をほとんど撃墜してしまった。
山本編隊は、厚木上空で下方に「コルセア」、グラマン「アベンジャー」、F6Fなどを発見、高度をとって理想的な後上方攻撃の態勢から、下がっては上がり、下がっては上がる反復攻撃をくわえて、次々に撃墜したが、余りの猛烈な攻撃に敵は逃げることもできなかったらしい。
山本らの目ざましい活躍は、翌朝の新聞にのった。
岩下編隊も、同じような戦闘でF6F「ヘルキャット」を落としたが、岩下はなにしろ初めての「紫電」改だったので、脚の引込操作が不充分だったらしく、ロックがはずれて片脚が少し出たまま空戦をやったほど、その性能には余裕があったらしい。
また、塚本大尉の部下の武藤金義少尉(のち三四三空に転じ戦死)は、たった一機で二一機のグラマンに挑み、四機を撃墜するという放れ業をやってのけた。
この日、関東地区に来襲した敵機は延べ六〇〇機、陸海軍合わせて二七三機を撃墜したと言われるが、「紫電」改の強さをまざまざと見せつけたこの日の戦闘は、やがて来るべき三四三空の活躍の前ぶれとして、とかく沈みがちだった海軍戦闘機隊に、明るい希望をもたらした。
2 宿敵と対決のとき迫る top
一方、紫電改部隊の本命である松山の三四三空では、三月十日頃から警戒態勢に入り、戦闘機隊は迎撃待機を始めた。
関東地区を襲ったのち、いったん西カロリン諸島ウルシー泊地に戻って補給、整備をしていた敵機動部隊が、いつの間にかいなくなっているのが偵知されたからだ。
源田司令、中島副長、志賀飛行長らは、瀬戸内海西部に敵艦載機群が来襲した場合を想定して図上演習を何度もやり、慎重な迎撃計画を練り上げていた。
三月十三日、警戒警報が発令になって、四〇七飛行隊長・林喜重大尉を総指揮官として、四〇機の「紫電」改が出動したのを皮切りに、連日警戒飛行が続けられ、三月十八日、索敵に出た偵四の偵察機「彩雲」が、ついに土佐沖南方で敵機動部隊を発見した。
すぐに七〇一飛行隊長・鴛淵孝大尉を指揮官として、三個飛行隊七二機の全力出動となったが、この日は九州地方を襲っただけで、三四三空の守備範囲にはやって来ず、決戦は翌十九日にもちこされた。 |
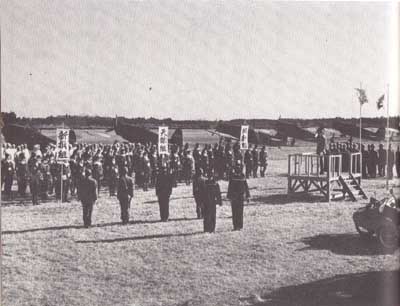
三四三空を再現した東宝映画「太平洋の翼」の一場面
|
明けて昭和二十年三月十九日早朝、螫備員たちはいつものように、はやくも受け持ちの飛行機に向った。
早春とは言え、冷えこみはひどく、オイルがかたくなってエンジンはまわらない。
それをバーナーであぶって暖めて始動する。なにしろ、むずかしいエンジンだ。
「一発でまわってくれよ」と祈るような気持でイナーシャ(起動用ハンドル)を回す。
未明の三時頃から各飛行隊の列線でエンジンの試運転が始まり、轟々たる爆音に人々は暁の夢を破られた。
午前五時、搭乗員全員集合。指揮所前に戦闘七〇一、戦闘四〇七、戦闘三〇一および偵四の各隊員が、マフラーで襟元をキリッとしめた飛行服姿で並んだ。
一段たかくなった指揮所から、源田司令は簡明な訓示をあたえた。
「今朝、敵機動部隊の来襲は必至である。わが剣部隊は、この敵機に痛撃をあたえる考えである。
目標は、あくまでも敵戦闘機である。今日は、態勢挽回の第一歩だ。徹底的に撃墜せよ」
このあと、副長、飛行長から敵情説明やこまかい注意があって、各隊員はそれぞれの待機列線に向った。
午前五時四十五分、ひときわたかい爆音がとどろき、三つの機影が南の空に消えた。
四国南部の足摺岬と室戸岬の間を哨戒し、敵飛行機隊を発見すればただちにこれに触接、敵情報告を送り続ける任務をおびた空の忍者、偵四の「彩雲」偵察機だった。
続いて八機の「紫電」が出発線に向かって走りだした。
これらの「紫電」は「紫電」改がそろうまでの訓練用として使われていたものだが、この日は飛行場上空の制空と、本隊が飛び上がったあとは上空掩護(えんご)の大任を負って戦列に加わったのだ。
山田良市大尉(前出、空幕長)を指揮官とする七〇一飛行隊の四機、市村吾郎大尉の指揮する四〇七飛行隊の四機だが、列線を出ようとした山田大尉機の右主脚がポッキリ折れた。
この頃、脚回転支柱の材料がわるくて、折損事故がしばしば発生していた。
不吉な! だが、闘志満々の山田大尉は少しも意に介せず、四番機の搭乗員をおろして乗りかえ、結局、七機がまだうす暗い飛行場を本隊に先行して飛び立った。 |

川西の鳴尾工場と姫路工場と、松山の紫電改の基地三四三空
|
一方、地上の各戦闘機隊の待機所では、むやみに煙草をふかす者、落下傘バンドを付けたり外したりする者など、搭乗員たちが思い思いのスタイルで出動命令を待つ。
飛び上がる前の気持は、なんとなく落ちつかないものだ。
特に初陣の若い搭乗員には、つらい時間である。
はたして今日、生きて地上に戻れるだろうか。
緊張と不安が入りまじって、間がもてないのである。
山田、市村両大尉らの紫電制空隊七機が高度を取り終った頃、東の地平線の彼方、紫色にたなびく断雲を割って朝日が姿をあらわし、地上には、松山基地の待機列線にならぶ数十機の「紫電」改の姿が、うっすらと見え始めた。
こうしているうちにも、基地はしだいに明けわたり、戦機は刻々と熟す。
3 「ヘルキャット」を迎え撃つ top
「敵機動部隊見ゆ、室戸岬の南三〇カイリ」
午前六時五十分、先発隊にやや遅れて出発した偵四の「彩雲」四番機から暗号の第一電が入った。
やっぱりきたか! 敵は連合艦隊のいる呉軍港をねらっているのだ。
ただちに「全飛行隊即時待機」が下令され、エンジンが一斉に始動された。
続いて、第二電。
「敵戦爆連合大編隊、豊後水道を北上中、高度三〇〇〇メートル」
偵察機と足摺岬のレーダーとの両方からだ。
「全機発進!」
源田司令の声が鋭くとび、志賀飛行長の白旗がサッと振り下ろされると、空中総指揮官・鴛淵大尉機を先頭に各隊は発進を開始した。
飛行場はプロペラ後流の巻起す砂煙におおわれ、その中を「紫電」改がまるで突進する犀(さい)の群のように全速で疾走する。
鴛淵大尉の七〇一飛行隊一六機、林大尉の四〇七飛行隊一七機、菅野大尉の三〇一飛行隊二一機の順に、北に向けて編隊のままあがった。
戦闘機隊を誘導のため「彩雲」一機も、続いて離陸した。
この間に第三電が入った。
「さらに敵三個編隊見ゆ。戦爆連合約一〇〇機北上中、高度四〇〇〇メートル、地点高知の西二〇カイリ」
続々入る無線によって敵編隊の位置が明確にされ、伝声管を通じて報告された。
司令室からはただちに上空各隊にも通報された。
七〇一、四〇七両飛行隊は、左に大きく旋回しながら高度をとったが、後続の菅野大尉の三〇一飛行隊は、やや遅れた。
偵察機からの敵発見の報は、機上電話によって上空哨戒中の紫電隊七機にもつたえられ、続いて
「サクラ、サクラ(飛行機隊の秘匿符号)全機ただちに発進せよ」
「ハヤテ、ハヤテ(上空直掩隊の秘匿符号)本隊に合流せよ」
と、矢継ぎばやの指令が発せられる。
充分な高度をとるため、会敵をさけてひとまず予想戦闘空域を遠ざかった本隊に合流すべく、上空哨戒の任を解かれた山田、市村両編隊は、バンクを合図に分かれて、それぞれの本隊を追った。
高度五〇〇〇で飛ぶ紫電隊が、断雲の合間に約一〇〇〇メートルほど下方を西進する本隊を発見した時、さらに下方をひしめき合うような密集隊形で北上する約三〇機の編隊が目に入った。
敵だ!
こちら四機の密集編隊は、ただちに二機ずつのペアに分かれ、散開した戦闘隊形をとった。
松山基地の南西約一〇カイリの地点、敵はまだこちらに気づいていないようだ。
以下、戦闘七〇一飛行隊先任分隊長・山田良市大尉の記述による。
《……「おしぶち一番、おしぶち一番、前方に敵機発見、高度四〇〇〇」
私は、鴛淵隊長に呼びかけた。
「紫電改」隊は敵よりもやや高度がたかく、われに有利な対勢で戦闘の火ぶたは切って落された。
敵は艦載機グラマンF6F「ヘルキャット」だ。
鴛淵隊長は、間合いをとりながら回りこむように編隊を誘導し、頃合いを見てサッと切りこんだ。
敵味方の編隊がまともにぶつかったと見るや、はやくも一機が火達磨になって墜ちた。
続いてまた一機、黒煙を吐きながら海中に突っ込んでいった。
味方編隊の後上方に占位している私には、敵味方の識別が判然としないので気になる。
私の任務は、味方「紫電改」隊の上空掩護であったので、空中戦闘圈直上まで急いだ。……
敵味方入り乱れての巴(ともえ)戦が展開されている。
よく見ると、「紫電」改がF6F「ヘルキャット」を追いつめている。
戦闘圈が徐々に拡大するにつれて、F6Fが戦闘圈外にはみ出ていく。
不利な戦闘で、苦しまぎれにはみ出したF6Fが、戦闘圈からいったん離脱すれば、有利な態勢に立て直して来襲する恐れがある。
これを叩き潰すのが、わが任務だと直感し、F6F四機編隊の後上方から攻撃に入る。……
グッと腹に力を入れ、敵の真うしろ一〇〇メートルに接近する。まだ敵は気づいていない。
さらに、照準器も不必要な距離まで接近、スロットル・レバーについている発射ボタンを押す。
瞬時にF6Fが火を吹いた。さらに一連射、尾翼が吹っとんだ。
頑丈そうなF6Fもダラリと傾く。さすが二〇ミリ機銃の威力は大きい。
二番機も一機を仕止めたが、機銃を発射してF6F二機が燃えて傾くまで、ものの二秒とかかっていない。
この間F6Fの編隊長機は、無傷の二機で急上昇旋回、機首をこちらに向けてくる。捨て身の思い切った操縦だ。
こちらは接近時、せっかくの優速を殺しすぎた。
また、乗機も旋回性能の悪い「紫電」なので、深入りをさけて旋回、外側上方に引き上げてやっと離脱、次のはみ出したF6Fを求めて、再び戦闘に加わった》
(雑誌(航空ファン)所載ならびに談話) |
4 松山上空、激戦続く top
続いて上がった戦闘四〇七飛行隊は、どうだったか。
以下、同飛行隊員・小高登貫上飛曹の記述ならびに談話による。
《……がっちりと組んだ大編隊は、松山市上空の東方に位置し、目を皿のようにして敵機の見張りを続けた。
「アッー 敵機発見!」
おびただしいF6F「ヘルキャット」の大群が、松山市を一呑みにするような形で、私たちより五〇〇から一〇〇〇メートル下を、広がって進んでいる。
敵の大編隊と四つに組んで戦うのは、ラバウル以来、初めてのことだ。
私はとたんに、ブルブルッと武者ぶるいがした。
どんなベテランでも、敵の大編隊を前にしたときには、ガクガクふるえる。
何でこんなに足が動くのか、と不思議なくらいだ。
死の予告に対する本能的な恐怖か、あるいは、これから始まろうとする闘争への筋肉の自然反射運動なのか。
しかし、これがおさまった時、本当の闘志がわいてくる。
「突撃開始!」
りんとした林隊長の声が入った。
「りょう、りょう」(了解の意味)
機上電話は混乱を防ぐため飛行隊長、中隊長、小隊長らだけが「送」、あとは「受」の位置に切りかえてある。
いよいよ戦闘開始だ。
一斉に空戦フラップを空(自動)に切りかえる。
178
ただし、ベテランは手動のままで、使いたい時だけ使えるようにしておく。
これまで整然としていた編隊がくずれ、にわかに生き物のように動きだした。
各四機の区隊は二機二機の戦闘隊形となり、先頭小隊がまず猛然と突っこんだ。
ダダダダダダダー。
灰色の雲を背にして、「紫電」改の翼から射弾が、ツーッと伸びていくのがありありと見える。
敵にとっては恐るべき火箭(かせん)の束なのだが。
と、見るまにF6Fが一機、二機と墜ちていく。
まさに紫電一閃、名刀の冴えにも似た鮮やかな攻撃だ。
このとき私たちの小隊はまだ上空にいたが、やっと番がまわってきた。
相手にとって不足なしのF6F四機である。
場所もすでに松山南方上空に移っていた。
小隊は、すばやく切り返した。
真下のF6Fの青黒い翼には、米軍の星のマークが、くっきりと描かれている。
後上方からの攻撃で、高度差は一〇〇〇メートルある。F6Fの一機を照準器に、ピタリと入れた。
距離八〇〇、五〇〇、三〇〇、二〇〇、私は思いきり発射レバーをにぎった。
弾丸が吸いこまれるように敵機に命中する。 やったぞ!
思わず叫んだその瞬間、F6Fは白煙をふいて横にねじれながら、松山南東の山中に突っこんでいった。
と、横を見れば、区隊長の本田稔少尉も、確実に一機を撃墜したらしい。
火をふいて山中に突っこんで行くのが見られた。
私は上昇のまま、次のグラマンを探しもとめた。
すると、私の目にめずらしくもあり、またなつかしいF4U「コルセア」の編隊が後続してくるのが望見された。
即座に切り返し急反転の体勢でやや斜後方からF4Uの一機に食いつき、射程二〇メートルまで接近して機銃を連射したが、敵は私の近寄ったのに全く気づかなかったらしい。
水平飛行のまま命中と同時に黒煙を吹いた。また一機撃墜だ。
上昇しながら、次の敵影を探し求めたが、後方には一機の敵影も見あたらない。
どうやら私たちの小隊が攻撃したのは、敵編隊の最後尾だったらしい》
(小高登貫『わが翼いまだ燃えず』甲陽書房刊より) |
5 米艦載機を大量撃墜 top
最後に離陸した菅野大尉の三〇一飛行隊は上昇中、はやくも「敵機三〇、飛行場上空に向かう」の電話を聞いた。
このまま先頭編隊に続いて左旋回しては、まともに敵とぶつかり、劣位戦となってやられるのが“おち”とみた菅野隊長は、思い切りよく他隊と別れて右旋回に移った。
この間に敵編隊と鴛淵隊、林隊との空戦が始まり、菅野隊はまんまと上昇中に会敵というピンチを脱することができた。
以下、戦闘三〇一飛行隊・笠井智一上飛曹の談話による。
《わが戦闘三〇一飛行隊は呉上空で集合を終え、戦闘隊形をとった。
「紫電」改の無線電話は、空七号になってから感度がよくなり、敵情が的確に入ってくる。
呉の手前、瀬戸内海上空で敵戦爆連合の大編隊をつかまえた。
どうやら敵の第二波らしい。 いよいよ決戦の時だ。
周囲を見回すと、酸素マスクをつけたものものしい顔が、風防ガラスの中からうなずいている。
隊長機がサッと降下に移り、小隊ごとに攻撃開始。
「紫電」改は、全く素晴らしかった。
一航過でグラマンF6Fと力ーチスSB2C爆撃機二〇機を一挙に撃墜した。
あわてた敵編隊の攻撃機は、爆弾を全部、瀬戸内海に落として引き返し始めた。
編隊空戦だから、個人戦果というのは意味ないが、菅野大尉の三番機だった甲飛九期の加藤勝衛上飛曹は九機落とした》 |

カーチスSB2-C「ヘルダイバー」急降下爆撃機
|
|
菅野隊長の勇戦も見事だった。
敵の大群の中に躍り込んだ菅野機は、敵弾で右翼の補助翼(エルロン)を三分の一ほど吹っとばされてしまったが、それでも最後まで戦闘をやめず三機を撃墜した。
だが、基地に帰投する直前に、新手のグラマンにぶつかり、火災を起してしまった。
顔面に火傷を負いながらも落下傘で脱出し、降下した近くの農家でもらった赤飯を持って帰ってきた。
顔が焼かれてペロリと皮がむけ、真赤な顔をしていた菅野を見て、敵と思った付近の農家の人たちが鎌や鍬を持って追いかけてきたという。
一方、地上からはこの戦闘をどのように見ていたか、戦闘三〇一飛行隊先任搭乗員の堀光雄上飛曹(戦後、三上と改姓、東京在住)は語る。
《私はこの日は、二直(二回目の搭乗勤務)になっていたので、一直の五四機が飛び立って間もなく、指揮所前に出て見張用双眼鏡をのぞきこんだ。
すると、視野内にずんぐりした格好の単発機が飛び込んできた。
「あっ、グラマンだ!」
、思わず私の口から大声が飛び出した。
約三〇機の敵は、整然として編隊のまま飛行場に向かってくる。高度三〇〇〇、距離六〇〇〇。
電話連絡がとれたのか、近くにいた林大尉の四〇七飛行隊が全速で飛行場に引き返してきた。
高度四〇〇〇メートルにいる味方一七機の動きを地上では固唾(かたず)をのんで見ている。
この空戦に参加できないのが、私には残念でたまらない。
敵味方の編隊は、飛行場を少しはずれた海上で真正面からぶつかろうとする。ほとんど同高度――。
両編隊がバリカンの歯のように重なったと思うと、はや一機が火を吐いて墜ちた。
それは胴のつまった感じの飛行機――しめた! 墜ちるのはF6Fだ。
「やった! やった!」と地上の指揮所のあちこちで興奮した声があがった。
この戦いは「紫電」の勝ちになりそうだ……。
我々の上空では、敵味方四十数機が、ワンワン入り乱れての空中戦が始まった。
またF6Fが一機、黒煙を吐いて墜ちていく。
そのうち、空戦のうずは、しだいに山の方に移動していった。
タン、タン、タン……。
上空に見とれていた我々は、背後の銃撃の音に驚いて振り返ると、今しも超低空の敵十数機が、海岸に並べた囮(おとり)機に向かって機銃掃射の姿勢をとっている。
これは動けなくなったのや、訓練中に壊したものなどを、あたかも健在な機体のように見せかけて並べ、その周囲には機銃陣地が配置されていたのだ。
敵はグラマンF6Fと、特徴ある逆ガル翼のシコルスキーF4U(コルセア)だ。
まんまとこちらの欺瞞策(ぎまんさく)にひっかかり、一列に並んだ囮機をパラパラ銃撃した。
機を見て私は、防空壕に待避した》 |
敵の第一波と剣部隊との組織的な戦闘は十数分で終り、あとは後続の敵編隊との乱戦になった。
「只今、基地空襲中、滞空機は他の飛行場に着陸せよ」
地上からの電話がしきりに叫んでいるが、空襲の合間をぬって降りてくるもの、弾薬、燃料を補給してあわただしく第二撃に上がっていくもの、基地はまさに戦場だった。
この頃、瀬戸内海の海面には、赤、黄などの絵具をとかしたように色鮮やかな波紋が、無数に広がっていた。
赤、黄は敵機の、茶色のは味方機が海中に墜落したあとだった。
敵は洋上不時着の際の発見を容易にするために、特殊な顔料をまいたものらしく、圧倒的に多いその数が、「紫電改」部隊の勝利を決定づけていた。
この日の総合戦果は、F6FおよびF4U合わせて四八機、SB2C(力-チス「ヘルダイバー」)四機、このほか地上砲火によって撃墜したF4U五機を含めると、全部で五七機に達し、その後、判明したものもあって、この数字はさらに増えた。
夕方、通信隊が傍受した敵の無電は、次のように報じていたという。
「旗艦のグラマン戦闘機隊は全滅せり、日本海軍に新型戦闘機あらわる」
この日、主として「紫電」改の犠牲になったのは、米第58機動部隊の 「ホーネット」「エセックス」など数隻の空母艦載機で、特に「ホーネット」のF6F「ヘルキャット」隊の損害が大きかったようだ。
6 貴重な犠牲避けられず top
F6F「ヘルキャット」に勝つことのできる戦闘機と戦闘機隊が、やっと出現したわけだが、決して完勝したわけではない。
日本側にも自爆・未帰還一三機、地上炎上五機のほか若干の不時着機を出した。
いかに精強「紫電」改をもってしても、圧倒的な数の優位の前には、これだけの損害はさけられなかったのだ。
数と同時に、もう一つの問題は練成期間だった。
十九年末に二代目三四三空が創隊され、実質的に部隊としてまとまったのが二十年一月末たった。
もちろん、鴛淵、林、菅野の各飛行隊長をはじめ、各編隊の核心となるパイロットには歴戦のベテランがかなり配されていたが、その下の隊員となると技量は優秀でも実戦の未経験者が多く、また、近代的な編隊空戦に適合させるには、かなりの訓練期間が必要だった。
司令の源田大佐は、もとよりそんなことは百も承知で、その目標を五月中旬頃とし、充分な練成ができるまでは第一線の戦闘に流用しないつもりだった。
しかし、戦局がそれを許さず、予定より二ヵ月も早く実戦に投入することになったのである。
182
米軍の例をみると、一九四三年(昭和十八年)初め空母「エセックス」に配属されたF6F-3「ヘルキャット」は、実に七ヵ月以上も「エセックス」艦上で訓練を重ねてから、最初の実戦であるギルバート諸島攻撃に参加している。
このように新しい部隊編成、特に機種が新しい場合は、なおさら訓練に時間をかけなければならないが、切迫した日本側の事情では不可能なことであった。
一口に「搭乗員の技量未熟」と言ってしまえばそれまでだが、未熟を脱し切れないうちに実戦に投入しなければならなかったと頃に問題があったのだ。
この日の戦闘での戦死者は、次の一六名であった。
少佐・松崎国雄、嶋幸三
大尉・渡部幸博、井上伊三郎、高田満
飛曹長・影浦博、中島満夫、日光安治、遠藤稔、石川菊一、遠藤司郎
上飛曹・竹島治彦、久保典儀
一飛曹・信田時正
二飛曹・和木逸夫、中谷美弘、斉木世一
(いずれも階級は戦死後進級のもの)
うち三名は偵察第四飛行隊の隊員だった。
7 壮烈、偵察機の最期 top
この三名、すなわち偵察員・高田満少尉(機長)、操縦員・遠藤稔上飛曹、電信員・影浦博上飛曹(いずれも戦死前の階級)は、敵発見の第一電を発した偵四の「彩雲」偵察隊四号機の搭乗員で、彼らの最期は戦闘機隊に劣らぬ壮烈なものだった。
高田機は敵編隊と触接をたもち、次々に敵の動きを打電して、味方戦闘機隊を有利な態勢に導くきっかけをつくったが、途中から「誉」テンジンが不調になったらしい。
偵四隊員として、このとき地上の司令室の電信機のそばにいた田中光也飛行兵曹長(のち少尉、戦後海上自衛隊二等海佐、日本ブラインダーサービス)は、刻々と高田機から送られてくる無電に耳をそばだてていた。
すると七時四十分頃、突然それまでとは違った「ク連送」が送られてきた。
それは「われ空戦中」を意味する緊急電だったのだ。
《敵戦闘機と交戦中だ! 壕内はシーンとなった。誰かが「遠藤がんばれ!」と怒鳴った。
みな、固唾(かたず)をのんで電信機をにらんでいる。
むらがる敵を相手に、単機でたち向かう「彩雲」の勇ましい姿が、目の前にちらつく。
七時四十三分。
「ク運送」につづき、すぐに「われ突入す」。あとは「− ――」の長符。
サッと緊張がみなぎる。五秒くらい経ったろうか。プツリと無電が切れた。
「やったか!」
ついに体当たりして自爆したのだ。搭乗員三人の顔が、私の脳裏を走馬灯のように走り去った。
―二日後、高知憲兵隊からの連絡により、同機の調査のため高知県東津野村へ向かった。
午後九時、海抜七〇〇メートルの同村新田部落についた。
村民から当時の模様を聞き、また現場を調査した結果、四つの峰にわたって敵味方の機体やエンジンが四散し、激突の激しさを物語っていた。
敵戦闘機の集中砲火を浴び、敵編隊よりの離脱困難とみるや、傷ついた愛機を操縦し、最後まで敵情を報告し続けながら反転して敵機に体当たりし、余勢をかって、さらに他の一機にも体当たりを敢行して、自爆を遂げたのだった》
(雑誌(丸)所載) |
高田機の壮烈な奮戦の模様は地上からも望見でき、当時の感銘をいまだに忘れ得ぬ人々によって、最近、自爆のあとに記念碑が建てられた。
「彩雲」の車輪一個が残されているという。
数日後、三四三空の、この戦果に対して連合艦隊司令長官から、次のような部隊感状が授与され、全員を前に源田司令によって読み上げられた。
昭和二十年三月十九日、敵機動部隊艦上機の主力をもって内海西部方面に来襲するや、これを松山基地に邀撃し、機略に富む戦闘指導と尖鋭果敢なる戦闘動作とに依り、忽ちにして敵機六十余機を撃墜し、全軍の士気を昂揚せるは、その功績顕著なり。
依って茲に感状を授与す。
昭和二十年三月二十四日 連合艦隊司令長官 豊田 副武 |
また、源田司令も「紫電」改をつくった川西航空機に感謝電報を送り、資材不足で生産があがらず意気消沈ぎみだった工場にも、久しぶりに歓声があがった。
top
**************************************** |