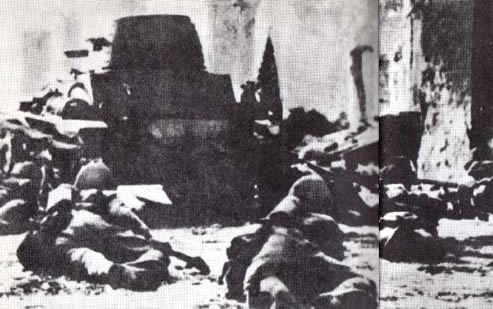|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
7 バターン半島へ撤退
|

マニラに向けて進軍する日本軍自転車部隊
|
ラモン湾に根拠をかまえた日本軍の攻撃方式――第一日目の空襲によって開始される――の概要が、極東米陸軍にもしだいに明らかになってきた。
1 バターン半島への撤退も考慮 top
日本軍の地上部隊の主力は、マッカーサー軍をハサミ撃ちにするため、南北からマニラにむけて進撃をつづけていた。
防御軍は、両方面からくる日本軍と、中央平原の無防備地帯で、戦闘をまじえなければならないだろう。
このことは、日本軍の戦略計画の骨幹でもあった。計画によると、本間軍司令官は、五〇日以内にフィリピンで決定的勝利をおさめることになっている。
それは、その後の東南アジア進攻に、第14軍をつかうことになっていたからである。 |

マニラ占領をめざし、戦闘のあいまをぬって進撃する日本軍自転車部隊
|
レガスピ上陸が遂行された十二月十二日、マッカーサーはケソンに、はやくもバターン半島への後退について語っていた。圧倒的に優勢な日本軍が上陸してきた場合、防御軍を諸島に分散するよりも、バターン半島に集結させたほうがよい、分散すれば日本軍に一掃されるだけである、というのがマッカーサーの意見だった。
バターン半島へ移動するとなれば、政府、アメリカ高等弁務官フランシス・セイヤーの事務所、および極東米陸軍司令部はコレヒドールにおかれる。
コレヒドールはマニラ湾内の有名な要塞島で、将兵たちはその難攻不落を信じて「ロック(岩窟)」とよんでいた。
これは、有名な「ジブラルタルの岩窟」を念頭においていることはいうまでもない。
ケソン大統領はまた、マッカーサーから「もし実際に、このような処置が必要となった場合には、マニラの無防備都市宣言を、四時間まえに通告して、日本軍にあけわたすであろう」といいわたされたのである。
典型的なフィリピン人らしい小柄な体格、ふとってはいるか、機敏で知的な眼をしたこのフィリピン大統領は、この話をきいて恐怖にかられ、「これは最悪の場合を想定しているにすぎない」とマッカーサーがいくらいっても、彼のふるえはとまらなかった。
ケソンの懸念もわからないことはない。四〇年以上にわたり、彼は国民の自由の代弁者であった。
あと一、二年しかもたないとおもわれる肺結核をわずらい、ルーズベルトと同じようにいつも車イスに乗っているいまの彼にとって、それは、高価な代償をはらって手にいれたフィリピン人の自由が、もろくもくずれさることのように思われた。
2 “オレンジ3”作戦に逆戻り top
マッカーサーが、バターン半島への移動になんら積極的な行動をとらなかったのは、おそらくケソンの反対があったからであろう。
十二月二十二日に日本軍主力部隊が上陸したあとも、指令に変化はみられず、マニラはいぜんとして、極東米陸軍司令部をはじめ、政府、行政の中心地であった。
しかし、ワシントンのマーシャルにあてたマッカーサーの至急報では、移動が必要かもしれないとのべている。
この報告では、日本軍の上陸兵力がいちじるしく誇大報告されていて、七〇〜八〇隻の輸送船が動員され、およそ八〜一〇万の将兵が上陸したとされていた。
それにたいし、ルソンには四万人の軍隊しかいない、と味方の兵力については過小評価していたが、実際の兵員総数は、七万五〇〇〇から八万をくだることはありえず、日本軍の兵力も、四万三〇〇〇をこえてはいなかったのだ。
マッカーサーが、事実を自分に都合よくつくりかえたのには理由がある。
“オレンジ3”作戦にもどろうとしていたのだ。
この作戦は、彼自身がとりさげたもので、それはフィリピンの軍隊が敵よりはるかに弱体である場合を想定していた。
マッカーサーは、いまや前任者の誰一人考えられなかったほどの大兵力をもっていたにもかかわらず、“オレンジ3”作戦にもどろうとしていたのである。
マッカーサーは、バターン半島をまもり、コレヒドールを堅持したい、とマーシャルに申請した。
この計画を認めた参謀総長は、援軍の派遣にはできるかぎりの努力をすると約束した。
だが、マーシャルの意図が、マッカーサーを元気づけるだけであったのは明らかである。
日本軍に制海、制空権をにぎられている以上、とおくからわざわざ危険をおかして海軍を派遣することなどありえなかった。 |

バターン半島につくられた防御線:防御軍は、この背後まで後退せざるをえなかった
|
そのかわりマーシャルは、オーストラリアとジャワを経由するフィリピンむけ兵站線を設置するようとりはからい、「費用をおしまない」よう指令した。
オーストラリア駐在アメリカ軍将校が、そのための船舶をもとめる交渉をおこなったのは事実である。
とはいっても、このような方法でもたらされる増援は、ほんのわずかなものにすぎず、マッカーサーが考えていたような、あふれんばかりの補給と訓練部隊をもたらすことがないのは、はっきりしていた。
増援のこないことがわかったマッカーサーは、ただちに海軍の小心さを非難した。
3 コレヒドールに司令部を移転 top
十二月二十四日、日本軍がロサリオに到着すると、マッカーサーはおくればせながら、バターン半島への移動計画を実行する決心をした。
フィリピン人の士気がおとろえるのを懸念して、それまで退却凖備にはいっさい手をつけていなかったのである。
当時半島にあった物資は、“WPO3”作戦にそなえて緊急にあつめたものだが、それほどの集積量ではなかった。
弾薬三〇万ガロンの石油、潤滑油、グリースなどで、そのほか缶詰の肉や魚もあった。
東海岸のリマイには、マッカーサーによって陸軍病院も建設されていた。
十二月二十四日、ウェーンライトは、アグノ川南方への後退をもとめてきた。
この要請でマッカーサーは、最終的な決意をすることになった。
その日、“WP03”作戦の実施が、全アメリカ軍指揮官に簡単に知らされた。
翌朝、極東米陸軍参謀会議の席上で、サザランドが司令部のコレヒドール移転を発表した。
行動にうつすのがおそかったため、もちだしを許可された荷物は、一人につき自分の野戦装備とスーツケースか寝具一個だけとされた。
同じ日の午後、ケソンと高等弁務官セイヤーは、フェリーでコレヒドールに渡った。
|

日本軍の攻撃をうけた米巡洋艦「マーブルヘッド」

パターン半島援護のために、マニラ湾に待機している米補給艦「カノバス」
|

米潜水艦「シャーク」:ハート海軍大将は
この舟に搭乗して、フィリピンから退避した
|
海軍司令部では、ハート海軍大将にマニラ湾に二隻のこっていた駆逐艦を、ジャワヘむけるよう指令をだした。
そこで「マーブルヘッド」に乗船していたウィリアム・A・グラスフォード海軍少将に、至急極東艦隊を再編成させようとしたのである。
ハート自身はその二日後、潜水艦「シャーク」でジャワへ出発し、マニラ湾には補給艦「カノパス」と機雷敷設艦、砲艦、魚雷艇のわずかだけが残され、ロックウェル海軍大将の手にゆだねられた。
それは、陸軍のバターン半島防衛の援護にあたることになっていた。
マニラ市内は、せまりくる凶運を感じて、重苦しい空気がたちこめていた。
いまや避難に一刻の猶予もならないため、あつめられるかぎりの船舶、ハシケが徴用され、こうこうたる月光の下で、バターン半島とコレヒドール島のあいだを往復した。
破壊班によって、日本軍が使用できると思われるものはことごとく打ちこわされ、市内における士気喪失はその頂点にたっした。
何百万ガロンにものぼる燃料が焼きつくされ、臨時燃料集積場から立ちのぼる黒煙が、マニラ全市をおおった。
翌日は、悲しみに沈んだクリスマスとなった。
朝、日本機が飛来してビラをまき、旅客列車を銃撃して数人の死傷者をだした。 |

W・A・グラスフォード海軍少将
|
4 六ヵ月の防御戦にそなえる top
マニラでの軍事行動がしだいにおとろえてゆくのと反対に、バターン半島では、日ごとに活気をおびてきつつあった。
防御戦がながびくのを予想して、軍隊と市民によって森の中に補給廠がつくられ、リマイ、ラマオ、カブカーベンには埠頭(ふとう)が建設されて、道路網も改善された。
流れがあるところには製粉所と屠殺場が建設され、製塩のための塩田もつくられ、漁場も整備された。
物資はひきつづきもちこまれて、クリスマスのおわるころまでには、四八時間にわたる努力のかいがあって、バターン半島は、すくなくとも必要不可欠の物資だけで、六ヵ月の攻囲にたえられるであろう、と思われるほどになった。
もちろん、まだ手にはいらない物資や、不足している物資があったのはいうまでもない。
軍隊も到着しつつあった。
二十四日には、わずかにフィリピン師団と臨時航空連隊しか、この半島にいなかったが、他の部隊が到着したので、新しい防御線が構成され、将兵は土木作業にとりかかった。
いままでバターン防御隊といわれていた部隊は、ウェーンライトの到着とともに再編成されて、西部地区を担任することになり、第1フィリピン軍団とよばれることになった。
また、東部地区にある諸隊は第2フィリピン軍団となって、パーカー陸軍大将の指揮下にはいった。
しかし、現在全島にわたって分散配置されているアメリカとフィリピンの軍隊が、日本軍のハサミ撃ちにあうまえにバターン半島に集結しなかったなら、この準備はなんの役にもたたなくなってしまう。
このカギになるのは、7号道路の確保である。
この道路は、サンフェルナンドの南、パムパンガ川をわたるカルムピット橋(実際は一対の橋である)でマニラ郊外からくる3号道路から分岐して、北西の方向にのびている。
南ルソン部隊は、この道路ぞいに退却するはずであった。
橋から7号道路にそってバターン半島にはいるには、さらに一六キロ北上しなければならない。
ということは、北ルソン部隊は、南ルソン部隊が無事半島に到着するまで、なにがなんでも日本軍をサンフェルナンドとカルムピット橋によせつけないようにしなければならない。 |
 |
もしそれに失敗すれば、マッカーサーはたよりとする防衛力の半分を失うことになる。
この退却を援護するのは、ウェーンライトの北ルソン部隊で、南ルソン部隊の無事な撤退をたしかめるまで、持久戦闘をつづけなければならない。
ウェーンライトは、中央平原の五つの防御線で日本軍を阻止するように命じられていた。
5 マニラの無防備都市を宣言 top
これらの防御線が設定されたのは戦前で、防御に適した自然の地形をあますところなく利用している。
各防御線相互の距離は、一晩で到達できるものである。
両翼はいずれも高地になっていて、マニラヘの主要二幹線である3号および5号道路を援護していた。
これらの防御線を維持するため、マッカーサーは、ウェーバーの臨時戦車大隊から、その大半を出動させた。
作戦は、すべてが非常にこみいって複雑であり、関係者には正確なタイミングと命がけの勇気が要求されていた。
失敗すれば、バターン半島防衛計画全体が崩壊してしまうのだ。 |
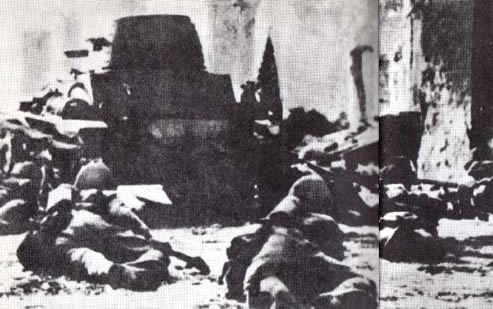
歩兵部隊に援護されながら、用心ぶかくマニラ市内へはいる日本軍戦車
|
残されているもう一つの主要な問題は、南部にある兵力をかぎられた時間内に、いかにしてバターン半島へ移動させるかであった。
これは、マッカーサーの前任者の一人によって、手段が講じられていた。
大部隊を緊急に移動させるための輸送手段の不足をみこし、この前任者は、ルソン島に運行路線をもつ商業バス会社の利用を考えた。
そして会社の従業員を、軍隊組織に準じて、臨時自動車輸送数個大隊に編成がえした。
一般市民は交通の足をうばわれることになったが、これら輸送諸大隊は、陸軍のトラックや自動車にまじって、物資、装備品、弾薬、医薬補給品、人員を、バターン半島ヘピストン輸送するため、夜を日についで活躍したのである。
あの南方人特有のけばけばしい色をぬったバスは、異様な光景であったが……。
十二月二十七日、マッカーサーは、マニラを公式に無防備都市として宣言した。
ワシントンとの協議のもとに作成された声明文は、新聞とマニラのラジオを通じて発表された。
その日から、マニラの灯火管制が解除された。
しかし、声明発表でおわると思われた日本軍の爆撃はやまなかった。
気やすめ程度だったとはいえ、日本機の低空飛行を妨害していた高射砲がなくなったのをよいことに、日本軍は手あたりしだいに爆撃した。
行政庁、サン・ホアン・デ・ラトラン大学、サンド・ドミンゴ教会、サンタ・ローザ大学、サンタ・カタリナ大学といった、アジアでも最古の建物が破壊され、数百人の市民が殺された。 |
 |
6 日本軍、マニラ占拠方針変えず top
マッカーサー司令部のコレヒドール島への移転、陸軍部隊の一部バターンへの移動について、第14軍の情報主任参謀、中島義雄中佐が報告したのは、マニラが無防備都市宣言をした日であった。
本間中将は、マッカーサーがバターン半島およびコレヒドール島で持久戦にはいるかまえであることを、ただちに察した。
しかし、第14軍の任務がマニラを占拠することであるため、第14軍参謀には、主力部隊はこの任務遂行にあたるべきで横道にそれるべきでない、とする意見がつよかった。
その場にいた幕僚のなかには、マッカーサーの“横すべり”は、任務完遂にかえって都合がよい、と考えた者もいたくらいである。
マッカーサー軍は、ある日本人将校の言葉をかりれば、“飛んで火に入る夏の虫”であった。
それでも、日本軍が目的地マニラへ到着するまでには、なおウェーンライトの北ルソン部隊を相手にしなければならない。
第26騎兵連隊の執拗な抵抗により、日本軍は、それまでアグノ川をこえることができなかったが、いっきょに攻撃にでて、戦線の右翼を守備していたフィリピン陸軍部隊を撃破し、クリスマスの正午にはウーダネータの町を占領した。
そして米軍は、第二防御線まで後退しなければならなかった。
日本軍の強行攻撃は続行され、二十六日には二ヵ所から渡河したが、一ヵ所はカルメンから鉄道で避難中の第11師団の一部の退路を、ほとんど遮断していた。
七五ミリ自走砲一門と戦車三台とて、いそいで道路をふさいだため、日本軍の突進は3号道路で阻止され、モンカダでフィリピン軍が遮断される事態をまぬがれることができた。
二十七日夜までにウェーンライトは、マニラから九七キロの地点にある、クルラックからカバナチュアンまで、平原を西から東にわたってのびている第四防御線へ後退した。
まえもって打ち合せておいた撤退計画では、ウェーンライトは、各防御線を、日本軍主力が攻撃準備をおわるまで維持しておいてから、後退することになっていた。
日本軍の撃破が目的ではなく、時間をかせぐためであったからである。
だが彼は、タルラック〜カバナチュアンの線で交戦することにし、南ルソン部隊に時間の余裕をあたえ、広範な陣地を確保しようとした。
ところが十二月二十八日、日本軍は戦車第4、第7連隊を最前線に、アグノ川から大挙進撃を開始した。
戦車がカバナチュアンにちかづいたとき、日本軍の歩兵第47連隊は、砲兵隊の支援弾幕に援護されながら川をわたった。
防御軍は翼側を包囲されて後退し、十二月二十九日夜、日本軍はカバナチュアンにはいった。
7 激しい攻防、上島大佐戦死 top
三十日、後退するフィリピン第91師団を追って、日本軍の第48師団、山砲および野戦重砲による追撃がつづいた。
防御軍はペナランダ川をわたり、鉄橋を破壊して、第92歩兵連隊のフィリピン兵およそ六五人と、ちょうどこの線に到着していたマニラからの学徒動員兵三〇〇人とで、後衛部隊を組織したが、日本軍は難なくこれを突破してしまった。
ついに最後の第五防御線まで後退した防御軍にたいするつぎの攻撃は、いままで連続してアメリカ軍陣地を攻撃してきた菅野支隊の小部隊であった。
彼らは、アメリカ軍戦車に発見されて八二人をうしない、後退した。
しかし日本軍の追撃の勢いがますにつれ、再度撤退しなければならなくなったアメリカ軍は、こんどは平原を横断して流れるサラゴーサ川をわたったが、神経質になった工兵が橋の爆破をいそぎすぎたため、貴重な戦車と、第11師団の一部とをうしなった。
同じ防御線の西翼においても、日本軍は進撃をつづけていた。
クルラックの南で、戦闘経験のないフィリピン第21師団は、上島支隊の攻撃をうけ、三十日にクルラックをうしなった。
しかし第二次攻撃で、フィリピン防御軍将兵は善戦してふみとどまり、日本軍に多大の損害をあたえた。
そのなかには、上島大佐の戦死もふくまれていた。
アメリカ人、カール・J・サボア中尉に指揮される第21師団の砲兵隊が、終始激烈な戦闘をつづけたため、日本軍の迫撃ははかどらず、第21師団は無事退避することができた。
しかし日本軍は、三十一日には、マニラまで五〇キロ以内の地点に到達していた。
日本軍の進撃により、南ルソンからひきあげてくる部隊の右翼が危険となったため、マッカーサーは、どんなことがあってもバターン半島へ左折する地点で援護する必要がある、と考えた。
そこが、もっとも攻撃をうける可能性がたかかったのである。
そのために、カルムビット橋周辺の維持が最大の問題となった。
マッカーサーは、使用できるかぎりの部隊をすべてバリウアグ・バラリゲル地帯、パムパンガ川の南方約六キロの線にそって配置した。
三十日、日本軍がプラリデルにむけ進軍中との報告があったが、翌三十一日、バリウアグ近郊に到達した。
日本軍は、ここで予期しなかった抵抗にあい、一時退却したが、正午までに多数の軍隊を町の周辺に集結させた。
これに対抗するため、ウィーバーの臨時戦車大隊から使用可能な戦車がすべて反撃に参加して、日本軍戦車八台を撃破するほど善戦した。
その結果この線は、もちこたえることができた。
8 アメリカ軍の撤退作戦完了 top
一月一日午前五時、最後の部隊がカルムピット橋をわたり、バターン半島へむかうことができた。
日本軍が、戦略的な拠点であるカルムピット橋の破壊をおもいつかなかったとは、特にその絶対優勢な航空兵力を考えれば、信じられないくらいである。
同日午前六時、橋はウェーンライトの工兵によって爆破された。
top
**************************************** |