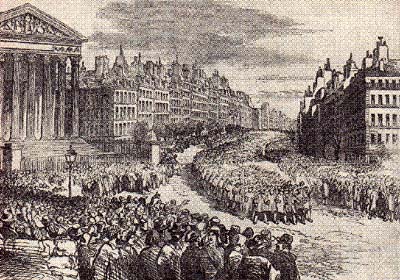|
****************************************
Index 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
世界の歴史11――帝国主義への道
1 二月のバリケード――第二共和制へのフランス
労働者は団結で「二月革命」で皇帝を追放したものの、「六月事件」でブルジョア連中に叩きつぶされた。
1.1 美しい先駆者 top
女流作家フロラ・トリスタン! 彼女は美しかった。
「すばらしい」「きれいだ」などという言葉は彼女のために作られたように美しかった。
すらりとした身のたけ、情熱に燃える瞳、長く黒い髪、輝くばかりのオリーブ色の肌、ととのったまっ白い歯、優美で上品な身のこなし、地味でさっぱりした衣服……。
フロラ・トリスタンは私生子であった。
彼女は一八〇三年、パリに生まれた。
父はペルーの貴族で、スペインの陸軍将校、母はフランス人である。
フロラの幼いときに父は世を去り、彼女は母の手で貧困のうちに育った。
働かねばならなかった。
十七歳のとき、フロラは彫師アンドレ・シャザルのもとで、彩色女工となった。
この娘に魅せられたシャザルの求婚、母のすすめによって、一八二一年二月、フロラは結婚にふみきった。
しかし夫を「愛することも、尊敬することも」できない結婚生活は、不幸であった。
離婚? 当時それは法的に認められておらず、彼女はみずから家を出て、また離婚にかわる別居によって、新しい人生にふみださざるをえなかった。 |

フロラ・トリスタン
|
そしてフロラはイギリスや父の一族が住む南米のペルーに旅して見聞を広め、一方、社会主義者サン・シモン、フーリエ、オーウェンなどの影響をうけた。
この間彼女は自分を「パリア」(社会ののけ者)と感じながらも、個人的な苦しみや悩みを人間の、とくに女性のそれにむすびつけた。
そして苦悩する人びとのためにつくすことに、自分の使命を見いだした。
つまり自分の内に、外に、「プロレタリア」を発見したのである。
フロラは絵のたしなみがあったうえに、文筆の才にめぐまれていた。
一八三八年、『あるパリアの遍歴』が出版されたころ、妻に憎しみとコンプレックスを感じた夫シャザルは、彼女の背にピストルを放った。
重傷ながらも、さいわい一命をとりとめたフロラは、シャザルが禁錮刑となったため、かえって身の自由をえた。
フロラは四度訪英しているが、彼女はそこで「産業革命」の国の民衆、とくに婦人労働者の悲惨な生活や社会的地位の低さを、まのあたりにした。
彼女は多くの場所に出入りし、多くの人びとに接した。
そして一八四〇年、フロラは『ロンドンの散策』を著わし、イギリスの現状をあきらかにして、社会思想家、文筆家として知られるようになった。
つづいてフロラは、その主著となるべき『労働者の団結』(『労働同盟』などとも訳される)を準備する。
出版社をもとめて徒労に終わったとき、彼女はその信念を説いて寄付にたよることとした。
パリで馬車に乗る金を節約し、徒歩で、これぞと思われる人びとの屋敷を訪ねて行く。
むなしく戸が閉ざされる場合も多かった。
日がとっぷり暮れたころ、あるいは雨にぬれ、風にうたれ、疲れきり、悲しみに沈み、なかば死んだようになって帰ってくる……。
やっとのことで、一八四三年『労働者の団結』が本となった。
小冊子にすぎないが、フロラの思想がはっきりと示されている。
彼女は労働者の悲惨の原因は「分裂」「孤立」にあり、彼らをすくう方法は「労働者の団結」「男女労働者の普遍的組合」にあると考えた。
そしてこの組合の自主的運営によって、労働者の経済的、知的向上をはかることを主張した。
そして彼女は他の階級に労働者の権利を理解させ、協調しつつ社会改革をすすめようとする立場をとり、この点、当時の社会主義者たちの影響がみられよう。
しかし彼女がマルクス主義にさきだって、これと関係なく、「プロレタリアの団結」を主張し、また女性の解放を男性のそれとむすびつけたことはユニークであった。
この解放のためには、労働者、女性がまず強い自覚をもつ必要がある――
この啓蒙をめざして、彼女は情熱的な使命感に燃えつつ、一八四四年四月から、フランス各地を伝道してまわった。
出発のまえに、彼女は書いている。
「……世間の人びとはほとんどみな、私に反対しています。
男たちは私が女性解放を要求するために、資産家たちは私が労働者の解放を主張するために。」
そして他方においては、「石の上に種をまいている。」というような感じを受けるとともに、「しかし私は落胆しない。私の使命はそれを許さないから。」と、気力をふるいたたせる日々であった。
官憲のとり調べや、いろいろな妨害をうける一方、賛同してくれる人びともあり、組合結成の動きもあった。
しかし諸都市をめぐって九月末、ボルドーまで来たとき、すでに健康を害していたフロラは病に倒れ、十一月のある寒い日、世を去った。
葬儀には多くの労働者が列席し、そのうちの四人――指物師(さしものし)、仕立屋、鋳掛屋(いかけや)、錠前屋(じょうまえや)が棺をはこんだ。なおフロラはシャザルとのあいだの一女を介したが、画家ゴーギャンの祖母である。
一八四八年二月、後述のようにパリに革命がおこり、第二共和政がうまれる。
女性たちのなかにも、結社やクラブを組織して革命をよろこびむかえる者が少なくなかった。
パリに組織されたいろいろな女性クラブは、離婚や参政権など、女性にとって切実な問題を論じた。
しかし臨時政府は無関心であり、人びとはむしろ彼女たちを嘲弄の的(まと)にさえした。
会合を終えて帰途につく女たちを、市民は冷たくあしらった。
一八四八年十月二十二日、労働者たちの寄付金によって、フロラ・トリスタンの記念碑の除幕式がボルドーで行なわれた。
彼女をたたえる数多くの言葉のなかには、ある桶屋の自作の詩があるが、それは、
「団結せよ、団結せよ、しかり、我々は団結しよう……。」という句ではじまっていた。
この一八四八年十月といえば、それにさきだつ「六月事件」によって、労働者がはげしく弾圧されたあとのことである。
では二月革命、六月事件に話をうつそう。 |

当時のある女性クラブの戯画
|
1.2 発端 top
一八三〇年の七月革命によって成立した七月王政は、イギリス流の立憲王政をめざし、国王ルイ・フィリップ一世ははじめは「市民の王」「バリケードの王」というわけで、気軽にパリ市中を歩いたり、労働者と酒をくみかわしたりしていた。
しかしこの王政は少数の金持ちたち――大地主、銀行家、大商工業者などによって支配されていた。
選挙権は納税額によって制限されており、国民の多くは政治に参加できなかった。
大臣のギソー(一七八七〜一八七四)はいうであろう。
「選挙権がほしければ、金持ちになりたまえ。」
また議員の買収もさかんに行なわれて、議会政治はしだいに腐敗していった。
しかも政府与党のなかにも、政争がはげしかった。
こうした七月王政に対して、いろいろな反対勢力があった。
その中心は新興の産業資本家層で、王政下に発展した産業革命によって進出してきたものだ。
またフランスは小市民の国であり、中小商工業者、金利生活者、自由職業家なども数多い。
一方、産業革命は労働者階級をもうみだし、そのなかには種々の刊行物や秘密結社によって、社会主義思想が発展していった。
社会主義者としては、パリのほとんどの暴動に関係し、生涯の約三十年を獄中ですごした革命家ブランキ(一八〇五〜八一)、無政府主義的なプルードン(一八〇九〜六五)、『労働組織論』(一八四〇)で有名なルイ・ブラン(一八一一〜八二)、『イタリア旅行記』(一八四〇)で共産主義ユートピアを構想したカベー(一七八八〜一八五六)など、多彩であった。
そしてこれら反体制側のあいだに、普通選挙制、共和政をのぞむ声が強くなり、いわゆるブルジョワ共和派や社会主義共和派がうまれた。
彼らはパリをはじめ諸都市で、「改革宴会」という演説会と食事の会とをあわせた形の反対運動を展開した。
これは一八四七年夏ごろから行なわれたもので、はじめは「国王ばんざい!」「改革ばんざい!」と祝杯があげられていたが、しだいに「普通選挙」「人民主権」「国民公会」「ロベスピエール」や「労働の組織」などのために乾杯されるようになった。
会場では政治・社会問題が熱心に論じられ、「ラ・マルセイエーズ」が高唱された。
政治上の不満に経済問題が加わった。
一八四七年、国際的な恐慌がおこったうえに、そのころフランスは凶作、物価上昇、失業、金融不安におそわれ、政府の無策のうちに、破局がせまってきた……。
一八四八年二月二十二日火曜日、パリのある区で改革宴会が開かれる予定であった。
政府はこれを禁止し、主催者側もしたがい、ことは終わるかのようにみえた。しかし、もはや革命への動きを、押えることはできなかった。
この二十二日朝九時ごろから、つめたい雨のなかで民衆はデモをはじめた。
平日にもかかわらず労働者や学生が加わり、しだいに数をまし、彼らは口ぐちに叫んでいた――
「ギソー(当時は首相)を倒せ!」「改革ばんざい!」
デモは開会中の議会の前などで気勢をあげ、そこここで官憲と衝突したが、夜になるにつれて静かになっていった。
二十三日朝、デモの民衆はさらに数をました。
経済不況に苦しむ小企業家や職人、小商店主や雇傭人なども加わり、バリケードもつくられた。
政府は国民軍を召集して鎮圧にあたらせようとしたが、これは失敗であった。 |
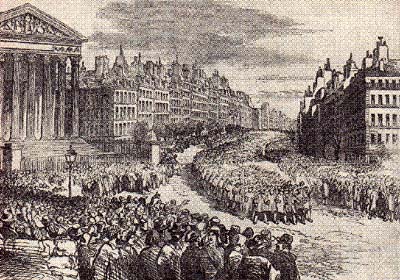
二月二十二日のデモ
|
国民軍は公の秩序維持の目的で組織され、ブルジョワ市民からなっている。
元来は七月王政をまもる忠誠な軍であるが、いまでは反ギゾー、いや、反七月王政の者が少なくなかった。
そこで政府は国民軍召集によって、民衆の動きに加えて、いわば武装し、組織された革命勢力を動員する結果となった。これに驚いた国王ルイ・フィリップは、急にギゾーを解任した。
改革運動の一応の勝利であるが、民心はこうした個人の進退では押えきれぬ状態であった。
二十三日の夜、街頭では依然、民衆のさわぎがつづいている。
九時半ごろ、彼らはカピュシーヌ街にあるギソーの官邸の前へ集まってきた。
このとき、まったく思いがけない事件がおこった。真相はいまだに不明であるが、おそらく偶然のことから、警備の軍隊が民衆に向かっていっせい射撃をおこない、五十名ほどの死者と多くの負傷者がでた。
犠牲者を横たえた車は、警鐘がなりひびくなかを、たいまつの光に照らされながら、街路につづいていった。
これにしたがう行列のなかで、人びとは口ぐちに叫んでいた。
「武器をとれ! 復讐だ!」 |

カピュシーヌ街の衝突で死傷者を運ぶ民衆
|
1.3 自由の樹 top
二十四日の早暁(そうぎょう)から、武器商をかすめて武装をととのえた民衆は、戦闘の準備にうつった。
明け方にはぞくぞくとバリケードがつくられ、午前十時ごろ、彼らは攻勢にでた。
ルイ・フィリップから軍の指揮をゆだねられていたビュジョーは、老練な将軍である。
彼の作戦をもってすれば、容易にバリケードを撃破できたかもしれない。
しかしルイ・フィリップは軍事的弾圧をさけ、妥協や交渉による解決をのぞんでおり、また国民軍の動向も不安であった。そのうえ軍の兵士たちのなかにも、民衆の側についたり、武器をすてる者もあるのだ。
1.4 飢えと貧困のゆえに top
革命直後、労働者はバリケードの英雄として歓迎され、第二共和政は彼らの夢をみたすかのようであった。
しかし牧歌はやがて消えていった。
一八四八年三月から六月まで、新たに展開するのは、ブルジョワ共和派と社会主義共和派との対立である。
つぎのエピソードは、早くもこれを示しているかもしれない。
二月二十五日、「社会主義共和政」のしるしとして、赤旗の採用を要求する民衆に対して、ラマルティーヌが、
「赤旗はシャン・ドーマルス広場を人民の血にそまって一周したにすぎないが、三色旗は祖国の光栄と自由とともに世界を一周した。」
という意味の有名な演説をもって答えた。
そして臨時政府は、三色旗をもって国旗と決定したのである。
七月王政の廃止、共和政の成立、普選の実現で満足しているブルジョワ共和派に対して、社会主義者はさらに社会変革をめざした。
たびたびの革命をへてようやく政権をにぎり、資本主義体制を生命としつつ、生産活動を活発にしようとしているプルジョワにとって、現存の秩序の変革は許しがたいことではないか。
いまでは社会主義、すなわち「赤」こそ、ブルジョワの敵である。
革命後、臨時政府は民衆の要望を無視できず、また社会主義派の閣僚にうながされて、労働者対策委員会、いわゆるリュクサンブール委員会(本部がリュクサンブール宮におかれた)や、ルイ・プランの構想にもとづく国立作業場を設立していた。
しかしブルジョワ勢力は、これらをまじめに運営するつもりはなかった。
そのうえ一般の国民は、とくに農民層は、総じて社会主義を私有財産の没収、均分と思いこんで恐怖心をいだいた。
この心理をブルジョワ共和派はたくみに利用した。
革命前後の経済危機のなかで適当な仕事は少なく、二日の大半を空費しながら日当をもらっている国立作業場の労働者たち、過激な議論に花を咲かせているリュクサンブール委員会の連中、彼らに対するパリその他の一般市民の嫌悪は、すなわち社会主義派や労働者階級によせる反感である。
また政府は財政難に対処するため、直接税一フランにつき四十五サンティームの付加税を課した。
これに対する国民の不満は、国立作業場で「税金をくいつぶしている」労働者にむけられたが、これもブルジョワ側の思う壺(つぼ)であった。
一八四八年四月、普選で選出された憲法制定議会では、ブルジョワ共和派が勝利をしめた。
王党派もかなり進出した。議会の成立とともに、臨時政府に代わって行政部が組織されたが、その閣僚はブルジョワ側に独占され、ルイ・ブランら社会主義者はそれからしめだされた。
選挙の勝利によって、リュクサンブール委員会や国立作業場の利用価値は失われ、まず前者は廃止された。
つぎは国立作業場である。
失業者は日ましにふえているが、それはとくに金づまりになった中小商工業界や、ぜいたくな生活に関係がある仕事に従事している方面――貴金属、装飾、家具、技芸などの職業に多い。
これらの失業者の収容によって、五月には労働者十万をこえ、六月には十二万に近づく国立作業場――それは一種の失業救済機関となっていた――の出費は政府にとって相当な負担である。
また、なにか暴動でもおこったような場合、この国立作業場は「ブルジョワに対する労働者の軍隊」となる危険もあった。政府、議会では作業場解散の意向が強くなった。
一八四八年五月十五日、ポーランド独立運動の援助を要求して、労働者のデモが高まりその一群は議会をおびやかした。
けっきょく鎮圧されたが、この事件に国立作業場から、かなりな数の労働者が参加したことは、いよいよ「反乱の温床」の感を深くした。
王党派を中心とする保守勢力は、国立作業場即時解散の主導権をにぎった。
その背後にはパリ労働者に対する地方の反感、資産家階級の恐怖感、カトリック勢力の同調があった。 当時の有名なある経済学者は財産家たちの声を代表するかのように、行政部へ公開状を提出した。
それは「あなたがたが信用の回復をのぞむならば」「産業の復興をのぞむならば」などの十八の条件をあげて、それらをみたすために国立作業場の解散をせまるものであった。
ついに六月二十一日、議会は解散を決定した。労働者のうち若者は軍隊に編入され、その他は地方の土木事業にまわされ、これらを拒否する者は解雇である。
政府側と労働者代表との会見も決裂し、二十三日午前中にパリの東部はほとんどバリケードでうずまる。
市街戦がはじまる直前、行政部のアラゴ(一七八六〜一八五三)はバリケードまで出むいて、労働者たちを説得しようとこころみた。
バリケードからはつぎのような答えがあった。
「ムッシュー・アラゴ、あなたは勇敢な市民であり、我々はたいへん尊敬しています。
しかしあなたには、我々を非難する権利はありません。
あなたは一度も飢えたことがなく、貧困というものをごぞんじない。」 |
|
六月二十三日午後から、これまでの史上最大といわれる市街戦がはじまった。
鎮圧軍の総司令官はカベニャック将軍(一八〇二〜五七)である。
彼は事件を小規模のうちに弾圧せず、むしろこれを拡大した。
血を血であらう四日間の凄惨な戦い――。
この事件には国立作業場の労働者の一部も参加したが、中心となったのは職人的な手工業労働者(その多くは失業中)であり、社会主義思想の洗礼をうけた労働者たちもいた。
これに対してパリの小市民たち、さらには地方から、農村から、はせつけて来た人びとが軍隊と協力し、社会秩序をみだす「赤」を恐れて、憎悪をこめて戦った。
そして二十六日昼まえ、議長が喜色満面、感動に身をふるわせながら、わきかえる議場で報告した。
「サン・タントワーヌ街は、無条件で降伏した。
おお諸君! 私はうれしい。
諸君! 私は心から喜びつつ、いいます。
神よ、ありがとうございました、共和国ばんざい!」 |
労働者が多く住んでいるサン・タントワーヌ街は、反徒の最後のとりでであった。
「ブルジョワ連中は熱狂した歓声をあげ、帽子をふり、拍手し、踊り、兵士たちにだきつき、酒をすすめ、婦人たちが投げる花がバルコニーから降るようであった。」
歓迎される軍隊にくらべて、反徒やその家族に加えられた弾圧は想像にあまりある。
「ブルジョワたちは耐えしのんできた死の恐怖のつぐないに、前代未聞の野獣性を発揮した。」
正確な数は不明であるが、即時銃殺された者は千五百人におよび、逮捕された二万五千人のうち、多くは十分な裁判もうけず、死刑、流刑、強制労働などに処せられたという。
六月事件はブルジョワとプロレタリアとのあいたに展開した「最初の大規模な階級闘争」ともよばれ、それは、二月革命以来のブルジョワ共和派と社会主義共和派の対立に終止符をうち、第二共和政の安定は「二月」ではなく、「六月」からはじまったともいえよう。
|

最後の戦い

流刑者の出発
|
同時に六月事件は、ヨーロッパ「諸国民の春」にも影響した。
これをおりに、各地の革命勢力も後退し、保守勢力が復活してくるのである。
二月革命の報によって大軍を国境にうごかしたというロシア皇帝ニコライ一世は、六月反乱の弾圧者カベニャック将軍を賞讃した。
top
**************************************** |