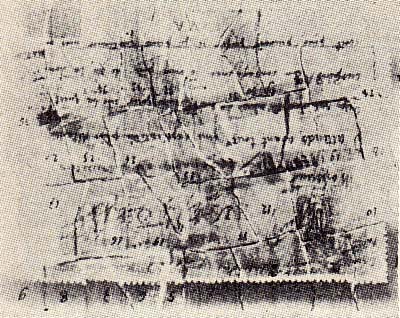|
****************************************
Index 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
世界の歴史11――帝国主義への道
5 フランス第三共和政
5.1 ブーランジェ将軍の悲喜劇
top
パリ・コミューンの革命(一八七一)が終わったフランスでは、王党派が多い当時の議員数からすれば、政体のうえでは王政復古のはずである。
しかしこの派は、あいかわらずブルボン派とオルレアン派とに分裂して、たがいに仲がわるく、これは共和派にとって有利であった。
ところで王党派の大地主、大資本家たちと共和派ブルジョワ層とのあいだに、ブルジョワ支配体制そのものについては、根本的な対立はありえない。
しだいに妥協が成立し、フランスはいわば「うしろ向きに」共和政にはいっていった。
一八七五年の憲法は、このような妥協的法案を集成したものであり、三権分立、二院制(代議院と元老院)、七年制大統領、男子普選などをふくみ、一九四〇年フランスがドイツに敗北するまで、フランス第三共和政の支柱となった。
一八七七年、保守的なマクマオン大統領および元老院と、共和派が多い代議院とが対立したが、後者の勝利となってからは、共和政も安定化の道をたどる。
同時に、敗戦以来のフランスの国際的地位も回復してきた。
これにつれて、共和派のなかで主導権をにぎったのは、いわゆるオポルチニストである。
これは「時宜をえた(オポルタン)」政策をもって、おもむろに社会改革を実行しようとするガンベッタたちの一派である。
彼らは、王党派と妥協した共和派大ブルジョワの意向を代表するとともに、中小プルジョワ――商店主、中小企業家、俸給・金利生活者などの気持ちを代弁していた。
この「新しい社会層」は、フランス資本主義の発展と安定につれて、穏健な共和主義の支持者となった。
こうした動向に不満な一部の共和派は、ジョルジュ・クレマンソー(一八四一〜一九二九)らを中心として、「ラディコー」(急進派)を形成した。
一方、フランスは普仏戦争の敗北から早く回復したが、フランス人のドイツに対する敵意は強く、仏独関係は依然として好転しない。
フランスの報復を警戒するドイツは、これを孤立させておくため、一八八二年、独墺伊の三国同盟を成立させた。
フランスで、この対独復讐熱の中心となったのはブーランジェ将軍(一八三七〜九一)である。
一八八七年四月、フランスの一警察官シュネーブレが、普仏戦争の結果ドイツに併合されたロレーヌで、スパイの嫌疑からドイツ官憲に逮捕された。
事件を知ったとき、フランス人は「腰かけていた席から、思わず立ちあがらずにはいられなかった」というほどの衝撃をうけた。
わきかえる世論のなかで、ドイツに対して開戦をも辞さない強硬態度をとったのが、当時の陸相ブーランジェであった。
事件はドイツ側のシュネーブレ釈放で解決したが、これはドイツの宰相ビスマルクが、ブーランジェを恐れたためであるという判断をくだされ、将軍をめぐって爆発的な人気がうまれた。
盛装した彼が黒い馬で現われるようなとき、民衆の熱狂は頂点に達する。人びとは歌った。
「あれごらん、笑って通るあの男
アルザス・ロレーヌ、とり返したぞ。」 |
国粋的な右翼団体などは、ナポレオンの再来、対独復讐の時はせまったとさけびたてた。
王党派も、ボナパルト派も、「馬上の男」をかつぎ、前者は運動費を提供していた。
さらに経済不況からうまれた失業者たちをはじめ、共和政になんらかの不満をもつ人びとが、そのはけ口をこの人物のなかに見いだした。 |

ブーランジェ派の宣伝ビラ
「くたばれビスマルク……
ブーランジェばんざい」
|
将軍の頭をつけたパイプ、ブーランジェと命名した酒や石けんも売り出され、『ビスマルクをしりごみさせる男』『護国の英雄』『独仏戦争未来記』などの小冊子類が、本屋の店頭をにぎわすありさまであった。
危険を感じた政府は、一八八七年五月、ブーランジェを陸相から解任し、ある地方の師団長に左遷した。
七月八日、将軍がパリを去るとき、民衆は大挙して駅頭におしかけ、線路になだれこみ、列車がうごくのを妨害した。
人びとは口ぐちにさけんでいた。
「エリゼ宮へ!」 エリゼ宮とは、むろん大統領官邸である。
もしこのとき、彼が決断していたならば……。
しかし内心は、自分がつくりだした冒険がおそろしくなっていたらしいブーランジェは、おとなしく任地におもむいた。
深夜、パリは平静にかえり、エリゼ宮も夜の沈黙にとざされた。
思いがけない事件が、ブーランジェの復活をうながした。
一八八七年十一月、大統領ジュール・グレビ(在任一八七九〜八七)の女婿で代議士のダニエル・ビルソンが、勲章などをめぐる不正事件に関係して、スキャンダルをひきおこし、共和派は世論にきびしく批判された。
結局、グレビは辞職した。ブーランジェ派は憲法改正をもちだし、現共和体制の議会主義をおびやかすにいたった。
一八八八年三月、政府はブーランジェを現役から引退させたが、これはかえって、彼に選挙にうってでるチャンスをあたえることとなった。
いまや「不平家の結社」となったブーランジェ派のなかには、一部の社会主義者もふくまれていた。
一八八九年一月パリの補欠選挙で、共和諸派の統一候補に対して、ブーランジェの圧倒的な当選が判明した二十七日の夕方、それがクライマックスであった。
「エリゼ宮へ!」という声が、ふたたびパリに満ち、じじつ、側近にはクーデターをすすめる者もいた。
右翼は、その準備をもととのえていた。
しかしその夜ブーラシジェは熱狂する群衆をさけて、恋人マルグリート・ド・ボヌマンの家を訪れたらしい。
二人はなにを語ったのか?
ともかく彼は合法的にとどまる決心をした。
側近の一人は、彼の宿舎をたち去りながらもらした。「零時五分か、諸君、たった五分前からブーランジェ運動の潮はひきはじめたのです。」
一月二十七日は、共和派に大きな衝撃をあたえた。
彼らは共和国をまもるために団結し、ブーランジェを、国家に対する陰謀の罪に訴えた。逮捕されるといううわさによって、ブーランジェは八九年四月、恋人とともにブリュッセルヘ逃亡した。
まるで「公金を消費した書記のように」――。
なぜ、逃げるのか、罪の根拠はきわめて薄弱ではないか、逃げたことは罪を肯定するものととられるではないか、それに裁判にかかれば、かえって殉教者として人気が高まるではないか……。
ブーランジェ派の懇願にもかかわらず、彼は帰国を拒否しつづける。八月、ブーランジェは欠席裁判で、有罪、流刑を宣告された。
しかし意外な結末となってしまった。 |

ブーランジェの恋人
マルグリート・ド・ボヌマン
|

自殺するブーランジェ
|
一八九一年九月三十日、すでにこの年七月に病死していたマルグリート・ド・ボヌマンの墓前で、彼は自殺し、「ロミオのように」生を終えたのだ。
爆発的な人気ではあったが、ブーランジェ将軍には、ナポレオン一世や三世の場合のような広い国民層の、とくに農民の支持がなかった。
むしろ彼らは恐れていた、もしブーランジェが政権をにぎると、戦争と、それにともなう増税がくるであろうことを。
彼の不決断や逃亡によって首都の熱狂がさめたとき、この「ファシズムの先駆的現象」は、急速に衰えてゆき、彼の死とともに終わった。
5.2 ドレーフュス大尉の受難 top
ブーランジェ事件のあいだに、フランス政界の再編成がすすんだ。
一方では急進派はしだいに急進性をうしない、たとえば元老院廃止、一院制というような意味での改憲論もなりをひそめた。
一方では、王党派の一部はさらに共和派に接近した。
しかし政界には、事件にことかくようなことはなかった。
たとえば、パナマ運河会社事件のような疑獄である。
スエズ運河の生みの親で、すでに七十歳をこすレセップスは超人的精力をもって、一八八一年パナマ運河の工事に着手した。
しかしこれは失敗し、八九年、運河会社は破産を招いた。
ところがこの会社の社債発行の立法化にかんして、九二年、有力な政治家たちが「収賄者」と目されることとなった。
このパナマ疑獄がもう少し早くおこっていたならば、議会政治の腐敗は、おそらくブーランジェ派に勝利をもたらしたであろうといわれる。
事件は共和派の政治家の交替をまねき、新人の登場となった。
急進派の雄クレマンソーさえ、政界から姿を消した。
しかしこれとは比較にならないほど、世紀末フランスをゆりうごかした事件が起こった。
一八九四年九月のこと、ある文書の一部――明細書(ボルドロー)とよばれる――がパリのドイツ大使館から、フランス側に盗みだされた。
それは、フランス情報機関の指示にしたがい、屑籠の紙を集めていたドイツ大使館の家政婦が、入手したことになっている。
しかし真相は、はっきりしていない。軍の情報を売ったこの文書は、フランス軍籍にある者の手になることが判明するとともに、筆跡の類似から、砲兵大尉アルフレッド・ドレーフュス(一八五九〜一九三五)に嫌疑がかかった。
彼はユダヤ人である。報告をうけた情報部のある上官はいった。
「当然、考えられることだ。」
十月なかごろ、よびだされたこのユダヤ人将校は口述筆記をさせられたのち、ただちにその場で逮捕された。
しかし筆跡鑑定者の意見は一致していなかった。
なかには類似を否定する者もあった。
三十五歳、産業ブルジョワの家にうまれ、優秀な成績で陸軍大学まで卒業し、あかるい前途をもち、富裕な商人の娘と、幸福な結婚生活にはいり、二人の子までもうけているドレーフュスは、およそスパイ行為からは縁遠い存在である。 |

ドレーフュス
|
彼が証拠不十分で無罪となる可能性もあった。
しかしジャーナリズムというものが存在していた。
参謀本部のだれかが、新聞に投書した証拠も残っている。
十月二十九日、『リーブル・パロール』紙はこの事件とドレーフュスの逮捕を報ずるとともに、陸軍当局の沈黙を非難した。さらに十一月一日、同紙はセンセーショナルな見出しで、世論を刺激する。
はたして反ユダヤ主義者たちは、売国奴の死刑を要求してさわぎたてた。
軍上層部はいそいで軍法会議をひらき、ドレーフュスの無実の主張にもかかわらず、十二月全員一致で有罪、終身流刑の判決をくだした。
世間では、銃殺をまぬがれたことに対する不満さえきかれた。
一八九五年一月五日、こおりつく朝、パリ士官学校で、ドレーフュスは衆人環視のうちに位階剥奪の式の屈辱にたえねばならなかった。
そしてドレーフュスはフランス領ギアナの悪魔島に送られ、国民は事件は終わったと思っていた……。 |

ドレーフュスの位階剥奪式
|
偶然のことであった。
九六年三月、やはりドイツ大使館から持ちだされた紙屑のなかから、フランス側のエステラジー少佐にあてられた、いわゆる封緘(ふうかん=封をした)電報が復元された。
そこでこのエステラジーを調べていた情報局長ピカール大佐は、意外なことに気づいた――
エステラジーの筆跡は、まえの明細書のそれとまったく同一ではないか!
これを見せられた人びとは、だれかが、ドレーフュスをまねたものなどと、言を左右にした。
しかしピカールは、日ごろ、いかがわしいところがあるエステラジー ――
借金で首がまわらず、あやしげな生活をおくり、大のばくちうちである、ハンガリー貴族出のこの伯爵こそが犯人だと確信した。
ではドレーフュス再審であろうか?
しかしこれは、軍法会議の名誉を落とすことになろう。
ピカールから報告をうけた将軍たちは、軍の名誉のために「ひとりのユダヤ人」を犠牲にすることにきめた。 |
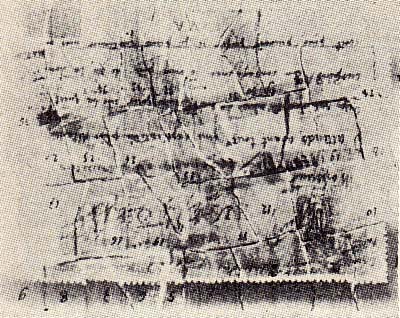
封緘(ふうかん=封をした)電報
|
しかもピカールは、北アフリカのテュニジアに左遷された。
ピカールはこの秘密をにぎったままで、アフリカに行きたくはなかった。
彼は友人であるパリの一弁護士に、自分の発見した記録をゆだねていた。
この弁護士は、政界の重鎮である上院副議長シューレ・ケストネルに、この新事実を示す機会をえた。
ケストネルはドレーフュスの無罪を信じて、再審要求運動の先頭にたつことになった。
世論も活発となった。
かねてから弟の無罪を信じていたドレーフュスの兄マティウーは、一八九七年十一月、エステラジーを告発した。
しかし、九八年一月、軍法会議の結果、エステラジーは無罪放免となった。
かわりに告発されたピカールは、二月、退役に処せられた。
これで政府、軍部はふたたび事件が終わることを期待していた。
5.3 「わたくしは弾劾する!」 top
エステラジー放免の直後、九八年一月十三日、クレマンソーを主筆とする新聞『オーロール(曙光)』紙は「わたくしは弾劾する!」という大見出しのもとに、自然主義の文豪エミール・ゾラの公開状、『共和国大統領へあたえるの書』をのせた。
それはドレーフュスを無罪として、当時の陸相メルシエはじめ、参謀本部、軍法会議などの関係者で、彼を有罪とした人びとを非難したものである。
新聞は二十万部を売りつくし、パリの町かどにもはりだされたという。
『オーロール』の主筆クレマンソーは、パナマ運河疑獄に関係し、政治的生命を終えたかにみえたが、いまやペンで新しい道をきりひらこうと決意していたのだ。
しかし名誉毀損で軍部に告発されたゾラは、有罪の判決をうけ、一年ばかりイギリスに亡命した。
反響は大きかった。フランスは二つにひきさかれた。 |

ゾラの公開状をのせた『オーロール』紙
|
一つは「正義と真実」のためのドレーフュス派、または再審派、一つは「軍の名誉」のための反再審派である。
この場合、「ドレーフュスは一つの象徴にすぎない。」
争点は個人の擁護にとどまらず、ドレーフュス派は共和政の支持者を集め、反ドレーフュス派は反共和主義的なカトリック勢力、王党派、国粋主義者などからなっていた。
興奮がうずまくうちに、一八九八年の夏をむかえた。
陸相カベニャックは七月、さきの軍法会議にも提出された証拠にもとづいて、ドレーフュス有罪を確信した。
しかしこの証拠は信頼できるものか、偽造ではないか?
この疑惑に応ずるため、カベニャックによって審査を命ぜられたある士官は、その疑惑が正当であることを発見する。
八月末、尋問、自白、そして投獄された偽造者アンリ大佐は、入手経路不明の剃刀(かみそり)で自殺した。
死をまえにして、彼が妻に書きおくった手紙には、のちのち人びとが判断に苦しんだ一行があった。
「私がだれのために働いたか、おまえには分からないわけではあるまい。」
エステラジーのためか? 上官たちのためか? ほかのスパイたちのためか?
アンリ大佐は「誠心誠意、国を憂うのあまり」、この挙にでたものであるという「愛国的偽造」がでっちあげられたものの、反ドレーフュス派がうけた打撃は大きかった。
退役となったエステラジーはイギリスに高飛びした。
再審派が世論を制し、九八年九月、政府は再審を決定、十月、最高裁判所は審理請願を受理する。
この年、すなわち一八九八年九月、フランスはアフリカでイギリスと対立し(ファショダ事件)、当時英仏開戦の危機感のうちに、国粋主義、ミリタリズムが高まっていた。
審査を不満とする軍部のクーデターのうわさも流れた。
これに対して社会主義者は、ドレーフュス派、共和政擁護の側に加わった。
こうしてこの事件は、フランス社会主義諸派を統一に向かわせる重要な機会となり、この間、名実ともに社会主義者を指導したのは、ジャン・ジョーレス(一八五九〜一九一四)である。
社会主義とヒューマニズムの結合をとく彼にとって、ドレーフュス事件は人間の権利のためのたたかいであった。
彼の果敢な雄弁や文章は、たしかに世論をうごかした。
一八九九年六月、事態は高潮する。最高裁判所は九四年の裁判を無効として、再審を命じた。
激昂する反ドレーフュス派に対抗して、バルデック・ルソー(一八四六〜一九〇四)を首相とする「共和政防衛内閣」がうまれた。
この内閣は約三年つづき、フランス政界の転機となった。
一八九九年九月、レンヌの軍法会議における再審の結果は、意外にも有罪、情状酌量して十年の禁烟という判決であった。
無罪を信じていたドレーフュス派のショックは大きかったが、大統領はその権限をもって恩赦をあたえた。
無罪にすれば軍部に責任者をださなければならず、右翼による混乱を覚悟しなければならない。
恩赦は「きわめて政治的な利害関係」による妥協であったといえよう。
後日のことを付記すれば、一九〇六年七月最高裁判所は再審の結果を破棄して、ついに無罪の判決をくだした。
もはや、なんのさわぎも、興奮もなかった。
復職したドレーフュスは、同じく復職したピカールとともに昇進する。
少佐に任命されたドレーフュスの叙勲式は、一九〇六年七月二十二日、かつて位階剥奪式が行なわれた同じ士官学校の校庭で挙行された。
彼は少将となったピカールとともに、レジーン・ドヌールに勲章を授与されたのである。
なお現在では、真犯人はエステラジーで、ほかに協力者があったらしいとみられているが、確定的ではない。
5.4 ヨーロッパの高利貸し
top
ドレーフュス事件における共和政擁護の動きのなかから、オポルチニストにかわって、共和派左派、つまり急進派が進出して、一九〇一年、いわゆる急進社会党が成立する。
急進社会党といっても、ブルジョワ共和派であることにはかわりはないが、これはフランスにおける最初の近代的政党で、第二次世界大戦まで、フランス政界の中心的存在となった。
社会主義勢力もパリ・コミューン敗北の打撃から回復し、ゲード(一八四五〜一九二二)たちによってマルクス主義が発展してきた。
一八八九年、第二インターナショナルがパリで成立した。
同時に改良主義者もあらわれ、ブランキ派のような暴力的革命主義者にも、この傾向がうまれた。
またドレーフュス事件によって団結をうながされた社会主義諸派は、ジョーレスらを中心として一九〇五年、統一社会党を結成した。
労働運動ではすでに一八九五年、労働総同盟がつくられていた。
これはまだフランス労働者の一部を組織化するにすぎないが、ゼネスト、サボタージュなど、直接行動にうつたえるサンディカリスムの理論は有名である。
一九〇六年の「アミアン憲章」は、その基本方針を示し、代表的理論家はジョルジュ・ソレル(一八四七〜一九二二)である。
第三共和政下、フランス資本主義の発展は、原料の獲得、商品の販路、資本の投下などのために、国外市場をもとめてフランスを帝国主義政策にかりたてた。
ビスマルクが対独復讐熱をそらすため、フランスに植民地経営をすすめたことも忘れられない。
フランスのすぐれた文化を、後進諸民族にひろめてゆくという、一種の「使命感」も、そこにあったといわれる。
こうしてフランスはアジアでは、清仏戦争(一八八四〜八五)の勝利ののち、仏領インドシナ連邦を成立させ(一八八七)、
日清戦争後の三国干渉(一八九五)や義和団出兵(一九〇〇)に加わって、諸列強とともに本格的な中国分割にのりだした。
アフリカではモロッコ、テュニジアに進出、またマダガスカル島、ソマリランド、チャドなどがフランスの植民地となり、やがて二十世紀はじめ、仏領赤道アフリカの広大な植民地に発展してゆく。しかし、フランス人レセダプスが完成したスエズ運河のエジプトで、フランスはイギリスのために後退をよぎなくされた。 |

アフリカのフランス勢力範囲
|
またフランスはこのイギリスのアフリカ縦断政策とナイル上流地方のファショダで対立し(一八九八)、けっきょく譲歩して、アフリカ横断政策を放棄せざるをえなかった。
後進国への投資はフランス帝国主義の大きな特色であるが、一八六〇年代末から九〇年代はじめまでに、外国への投資はおよそ倍加している。
そしてこの投資は、産業上よりも国債にむけられる場合のほうが多く、「高利貸し的帝国主義」という表現もある。
ロシアに対してもそうであった。
当時ロシアは軍備拡大や生産拡充などから、外国資本を必要とした。
パリの銀行家たちは「愛国的な熱心さ」をもって、ロシアの募債に協力した。
帝政ロシアのほうでも、必要は共和国と同盟するというためらいにうちかった。
一八九一年七月、フランス艦隊はクロンシュタット港を訪問し、皇帝みずから旗艦を訪れ、国禁である革命の歌ラ・マルセイエーズに敬意を表した。
この年、両国間に成立した政治上の協定は、九四年軍事上の同盟に発展して、露仏同盟ができあがった。
これはドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟に対抗するものであり、ここにヨーロッパ大陸は二つの陣営に分かれた。
すでに一八九〇年、ビスマルクは政界から引退している。
つづいて、フランス孤立化を策する彼の外交も終わったわけである。
前述のようにフランスが中国やアフリカに進出した背後には、露仏同盟によって支援されるという情勢もあったわけだ。
なおこれらの同盟関係の存在は一般にわかったが、内容は秘密のため、第一次世界大戦で、とくにロシア革命で情勢がかわるまで、推測以上にはでなかった。
こうした秘密外交は、帝国主義時代のひとつの特色である。
ところで、前述のファショダ事件は、この伝統的な宿敵である英仏抗争のクライマックスであった。
それが解決したのち、両国のあいだに接近の道がひらけた。
フランスは、同盟国ロシアが日露戦争などで極東に関心を奪われている不利を補い、また進出めざましいドイツに対抗する必要があった。
すでに日英同盟(一九〇二)にふみきったイギリスは、諸国の対立の激化のなかで、ヨーロッパでも友好国をもとめた。
一九〇四年、英仏は植民地における紛争を解決し、とくにエジプト、モロッコをそれぞれの勢力範囲としてみとめ、こうして英仏協商が成立した。
これを推進したのは、外相デルカッセ(一八五一〜一九二三)である。
さらに一九〇七年、英露協商が成立ここに露仏同盟、英仏協商とあいまって、これら三国間に、いわゆる三国協商関係が形成され、対ドイツ包囲体制がととのえられた。
このドイツとフランスの対立は、一九〇五年および一一年の二度におよぶモロッコ事件などによって、ますます深刻になってゆく――。
第一次世界大戦前、十九世紀末から二十世紀はじめにかけては、しばしば「ふるきよき時代」といわれる。
女性のモードで世界の中心となっていたパリでは、すでにエッフェル塔はそびえたち、やがてサクレ・クールの教会堂がピザンツふうの威容をととのえ、オペラ座の新装もなり、コメディー・フランセーズ座では、サラ・ペルナール(一八四四〜一九二三)が世界的人気を博した。
エッフェル塔は技師エッフェル(一八一三二〜一九二三)により、一八八九年の万国博覧会のため建設されたものである。
文化人たちは首都の美観をそこねると抗議し、なかには田舎にひっこんだ人もいたといわれるが、一般的には好評で、最初の年だけでも二百万の人がのぽった。
一方、ムーラン・ルージュのカンカン踊りや、ミスタンゲット(一八七三〜一九五六)のシャンソン、踊り、さらにその「美しい足」がパリっ子の話題となり、新しくあらわれた活動写真も、人びとの好奇心をそそる。
そしてドーバー海峡の横断飛行がはじめて行なわれたのは、一九〇九年のことである。
画壇は印象派の黄金時代となり、マネー(一八三二〜八三)、ドガ(一八三四〜一九一七)、モネー(一八四〇〜一九二六)などに、セザンヌ(一八三九〜一九〇六)、ルノワール(一八四一〜一九一九)らがつづく。
ゴッホ(一八五三〜九〇)、ゴーガン(一八四八〜一九〇三)も登場する。
モンマルトルの盛り場に耽溺しているロートレック(一八六四〜一九〇一)のかたわらには、やがてパリを美術のメッカとするエコール・ド・パリの画家たちも現われはじめていた。
ロダン(一八四〇〜一九一七)の傑作もあいついでいる……。
ブルジョワたちはイギリス流のスポーツである競馬やフットボールに興じ、またイギリスの例にならって海水浴や遊覧旅行など、レジャーの味を知りはじめていた。
そして小市民は「小金をたくわえ、小金利と小家屋と小庭とで満足し」、小農も、その小土地所有に安住できることを願っていた。 |

当時の人気女優サラ・ペルナール
|
フランスでは、ドイツやイギリスほどには大工業は発達しなかったが、新産業としての自動重工業はやがて世界的なものとなる。
そして絹製品、手袋、香水、レース、ぶどう酒などの生産、輸出はフランス独特のものであろう。
電燈、電話、写真、自転車、百貨店なども生活のなかにはいりはじめ、ジャーナリズムも発達し、教育も普及し、女性の職業的進出もみられるにいたった。
人口は農村からしだいに都市に集中していたが、出産率の低下は――とくにドイツにくらべて――フランスの大きな悩みとなった。
なお七月十四日が国祭日に、ラ・マルセイェーズが国歌に定められたのも、第三共和政下のことである。
top
**************************************** |