|
****************************************
Index 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
世界の歴史11――帝国主義への道
2 マルクスとその時代
2.1 青春と恋愛 top
カール・マルクスは一八一八年五月五日、プロシア(プロイセン)のライン地方、ツリール(トリエル)という小さい町に生まれた。
父方はラビ(ユダヤ教の律法学者)の家柄である。
弁護士で、教養が高く誠実な人柄の父は、カールが幼いときキリスト教に改宗し、ルソーに傾倒しているような自由主義者であった。
母はオランダ出身で、家庭的な婦人であったが、この母方も代々ラビをだした家柄である。
カールは九人の子のなかの三番目にあたる。裕福で幸福に育った。
少年時代のカールは成績のよい普通の子どもで、やや性格の強いのが目立った。
高等学校の成績をみると、歴史とドイツ語の作文、古典語にとくに優れていた。
今日、卒業試験の作文『職業の選択にかんする考察』が残っているが、そこには理想主義的な人生観が情熱をこめて述べられている。 |

大学生時代のマルクス
|
「……
職業を選ぶにあたって、我々を導くべきおもな道標は、人類の福祉と目己自身の完成とである。……
歴史は、社会のために働くことで自己自身を高める人を、偉大な人物と呼んでいる。……
我々が人類のために献身的に働きうる地位を選んだとしたら、その人の肩にどんな重荷がかかっても、このため挫折するようなことはないであろう。……」 |
ボン大学にはいり、父の希望にしたがって法律学をまなんだが、学生らしく飲んだり騒いだりしたようである。
このため父の意志で、ベルリン大学に転学することとなった。
彼はこのころイェニーという女性と恋愛し、婚約する。
彼女はツリールきっての名門で、貴族のルードビヒ・フォン・ベストファーレンの娘で、カールより四歳年上である。
二人の住居は近く、親しくつきあっていたので、二人は幼なじみであった。
カールはしばしばイェニーの家を訪問し、ルードビヒからホメロスやシェークスピアなどの話をきいたという。
イェニーはツリール社交界の花といわれる美人で、また才媛であり、縁談にはこと欠かない。
秀才だけがとりえのカールでは、ベストファーレン家に反対が強く、婚約は難航したが、彼の父の奔走もあって、ようやく実をむすぶこととなった。
婚約の喜びを胸にカールは一八三六年十月、ベルリンに向かった。
彼はベルリン大学で勉学のかたわら、詩作にふける。
そして『愛の書』第一部と第二部を、イェニーに捧げた。
しかし彼の詩はあまりりっぱなものではない、というのが定評である。
マルクスがベルリン大学にまなんだころ、すでにヘーゲルは死んでいた。
しかしヘーゲル哲学は依然として盛んであり、右派と左派(青年ヘーゲル派)に分裂しはじめていた。
マルクスはブルノー・パウエルら左派のグループに属し、哲学の勉強に没頭した。
一八三七年、「ゲッティンゲンの七教授事件」がおこった。
ハノーバーの新しい王が、七月革命(一八三〇)の影響で成立していた自由主義的な憲法を廃止した。
そこでゲッティンゲン大学の七教授――歴史家ダールマンや童話で有名な言語学者のグリム兄弟など――はこれに抗議したため、罷免された。
この事件は全ドイツに大きな反響をまきおこした。
マルクスが尊敬するガンス教授の誕生日を祝う会は、七教授擁護の会合になった。
この会合におそらくマルクスも参加したであろう。
こうして彼の学生時代には、なおウィーン体制下に、ドイツは保守的情勢が強かったのである。
一八四一年、マルクスは古代ギリシア哲学にかんする論文、『デモクリトスとエピクロスの自然哲学の相違』を学位請求論文としてイエナ大学に提出した(ベルリン大学は保守的になっていた)。
この論文はイェニーの父に捧げられ、唯物論と、その必然性のなかでの自由や自己意識などを明らかにしたものだ。
「不敵で挑戦的」であったため提出されなかった序文で、マルクスは「率直にいおう、自分はいっさいの神々を憎悪する。」というプロメテウスの告白を引用しているが、これこそマルクスの生涯をつらぬく信条であった。
学位をえて大学生生活を終えたマルクスは、ボン大学の講師になろうとするが、これを勧めたパウエル自身が、すでに急進的なため大学を追われていた。
やがて彼は、創刊されたばかりの『ライン新聞』の編集者として招かれ、ジャーナリストとして身をたてることとなった。
『ライン新聞』とは、ライン地方の自由主義的資本家カンプハウゼンやハンゼマンによってケルンで発刊された新聞である。
一八四〇年フリードリヒ・ビルヘルム四世(在位一八四〇〜六一)が即位すると、国民は王に憲法の制定と自由主義的改革を期待した。
だが王にはその意志がなかった。
これにたいし『ライン新聞』は改革を要求するため、企画されたものである。
鋭い論理と諧謔(かいぎゃく)にとみ、生彩あふれる記事によって、マルクスの名声は高まり、四二年十月、彼は編集長となった。
これまでヘーゲル左派として、哲学ないし宗教批判にたずさわってきたマルクスは、ここでいやおうなしに、具体的な現実の問題に直面せざるをえなかった。
貧しい農民の木材盗伐や土地所有の問題、出版検閲や関税の問題……などと取りくむなかで、彼の視野はひろげられると同時に、社会科学、とくに経済学を勉強する必要を痛感した。
いっぼう、彼の批判の鋭さはプロシア政府の弾圧をまねき、四三年三月、彼は『ライン新聞』を去った。
この年六月、彼はイェニーと結婚する。
マルクス二十五歳、イェニーはすでに二十九歳である。
婚約してから七年もたっていた。
新婚の喜びにひたりながらも、彼は精力的な勉強をつづける。
数ヵ月のあいだに、モンテスキュー『法の精神』、ルソー『社会契約論』、マキアベリ『君主論』など、百冊におよぶ政治学や社会学にかんする書物を読破し、ノートをとっている。
四三年十一月、かねてから計画していた『独仏年誌』発行のため、マルクス夫妻はパリに移った。
しかしこの雑誌はたった一冊刊行しただけで、つぶれてしまった。
パリで彼は亡命中の詩人ハイネと親交をむすび、革命家バクーニンやプルードンと交際するが、重要なのは、大革命の伝統をもち、サン・シモン、フーリエなどを生んだ社会主義の理論と現実をまなび、さらにスミス、リカードなど、イギリス古典派経済学の研究に没頭したことであろう。
そしてマルクスが終生の友エンゲルスをえたのも、この「革命の都」パリである。 |

マルクス夫人のイェニー
|
2.2 エンゲルスとともに top
フリードリヒ・エンゲルスは一八二〇年十一月二十八日、プロシアのライン地方、バルメンの紡績工場主の長男として生まれた。
マルクスより二歳年下である。なかなかの文学少年であったが、十八歳のとき、家業を習うため、父の会社の通信員としてブレーメンに派遣された。
彼はこのころすでに、急進的な論文を書いている。
四一年秋、兵役につき、約一年をベルリンの砲兵隊ですごすが、ここで彼は軍事問題にかんする十分な知識をえた。
しかもひまをみつけては、ベルリン大学へ聴講に出かけた。
兵役を終えると、エンゲルスはマンチェスターの父の会社に勤めるため、イギリスに行くこととなった。
途中、彼は『ライン新聞』の事務所を訪れ、ここではじめてマルクスに会った。
一八四二年十一月のことであるが、このときはまだ思想的に共鳴できず、「最初の出会いはきわめて冷たいもの」(エンゲルス)であった。
しかしマンチェスターにおちついたエンゲルスが、マルクスのしかめっつらにもめげず、イギリスの社会経済にかんする論文を『ライン新聞』に投稿しているうちに、二人の仲は接近していったものとみえる。
一八四四年夏、彼はバルメンに呼びもどされるが、このときパリに立ち寄り、マルクスと二度目の会見をした。
それは、最初の出会いとはまったく違っていた。 |

エンゲルス
|
すでにエンゲルスは、イギリスの状態にかんする研究のみならず(彼の処女作は『イギリスにおける労働者の状態』(一八四五))、古典派経済学の批判『国民経済学批判大綱』を書いており、マルクスに大きな刺激をあたえていたし、またエンゲルスも、マルクスのへーゲル『法哲学』にかんする論文に、敬服していたからである。
二人はたちまち意気投合し、『神聖家族』という題で、パウエル批判論文を共同執筆したが、それはマルクスのかっての先輩パウエル一派を神聖家族とよび、その非現実的な思弁哲学を批判したものである。
バルメンに帰ったエンゲルスは、家族のわずらわしさにたえかねて、半年あまりで一八四五年四月、マルクスのいるベルギーのブリュッセルにおもむいた。
元来、パリには多くのドイツ人の亡命社会主義者がいたが、プロシア政府はその取り締まりをフランス政府に依頼し、四五年二月、マルクスも退去命令をうけて、ブリュッセルに移っていたのだ。
二人は町はずれの貧民区に住んだ。
エンゲルスは、内妻メアリー・バーンズをつれていた。
このブリュッセル生活(一八四五〜四八)のころ、彼らは二十代の後半にさしかかっており、生活は苦しかったが、新しい世界観の創造にもえたち、研究と議論に没頭した。そしてパリの時代からこのころまでに、彼らは社会主義者となっていた。
二人の共同作業は、ヘーゲル以後の哲学を批判するという形で行なわれ、『ドイツ・イデオロギー』という著書となり、史的唯物論の基礎がすえられた。 |

マルクス関係図
|
しかしそれは生前には発行されず、一九三二年に公表された。
マルクス、エンゲルスに強い影響をあたえた哲学者の一人に、フォイェルバッハ(一八〇四〜七二)がいた。
この思想家はキリスト教を唯物論的に批判し、またヘーゲルの観念論について、精神を神聖化し、絶対化して、逆立ちしているものと批判した。
マルクスたちはこの論を熱狂的にうけいれるとともに、フォイェルバッハに欠けている実践的、社会的な人間の把握をこころみた。
すなわち歴史的存在である人間の意識は、とくにものの生産と関連して形成され、意識から生活がうまれるのではなく、生活からさまざまの意識がつくられる。
そして生産過程、それに由来する人間関係、そこに発する意識形態は弁証法的に発展してゆくのであり、歴史をこうした発展段階においてとらえる観点が、マルクス主義唯物史観の根底をつくっている。
こうしてドイツ哲学を批判したマルクスは、さらにフランス社会主義思想の清算をこころみた。
すなわち、プルードン(一八〇九〜六五)の『貧困の哲学』(一八四六)が示す一種の個人主義的な改良主義に対して、マルクスは人間の生産様式が社会関係や思想をかえるものであると、その史観を具体化するとともに、資本主義社会でブルジョワジーが成長するにつれて、新しい敵対的な階級、プロレタリアートがうまれ、階級闘争が発展することを明らかにした。
そしてこのプロレタリアートこそが、人間解放の主体的存在であり、共産主義社会をつくる任務をもつものなのである。
さらにマルクスは一八四七年末のある講演で、いわゆる剰余価値によって資本主義生産の維持拡大が行なわれることを説き、彼の経済理論の基磯をすえたが、これは少しのち『賃労働と資本』としてまとめられた。
理論とともに実践をおもんずるマルクス、エンゲルスは、社会主義者の国際的結束をよびかけ、一八四七年六月、ロンドンで「共産主義者同盟」が組織された。
目的は、「ブルジョワジーの打倒、プロレタリアートの支配……階級と私有財産制がない新しい社会の建設」であった。
この四七年十一月から十二月、共産主義者同盟の第二回大会がロンドンで開かれ、宣言の起草がマルクス、エンゲルスに一任された。
こうして翌四八年二月ロンドンで発行された小冊子こそ、有名な『共産党宣言』である。
「ヨーロッパに一つの幽霊がでる――共産主義という幽霊が」にはじまり、「万国のプロレタリアよ、団結せよ」に終わるこの宣言は、プロレタリアートの本質をとらえ、その現在の地位を示し、これからの使命を論じつつ、唯物史観、階級闘争論、共産主義およびその主義者論、プロレタリア革命におよび、いわばマルクス主義のエッセンスを示す白熱の文字である。
ときにマルクスは三十歳たらず、エンゲルス二十七歳。
2.3 ドイツ三月革命 top
『共産党宣言』が刊行された一八四八年二月は、フランスの革命と同じ月である。
ウィーン保守体制下、国土が分裂しているドイツでは、すでに自由と統一をもとめる動きが高まっていたが、二月革命はこれを大きく刺激した。`
四八年三月、まずオーストリアのウィーンに革命が起こり、多年ヨーロッパ反動の中心であった宰相メッテルニヒ(一七七三〜一八五九)は、イギリスに亡命した。
皇帝フェルディナント一世(在位一八三五〜四八)は民衆の武装組織「国民防衛軍」や言論の自由をみとめ、憲法制定議会の召集を約し、七月、普選による議会が開かれた。
オーストリアはマジャール人(ハンガリー)、チェコ人(ベーペン)、イタリア人、スラブ系の諸民族など多くの異民族からなる国である。
彼らはそれぞれにドイツ人の専制支配に反抗し、民族意識にめざめていた。
そこでハンガリー、ぺーメン、北イタリア方面で、民族解放運動の火の手があがった。
ハンガリーでは三月ごろ、コシュート(一八〇二〜九四)を中心とする民主的な独立政府が成立し、ウィーンの革命に直面している皇帝は、これを認めざるをえなかった。
ベーメンのチェコ人も自治権を獲得し、彼らはまた民族平等の原則のもとに、オーストリアの国家体制の改革などを要求した。
イタリアでは北部のベネチア、ロンバルディア地方(ウィーン会議でオーストリアが領有)には反墺暴動かあいつぎ、またサルデーニャ王国を中心に、イタリア統一戦争がオーストリアにいどまれた。
一八四八年前半、オーストリア帝国は崩壊の危機にたった。

放棄するベルリン市民(三月革命)――この頃はヨーロッパ中で革命騒ぎがあった。
マルクス・エンゲルスはケルンで世界最初のマルクス主義新聞を発行する。 |
一方、プロシアの首都ベルリンでも、四八年三月、民衆が蜂起し、国王フリードリヒ・ビルヘルム四世は言論の自由をみとめ、憲法の制定を約した。
三月末、カンプハウゼン(一八〇三〜九〇、ライン地方の資本家)を首相とする自由主義内閣が成立した。
そして五月、普選による国民議会が召集され、プロシアの憲法制定にとりかかった。
全ドイツでも、統一運動が高まる。四八年五月、フランクフルト・アム・マインの聖パウロ数会堂に、ドイツ国民議会が召集された。
そこでは官吏、弁議士、大学教授など中産階級が圧倒的多数を占めていた。
彼らは徹底的な社会革命を欲しなかった。
まず国家権力をにぎって、封建的諸国家を倒すべきであったにもかかわらず、いたずらに新憲法の審議に時をすごし、事態が反革命的な方向に急転回してゆくのを坐視することとなった。
二月革命が起こると、その影響を恐れたベルギー政府は、四八年三月はじめ、マルクスを国外に追放した。
夫妻は三人の子どもたちをつれて、パリに向かった。
フランス臨時政府は、「暴政はあなたを追いだしたが、自由フランスはふたたび門戸を開いています」と歓迎したが、この年四月、マルクスはエンゲルスとともに、ドイツのケルンに帰ってきた。
そして革命ドイツの激動のなかで、世界最初のマルクス主義の新聞ともいうべき『新ライン新聞』を発行する。
一八三〇年代からの産業革命の進展により、ドイツにおいても労働者階級が成長しつつあった。
このプロレタリアートに希望を託しつつ、二人はドイツにおける民主主義革命の成功を期待した。
新聞の第一号は六月一日にだされるが、まさにこのころ、革命は大きな転換期にさしかかる。
パリの「六月事件」はブルジョワジーの反動化をまざまざと示すであろう。
フランクフルトの国民議会は空談義の徴候をみせていた。
マルクスは、フランスのブルジョワが労働者にくわえた「白色テロ」やフランクフルト国民議会の「議会的痴呆症(ちほうしょう)」に激しい批判をあびせ、一方、イタリア独立戦争を支持している。
じじつ、革命側にブルジョワとプロレタリアとの対立がうまれてきた。
前者は急激な社会革命をおそれ、むしろ旧勢力との妥協をえらぶ。
ドイツ労働者階級もまだ未成熟である。
自由主義、議会主義も、プルジョワジーの反動化につれて形骸化してきた。
そのうえ、諸民族の運動に連絡がなかったのみならず、たがいに偏狭さをもって嫉視(しっし)、反目していた。
一度後退したものの、やがてもりかえしてきた保守勢力にとって、こうした分裂は絶好のつけ目であり、反革命の波動はしだいにひろがってゆく。
一八四八年十〜十一月、オーストリア軍は攻勢にでて、ウィーンの国民防衛軍は制圧され、四九年三月議会は解散させられ、専制政治が復活する。
これに呼応してプロシアでも、国民議会に弾圧が加えられ、すでにカンプハウゼン内閣も辞任していた。
ベルリンの国民防衛軍は武力抵抗を、そして議会は納税拒否を決議したが、むなしかった。
十一月、ベルリンはプロシア軍に占領され、やがて議会は解散を命じられる(国民をなだめるために欽定憲法が発布された)。
なおこのときマルクスは、武力抵抗と納税拒否を全面的に支持したため起訴されるが、たくみな弁論によって無罪の判決をかちとった。
こうした反革命の攻勢をまえに、フランクフルト国民議会は四九年三月、自由主義的憲法を採択するとともに、プロシア王を統一ドイツの皇帝に選出した。
しかしフリードリヒ・ビルヘルム四世は、帝冠と憲法とをすげなく拒絶してしまった。
議会は憲法の実現をうったえ、五月〜七月各地で民衆の蜂起がみられたが、このいわゆる「ドイツ帝国憲法闘争」も、プロシア軍により鎮圧され、議会も解散となった。
オーストリア内の民族独立運動も弾圧される。
「ヨーロッパの自由は、ハンガリーの戦場に賭けられていた。」
このハンガリー、最後まで反抗したハンガリーも、ロシア軍の援助をえたオーストリア軍によって、四九年夏平定された。
亡命したコシュートは諸国をまわって独立の援助をもとめたが、むなしかった。
サルデーニャによるイタリア統一戦争も失敗に終わり、各地の革命運動もついえ去った。
イギリスのチャーティスト運動もすでに四八年四月、最後の高揚をもって挫折していた。
しかし一八四八年の「ヨーロッパ革命」は、自由主義、国民主義の潮流を十九世紀史の本流にすえた意味において、社会主義のうごきを登場させた点において、一つの重大な転機を示すものといえよう。
2.4 ロンドンにて top
反革命のあらしは、当然マルクスをまきこんだ。
一八四九年五月、ケルン当局は彼の追放令をだした。
十九日、『新ライン新聞』は赤刷りの最終号を発行し、マルクスはパリに去った。
「……我々の最後の言葉は、いつどこにあっても、いわく、労働者階級の解放!」
保守化した第二共和政下のパリは、マルクスにとって、けっしてここちよいものではなかった。
四九年秋、マルクスはロンドンに移る。彼はその後、約三十五年の生涯をこの地ですごす。
この年の末、エンゲルスもロンドンに到着した。
軍隊の経験がある彼は、ある革命軍に参加し、長く語り草になるほど奮戦したが、敗北してスイスに亡命していたのだ。
ロンドンにおけるマルクスの生活は、貧乏のどん底であった。
「家のなかに文字どおり一文(いちもん)もない」こともしばしばで、イェニーは借金と質屋がよいに走りまわった。
マルクス夫妻は四人の娘と二人の息子のうち、長男、二男、三女を貧困のうちに失った。
葬式の費用もなく、近所から借りた二ポンドで、小さい棺が用意されたこともあった。
裕福な家庭に育ったイェニーは、家計のやりくりがへたで、浪費的な点があったともいわれる。
しかしマルクスは屈しないで、とくに経済学の研究をつづけた。
彼の勉強の場所は、「無尽蔵の蔵書」がおさめられている大英博物館の図書室であった(彼がつくったノートは、いまの大学ノートで数百冊におよぶという)。
生活の資をうるために、ジャーナリスティックな仕事に手をださざるをえなかったが、これら当時の時事評論も、マルクス主義の貴重な文献である。
一方『経済学批判』や『資本論』に結実する苦闘がつづいた。
あるとき、二人の娘にきかれたかずかずのアンケートのなかで、たとえば、
「パパの幸福感は?――たかうこと!
パパの不幸は?――屈従すること!
パパの好きな格言は?――人間的なことで、わたしの心をとらえないものは、なにもない!」
というような答えは、いかにもマルクスの人柄を語っているではないか。
こうした生活のなかで、マルクス夫妻はたがいに愛し、理解し、信頼しあっていた。
貧苦のあまり、ときには夫の心を傷つけることもあったというイェニーではあるが、つねに明朗、機知、ユーモアを失わないようにつとめた。
それはともかく、美しい夫婦愛であった。
そしてまた、うるわしい友情があった。
マンチェスターの父の会社にもどったエンゲルスは、一八六九年ころまで、実業家としても相当な手腕を発揮し、マルクスを経済的に援助したのである。
彼は三十年にわたって、返却をのぞまず、感謝を期待せず、自分の力の限度をこえてまで、この偉大な友を援助しつづけた。
一八六七年、『資本論』第一巻の校正を終えたとき、マルクスはエンゲルスに書いた。
「こうして、この一巻はでるばかりになった。
ぼくが感謝しなければならないのは、きみだけだ。
きみの犠牲がなかったならば、おそらくぼくはこの厖大(ぼうだい)な著述を、やりとおすことはできなかったろう。
ぼくはきみを抱擁する、感謝でいっぱいだ!」
ロンドンにおけるマルクスの公的生活として、注目すべきものは、第一インターナショナルとの関係であろう。
一八六〇年代になると、革命や労働運動はふたたびヨーロッパに高揚してきたが、同時に国際連帯の思想もよみがえった。
とくに一八六三年ロシアに対するポーランドの反乱を、英仏の労働者が支持したことは、両者の協力をすすめた。 |

エンゲルスとマルクス一家
|
そして彼らの代表を中心として、一八六四年九月二十八日ロンドンで、いわゆる「第一インターナショナル」(国際労働者協会)が成立する。
この新しい国際的組織の創立宣言と規約を起草したのが、マルタスである。
そこでは『共産党宣言』とだいたい同様に、階級闘争、労働者解放のための政党組織や政権奪取、労働者の団結などについてのべられている。
第一インターナショナルにはプルードン主義者(相互扶助に支えられた小財産制を理想とする)、労働組合主義者、バクーニン(一八一四〜七六)らの無政府主義者たちが多く、マルクスは彼らとたたかわねばならず、この点、組織は内部的にかならずしも強固ではなかった。
第一インターナシーナルの権威が高まったのは、パリ・コミューンの革命(一八七一)のときである。
マルクスはこの動きを冒険として、全面的には支持しなかったが、いったんコミューンが成立すると、この史上最初の労働者政権をもりたてようとした。
(彼はのち、『フランスの内乱』にまとめられたインターの三つの声明で、この事件のすぐれた分析を示した)
パリ・コミューンは短期間で失敗したが、この事件によって、諸国の支配階級はインターに対する警戒と弾圧を強化した。そして内部分裂も加わり、一八七六年七月、解散のやむなきにいたった。
しかし万国の労働者の団結というマルクスの思想は、こんごも生きつづけるであろう。
2.5 永遠の眠り top
インターナショナルが創立されてから、関係者がたえずマルクス家に出入りし、活発な論議がかわされていた。
マルクス夫人は、やさしさと気品をもって、彼らにも大きな影響力をあたえた。
しかしその解散ののち、マルクスの健康は急におとろえてきた。
そこヘ一八八一年十二月、この最愛の妻イェニーの死がおとずれた。
病気はガンといわれる。
「お母さまの一生とともに、お父さまの一生も終わりました」と、末娘エリナが嘆いている。
エンゲルスもいった――「マルクスもまた死んだ。」
精神的にも肉体的にもうちひしがれたマルクスは、あちらこちらへ転地したが、健康はしだいに悪化する。
さらに大きな打撃がくわわった。
八三年一月、フランスの社会主義者と結婚していた長女イェニーが、世を去った。
悲しみのうちに八三年三月十四日、マルクス自身の死がやってきた。
六十四歳。妻とおなじくガンであったらしい。
遺体はハイゲート墓地の妻のかたわらへ埋葬された。
最後の重要な著述は、ドイツ社会主義労働党(社会民主党の前身)の妥協性を批判した『ゴータ綱領批判』である(プロレタリア独裁論が表明されている点で有名)。
「第二バイオリンひき」をもって自任したエンゲルスは、いまやマルクスに代わって「第一バイオリンひき」となった。
そしてマルクスの死後ほとんど、エンゲルスは屋根裏にしまわれていた、おびただしい原稿の整理についやした。未刊であった『資本論』の続巻を、整理、出版(第二巻・一八八五、第三巻・一八九四)したのは、むろんこのエングルスである。このほか彼は文筆活動をつづけるとともに、諸国の社会主義運動、とくにドイツの社会民主党の指導にあたり、また一八八九年成立した第二インターナショナルにも関係した。
そして九五年八月五日、マルクスのあとを追った。
七十四歳。遺言によって、火葬後の骨は波高いドーバー海峡に沈められた(内妻メアリーは、すでに一八六三年没していた)。 |
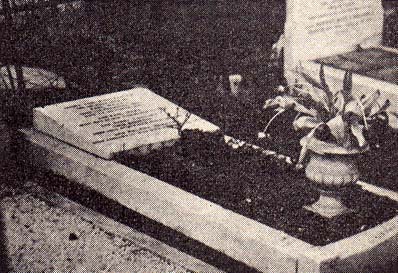
マルクスの墓

ドイツ・イデオロギーの草稿
|
top
**************************************** |