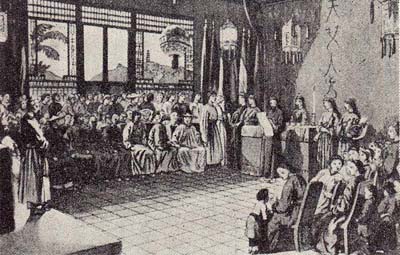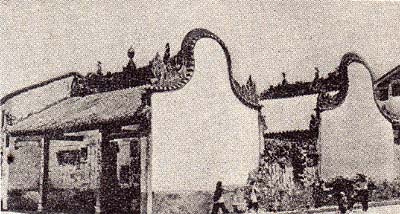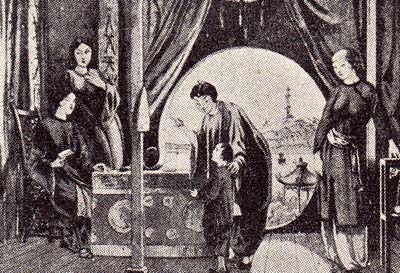|
****************************************
Index 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
世界の歴史11――帝国主義への道
13 太平天国の怒り
13.1 上帝会の誕生
top
清朝では、十八世紀後半の乾隆もなかばをすぎたころから、社会不安が深刻になり、嘉慶帝(一七九六〜一九二〇)が即位した年に、白蓮教徒の乱となって爆発した。
清朝はその平定に十年を要し、腐敗と無力ぶりを暴露した。
また嘉慶十八年(一八一三)におこった天理教徒の乱は、一時的とはいえ、北京の宮廷を、教徒の侵入により動揺させた。
乱は、ともに鎮圧されたとはいえ、国内に浸透する反乱の根を、たやすことはできなかった。
逆境におかれた貧民や少数民族の蜂起は、各地で続発し、道光帝の時代(一八二一〜五〇)には、蜂起のない年がすくないという実情であった。
イギリスとのアヘン戦争は、こうした形勢のなかで行われ、清は敗れて道光二十二年(一八四二)に南京条約をむすんだのである。
このころ広州の北方、花県というところに、洪秀全(こうしゅぜん)という人物がいた。
かれは天理教徒が華北で乱を起こした嘉慶十八年のおわりごろ、中農の家に生まれ、七歳から塾で学び、官吏を志して試験勉強にはげんだという。しかし三十歳になるまでに、四回の試験をこころみたものの、ことごとく失敗した。
村塾の先生などをしながらつづけた努力も、いまはむなしい。
傷心の洪秀全は、受験勉強に終止符をうち、清朝の官僚となることにみきりをつけた。
彼は、かつて試験をうけるために広州におもむいたとき、街角で手わたされたキリスト教の伝道書に目をとおした。
洪秀全の脳裡には、三回目の試験に失敗して帰宅したとき、失意のあまり高熱を発し、夢うつつのなかでみた光景がよみがえってきた。
それは、いま手にする伝道書の『勧世良言』に記されている内容と同じではないか。
この世を救うために、神からつかわされた自分なのだ。
洪秀全は、そう考えたという。
その限りでは、多くの宗教の創始者にまつわる伝説とかわらない。
上帝信仰を説く洪秀全の活動は、いよいよ開始されることとなる。
上帝とは、天主であり、エホバの神である。
しかし上帝は、もともと中国の天の思想に由来し、天帝をさすものである。両者の融合について、われわれは明末以来のイエズス会士の活動を思いだす。
イエズス会士は、キリスト教の布教をはかるために、中国在来の思想や習俗との調和につとめた。
あくまでも、それは伝道の手段であり、宮廷をはじめ、、中国社会の人々に接近するためのものであった。
しかし、そのために天主や上帝などの用語をあてたことは、みのがせない意味をもっている。
教義を漢訳するかぎり、その語句は生きているのである。 |

洪秀全(こうしゅぜん)
|
洪秀全は、科挙(かきょ=官吏試験)に失敗をかさねた読書人の一人である。
したがって身につけるものは、天の思想にむすびつく儒学の教養であった。
それは、あくまでも治者になろうとする者の教養である。
しかし、身につける教養が理想とする天下と、現実の天下とのあいだには、大きなちがいがある。
しかも洪秀全は、客家(ハッカ)の出身であったという。
客家とは、他地域からの移住者、外来者を指す呼称であり、古くから土着している本地人からは、とかくつめたい目でみられがちであった。
当時の広東地方には、客家の出身がきわめて多かったといわれる。
洪秀全もその一人であってみれば、矛盾した社会への不満はつよい。
そのうえ、官吏になるための試験は失敗の連続である。
こうした洪秀全が、伝導書に目をとおしたとき、あたらしい理想の世を建設しようと考えたのも、ふしぎではあるまい。
中国在来の天命とか、天徳の思想とキリスト教の上帝信仰とは、現実社会の矛盾にいきどおる読書人の洪秀全によって、融合されたのである。
それは、布教の手段として調和をはかったイエズス会士とは、立場がちがう。
「天下は、一上帝の主宰するところ、上帝が二人あるはずはない。
中国も、はじめは、帝(みかど)がこれをかえりみ、諸蕃国と同じ道をあゆんでいた。
盤古(ばんこ=中国の太古の王の名)より三代(堯・舜・禹)にいたる時代に上帝をうやまっていたことは、書の記すところである。
また商(殷)の湯(とう)王や周の文王も、上帝をうやまうこと、はなはだ鄭重であった。
ところが秦王政(始皇帝)以来、神仙思想(不老長寿を願う迷信)にまようこと二千年におよんでおり、漢の武帝や宣帝などは、はなはだしかった。
秦王政は無益にすごし、武帝は老いて後悔したとはいえ、若くして道をあやまった。
後漢の明帝は、おろかにも仏教をとりいれ、寺院を建て、わざわいをまねいた。 |
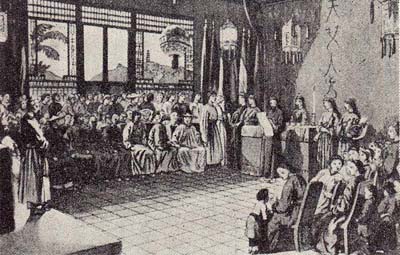
太平天国における礼拝
|
宋の徽宗(きそう)はさらにひどく、道教にとりつかれたあげく、上帝をあらためて玉皇(道教でいう天上の神)と称した。
そもそも皇上帝は、上主であり、天下の大天父である。
その尊号を伝えることは久しい。徽宗はなんたる人か。
あえて、みだりにその名を改めるとは。彼が金の捕虜となり、子とともに漠北に朽ちたのも、また当然というべきであろう。
ただ徽宗より以後、現在にいたる七百年間、そのあやまりにおぼれること深く、いまや上帝のことを講じてもこれを識る人はなく、みな閻魔(エンマ)の虜(とりこ)と化している。」 |
洪秀全(こうしゅぜん)が説く『天条書』や『三字経』の教えのなかには、このような意味の記述がある。
上帝は、この状態をいかり、中国を魔の手中から救うため、洪に大権をあたえてこの世につかわしたという。
したがって洪秀全は上帝の子となり、さらには地上の王となる。
しかも上帝エホバは天父、キリストは天兄、洪は天弟で、かつ天王であるといい、家族的秩序がかたちづくられる。
むかしから中国では、皇帝は天子といわれ、上帝や天帝の子とされる。
とすれば、上帝信仰における洪秀全の位置は、同時に中国の天の思想における天子におきかえられもする。
しかも、その秩序は中国在来の家族的秩序である。要するに、すべての人が上帝を信仰することによって、仏・道・神仙の迷信や邪教を廃し、ひいては清の皇帝をも必然的に否定することとなる。
13.2 金田村から永安へ top
上帝信仰は、花県から西方へのひろがりをしめし、隣接する広西省の東部諸県で信者の数をました。
活動した主要人物には、のちに太平天国が成立したとき王となった馮雲(ひょううん)山、楊秀清、蕭(しょう)朝貴、韋(い)昌輝、石達開がいる。
彼らは、やがて広西省の桂平県にある紫荊(しけい)山で、上帝会を結成したと伝えられるが、その間の事情についてはいろいろな記述があり、にわかに断定できない。
ともかく、のちに王となった主要人物たちは、それぞれの方法で信者をふやし、勢力をのばしたと考えられる。
信者の多くは、客家(ハッカ=よそ者)の系統のようであり、貧農や鉱山労働者をはじめ、炭焼きなどの仕事にしたがう貧困者が多かった。
しかし、地主や質屋をいとなむ者など、経済的に恵まれた者も、すくながらず参加していたようである。
上帝信仰が唯一神の信仰であり、仏教や道教や民間の迷信的信仰を、邪教としてしりぞけ、廟や神像を破壊する立場を叱る以上、既成の勢力から圧力をうけることは、必然的なことであったといえよう。
そのことは、七世紀にアラーの神を唯一の神とし、在来の諸神や偶像を否定したイスラム教がマホメットによってとなえられたとき、これにしたがう信徒たちが、他の神を信仰するメッカの貴族たちに、迫害されたことを考えれば、理解できよう。
マホメッ卜の場合は、メディナにのがれて教団の基礎をたてた。上帝会の場合は、どうであったか。
上帝会の信者たちは、家や財産を処分して、各地から桂平県の金田村に集結した。
いうまでもなく、挙兵のための集結である。
ときに道光三十年(一八五〇)半ばのことであったという。
この年正月、すでに道光帝は世を去り、第四子の奕貯(えきちょ)が十九歳で即位していた。翌年、元号を咸豊(かんぽう)と称したので、世に咸豊帝という。
金田村に集結した上帝会の信者たちは、進撃をはじめ、咸豊元年(一八五一)閠八月に、北の永安を攻略して、最初の拠点とした。このとき太平天国の建国を宣言し、洪秀全を天王としたというが、太平天国の建設は、それより早く道光三十年十二月十日(一八五一年一月十一日)、洪秀全の三十七歳の誕生日を期して行われ、同時に挙兵したともいう。
いずれにしても太平天国の建設が、咸豊(かんぽう)帝即位のはじめに行われたことは、かの白蓮教徒の乱が、嘉慶帝即位のはじめにおこされたことを、思いおこさせるものがある。偶然とはいいながら、ともに新帝の即位まもない時期であることに留意したい。
永安を拠点とした太平天国では、天王・洪秀全のもとに楊秀清を東王、蕭朝貴を西王、馮雲山を南王、韋昌輝を北王、石達開を翼王とし、丞相に秦日綱(のち燕王)・胡以胱(こいこう=のち豫王)を任ずるなど、諸制度をととのえはじめた。 |

金田村で蜂起した太平軍(浮彫)
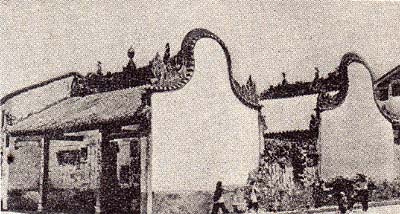
革命発祥の地、金田村の三界廟
|
そこにみられる王制や軍制に、とくにめあたらしいものがあったとはいえない。
それぞれの集団の首領的立場にあった者を、東西南北翼の各王に封じたにすぎない面もうかがわれる。
そのことは、王以下の諸官にしたがう典官、属官の数などにうかがわれる。
じじつ、天王をはじめ、諸王にしたがう典官、属官の数は一定せず、天王の場合がもっとも多い数をしめしているわけではない。
ところが燕王・豫王以下になると、位階に応じた数の規定がみられ、両者のちがいは挙兵以来の主要人物の立場をあらわしているようである。
さて永安を拠点とする太平天国の建設は、けっして順調にはすすまなかった。
清軍が劣勢をたてなおし、はげしい反攻をはじめることによって、永安は危機にさらされたのである。
「城外との交通はとざされ、糧食や弾薬は欠乏しはじめた。
包囲攻撃する官兵の大砲は城内にふりそそぎ、役所も住居も破壊された。
不安と恐怖のなかで浮き足だったものはすくなくない。
二月十六日、脱出の令が発せられた。
脱出は三隊にわかれて決行されることとなった。
章昌輝が二千余人をひきいて先行し、二番手の本隊は楊秀清、馮雲山らが五千人の軍をもって、洪秀全を擁護しながら出発することとなった。
このとき洪秀全は、婦女三十余人をともなって脱出した。
後陣をまもる第三隊は、われと蕭朝貴が一千余人をひきいて、これにあたることとなっていた。
われらが脱出するとき、洪秀全の本隊は、すでに十里のさきをすすんでいた。
われらは官兵の追撃をうけ、蕭朝貴が、わが意見をきかず、これを迎えうつことによって千余人を失い、われは、とらわれの身となった。」 |
湖南から広西におもむいて上帝会にくわわり、天徳王の称号をうけたなどといわれる洪大泉は、永安を脱出するときのようすを、このようにのべている。
記録は、彼が清軍にとらわれたときの自供であるという。
太平天国に関係する記録は、きわめて多い。
清朝の官憲による記録もあれば、西洋人の記録もある。
洪大泉や李秀成や石達開など、清側にとらわれの身となって、自供したという自述の類もある。
こういう状態で、どれがもっとも真実を伝えるものであるかの判断は、きわめて困難な問題である。
ここにあげた洪大泉の場合も、はたしてどこまでが事実であるか、にわかに断定はできない。
ことに洪大泉の場合は、洪秀全や太平天国のありかたに、きわめて批判的であったと考えられる記述がすくなくない。
「われは、王位をこのまず、先生とよばれる立場をとる。
しかし、国土を安んじようとする願いは、彼らよりはるかに高い。
妖術をもって人をまどわす洪秀全のような行為によって、大事をなしとげた例はない。
しかも、洪秀全は女色にふけり、三十六人の女をはべらしている。」 |
自述の内容はともかく、太平軍が永安を放棄し、洪大泉がとらわれたことは、まちがいない。
13.3 南京を首都に top
占領わずか六ヵ月にして、咸豊二年(一八五二)二月に永安を放棄した太平軍は、追撃する清軍に反撃をくわえつつ北上し、桂林の包囲と攻撃を開始した。
だが一ヵ月におよぶ猛攻もむなしく、桂林を攻略することはかなわなかった。
このため太平軍は、矛先をさらに北にむけ、四月に全州をおとしいれた。
その北は、湖南省である。しかし、このとき太平軍は、南王の馮雲山を失った。
挙兵以来の中心大物の一人であるだけに、その戦死は大きな痛手であったに相違ない。
それでも、勝ちにのった太平軍は湖南省に進出し、五月には道州を攻略した。
ついで江華、永明の各県をおとし、八月には湖南の要衝である長沙を包囲攻撃するにいたった。
忠王の李秀成は、太平天国末期の指導者であり、その滅亡のとき、清の捕虜となった。
彼の自供といわれる記録によれば、太平軍は湖南に進出してから、急速にふくれあがったという。
江華や永明をくだしたとき、二万人の人々が加わり、チン州で二〜三万、茶陵州で数千人の衆が太平軍に参加したという。
湖南の貧農たちが、ぞくぞくと太平軍に参加したとなれば、その進撃が活発になることも、じゅうぶん想像できるであろう。 |

太平軍進撃路地図(1)――益陽から南京までは船による快進撃
|
しかし、その大軍をもってした長沙の攻撃は、二ヵ月におよんでも成功しなかった。
長沙の攻撃において太平軍は第二の痛手をうけた。
攻城の先頭にたって指揮にあたっていた西王の蕭朝貴が、南門の外で砲弾をうけ、戦死したのである。
戦死の報はチン州に陣をおく天王や東王のもとに伝えられた。
このため、天王と東王は陣営を長沙付近にうつし、総攻撃を開始したが、おとすことはできなかった。
太平軍は長沙の囲みをとき、北上して洞庭湖の南岸に近い諸県城をおとし、西岸の常徳にいたって、この地を拠点にしようとした。
しかし、益陽をおとしいれたとき、計画は変更された。
そこで数千の舟を手にいれた太平軍は、川を下って洞庭湖にのりだし、東北岸の長江に通じる岳州に上陸して、府城を占領した。
李秀成の自述によれば、太平軍は、岳州で多くの武器を手にいれたという。
しかもその武器は、百七十年ばかり前の三藩の乱(降清漢人武将の清に対する反乱)のとき、呉三桂征討によってえた武器であったと伝えられる。
益陽で舟を手にいれ、いままた岳州で武器を大量に手にいれた太平軍は、長江の流れにのりだし、東にむかって下りはじめた。
そこは湖南省をこえた湖北の地である。
ときに咸豊二年十一月のころであった。
長江の流れにのる太平軍の進撃は早い。
またたくまに漢陽をおとしいれ、漢口をおさえ、猛攻二十余日にして、十二月はじめに武昌を占領した。
武昌にとどまること一ヵ月、準備をととのえた太平軍は、あくる咸豊三年正月ふたたび行動を開始した。
長江ぞいに水陸両路から東進する太平軍の大部隊は、旬日ならずして、江西省境の九江をおとしいれ、安徽省にはいって安慶をとり、蕪湖、太平を手中におさめた。 |

清の兵船を攻撃する太平軍
|
太平に近い長江の両岸は、五百年ばかりまえに、明の建国者朱元璋が、江北から渡江を決行し、やがて南京に都を定めたゆかりの地である。
いまや太平軍は、その地に達した。
明以来の江南の旧都、南京は目前にある。
太平軍の士気は、いよいよ高った。
いっぼう、これをむかえうつ南京城内では、不安と恐怖をましていた。
水陸より進撃してきた太平軍は、ついに南京城外に達する。
水軍は、西門にむかって集結をはじめ、陸兵は、南門外に陣をしくかの形勢にみえた。
このため南京の守兵は、西南一帯に布陣したという。
二月十日、太平軍の一隊は、東門を爆破し、城内に侵入した。
かつて武昌を攻略した際、官兵の非道をいきどおった難民が、城内から太平軍に内通し、攻略をたすけたといわれるが、南京においても、太平軍に内応するものがあったという。
腹背をつかれた防衛軍はたちまちくずれ、山をなす死体のなかで、南京は陥落した。
天王洪秀全は、群臣をひきいて堂々と南京に入城し、これを太平天国の首都とさだめた。
南京の名は、天京と改められた。
いよいよ太平天国の理想郷が、地上に建設されるべきときがきた。
永安を脱出してから、まさに一年になろうとする。
この間、六省にまたがる行程は、移動と進撃の連続であり、席のあたたまるひまはなかった。
いまや天国の都は定まったのである。
13.4 咸豊(じんぽう)は胡奴(こど=北方野蛮人)
top
「天に順(したが)うものは生き、天に逆(さから)うものは亡びる。
満州人の妖怪である咸豊(かんぽう)は、もともと胡奴(こど=北方の野蛮人)であり、わが中国の先代からの仇(かたき)である。
彼は人類を胡類にかえ、邪神を拝して真神にさからっている。
その反逆は、皇上帝のゆるさないところであり、かならず誅すべきものである。
なんじら団勇は、ものの本源を知らないで、足である胡虜を上とし、首である中国を下としてへつらい、高天の大徳に背をむけて、かたきにつかえ、蛇魔(だま=地獄の大王である閻魔(エンマ))の迷いにとりつかれ、恩をわすれ、主にそむき、中国が善土であることに思いをいたしていない。」 |
「天下は上帝の天下であり、胡虜の天下ではない。
衣食は上帝の衣食であり、胡虜の衣食ではない。
子女民人は上帝の子女民人であり、胡虜の子女民人ではない。
しかし、なげかわしいことながら、満州人の輩(やから)が、ほしいままに害毒をながして中国を混乱におとしいれてからのち、中国の広大な土地と民衆を、胡虜の支配にまかせ、平然としてあやしもうとしない。
これでもなお中国には、人材があるといえるのか。
胡虜の暴虐と流毒のはなはだしいなかにあって、中国の人々は、かえって平身低頭し、甘んじてその臣となり、下僕(しもべ)となっている。
中国に人材のないことは、まことにはなはだしいといわざるをえまい。
もともと、中国は首となるものであり、胡虜は足(あし)であるにすぎない。
中国は神州であり、胡虜は妖人である。
中国を神州と名づけるのはなぜか。
天父皇上帝は真神であり、天地山海は真神のつくるところである。
ゆえに、古くから神州の名をもって中国に名づけたものである。
胡虜を妖人とするのはなぜか。
蛇魔や邪鬼を敬拝するのは、韃靼(だったん=蒙古)の妖胡のみである。
ゆえに、当今では、胡虜を妖人と見なすのである。」 |
太平天国が、清朝の中国統治を悪魔の支配とののしる態度は、まことにはげしいものがある。
上帝と中国古来の天帝とを一致させ、これを真の神とみなし、真神の創造した中国を神州とよぶ。
しかも、神州の中国を、邪神を崇拝する悪魔の満州人からとりもどし、中国人の神州、つまり天国をつくろうという意気ごみにみちみちている。
天京に都をさだめた太平天国が、つぎに北京をめざすであろうことは、明らかである。
詔(みことのり)して曰(い)う、
「功ある者は、封ぜられるべきであり、罪ある者は、くだすべきである。
いまや、朕(天王・洪秀全)は北燕(えん)の地(北京を指す)を妖穴(妖人の住む洞穴)とみなしている。
妖人が、その地を穢(けが)しているためである。
妖人(清をさす)に罪あり。ゆえに、その地にもまた罪がある。
これにより、直隷(ちょくれい)省(北京のある省)の名をさげて罪隷省とする。
天下の万国に朕(ちん)と名のるものが二人あるはずはなく、京(都)が二つあるはずもない。
ゆえに、ここに天京のほかに、僣越(せんえつ)にもひそかに京と称することはゆるされない。
とくに守城と出軍の将兵に、すみやかに告げるのは、このためである。
朕が北燕の地を妖穴となし、妖人をほろぼすのをまって、ふたたび北燕の名にもどすことを理解せよ。
また朕が直隷省を罪隷省となし、この省が罪をむくい、天父上帝を敬拝するようになるのをまって、罪隷の名をあらため、遷善省(善となった省の意)となすことを衆知せよ。
天下万国のものは、天父上帝が胡虜をふかく怒り、この罪人を誅するものであることを知れ。」 |
清朝を妖魔ときめつけ、かならず誅すべきことを叫びつづけてきた太平天国である。
それにこたえて、天国の傘下にくわわった数十万の将兵たちである。
天京を都としたいま、ただちに北伐にむかうのも当然である。
清朝配下にある北京付近の地を妖穴とし、直隷省の名を罪隷省と名づける詔(みことのり)は、太平天国の士気を鼓舞するものであったともいえよう。
清朝の打倒や排満と中華の回復を、上帝信仰とむすびつけたとはいえ、これほど明確にうちだしたものはすくない。
天京に位置した太平天国の軍は、休むまもなく、鎮江から対岸の揚州をおとしいれた。
二月も末に近いころである。
揚州は、華北と江南をむすぶ輸送の大動脈の南端に位置する要衝である。
咸豊三年(一八五三)四月はじめ、北伐軍は揚州を出発し、北にむかった。
ひきいるのは李開芳や林鳳祥(ほうしょう)ら、太平軍挙兵以来の猛将である。
しかし、その北伐は、五百年ぽかりまえ、明の朱元璋が第一の名将徐達らに十万の大軍をひきいさせて北伐(元朝に対する)を決行し、江北の住民に烈々たる檄文をとばしたときにくらべると、その規模においてはなはだしく小さい。これは、どうしたことであろうか。
金田村で挙兵して以来、すでに二年、永安を出発してから一年になる。ことに湖南へ進出してからのちに、天国のもとに加わるものは、十万をこえたと伝えられる。
しかも太平天国の建国を宣言し、湖南を北上するころには、排満のはげしい呼びかけが行なわれている。
にもかかわらず、はげしい口調の清朝打倒とはうらはらに、北伐軍の規模は、けっして大きくはない。
朱元璋と同様に、華北の善良なる住民への檄文は、北伐軍が進撃する途上において布告している。
しかし、そこには北伐に全力を傾けるほどの動きはない。当面の急務は天国の整備なのか。
北伐軍は、揚州を発してから半年のあいだに、北京の東方にある天津の近くまで到達している。
進撃の早さは、永安から南京にいたる早さにまさるともおとらない。 |

天平軍進撃路地図(2)――北伐
|
しかし、南京にいたるまでにも、桂林や長沙の要衝をおとすことはできなかったように、河南の要衝である開封を攻略することはできなかった。
北伐軍は迂回して、山西省から直隷省にむかい、天津にせまったのである。
だが、迅速な進撃も、そこまでであった。
清軍と対峙すること四ヵ月、北伐軍は南へ後退しはじめた。
天京からは援軍がだされたが、すでにおそかった。
援軍とかろうじて合流した北伐軍は、もはや形勢を逆転できず、咸豊五年(一八五五)、くずれ去った。
林鳳祥も李開芳もとらわれの身となり、北伐は二年にして、挫折した。
13.5 天国の理想 top
「勲臣は世々、天禄を受ける。のちにしたがって来たものは、軍ごとに、家ごとに一人の伍卒をおく。
非常のことあれば、首領はこれを統率して兵となり、敵を殺し、賊を捕えよ。
ことなければ、首領は督励して農をなし、田を耕して、上にたてまつれ。およそ田は九等にわける。」 |
「およそ田は、人口に応じてわける。
男婦を論ずることなく、その家の人数の多少をもってする。
ゆえに、人が多ければ田は多く、人がすくなければ田はすくない。
わけるにあたっては、九等の田を公平に配分する。
もし一家に六人いれば、三人には好い田を、三人には悪い田をわけ、好悪半ばするようにはかる。」 |
「およそ天下の田は、天下の人が同じように耕す。
こちらに不足があれば、あちらにうつし、あちらに不足があれば、こちらにうつす。
およそ天下の田は豊荒あい通じなければならない。
こちらが荒であれば、あちらの豊をうつして荒をうるおし、あちらが荒であれば、こちらの豊をうつしてうるおす。」 |
| 「天父上皇帝の大いなる福は、田があれば、同じく耕し、飯があれば同じく食べ、衣があれば同じくつけ、銭があれば同じく使うようにして、平等に整わない所はなく、平等に衣食のわたらない人はないところにある。」 |
「およそ男婦の、十六歳以上は、一人前の田をうけ、十五歳以下は、半分とする。
もし十六歳以上に、上上田(九等に分けた最良の田)一畝をわければ、十五歳以下はその半分とし、上上田五分をわける。もし十六歳以上に下下田三畝(九等に分けた最悪の田で、三畝が上上田の一畝にあたる)をわければ、十五歳以下には、半分の一畝五分をわける。」 |
「およそ天下には、桑をうえ、婦人は蚕(かいこ)をかい、衣服をつくることにはげめ。
天下の各家では、五羽の鶏と二頭の豚を飼(か)え。」 |
「およそ収穫のおわったときには、両司馬(二十伍卒の長)は、伍長(四伍卒の長。その編成は五家を単位とし、一伍長と四伍卒で構成)を監督して、二十五家の人々が、つぎの新穀がとれるまでの食べる量をとれ。
余りは国庫におさめよ。
穀類、衣類、家畜の類から銀銭にいたるまで、すべてそのようにせよ。」 |
「天下はみな、天父上主皇上帝の一大家族である。
天下の人々が私有として受けるものではない。
すべてのものは上主にぞくする。
上主は、これを平等公平になるように運用するものであり、これこそ、天父上主皇上帝が、とくに太平真主に命じて世をすくう旨意である。」 |
太平天国が、天京に都をさだめたのち、ただちに布告したといわれる天朝田畝(てんちょうでんぽ)制度には、このようなことが、こまごまと記されている。
そこにあるものは、まさに、天下を一家とみなすものであり、すべてを平等にわけ、私有をゆるさぬきびしい態度である。
しかも、農本国家の中国における太平天国の基礎は農であり、兵農一致の体制であった。
それは、そのまま軍事編制につながる社会組織でもある。
しかも、宗教的な一つの生活規範がある。 |
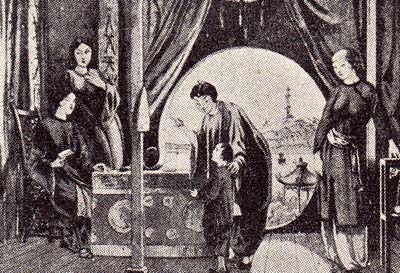
太平天国の伝道教育
|
「およそ二十五家には、国庫と礼拝堂を一つずつ設け、両司馬がそこにいる。
二十五家のなかで、婚礼その他の慶事があれば、国庫から支出する。
ただし、一銭たりとも規定をこえた使用はできない。
慶事には、一様に銭一千と穀一百斤を給する。出費には節度をもち、つねに凶荒に備えるべきである。
二十五家のなかでまかなう冶金、木工、石工などの仕事は、伍長や伍卒をもって、これにあて、農業の合間(あいま)にすべきである。」 |
「およそ両司馬は、二十五家の慶事などを処理し、すべて、天父上主皇上帝を拝して報告しなければならない。
また、いっさいの旧時の悪習は、ことごとく除かなければならない。
二十五家の童子は、毎日礼拝堂におもむく。
両司馬は、旧約聖書、新約聖書、真命詔旨(おおもこと)書を読み、教えなければならない。
およそ日曜日には、伍長は、それぞれ男婦をひきつれて礼拝堂にいたり、男女の別をわきまえ、道理をきき、天父上主皇上帝をたたえまつらなければならない。」 |
「およそ二十五家のなかで、農につとめるものは賞し、農をなまけるものは罰をうける。
家に争いごとやうったえごとがあれば、両司馬は、その是非をただし、上司に告げよ。
上司は合議して、法にしたがって判断し、つぎつぎと所属の上司につげて天王に奏上する。
天王は、それにもとづいて断をくだす。
生きるも死ぬも、あたえるも奪うも、すべて最高の上司である軍師が、天王の主旨にしたがって決定する。」 |
「天下の官民で、天条十款(十ヵ条のいましめ)をまもり、命令にしたがい、忠をつくし、国にむくいるものは、忠なるものとし、下級のものは高位にのぽらせ、その官をつがせる。
もし官にあって、天条十款(かん)をおかし、命にしたがわず、賄賂をむさぼり、悪にふけるものは、奸なるものとし、高位のものは下級にくだし、あるいは農とする。
民にして、よく天条にしたがい、命にふくし、農につとめるものは、賢者となし、良者となして、あるいは挙用し、あるいは賞をあたえる。
もし、民にして条令にそむき、農をなまけるものは、悪人となし、あるいは誅し、あるいは罰する。
毎年、人材を登用して諸官の欠員をおぎなう。
人材を推挙した保挙(推薦した人)は、賞をうけ、人材でない者を推挙した保挙は罰をうける。」 |
生活規範や信賞必罰、人材登用など、上帝のもとにおける規定は、かぎりがない。
農本国家である太平天国の理想とするものの多くは、中国の古典やキリスト教の聖書からくみとっていた。
13.6 自滅への道 top
理想の天国をうちたてるため、きびしい軍律と生活規範をさだめ、古い悪習をたち、邪教をしりぞけ、悪魔ともいうべき胡族の清朝を打倒すべきことを強調した洪秀全たちであった。
天朝田畝制度といい、天条十款といい、説くところは、きわめて理想的な世界の建設を目ざすものであった。
明にせよ、清にせよ、建国の祖となるものは、多かれすくなかれ、その時点の社会の矛盾や、民衆の苦しみを指摘し、官僚の横暴をいましめ、軍紀の厳正をとき、貧民の救済を政策の一つとした。
しかし、そのよるところは、儒家の思想を一歩もでなかった。
その点、信仰をもって共通のよりどころとした太平天国の場合は、これまでに例をみない要素をくわえている。
ことにキリスト教的信仰を基礎としたことは、生活規範をいっそうきびしいものとした。
纏足(てんそく)を禁止し、胡俗の弁髪(べんぱつ)をやめ(このため清側から長髪賊とか、髪逆などと呼ばれた)、アヘンの吸飲や賭博を厳禁し、飲酒や喫煙の禁止にまでおよぶ禁令は、きびしすぎるほどの徹底さをしめしている。
しかし、それが旧来の民間信仰や仏教、道教などを邪教としてしりぞけ、寺観、神廟、神像などを破壊する行動にでたことは、旧習をうちやぶろうとするなかで、あまりにも理想にすぎ、かならずしも全面的支持をえられないものがあったことを否定できまい。
それは、やがて、外国の圧力によって、清朝が、キリスト教の布教の自由を認めたとき、太平天国とは、事情が異なるにせよ、民間で激しい仇教(キリスト教反対)運動が展開されたことからも推測される。
理想と現実は、しばしば遊離する。天国は、軍民にきびしい規範を強制した。
しかし、それをくずしたのは、上帝会以来の主導者ともいうべき諸王であった。
中国諸王朝が、しばしばあゆんだ「一将功なりて、万骨枯る」から、「建国なりて功臣消ゆ」というおきまりのコースそのままではないが、大同小異の「建国なりて、諸王争う」という事態をおこし、自滅にみちびくわざわいの種(たね)をまくにいたったのである。
天京に定住してからのちの天王は、すくながらぬ詔書類をだし、新制度を布告している。
しかしながら、その内容と天王・洪秀全みずからの行動とは、一致するものではなかった。
洪秀全は、いつしか中国在来の皇帝と同じような生活にあこがれるようになり、政治をかえりみず、内廷に多くの美女をひきいれて、享楽の毎日をおくるようになったという。
天王の政治放棄にかわって、政治を左右し、実権をにぎったのは、東王・楊秀清であった。
「東王の命令はきびしく、軍民は、これを畏(おそ)れた。彼は自己の威風をたかめ、これを卑下することを知らない。
北王・韋昌輝と翼王・石達開をはじめ、秦日昌らは、心を一つにし、家にあって、ともに事を議する人たちであった。
かれらは、東王の専権がはなはだしくなるにつれ、表面をつくろいながらも、心中では、うらみや怒りをましていた。
北王と翼王の二人は、心をおなじくしていた。
東王への怒りから、二王はひそかに、東王の殺害を謀議するにいたった。
ときに、天王の信頼をうけて実権をにぎる東王は、天王にかわろうとする野心をいだきはじめていた。
たまりかねた北王は、東王を殺し、配下の一族をはじめ、文武大小の官員から男婦にいたるまで、みなごろしにした。
東王とその兄弟など、数人を殺すという約束をやぶった北王にたいして、翼王は怒つた。
北王は、さらに翼王をも殺そうとした。
これを知った翼王は、天京を脱出した。
しかし、天京にのこした翼王の家族は、ことごとく北王の手によって殺された。
北王は、朝にあって実権をにぎり、文武大小の官員男女をみだりに殺害するようになった。
このため内外の衆は、心をあわせて北王を殺害し、その首を翼王にしめした。
翼王は、ふたたび天京にかえり、政務をとるようになった。
衆人は大いによろこんだが、天王は、これをこころよく思わなかった。
天王は、もっぱら長兄の安王洪仁発と、次兄の福王洪仁達を用いた。
しかし無能な二人の王を、衆人はよろこばなかった。
翼王は、天王のやりかたに絶望し、天京を去った。
遠征にでた翼王は、もはや天京にかえることはなかった。」 |
李秀成の自述は、天京での諸王たちの争いを、このように記している。
天王をはじめとする諸王たちのみにくい争いが、多くの血を流したことは、記録にみえる。
東王・楊秀清の殺害に際しては、万余のものが殺されたという。
はげしい争いがくりひろげられ、殺害がくりかえされたのは、咸豊六年から七年のあいだであった。
北伐軍が崩壊した翌年である。
天京にいたるまでに、南王馮雲山と西王蕭朝貴をうしない、天京にいたって東王・楊秀清と北王・章昌輝は殺害された。
のこる翼王・石達開も天京を去って、ふたたびかえらない。
太平天国の建国にさいし、王に封じた五王はすべて天王のもとから消えた。
天王のたのみとするものは、もはや一族のみという事態となった。
自滅への道をあゆみはじめた太平天国のなかにあって、なお、その軍事力をささえ、献身的な活動をつづけたのは、忠王の李秀成と英王の陳玉成たちであった。
そのころ、天京を去った石達開は、各地を転戦しつつ、西へむかっていた。 |

忠王・李秀成
|
金田村に集結してから六年、太平天国の建設を宣言し、永安から天京に進出して、ここを都とさだめてから三年。
理想の天国は、その足もとからゆるぎはじめた。
かかげる理想は、多くの貧しい人々の心を動かし、天国の軍民は、社会不安や矛盾の克服に大きな期待をかけていた。
けれども理想と現実は、ついに遊離してしまった。
主導者が内争によって自滅し、天王が政治をかえりみないとなれば、理想の天国は、未完成のままに、くずれざるをえない。
ときに、清朝も第二次のアヘン戦争ともいうべきアロー戦争にくるしみ、華北では捻(ねん)の反抗にくるしめられていた。
清側の反攻が意のままにならない好機に、天国もまた自滅の道をあゆむとあっては、理想の実現はのぞみえない。
かかげた理想のかずかずは、のちの世に託された。
同治三年(一八六四)六月、清朝を援助する漢人官僚の軍隊や外国人の協力によって天京南京は陥落した。
そのすこしまえ、天正洪秀全はみずから命を絶っていた。
top
**************************************** |