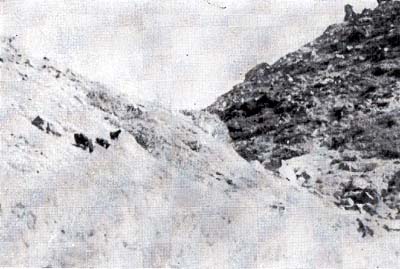|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章
一章 森の王者
1 原始林の旅 top
① クラーク先生を想う
|

エルムの樹蔭しすかな北海道大学校庭
|

クラーク先生か別れをつげた島松駅頭の記念碑
(前列中央が著者)
|
明治十年四月十六日、北海道島松駅頭に「ボーイズ・ビー・アンビシャス」という、名高い言葉を残して、クラーク先生が故国アメリカに帰られて以来、札幌農学校ではホイラー教授を教頭に任じ、生徒一同恩師の訓言(くんげん)を肝に銘じて、学びの道にいそしんでいた。
そのうち、藻岩山も手稲山も全山みどりにつつまれて、待望の夏休みがやってきた。 |
はなたれた籠の鳥の喜びを胸にいだいて、故郷の空へ旅立って行った二三の者をのぞき、のこった生徒は二班にわかれ、ホイーラー教授を班長として豊平川をさかのぼり、胆振(いぶり)方面に進出する新道の測量をこころみる測量隊と、ペンハロー教授を班長として人跡まれな石狩川をさかのぼり、空知川にわけ入って、無限の宝庫石狩炭田の地理的調査を行う探検隊とが組織された。
後者はそうとう大規模な計画で、筆者の父大島正健(札幌農学校第一期性)をはじめ、学生六名をひきいたペンハロー教授の本隊に、物資をはこぶアイヌの人夫十名がしたがった。
その所要日数も五十日という長さでもあり、測量隊にくらべて人数もおおかっただけに、頤(あご)をはずすようなおもしろい語り草が世に残された。
② 奇妙な顔のアイヌ top
引連れたアイヌの人夫の中に、つぶれた片目が口のところまで垂れ下がった姿の男がいた。
右と左がちぐはぐな人間の顔は、じつに奇妙なものだが、じつはこのアイヌこそ、力強いヒグマを噛み殺した、すばらしい勇士であった。
涼風が袂をはらって、野山がようやく紅葉になろうとするころ、空をおおわんばかりにしげっていたくるみの木の葉が、一つ二つ混ぜに舞い、うれたくるみがぽたりぽたりと地におちる。
そして熊笹が生いしげった山路に、厚い皮をかぷったうまそうな果実がいっぱいになる。
しかし人跡まれな深山のこととて、天のあたえたこの宝をひろう人もなく、くるみはやがてくる春の芽生えを待つばかりである。
しかし、充分な腹ごしらえをして、冬籠りのしたくをしなければならぬ山の王者熊どもがどうしてそれを見逃そう。
熊笹をカザコフとかきわけ、爛々(らんらん)たる目をかがやかしながら、二頭、三頭また四頭、くるみの木をめぐって、おちたくるみをうばいあう熊どもの姿はなかなかの壮観である。
ここは十勝の奥のアイヌ部落、澄みわたる秋の空に、心もうきたった若者の一人が、はるかにひびく熊のうなり声を目あてに、弓に毒矢をつがえて、目ざすくるみ林へ進んで行った。
すこし小高い丘の上に立って、行く手を見おろすと、こんもりとしげった熊笹の中から、高くそびえている一本のくるみの木が目についた。そして風はないのに、そのあたりの笹の葉がざわざわと波打っていた。
さては、と抜足さし足、その場に近づき、熊笹のすきまからにゅっと顔をだしてみたら、なんと五頭の大熊がいた。
それらがまた人の匂いに感づいたか、大手をひろげてすっくとばかりに立ちあがっていた。
若者もさるもの、ねらいすました第一の毒矢を、弦をしぼってびゅーつとはなった。
瞬間、脳天を射られた一頭の大熊が、地響き打ってドウとたおれる、つづいて一頭また二頭、いじのわるそうな五頭目をねらって、最後の矢をつがえた刹那、敵は飛鳥のごとくアイヌに飛びついて来た。
負けぬ気の若者は渾身の力をこめてねじあったが、なにをこしゃくなと、怒れる熊は大きな掌で若者の顔に一撃をあたえ、顔面をむちゃくちゃにかきむしって、右の眼球をどこかへ消しとばしてしまった。
しかし、なおも激闘数刻、さすがの大熊も戦いつかれたのであろう。
長距離を走りとおした犬か馬のように、はっはっと大息をつきながら舌をだらりとたらし、下になったアイヌの顔を、じっと見おろしていた。
それと感づいた盲目のアイヌは、手をのべてほとんど無意識にその舌をにぎりしめ、噛みつこうと顔をよせて来た熊の口を押しのけて、その舌にがぶっと噛みついた。
アイヌはついに熊の舌を噛み切ってしまったが、やがて夜露に打たれて、長い長い夢から目ざめたとき、この勇敢なアイヌの若者は自分と枕をならべてたおれている大熊のなきがらを、そこに見いだした。
そしてはるかな谷底を流れる水の音に耳をすまし、熊笹をかきわけかきわけ、ようやく流れのほとりににじりよって、玉とわく真清水に喉をうるおした。
気の強い若者は、流れの音をたよりに、手さぐりで里と思われるほうにはい出たが、それから幾日かかかって、この勇士はようやく救われて部落に帰ることができた。
そのときの傷のため、“すがめ”の妙な顔になってしまったが、傷は全く癒(い)えて、今度の探検隊の人夫にくわわっていたのである。
③ 芦別川をさかのぼる top
ベンハロー教授の一行が、糧食その他の必要品を満載した特別仕立ての和船に身をたくし、札幌の郊外を流れる豊平川をくだりだしたのは、七月なかばのことであった。
やがて江別にたっして石狩の本流に棹(さお)さし、元気いっぱいで一望はてしなき石狩原野にわけ入ったが、役立つと思って工夫をこらしたその和船が、流れの急な石狩の本流に入るとともに役立たなくなり、いたしかたなく、アイヌのいうがままに物資を独木舟に積みかえた。
そして、ゆるやかな流れに出ると、みな舟に乗り、急流にかかれば船頭だけのこして、あし生いしげる河岸を歩行した。
一行がそれからあゆみを転じて、さらに深くわけ入ったのは、空知川の流域であった。 |

親仔づれの熊
|
これは石狩川の最大の支流で、十勝日高の西斜面にみなもとを発し、富良野盆地を北流して夕張山脈を横断し、ここで空知川峡谷を形成しつつ滝川平野に出て、芦別川をあわせて石狩の本流にはいるのであるが、今日ではこの流れにそって、根室本線が通過し、鉄路はえんえん狩勝峠に向っている。
しかし、当時このあたりは、大熊が出没するうっそうとした原始林で、道路などあろうはずがなく、沢また沢をわたり、岩をよじ、いばらをわけて進むありさまであったから、踏査の危険と困難とは想像のほかであった。
④ 熊の巣にいどむ top
歌志内といえば、砂川から分派する鉄道の終点で、付近にいくた著名な炭坑があり、北に行けばただちに空知平野に出ることができる要地となっている。
しかしこのあたりこそ、その当時、能一の出没のもっともさかんであったところで、探検隊が河岸に天幕を張って眠りにつくと、どこからともなく、出て来る熊どもが、張り綱を引っぱって天幕をゆり動かし、一同の胆をひやさせることが何回あったかわからない。
北海道の宝庫石狩炭田の開発がはじまったのは、明治十二年二月のことであるから、ペンハロー教授の一行が空知川をさかのぼり、さらにその支流である芦別川流域にふみ入って、石狩炭田の北方に進出したときは、あたりには炭坑など全くなく、付近一帯は真に人跡未踏の処女地であった。 |

流れに坐して鱒をすなどる
|

|
空知川から芦別川にあゆみを進めた一行は、日ごとの悪路で荷物の運搬になやまされ、相談の結果、糧食は各自必要量だけを携行し、帰路の分は道すじの要所要所にのこし、雨をふせぐだけの用意をしておくことにした。
熊は元来雑食性のもので、植物性の食物もとるし動物性の食物もとる。
ことに春の雪どけのころに、残雪のあいだから出るふきのとうが大好物であるが、その頃には谷川の氷はとけて清い流れが顔をだすから、その中にひそんでいるザリガニをさがして飽食(ほうしょく)する。
新緑のころになって熊笹の中に顔をだすエゾカンゾウやギボウシの葉、さてはまた秋のコケモモや山ブドウなど、山には熊の大好物がたくさんある。
また秋たけて産卵床にいそぐ鮭や鱒を、たくみにすなどる能の姿に接する場合もまれではない。
その頃の熊は冬籠りのために、充分の栄養分を身にたくわえねばならないので、きわめて貪食(どんしょく)となり、里に出て人畜をもおそうようになる。
初秋のころの熊の食欲はものすごく、近来は山をおりて来ては、さかんに農耕地を荒らすようになった。
もっともこのんで喰べるのは燕麦(えんばく)で、トウモロコシやリンゴなども、そうとうに喰い荒す。
さて、軽装した探検隊の一行が芦別川に沿って進んで行ったところが、折から鱒(ます)の産卵期であったので、急流をおどり越えては上流にさかのぼる魚の群が、流れにひしめく壮観さは言語にぜっするありさまであった。
アイヌは普通マレップと称する独特な投げ槍でこれを突いて捕るが、学生たちは即製のやなぎの胴で、数多く鱒を生捕って来たので、おかけで連日の副食物にはことかくことがなかったが、食塩が早くも欠乏し、大きな鱒を木の枝に突きさして火であぷり、塩気なしでそのままかぶりつく日がつづくようになった。
いくらうまい鱒でも、白焼きには降参したと後年参加者の一人が物語っていた。 |

秋の味覚の王者鮭(さけ)

マレップ(投槍)を手にして鱒をねらうアイヌ
|
夢にも人に会わぬ原始林の旅は、しばらくはことなく進行したが、行くにつれて芦別川の両岸がせまって映谷となり、岩を噛む激流が絶壁のあいだを流れて、進む道もない場所にやって来た。
一行は河岸に切り立った絶壁にヤモリのごとく張りつき、一列横隊になって、大の字に手足をふんばって、先行する者のふんだ岩角をたどっては、藍(あい)をたたえる深淵を越えて行こうとしたところが、先頭をうけたまわった学生の一人が、まがり角にたっして顔をかなたにふり向けると同時に、
「いたっ!」
と奇声を発したまま、岩にしがみついてしまった。
行手の流れにものすごい熊ががんばって鱒をつかまえていたのである。
進むに進まれず、しりぞくにしりぞかれず、青くなった一同は、手足をふんばったまま岩壁に張りついてしまった。
⑤ 凱歌(がいか)をあげて top
かような難行苦行をかされて、一行は芦別川の水源目ざして突進したが、ある日のこと断崖絶壁そびえ立ち、翼なくてはとび越えがたい地点に到達し、うらみをのんで引きかえさねばならぬこととなった。
地図はなし、測量をこころみたわけではなし、日々の行程を歩測(ほそく)によって記入しておくありさまであったので、探検を中止した場所がどこであったやら、今となっては知るすべもない。
まさに開発の機運にあった石狩炭田地域の、地理的調査を遂行し得たことを、せめてものなぐさめとして、一行はふみわけた道を逆行し、更にまた幾春別川をさかのばった。
この河岸で発見した、見事なアンモナイトの化石層は、学界の珍品として今なお貴重視されているところで、この発見だけでも一行の探検は、すこぶる意義のふかいものとなった。
風雨にたえた五十有余日の敢闘をおわって、いよいよなつかしの学窓に帰着しようとしたとき、学生中の長老で後の北大総長となった佐藤昌介は、
石狩原野 月上ること初(はじめ)なり
豊平河岸雨晴るるの余
四旬の征旅(せいりょう)帰心切なり
夜を徹し程(てい)を益(ま)して学盧(がくろ)に入(い)る |
と一詩を賦(ふ)して、その感懐をのべたが、北海道の大自然にはぐくまれた先哲の若かりし日の足跡をしのぶことは、けっして無益のわざではなかろうと思う。
2 厚岸(あっけし)の金毛(きんけ)熊 top
熊話がなくては本当でないように思われていた北海道の熊も、開墾の手がとどくにつれて、その安住の地をうばわれ、はるかに海をへだてて千島の一角を望見する知床半島方面においこめられてしまうようになった。
したがっておそろしい熊物語も、今日では釧路や根室方面に足をはこばねば、そのスリルをあじわいかねるような状態になっているが、ここに書きしるすのは、北海道大学の犬飼哲夫教授が阿寒湖畔に居住するアイヌで、無双の熊捕りときこえた土佐藤太からききとられた実話と、北海道大学の雨龍(うりゅう)の演習林付近で起った惨劇のありさまである。 |

国立公園阿寒湖の景観
|
① 森林主事襲わる
|

からだをゆすぶって進んで来る
|

大きな熊がこちらを眺めていた
|
指折りかぞえれば、今から二十数年も昔のことであるが、釧路の真龍駐在であった森林主事宮崎富次郎が、天高く澄みわたったある秋の日、ほど遠からぬ糸魚沢(いといざわ)の払下官林伐採地の伐根(ばっこん)調査のために、宗井宗吉、後藤与吉の両名と、厚岸湖にそそぐ別寒辺(べかんぺ)牛川をさかのぼり、一里半ばかり山にはいって現場の調査を行った。
この付近は見わたすかぎりの草原で、立木はすくなく、展望もよくきいていたうえに、この日はめずらしい晴天であったので、おそろしい熊の襲撃などは夢にも考えず、だいたいの調査がおわった一行は、昼食をおわってから、心地よい秋風に送られながらゆうゆうと帰路についた。
笑い話に興じながら、一行が眺望台と呼ばれる小高い丘にさしかかったさい、行く手の草むらの中に異様な物音がした。
まさか熊とは思わず立ちどまった一同が、じっと目をすえて見ると、突然黒い大きな動物が動いたので、やっと、熊だなということに気がついた。
山の王者である熊も人間だけはおそろしいのだ。こちらが人間さまであることがわかれば、彼はたちまち退散するのだとかねがねきいていた四人は、まず声をそろえてどなってみた。
しかし相手の熊はおどろくようすもなく、首をひくくたれ、右に左にからだをゆすぶって進んで来たので、以前に熊にあった経験のある後藤は、
「あの熊はすこしおかしいぞ」
と注意を発しながら一同を誘って熊の姿が見えない丘の反対がわに迂回した。にらみあった熊が追って来る気配もなかったので、やれやれと一同が胸をなでおろしたのも束の間、姿をかき消したと思った大熊は、丘の裾をまわって行く道の目前に、突然立ちだかり、真正面からウオッとうなってとびかかって来た。
あまりとっさの場合なので、宗井はむちゅうになって、道ばたのにれの木によじのぽったが、ちんばであった後藤は、やむなく草の中に腹ばいに身を伏せた。
ためらっていた馬場も、死んだ振りをしていると熊は喰わぬときいていたので、後藤のあとを追って同じく身を伏せた。
怒れる熊は木によじた宗井にせまり、樹幹にとりつくなり手をのばして宗井の足に手をかけた。
失心しそうになった宗井は、頭上にあった太い枝にしがみつき、足を振り振り相手を蹴とばし、五分間あまりも死の敢闘をつづけたのであった。
その後どの位たったか――ようやくわれにかえって、おそるおそる木の根本をながめたら、どこへ退散したのか、おそろしい熊の姿はもう見えなかった。
ただ草むらに伏している僚友二人の無事な姿が目にはいったので、
「熊はいないぞ」
と樹上から呼びかけた。
夢からさめたように、後藤と馬場とは立ちあがり、そのにれの木の根元に近づいて来たが、後藤は伏していた自分の上を熊公がおそろしいいきおいでとび越えたことを意識していた。
それにもかかわらず、二人ともかすり傷一つ負っていなかったので、これはふしぎとかたりあっその刹那、はじめて宮崎主事の姿が見えないことがついた。
声をそろえて呼んでみたがなんの答えもない。
ひとかたまりになった三人は、おそるおそるあたりをさがしてみたところが、にれの木から五十メートルあまりをへだてた丈なす草むらの中に、宮崎主事の帽子がおちていた。
つづいて鮮血にそまった外套とシャツの破片が散らばっているのが目についた。あたりの草はすっかりふみにじられ、そのさきの深い熊笹の中に血痕(けっこん)がつづいていた。
こうして主事が、いつの間にかやられたことが確実となった。
ふと向うの丘の上を見ると、大きな熊がスックと立ちあがり、舌なめずりをしながらこちらをながめていた。
三人はぞっとしてわなわなとふるえていたが、やっと思いついてマッチをとりだすより早く、あたりの熊笹に火をはなった。
さいわいにして、火は燃えひろがって熊のいるほうにせまって行ったが、どうしたことか彼はおどろきもサず、爛々(らんらん)たる目をかがやかせながら、じっと焔を見つめていた。
このまにと三人はじりじりと後退し、熊の視界をはなれるやいなや脱兎のごとく逃げだしてようやく日暮れに糸魚沢(いといざわ)の民家にたどりついた。
息せき切って逃げこんで来た三人から、事のしだいをききとっだ村の人々は、とりあえず宮崎主事や救わねばと、屈強の銃手両三名を遭難現場に送ったが、その日はなんら得るところなくして、一同は引きかえした。
不安な一夜はあけそめた。早朝からせいぞろいをした、茶内、糸魚沢、真龍(しんりゅう)などの諸部落の青年団消防隊六十余人が三隊にわかれ、警戒おさおさおこたりなく、現地に押しよせたが、眺望台にたっしてみたら、ずぶとい熊はまだ去りもやらず、悠然とせまりきたる者どもをにらんでいた。
おのれっ、と銃手の一人がぶっぱなした弾丸は相手の頭上を越え、あざ笑うがごとく熊は深い熊笹の中に姿をかき消してしまった。
なにかうまいものを喰っていたらしいようすだったので、熊のいた付近や捜索してみたら、なかば土と草とておおいかくされ、腕は折られ大腿部は喰いつくされた、見るも無残な宮崎主事の屍体が現れてきた。
この日は主事のなきがらを収容して引きあげ、翌日から本格的な熊狩りが続行されたが、逃げ去った熊はついに姿を現さず、いたしかたなくて捜査は一時打ち切りとなった。
|

熊祭り
アイヌ部落でおこなわれる一番盛大な行事。メノコ(アイヌの女)が育てた仔熊を曳きだし、若者か槍をふるって突き殺すのである。
|
② おどリ出た大熊 top
|
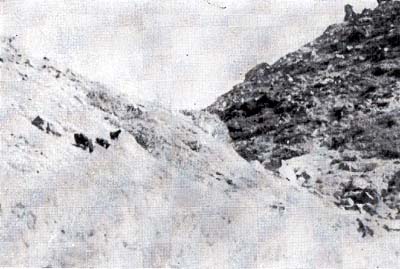
大雪山腹に遊ぶ熊の親仔(犬飼哲夫氏より贈らる)
|

吼ゆる密林の王者
|
ところがそれから約二週日をへて、同じ熊らしいものが、遭難現場から十数里をへだてた太田村のチャンベツに姿を現した。
宮崎主事が住んでいた真龍には、三井物産の造山部の事務所があり、そこに勤めていた、干場(かんば)甚作、小納谷(おなや)久吉、野呂田(のろた)長治、西(にし)太郎の四名が、きたるべき冬山の造材準備として、道路を作るべくチャンベツに出かけたが、仕事をおわって帰る途中、行手にあたって突然大熊があらわれた。
一同が、「熊だっ」と叫んだとたん、青年西はくびすをかえして脱兎のごとく逃げ去ったが他の三人は胆をつぶしてまごまごするばかり。
それと見た熊は、一同を目かけて猛然と突進して来る。そこで干場と野呂田とはかさなりあうように路傍の立木によじのぼり、小納谷はなすすべもなく地面に身を伏せて死んだ真似をした。
せまりきたった熊は、二人の人間がしがみついている木の幹がすこしななめになっているのを見すまし、根元からそろりそろりとのぼって来た。
危難が身にせまった二人の中で熊に近かった野呂田は、腰にした鉈をぬきとって振りまわし、大声でどなりながら防戦していたが、そのとき、死をよそおっていた小納谷が、よせばよかったのに、
「あまりさわぐと、かえって悪いぞ」
と熊にきこえないつもりで小声で注意した。
人声をききつけた熊は、樹上の二人をすてて地におり立ち、注意ぶかく小納谷のほうにあゆみよった。そして息をころして地に伏せていた小納谷のまわりを、ひとめぐりしてから、いきなり頭にかぶりついた。
痛さをこらえてなおも動かずにいると、今度は肩のあたりを、がぶりと喰いついた。もはやこれまでと起きなおった小納谷が、右手にしっかと鉈(なた)をにぎりしめ、一振り二振り力をこめて熊の面部をめった打ちにした。
不意をくらった熊は、耳のつけ根から鮮血を流しながら、もんどり打ってたおれたが、そのひまに起きあがった小納谷は、鉈(なた)をふりまわしながら熊を威嚇し、じりじりと後退しながら、さぐりあてた大きな木に手早くよじのぼった。
まもなく立ちなおった大熊は、怒り心頭に発したものと見えて、その木の根元にせまり、金毛をさかだててウオッとうなる。
そして幹に手をかけてのぼろうとすると、樹上の小納谷はけんめいに鉈をふるってこれをふせぐ。
あきらめた熊は、とってかえして野呂田たちの木に迫る。
往きつもどりつしているうちに、日はとっぷりと暮れてきた。
生きた心地もない樹上の人間たちの口からもれる念仏の声を尻目に、いつか熊は闇に姿をかき消した。
さればとて、危険が全く去ったとは思われないので、三人は夜を徹して木にしがみついていたが、救いをもとめたところで人里はなれた山路で、なんともいたしかたがない。
夜の白むのを待って、つかれはてた干場がまず木からおりて根元で火をたき、ついで他の二人も地上の人となってあたりを探索し、熊がいないという見とおしがつくやいなや、脱兎のごとく山を馳せおりて民家にたどりついた。
さっそく食事をもとめて元気をとりもどしたうえ、九死に一生を得て真龍に帰ることができた。
小納谷の傷はかなり深手で、さっそく病院に収容されたが、全治までには二週間を要するとのことであった。
③ 土佐藤太の手柄 top
事件が発生してから、一ヵ月あまりたったある日のことだった。 、
腕っこきのアイヌ土佐藤太が、宮崎主事が遭難したところから、やや奥の、別寒辺(べかんぺ)牛川の上流チェロで探索していると、はからずも草むらの中に寝ている大熊にめぐり会った。
しめたと勇躍した土佐は。相手から七、八間のところまでしのびより、ねらい定めて手練の第一弾をドーンとはなった。
とたんに熊はウオッと立ちあがり、死物ぐるいでとびかかって来た。
間髪を入れず射ちだされた第二弾は、見事腹部を貫通したので、痛手に弱った大熊はくびすをかえして逃げだした。
土佐はすかさず追いうちをかけて、ついにこれを打ちとめたが、多くの人の手でやっとはこびだしてみたら、なんと体重が八十貫(320kg)、身の丈六尺(180cm)にあまる雄熊で、体は見事な金毛でつつまれ、耳の下には鉈でやられたなまなましい傷痕があった。
それが小納谷にやられた傷であることはたしかで、宮崎主事を喰ったのもこれだということになったが、部落民がおそれた山の王者も、ここにようやく仇を討たれたのである。
3 雨龍(うりゅう)の惨劇 top
① お祭り帰リ
今から三十年ばかり以前のできごとであるが、その当時天塩にあった北海道大学の演習林のほとり雨龍郡沼田村の村民たちは、八月二十一日の村祭りを祝うために、村で一番にぎやかな恵比島にあつまっていた。
村の一番奥にある開墾地に住んでいる村田家の主人三太郎と妻ウメ、長男与四郎と弟の幸四郎、それに近隣の林という農夫をくわえた一行五名が、祭礼もおわった夜の十一時ごろ、おもしろかったさまざまな催し物の話などをかわしながら帰路についたときであった。
恵比島からわずかに一里もはなれたであろうか、思わぬ場所にひそんでいた大きな熊が、しのび足で一行に近より一番最後を歩いていた林の後にまわって、いきなり帯に爪をかけ、力まかせに引きもどした。
振りかえって見て熊と気づいた林は、大声で一同に危急を告げるや、いきなりせまった熊とねじあった。
さいわいに帯がとけて、するすると着衣がぬげたので、ぬけがらを熊にあずけたまま、けんめいにかけだした林は、あわてまどっている四人をはげまし、ともに行手をいそがせた。
着衣をやぶりすててせまって来た熊は、一ばん若くて足よわの幸四郎を難なく引っとらえ、腹部に一撃をくわえて即死させると、死体を引きずって森の中へ逃げ去ろうとした。 |

里を荒した金毛熊
|
それを見た母親は、ボーッとなって立ちどまってしまったが、よき獲物と思ったのか熊は幸四郎をすて、やにわに母親に向って来た。
いとしの妻があやうしと見た三太郎は、とってかえしておそろしい熊にとびかかった。おさないながら与四郎も勇気をふるい起し、狂気のようになって熊の尾にぶらさがる。
逆襲をくった熊は、たけりくるって村田の背や頭に噛みつき、与四郎に強い一撃をくわえて、父子もろとも地上にたたきたおした。
こうして熊が一息いれているすきをうかがい、むっくと起きなおった村田は、うろうろしている妻と林とをうながし、その近くにあった持田という農家に救いをもとめて逃げこんだ。
② おそろしい追撃 top
しかし荒れくるった熊は、そのあとを追って持田の家にせまって来た。
中では、みなの者が力をあわせて戸をかたくとざし、息をころして熊のようすをうかがっていたが、おりから裏庭にまわった熊は、窓のところに立ちあかって両手をかけ、目をぎょろつかせて内部をうかがった。
そのとき家の中にはランプがともしてあったが、火事を心配してフッと吹き消し、炉の中に白樺の皮を投げこんで、燃ゆる火に室内をあかあかと照らし、熊がのぞいている窓に手あたりしだい座ぶとんや枕などを投げつけながら、一同喊声をあげて威嚇してみた。
そのいきおいにびっくりしたのか、熊の顔はいったん窓から消えうせたが、今度は策戦をあらためて、表へ廻って来た。
そして扉のガラスに爪をかけヽて、かきやぶろうとしたが、なかなかガラスはやふれない。
短気な熊は、さらばと体当りをくらわせ、石のような頭をぶっつけて、ガラスをたたき割った。
そのとき、村田は重傷にあえぎながら、熊を入れまいと両手をのべて力のかぎり扉をおさえていたが、熊がガラスをたたきやぶって闖入(ちんにゅう)したとたん、熊のおもみで扉がたおれ、その下敷きになってしまった。
びっくり仰天した家の中の者は、ふとんをかぶる、便所や戸棚にかくれる、梁にあがる、という大さわぎを演じて身をかくしたが、人影がないのを見て怒りをはげしくした熊は、炉の火をふみにじり、器物をたたきこわし、大あばれにあばれて一同をヒヤヒヤさせた。
ところが村田の妻のウメだけは、子供のことが心配でたまらず、フラフラと戸外に出てしまった。
それと気がついてあとを追った熊は、たちまちウメにとびつき、抱きすくめてしまった。
玄関の扉の下敷きになりながらそのありさまをかいま見た重傷の村田は、憤然と立ちあがり、あたりにあったスコップを手にとるなり、われをわすれて戸外にとびだし、「畜生、畜生」と連呼しながら、妻をかかえている熊をぷちのめした。
しかし戦いなれた熊は、そのくらいのことは平気である。
すでに息たえたウメのむくろを引っかかえて、ほとりの笹藪の中に姿をかくしたが、そこで死体を喰い散らしているありさまが、闇をすかしてうかがわれるようであった。
③ とどめの銃火 top
大惨事をききつけた、村の青年団や消防団などが、あわてて、この山奥にかけつけて来だのは、二十二日の夕暮れ近くであった。その夜は一晩中警戒陣がはられたが、なにごともなく過ぎた。
翌日になると、この惨劇をききつけたとなり村からも、熊打ちの名人といわれる、アイヌどもをえりすぐった一隊が応援にかけつけて来た。
なかでも猛者として知られている、永江政蔵というアイヌがちそろしい熊のしわざをきくやいたく憤慨し、かならず自分の手でしとめて見せるとばかり、人々がとめるのをきかずに、単身森の奥深くわけ入った。
しかし夜になっても永江は帰らず、あべこべに熊にやられたと見られるようになり、不安はいよいよつのるばかりとなった。
そのうち、警官や御料局の人々も変をきいてかけつけ、ついに、総勢二百二十名にたっする攻撃軍が陣容をととのえることとなった。 |

打ちとめられた大熊(犬飼哲夫氏より贈らる)
|
そこで事が起ってから三日目の八月二十四日午前九時、銃士を付した七班の熊狩隊が編成されて、総攻撃にうつることとなった。
隊員一同は大喊声をあげ、各班はそれぞれきめられた進路から、ここぞと思う森林をとりまいて、しだいに環をせばめていった。
かくて正午近く、その第一班が林内十五町ほどわけ入ったとき、前衛の射手をやりすごしてから、目ざす大熊がウオッとうなって横合からおどり出た。
そして、攻撃隊の中堅としてひかえていた一青年の頭部をしたたかなぐりつけた。
不意打ちにおどろきさわぐ隊員どもを尻目にかけて、つぎに進んで来た者をまたもやはりとばしたが、そのときようやく銃士の陣立てはととのい、猛然たる一斉射撃がくわえられた。
手ごたえあって、さすがの熊もコロリとたおれたが、つるべ打ちの猛射に急所を射ぬかれたのであろう。
さすがの荒熊も二度と立ちあがって来なかった。
さて永江はどうしたろうということで、アイヌどもが捜索班を組織して森の中にわけ入ったが、熊の最期の場所からほど遠くない沢の中に、彼の無意ななきがらが発見された。
残っていたのは永江の頭と革帯と三つに折られた銃だけであった。
おそらくはかの日、彼はここでもとめる熊にめぐりあったのであろうが、銃は無念不発におわり、ついに熊との大格闘が演ぜられた結果、組みしかれてしまったのであろう。
この猛悪な一頭の熊のために、村田と熊狩隊の壮丁二名とが重傷を負い、村田の妻と愛児二名とが無残な犠牲者となった。
さてもおそろしい祭りの夜のできごとであったよと、今も土地の人々は語り伝えている。
|

動物園の金毛熊
|

巧みに流れを渡るひぐま
|
top
**************************************** |