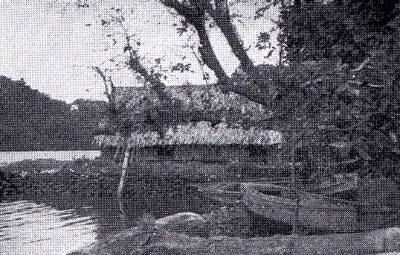|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章
十章 めざましい自然敵
1 恐ろしい大カタツムリ top
篠(しの)をつくように豪壮なスコールが過ぎ去って、さわやかな風が頬を吹き、南十字星がなごやかな姿を現すころ、しのびよる菜園の強盗を引っ捕えようとて、パラオ熱帯生物研究所にたむろする若者どもが、手に手にバケツと懐中電灯とをたずさえ、しのび足で宿舎の後園に立ちいでた。
青いもののすくない南洋群島で、天水を命の綱とたのむ住民たちが、額に汗して作る猫の額ほどの菜園を、根こそぎ喰い荒らしてしまうおそろしい害敵め――。
今夜はスコールのおしめりにいきおいを得て、ぞろぞろと出ているにちがいないぞと、畠のうねを電灯の光で、パッと照らしてみる。
いるわいるわ、大きなカタツムリがウヨウヨしている。
手ぐすねひいて敵をもとめていた若者どもによって、わずか一時間ばかりの間に、大小とりまぜ大きなバケツにあふれるほどのアフリカ大カタツムリが捕まえられた。
南洋庁当局が小学児童をはげまし、懸賞つきでその駆除に乗りだすまでになっていたおそるべき害敵アフリカ大カタツムリ、さて、ここでその身許を調べてみよう。
① アフリカ大カタツムリとは top
かって、日本の委任統治領であった南洋群島の中にある、パラオ島コロールにあった熱帯生物研究所の構内には、台湾から移植されたこのアフリカ大カタツムリが大繁殖をとげ、構内のパパイア、椰子(やし)、仏桑華(ぶっそうげ)などの、大きな樹にのぼり、ことにパパイアの樹のてっぺんに集った葉の根もとに、数十匹もむらがっているありさまであった。
また板塀や石垣の間、もしくは藪の中などその姿を見ない場所はないというありさまであった。
かれらは日中、日かげにじっと静止しているが、朝早くとか夕方になると、おもそうな貝殻を引きずって、はいまわり、蔬菜(そさい)・花卉(かき)・果樹などを喰い荒らして大被害をあたえる。 |
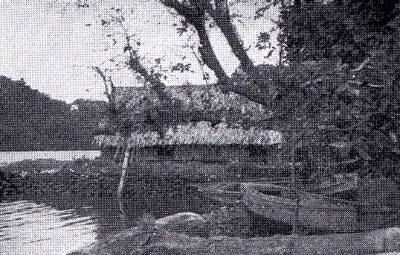
パラオ島コロール土民部落の風景
|
このカタツムリは、元来は東アフリカの原産であるが一八四六年ごろ、インドのカルカッタに移入せられて、同地方に大繁殖をとげ、一九〇〇年ごろにはセイロン島に、また一九二二年ごろにはマレー半島およびシンガポール付近に大発生し、一九二九年ごろにはボルネオ島のサラワックに、一九三三年ごろには、ジャバのバタビヤ付近に現れ、菜園の大害敵として、いたるところ大恐荒をおこさせたものである。
一方この大カタツムリは、食用価値が大なるものとして、「陸鮑(りくあわび)」などと称せられ、一獲千金をゆめみるやからがその害悪を無視して、ひそかに輸入繁殖をはかるなどのこともあって、きわめて短期間に、この大害敵が常夏の地域に予想外の繁殖をとげるようになった。
わが国においては、農作物の被害を未然にふせぐため、昭和十一年には農林当局の英断によって、これが移入を禁止してしまったが、太平洋戦争の結果、アフリカ大カタツムリの繁殖地を手中にいれた米国では、原産地との交通がひんぱんになったため、この強敵が本土上陸に成功するようになっては一大事と、おそれている。
その対策のため、農林当局は今や大わらわのありさまであるという。
② ダビデとゴリアテ top
アフリカ大カタツムリの老成したものは貝殼の長さが18cmあまりもある。
これはカタツムリの中の巨大漢で、ゴリアテと呼んでしかるべきものである。
過去三年間に、この猛悪な強敵が船によってはこばれ、米国本土上陸をくわだてた場合が七回もあったので、米国の植物検査所では、その脅威を未然にふせぐために厳重な罰則を設け、これを米国に輸入した者は五百ドルの罰金を課したうえに、一年間の禁錮に処することを宣言した。
日本が手をやいた島々 *
を傘下におさめた米国は、力強いゴリアテのたゆみなき進攻には、全く匙を投げた。
* 日本が手をやいた島々 第一次世界大戦に日本は連合国側で参戦し、敗戦国ドイツの統治領であった南洋の島々は日本の統治領となった。
しかし、第二次大戦で日本が敗れ、それらは米軍統治となった。マリアナ諸島、トラック諸島など多くの小さい島々であった。
青酸ガス、火焔砲、塹壕、毒餌、蒸気など、あらゆる手段をつくしたが、この強敵は屍を乗りこえ乗りこえ進んで来る。
専門学者もその対策には思案投首(なげくび)であったところへ、最近一大福音がもたらされた。
それはゴリアテの生れ故郷である東アフリカから、この巨大なカタツムリを嗜食(ししょく)する小さなカタツムリが、ケンヤ地方に発見されたという朗報が舞いこんだのであった。
これはゴナキシス属の指先ほどの大きさの小さなカタツムリで、アフリカ大カタツムリをゴリアテになぞらえるならば、これは巨人を打ちひしいだダビデに比(ひ)すべきものであろう。
米国学術研究会議の太平洋学術委員会では、さっそくこの問題を取上げた。
そして他に迷惑をおよぼす心配のない、マリアナ群島テニアン島の北に横たわる小島アギーガンを試験地にえらび、ここにダビデとゴリアテとを放飼して、その戦闘ぶりを観察することとした。 |

断崖紹壁でかこまれたマチアナ諸島の無人の孤島アギーガン
|
③ ダビデを求めて top
一九四九年、アフリカ大カタツムリの大敵であるゴナキシスをさがしもとめるために、ウィリアムズ博士が英領東アフリカに派遣せられ、ケンヤ・タンガインカおよびザンジーバルなどの諸地域において探査の歩がすすめられたが、モンバサの南に横たわる小さな密林の中で、学名をゴナキシス・キブウェチェンシスと呼ぶ小さいカタツムリを発見し、これが、ゴリアテを屠殺するダビデであることを確かめたのであった。
ほかにマングースや野ネズミや“ひひ”の類なども大カタツムリを嗜好するが、この小カタツムリこそ性質きわめて温順で、人間社会にはなんらの危害をくわえないから、アフリカ大カタツムリの大敵としては、利用価値がすこぶる大であることを報告した。
その後一年をへて、米国国立博物館の貝類研究員であるアポット博士が、したしく現地におもむき、ウィリアムズ博士が報告したダビデを多数集め、生きながら輸送してアギーガン島で実地試験を行うよう命を受けた。
そこで同博士は肌寒き四月の朝、首都ワシントンを飛び立ち、二十四時間後にはナイル上空において縦横に閃光をあびながら大雨圈を突破し、暁にははるかな地上にビクトリア湖をながめ、灼熱の太陽が中天にかがやくころ、ケンヤ州の首都ナイロビの広大な飛行場におり立った。 |

アボット博士かゴナキシスの夏眠現象を発見した
ケニヤ州ディアニ・ビーチの仮寓
|
五月にはいるとともに、アボット博士はモンバサの南二十マイル、インド洋にのぞむディアニの海岸に小屋をしつらえて作業の根拠地とし、昼はダビデをもとめて付近の密林を踏査し、夜は石油ランプの火影に研学をつづけるという生活をくりかえした。
要は短期間に、小カタツムリの生きたものを、多数捕まえるということにあったが、ウィリアムズ博士やその他の貝類学者の進言により、春の雨季がこの類のカタツムリを捕まえるためには、もっともよいときであることを知らされていた。
ところでこの地方の雨季はすでに二十日を過ぎていた。
そして野も山もいぶきを吹きかえしてふかい緑につつまれ、生けるゴリアテをその故郷にさがしだすのは、容易なわざではなかったが、ある綮った森には、その多数が食をもとめて、はいまわっているのをみつけた。
しかも付近のジャングルの中には、その死骸であるうつろの貝殻が、るいるいとして散らばっているのが目についた。
これはこの大カタツムリを倒す、なにものかがひそんでいることを物語っているので、アボット博士は喜びいさんで草の中、落葉の下に力強いダビデをさがしもとめたが、苦心はついに報いられ、ある日のこと、なかば体が土にうもれている大カタツムリの体に、しっかり喰いついているダビデの姿を見いだした。
この事実は大カタツムリが静止しているとき、もしくは土中に産卵しているときを見すまして、小さなダビデがおそいかかるのだということを物語っていたので、それからは注意して、そのような場面をさがしもとめた結果、ようやく十二匹の生ける小ゴナキシスを入手することができた。 |

米国国立博物館研究室でアフリカ大蝸牛(かたつむり)の
大敵を研究するアボット博士(下)とゴナキシス(上)
|
|

ゴリアテ(上)とダピテ
|

ゴリアテを襲撃するダピテ
|
| この小さいカタツムリは、特別な攻撃器官をそなえているわけでなく、空腹になると鋭敏な嗅覚器によって、 |
ゴリアテの所在を確かめ、敵にめぐりあうと、たちまちその体に吸いついて裸出(らしゅつ)している体内に喰いつく。
おどろいた大カタツムリは、意外な強敵の襲撃をさけようとして身をちぢめ、厚い蓋をしっかりとざして、その周囲に濃厚な粘液を放出するが、喰いさがっているダピデは、深く相手の肉にもぐりこんだまま、蓋のすきまを通って貝殻の中に侵入し、もはや大丈夫と安心しているゴリアテを、生きながら喰いつくしてしまう。
さて、苦心採集の結果がわずか十二匹では、少なくとも千匹の生活体を捕獲輸送しなければならないアボット博士にとっては、成功とはいいがたいので、能率をあげたい一心から、大カタツムリの多数を捕まえ、その肉をくだいて密林中に撒布してみたが、このまき餌は結局効果がなかった。
知恵をしぼった結果、これは土民を動員し、適当な代価で買上げるのが一番であると考え、さっそく実行したところが、初日の夕刻には博士のキャンプの前には土民が列をなし、はなはだしい数のダビデが貨幣にかえられた。
それが毎日つづいて、十日の間に健康なダビデが二千以上も集ったので、博士はついに買上げを中止した。
この賢明な方法で、博士も目的をたっしたが、土民たちも石を持ちあげてみたり、密林の中を探索してみたりするだけの労力で多額の労銀を得て付近のタバコ屋の親父が、この数日ほど高いタバコがよく売れたことはないといって、ホクホクしていたほど、すべての人が幸福感にひたることができた。
④ 空の旅へ top
遠征の目的をたっしたアボット博士の喜びは、筆紙につくせぬものがあったが、さて二千以上の生きた貝を、そのまま試験地まで輸送するにはどうしたらよいか、そこに、大きな不安が横たわっていた。
ためしに五十匹ばかりを一つの箱に収容してみたらすべての貝が粘液をだして。毬のようなひとかたまりになってしまう。そして内部のものは酸素の不足をきたして死滅するばかりでなく、とも喰いをする心配もないとはいえなかった。
一匹一匹をうすい紙でつつんでみたが、貝自体が粘液をたすので、紙はたちまちしめってなんの役にも立たなくなる。
そこで、死をまねかないていどで貝を乾燥させるということが、輸送に成功する秘訣のように思われたが、貝にとっては心地よいであろう雨がしとしとと降っている。
その音をききながら、思いをねる博士は、全く眠りにつきかねた。
不眠の一夜をすごしてはね起きた博士は、とうとい材料を試験の犠牲に供するつもりで、これを二十の群にわけた。
そして、夏になって水も食物もなくなった場合に行われる、夏眠の状態を人為的に行わせる実験に着手してみた。
ふるい木製の衣裳箱を、孵卵器がわりに利用し、その内部に二個の石油ランプをともして空気を乾燥させ、蓋をすこしひらいて換気が行われるようにした。
このような容器におさめた最初の百匹は、三時間後には全部が殼の中に引っこんで蓋をかたくとざしていた。
そこで各個をかわいた紙でゆるくつつんでみたが、実験後一日をへてからその結果を調査したところが、このように処置したもの五百のうち、かろうじて生命をたもっていたのは、わずか十二匹で、他はすべて死んで腐臭を発していた。
次には直射日光による乾燥を思いたち、五十匹ずつを盆に入れて、戸外の日光にあててみた。
ところが夏眠現象をひき起すどころか、二百匹を犠牲に供したことになり、十五分間の天日にあてるだけで死んでしまうことがはっきりわかった。
アボット博士はすっかりこまって、なにかいい方法はないかと、考えていたが、運は寢て待て、というとおり、遇然のことから一道の光明を見つけだした。
湿度があまり高くなかったある夜のこと、博士は寝室をダビデがはいまわるにまかせて眠りについた。
ところが、夜を徹して四方八方動きまわっているうちに、体内の水分が蒸発したためか、朝になってみたら、その大多数が蓋をとじて殼の中にひっこみ、のこったものもなかば動けなくなっていた。
湿度が高くない日に、乾いたテーブルの上や壁面をはいつづけていると、体内の水分を発散しつくすので、カタツムリは乾燥期がきたような錯覚を起す。
そして蓋をとじて夏眠状態に入り、雨がしとしととふりだす日を、待つわけであるが、博士はこの遇然の事実にヒントを得て、ダビデの輸送計画を立てた。
すなわち、苦心採集し得た貴重な資料をたずさえて、モンバサに帰着するやいなや、博士は近代的ホテルに泊って市中で一番乾燥度が高いといわれている一室に陣どり、三日間をついやしてすべてのダビデに夏眠をとらせ、はたして生きているかどうかを匂いでかぎわけ、大丈夫と思うダピデをかわいた紙でつつみ、それらをていねいに箱につめて、空輸の用意をととのえた。
アボット博士が去ったあとでその室に、いくたのカタツムリがのこした銀色のはい跡を見つけて、ホテルの支配人はなんと思ったろうと博士は書きしるしているが、第一便として、モンバサから速達便で送りだされた四百匹の生きたダビデは、エジプト、パキスタン、インド、香港を経て、空路マリアナに送られた。
グァム島にあってこれを受けとった植物検査官オーウェン氏は、快速の汽艇で珍客ダビデをアギーガン島に送りつけ、その島に棲むゴリアテ、すなわちアフリカ大カタツムリにたいし、戦いをいどませることとした。
時は一九五〇年五月三十一日のことであった。
東アフリカ出発後三週間目に戦場に到達したダビデは、たちまち夏眠よりさめて、猛然ゴリアテに立ち向ったことであろうが、故郷におけるのと同様、凱歌をあげているかどうかは、孤島の環境がダビデの生活に適するかどうかによって定まるのである。
さいわいにしてダビデが生れ故郷におけると同様、アフリカ大カタツムリを殲滅することに役立つことがはっきりわかるならば、その脅威になやむ人々の幸はこれにすぎないであろう。
2 敵か味方か top
① 初見参のマングース
古来沖縄は、毒蛇ハブの産地として有名であり、ハブによる被害も、年々相当数にのぼるので、この駆除には官民ともに頭を悩ましていた。
ところがインドには、毒蛇を好んで食べるマングースという小動物がいることをつたえきき、これを輸入してハブを征伐しようという議が持ちあがった。
それは今から四十年前のことで、主唱者であった渡瀬庄三郎博士が、わざわざインドに渡航し、その数頭をたずさえ帰って、慶良間(けらま)群島と久米(くめ)島との中間の小島、渡名喜(となき)島にはなってみた。
この動物は麝香猫(じゃこうねこ)科に属するもので、イタチよりは大きく、その動作敏捷で。毒蛇と闘わせると、みごとに相手を征服して捕食する。渡名喜島は、マングースの生活に適していたとみえて、その後数年間に頭数も増加し、ハブもめっきり減少してきたが、好む食物がなくなってきたためか、彼らはときおり里に出て、鶏舎や家畜小屋を荒らすようになった。
この結果、折角輸入したマングースも、島民の憎悪の的となり、山でその姿を見ると、
「博士が出て来た」
といってこれをたたき殺すという始末となった。
その結果今日では、沖縄のマングースは絶滅したとのことであるが、この小動物は野ネズミの捕食にも巧みなので、その害になやむ国では大規模に輸入して、その能力を発揮させている。
② ハワイ農民の声 top
甘蔗(かんしょ)畑を荒らす野ネズミを駆除する目的で、ハワイ群島にマングースが移入されてから、すでに六十余年の歳月が流れ、今やマングースはハワイにおける、もっとも普通の哺乳動物の一つとなっている。
一八八三年の「栽培者月報」と題するささやかな農事雑誌に、
「インドに棲息するマングースと称する小動物は、ネズミを捕まえる能力において、猫やイタチなどにまさること数等である。
畑の野ネズミを駆除するために、このものを移入せよ」
という記事がのっていたが、ヒロに居住する一農民は、野ネズミによる一年間の損害は自分だけでも一万ドルにのぼるだろうとのべていた。
|

立ち上ったマングース
|

ハワイの主となったマングース
|
マングースの力で野ネズミを退治しようという気運がしだいに結実し、まもなくヒロの栽培者組合は、マングース購入費として一千ドルを集めた。
そして一八七二年に、西インド諸島のジャマイカに移入されていた。
ジャワ種金茶マングースの子孫七十二頭をもとめ、一八八四年に、それらをハワイ島に放ち飼した。
そのことあって以来、年々鼠害がはげしかった甘蔗園に、ネズミに喰われた甘蔗は一本も見つからなくなったとのことである。 |
日本でもかってペスト予防の目的で、ネズミの買上げを懸賞つきで励行したことがあったが、ずるい人間どもが得たりかしこしと、ひそかにネズミを飼育して増殖させ、それを警察に売りつけては懸賞金にありつくという、あくどい手段をとるなどのことがあった。
ハワイでも同様で、利にさとい中国人たちが、野ネズミをとった証拠に尾を切って持参したものに、頭数だけの金をはらうのをよいことにして、尾を切った野ネズミをやしなって子をふやし、その尾を切っては持参するという、ずるい方法をとるようになった。
これではせっかくの野ネズミ退治も、あべこべの結果になったわけであるが、マングースがふえるにつれて野ネズミが激減して行ったことだけは確かな事実であった。
③ 苦情の種 top
喉もとすぎれば暑さをわするとはよくいったもので、野ネズミの影がうすれてきたら、その昔を忘れた農民たちが、マングースはどうも鶏に損害をあたえて困ると言い出した。
しかし、一八八八年の栽培者月報に、
「近ごろ、マングースが鶏をおそうとて、不平をもらすやからがあるようだが、この小さい動物のために、自分は数千ドルの損害をまぬがれた。
鶏は米本国から、いくらでも輸入できるではないか。
鶏がやられたとて、その数は知れたものだろう。
野ネズミの害とは、同日の論ではなかろうではないか」
という投書記事がのっていたくらいで、この問題はさして世間の注意をひかず、以後数年間は、マングースと野ネズミとの戦闘が、よどみなくつづいていた。
ところが、これはまた意外なところから反撃の火の手があがってきた。
ハワイの狩猟家協会では、猟鳥のすくないハワイに、さまざまな狩猟鳥を放飼する計画を立て、ウズラ、キジ、山鳥などを輸入してその増産をはかることとしたが、地上に巣をかまえるその上うな鳥類は、根こそぎマングースにやられてしまうばかりでなく、マングースの出現以来、目ぽしい野鳥の数が著しくへってきたと主張し、一般市民の反対熱を、さかんにあおりだした。 |

呼ぺば近づくマングース
|
それ以来、マングースにたいする賛否両論が、新聞雑誌をにぎわすこととなったが、ハワイを経済的にささえている農民たちは、熱心なマングース党であるのにたいし、養鶏家と狩猟家とは、マングースの姿を見つけしだい射殺してしまえ、と叫ぶような対立がまき起った。
そして狩猟家たちは、マングースの頭皮一個に十五セントの賞金をかけ、かかる悪獣を飼育したり移入したりする者は、罪人として所罰すべきだと主張した。
そこで農民たちは、この不法な抗議に対抗すべく、科学的調査を開始し、まず第一にマングースの糞便検査をおこなったところが、その食物の八割は昆虫の残骸であることがわかった。
かつまたハワイ群島の中で、マングースが棲んでいるオアフ、ハワイ、モロカイ、およびマウイの四島と、マングースを放飼しなかったクサイ、およびラナイ二島との野ネズミの数を調べてみたところが、前者には比較的無害な種類しかいないのに、後者には、蔗園をひどく荒らすエジプトネズミが群棲していることがわかり、こんなにありがたい動物を、薄弱な根拠から悪くののしるのはけしがらんと、いきまくようになった。
④ 仲良しこよし top
ハワイのマングース問題は、このような筋道をたどって対立をつづけてきたが、オアフ島の一角には、マングースと人間と野鳥とが、仲よしの生活を送っている場所がある。
今から数年前に、その場所に鳥類保護区域が設定せられ、ささやかな鳥類飼育所がもうけられたが、付近に棲むマングースは、野鳥にあたえる餌料の裾わけにあずかろうとして、時をきめて姿を現すようになった。
雨の音がおさまって、東の空があかねさすころになると、この保護区域に宿るペキンナイチングールが、まず第一に群をなして給餌場に飛んで来る。そしてチイと呼ばれる百合科の植物の葉影に身をかくすが、好む餌がさっとまかれると、彼らは羽音も高く地におりたち、なんのおそれるところもなく、ききとしてそれをついばむ。
東洋から来たこの鳥どもは、メキシコ原産の緋色のウソや、インドのマイナースや、中国豪州から輸入された山鳩どもに。ときおり平和をかきみだされるが、おそれをなすマングースが姿を現すまでは、チッチッとさえずりながら、たのしげに朝の餌をひろっている。
そこへ早くも目ざめたマングースが、深い草をわけてほっそりした姿を現す。蛇のように身をうねらせながら、注意ぷかくしのびよった彼は、できるだけ身を立て、するどいまなこを見はって危険はないか、とあたりを見まわしたうえで、そろりそろりと給餌所に近づいて来る。
山鳩やウソなどは、間近に通る魔のごときものの姿におどろきもせず、平気で餌をひろっているが、さすがに小心のナイチングールは、それと見て羽をそろえて飛び立ってしまう。
しばらくすると、四方八方から、老若さまざまなマングースがおどり出る。
あるものは単身で、あるものは雌雄同列で、あるいはまた母が二頭ずつの仔を引きつれて、いずれもが、まかれた餌を目かけて突進する。
給餌所の窓があけはなたれていると、その内部に彼らを見まもる人影がしても、彼らはすこしの懸念もしていないようすで、投げられたパンヤ果実や野菜や肉片などをたちまち喰いつくしてしまう。
そこで顔見知りになった所員が、朝の残飯をかき集めてにっこり笑いながら姿を現すと、待ってましたといわんばかりにかけよって来るものもある。
なかには行儀よく路傍で待っているのもあるが、彼らの好餌であるベーコンの一片を指でつまんでさしまねくと、なれたものは草むらから黒い鼻先をつきだして、ご馳走にとびつくなり、鼻をならしていそいそと退却する。
はじめてこの給餌所が創設されたころには、うたがいぶかいマングースどもは、かくれ場所からとびだして食物をくわえるなり、矢のごとく逃げ去るのが常であったが、おそろしいと思った人間が、べつに彼らに危害をくわえるでもなし、引っ捕えて艦にぶちこむのでもないことを知るとともに、だんだんと所員と、馴れしたしむようになった。 |

敵をうかがうマングース

果実を嗜食するマングース(左上)と野ネズミを捕えたマングース(右下)
|
そして給餌の時間を、午前八時ときめたところが、その時刻をおぼえたものとみえて、八時近くなると草むらや藪影に、きまって彼らの姿が現れ、食をとるありさまを人間がながめていても、いっこうにおどろかなくなった。
そして、勇猛心をふるい起して人間に近づいたものが、一番大きなパン屑やごちそうにありつくことを悟るとともに、だんだん人間の手から食物を喰べるようになったが、給飼所ができて一年後には、そのような人に、馴れしたしむマングースが、三頭も現れるようになった。
さて、マングースが給餌所に姿を現すようになってこのかた、鳥の世界にはなんの変化も起らなかった。
おそろしい害敵であるべきはずのマングースは、人間さまにもらう食物のほうが、よほど魅力があるものとみえて、鳥どもには目もくれないので、野鳥の群は木木の梢から給餌所の庭へ、なんのおそれげもなく舞いおりて無心に餌をひろっていた。
それに対して飼い猫は、かれらにとってよほどおそろしい動物であるとみえて、猫がひそかに草むらに身をひそめたのを感づくと、鳥どもは容易に地におりようとしなかった。
マングースと野鳥の類がこのように仲よく暮しているありさまを、声を大きくして論争しあっている人間たちがながめたらなんというであろう。
利用するだけ利用したあとは、難くせをつけてたたきだしてしまえという、さもしい人間の心情をさぐりあてて、マングースはさびしい笑みをもらしていることであろうが、元来が蛇を好んで食べるマングースにとって、ミミズに似たメクラヘビ以外に、蛇がいないハワイ群島は、けっして棲みよい場所ではないはずである。
しかし彼らの好んで喰べるパパイヤは、群島いたるところにうれているし、夜行性で樹にのぼることのたくみな野ネズミどもは、昼の動物でも樹木にのぼる能力のないマングースの攻撃をさけることができるので、年をへても絶滅するまでにはいたるまい。
すでに実証されたとおり、マングースの活躍から、重大な鼠害をまぬがれることができたならば、まれに起る過誤は、寛大な心をもってゆるしてやるべきではあるまいか。
せっかく渡瀬博士が、インドから迎えたハブの大敵マングースを、「博士」とよんで根だやしにしてしまった沖縄島民が、今日なおハブの被害におびえている現状を見て、大局を考えない人々の短見を笑わざるをえないが、しかしまた、一方では、細心の注意をはらわずして、外国産の動植物を輸入し、自然界のバランスをやぶるということが、とんでもない結果をまねくことをも、あわせ考えねばならない。
top
**************************************** |