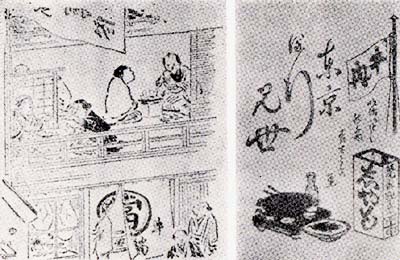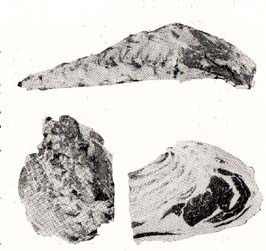|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章
1 肉と体温
人間は食べた食物のカロリーだけ体から熱を発生している。
一日三〇〇〇キロカロリーの食べ物をとると、平均して一五〇ワットの電熱器と同じ量の熱エネルギーを体から出す計算になる。
一部屋に多くの人が集まると暑くなるのは、一人ひとりが電熱器を持ちこんだのと同じだからである。
一日中いつも一定量の熱エネルギーを体から出しているのではない。
前の夜から食事をせず、一晩よく寝た朝の量がもっとも小さくなる。
食事が終ってしばらくたつと、熱の発生が大きくなる。
この食事のあとで一時的に熱の発失が大きくなる現象を、「特異動的作用」とか「食物の熱効果」とよんでいる。
寒い冬、家にかけこんでなにか食べると、体が暖まってくるのはこのためである。
特異動的作用がつづく時間、つまり体が暖まっている時間は、そのときの食べ物の性質によってちがってくる。
御飯を主食とする澱粉質や脂肪が多い食べ物をとった場合には二時間から三時間、蛋白質が多い食べ物では、食後六時間も七時間も体が暖まっている。
質のよい蛋白質が多い食べ物は肉なので、肉を食べると長い時間体が暖まっている。
寒い冬に肉を食べることが多いのは、また寒い土地に住む人が肉を多く食べるのは、人間の生理現象にかなっている。
日本列島のほとんどは、暖流に現れている。
温暖なこの土地に住む人々は、肉を要求しなかったのだろうか。
生理的な要求があって、人間は食べ物を選ぶのだろうか。日本の肉食史をたどってみたい。
2 日本への肉食文化の渡来
日本人にとって明治時代のはじめには、肉を食べることが「文明開化」のしるしでもあった。
それまで、ほとんどの日本人は、肉を常食としてはいなかった。
今日、日本人といわれている人々は大昔から肉を食べなかったのだろうか。
日本にはもともと、イヌ、ウシ、ウマ、ニワトリはいなかった。ネコもいなかった。
みな大陸からきた外来動物である。
縄文時代後期には、ウマが大陸から日本に入り、その後、弥生時代のはじめころにウシも入ったとされている。
朝鮮から中国から日本へ移住した人々の数は、古墳時代後期(五世紀)以来急速にましている。
今日の法律では「密入国者」にあたるが、大昔の日本では旅の危険をのぞけば、移住はやさしかった。
本国での戦乱をさけ、あるいは祖国が滅びたために海を渡ってきた人々であり、そのなかにはすぐれた技術者が多かった。
日本に近い朝鮮では、古くからブタが食用動物として飼われていたし、北から来た帰化人は、肉を食べるのが習性であった。
四、五世紀頃から、ウシ、ウマ、ブタの肉を食べる大陸的な食生活が、古代の西日本人に現れるのである。
しかし、それまで日本にいた大多数の人江、主として東南アジア方面から日本に入ったといわれる。
ヒエ、アワ、イネを中心とした農耕によって食生活をいとなんていた。
ウシ、ウマのような家畜を知らない文化である。
この「南方的」ともいうべき食生活をつづけるグループのなかに、肉食の風習を持つ北方的食生活のグループが加わったのである。
食べ物の習性は子孫に受けつがれてゆく。食べ物の風習はすぐにはあらたまらない。
もっともあらためにくいのが、食べ物の風習であろう。
したがって、現在でも、アメリカに日本人街ができたり、日本に中国人街ができたりする。
3 仏教の教えと日本人の肉食
六世紀に入って仏教が朝鮮から渡来し、「殺生禁断」の教えにしたがって、ウシ、ウマ、ニワトリ、イヌなどの家畜、家禽の肉を食べることが禁止された。
仏教には人は死んだ後には、ウシ、ウマなどの動物に生まれがあるという「輪廻(りんね)」の考えがある。
動物も人間も元は同じという考えである。
仏教も中国、朝鮮をへて日本に入ってきた。
中国では、インドから仏教が入ってきても、ウシ、ブタ、ヒツジの肉を食べ、ウマの肉も食べている。
中国では根強い肉食の伝統があって、仏教はこの伝統をくずすことはできなかったのである。
食べ物の伝統を命令によって変えることはできない。
朝鮮の王国新羅(しらぎ)では、仏教を公認した年の翌年五二九年に動物の殺生を禁じ、百済(くだら)も五九九年に殺生禁断の命を出している。
しかし、くりかえし禁令を出しても、肉食をおさえることはむずかしかった。
日本での「殺生禁断」の命が効果的だったのは、それまで肉食の風習を持たぬ人がほとんどであったからである。
家畜動物を食べる肉食の風習を持たないグループに対しては、この命令はなんでもないことであるし、肉食の風習を持つ小数の渡来グループに対してはこの命令は肉食しない人ごとに同化せよという意味を持っている。
先住の農耕民族は、狩猟によって得た小さな野獣を食べても、数少ない外米の大型動物であるウシ、ウマを食べようとはしなかった。
水田耕作にてきした数少ないウシを食べることはできなかったであろうし、水田のなかに刈った草をふみこませて肥料とするのに、当時の小さなウマを使ったのかもしれない。
飼料にも問題があるのだろう。ウシが一キロの体重をふやすのに、現在でも飼料は十キロ必要という。
同じ一キロをふやすのに、ニワトリは二キロ、ブタは三キロの飼料ですむという。
しかし昔のブタは、体重が九十キロに成長するのに三年半かかったが、現在では一六○日で九十キロになる。
育種改良のたまものである。
日本に入ってきた仏教は、やはり「血はけがれたもの」とみて、動物の殺生や肉食を禁じてきた日本のそれまでの宗教、「神道」の考えと一致したため、神道とともに広まることができた。
この二つの宗教の一致した教えにより、日本には肉食の風習は広がらなかったのである。
同じ仏教を国の教えとする朝鮮には、十三世紀に元(蒙古)が侵入する。日本の鎌倉時代である。
侵入して、日本への進出の準備をする。
元は軍馬、食糧としてのウシを確保するために、朝鮮各地に牧場を開いている。
牧場にはラクダも飼われていたという。
元軍のために生産される多量の肉が、朝鮮の人々の食べ物の風習に影響をおよぼすのは当然であった。
日本について同じ例は、太平洋戦争敗戦後のアメリカ軍の進駐ということになろう。
風習や宗教も、戦争や征服という事実によって大きな影響を受ける例である。
十六世紀に日本にキリスト教が伝わる。キリスト教徒には、肉を食べても罪の意識はない。
キリスト教には「輪廻(りんね)」の考えはないのである。
人間は「神の似姿」であって、人間と動物とは全く縁がない。
人間はあらゆるものの上位にあるので、動物を殺して食べるのに、なんらの不都合はないのである。
キリスト教は、当時の人々に受入れられなかった。彼らは日本人とちがうけがれた者とみられたのである。
4 徳川幕府と肉食
十五世紀の半ばから、十七世紀の終わりごろまで、日本では農業の技術が発達している。
大きな川に堤防を築き、平野に水を引く技術がはじめて発達した。
大平野で水田耕作が行われ、越後平野とか関東平野はこの時期に開かれている。
この時期に日本の田畑は約三倍に増えている。
徳川幕府の時代が始まる十七世紀は、新田開発のさかんな時期である。
徳川幕府も仏教の教えを基礎にして人々を治めようとした。
昔の山林には野鳥、野獣が多かった。
山林の野鳥、野獣から田畑をまもるために、農民は鉄砲を使って追いはらっていた。
野鳥、野獣による被害は、今日の田畑がサル、サギなどからこうむる害とくらべられないほど大きかった。
農民は野鳥、野獣を獲り、食べていた。農民は猟師でもあった。
かつて戦場に使われた大量の鉄砲は、田畑を保護する必要な農具として用いられていたのである。
獲ったイノシシやシカの肉は、薬とするか、山野の「野菜」という名目で食用にされていたが、普及することはなかった。
普及はしなかったが、肉がおいしいことを知っている人もたくさんいたのである。
幕府も民衆が肉を食べることを嫌っていたが、長崎を通じて、外人の肉食の風習を知っていた。
たとえば、徳川吉宗はチーズをつくらせ、牛肉を栄養のある薬という名目で食べていたという。
十九世紀半ばになると、江戸に牛肉を煮て売る店が現れる。
薬を売っているのであって、肉を売っているのではない。
仏教を説く僧侶までこれをもとめていたという。
徳川時代後期には、蘭学の普及とともに、肉食の風習は一部の人たちの問に広まった。
しかし、何百年に渡ってうえつけられた肉食をさける思想は、明治時代に入っても残ったのである。
5 文明開化と肉食
明治五(一八七二)年に牛肉が天皇の食卓に上がり、牛肉屋は「官許(政府がゆるす)」の看板をかかげた。
同じ年は、僧侶に肉食と結婚がゆるされた年である。徴兵制が発せられた年でもあった。
明治時代への道を開いた指導者には、昔の風習をすべてあらため、人々の考えを全く変えてしまう必要があったのである。 だから文部省は肉食と牛乳を飲むことをすすめ、この年に、近藤芳樹に『牛乳考』『屠畜考』を書かせている。
「文明開化」をすすめるためには、天皇みずからも模範をしめず必要があったのであろう。
明治八(一八七五)年、東京には七十軒の牛肉店、七十七軒の鳥肉店があったが、物ずきな人がたまに肉を食べる程度であった。
大部分の人が牛肉を食べる体験をしたのは、徴兵令によって軍隊に入ってからである。 |
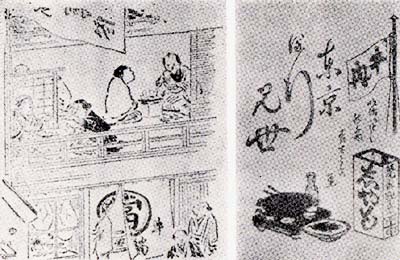
図32 明治時代はじめの牛肉店
|
(明治では国民が貧しくて粗食だったので、徴兵で軍隊にいった若者が軍の立派な食事に慣れて、除隊後、元の粗食に耐えられなかったという)
兵士には蛋白質の多いものをあたえ、体力のある強い兵にしなければならなかったのである。
ことに、日清、日露戦争に参加した兵士が帰ってから、肉食は全国的に普及した。
日清戦争が明治二十七(一八九四)年におきて、牛肉の缶詰が日本で作られはじめる。
この頃、家庭かきの西洋料理に名節が現れるのは、ロールキャベツとコロッケとライスカレーである。
肉食が全国的に普及したといっても、そう多くは食べていない。
明治四十三(一九一〇)年の牛肉消費量は三万八四〇〇トンであって、一人あたりの年間消費量は六一〇グラムにすぎない。
この頃、カツレツ(トンカツ)が家庭料理に現れている。
もうすこしたった大正七(一九一八)年の肉の値段をしらべてみた。
十銭(一円の十分の一)で買える牛肉は二十四匁(九十グラム)ぐらいであった。
牛乳は一二〇〇ミリリットルぐらいである。
当時、四人家族の労働者の家では、米十四円、副食費七円程度を平均して食費にあてていた。
一人一食の副食費は約二銭にあたる。
役人でも、一ヵ月の給料が二十五円以下の人が多かった時代である。
まだまだ肉は普通の日に、食べる食べ物ではなかったし、牛乳は病人の飲みものであった。
大正十一(一九二二)年の陸軍の調査では、その当時の国民一日一人あたりの動物性蛋白質は、鮮魚二十五・三グラム、塩乾魚十六・九グラム、食肉三・七五グラムであったという。
三・七五グラムは年間一・四キログラムにあたる。食肉は豚肉が多くをしめていたと思われる。
この頃、東京歩兵連隊で好まれた献立の順は、フライ、カツレツ、コロッケ、焼肉、焼魚、オムレツである。
魚も乾魚が多い。昭和初期までは、生の魚を売る店とならんで乾物屋が多かった。
カチカチに乾いた数の子、ほした貝が店頭に積みあげられていた。
するめ、わかめ、ほした魚などを売っていた。町をはずれると、魚屋よりも乾物屋のほうが多かった。
牛肉をもっとも食べていた都市が神戸(兵庫県)であった。 大正十三(一九二四)年、神戸市民一人あたり年間九キログラムの牛肉を食べていた。
今日の日本人全体の牛肉消費量の平均値より多い。
しかし、神戸の市民だけが食べていたわけではない。神戸は当時日本一の貿易港で外人も多い。
その外人や神戸牛のおいしい評判を聞いた国内の旅行者の食べ九分も合計した数字である。
この年の牛肉国内生産量は約六万トン。
輸入牛肉は一万五〇〇〇トン。 輸入量の八十パーセントは中国青島(チンタオ)産であった。
昭和に入って、国民一人あたりの年間牛肉消費量は、ようやく一キログラムにたっしたが、東京市内に食肉の配給が行われたのは、太平洋戦争開戦後の昭和十七(一九四二)年はじめからである。 |

図33 明治初期の貿易港神戸(毎日新聞社提供)
|
一世帯あたりの一回の配給量は、「二人までの家庭に三十匁、五人まで五十匁、八人まで八十匁、十人まで百匁」であった。
三人以上は一人あたり十匁、いまの三十七・五グラムにあたる。
配給の肉は、すき焼のネギ、白滝、焼豆腐にうもれて、かくれていた。
父母が、祖父、祖母が食べていた肉の量はこの程度であった。
6 牛肉の科学――霜降肉(しもふりにく)
肉のなかでも、日本人は牛肉を好む。牛肉のおいしさをさぐってみよう。
ウシの背中の中央部の肉をロースという。
くらの下にあたるのでくら下ともいう。
頭に近いほうのロースガリブ、尾に近いほうがロインである。
ワインを使ったステーキをサーロイン・ステーキという。
ロースの内側にある肉がヒレで、ウシの肉のうちで一番柔らかくてよいところである。
ヒレ肉の最もふとい部分をシャトーブリアンといって、このステーキがシャトーブリアン・ステーキである。
筋肉のなかに脂防が網の目のようにまざったものを霜降肉という。
柔らかく、舌の上でとろけるようなこくがあるために、日本では最高級とされている。
霜降肉は和牛(日本古来のウシ)からとる。
栄養が十分でないと霜降肉ができないので、ムギ類など穀物をおもな飼料として飼い、ビールを飲ませてから体に焼酎をふりかけてマッサージする。三重県松阪市の霜降肉が有名である。 |
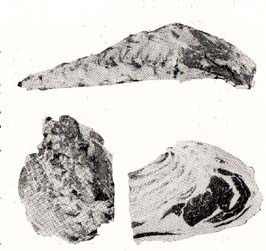
図34 牛肉の部種
(上:ヒレ、左:ネック、右:リブロース)
|
きめがこまかく、正に世界一の肉といわれている。
なぜ、日本人に霜降肉が好まれるのだろうか。
日本の肉料理は、すき焼で代表されるように、肉を水に入れて煮ることが多い。
肉の中の脂肪は水にとけ出して、肉とともにに野菜などの味をよくする。
しかし、肉から脂肪分が出てゆくので、肉そのものの味は長くにると悪くなる。
したがって、筋繊維の間の脂肪が網のように入っていて、煮ても脂肪がのこる霜降肉が好まれるのである。
肉を焼くか、むし焼きにして食べる場合には霜降肉でなくてもよい。
脂肪が筋肉とわかれていても、加熱によってちぢんだ肉の問にとけた脂肪分がしみこんでゆく。
したがって、欧米での肉用ウシの改良目標は、肉全体のうちで、食べられる部分の割合を大きくすることであった。 |

図35 和牛の飼育
|
霜降肉のステーキはおいしいが、食事のうちに肉がしめる割合が大きく、肉を常食とする場合には、むしろ淡白な味の肉が好まれる。
肉を常食とする国では、霜降肉を作り出すことをしなかった。
薬として牛肉を用いる鍋料理の伝統のある日本で、和牛から霜降肉を作ったのである。
畜産用のウシが、肉質のよい和牛と、乳を出すことを目的とする乳牛のアメリカ型のホルスタインの二つに区分されてきたのは、日本的な肉の食べ方によっている。
7 牛肉の科学――ウシとシロアリ
top
霜降肉をとる松阪牛(和牛)は、近畿各地の農家で育ててから、松阪付近の農家で特別な飼料をあたえたものである。
食べさせるものによって、ウシは体内の脂肪の量がちがってくる。
ウシは草を食べて大きくなる。植物だけを食べて、丈夫に育つ。
人間は魚や肉の動物性蛋白質を食べないと病気になる。
ウシとヒトとはどこがちがうのだろうか。
ウシの胃は四つにわかれている。第一胃と第二胃を反芻胃といって、第一胃はとても大きい。
飲みこんだ食物をまた口にもどして、よくかんでからまた飲みこむことを反芻(はんすう)という。
第一胃にはいつも微アルカリ性の唾液が流れこんでいて、多くの微生物がすむ安定した環境にたもたれている。
第一胃(ルーメン)中の「ルーメン微生物」は、原生動物と細菌で、細菌のなかでは、植物繊維の主成分であるセルロースを分解する菌が大切な役割をはたしている。
ウシの飼料は、ルーメン微生物によって分解され、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸などの脂肪酸を生じ、それが胃壁から吸収される。
一方、ルーメン内でふえた細菌や原生動物は第四胃に送られる。
第四胃だけは、胃が一つしかない他の動物と同じように胃液を出す。
ルーメン微生物は、ここで消化されて栄養となる。
つまり、ウシが栄養源としているのは、反芻胃中の微生物が増殖するさいに出す代謝物質と、ふえた微生物である。
我々が草を食べる代わりに、ウシに草を食べさせて、そのウシの肉を食べるのは、ウシの中の反芻胃という「生物反応器」を利用して、草をウシの栄養となる代謝物、微生物に変えて、肉を生み出しているからである。
植物を作っている物質のうち、一番元になる細胞壁を作っているのがセルロースである。
木材はセルロースを五十パーセントふくんでいる。
セルロースが化学的に安定なので、法隆寺のように、木造建築が一〇〇〇年以上ももっているのである。
化学的に安定なものが、胃のなかで短時間に分解され、消化されるはずがない。
シロアリが木を食べるのは、シロアリの腸のなかに多種類の微生物が寄生しているからである。
宿主のシロアリは、微生物が木材中のセルロースを分解してグルコースにしたものを栄養源としている。
シロアリ中の原生動物は強力なセルロース分解酵素、セルラーゼを持ってして、セルロースの七十から七十五パーセントを分解してしまう。
シロアリと原生動物とは共生の関係にあるので、原生動物を殺すとシロアリも死んでしまう。
シロアリを食べる動物は、木材を分解して、分解物を栄養源として育ったシロアリという蛋白質を食べていることになる。
ウシを食べることは、ウシに共生する微生物の働きをかりて、草を食べていることになる。
広大な牧草地でウシが育つのならば、ウシの食べる草は十分にある。
ウシを放牧して飼うことができる。
しかし、広い牧草地がのこされている場合でも、今日ではウシをせまい場所に集めて飼うようになってきている。
管理しやすいためである。
ウシにあたえられるのは濃厚飼料であって、本来の牧草飼料は少なくなってきている。
ときには、反芻胃の中の微生物不正常に働かなくなって、ウシが病気になることもある。
かつては家畜動物を利用する畜産は農業にふくまれていた。
今日では動物蛋白質製造工業の「生物反応器」として、家畜動物が扱われている。
家畜というよりも、アニマル・マシンというべきであって、ブロイラー(食用ニワトリの飼育)がその代表例であろう。
人間の腸のなかに有数百種もの細菌がすんでしる。
ある細菌は老化をふせぐ作用をもっているし、人間の食生活の歴史とこの細菌とは関係があるのだろう。
パプアニューギニアの奥地に住んでいる原住民はタロイモを主食としている。
動物蛋白を食べる量はとても少ない。
それなのに、彼ら不健康をたもっているのはなぜだろうか。
今日その調査がすすめられているが、彼らはアミノ酸や蛋白質を作り出すある種の菌を腸のなかに持っているからともいわれている。
この菌をのぞき、栄養に富む食べ物に代えることが食事の近代化になるのだろうか。
ヒトという動物の特性を消すことになるだろうと思う。
top
**************************************** |