|
****************************************
Home 電気 機械 医学 化学 化学工業 生活 食べ物
食べ物の発明発見物語
(『縄文人の食卓から宇宙食まで』遠藤一夫著 発明発見物語全集13 国土社 1985年刊)
概要 top
|

1 食べ物の起源
昔、人間は、食糧のほとんどを狩猟にたよっていたのだろうか?
農業は一体どこから、どういう形で始まったのだろうか?
牧畜と農耕はどちらが早いものだろう?
など、食糧獲得の大本を探る。
|

2 農業とともに
生まれた技術
農業が始まるとともに、人間は、定住するようになった。ここで、いろいろな技術が生まれてくる。調理の技術、焼き物の技術、織り物の技術……などなど。これらの技術は、一体どんなふうにして
起こったのだろう? |

3 米と日本人
日本人と最も密接なかかわりを持つ米は、いつ頃から主食として食べられてきたのか。
歴史の上で、ほとんどの時代で
“米のめし”を食べられたのは、
特別の人、特別の日だけであった。
|

4 コムギとパンの科学
コムギは、いつどこで起こったのか。
どのようにして、パンに作りあげたのか。
さらに、それにともない発展した
様々な技術を探る。 |
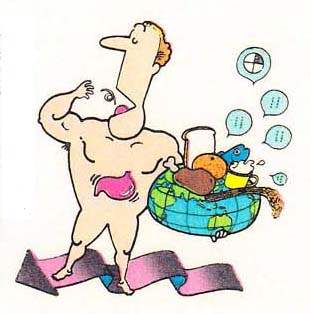
9 食べ物と栄養
身長の違いは、遺伝的人種差より食生活によって決まるという。たん白質の摂取量が多いほど、身長も高い。戦後の日本人は、肉を多く食べるようになり、身長が伸びたという。
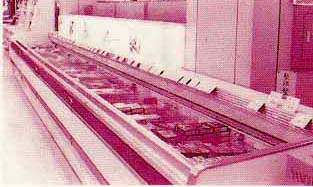
12 食品の保存技術 “オレゴン・トンネル”
これは19世紀の終わり、アメリカのオレゴン州で、
実用化された果実や野菜の乾燥装置のことである。
これ以後、食べ物の保存技術は、飛躍的な進歩をとげた。
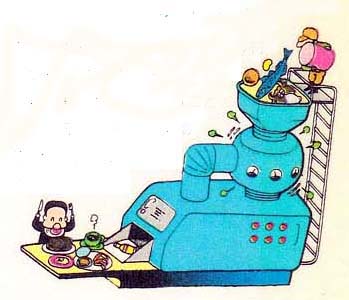
13 偽物の味、本物の味
現代の食品科学では、全く別々の材料から、
味も匂いも歯ざわりも、同じ食べ物を作ることができる。
どちらが本物で、どちらが偽物」なのか。 |

10 戦争と食べ物
20世紀に入ってからも、食べたい物をめいっぱい
食べることのできない時代が、日本にもあった。
それは、戦争の時代である。戦争は人々に、
一体どのような食生活の変化をもたらしたのか。

11 ガムとチョコレート
チューインガムとチョコレート。
子供に一番人気があるこのお菓子も、
新大陸からもたらされた。
明治の人々は、どんな気持ちでこれらと接したのだろう。

14 人間の未来と食べ物
科学が発達したとはいえ、人間は食べなければ
生きられない。しかし、現在、地球の全人口の6分の1が、
飢えに苦しんでいる。その飢餓が、明日には
私たちの身におし寄せてこないとは限らない。 |
あとがき 一九八五年四月 遠藤一夫 top
一九八五年、世界の人口は四十八億人にたっした。二〇二〇年には七十八億人になると見こまれている。
人口の増加のうち九十三パーセントは開発途上国で生じ、南アジアと東南アジアの人口は、二〇二五年までに、一九八〇年の全人口の二倍に増加し、南アメリカでは二・四倍に、またアフリカでは三・三倍にたっするといわれる。
ここで四・八人、つまり五人に近い家族を想定しよう。
一人が十億人を代表するとすれば、この家族が世界の人々を表わしている。
この地球の上で、一家のまわりに何が現れてくるのだろうか。
この家族のまわりにはウシが一頭いる(全世界には十二億頭ぐらいのウシがいる)。
一頭たらずのブタがいる。
四家族から五家族で乳牛を一頭飼っていて、乳牛は年にニトンの乳を出し、みんなでわけている。
二家族で三頭のヒツジの毛を刈りとっている。そして、一家族でニワトリを六羽飼っている。
今日、僕たち日本人は、一年間で肉用ウシを五十人で一頭食べ、ブタを十三人で一頭食べている。
ブロイラーは一人で五羽食べている計算になる。二五〇人が住むアパートのまわりには、五頭のウシが、二〇頭のブタが、七五〇羽のニワトリがいて、これらの家畜を一年で食べてしまったということになる。
まことに無気味な風景を思わせるが、生きたブタを見たことがない今日の子供たちは、ソーセージを、ハムを好んで食べている。
豊富な食べ物に囲まれている。ありがたいと思ってよい。
が、くらしを支えてきたこの見えぬ家畜の、作物の背景は忘れさられている。
先ほどの世界人一家にもどろう。
米がよくできるようになった。世界の米の生産量は、この三十年で二倍になった。
全世界で四・四億トンとれる。この家族で年四四〇キログラムの収穫があった。
〇・一四ヘクタールの耕地でたりる。〇・二四ヘクタールの耕地で、コムギは四五〇キログラムとれた。
ジャガイモは二六〇キログラム。大豆は九〇キログラム。トウモロコシは四五〇キログラムもとれた。
世界全体の生産量から算出したこの家族についての平均値である。
食べ物に困ることはない。そう思うかもしれない。
日本人は一人あたり米を年に七十六キログラムぐらいしか食べない。
コムギは三十二キロ、ジャガイモは十四キログラムしか食べない。
五人家族として五倍しても、世界人一家の収穫で十分たりる。
しかし、ウシが十二億頭いた。ウシとブタで二十億頭いた。
四十八億のヒトと、十二億のウシがこの地球にいる。
四・八人のヒトと一頭のウシと、どちらがたくさん食べるのだろうか。
食物のカロリーを必要とするだろうか。
平均的世界人のこの一家は、家畜を養えるのだろうか。
先ほどの収穫量は、家畜をふくめて算出したものではない。
地球上に住む人々が平均的に食べ物に困るとすれば、食べ物が豊かな国があれば、その一方には食べ物に困る数多くの国が残されていることになる。
もっと土地を耕して、農耕地を広げればよいのだろう。
今の農耕地から収穫をふやせばよいののかもしれない。人間の食べ物を生み出すのは土地である。
土地が人間を養ってきたのであって、近代的高層ビルが人間に食べ物をあたえてきたのではない。
(A)肥料、農薬を用いず、土地を保護することもしない、人手による耕作だけで作物を作る場合、
(B)多少の肥料、農薬を用いて、耕作の道具を改良した場合、
(C)機械化を完備して、科学的に土壌を保護し、高カロリーの作物を選んだ場合、
それぞれについて、一ヘクタールあたりの人間を養える数がちがうのは当然である。
Aでは一人以下、Bでは二人程度、Cでは五人程度といわれる。
したがって、Cのレベルで農業を行犬は食糧は増加する。
Aの土地の農業水準をCに高めれば、人口が増えても困らないことになる。
日本の農業技術はすぐれている。Cのレベルである。
高度なレベルにたもつために、苗を選んで育て、肥料を十分あたえ、気温が低下すればハウス内を暖房する。
Aにくらべて、人間の労力以外ので不ルギーが大量に加わっている。
ハウスもののトマト一キログラムの収穫に対して三四七〇キロカロリーのエネルギーが、ハウスものキュウリ一キログラムでは四二八七キロカロリーのエネルギーが投入されている。
このエネルギーのほとんどが石油によっている。
キュウリ一キログラムを作るのに、ほぼ〇・五リットルの石油が消費されているのである。
現在、日本で作られる食べ物に対して全体で二三〇〇万キロリットルの石油に相当するエネルギーが投入されている。
日本の人口の四十倍が世界人口である。
Aレベルの農業が、一人あたりに同等に全世界におよぶと仮定して、風土のちがいを無視すれば、二三〇〇万キロリットルの四十倍、九億⊃○○○万キロリットルの石油を必要とすることになる。
大変な量である。全世界の石油消費量の三分の二程度となろう。
風土の、作物のちがいを無視しているこういった単純な計算は正しくはないが、石油の消費量は現状よりも著しく増加することはまちがいない。
大量なエネルギーを投入すれば、夜間でも人工光によって植物を育てることができる。
多くの電力を消費した肥料を用いて、屋内で成長能率のよい水耕裁培を口りことができる。
土からはなれてゆく近代植物工場である。
しかし、石油エネルギーにささえられたこのような近代技術を全世界におよぼすことはほとんど不可能である。
食糧という人間の基本的な課題を考えるとき、土からはなれてゆく近代技術は地球規模では「技術」になりえない。
近い将来、食糧が不足するかもしれない。しかし、土がなくても植物を育てることができる。
無人の工場で食糧を作ることができる。食糧の不足は、科学技術によっておぎなわれる。
そう考えるのはあやまちかもしれないということである。
常識的に考えて、当然のことができなかったので、食糧が不足してきたと考えてよいのだろうと思う。
アフリカの食糧自給率は一九六〇年では九十八パーセントであった。
一九七〇年代の後半に入ってから、自給率は急激に低下したのである。
今日、アフリカ五十六ヵ国の半分以半が食糧に不足し、一億五〇〇〇万人が飢えている。
食べ物を買うために、職をもとめて農村から都市に人々が集中している。
食糧増産のため、半乾燥地帯ではヒツジが放牧されて、砂漠化か進んでいる。
熱帯雨林地帯では乱伐がつづき、焼畑が広がっている。
自然には国境はない。国境を作ったのは人間である。
人間の作り出した居住地の制限によって、人間は移動することができない。
砂漠化してゆく地帯から脱出することを許されずに、餓死する人々を生み出しているのである。
そして、アフリカでは耕作可能面積の三十パーセントしか利用されていない。
その多くは植民地時代に作られたコーヒー豆など輸出農産物でしめられている。
近代的な工場を作り、ロボットを導入して、すぐれた自動車、電気製品を作って世界に売り出せば、食糧を買うのに困ることはない。
草地を焼いて立派なスポーツ場とし、コーヒー豆を作り、ハウスでトマト、セロリなどを作ればよい。
君たちはそういうのだろうか。
人間が生きる条件が、そんなにせばめられたのはおかしい。
工業の進んだ国だけが、食べ物に困らないというのはおかしい。
中国では、世界耕地の七パーセントで世界人口の四分の一が生活していた。
食糧という人間の基本的な課題を考えるとき、現状では幸いにして食べ物が豊富な僕たち日本の国からはなれて、人間の暮らし方について、あらためて考えることが大切と思う。
耕地を広げるとともに、少なくとも砂漠化してゆく土地が、これ以上広がらないようにつとめなければならない。
一部の地域に人口が集中するとき、土地には過大な負担がかかって、土地を保護する余裕がなく、作物を育てる能力をうしなう。
その結果、土地は砂漠化し、人間はこの土地をすてて新たな土地をもとめることになる。
そして、新たな土地もやがて砂漠化してゆく。
土地に過大な負担をかけることによる侵食、砂漠化の影響によって、二〇〇〇年には、農業生産の低下がアフリカでは二十五パーセント、南米では二十二パーセント、東南アジアでは十二パーセントも減ることが見込まれているのである。
科学技術が必要なのは、食糧の生産を高めるとともに、この侵食を防ぐためである。
耕地を広げるために、森林を伐ってゆけばよいのだろうか。
現在、熱帯森林資源は年間一一〇〇万ヘクタールずつ消滅している。四年間で日本の面積をこえる。
伐られた森林地帯はもとの姿にもどることはない。
大切なのは、人間の将来を考えて、科学による技術による判断を行うことである。
能率よく森林を伐るのも技術ならば、伐らないという判断を下すのも技術である。
食べ物の歴史を追ってきた。
地球規模で現状を記したのは、食糧の歴史のうちで現在が重要な意味をもっていることを、告げたかったからである。
食べ物の話に、チョコレートとか、砂糖とかを加えた。
食べ物に親しみ、人間の行ってきたことに親しみをもってもらいたいからである。
重要なことは食べ物の歴史は、人間が生きる条件の歴史であったということであって、この本ではその周辺を追って直接には記していない。
人間が住みつく土地は、作物ができよい飲み水が得られるところであった。
食べ物が手に入りやすい農業の適地だったから、人間はそこに集まった。
人間が集まると都市となり、農業の適地は失われていった。
ときには、砂漠化によって都市がほろんでいった。人間がくりかえしてきたことである。
食べ物の歴史には、人類の生き方すべての歴史が含まれているといっても言いすぎではない。
君たちに、明日を考えてもらいたいと思う。
不統一な原稿の整理などに、丸山八朗氏に御世話になった。付記したい。
top
**************************************** |