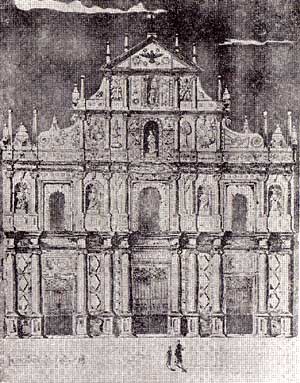|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
3 日本からインドへ
1 日本を離れる top
長い岬がつきだした静かな入江。
その岬の高合には、大きい教会がそびえ、海辺には今こそ帆をあげて走りだそうとしている三本マストの巨大な南蛮船。
長崎! ここは十年余り前から、ポルトガル人が来るようになった港です。
彼らは、「これこそ世界中で一番よい港だ!」と言いました。
長い航海に必要なたくさんの荷物は、もうすべて積み終わっています。
高台の教会から、大勢の人たちに送られて、きわだって背の高いバリニャーノを先頭に、使節となってヨーロッパまでいく人々が海辺におりてきました。
長い黒い服を着た南蛮のバテレン、それに、同じように黒い服を着た日本人……。
そして、伊東マンショをはじめとする四人の少年。
その顔は興奮をおさえぎれないように、赤みをおびて輝いていました。
そのとき、見送りの群集をかきおけて一人の婦人がとびだしてきました。
「バテレンさま! 私の子供を連れていかないでください。
ミゲル! いってはいけません。」
バリニャーノの顔色が、サッと変わりました。
彼はかたわらのバテレン・メスキータに一言、二言耳うちし、彼に通訳させて婦人にやさしく語りかけました。
ミゲルのお母さん。あなたはこの間お会いしたとき、賛成してくださったではありませんか。どうか……。」
「バテレンさま。いとしい私の一人ッ子のミゲルを、生きて帰れるかどうかもわからないところへ、手離すわけにはまいりません。」
「お母さま。私は……私は……、必ずミゲルを日本へ連れて帰ります。
自分の命をすてても、私はミゲルを守ります。 |

|
私はデウスさまに、その事をお誓いいたします。
お母さん。あなたの気持は、よくわかります。どうか、どうか、私を信じてください。」
ミゲル少年は、うなずいていました。少年の母親の目から、熱い涙がポロポロこぼれおちました。
バリニャーノの目にも、きらきら光るものがありました。
彼は見下ろすようにしながら、ミゲルのお母さんの両肩を大きな手でおおいました。
真心というのは、こういうものでしょうか。千々石ミゲルのお母さんの心は動きました。
そして、うなずきました。
高いマストによじのぼっていた黒人たちが、帆の綱を解き始めました。
「元気で!」
「ばんざーい。」
「さようなら。」
船はゆっくり、舳先(へさき)を外海にむけて動き出したのです。
見送りの人たちの顔が、みんな見えなくなるまで、いや日本の美しい緑の山野が、すっかり視界から消えさってしまうまで、船の甲板では、四人の少年は黙ってたたずんでいました。
「立派につとめをはたして、この長崎へ、きっと戻ってくるぞ。」
という決意が、みなの表情からうかがえました。
しかし、再び生きてかえれぬかもしれないとかもうと、胸のなかから、熱いものがこみあげてくるのでした。 |
 |
少年使節と同行する事になったのは、パードレ・バリニャーノと、メスキータとロヨラという、二人のイエズス会の修道土(イルマン)でした。
それに、コンスタンチーノ・ドラードと、アウダスチーノという日本の少年も加わっていました。
メスキータは、安土のセミナリオの先生をしていたポルトガル人で、日本語にも通じていました。
彼は南シナのマカオまでいったときに、パードレの位にあげられました。
ジョルジ・ロヨラは、かなりの年をとった日本人で、旅行中、使節の少年たちに日本語の読み書きを教えたり、日本文の手紙を書いたりする役目をおびていました。
コンスタンチーノとアウグスチーノの事はよくわかりませんが、ヨーロッパにいるあいだに印刷術を学んでくる事になっていたようです。
コンスクソチーノは使節の少年たちとほとんどかわらない年齢でしたのに、早くからポルトガル語が上達していたといわれています。
日本人がいま記したように、外国人の名前でよばれる事を不思議に思う人もいるでしょう。
それには、わけがありました。
日本人の名前のなかには、外国人に発音しにくいものや、彼らの言葉では、大変こっけいな意味になることがあったのです。
たとえば、「金谷」という姓をとりあげてみましょう。
それは、スペイン語では、「悪党」とか「ならず者」という意味です。
また「マリ子」という名前は、「女みたいな男」という事です。
そのような、こっけいな名前でよぶわけにはいきません。
そこで日本人の名前は、南蛮人のあいだでは別につけられることがあったのです。
また、私の名前の「マツダ」というのも、彼らには、いいにくい発音です。
そこで彼らは、「松かさ」の事を「ピーニャ」というところから、それに「ダ」をつけて、私の名宜えを「ピニェーダ」とよんでいました。
使節の一人に「原マルチノ」という人がいます。
この「ハラ」も、彼らは正しく発音できませんでした。
そこで「野原」の事をポルトガル語では「カンポ」といいますので、原マルチノは「マルチノ・デル・カンポ」と名づけられました。
長崎を出てから二日ほどは、海はおだやかでした。だが、三日めあたりから、嵐となってきました。
怒りくるったような波が白い歯をむきだしにして、次から次へ船を襲いました。
雨をまじえた激しい風が、ふきつのりました。
長崎の港で見てこそ大きかった南蛮船も、大海原では、まるで一枚の木の葉のようなものでした。
親切な船長のイグナシオ・デ・リーマは、自分の船に日本の殿さまの代理を務める少年たちが乗る事になってから、大変な気のくばりようでした。
船長は自分の部屋を、使節たちに提供しました。
千々石(ちじわ)ミゲルも中浦ジュリアン、原マルチノも顔はまっさおになり、吐き続けていました。
彼らはもうこれで死んでしまうのだと思い、くるしそうな呼吸をしながら、目をつぶって祈っていました。
不思議な事に伊東マンショだけは、船酔いに悩まされませんでした。
でも彼は生まれてから見た事も聞いた事もない恐ろしい嵐にすっかり脅えきって、ただガタガタ歯をならしていたのです。
2 マカオに上陸 top
十七日がたちました。
海面がにわかに静まって、まちにまった陸地が見えてきました。
それまでの青黒い海の色が黄色をおび、島かげでは釣り舟が帆をあげていました。
ジュリアンが甲板にでてきて、
「やれ助かった! 僕ははらわたが、全部でてしまいそうだった!」
といいますと、修道士のロヨラが、おなかをかかえて笑いました。
丘の斜面に、白い家がぎっしりと建ち並んでいます。
教会の塔もくっきり見えてきました。
ここは、ポルトガル人のアジアの根拠地マカオです。
南に向って吹く季節風はもうとまっていましたので、使節一行はここで秋まで実に九ヵ月もの長いあいだ、待っていなければならなくなりました。
慈愛深い父のようなバリニャーノが、練りに練った時間割にもとづいて、少年たちは高台にあるイエズス会の修道院で、毎日、勉強しました。
ラテン語とポルトガル語、それに日本語と音楽、それらが彼らの学習課目でした。
もちろん少年たちは、マカオの町を散歩して、めずらしい風物を見て楽しみました。
マカオは十六世紀のなかばごろに、ポルトガル人が住むようになり、しだいに大『きい町へと発展していったところです。 |
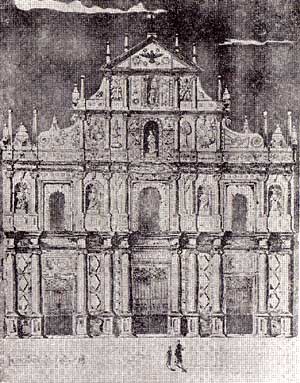
マカオの聖パウロ教会(復元図)
|
中国大陸から日本の天の橋立のような形に半島がつきでていて、その斜面と丘の上を人家がおおっているのです。 長崎も初めはポルトガル人が見つけて住みつくようになったところですが、やはり丘と斜面に町がかたちづくられています。
ポルトガル人は、よほど斜面がすきな国民とみえます。
このマカオは今では、近くの香港に繁栄を奪われ、寂しくなっています。
それでも、古いポルトガルふうな建物が、たくさん残っています。
なかでも、私たちの目をうばうのは、丘の上の“聖パウロ教会”の遺跡です。
それは、十七世紀に建てられたのですが、教会の正面の壁だけが、そそりたっています。
少年たちがすごした場所は、その隣の建物ですが、おしい事に十九世紀になって、火事で焼けてなくなってしまいました。
この辺りからの景色は本当に見事で、マカオの町がひと目で見下ろせますし、向うのほうに中国大陸を望むことができます。
川と海には、小さいジャンク(沿海や川で使う帆かけ船)がいっぱい浮んで、そのなかに、ちらほらポルトガルの軍艦が見うけられます。
使節の少年たちも、これと余り変わらない風景を眺めながら勉強したのでしょう。
さて一五八二年の大晦日に、一行は再び船に乗込みました。
|

マラッカの城と町
|
3 マラッカに入港 top
南へ、南へ。
それとともに気温はグングンあがり、甲板にでると太陽の光はギラギラとして、肌をこがすように思われました。
海南島の付近では、また大しけとなって、激しい波が船上を洗いました。
ドーンドーンと、音をたててぶつかった大波は、船に地震のようなショックをあたえました。
ザザザー!と、へんな音がしたかと思うと、高い船室まで海水が流れこんできました。
「沈没するぞ!」と、伊東マンショは叫んで、手をにぎりしめました。
千々石(ちじわ)ミゲルは、まっさおな顔をしたまま、柱にしがみついていました。
マレー半島の南端のシンガポールの町は、まだその頃にはつくられていませんでした。
このせまい海峡をとおりぬけるのも、航海者にとっては大変な苦労なのですか、使節の少年たちは、そこで漁師たちが小舟で魚をとる有様を見て楽しみました。
船はマレー半島の西海岸にそって北上を続けたのち、マラッカに入港しました。
高い丘の上には、“聖母の教会”がそびえていました。
城壁に囲まれたこの町は、まるで要塞のようでした。
ひさしぶりに陸上にあがった少年たちは、にわかに元気を取戻しました。
丘の教会にたどりつくと、マラッカ海峡が目の前に開けており、自分たちを日本からここまで運んでくれたリーマの船も、よく見えました。
パードレ・メスキータは、ここで次のような話をして聞かせてくれました。
「今から四十年ほど前の事です。
日本から逃れてきたヤジロウという侍が、今あなた方がいるこの教会で、聖なるバテレン、フランシスコ・ザビエルさまに、お会いしたのです。
ザビエルさまはこの男が、さきごろ見つかった日本という国からきた事を知って、大変驚きました。
そしてヤジロウと話しているあいだに、なんと日本人はすばらしい国民だろうと感心しました。
そして、日本へいく事を決心されたのです。
いいですか。人は外国へいくと、皆その国民の代表者となるのです。
あなたがたは、これからいく先々、いろいろの国で多くの人たちに会う事でしょう。
あなたたちを見た人たちは、アー日本人というのは、こういう人たちなのだ、と強く印象づけられるのです。」
少年たちは日本人としての誇りとともに、責任の重さを感じずにはおれませんでした。
私はそれから四百年近くもたったときに、このマラッカを訪れてみました。
ヤジロウと天正の少年使節にゆかりの深いこのマラッカの教会は、今では天井と屋根が崩れ落ちて、周りの壁を残すだけとなっています。
その壁の色は長いあいだ雨と風にさらされて、茶、赤、緑、灰色と、色とりどりに美しくそまっています。
私は、天正使節の少年たちの事を想い浮かべながら、その丘をくだっていきました。
そして海岸にでると、ポルトガル人の子孫にあたる人たちの村がありました。
そこから混血児らしい小学生や中学生の男の子が大勢でてきて、日本人の私がめずらしいのか、回りにむらがってきました。
その子供たちは、ポルトガル語を話していました。
それも二十世紀のポルトガル語でなく、十六世紀の古い言葉なので、私はびっくりしてしまいました。
そして、伊東マンショたちと同じ時代の人にあったような気持になって、とてもうれしく思いました。
4 苦しく、退屈な船旅 top
使節の一行は二月四日、日本では寒い冬だというのに、真夏のような暑さのマラッカを出帆しました。
スマトラ島が見えなくなると、あとはインドまで、二ヵ月の長い長い船旅が続きます。
あたりは毎日、毎日、はてしない大海原です。水平線から日がでて、船の上を追いこし、先のほうへしずんでいきます。
それといれかわりに月がのぼって、インド洋の海面に銀の粉をまきちらします。
「インド洋、月は東に、日は西に」
日本語の先生、ロヨラ修道士は、よい句がうかんだので、満足しながらノートに筆で書きとめました。
風がすっかりやんで、船はとまってしまいました。
熱をふくんだカラカラの空気が部屋の中でよどんでいました。
船の飲料水はどんどん少なくなって、船長は一同に、水の節約を厳しく命じました。
病人が続出したなかに、伊東マンショもいました。
彼の病いは、ますます悪化していきました。
熱は高くやつれはてて、手のほどこしようもありません。
彼を介抱するパリニャーノの姿は、見るにしのびないほどでした。
パードレは、つねにマンショのかたわらに付ききりで、時々目をつぶるほかは、横になろうともしませんでした。
「デウスさま、マンショを死なせないでください。私の命を、代わりに奉げます。
私はこの日本の少年たちを、彼らの母国まで、無事に送り返す事を約束してきたのです。
どうか私に、その約束を守らせてください。」
バリニャーノは、毎日、愛する神さまに祈り続けました。
無風と熱気との苦しく長い戦いののち、船はまた走り始めました。
涼しい風が、流れてくるようになりました。
夜空はすみきって、無数の星がまたたいていました。
船首にかきわけられた波の上で、夜光虫がキラキラ光りました。
本当に退屈でさびしい航海でした。
それだけに、セイロン島のコロンボの灯がゆく手に見えたとき、人々はどんなに喜んだ事でしょう。 |

伊東マンショが重い病にかかったので、回復を祈るバリニャーノ
|
|

ポルトガル船の寄港地、マカオ、マラッカ、コロンボ、コーチン、ゴア(現パナジ)
|
5 バリニャーノとのわかれ top
一行は南インドに上陸し、陸路をとってポルトガル人の根拠地であるコーチンにたどりつきました。
そしてこの地で、またしても半年ものあいだ、留まらねばならなくなりました。
少年たちは暑さに悩まされながら勉強を続けており、バリニャーノは総長に差出すために、せっせと日本についての長い報告書を書いていました。
十月二十日の事です。彼のもとに、ローマの総長から、一通の手紙が届きました。
これを読んでいたバリニャーノは、ハッと立って手紙を机の上に置き、しばらくは動こうともしませんでした。
彼は少年たちを連れて、ローマまで行く積りでいたのです。
ところが、この総長の手紙には、
「あなたは、東洋のわが会の最高責任者として、インドに留まって指揮しなさい」
と、書かれているではありませんか。
彼は、総長の命令に絶対服従せねばなりませんでした。
それに遠く離れたローマまで、どうしてこちらの事情や気持をすぐに伝えることができるでしょう。
バリニャーノは元気になった使節の少年たちを見ながら、この悲しい知らせを語る気持になれませんでした。
彼は自分に代わって少年たちをヨーロッパまで連れていく人に、厳重にそして細かい注意を書いて渡す事にしました。
「使節の目的は、日本での布教に必要な援助をもとめる事である。
また、日本人に、キリスト教の偉大さを知らせる事である。
そのためには、国王陛下の宮廷や、ポルトガルその他の町で、信仰に役だつもの、教会・宮殿・庭園・金銀財宝などありとあらゆる、すばらしく偉大なものを見せるべきである。
それに反するようなものを、いっさい見せてはならぬ。」
「ポルトガルについたら、学生風の洋服をつくってもらって着せるがよい。
日本の着物は、王家の方々を訪問するとき以外には、着せぬようにせよ。」
「少年たちにはいつも案内者がつきそっていき、良いものだけを見せるように。悪いものはけっして見せてはならぬ。」
「彼らはいつも、修道院に宿泊させて、いっさい外部の人と付き合わせてはならぬ。」
バリニャーノは思い浮ぶ事を、書き続けました。
日本でのキリスト教の発展と、少年たちの旅行の成功をひたすら願っていた彼は、自分の命令がいよいよ厳しくなっていく事を、どうしようもなかったのです。
「彼らはまだ子供だ。子供が悪にそまらぬようにと願うのは、当然の事だ。
自分は彼らの主君と親から、あの子たちを預かってきたのだ。私はあの子たちの父親なのだ。
どうか、良いものだけを見てきておくれ。ヨーロッパ世界は、良いものだけではない。
見せたくない悪もはびこっている。
キリスト教の世界は、なんとすばらしいことだろう。
ヨーロッパ人は、本当に偉大だという印象をもって、帰ってきてほしいものだ。」
バリニャーノは時々ペンをおいては、自問自答しました。
彼はふと思いついて、その注意書きにこんな事も書きつけました。
「少年たちを階上に泊らせないように。階段をおりるときに、怪我でもしてはいけないからだ。」
旅先では十九も、二十(はたち)にもなっていく使節たちに、このような幼児にたいするような注意が、不必要であることはいうまでもありません。
しかし私は、こんな事まで書いたバリニャーノというパードレ(神父)の気の使いようを、いとおしく思います。
ありがたいことだとも思います。
コチンからポルトガル領インドの都ゴアについて、バリニャーノは深い悲しみのうちに、少年たちに別れねばならなくなった事を知らせました。
少年たちが嘆き悲しんだことは、いうまでもありません。
top
****************************************
|