|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 年表
1 メッチャカ人生
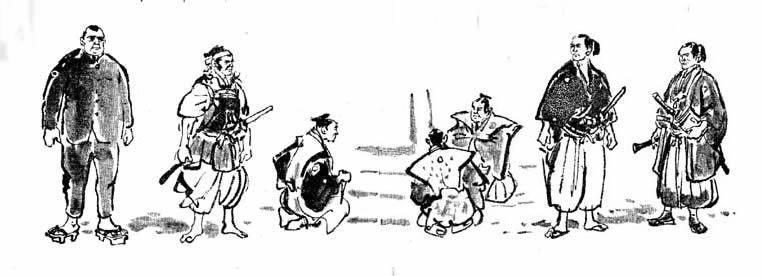
正月の男の子の遊びは凧上げ。
一番小さいのが紙一枚の一枚張りという奴。それから二枚張り二枚半張り、四枚張りとだんだん大きくなって十二枚張りなんていう、唐紙のようなのもある。
奴凧、とんび凧、字凧、絵凧、剣凧と思い思いの凧が、真青ながら初春らしいうるんだような空を威勢よく舞い上っている。
「ヤア、上ってるな。元気がいいぜ。子供が空を見上げるのは体にいいんだ」
大人も、凧上げの子供が、めくらめっぽう後ずさりで駆けようが、自分の方から避けてやる。
江戸一番賑やかな日本橋なんて町家の混みあったところは、物干しや屋根へ上ってあげたもんで。
小吉が青海波の絵だこをもってかけると、体はすっぽり凧の影に入ってしまう。
体にあった一枚紙か、奴凧くらいにしておけばいいのに、何でも負けず嫌いだから四枚紙なんてのをひきずってかける。
うしろに目がないものだから、バタと誰かにぶつかった。
「ヤイ、気をつけろ、馬鹿野郎め」
と、どなったのは前の町の仕事師の子の長吉で今年八つになる。
長吉も凧をあげて糸をひくのに無中だから往来をくる者なんか見ちゃあいない。
つきあたられた拍子に手が狂って、凧はくるくる舞い落ちてきた。
「この野郎。てめえのおかげで俺の凧が落ちたぞ」
長吉はやにわに小吉の凧をうばいとると張り張り紙を破いた。小吉はまだ五つだが侍の子である。
「何をする」
と、長吉のむなぐらにとりっいた。
「しゃらくせい。こうしてやらぁ」
長吉は小吉をつきとばし、凧をめちゃくちゃに足でふんづける。
小吉は道の石をひろって、「おのれ!」と、顔をひっぱたいた。
石は長吉の唇を切って、血がパッと散り、だらだらと流れ出る。
血を見るとだらしがない。長古はウェーンと泣きながら逃げ出した。
泣き声を耳にして、垣根ごしにこっちを見たのが、小吉の父、男谷(おとや)平蔵だ。
旗本で千石取り、御小十人頭という役。すぐ下男が呼びにきて小吉は父の前にすわらされた。
「小吉、おまえは何という奴だ。人の子に傷をつけてすむかすまぬか、そんな事がわからぬか」
小吉は小さな体を岩のようにつっぱっている。五つの子とは思えぬふてくされようで返事もしない。
平蔵は、
「こいつ、どうすればわかる。おまえも相手の身になってみろ」
と、いきなり縁の柱に縛りつけると庭下駄で思いきりびっしやり頭をなぐりつけた。
「……」 |
 |
小吉はあやうく目を回すところだった。
ぶたれたところがぺこんと音がしてへっこんだようだったが、皮が破れてみるみる血があふれた。
これくらいのせっかんで小吉の乱暴がやみはしなかったが、この傷跡は一生残って小吉を困らせた。
江戸時代のことだから頭の前をそってちょんまげを結うのだが、この頭をそるとき傷跡のへこみにかみそりの刃がひっかかって血が出る。
そのたびに、長吉や父の事を思い出すのだった。
男谷平蔵の家は、江戸、本所にある。
小吉が七歳のとき父は将来の事を考えて勝家へ養子にやることにした。
どういうわけかというと、自分が死んだ場合、長男の彦四郎があとを継ぐ。
これは千石そのまま引継ぐ事ができる。
が、二、三男は禄がもらえないしきたりだから兄の世話にならねばならない。
二、三男で一生嫁ももらえないという話はたくさんある。
それでは兄も弟たちも困るばかりだから三男の小吉だけでも一本立ちできるようにしておいてやろうとしたわけだ。
ちょうど勝甚三郎という四十一石とりの貧乏旗本が亡くなって、後継がない。
母と五つになる女の子だけなので男の後継をきめないととりつぶしになってしまう。
ここへ養子にやって勝の家を継がせれば、何とか一人立ちもできるだろう、というわけ。
それで勝家へ金を出してやって七つの小吉と五つの女の子のぶを、行く先夫婦にすることにして、勝小吉と名乗らせ男谷家の別棟に一家三人を住まわせることにしてやった。
養子になって勝家の跡取りになりましたといっても、ちゃんと支配頭に届けでて許可をもらわなくちゃならない。
家を継ぐには元服をすませてないと駄目で、元服というのは普通は十六歳、大名などの格式のある家では十五歳で元服、つまり成年式をやる。
ところが小吉はまだ七歳。もちろん元服なんか先のことだが、支配頭へ届け出るには当人がいかなくちゃ駄目なので羽織はかまで小普請支配頭石川右近将監のところへ挨拶にいった。
「勝甚三郎の養子か。名は何という」
「小吉と申します」
「して、年はいくつになる」
「十七になります」
と、十もさばをよんだ。十二、三くらいならまあまあだがこれには石川もあきれて、
「イヤ、十七とはふけたなあ」
と、大口あけて笑った。それで届けはすんでしまった。形さえ整っておればよかったのである。
これで正式に勝家の主人になったのだから、名前もえらそうに左衛門太郎と改めたが、なあにまだ子供だから婿入りもへちまもない。同じように父の家にいるのだし毎日遊ぶのが仕事で、喧嘩ばかりやっている。
子供の喧嘩は大抵町と町と分れてやる。こちらの町と隣町の境に木戸というものがあって夜になるとしめる。
江戸八百八町はみなこうなっていた。
それだから余計子供たちを区分けしてしまい、何の理由もないのに憎まれ口をたたきあって喧嘩をする。
棒や長い竿をしごいて槍にし、町人の子は前だれをしていたからこれで頭をつつんで兜にし、敵も味方も木戸口を城門に見たてて、石をぶつけあい、槍をしごいて突き合う。
親が驚いてとびだすとたちまち敵も味方も蜘蛛の子をちらすのが普通で、この子供喧嘩というのが実に多かった。
ところで七つの勝小吉はたった一人で前の町の子供二、三十人を相手に闘った。
初めのうちは小吉も竿で叩きあっていたが、何しろ敵は数が多いからだんだん追いつめられ、物干し場になっていた石塀の上へ追いあげられ、長い竿で散々叩かれた。
元結が切れて髪はさんばらになり、とうとう泣きだしてしまった。それでも降参するとは言わない。
泣きながら刀をぬいて、ついてくる竿を右に左にきりはらっている。そのうちにもうどうしようもなくくたびれてきた。
「畜生、もうこれまでだ」
いきなり石の上に座り込んでぐっと着物の前を開いて腹をだした。
武士の子らしく腹を切ろうと思ったのだ。
そうしたら攻めていた子供の方が青くなっていっせいに竿を引いた。
町人の子ばかりだから震えている。わっといって一人逃げ出したと思うとみんな大あわてに駆け出した。
その騒ぎで米屋の親父が出てきた。
「あれ、男谷のお坊ちゃま。あぶない、おやめなされ」
米屋の親父が体をだきかかえておろし、家まで送ってくれた。
一人で大勢を相手に闘うときの度胸がこうしてついていった。
八歳の時にも大喧嘩をした。
小吉の飼っている犬と亀沢町の犬がかみあった。
それが喧嘩のもとで、小吉の方は隣の家の安西養次郎が十四歳でかしら、近所の黒部金太郎、弟の兼吉、篠木大次郎、青木七五三之助、高浜彦三郎、同じく七歳の弟鉄朔の合計八人でみんな侍の子。
亀沢町の子供たちは緑町の子供を加勢に頼んで四、五十人ばかり、喧嘩好きの子供ばかりだから用意がよい。
いつもの竹竿をもつて叩いたり、ついたり。
こっちの方が六尺棒や木刀や竹刀を思い思いに持って振り回し、
「こん畜生。やっちまえ」
と、追って出ると、そら出てきた、逃げろと汐のひくように退る。そしてはまたわっと押しよせる。
小吉らは家の門を砦にして暴れた。
手ごわいとみたか、町の子供たちがばらばらと引き下がり、八人がほっと一息入れていると今度は大人が先頭に立って攻めてきた。
血の荒い若い衆がガンガン竿をふりたてるから、小吉らはたまらず追い立てられ、とうとう隣の滝川家へ逃げ込んで門をびっしやりしめて防いだ。
「ヤーイ、卑怯者。出てこい」
「門をぶちこわすぞ」
そのうち丸太をもってきて、トーンと扉を突きだしたから八人が覚悟をきめた。
こうなれば武士の面目見せねばならぬとなまくら刀を引抜いて門を開けた。
「それいけ」
と、切って出る。子供の刀は刃どめがしてあるが、切れば血は出るから町の連中は驚いて逃げ出した。
こっちは追いかける。七つの鉄朔が一番先にかけていく。
すると前の町の仕立屋の子の弁次というのが引き返してきて竹槍で鉄朔の胸をついた。
そこへ小吉がとびこんで弁次のみけんを、「えい」と、切りつけた。
「ウワー!」
と、弁次はしりもちをつき、ころころとどぶの中へ落っこちる。そこをまたつづけさまに顔を切る。
なまくらだから大して傷にはならないがひどく痛い。知らせがはいったか親父がとんで来る。町中大騒ぎになった。
八人の侍の子供らは、ザマー見ろとばかり滝川の門内にはいり、やったやったと勝鬨(かちどき)をあげた。
そこまでは威勢がよかったがまた父平蔵に散々叱られ、三十日間押込められて目通りを止められた。
部屋に閉じ込められて父の前へは出られないのだから、いいやら悪いやら、やっぱり退屈だから仕置にあうのはつまらない。
侍の子だから武芸を習う。
九歳から柔術、十歳馬の稽古、十一歳剣術、十二歳学問。どこへいっても問題をおこす。
暴れん坊でみんなに憎まれるのだ。 。
柔術の寒稽古の時、夜つぶしといって夜おそくまで稽古をする事がある。その時それぞれ夜食をもちよって勝手ほうだい食べあう。小吉も重箱に饅頭をつめてもらって持っていき、夜十二時稽古が終わって、
「さあ、みんなでうまいものを食おう」と、ごちそうを出しあった途端、「それ、やっちまえ」と稽古仲間がいっせいに小吉にとびかかり、しぼりあげて天井から吊り下げてしまった。
上から見おろすとみんな車座になって、うまいうまいと食いあっている。小吉の饅頭もむしゃむしゃ食っている。
「泥棒。ぬすっと。饅頭は俺のものだ」
と、小吉は怒鳴ってあばれたが、みの虫みたいにぶら下ったままだからどうしようもない。
「畜生、これでも食らえ」
ジャーと、そのまま小便をふりまいた。
「わあ、きたない」
「ペッ、ペッ」
これで楽しい夜食もメチャメチャになった。
剣術の道場では支配頭石川右近将監の息子も一緒だったが、このせがれが小吉を馬鹿にする。
親がお頭でその取締りにあっているのだから家来同然。
「こいつはたった四十一石とりの身分だ」と、大勢の前で笑う。
四十一石というのは、勝家の禄高で、一年にそれだけの米を徳川幕府からもらっている事。
それも表高で実際には八石ほどしか入ってこないから、まるまる売ったとしても今の金で二〇万にもみらないから、とても暮らせるものではない。
小吉は一生貧乏で苦しんだが、この時はまだ十一歳で男谷の父が面倒をみてくれていたから食うに困りはしない。
それだけに癪にさわる。お頭の子だからと我慢に我慢をしていたが堪忍袋の緒が切れて、
「おのれ、人を馬鹿にしおって。口でなく剣術でこい」
と、木刀をとってボンボン打ちこみ、倒れたのを思うさまぶちのめした。
相手は蛙のように平つくばってオイオイ泣いたので、先生の鵜殿(うどの)甚左衛門が奥からとびだし、
「これ何をする、謝りなさい」と叱りつけた。
下の者が上の人をやりこめるなんぞは天と地がひっくり返るほど悪い事とされていた時代だ。
学問の方は、幕府の学問所、聖堂(せいどう)の林大学頭へ挨拶をし、先生たちに教えてもらったが一日で嫌になり、毎日逃げ出しては馬にばかり乗っていた。
子供の頃からこんな具合で喧嘩ばかりしている。
十三の時に家出をして東海道を乞食のようにさまよい、帰ってからは剣術修業や他流試合に精を出した。
二十一歳の時にまた家出をして旅先で剣術を教えていたが、当時旗本が勝手に江戸を抜け出るのは禁じられていて、家をつぶされ死刑にもなりかねないことだったから、旅先で人に意見をされ、それならばと江戸へ戻ったところを待ってましたと家の者に捕まった。
父平蔵はもう承知できん、押込めてしまえと座敷牢を手回しよくこしらえていて、ぶちこんでしまった。
太い柱格子でふさいだ三畳間で、二十一の秋から二十四の冬まで小吉はこの中に押込められていた。
本編の主人公勝麟太郎がオギャアと生まれたのが一八二三年(文政六年)一月十三日。
生まれたての赤ん坊にはわからないが親父は牢の中に入っていて、初めての子供を抱いてやることもできない。
赤ん坊がヨチヨチ這い、物につかまって歩くようになって見ると、親父は太い格子の中にいて、食事はお膳を穴からさしこんでもらっている。
退屈してポカンとしている時もあれば、何か本を読んでいる事もある。
友達がきて牢の中と外で笑いあうこともある。友達がくると婆さんが嫌がって、聞こえよがしに、
「また悪い奴が来る。あんなのと付き合うからろくでもない」
と、文句をいう。母親ののぶも可愛い子供を父親に抱かせられぬのでしじゅう悲しがる。
麟太郎が生まれて初めて見た光景がこんな有様だから、幼な心に暗い影をおとした。
赤ん坊のくせに何に腹を立てるのか、疳癪もちである。
さすがに親の小吉も、長男ができたのにこんな有様ではいけないと反省した。
いまは小普請組といってなんにも仕事のない身分である。
大体幕府には文官と武官の役があって、何かの役につくとお手当がつき、毎日出勤もして威勢もよいが、何の役もない小普請組ほど辛い者はない。
大の男がいつ役に付けるかと待ちながら、ブラブラしているのだから、はた目にもむさ苦しい。
小吉も長兄の男谷彦四郎燕斉が信州へ出張した時についていった事があるが、江戸からお旗本の殿様の御入来といって、それは威張ったものだったし、自分までいろんな贈り物をもらった。
もういい年になったのだから、どこかのお番に入れてもらいたい者だ。
番というのは大番、書院番、小姓組番、新番、小十人組という五つの組でどれも警備の役目である。
どれでもいい、入れたら手当もつき俸禄も上がる。
四十一石が百石になるだけでも違うというものだ。
ただ小吉のように役の無い者が大勢いる。
徳川幕府始って二百年この方、戦争が全くないのだから侍の用はぐんと減っている。
旗本五千、御家人一万七千が幕府直属の家来だが、御家人はあぶれ者がいっぱいいる。
そういうのが小吉と同じように役につきたがってお頭のところへ、へいこら頼みにゆく。
小吉は二十四歳(一八二五、文政八年)の冬、牢を出されると、さっそく就職運動にとりかかった。
夜の明けぬうちに上下をつけ提灯をつけて本所の家をとびだし、赤坂の支配頭大久保上野介(こうずけのすけ)の屋敷へゆく。
行ったって大久保が役所へ出勤するのをハアッと平伏して見送るだけだが、これを毎日やる。
ほかの奴もまけずにやっている。
小吉は面会日に挨拶をして、ついでにこれまで自分のやった悪い事をみんな書き付けにして差出した。
これまでこんな悪い事をしてきた、しかし心を入替て出直し一心に働きたいと気張っている、と心のうちをさらけだした。
大久保が調べさせてみるとその通り、実に何度も家出をしているし、喧嘩はするし、座敷牢にも入っている。
それを洗いざらい書き出している小吉の死物狂いの正直さ、熱心さが大久保にはわからない。
ただただあきれてしまった。大久保は、
「大抵は隠すものだが、お主はよく打明けた。しかし改心して満足だ。そのうち取立てやるからしっかりやれ」
と口先だけうまい事をいう。
小吉はその積りでますます精勤してハハァと頭を下げにいき、剣術も一生懸命励んでいたが、一向に何の音沙汰もない。
支配頭の方では調べてみてあんまり乱暴者だから、取り立てる気なんぞまるっきりないのだ。
そうしているうちに父の男谷平蔵が亡くなり、勤めに出る気もすっかり無くした。
食うために刀の売り買いをしたり、古道具やをやったり、喧嘩の仲裁をしたり、道場破りをしたり、貸し金の取立をやったり、ゴロツキの親分になったり、だんだん町の顔役といったふうになった。
金ができたときは、元々気っぷのよい質(たち)だからむやみと人におごる。
博奕などもやる。負けると金をこしらえなくてはならぬから借金する。
ちょうど天保の大飢饉とぶっかったときなんぞは、貧乏のどん底におちてしまった。
子供の麟太郎も貧乏に慣れていたが、この時は土の団子を食って体中黄色くなって生きのびたものだ。
兄の彦四郎燕斉は文学好きの静かな人柄だったが、街のならず者のような弟を野放しにしておいては家名にもかかわるので、父と同じように座敷牢をつくって閉じ込めようとした。
兄の家から呼出しがきた時、小吉は覚悟をきめた。実は兄貴の名前で黙って借金をしている。
今度はもう駄目だと覚悟をして本家へ出かけていった。
兄は留守で、兄嫁が涙を流しながら庭にできたばかりの檻を指さし、
「あれごらんなさい。兄さんはあなたを檻(おり)に入れようとおっしゃっています。
いくら私どもがとりなしても聞きいれてくださらない。
息子の精一郎も、叔父さんを檻に入れるなんてあんまり情ないと頼みましたが、とうとう檻ができてしまいました」
と、いった。
二重でかこった厳重な牢が庭にできている。
「姉さん、私は覚悟をきめてきました。何も思い残す事はありませんから、檻の中で断食して死にます」
「まあ、そんな無茶をおっしゃっては困ります。兄さんにはよくいいますから、どうか今日はお引取り下さい」
兄嫁はやさしい人で、小吉がおとなしくなるよう願かけをした事がある。
その人のいうことだから素直に家へ帰った。
彦四郎が戻って話を聞き、断食をして死なれても困るので、牢はやめて、今後はまじめになると証文を書かせようとした。
が、そんなものは嫌だといって、書かない。
兄嫁はいっそう心配して、今度も寺詣りをして願をかけた。
これには小吉も参って、もう兄嫁に心配はかけませんと隠居をし、家を麟太郎に譲ることにした。
この時三十七歳、麟太郎は十六歳だった。
小吉は隠居になってもまだ三十代の若さだから相変わらず博奕は打つし、遊びまわるし、人を脅すし、ゴロツキみたいに世間を押し歩くのでとうとう組頭から他行(たぎょう)止めといって出歩くのを禁止され、一八五〇年(嘉永三年)四十九歳で亡くなった。
小吉が三十六歳の時には天保の飢饉に苦しむ人々を救おうとして大塩平八郎(おおしお・へいはちろう)が大坂で兵をあげた。
また三十八歳の時には海外に目を開いた洋学者渡辺崋山(わたなべ・かざん)、高野長英(たかの・ちょうえい)らが幕府につかまる蛮社の獄という事件があった。
勝小吉は学問嫌いで洋学も知らぬし、大塩平八郎が民衆のために起ち上がった理由も考えなかった。
これが息子の麟太郎の時代になると黒船がやってきて日本をゆるがし、外国の勉強、洋学をやって目を広く世界にむけ、アメリカへ渡り、尊王討幕の嵐の中で日本のゆく道を見定めて大活躍し、小吉が一生役にもつけずに終わったのに、どんどん役にもつくし階級も上がってゆくことになる。
小吉の時代は幕府も腐れきって古くさいしきたりばかり重んじ、力のある元気な若者を引抜く事は全くしなかった。
小吉は小普請組四十一石取りという無役の日の当らぬ場所で、一生不平不満をぶちまけて暴れ通しただけだ。
小吉の時代は暗かった。 |

|
top
****************************************
|