|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6 7
8 9
10 11
12 13
14 年表
3 蘭学(らんがく=オランダ語)猛勉強
本を読まずにおれない人がいる。
昔の人は、一日本を読まないと目に垢ができるといった。
書物というものは自分の知らない、気づかない事を教えてくれるので、新しい事を知ったとき思わず目が洗われたようにハッとする。
目がさめる心地がする。
麟太郎も蘭学を始めたらおもしろくてたまらない。
毎日、本屋へいって、「何か新しい本はないか」と探すのだが、そういつも珍しい本があるわけではない。
国内での出版の数がいたって少ない上に外国、主にオランダからだが、そう次々と入ってくるわけでもなく、仮に入ってきても部数が一部二部という貴重なものばかりでめったに手に入らない。
でも、麟太郎はハゲタカが獲物をねらうように本屋を歩きまわる。
ある日の事、なにか今日は当りそうな胸騒ぎがして本屋へやってきた。
「ある!」初めて見るオランダの本がある。
胸をワクワクさせながら、うわべは平気な顔をして手にとってみると兵学の本だ。
兵学すなわち軍事用で、麟太郎は父や本家が武道の筋、島田先生の教えもあって、もっぱら兵法の学問をしているのでとびつく思い。
が、足元を見て高く吹きかけられては困るので、落着きはらって、
「これはいくらだ」
本屋の主人は、あなたのような貧乏旗本にはとても無理だというように、
「天下に二冊とない珍しいものですから、お値段は五十両で願ってます」と、麟太郎の手から本を取上げた。
五十両――ウームと麟太郎はうなった。五十両といえば、米が三十石買えた。
勝家は表むきは四十一石どりだが実際は一年に八石たらずの収入、鯱(しゃちほこ)立ちしたって及びもつかない。
あきらめて一旦は店を出たものの、道を歩いても家に帰っても本が目先にちらついて、いてもたってもいられない。
いらいらして一人プンプンしている。
とうとう我慢できなくなって親類へ金を借りに出かけた。
こういうとき本家の男谷(おたに)家がしっかりしているからありがたい。精一郎信友が心よく金を出してくれた。
「さあ、しめた」
麟太郎は目を血ば知らせて本屋へかけてゆく。
「さあ、くれ」
「はてなんでしたろう」
「オランダの本だ。兵学の本だ」
「ああ、あれならもう売れてしまいました」 |
 |
「エッ、なぜ売ってしまったのだ」
体がブルブル震えるほど腹が立つ。
「ヘイ、別にあなたさまはとっておけともおっしゃりませんでしたし……」
麟太郎はやっと落着いてきいた。
「そして、どこのどなたが求められた?」
「ヘイ、四谷の大番町にお住居の与力(奉行のもとで下役を指揮する役)のお方でございます」
名を聞くなり麟太郎は駆け出し、四谷の与力の家へとびこんで頼んだ。
「私にゆずって下さい。金をつくるのに手間どってあなたに買われてしまったのです」
相手は、失礼な奴だとにらみつけ、
「拙者も必要あって求めたのだから譲るわけにはいかない」とつっぱねる。
「それならしばらく貸して下さい」
「それは困る」とりつくしまもない。しかしオメオメ引き下る麟太郎ではない。
「それではお読みにならぬ時に見せて下さい。夜、お休みになってしまえばご入用ござるまい。あなたの寝ていられる間、貸して下さい」
これには相手も驚いた。
「それなら四つ時(夜十時)過ぎには寝ますからそれから朝までお貸ししよう。しかし本を持ち出されては困るから家へきて読んでもらいたい」
「ありがとうございます。そうさせて下さい」
それから毎晩本所から四谷まできて、十時から本を写しとり、夜明けに帰ってゆく。
そうして半年がかりでとうとう写しおえた。中には意味のわからぬ事がたくさんある。
「これはどういう意味でしょう?」と、与力に聞くと向こうは頭をかいた。
「いや、あなたの根気には驚きました。拙者など毎日そばにあっても到底読み進めない。
第一言葉がよくわからない。宝の持ちぐされとはこのことだ。よろしい、あなたにこの本を差上げましょう」
「いえ、私はもう写させていただきました。お礼の申しようもありません」
麟太郎は貧乏の余り、写しとったこの本を後に売りはらったが三十両になった。
一八四五年(弘化二年)、麟太郎は二十三歳で妻をもらった。君江さんという。
そのあくる年、もっと蘭学勉強にうちこみたくて永井先生のそば、赤坂田町へ若夫婦で引越した。
この頃、外国船がどんどん日本へくるようになった。
元々日本は三代将軍家光が鎖国令を出して外国との交際を打ちきって二百年余り、中国とオランダだけ長崎で通商を許すだけで、ほかの国の船はいくらやってこようと寄せ付けない。
ところが世界の海運は次第に進んで、帆と蒸気の大きな船がよその国との通商を求めて、七つの海を押し渡るようになってきた。
フランス船が琉球に来る。
アメリカ船が漂流した漁民を送って浦賀に来る。イギリス船が長崎へ来る。
麟太郎が結婚した前の年でもこんな有様で、続いてフランス軍艦、イギリス船が沖縄に来る。
アメリカ人七名がエトロフ島に流れつく、アメリカ東インド艦隊が浦賀に来る。
ヨーロッパのただ一つの通商国であるオランダからは国王の親書がきた。
それは、もう鎖国の時代ではない事、広く世界の国々と付き合うようにすすめる事、イギリスが中国を攻めたアヘン戦争(一八四〇年)の勝利に乗って日本を攻めるのではないか、という注意だった。
幕府はオランダ国王の開国の勧めには反対だったが、中国のような大国がイギリス海軍に負けたことには神経をいらだたせた。
なにしろ長い間の鎖国で大船の製造を禁止していたから、外国船を見ると大きさにびっくりして心細くなってしまう。
沖縄に近く長崎をかかえた九州の大名たちはほかの大名にくらべると、早くから国の防備に熱心だった。
永井先生の殿さま黒田斉溥や佐賀藩主鍋島斉正(なりまさ)らは長崎の防備を幕府に訴え、幕府はあわてて大砲をつくる許可をあたえる有様。
外国船の渡来は長い太平の夢にひたっていた幕府や大名たちにいいようのない不安をあたえだした。
こうなると外国を知るためにいっそう蘭学の必要になるのは当り前で、麟太郎が勉強に夢中になるのも押しよせる外国船の波しぶきにいっそうあおられたからである。
蘭学を勉強するには、何といっても言葉の意味をしる辞書がいる。
この頃オランダ語=日本語の辞引きは『ハルマの辞書』だけだった。
これは長崎でオランダ人の通訳をする人達がつくりはじめ、途中亡くなる人もあれば新しく加わる人もあって、結局白河藩松平定信の家来、石井恆右衛門(つねえもん)がまとめた大事業で、ハルマという出版者の『オランダ語=フランス語辞典』を元に作った我国最初の辞引き、語数六万四千三十五、これを五十八巻にまとめ三十部だけこしらえた。
その一組が江戸の蘭学者大槻玄沢(げんたく)におくられ、熱心に写す人達の手で少しずつふえていった。
これを買おうとすると六十両。相変わらず貧乏な麟太郎には手が出ない。
そのうちにオランダ医者赤城という人がもっていると教えてくれる人があった。
そうなると麟太郎はもう我慢ができない。早速押しかけて、
「是非写したいからお貸し願いたい。一年のうちには写せるでしょうから、一ヵ年十両のお礼でいかがでしょう」
と、相手がいやといおうがお構いなく、粘りに粘って借り出しに成功した。
それから朝も晩も一日中机に向いっぱなし。
この時の勝家の貧乏はお話にもならない。
煮たきをする薪を買う金がないので、初めは天井板をはがしてしまった。
それから縁側をこわした。しまいには柱をけずった。
切ってしまうと家がつぶれるのでけずって薪をこさえるのだ。
畳みも破れたのが三枚しかない。妻の君江さんはぼろぼろの帯を年中しめている。
夏は蚊帳がなく、冬は火がない。
麟太郎は稽古着一枚で夏も冬も頑張り、寝るのも机にもたれたままで、目が覚めればそのまま書き続けてゆく。
秋から初めてあくる年の秋がやって来る。
ようやく写しおえたときのうれしさ。
「できた。やった。やったぞ」
と、怒鳴っておどり上がったが、はて一年十両と約束した借り賃と紙屋の払いができない。
「ようし、もう一部作ってやれ」
一度写したものはやりやすい。今度はスピードが出た。
こうして二部作っだので一部を売って無事謝礼もだせ、米代もたっぷりできたが、麟太郎はぐったりして目はおちくぼんでしまった。
しかし世の中は見捨てたものではない。これほど努力しているのだから、どっからか救いの手がさしのべられる。
この時は同じ本好き勉強好きから、それも遠く北海道箱館の商人からだった。
麟太郎がたびたびのぞきにゆく本屋が日本橋にある。
店の主人嘉七は麟太郎の貧乏を知っているから立ち読みをいくらしようとちっとも文句は言わない。
この店へ北海道から商用で江戸へくるたびに寄っていく渋田利右衛門という人がいる。
嘉七がこの商人に、
「勝さんという御家人で熱心な方がいる。よく勉強していなさる」
と、話した。嘉七の紹介で、二人はこの店であった。
渋田は自分の宿屋へ無理にひっぱっていって、子供の時からどんなに本好きだったか、話した。
色が白くてやせ型で、ちょっと見ると女のようだがどことなくしっかりしていて、芯が強そうだった。
二、三日すると渋田の方から赤坂の家へ訪ねてきた。
なにしろ天井もない、破れ畳み三枚のあばら家だが渋田は一向に平気な顔をしている。
そのうちに昼になった。話はつきないし、先日はごちそうになっているので、そばをとった。
そばは十六文ときまっていて一番安い食い物である。それを喜んで食べた。
やがて帰る時になると渋田は懐から二百両の金を出していった。
「勝さん、失礼ですがこれで本でも買って下さい」麟太郎は余りの大金に面食らって返事ができない。
「遠慮なくとって下さい。珍しい本をお読みになったら私に教えて下さい。翻訳して下さればなおありがたいですよ」
と、別のふろしきから渋田用箋と刷った罫線の束を差出した。
紙にも困るだろうと思って持ってきてくれたのだ。
麟太郎は感激した。二百両はうれしかった、用紙も助かった。
しかしなにより渋田の人柄が何ともいえずよかった。
町人であろうが商人であろうが人間は心できまる。
ろくでもない武士どもより、この人とは生涯長く付き合いたいと麟太郎は思った。
渋田とはその後もたびたび手紙のやりとりがあった。 |
 |
やがて麟太郎がだんだん出世するにつれて我が事のように喜び、自分の取引仲間の立派な商人を紹介して、いざのときの後援を頼んでくれた。
のち、神戸の海軍所を造った時など、これがどれほど役に立つたかわからない。
こんな親友が口惜しいことに長崎海軍伝習所へ入るとき亡くなった。
麟太郎はのちに幕府最高の役についたがそれを見ることもなかった。
アメリカへ渡った話もできなかった。麟太郎にとってもっとも心残りな渋田の死だった。
さてもう一人の人がいる。
麟太郎のゆくべき目標をさし示してくれた時代の英雄、佐久間象山にあったことだ。
象山(一八一一〜六四)はずばぬけた新しい人で、蘭書をもとにガラスを作り、電池を作り、地震計を作り、元込め銃を作り、四つ足として嫌われた牛肉も大好きという開けた人たった。
信州(長野県)松代藩の江戸屋敷で蘭学を教えていたが、この象山門下には吉田松陰、坂本竜馬がいる。
のち松陰が下田にきたアメリカ軍艦に乗ろう(一八五四、安政元年)として捕えられた時、象山がそれをすすめたのを理由に獄に入れられたがやがて許され、今度は幕府の命令で攘夷攘夷とやかましい京へのぼって朝廷へ開国の必要を説く役目をやった。
西洋式の服装で平気で京の町をのし歩き、川上彦斉という殺し屋に切られた。
この象山は麟太郎より十二歳年上になる。
麟太郎は蘭学の先輩として敬意を表しにいった。
一見、象山はひどく麟太郎を気に入り、
「これからの日本は海外に雄飛しなければいかん。それにはまず海軍をおこすことだ。君、かならずやれよ」
といって、「海舟書屋」という宇を書いてくれた。
麟太郎はこれを横額にしたてて勉強部屋にかけた。
麟太郎はこの海舟を号にして、勝海舟といった。麟太郎よりもこの方が有名だ。
それから象山とは親戚になってしまった。
麟太郎の妹、順子が象山に嫁入りしたからだ。仲人には剣の先生島田虎之助見山がなった。
ここでちょっと象山の逸話を話そう。
象山は大柄で筋骨たくましく、顔は長く、額は広く二重まぶたで目はくぼみ、あごひげをたれて、中々厳しく、また人を人とも思わぬ威張ったところがあった。
吉田松陰が弟子入りにきたとき象山は虎の皮の敷物を出して「これをお敷き下さい」といった。
松陰は礼儀正しい人だったし、初めて先生にあうのだから遠慮した。
すると象山は「これは死んだ虎の皮だから食いつきはしない」と馬鹿にしたようにいったという。
こういう人を食ったところがあって、蘭学者がくれば漢学で、漢学者がくれば蘭学で煙にまく。
大抵初めはびっくりしてしまう。
麟太郎は二十八歳(一八五〇、嘉永三年)の時、蘭学の勉強が進むとともに赤坂の家を塾にして教え始めた。
噂を聞いて杉享二(きょうじ)が行ってみると、家の中からもつっかえ棒をしてやっと持ちこたえているあばら家だった。
杉享二は麟太郎に教わり、我国統計学の開祖といわれる人になった。 |
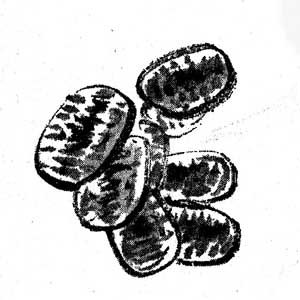
|
top
****************************************
|