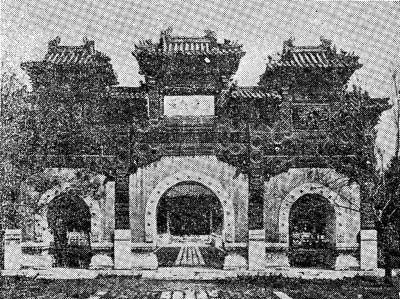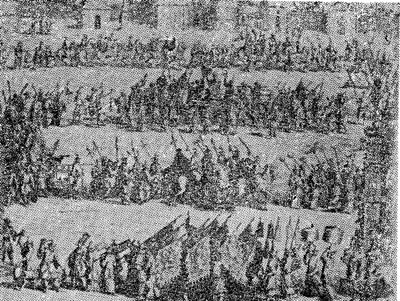|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15
16 世界の歴史8 アジア専制帝国
12 恩恵と威圧の世
1 明と賊と清 top
「明の官紳軍民に告ぐ。
さきにわが清は、なんじらの明と修好し、ながく太平に暮らしたいとのぞみ、しばしば皇帝に書をおくったが、応じようとしなかった。
このため、四度にわたって本土にふかく進出し、北京にせまった。
それは、ただ修好実現をはがるためであり、他意はない。
しかし明が流賊にほろぼされた今となっては、すべて過ぎ去ったことである。
あらためて論じたところでどうにもなるものではない。
ただ、天下は一人の天下ではなく、有徳の者が君臨すべきものである。
また軍民も一人の軍民でなく、おなじく有徳の者が、これを統轄すべきものである。
このゆえに、わが清は、いま北京にせまっている。もとより、明朝の君父の仇を討たねばならぬからである。
わが清は、すでに破釜沉舟(はふちんしゅう=決死の覚悟)やって来た。
もはや賊をほろぼさないでは、絶対にあとには引かない。
北京にいたるまでに通過してきた州県の者は、すべて薙髪(ていはつ)し、われらに帰順している。
なんじらが城門をひらいて、平和のうちにわれらを入れるならば、爵禄をあたえ、富貴に暮らさせよう。
もし拒んでしたがわないのならば、有能と無能の区別なく、ことごとく殺戮するのみである。よく考えよ。」 |
北京城にせまったとき、ドルゴンは城内の漢人にむけて、このような激又をとばした。
北京城は内側からひらかれた。かくて清による五族の中国建設は、本格的にはじまった。
しかし漢人の武将を味方に引きいれた清朝が、つぎに必要としたものは、文官と読書人(知識人)と民衆を、いかにして清朝のもとに協力させるかにあった。
それは、すでに後金国から大清国を建設する過程で、遼東の農耕社会において経験してきたものであった。
清朝が漢人に対して、恩威ならびおこなう政策をとったといわれるものは、すでに瀋陽時代において経験してきたものである。
「漢をもって漢を制す」という方法は、軍事行動のみではない。
明朝の制度をほとんど踏襲したとか、満漢の併用をおこなったとかいわれるものは、結局のところ「漢の制度、すなわち明朝の制度をもって、漢すなわち明朝の社会を制す」ということになる。
その場合、当面の問題はふるい明朝の社会における弊政を除去することであり、そのためには、事情を知る明朝の文官の協力を必要とする。
恩威ならびおこなう政策は、そこに生まれ、恩恵と非情が同居する政策となる。
いきおい、それは漢人を従と不従とに分離することになる。
従清の漢人には満蒙の一体をとき、不従清の漢人には弾圧をもってする。
夷狄(いてき)という立場をせおう大清王朝の苦肉の策が、そこにある。
「明につかえ、ついで賊首の李自成にしたがい、いままた清につかえる。
まことに金之俊(きんししゅん)こそは三朝の元老であり、大忠臣というべきか。」 |
当時の人びとが、このように皮肉った金之俊は、明朝の兵部右侍郎(国防次官)で、李自成に捕えられ、ついで清軍の北京入城とともに清に帰服して、要職についた人物である。
清初、かれがいかに重用されたかは、たびたび引退を願いでても許されず、十八年にわたって政務に参与した事実から想像できよう。
かれの業績として、難民の救済や、南北をむすぶ漕運路の回復そのほかをあげ、明末における弊政の除去に功あったことが指摘されている。
これも、かれが貴重な存在であったからにほかならない。
一説によると、当時の人びとに皮肉られた金之俊(きんししゅん)は、無条件で清に帰服したのではないという。
かれは投降にあたって、満人に損なく、漢人が希望する十項目をしめし、受けいれれば投降するが、さもなくば死をえらぶのみといって、ドルゴンにせまったというのである。
真偽のほどは明らかでないが、かれは不従をもって従に利用する十項目として、男従と女不従というふうに、男と女、生と死、陽と陰、官と隷、老と少、儒と釈道、娼と優伶(ゆうれい)、仕宦と婚姻、国号と官号、役税と語言文字の十対をあげている。
一見、何のことかわからない十項目をみとめた武人のドルゴンに、はたして理解できたかどうか、あやしいものである。
それが金之俊(きんししゅん)のねらうところであったのかも知れない。
伝えるところによれば、清初、旗人が商業を経営することを禁止し、王公がかってに北京をはなれることを禁じたりした背後には、金之俊の策謀があったという。
のちになって乾隆(けんりゅう)帝がこれを知り、改革しようとしたが、すでに祖法となってはどうにもならず、非常にくやしがったとさえ伝えられる。
不従をもって従に利用するという金之俊の策は、こうなると、旗・漢の間にくさびをうちこむ役をはたしたことになる。
旗人が商業の経営にしたがわず、漢人がこれに従う。
不従をもって、みごと従に利用したばかりか、従を生かしたことになる。
満人に損なく、漢人が願っているという真意は、ここにあったのかもしれない。
皮肉なことに、現実の問題としては、やがて旗人が生活に困窮する一因ともなり、旗人にとって、大きな損失となる一面をまねいたのである。
明と賊と清につかえて三朝の元老、大忠臣と皮肉られた金之俊の生き方は、結果において明末の弊政と、夷狄の王朝たる清の支配という両面の問題を、たくみに克服したことにもなる。
恩威ならびおこなう政策をもって漢人に対した清朝と、従不従をもって満人に対した漢人の文官と、はたしていずれが大清王朝を結果的に左右したか。
ドルゴンの檄文と、金之俊をめぐる十の不従論の伝えとは、きわめて興味ある問題を提供してくれる。
明快なドルゴンの恩威策は、だれにでもわかる、きわめて一般的な政策といえる。
しかし金之俊の不従論は、まことに複雑であり、にわかに理解できるものではない。
満人にとって、漢人の文官や読書人(知識人)が、いかに手ごわい存在であったかをうかがわせる。
そこに文字の獄が吹きあれる一面があった。`
2 恐怖の筆禍 top
北風たる清朝が中国の本土に進出すると、その武力にくわえて胡俗の辮髪(べんぱつ)を強制するという恐怖を、中国の全土にまきおこした。
それは、まさしく不従清に対する威の行使であった。
では、清の統一がいちおうの達成をみたとき、威の行使は終わったのであろうか。
「聖徂(康煕帝=こうきてい)の在位六十一年、外に外敵を討って内を安んじ、その兵威はきわめてさかんであった。
しかも内における漢人を、武力のみで治めることのむずかしさを知った聖祖は、儒学をもってこれを補った。
満州族たる清朝の命脈が長く存続できたのは、一に康煕(こうき)一代にはじまる儒学をもって、天下の人心を籠絡(ろうらく)する策にあった、といわれるのも、けだし虚言ではない。」 |
こうした記録をみる限りでは、威の恐怖は、康煕の代に終わったかの感をうける。
しかし籠絡の背後には、きびしい筆禍(ひっか)の獄が、ともなっていたのである。
中国史の上で、思想の弾圧や文字の獄は、たいていの統一王朝にみられた現象であり、ちかくは明の洪武(こうぶ)帝のきびしい文字の獄が思いおこされる。
にもかかわらず、史上ふしぎに有名なのは、最初の統一王朝をたてた秦(しん)の始皇帝(しこうてい)による弾圧と、最後の王朝たる清朝(しんちょう)の時代に吹き荒れた弾圧である。
それは康熈(こうき)・雍正(ようせい)・乾隆(けんりゅう)の三代にわたった。
始皇帝によるものは「焚書坑儒(ふんしょこうじゅ)」として、清朝のものは「文字の獄」として、巷間(こうかん)の史書にかならず登場する。
康煕帝時代に戴名世(たいめいせい)という文人がいた。かれは康熈四十四年の郷試に合格し、四十八年(一七〇九)には二番というすばらしい成績で殿試に合格して、進士(しんし=科挙の合格者)となった。
ときに五十七歳、やがて還暦をむかえようとする老齢であった。
そのころの科挙の試験がいかに激しい試験地獄であったかをうかがえよう。
戴名世がようやくにしてえた進士合格の喜びも、ながくはつづかなかった。
いや、むしろ優秀な成績で合格したことが、かえってかれを悲劇の主人公にしてしまったのである。
かれは、かつて江南に自立した明朝の遺臣の足跡について『南山集孑遺(けつい=残り)録』という本を書いていた。これを知る者が、かれを密告する挙にでた。
たちまち捜査の手がのび、南山集の内容調査がおこなわれた。
その結果は、はじめから明らかであったといえる。 |
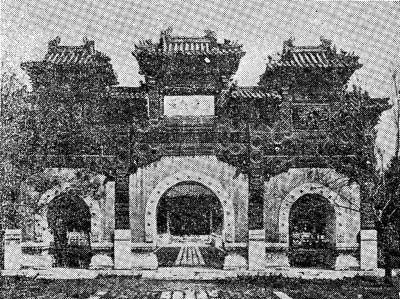
官吏志願者のあこがれのまと国子監
|
書中に清朝の年号をもちいず、永暦という遺王の年号がもちいられ、「大逆」の二字が各所に記されているなど、こじつけの罪状が列挙された。
戴名世は八つ裂きの極刑に断じられ、累(るい)は一族縁者におよんだ。
十六歳以上の者は死刑、それ以下の者は功臣の家に引きわたされ、奴とされるというきびしさであった。
そればかりではない。
戴名世と関係のあった方孝標(ほうこうひょう)は、すでに故人となっていたが、その書に弘光・隆武・永暦など、明朝心遺王の年号があり、「大逆」の語も多いなど、おなじような理由をもって弾劾(だんがい)された。
断罪は、その評骸をあばき、累を一族におよぼすという非情さであった。
雍正(ようせい)帝時代のこととして、巷間(こうかん)に知られる著名な筆禍事件は、査嗣庭(さしてい)の獄であろう。
雍正四年(一七二六)、査嗣庭(さしてい)は江西省でおこなわれる郷試の試験官として派遣された。
かれは問題のなかに、詩経のなかの一節「維(こ)れ民の止(お)るところ(維民所止)」という句を引用した。
結果は、たちまち密告者の餌食(えじき)とされたのである。
「維と止」の二字は、それぞれ「雍と正」の頭をはねたものであり、雍正帝、ひいては清朝に反旗をひるがえさんとする意図あり、と断ぜられてしまった。
そのうえ、かれの宿所の荷物のなかから、批判的な内容ありとされる日記まで発見されてしまった。
結果はいうまでもなく死刑であり、累は一族におよんだ。
雍正時代の獄では、このほかに呂留良(ろりゅうりょう)の事件があり、多くの者に累がおよんでいる。
帝に対する根ぶかい恨(うら)みは、帝が急死したとき、呂留良の孫娘が帝を暗殺したのだ、との風評をうんだほどである。
乾隆時代の筆禍事件は、さらに激しさをました。
「壺児」と書いてあれば「胡児」に通じると処罪された。
乾と龍の字があれば、龍は隆を意味すると断じられた。
そのほか、赦や世表という文字をつかえば僭越(せんえつ)とされるなど、ことごとに筆禍の対象となり、処刑された者は数知れない。
それのみか、帝は天下の古書をせんさくさせ、不都合とおもう書を焼き、禁書目録までつくりあげる始末であった。
これでは、いかに儒学を尊重するといっても、そのままには受けとれない。
清朝を異民族であると指摘するかのような文字や語句には、異常な神経をとがらし、非常識ともおもわれる理屈をつけて処刑する。
こうした康煕・雍正・乾隆の三代を、盛世と謳歌するのは、矛盾した話しである。
いわゆる「盛世(せいせい)」は、恐怖の上になりたっていたのである。
3 教育と大義 top
一、孝弟を敦(あつ)くし、 人の倫(みち)を重(おも)んじよ。
一、宗族を篤(あつ)くし、 雍睦(むつま)じくせよ。
一、郷里の党(なかま)と和し、争訟(あらそい)を息(や)めよ。
一、農桑を重んじ、 衣食を充足せよ。
一、節倹を尚(とうと)び、 財用を惜(お)しめ。
一、学校を隆(さかん)にし、 士習を端(ただ)せ。
一、異端を黜(しりぞ)け、 正学を崇(とうと)べ。
一、法律を講じ、 愚頑を儆(いまし)めよ。
一、礼譲を明(あきら)かにし、 風俗を厚くせよ。
一、本業に務め、 民志を定めよ。
一、子弟に訓(おし)え、 非為を禁ぜよ。
一、誣告(いつわちつげる)を息(や)め、 良善を全(まっと)うせよ。
一、窩逃(にげかくれ)を誡(いまし)め、 株連(かかわりあい)を免(まぬが)れよ。
一、銭糧を完納し、 催科(とくそく)を省(はぶ)け。
一、保甲に聯(つらな)り、 盗賊を弭(や)めよ。
一、讐念を解(と)き、 身命を重んじよ。 |
明の洪武帝の「六諭(りくゆ)」を思わせるこの十六条は、民衆の教化に熱をいれた康煕帝の教えである。
「六諭」とおなじく儒学、とくに朱子学による道徳教育にほかならなかった。
ふしぎなもので、明代では「六諭」の教えは、むしろ明末の社会不安が増大したころに、地方で自発的にとなえられ、郷党の結束をかためたという。
清朝でもこの明末の風をうけつぎ、順治帝の代には「六諭」をとなえさせていた。
明朝のあとをつぐ意味であろう。さすがに康煕帝は、そのままを真似ることはしなかった。
あらたに「聖諭広訓」をつくり、数をまして十六条を郷村でとなえさせるようにした。
清代では、それが郷約の自発的立場からではなく、中央からの強制として推進され、違反する者は厳罰という威をともなっていた。
民衆の教化もまた、恐怖の教育という一面をそなえていたのである。
独裁の皇帝をめざした雍正帝は、文字の獄ともあいまって、清朝の正統性を強調するために、呂留良の獄の一契機をなした曾静(そせい)なる人物との問答を書に編し、『大義覚迷録』と題して、これを公刊した。
大義をもって曾静を迷いから覚めさせた記録、を意味するものである。
康煕帝の十六条が、民衆の教化を意図するものであるのに対して、雍正帝の『大義覚迷録』は文官や読書人の教化を、めざしたものであるといえよう。
両者ともに、そのもとづくところのものは儒学、ことに朱子学に発していることにおいて、かわりはない。
ただ康煕帝の十六条は、あくまでも家族道徳の域にとどまるものであり、郷村の内部にとどまるものであった。
これに対して雍正帝の大義は、君臣の道であり、王朝国家の大道であった。
したがって、そこに強調されるものは、偏狭な中華主義の克服であり、夷狄(いてき)をふくめた天下の大義を主張するものであった。
まさにそれは、次代に実現した五族の中国に適応される大義である。
雍正帝は、むかしの聖王が、夷狄の出とされながら聖天子として後世の範とされるごとく、天子に夷狄の区別なしと強調するのであった。
漢民族を中心とする思想では、夷狄との間に君臣の関係なしとし、夷狄の君主をいただかずとする。
そうした一部の知識人に対して、雍正帝はきびしく挑戦したのであった。
民衆は、家族や郷党のわくにとどめ、読書人は偏狭な漢人中華のわくを脱せよと強調する清朝の政策は、まさに苦肉の策といわざるをえまい。
しかも一方においては夷狄の出身であることに神経質となって、文字の獄をくりひろげる。
これでは、かえってみずから中華と夷狄の観念にとらわれ、読書人の関心をよびおこすようなものといえよう。
清朝は中央の行政機関において、満漢併用の策をとった。
また学者を動員して、明朝にまさる大編纂(へんさん)事業をおこない、『康煕字典』『古今図書集成』『四庫全書』など、多くの文化的貢献をした。
この三代は、五族の中国を建設したこととならんで、大清の盛世(せいせい=国力が盛んな時代)とよばれる。
さらには儒学の尊重や天壇そのほかの壇廟の祭祀をさかんにおこなったことなどをあげて、康煕帝を偉大な皇帝とたたえ、雍正帝や乾隆帝をたたえるむきもある。
歴史にいう盛世とは、いったい何か。
領域の拡大か、武力の強盛か、儒学の尊重か、恐怖の政治か、まことに考えれば、ふしぎな表現といわざるをえないといえよう。
もとより、それは清朝のみにかぎったことではない。
洋の東西をとわず、盛世とか繁栄という言葉は、史上しばしば乱用され、かならずといってよいほど、最大版図を指摘する。それは、いったい何を意味するのか。
あらためて考えさせられる反省であり、疑問である。
清朝の治世は、こうした多くの矛盾をともないながらも、歴代の王朝がたどった道を、ふたたびたどっていったのである。
それが専制国家の宿命であるかのように。
4 丁税の廃止 top
清朝は一六四四年、北京に入城すると、民心を安定する一策として、三餉(さんしょう)とよばれた明末の三つの悪税を、さっそく廃止するよう命じた。
しかも、それが善政であるかのように伝えている。
いったい、三餉とは何か。三つの悪税といわれた遼餉(りょうしょう)と剿餉(しょうそう)と練餉(れんしょう)との総称である。
ともに明末の臨時軍事費として、田上に付加した税である。
遼餉(りょうしょう)は、遼東地方における対清軍事費にあてるために(一六一六)、剿餉(しょうそう)は、国内の反対勢力を鎮定するに必要な軍事費として(一六三七)、また練餉(れんしょう)は、辺境の軍隊の訓練費を調達するために(一六三九)、それぞれ徴収しはじめたものである。したかって三餉は、あいつぐ軍事費の不足をおぎなうため、つぎつぎと名目を設け、税の増額をはかったものといえよう。
「賊の平定には兵を要し、兵の養成には餉(しょう=軍費)を要す。されど餉は民によるほかはなし。
よって民に一年の助力をもとむるも、またやむなし。」
こういう弁明をして徴収したのが、剿餉である。それでも軍事費は不足をつづけた。
しかし、おなじ泣きごとでは通用すべくもない。苦肉の策として、
「いま、田土を所有する者の多くは富豪にあり。ゆえに付加税の増加は、富豪の土地兼併を抑圧するの効あり。」 |
という意味にもとづいて徴収したものが練餉であったという。
しかし付加税とはいえ、額は正税に倍し、年間一千七百万両におよんだといわれる。
これでは農民が苦しむのも、また当然といえよう。
種をまくのは為政者で、あと始末の負担に苦しむのは人民である。
決して為政者のたくわえた巨額の私財をあてようとはしない。似た現象は、現代の社会にも多い。
清朝が三餉を廃止したことは、その名目からみて当然のことである。
こうした明末の臨時付加税を廃した清朝は、その後の康煕から乾隆にかけて、しばしば免税をおこなうなど、善政を推進したといわれる。
また地丁銀(ちていぎん)の制を施行して、古来の丁税(人頭税)を廃止したのが特筆される。
「いまや、太平の世となってすでに久しく、戸口は日ごとに増加の一途をたどっている。
それゆえ人丁を把握して、銭糧を徴収することは、容易ではない。
人丁は増加しても、それに比例して田上がひろくなるわけではない。
これよりのちは、現在の台帳に記載されている人丁数を規準として、ふやすこともへらすこともなく、ながく定額としたい。
よって、以後に増加する人丁は、銭糧の徴収をやめ、別台帳に数のみ記載せよ。
余が地方を巡幸したときの見聞では、一戸に五〜六人の人丁がいながら、銭糧をおさめているのは一人、などというのが実情であった。
理由をただしたところによると、余の宏恩(こうおん)に浴して税をまぬがれ、安楽をえたいためとのことであった。
理由はもっともである。ただ、これでは天下の人丁の実数がわからない。
平和の回復した現在では、田土の復興やあらたな開墾も終わり、もはや田土をひろげる余地はない。
しかも財政はゆたかで、不足のおそれもない。したかって銭糧の増徴をはかる必要はない。
これからは銭糧の増徴をやめ、人丁数の正確な把握をしたい。
それは民のためによいばかりでなく、わが朝の盛事をしめすことにもなろう。
余は人丁の実数を知りたいだけである。」 |
康煕五十一年(一七一二)、帝はこのような内容の勅諭をくだし、翌年以後に増加した人丁数は別の台帳に登録させた。
この新しい台帳を滋生冊、記載された免税人丁を盛世滋生人丁などとよんでいる。
盛世滋生人丁制の実施によって、徴税の対象となる人丁数は固定し、徴収する丁銀も固定することとなった。
そこで考えだされたのが、丁税を地税のなかにくりいれ、丁税としての独立項目をなくすことであった。
こうして成立したのが、地丁銀(土地税と人頭税を合せた税)制とよばれるものである。
地丁銀をめぐる学者の解釈はいろいろであり、決して一致はしていない。
けれども、古来の丁税という独立の税目がなくなり、地丁銀の名で、やがて全国に普及し、清末まで財政上の重要な収入源となっていたことは事実である。
要するに、それは丁銀の総額を固定したことによっておこったものであり、地丁銀の名のように、丁銀がまったく消滅したものとはいえない。
清朝は、こうして免税をおこない、また丁税の総額を固定したりしながら、しかも清初の国庫には余裕があったと伝えられている。
それは節約や、支出の引きしめによるともいわれる。はたして、それだけであろうか。
5 世は金次第 top
清朝は、中国の民心を安定させるためには、まず明末の三餉をやめ、貧民の救済にあたり、ときには免税もおこない、人丁にかける税の総額を固定して、地丁銀の制を実施した。
このような政策をとりながらも、順治帝の代にはなお苦しかった財政が、康煕の時代からのちは、しだいに好転し、康熈末年には、六百万両の蓄積ができたという。
雍正帝の代は、わずか十三年にすぎないが、その前半には、六千万両の蓄積ができ、その後ズンガルヘの外征によって、なかばを支出したが、乾隆の初期には、なお二千四百万両の在庫があったと伝えられる。
乾隆帝の代は、国庫の蓄積の増減がはげしく、回部(ウイグル)の平定に三干万両の支出をした結果、蓄積わずか七十万両ばかりになった時期がある。
しかし、その後ふたたび増加し、四十一年の金川平定には七十万両を支出しながら、なお六千万両の余裕があり、さらに四十六年(一七八一)には七千八百万両に増加したという。だが、その蓄積も四回にわたる免税や、帝の六回にわたる南方巡幸などにより、乾隆末年には、ほとんど国庫の蓄積を消費してしまったといわれる。
国庫の蓄積に増減ありとはいえ、ともかく蓄積がつづいたことは、記録のしめすところである。
しかも、赤字財政をうつたえる動きはない。しかし、そこには清朝弊政の一つの要素がかくされていた。
中国の王朝では、秦漢のむかしから、穀物や金銭を自発的におさめる方法によって、官職そのほかの恩典を手にいれる道があり、それが一つの財政収入源とされていた。
この制度は、のちになるほどさかんとなり、明代には通例となる始末であった。
一般にこれを、捐納(えんのう・捐輪・捐官などという。(捐=捨てる、放棄する、与えるの意、例=義捐金)
まさにそれは「世のなか、すべて金(かね)しだい」という一面を、政治的に利用したものである。
免税などをおこない、民心の安定をはかる善政をおこなったという清朝は、この捐納の実施において、歴代の王朝にまさるともおとらない。
その施行は、順治のころ、すでに認められるが、記録の上では康熈帝以後さかんとなり、清末にいたるほど、はなはだしさを加えている。
康煕初期の例は、まず三藩の乱の当時にみられる。
そのころ湖広・福建・貴州・雲南など、乱を鎮定するために清軍が活動した地域で、捐納をおこなったことは、現地における軍事費の調達をねらったものにほかならない。
この期における捐納について、「収入わずかに二百万両、捐納による知県(県の長官)就任は五百余人」などと伝えているが、その数はかならずしも信用できない。
なぜならば、異民族なるがゆえに、ことさら善政を強調する清朝は、悪政ともいうべき捐納の施行を、つとめてあいまいにしようとする意図が見うけられるためである。
歴代の王朝にみられた弊政を、清朝もまた踏襲している事実を、公然とはしたくなかったものといえよう。
明末の三餉にかわって、清朝がおこなった軍費の調達法は、捐納であった。
捐納の収入わずか二百万両、などというが、決して少額ではない。
またそれが、効果すくなしというのなら、その後において、軍費の調達のみならず、河川の修理から流民の救済、また城壁の修理や建築工事にいたるまで、そのつど捐納をおこなうはずはない。
しかも当時の中国では、官吏の志願者がきわめて多い。
そこには、想像を絶する試験地獄がひかえている。
まず学校に入るための入学試験、卒業したら郷里の任用試験、さらに中央の試験と、いくつもの段階の試験に合格しなければ、官吏としての将来は約束されない。
ようやく資格をとったときには、五十歳をすぎていたという例が、すくなくない。
「郷里の試験に合格したものならば、千五百両だせば、知県になれる」ということになれば、金のある者が、その方法を選ばぬはずはない。 |
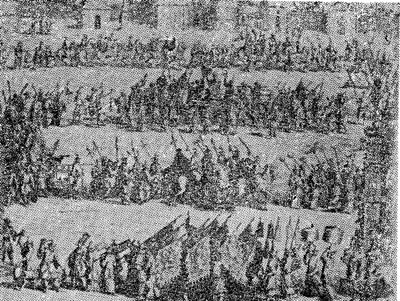
清朝官僚の行列
|
捐納は出世欲にとりつかれたものがある限り、必要悪として便利な財政の収入策であった。
民心の安定をうたう減税と、出世欲にとりつかれたものを利用する捐納。
そこに、清初の国庫に余裕をうんだ一つの鍵がある、といわざるをえないであろう。
捐納による官吏の登用と昇進も、欠員の多い場合には、支障がすくなかった。
しかし欠員がすくなければ、みにくい争いを生みやすい。
それだけではない。試験の合格者でも同じであるが、捐納で任官した者が有能とは限らないのである。
むしろ正規の試験をこえた者より無能者が多かった。その弊害を伝える記載はすくなくない。
悪弊は悪弊をうみ、それが清朝の屋台骨をゆるがす一つの要素となったとしても、ふしぎではないであろう。
専制王朝と官僚国家の矛盾はつきないのである。
top
**************************************** |