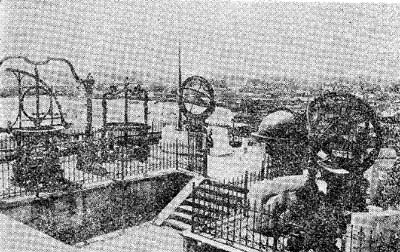|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12
13
14 15 16
世界の歴史8 アジア専制帝国
14 西から寄せる波
1 仏郎機(フランキ=ポルトガル)きたる
top
明朝がきずいた北辺の長城は、清朝の成立によって無用の長物と化してしまった。
それでは南に対してとった明朝の海禁策は、倭寇(わかん)がしりぞいたのち、どうなったのであろうか。
倭寇は、海上の密貿易と、密接不離の関係にあった。
密貿易は、海禁のためにおこる現象である。
禁をおかしてまで貿易するというのも、沿海の住民にとって生活の道がそこにあり、かつ利益がすくなくないためである。
海禁は時代に逆行するものであった。
ことに、南方の海上からヨーロッパ人があらわれたことは、海禁をますます時代おくれの政策とした。
しかし明朝も清朝も、西洋の実状を知ることはできなかった。
話は明代の半ば、十六世紀はじめにさかのぼる。
そのころ広東の洋上に見なれぬ船が姿をあらわして、官憲に交易をもとめた。
アラビア人通訳の言によれば「仏郎機(フランキ=ポルトガル)」であるという。
官憲たちは、はじめて耳にする呼称におどろいた。
とりあえず中央にうかがいをたて詔(みことのり)にしたがって積み荷を買いあげ、帰国させようとした。
しかし、なかなか去ろうとはしない。
通訳のいう「仏郎機(フランキ)」とは、実はポルトガル人であった。
アラビア人たちが、ヨーロッパ人をフランクの名にちなんで呼んでいたことから「仏郎機」と音訳されたのである。
このため明代では、ついであらわれたスペイン人も「仏郎機」とよんでおり、区別していない。
余談ながら、清代にはフランス人も来航し、清朝ではフランスを「仏郎機」と音訳した。
このため清代では、明代の「仏郎機」をもフランス人と考える誤解が生まれたという。
ポルトガル人とスペイン人を、ともに「仏郎機」と表記した明代では、おもしろいことにオランダ人を同じようには扱っていない。
「和蘭(オランダ)、またの名は紅毛蕃」としるし、
「紅毛蕃は、目がふかく、鼻は長く、頭髪や眉や髭(ひげ)はみな赤い。足は長く、背の高きこと常人に倍する」 |
などと表現している。
スペイン人とオランダ人との対立は、すでに明代の人の知るところであり、史書のなかでも仏郎機伝と和蘭伝というふうに区別している。
さて、仏郎機の来航をどうするか。明朝では、その対策をめぐって協議がおこなわれた。
「満刺加(マラッカ=マレー)は、わが明への朝貢国であるのに、仏郎機はこれを屈服させ、かつ、わが明には利益をもってへつらい、交易をもとめている。
そのやりかたは道に反するものであり、断じてゆるすべきではない。
よろしく使者をしりぞけ、道理をしめし、潸刺加を返還すれば、朝貢をゆるすべきである。
また、もし頑迷にして改めないならば、南蕃諸国に呼びかけ、これを討つべきである。」
これは監察機関の高官たる邪道隆の意見であった。同職の何傲(かごう)も、つぎのように強調した。
「仏郎機は、もっとも凶悪かつ狡猾(こうかつ)。その武力はまた諸蕃のなかで、ひとりずばぬけている。
前年、大船に乗って広東省城に突入したとき、その大砲の音は、大地にとどろいた。
かれらの無法は目にあまるものがある。
いま往来貿易をゆるせば、かならず争いや殺傷がおこり、南方の禍(わざわい)は、きわまるところがないであろう。
祖宗の遺訓では、朝貢に定まった期限があり、定制があったので、来貢する者も多くはなかった。
しかるに最近は、布政使の呉廷挙が献上の香物が不足であると奏したことにより、期限にかかわらず、来貢すれば積載の貨物を買いとるようになった。
このため諸蕃の船の来貢がたえず、蕃人は州城に雑集している。
いまや取締りはゆるみ、水路の往来はあふれている。
これこそ仏郎機の乗ずる好機といえよう。
よろしく諸蕃の船と潜居の蕃人を退去させ、かってな交易を禁じ、守備を厳重にすべきである。」 |
礼部の官もこれを支持し、その処置を、あわせ進言した。
「邱(きゅう)道隆は、さきに広東省頌徳の治にあたり、何鰲(なんごう)は頌徳の人である。
ゆえに現地の利害について精通している。よろしく満刺加(マラッカ)の使臣が廷にいたるのをまち、仏郎機(ポルトガル)が隣邦を侵奪し、内地をさわがす罪を責めるべきである。」 |
朝議は、仏郎機の要求をいれるところとならず、かえって海禁を強化する方向をたどるにいたった。
しかし仏郎機は、そのままいつまでも引きさかってはいなかった。
海禁が江南沿岸の倭寇を激しくさせたころ、仏郎機もまた広東方面への圧力を強めた。
交易の利は、現地の住民が欲するところである。
贈賄は地方官を動かし、仏郎機の武力は、対抗する者を圧した。
ついに仏郎機は、マカオに拠点をきずき、強引に貿易をおしすすめて、既成事実をつみあげてしまった。
マカオは、洋人来航の拠点と化したのである。
2 地図と大砲 top
仏邱機(ポルトガル)は、交易の利と大砲の力で、江南の沿岸に出没し、マカオを拠点とすることに成功した。
つづいて来航し、中国本土のなかに入りはじめたのが、キリスト教の宣教師たちである。
仏郎機の来航に始るヨーロッパ人の往来が、まず現地人の目を見はらせたものは、その船と大砲であった。
「蜈蚣(ごこう=洋人)船は、底がとがり、表面は平らで、風浪をものともしない。
船側には、板をもって矢や石をふせぐ道具があり、長さ、十丈、幅三尺におよぶ。
櫓は四十余本そなえつけられ、銃三十四丁が配置されている。
漕ぎ手は三百人も乗船しており、櫓も人も多いから、無風でも疾走することができる。
ひとたび銃を発射すれば弾丸は雨のようにふりそそぎ、むかうところ敵なしの観がある。
銃は銅で鋳造され、大きな銃は千斤以上の重さがあり、仏郎機と名づけている。」 |
|

ヨーロッパ人の描いたマカオ
|
これは嘉靖のはじめに、仏郎機人を招撫して、その船をえたときの記載である。
「かれらの頼みとするところは巨大な船と大砲にある。
船は、長さ三十丈、広さ六丈におよび、厚さは二尺を下らない。
船檣は高く、うしろは三層の楼をなしている。
船側には小窓が設けられ、銅砲が配置されているし、橋下には二丈におよぶ巨大な鉄製の大砲がある。
これを撃てば石城も破壊され、その震動は数十里にひびきわたる。
世に紅夷砲というのは、紅夷の製造にちなむ。」 |
これは、オランダの船や大砲についての史書の記録である。
火薬の発明は中国にあるといわれるが、これを利用した鉄砲や大砲の登場は、中国の人びとを驚かした。
鳥銃とか、仏郎機蔵とか、紅夷砲といわれる火器は、明末にいたって重視され、秀吉の朝鮮遠征のときにおける鉄砲の使用は、明側を刺激して、『神器譜』という鉄砲の解説書がつくられたほどである。
ことに、その後の東北におけるヌルハチの勢力に対抗するため、火器が重要視され、マカオの宣教師たちの協力をえて、鋳造をはじめるにいたった。
ヌルハチが寧遠城を攻撃して失敗したのは、明側の大砲の威力によるといわれ、ヌルハチは、そのときの傷がもとで世を去ったという。
大砲の鋳造に協力したことでもわかるように、布教のために来航した宣教師たちは、実用的な文化や科学知識をもって、中国の士大夫(しだいふ=インテリ)層に接近し、布教への道をひらいていった。
宣教師の活動は、十六世紀末から十七世紀にかけて活発となった。
その先端をきったのが、一五八二年マカオに達したマテオ・リッチや、その三年前にマカオに到着していたルズンエーリらである。
二人は、ともにイタリア出身のイエズス会土で、中国布教の開拓者であった。
マカオに到着したリッチらが、北京にいたる道は、決して容易ではなかった。
このことは一六〇一年、はじめて入京をゆるされ、北京に定住をみとめられた事実からうかがえる。
実に二十年に近い歳月を要したのである。
その間にリッチが布教法として身につけたものこそ、西洋学術の紹介を媒介とする知識層や官僚への接近であった。
南京は、その足がかりとなりえた。
リッチが中国の知識人をおどろかしたものは、すこぶる多い。
その代表的なものの一つに、世界地図の作成がある。かれは北京にいたる前に『山海輿(よ)地全図』という世界地図をつくり、知識人の関心をひいている。
北京でも一六○二年、李之藻の協力で『坤典(こんよ)万国全図』とよぶ大きな世界地図を製作し、人びとをおどろかした。
「天下は五大州からなる。第一のアジア州には百余国があり、中国はその一つである。第二をヨーロッパ州といい、七十余国があって、イタリアはその一つである。」
こうした調子で、アフリカ・南北アメリカと紹介されては、この方面の知識にとぼしい中国の知識人たちがおどろくのも無理はない。
紹介するヨーロッパ人も、いわゆる発見時代のころには、相当なさわぎであったことを考えれば、別にふしぎではなかろう。
マテオ・リッチが地理上の知識のみならず、中国知識人の関心をひく天文暦数にも長じていたことは、多くの人びとを動かすのに役だった。
徐光啓や李之藻らは、キリスト教の洗礼をうけ、信者としてリッチに協力するほどであった。
その成果が、さきの世界地図や、ユークリッド幾何学を漢訳した『幾何原本』その他の訳書であった。また明末には、アダム・シャールらと『崇禎暦書』などを作成している。大砲の鋳造に対する宣教師の協力も、徐光啓の努力によるものであった。
仏郎機(ポルトガル人)が、金(かね)と大砲をもって中国への拠点をきずき、その足場から宣教師が西洋学術とキリスト教をもって本土に入り、布教のためには大砲の鋳造にも協力する。それが現実であった。 |

マリオ・リッチ(左)と徐光啓
|
3 洋暦と典礼 top
『崇禎暦書』は、ヨーロッパの天文暦数を紹介しつつ、その学問的成果を導入し、かつ北京での実測をくわえて集成したものである。
まさに中国式の洋暦というふさわしい。
日蝕は、暦の正誤をだれにでもわからせるために、もっとも適切な材料である。
明朝も末に近い万暦三十八年(一六一〇)十一月の日蝕は、暦官の誤りを暴露し、暦の改修が相談された。
そのときの暦としては、「大統暦」が使用されていた。
これは元の郭守敬が実測によって作成した「授時暦」を、部分的に改めたものである。
改修の議に対して、宣教師が暦書にくわしく、中国では未見の書をもっているから、これを漢訳した上で参考にしては、という意見がでた。
すでに明初の洪武のときに、イスラム暦を研究した例があり、祖法にならうものとしてこの意見は採用された。
崇禎二年(一六二九)、夏の日蝕の日に、大統暦とイスラム暦と洋暦との精度がためされた。
結果は洋暦の優秀さが証明された。
『崇禎暦書』は、その後まもなく、四年の歳月をかけて編集されたのである。
背後に、崇禎帝の信をうけた礼部尚書の徐光啓の努力があったことはいうまでもない。
皮肉にも『崇禎暦書』が採用されたのは、清朝になってからのことであった。
「時憲暦」の名でよばれるものが、これである。
清朝では、順治帝の代に宣教師をそのまま重用し、天文暦法をあつかう欽天監という機関の監正(天文台長)に、アダム・シャールが任命されるほどであった。
シャールは、そのころ正式の官吏に任命された最初のヨーロッパ人である。
満州民族たる大清王朝の性格を反映したものといえよう。
キリスト教の宣教師を任用したことは、漢人の暦法家やイスラム暦法家の反感をうみ、さらに満漢高官の対立がからんで、一つの政治問題へと発展した。
それは康煕帝の親政への転機のころである。
問題は康煕帝が即位してまもなく、四大臣が輔政のときに表面化した。
漢人の暦法家たる楊光先が、シャールら宣教師に野心がある、と告発したことが発端となり、シャールらの断罪へとすすんだ。
しかし天変地異の続発が、刑の変更をもたらし、順治帝の母らの努力もあってシャールらは釈放された。
ただ欽天監の監正や監副は、楊光先やイスラム暦法家たる呉明烜(ごめいけん)らの手に帰した。
すでに洋暦の優秀さは、明末から順治の代に実証ずみである。かわった楊光先や呉明烜(ごめいけん)らの暦法が、これにまさることはできなかった。
不正確さは事実となってあらわれた。
親政に入った康煕帝は、洋暦の正確さを実証する三回の実験を、群臣の面前でおこなわせることにした。
日蝕にかわり、衆人がわかる実験として、宣教師のもちだしたものは、正午の時期における影の長さの計算と、実際との一致をしめすことであった。
三回の実験は、影の先端の到達を予測する線と、正午の影の先端との一致をしめした。
洋暦の勝利は、皇帝親政への道に大きな光明をもたらしたと学者は指摘している。
こうして宣教師は、清初の中国においても布教への足場をかためた。しかし、その地歩をゆるがしたものも、また宣教師じしんであった。 |
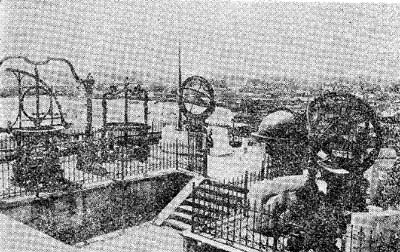
北京観象台(フェルピーストらの製作した天文儀がある)
|
活動する宣教師には、いろいろな派があった。
初期の宣教師はイエズス会士であったが、のちには他派の宣教師も、ぞくぞくと中国にきて、布教にあたりだした。
ところがイエズス会士以外の宣教師の布教活動は、思わしくない。
中国の知識人にとって思想の支えである儒教や、古来の風習を温存しつつ布教するイエズス会上の布教法が、効果をしめしていることに他派の宣教師はねたみをもち、布教法が邪道であるとローマ教皇に訴えた。
もとよりイエズス会士も負けてはいない。
布教の正当性を教皇に説き、康煕帝の上諭までもちだして反論を展開した。
カトリック教会の大論争となった布教問題は、曲折ののち、ついにイエズス会士の布教法を否とする断定をもって、教皇の方針とした。
康煕帝は、教皇の決定に対し、烈火のごとくに怒ったという。
儒教を否定してまでキリスト教の布教をみとめることは、絶対にゆるされない。
ことに儒学に対して、まれにみる熱意をもっていた康煕帝である。
ただちにイエズス会士以外の宣教師を追放するという、断固たる処置がとられた。
教皇の特使はマカオから一歩も入ることはできなかった。
この宣教師たちの争いに端を発した事件は、典礼問題といわれる。
それは、さらにイエズス会の解散という問題とからみ、中国におけるキリスト教の布教を禁止するところまで進んだ。
イエズス会が解散となれば、当然招来される結果である。
かれらは、みずから墓穴を掘ったといえよう。
布教の禁止は貿易制限とともに、世界の進展から清朝をとりのこす因となったが。
4 清末への道 top
明代末期からの洋学の実用化は、清代の初めにいたっていっそう進展した。
実用に供された最大のものは、けっきょくは、大砲と洋暦であったかも知れない。
建国初期、紅夷砲にくるしめられた清朝では、そののち積極的に大砲の導入をはかった。
漢人の火器部隊が重視されたのは、その一面をものがたる。
もっとも紅夷の夷は夷狄に通じ、夷狄の清朝に通じるとして、紅衣と改称するなどのいきさつもあった。
しかし大砲を重視したことは、紅衣大将軍などという名を付したことからも、うかがえよう。
夷を衣と改めるところには、清朝の夷狄性に対する神経質な配慮がある。
儒学を熱心にとりいれる必要性をみとめ、中国の王朝としての正当性を主張する清朝においては、それは現実の問題であり、中国知識層への対策でもあった。
それだけに、筆禍事件といういまわしい非情さを、一方では強く打ちだす始末であった。
洋学に基礎をもつ実用の大砲や暦法は、清朝の必要とする現実の問題であった。
清初における宣教師の活動は、その限りにおいて有益であったといえるかもしれない。
しかし、もともと宣教師の意図は、キリスト教の布教にあった。
ひとたびその布教が、中国古来の儒家思想と、それに密着する行事や慣習を否定するものとなったとき、儒教を重視しなければならない清朝の立場とは、あいいれないものとなる。
現実の必要性という観点にたったときキリスト教は、もはや無用の長物と化す。
それが、たとえ洋学の道をとざすにしても、断固とした処置をとらねばならない事態を、必然的にまねくものといわざるをえない。
儒学を重視しながら、文字の獄や筆禍事件をおしすすめたように。
実用に役だつ洋学を重視した清朝であったが、帰するところは、儒学とキリスト教との対決という現実問題のなかにおいては、布教の禁止と宣教師の弾圧へ、ふみきらざるをえなかった。
乾隆の貿易制限は、こうした現実とのからみあいのなかですすめられたものの一つといえよう。
それはまた、明朝以来の海禁問題につながるものであった。
皇帝と漢人官僚や知識人、皇帝と洋人宣教師、また皇帝と人民というように、五族の中国を建設した清朝には、これら多くの問題のなかで、現実の政治や社会や文化など、あらゆる面で矛盾を生んでいた。
そうした矛盾は、その克服をめざすことによって、あらたな矛盾をうみだし、一歩一歩と、末期への道をたどりはじめたのである。
そこには、歴代の王朝と似かよった要素が、決してすくなくはない。
しかし、夷狄の王朝という要素は、やがて表面化せざるをえない問題であった。
清朝が農耕社会にその拠点を置くかぎりは、さけがたいものであった。
さらに世界の動きから、みずから目をとざす結果をえらんだことが、清末への道に、いま一つの要素を投げかけた。
時代は大きく動きはじめていたのである。
top
**************************************** |